チェーホフ『箱にはいった男』あらすじと感想~精神の自由を放棄した奴隷人間の末路。チェーホフの問題提起

チェーホフ『箱にはいった男』あらすじ解説~精神の自由を放棄した奴隷人間の末路

チェーホフ(1860-1904)Wikipediaより
『箱にはいった男』は1898年にチェーホフによって発表された作品です。この作品はチェーホフの短編三部作の一作目にあたり、この作品の後に『すぐり』、『恋について』が続きます。
私が読んだのは中央公論社、神西清、池田健太郎、原卓也訳『チェーホフ全集 11』所収、『箱にはいった男』です。
さっそくあらすじを見ていきましょう。今回もチェーホフ研究者佐藤清郎氏の『チェーホフ芸術の世界』を参考にしていきます。
ここで言う「箱」とは、原語では「フトリャール」で、何かを蔵っておくためのケース、サック、または箱を意味する。箱に入っているかぎり、精神も身体も自由ではありえない。とらわれびとであり、奴隷である。
中学校のギリシャ語教師ベリコフは、まさにそういう箱をかぶった男である。心に自由さの微塵もない、頑迷にして固陋な形式主義者である。いつも何かを恐れているばかりか人をも恐れさせ、棺桶に入って初めて落ち着くという男の話が、「語り」の形で、つまり一人称で語られる。
この話の語られる場所は、月光を浴びたミロノシーツコエ村の村外れ、村の長老プロコフィーの納屋である。中学教師ブールキンが語り手で、聞き手は獣医イヴァーン・イヴァノヴィチである。
筑摩書房、佐藤清郎『チェーホフ芸術の世界』P288-289
この作品は中学教師ブールキンによって同僚のベーリコフ、いわゆる「箱にはいった男」について語られることになります。(佐藤氏はベリコフと呼んでいますが、全集ではベーリコフと訳されていますのでこちらの読み方を採用します。)
ではそのベーリコフというのはどんな人間なのでしょうか。
この男は、いつも黒眼鏡をかけ、耳に綿をつめ、胴着を着、袋に入った傘を持ち、時計までサックに入れて歩く。そして、いつも小心にきょろきょろと周囲を気にし、「ひょんなことにならなきやいいが」という不安げな文句を口癖のように言うのである。
筑摩書房、佐藤清郎『チェーホフ芸術の世界』P289
そしてブールキンはこう語ります。
ベーリコフはまた、自分の思想をも箱の中へ隠そうと努めていました。彼にとって明瞭なのは、何かを禁止する告示や新聞の論説だけだったのです。
例えば告示の中で学校の生徒が夜の九時以後に町へ出ることを禁止するとか、あるいは何かの論説の中で肉体的な恋愛が禁止されるとかすると、それは彼にとって明瞭で決定的であった、―つまり禁止万々歳というわけです。それが許可だの認可だのになると、いつも疑わしい要素というか、何か不明瞭で曖昧なものが潜んでいるような気がする。
町で演劇団体が許可されただの、読書クラブや喫茶店が認可されただのというと、彼はいつも頭を振って、小声でこう言ったものです。―『それはもちろんそれでいい、結構なことだ、ただあとで何か起らなければいいが』
中央公論社、神西清、池田健太郎、原卓也訳『チェーホフ全集 11』P54
※小説を改行するのは忍びないのですが改行しました
ベーリコフはその小心さ故自分で何かを決めることができず、お上、つまり権力者のお墨付きがなければ生きていけない人間だったのです。
お上による禁止というのは従う側にとっては何も考える必要がありません。ただそれを破った人間が悪。単純明快です。
しかしこれが許可とか認可になると、どこまでがよくて何をしたらだめかはある程度自分で考えなければなりません。彼は自分で考えることをとにかく恐れるのです。
ですから、べつだん彼に関係のなさそうな場合でも、およそ規則の違反だの逸脱だのが彼の心痛の種になるわけです。同僚の誰かが祈祷式におくれたとか、中学生が何か悪さをしたという噂が耳にはいるとか、級担任の女教師が夜おそく将校と一緒にいるところを見たものがあるとかすると、彼はひどく興奮して、いつも『あとで何か起らなければいいが』を口にする。
教員会議の席上でも、彼は例の慎重さや疑り深さや、彼一流の箱詰式想像でさんざんにわれわれを痛めつける。やれ男子部でも女子部でも生徒がふしだらなまねをして、教室で大さわぎをする、―ああ、教育長の耳にはいらなければいいが、ああ、あとで何か起らなければいいがだの、やれ二年生からぺトローフを除名し、四年生からエゴーロフを除名できたら実にいいんだがだのと言うわけです。
で、どうなったと思います?
この男が溜息だの泣き言だの、あの青白い小さな顔―ご存じでしょう、あのいたちのような小さな顔―にかける黒めがねだので、われわれみんなを圧迫したものだから、われわれも譲歩をして、ペトローフとエゴーロフの操行点を落し、ふたりを拘置して、あげくのはてにペトローフもエゴーロフも退校させてしまった。
中央公論社、神西清、池田健太郎、原卓也訳『チェーホフ全集 11』P54-55
※小説を改行するのは忍びないのですが改行しました
どうでしょうか。これを読んで思い当たることが出てきませんか?
そうです。今の日本と変わらない状況が浮かび上がってきませんでしょうか。
やれ「コンプライアンス」だ、やれ「人としてなってない」だ、「みんながこうしてるのにあの人はおかしい」だとか、悪者探しに躍起になっている世の中・・・チェーホフはそうした社会をこの作品で暗に風刺しています。
われわれ教師一同は彼を恐れていました。校長でさえ、恐れていたぐらいです。
ここで注意すべきは、われわれ教師というのは思慮に富む、しごくりっぱな連中で、ツルゲーネフやシチェドリーンを手本に教育されているわけですが、にもかかわらず、いつオーバシューズをはいて、こうもり傘をぶらさげたこの男が、丸十五年のあいだ中学校全体をその手に握っていたということなのです!中学校どころじゃない、町全体がそうだったのです!
町の婦人たちは、土曜日ごとに催していた家庭芝居をやめて、彼に顔を見られまいとびくびくしていましたし、坊さんたちは坊さんたちで、彼が居合せると肉食をしたりトランプ遊びをするのをはばかっていた。
ベーリコフのような人間の影響で、ここ十年―十五年のあいだ町じゅうが何かにつけてびくびくしはじめた。大声で話をするのも、手紙を出すのも、友だちづきあいをするのも、本を読むのも、あげくのはてには、貧乏人を助けたり、読み書きを教えたりするのまで心配になってきたわけです。……」
中央公論社、神西清、池田健太郎、原卓也訳『チェーホフ全集 11』P55
※小説を改行するのは忍びないのですが改行しました
ベーリコフはとにかく規則に厳格で、違反者を告発、密告しました。この男の存在で街の様子がすっかり変わってしまったのです。何をするにもびくびくしていなければならない。あげくの果てに人助けすらできないほどになってしまったのです。
佐藤氏はこう述べます。
べリコフは確かに誇張された特殊な像であるが、典型としてのべリコフ的人物はけっして特殊な現象ではない。現に、「制度」の支配する世界のあっちこっちで、この種の人物たちが、あるいは善意から、あるいは悪意から、気弱な人々を苦しめている!
この時代のロシア社会がべリコフのような人物を生み出したのは、デカブリスト事件(一八二五)、ぺトラシェフスキー事件(四九)、チェルヌイシェフスキー逮捕事件(六二)、ナロードニキ運動(七四)という歴史を経て、一八八一年のアレクサンドル二世暗殺後にやってきた厳しい弾圧政治のせいである。
つまり、中傷、密告、監視、尾行、投獄が日常現象であったと言われる時代が生みだした畸型的人物なのだ。
しかし、いつの時代にも、「人間」よりも「制度」が力を持つ社会では、歪みは形を変えて残りつづける。したがって、ベリコフたちのあとは絶えない。
べリコフという男の内容が形式としての箱を作り、その箱がまたべリコフを規制する。その箱の中にいなければ、は不安なのである。歪んだ性格が箱を作り、その箱が彼をさらに歪め、箱の中のみが「平安」の場所となってしまったのだ。
そしてその箱は、彼からばかりでなく、すべての人間から自由を奪う。箱は人間を殺す。みずからを護るためにかぶった箱が、かぶったとたん膨脹して、もはや脱げなくなるのだ。人間が歩いているのではない。箱が歩いているのだ!箱は臆病者がかぶる鎧であり、脆弱な体を護る貝殻である。
筑摩書房、佐藤清郎『チェーホフ芸術の世界』P290
※一部改行しました
制度という箱。お上から決められたものこそ箱であり、それに盲目的に従わなければ彼は不安でたまらないのです。箱から出て自分でものごとを考えるのが怖いのです。箱の中にさえいれば自分は守られている。彼はそう信じているのです。
やがてある出来事を経てベーリコフは精神的に病み、そこから体調も崩しあっけなく亡くなってしまいます。
この小心な「暴君」は、最後の箱、棺に納められる。
「棺に納まって、いまやその表情は、柔和でいかにも心地よさそうで、やっと箱に横たわったことを喜んででもいるかのように陽気でさえあった。この箱からはもはや出ないでいいのだ。そう、彼は自分の理想を実現したのである!」
箱の終着駅は棺であった。棺桶はベリコフという手のつけられない小暴君の、この世における唯一の、そして最後の安らぎの場所であった。
筑摩書房、佐藤清郎『チェーホフ芸術の世界』P292
埋葬からの帰り道の様子を語り手のブールキンはこう話します。
実を言うと、ベーリコフのような人間を埋葬することは、非常な喜びなのです。墓地から引きあげるときは、われわれ一同さすがに控え目な、神妙な顔をして、誰ひとりこうした喜びの気持を表わそうとはしませんでしたが、心のなかば、われわれがずっと昔、まだ子供のころ、大人たちが外出をして、子供たちだけで完全な自由を満喫しながら一、二時間庭を走りまわったときの気持にそっくりでした。ああ、自由、自由!自由というものは、そのほのめかしでさえ、その実現のほんの一筋の希望でさえ、人間の心に翼を与えるものです、そうじゃありませんか?
われわれは上機嫌で墓地から帰って来ました。ところが一週聞とたたないうちに、生活は以前のとおりになりました。同じ四角四面な、わずらわしい、無意味な生活、告示に禁じられてはいないが、さりとてりっぱに許可もされていないような生活―要するに少しもよくはならなかったわけです。なるほどベーリコフは埋葬した、しかしああした箱にはいった男がまだまだ大勢のこっていますし、これからもまだまだ出てくることでしょうよ!」
中央公論社、神西清、池田健太郎、原卓也訳『チェーホフ全集 11』P68
ベーリコフ一人がいなくなったとしても他にもまだ「箱にはいった男」はたくさんいる。そしてこれからもそうした人間はまだまだ生まれてくるだろうと語り手は述べます。これは作者チェーホフの認識でもあります。
そしてこの物語の最後に、聞き手の獣医師が鋭い言葉を残します。
「町の鬱陶しさと窮屈さの中で、おれたちは生きて、不必要な書類を書いたり、ヴィント遊びをしたりしている―これだって箱じゃないか?おれたちが一生、無為の連中のなかで、愚かしい遊惰な女たちや訴訟好きの連中のあいだで、さまざまなたわいのないことを話したり聞いたりして暮しているのも―箱じゃないのか?」
大きな「箱」、小さな「箱」は、あっちこっちにあるのだ!
「ひとが嘘をつくのを見たり聞いたりして、その嘘を我慢していることで馬鹿呼ばわりされ、侮辱やさげすみを我慢し、おれは本当は誠実で自由な人間の味方なんだと公然と宣言することをためらい、いつのまにか自分も嘘をつき、しかも微笑してみせるのも、みんな一片のパンのためだ、温かい一隅を確保したいためだ、一文の値打ちもない地位かなんかのためだ―ああ、こんな生き方は、もうできない!」
獣医の精神は一切の「箱」に対して、箱を生み出す状況に対して、激しいプロテストに燃えている。この叫び声に作者自身も、もちろん和している。(中略)
ソ連の研究者パぺルヌイは、チェーホフの作品の人物たちの抱く問題は、ハムレットのようにトウ・ビー・オア・ノット・トウ・ビーでも、生か死かでもなく、箱か人間かだと言ったが、これは至言である。彼の全作品は人間が真に自由になるための呼びかけである。
筑摩書房、佐藤清郎『チェーホフ芸術の世界』P203-204
チェーホフの鋭いところはベーリコフのような「箱にはいった男」はたしかに周りを不幸にするが、自分だって多かれ少なかれ箱的な要素があるではないかと自分自身をも批判するところにあります。
「ベーリコフみたいなやつは最悪だ」で終わらせるのではなく、「じゃあ翻って自分はどうなんだい?彼と何が違うんだい?周りの人のために君は何をしているんだい?」と問いかけるのです。
これは読んでいて「うっ・・・」と突き刺さるものがありました。チェーホフの人間洞察は本当に鋭いです。
頭ごなしにがんがん説教されるという感じではないのですが、話を聞いている内に「あぁ・・・」と自分の至らなさに打ちひしがれるような、そんな感覚になります。
20ページほどという短い作品の中でこれほどのものを表現できるとはやはり恐るべしチェーホフです。
この作品は今こそ読みたいおすすめな作品です。
以上、「チェーホフ『箱にはいった男』あらすじ解説―精神の自由を放棄した奴隷人間の末路」でした。
Amazon商品ページはこちら↓
チェーホフ全集〈11〉小説(1897-1903),戯曲1 (1976年)
次の記事はこちら

前の記事はこちら

チェーホフおすすめ作品一覧はこちら

関連記事












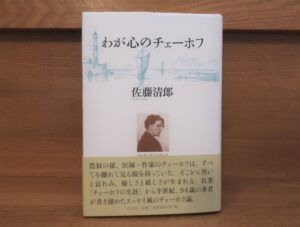



コメント