トーマス・マン『チェーホフ論』あらすじと感想~ドイツのノーベル賞作家が語る『退屈な話』の魅力とは

トーマス・マン『チェーホフ論』―『魔の山』『ヴェニスに死す』で有名なノーベル賞作家が語る『退屈な話』
前回の記事「チェーホフ『退屈な話』あらすじと感想~トルストイも絶賛した名作短編」ではチェーホフの『退屈な話』についてお話ししました。

その最後にドイツのノーベル文学賞作家トーマス・マンが『退屈な話』を絶賛したということを紹介しました。
トーマス・マンは『チェーホフ論』という論文を書いています。その中で彼は一番好きな作品として『退屈な話』を挙げていたのです。
今回の記事ではその『チェーホフ論』を見ていきながら、トーマス・マンの『退屈な話』評を見ていきたいと思います。

まずはじめに、トーマス・マンと言えば『魔の山』や『ヴェニスに死す』、『トニオ・クレーゲル』などの作品で有名なドイツのノーベル文学賞作家です。
トーマス・マンといえば映画の『ベニスに死す』の原作者として日本でも有名です。
この映画は私が学生時代、『美学』という講義の中で教授が紹介し、この映画を教材に「映画における美とは何か」ということを学んだ思い出があります。講義室の巨大なスクリーンで観たこの映画は今でも記憶に残っています。
そしてトーマス・マンの代表作『魔の山』は私の中でも特にお気に入りの作品です。この作品もいずれこのブログで紹介したいと思っています。
では、彼の『チェーホフ論』を読んでいきましょう。
ここで作品の名をあげ、称揚することを許していただけるなら、わたくしはどうしても、チェーホフの短篇中わたくしの最も愛する作品である『わびしい話』をあげないわけにはいかない。
これはまったく異常な、そして魅惑的な作品であり、その特徴をなすしずかな、もの悲しい調子は、あらゆる文学にほとんど比類をみないものだ。
この≪わびしい≫話と銘うった、しかも人に圧倒的な印象を与える作品が、三十にもみたない青年の透徹無比の洞察力によって、ある老人の口を通して語られていることだけでも、すでに驚かざるえない。
―この老人は、世界的に有名な学者であり、将軍相当の官位を持つ≪閣下≫である。彼自身も、その告白の中で、しばしば自分をそう呼んでいる―≪わが閣下≫だがその底にはかすかな嗟嘆のひびきがある。なぜなら、彼は位人臣をきわめたにもかかわらず、きわめて高い知性と、自己批判、いな一般に批判の能力とを持った人物であって、自己の名声や、人から受ける尊敬を愚劣なものと見なし、心の奥底では絶望しているからである。
彼の生涯、彼のすべての業績には、精神的な中心、≪一般的理念≫が欠けており、したがってそれは本質的には無意味な一生、救いのない一生であった。彼はこのことに気づいて絶望するのである。
中央公論社、原卓也編『チェーホフ研究』所収、トーマス・マン、木村彰一訳『チェーホフ論』P402
※一部改行しました
ここでは翻訳の関係で『退屈な話』が『わびしい話』となっていますが、彼はこの作品を「チェーホフの短編中最も愛する作品」と呼び、「≪わびしい≫話と銘うった、しかも人に圧倒的な印象を与える作品」と絶賛しています。
この論文ではこの後も『退屈な話』について述べられていくのですが、ノーベル文学賞作家が語る『退屈な話』論は非常に興味深いものがありました。
続いてこの論文におけるトーマス・マンのチェーホフ観をご紹介していきたいと思います。
西欧において、いなロシアにおいてすら、チェーホフが長いあいだ過小評価されてきたことは、自分自身にたいする彼のきわめて冷静な、批判的な、懐疑的な態度、自己の作品にたいする彼の不満、要するに彼のつつしみぶかさと無関係ではないように思われる。(中略)
この短篇作家は、あまりにも長いあいだ、自分は才能のとぼしい、芸術家としては無価値な人間だと思いこんでいた。彼がいくらかの自信―他人に自己を信じさせようとする以上は、どうしても持たねばならぬ自信を獲得して行った過程は、緩慢をきわめた、しかも困難なものだった。
彼には、文壇の巨匠とか、まして、トルストイふうの賢者ないし予言者とか、そういったおもかげは最後までまったく見ることができなかった。そのトルストイは、好意をもって彼を見くだし、そしてゴーリキイの語るところによれば、彼を≪すばらしい、ものしずかな、つつしみぶかい≫人物と考えていたという。
中央公論社、原卓也編『チェーホフ研究』所収、トーマス・マン、木村彰一訳『チェーホフ論』P391-392
※一部改行しました
以前ブログでも紹介しましたヴィリジル・タナズによる伝記でも「チェーホフが自身を才能のある人間だとは思っていなかった」ということは出てきました。トーマス・マンも同じようにチェーホフを見ていたようです。
肖像写真で見ると、彼は糊づけのカラーに、ひもつきの鼻めがねという十九世紀末の服装をして、とがったあごひげをはやし、均整のとれた、いくぶん悩ましげな顔にやさしい憂欝さをたたえた、やせぎすの人物である。
その顔立ちは、聡明な注意深さと、つつしみ深さと、懐疑と、善良さとをあらわしている。それは自分のことを大げさにいうことを好まない人間の顔であり、姿勢である。うぬぼれなどはみじんも感じられない。
彼がトルストイの教訓的態度を≪専制的≫だとまで感じ、ドストエーフスキイの作品を「いいものだが、つつしみがなく、尊大だ」〔一八八九年三月五日スボーリンあての書簡〕と言ったとするなら、何よりもまず内容空虚な尊大さが、彼の眼にどれほどグロテスクなものに写らざるをえなかったかは、想像にかたくない。
中央公論社、原卓也編『チェーホフ研究』所収、トーマス・マン、木村彰一訳『チェーホフ論』P416
ここでチェーホフから見たトルストイとドストエフスキー像が出てきました。これは今後トルストイやドストエフスキーを読んでいく上で非常に興味深い視点であると思います。
そしてチェーホフはこの論文を次のようにまとめます。
この作家の特質に、わたくしは魅力を感じている。名声にたいする彼の反語、自己の仕事の意義と価値とにたいする彼の疑惑、自己の偉大さにたいする彼の不信は、なんというものしずかな、つつましい偉大さにみちていることであろう。
「自己に不満を持つことは」とかつて彼は言った、「あらゆる真の才能の根本的要素だ。」〔俳優スヴォ―リンあての書簡にあることば、ただし原書簡は失われた〕
この命題においては、つつましさは、実際また、ある積極的なものに変貌している。すなわちそれは、次のことを意味している。
「なんじの不満に満足せよ。その不満は、なんじが自己満足を克服しえたことを、―おそらくは偉大にすらなりえたことを証明しているのだから。」
しかしこの命題は、疑惑や不満の誠実さをなんら変えるものではない。そして、窮極的な問題にはけっきょく答えることができないという意識を持ちつづけ、自分は読者をあざむいているという良心の呵責にくるしめられながらも、最後まで働くこと、誠実に、うまず働き通すこと、―これは依然としてふしぎな≪それにもかかわらず≫(Trotz-dem)である。
だが、事実はまさにそのとおりなのだ。
ひとは「物語を提供してまずしい人びとをたのしませながら、ひとかけらの救いの真理をも彼らに与え」ない。
ひとは「私はどうしたらいいんでしよう」というあわれなカーチャの問いにたいして、「良心にちかって、私にはわからないのだ」としか答えられない。
だが、それにもかかわらず、ひとは働き、物語を書き、真理を造形し、そして真理と清朗な形式とが、おそらくは魂を解放し、この世界をよりよい、よりうつくし、より多く精神の要求にかなった生活にたいして準備することができるだろうという、かすかな、ほとんど信念に近い希望をすてないのである。
中央公論社、原卓也編『チェーホフ研究』所収、トーマス・マン、木村彰一訳『チェーホフ論』P419
絶対的な答えはない。「どう生きればいいのか?」という問いにチェーホフは正直に「良心にちかって、私にはわからないのだ」と老教授に語らせました。
ですが「それにもかかわらず」チェーホフは葛藤しながらも書き続けた。やらずにはいられない何かが彼の中にあった。
そこにこそ彼の魅力があるとトーマス・マンは述べるのです。
今回は『チェーホフ論』の中の『退屈な話』に関する部分を基にトーマス・マンのチェーホフ観をお話しさせて頂きました。
前半にお話ししましたようにトーマス・マンの作品は私にとってもお気に入りの作品です。彼はドストエフスキーやトルストイにも大きな影響を受けています。
そのことも絡めていずれトーマス・マンの作品についてお話ししていきたいと思います。
以上、「トーマス・マン『チェーホフ論』~ドイツのノーベル賞作家が語る『退屈な話』の魅力とは」でした。
Amazon商品ページはこちら↓
次の記事はこちら

前の記事はこちら

チェーホフおすすめ作品一覧はこちら

関連記事












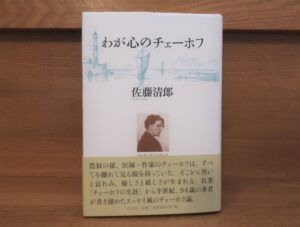



コメント