チェーホフ『サハリン島』あらすじと感想~チェーホフのシベリア体験。ドストエフスキー『死の家の記録』との共通点とは

チェーホフ『サハリン島』―地獄の島でのサハリン体験
『サハリン島』はチェーホフによって1893年に初めて発表されそこから何度も加筆修正されて発行された作品です。
私が読んだのは中央公論社、神西清、原卓也訳の『チェーホフ全集 13』所収の『サハリン島』です。
この作品は1890年にチェーホフが地の果てサハリン島への旅を通して得た経験をまとめたルポルタージュのような作品となっています。
サハリンと言えば私たち北海道民には馴染みの場所ですが、当時のサハリンは流刑囚が送られる地獄の島として知られていました。その環境は劣悪でまさしく死の家とも言うべき場所だったのです。
サハリン島は1875年にロシアの流刑地となりました。
ここにはかつて日本人も多く住んでいたのですが、幕末期の列強進出の流れでロシアがやって来ました。そして歴史の流れで実効支配されロシアの領土ということにはなっていますが、実際はまだ帰属問題が残る地となっています。
北方領土の問題はよく知られていますが、このサハリン(樺太)も帰属問題を抱えた地域となっているのです。
さて、チェーホフはそのような場所に自ら踏み込んでいくことになります。その旅程について巻末の解題で次のように述べられています。
われわれ日本人にとっては、サハリンが《北海道の隣り》という感じを持っているだけに、サハリン旅行といっても、その困難の度合いがピンとこないかも知れないが、シべリヤ鉄道のまだ開通していない十九世紀末に、モスクワからサハリンに行くのは、現在のわれわれが南極越冬に行くにもひとしい、いや、それ以上に大変な感じだった。(中略)
「全シべリヤを横断すること数千キロ、まだ鉄道のないころとて、馬や二輪馬車に揺られて行ったのだが、その道たるや泥濘に没し、まさしく”世界唯一の”でこぼこ道、轍にゆがんだ悪路ばかり、車輪や車軸をこわして、魂を放り出されるような目に会うこともまれではなかった。彼は道中、とくにトムスクあたりから、あまり激しく揺られたため、関節から鎖骨や肩や肋骨や背骨まで痛めてしまった。悪路にさしかかるたびにトランクははね上がり、手足は凍え、また馴れないために十分な食料を用意していなかったため食べるものに事欠いたり、何度か間一髪で奇蹟的に生命をとり止めたようなことさえあった。ある夜などは、道に放り出されて、二台のトロイカに衝突したこともあるし、またシべリヤの河を渡った時、乗っていた船が暗礁に乗り上げてしまったこともある……」(チュコフスキイ『人間チェーホフ』大朏人一訳、中央公論社版「チェーホフ研究」所収)
これによっても、サハリンに辿りつくまでが、文字通り命がけの旅行であったことがわかるだろう。しかも、そのような旅のさなかでチェーホフは、シベリヤのスケッチをせっせと書いていたのである。
中央公論社、神西清、原卓也訳『チェーホフ全集 13』P465-466
かつてのロシアの悪路というのは私たちの想像をはるかに上回るものとよく言われます。ロシア文学作品でもその悪名高い悪路はよく登場してきます。そんな極限の行程を通してチェーホフはサハリンまでやってきたのです。
サハリンにつくと、チェーホフは、本書にも明らかな通り、自分独自の調査カードを用意して、流刑囚、労役囚の一人一人に面接し、移住村の一つ一つをまわって、囚人や移住民たちの生活状態や、刑務所の設備などをくわしく調べた。彼の調査カードは一万枚以上に及んだ。
それだけではない、彼は移住村の地質や農業の収穫などまで綿密に調べあげているのである。サハリン調査を目的として派遺される学術研究隊でも、おそらくここまで突込んでは調べられないだろう、と思われるほどだ。
最初に、政治犯とは交渉を持たぬことという一札をとられているため、政治犯に関する記述こそ見られないが、彼の筆はそれ以外のあらゆる面に及んでいる。
また、彼はすべての人から好意をもって迎えられた。当時ドゥーエ刑務所長であったフェリドマンの思い出によると、概して人を疑いやすく、何事につけ平気で嘘八百をならべ立てる囚人たちも、チェーホフにだけは実に素直に、まじめに応答したという。
※一部改行しました
中央公論社、神西清、原卓也訳『チェーホフ全集 13』P466ー467
チェーホフは医者であり、科学的な思考を重んじます。そのためカードを使って客観的なデータをここで収集しようとしたのです。これは作品にも強い影響を与えていて、『サハリン島』はまるで「調査報告書」のような雰囲気すら漂わせます。ここには何軒の家がありここには何人が暮らしていてその割合は・・・というように客観的にサハリン島の様子を記していくのです。
ではチェーホフはなぜこんな極東の地獄の島サハリンまでやってきたのでしょうか。チェーホフ研究者の佐藤清郎氏の言葉を聞いてみます。
私は十余年前の旧著(『チェーホフの生涯』)で、総括的に「心を起そうと思わば、まず身を起せ」という島崎藤村愛好の文句を引用しているが、この旅が「まず身を起す」ための旅であったという考えはいまも変らない。サハリンの旅を何か一つの、一つだけの理由で説明しようとする者は誤りを犯すであろう。たとえば、マガーシャクのように、リジャ・ミジーノヴァとの恋から脱れるためだったとするのなどもそれだ。
複合した気分が彼を旅に駆り立てたのであるが、間違いなく言えることは、書斎的、観念的な生き方の追求にあきたらず、「まず身を起して」、ロシヤ社会の極限的場所でなまの人間、なまの現実にぶつかってみて、みずからの思想の基盤づくりの資にしたいと思ったのにちがいない。これは一つの脱出であり、一つの飛躍である。(中略)
一八九二年に、サゾーノヴァの観念的な「人生のための人生」論に対して、「可能である」とか「ねばならない」とかで固められた人生論に対して、現にどうあるのかをまず聞きたいと言って批判しているのも、彼の即物主義の表われである。サハリンへまでどん底の生活を見に行ったのも、精神において同じである。(中略)
ようやく人気上昇の坂をのぼり始めたばかりの新進作家が、安穏な生活を捨てて苦行にもひとしい旅に出たのだ。このこと自体、尋常な人間のやることではない。
私は、坐り心地のいい椅子から腰をあげて、シベリヤへ旅立った彼を思うとき、『往診中の出来事』のヒロインや『国語教師』のニキーチンや『いいなずけ』のナージャを連想しないわけにはいかない。いずれも「通常の意味での幸福」を捨て、安居を捨てて、世の人が「不幸」と見なす生活へ、心の自由を得るためにあえて「旅立」って行っている。それを作者みずから身をもって先に実践したのだ!作品世界の人物たちに歩ませるまえに、みずからその道を歩いているのだ!チェーホフはやはりロシヤ作家なのである。ロシヤ文学とは責任の文学なのだ。
筑摩書房、佐藤清郎『チェーホフ芸術の世界』P157-158
チェーホフは頭の中で考えるだけの抽象論ではなく、実際に人間としてどう生きるかを探究した人でした。頭で考えた理屈だけでは人間は動かない。まずは身をもって人間を知ること。自分が動くこと。そうした信念がチェーホフをサハリンへと突き動かしたのです。
極限の地サハリンで何を感じるのか。本や伝聞ではない、自分の生の感覚としてそれらの現実を知りたい。チェーホフはそう考え旅に出たのです。
佐藤氏が言うようにこれは並大抵のことではありません。せっかく長い間苦労をしてようやく作家としての名声を高めていたのにもかかわらず命の危険を冒してまでサハリンまで行ってしまったチェーホフ。
当然、周囲の人はこの決断に大反対したそうですが、チェーホフはまったく意に介さなかったそうです。チェーホフの意志の強さがそうしたエピソードにも表れています。
感想
サハリンは19世紀末における地獄の島でした。これはドストエフスキーの流刑先シベリアのオムスク監獄を彷彿とさせます。
ドストエフスキーが流刑となったのは1849年です。チェーホフがサハリンを訪れたのは1890年ということで時代を経るにつれ流刑先がより東へ東へと移動していったことが伺えます。
ドストエフスキーはその流刑体験を『死の家の記録』という小説で私たちに伝えてくれます。

ドストエフスキーは自ら流刑囚として体験した生々しい人間の有様をそこに描写しましたが、観察者としてやってきたチェーホフが描いた「死の家」も外部から見る冷静な視点によって同じように人間の生々しさを描いています。
ドストエフスキーとは違った立場から書かれる「死の家」の様子というのは2人の執筆スタイルの違いも感じられて非常に興味深かったです。
また北海道民である私にとってサハリンはとても近い距離にある場所です。しかしそこの歴史はほとんど知りませんでした。この作品を読むことで当時のサハリンがどのような場所だったかを知れてとても興味が湧きました。当時からアイヌの方や日本の外交官がそこにいてロシア人と共に生活していたというのも驚きでした。
チェーホフがはるか彼方のヨーロッパからわざわざここまでやって来て、帰国する時には日本にも寄りたがっていたというエピソードも私には驚きでした。やはり19世紀末のヨーロッパ人にとって日本という極東の国は未知なる興味深い国だったのでしょう。フランス人作家エミール・ゾラも日本趣味があったと言われています。私たちの住む日本の歴史を知る上でもヨーロッパ人から見た極東、日本を知ることも一つの学びであるなと感じました。
以上、「『サハリン島』あらすじ感想―チェーホフのサハリン体験~ドストエフスキー『死の家の記録』との共通点」でした。
Amazon商品ページはこちら↓
チェーホフ全集〈13〉シベリヤの旅,サハリン島 (1977年)
次の記事はこちら

前の記事はこちら

チェーホフおすすめ作品一覧はこちら

関連記事











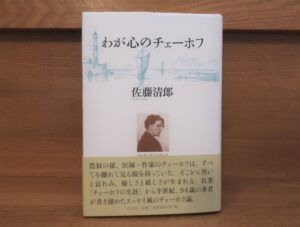



コメント