(2)スペイン異端審問の政治的思惑と真の目的とは

スペイン異端審問の政治的思惑と真の目的『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』を読む⑵
今回も引き続き、中央公論新社より2010年に出版されたトビー・グリーン著、小林朋則訳『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』を読んでいきます。

私がこの本を読もうと思ったのはソ連、特にスターリンの粛清の歴史を学んだのがきっかけでした。
スターリン時代はちょっとでもスターリン体制から逸脱したり、その疑いありとされただけで問答無用で逮捕され、拷問の末自白を強要されます。実際に有罪か無罪かは関係ありません。
こうしたソ連の歴史を読んでいると、私は思わずかつての中世異端審問を連想してしまいました。
異端審問も拷問の末自白を強要され、何の罪もない人が大量に殺害、追放された歴史があります。
そしてこの異端審問というものはドストエフスキーにもつながってきます。
ドストエフスキーと異端審問といえば、まさしく『カラマーゾフの兄弟』の最大の見どころ「大審問官の章」の重大な舞台設定です。

この本はとても興味深く、勉強になる一冊ですのでじっくりと読んでいきたいと思います。
では早速始めていきましょう。
1478年、スペイン王の勅書から見る異端審問の真の目的
1478年にはスペインはフェルナンド2世とイサベル1世という二人が王位に就いていました。

この二人はカトリック両王と呼ばれます。この二人の圧倒的な力によってスペインは統一に向かっていました。次の引用はそんな二人が要請し、教皇が出した勅書についてのお話です。少し長くなりますが非常に重要な箇所ですのでじっくりと読んでいきます。
両王は、教皇庁に使節を送って許可を求めた。一四七八年一一月一日、教皇シクストゥス四世は、スぺイン異端審問の創設を認める大勅書「工クシジット・シンチュレー・デヴォツィオニス・アフェクトゥス」を出した。この大勅書には、アンダルシアでの混乱を反映して、新たな異端審問制度を設ける宗教的動機と政治的動機とが混在している。それを如実に示すのが次の一節だ。
「余の知るところによると、汝らのスぺインなる王国の諸都市では、自らの自由意志により聖なる洗礼の水を受けて再生した者たちの多くが、ユダヤ〔教〕の律法と習慣の遵守へと密かに回帰しているらしい。(中略)こうした者どもの犯罪と、彼らに対する教皇庁の寛容な態度により、内乱や殺戮など数え切れぬほどの災厄が汝らの王国を苦しめている」。
一四四九年のトレドの場合と同じく、ここで表向き示された異端審問創設の政治的・宗教的理由からも、隠された本当の目的がはっきりと見て取れる。もちろんそれは、フェルナンドニ世がコンべルソの財産を強奪しようとしたとか、教皇庁がカスティーリャへの影響力拡大を狙ったなどということではない。
現在の都市化と、後に起こるアメリカへの帝国拡大とを推進する近代化の力が、社会の不和と対立を生み出しており、これを解消する必要があったのである。両王は、この現実を一四七七年のセビーリャでまざまざと見て、一つの解決策へと導かれる。それが、暴力の向かう先を、異端審問を通してコンべルソへ変更するという策だった。
加えて、「隠れユダヤ教徒の」コンべルソから没収した財産を資金の一部として、グラナダのイスラム教徒を改めて攻撃すれば、キリスト教徒たちを一つにまとめ、目下キリスト教徒を分断している不和を解消できると考えられた。
ああ、勇敢で冒険心に富み、栄光に満ちたスぺインよ!北はメキシコから南はぺルー、東は、ウルグアイから西はエクアドルまで、今でこそ寂れているが、かつては白漆喰の鮮やかだった植民地時代の町を一つまた一つと訪ねていると、ヨーロッパ大陸の端にある乾燥した大地に生まれた国が、どうやってあれほどの短期間に、あれほどの巨大帝国を築き上げたのだろうとの感慨を抱く。
だが、その理由はごくごく簡単なことだった。後に大国となるスぺインは、目的意識を作り出す方法の一つとして、敵を捏造したのだ。コンべルソを迫害し、グラナダを回復することで、新たに国民としての一体感と自信が生まれる素地を作り出したのである。
中央公論新社、トビー・グリーン著、小林朋則訳『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』P58-59
※一部改行しました
異端審問というと宗教的な不寛容が原因で起こったとイメージされがちですが、このスペイン異端審問においては政治的なものがその主な理由でした。
国内に充満する暴力の空気にいかに対処するのかというのがいつの世も為政者の悩みの種です。
前回の記事でもお話ししましたが、スペインでは長い年月レコンキスタというキリスト教徒対イスラム教徒の戦争が続いていました。1478年にはグラナダを残してほぼスペイン全土をキリスト教徒が占領します。

ですが、話はこれで終わりません。
それまで男たちは敵を倒す強い男であれと教育されていました。より好戦的で武に長けた者が偉いという風潮です。そうした男が多い方が戦争を戦う上で圧倒的に有利だったからです。そして対イスラム教徒の戦争をしているうちはその攻撃性をイスラム教徒に向けていればよかったのです。
しかしその戦いが終わってしまうと、行き場を失った攻撃性を持て余してしまいます。そうなると何が起こりうるかというと、その暴力が国内の不満と結びつきます。つまり国の政治に対する不満や、それならば自分が国のトップに立ってやるという軍事蜂起へと繋がっていきます。
スペイン王はそれを恐れたのです。国内の不満や暴力を自分達から反らさなければならない。これまではその矛先はイスラム教徒に向かっていた。しかしそれがなくなってしまえば次は我が身・・・なんとかして敵を作り出さねばならない。さもなくば国は内乱に突入するだろう・・・
というわけでスケープゴートを作り出す必要が生まれました。そのための制度が異端審問だったのです。
実はこうした攻撃性を反らすための方策はあの十字軍にもそういう側面があったとされています。
当時のヨーロッパでは武人が増えすぎ、彼らの食い扶持が減り、不満が高まっていたとされています。しかも彼らは相当血の気が多い存在です。過激な行動をしかねない彼らは安定した国家運営をする上で悩みの種となっていました。実は『ドン・キホーテ』で有名な「騎士道」というのもそんな彼らの道徳的向上を期待するために出来上がった側面が強いとも言われています。
十字軍はそんな彼らの攻撃性を中東のイスラム教徒に向け、存分に戦わせようという策でもありました。こうすることで当座の口減らしにもなり、さらには危険分子を国内から遠ざけることになります。為政者からすると一石二鳥以上の効果があったのでした。
ではスペイン異端審問に戻りましょう。
カトリック両王が一四七七年セビーリャに異端審問所の開設を決めたことについて、ほかにどんな選択肢があったのかは、いろいろと考えても容易に判断はできない。どうも人間というものは、危機的状況のときはスケープゴートを作りたがるものらしい。もしフェルナンドニ世とイサベル一世が王国の安定を模索しなかったとしたら、依然として続く反乱で最初の犠牲となったのは、間違いなくこの二人だっただろう。
中央公論新社、トビー・グリーン著、小林朋則訳『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』P63
攻撃性が高まった社会において、その攻撃性を反らすことができなければ統治は不可能になる。だからスケープゴートが必要になる。悪者探しを盛んに宣伝し、彼らに責任を負わすことで為政者に不満が向かないようにする。これはいつの時代でも行われてきたことです。このことは以前スターリンの記事でもお話ししました。私達も気を付けなければなりません。

悪者を作り出し、私達の憎悪や不満がそこに向くように誘導されていることに気づいたならば、いち早くそのスパイラルから抜け出す必要があります。さもなければ何が起こるか。それは歴史が証明しています。
告発が告発を呼ぶー誰がいつ自分を売るのかわからない密告合戦
異端審問がセビーリャで始まった頃、遠く離れたカスティーリャ高原の町シウダード・レアルは一触即発の状態になっていた。(中略)
設置された途端、法廷は大量の業務に追われた。異端審問所は公共エリアにあり、誰かが入っていくのを目にすると、誰もがあいつは誰を告発する気なのかと不安にかられた。自分から出頭して、心に秘めた(あるいは、秘めているはずと疑われた)やましいことを告白しない限り、ケマデーロ(※火刑場 ブログ筆者注)行きになることを人々は承知していた。かくして告発が別の告発を招き、そのため新たな法廷は多忙を極め、休めるのは祭日と、日曜日のうちアウトダフェ(※異端審問 ブログ筆者注)の行なわれない日だけという状況だった。
設置後すぐ裁かれた事例に、サンチョ・デ・シブダードとその妻マリに対する裁判がある。ニ人は、異端審問官が到着する二週間前に町から逃げ出していた。サンチョは地元の名士で、町会議員と徴税吏を務めていて敵が多かった。
彼に対する罪状は、ラビとして活動してユダヤ教の祭日を守り、イエスをあざ笑ったことだった。証言によると、サンチョは荷馬車の中でへプライ語の祈りを捧げているところを目撃され、自分のところへ動物を持ってくる際は必ず生きたまま連れてこいと指示していたという(これは、ユダヤ教の儀式に従って動物を殺すためたと推定された)。(中略)
実を言うと、コンべルソたちを隠れユダヤ教徒だとする証言は、虚実が入り混じっていた。裏づけの取れた証言もある。靴の修繕屋ファン・アレグレの自宅からはへブライ語の祈禱文が発見されたし、香料商人ファン・ファルコンは、ユダヤ教の安息日にへプライ語の祈禱書を読んでいるところを見つかっている。しかし、証言の大半はこじつけと大差なかった。たとえばシブダード家やラ・セレーラを告発する宣誓証言の多くは、一〇年以上前の出来事に関するもので、ジブダード家の場合に至っては、三〇年も前の話を持ち出した証言さえある。(中略)
このようにシウダード・レアルの異端審問は、純粋な異端者のみを罰したのではなく、宗教的立場が複雑な者のほか、善良なカトリック信者をも大勢火刑にした。これから先もよく見られることだが、真摯にカトリックを信仰している者も異端審問の犠牲者に含まれていたのだ。実際シウダード・レアルの裁判記録からは、多くの事例の根底に嫉妬や家族内不和のあったことが、はっきりと見て取れる。嫉妬と不和がある以上、一部の告発は悪意に満ちた不当なものだったに違いない
中央公論新社、トビー・グリーン著、小林朋則訳『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』P65-66
※一部改行しました
一度異端審問の制度が定着してしまうと、監視社会化が進んでいきます。そしてそこから互いに密告し合い、誰も信じられない分断社会へと変化し、それまでの自由で親密な文化は破壊されてしまいます。
この本ではこの先そうした実例をどんどん見ていくことになります。
続く
Amazon商品ページはこちら↓
異端審問: 大国スペインを蝕んだ恐怖支配 (INSIDE HISTORIES)
次の記事はこちら

前の記事はこちら

「『異端審問 大国スペインを蝕んだ恐怖』を読む」記事一覧はこちら

関連記事

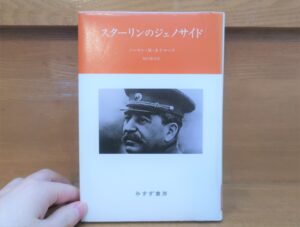














コメント