(8)いよいよ旅の始まりへ~ドストエフスキー夫妻はなぜヨーロッパへ旅立たねばならなかったのか

(8)いよいよ旅の始まりへ~ドストエフスキー夫妻はなぜヨーロッパへ旅立たねばならなかったのか
ここまでの記事でドストエフスキーの新婚生活を見てきた。
そして前回の記事「客だらけのドストエフスキー家の家庭状況と新婚早々親類からの嫁いびりに苦しむアンナ夫人」の最後ではついにアンナ夫人が限界に来てしまったことをお話しした。
今回の記事ではまずはじめにそんなアンナ夫人の様子から見ていくことにしよう。
義理の息子の無作法で厚かましいふるまい、兄嫁のおせっかい、夫とふたりきりになることもできないほどの、わたしには興味もない人々の絶えまない、うんざりするような来訪、ごたごたのおかげで絶えずおこる不安―こんな芳しくない雰囲気のうちに結婚生活の最初の数週間が過ぎて行った。
こんな暮しぶりから、夫がわたしから離れて行くように思われ、たびたび気落ちして苦しみ、こんなことでどうなってしまうだろうかと自問せずにはいられなかった。そのころのわたしの性格からすると、悲劇が起こったとしてもふしぎではなかったと思う。
じっさい、わたしはフョードル・ミハイロヴィチを限りなく愛していたが、その愛は、同年輩の男女にみられるような肉体的なものではなくて、純粋に精神的な、観念的なものだった。むしろ、才能のある、高い精神性をもった人物にたいする崇拝、賛美といったほうがいいかもしれない。
これほど苦しい思いをし、一度も喜びと幸福な目にあったことのない人、全生活を捧げてつくしてきた身内のものから当然やさしさと思いやりで報われるべきところを打ち捨てられたままのこの人にわたしの心は憐みでいっぱいだった。生涯の道づれとなり、苦労を分かちあい、生活の負担を軽くし、幸せにしてあげたいという夢想がわたしをとらえてはなさなかった。
フョードル・ミハイロヴィチは、わたしの神、わたしの偶像となり、わたしは生涯彼に仕えるつもりだった。ところがこの高い感情や夢想はみな、そのころのきびしい現実のまえにくずれ去るかもしれないようなものだったのだ。
周囲の状態から、だんだんわたしには、誤解と疑惑の時期がやってきた。あるときは、夫はもうわたしに愛想をつかしてしまったのではないか、わたしが空疎で、おろかで、まったく彼にふさわしくないこと、ひょっとすると結婚したことを後悔してはいるが、どう過ちをつぐなっていいかわからないのではないかと思った。どんなに熱烈に愛していても、もう愛されていないことがわかれば、わたしの自尊心はいっしょに生活することを許さない。たがいの共同生活が彼の重荷になるようなら、自分は犠牲になって身をひかなくてはならないとまで思った。
あるときは、彼のような「偉大な心理の洞察者」が、わたしがどんなに落ちつけずに苦しんでいるかがわからず、どうしてわたしの生活を楽にしようとつとめず、うるさい身内のものにわたしを結びつけて、あれほど意地悪するパーヴェル・アレクサンドロヴィチをかばったりするのか、と心底悲しく、夫にたいして憤りをおぼえた。
※スマホ等でも読みやすいように一部改行した
みすず書房、アンナ・ドストエフスカヤ、松下裕訳『回想のドストエフスキー』P127-128
アンナ夫人の、
「これほど苦しい思いをし、一度も喜びと幸福な目にあったことのない人、全生活を捧げてつくしてきた身内のものから当然やさしさと思いやりで報われるべきところを打ち捨てられたままのこの人にわたしの心は憐みでいっぱいだった。生涯の道づれとなり、苦労を分かちあい、生活の負担を軽くし、幸せにしてあげたいという夢想がわたしをとらえてはなさなかった。フョードル・ミハイロヴィチは、わたしの神、わたしの偶像となり、わたしは生涯彼に仕えるつもりだった。」
という言葉はこれから先の結婚生活においてあまりに大きな意味を持つ。ドストエフスキーはまさにこれから地獄のような体験をすることになるが、それでもアンナ夫人は献身的に、いや限度を超えた忍耐と寛容で彼を守り続ける。正直私たちでは想像すらできないほどの忍耐ぶりだ。そしてそれは彼女の「夢想」的な性格の賜物であり、それこそ彼女にとってドストエフスキーが「わたしの神、わたしの偶像」だったということも大きく関わっている。いずれにせよ、大文豪ドストエフスキーも常軌を逸した天才・大人物ではあるがその妻アンナ夫人も世界史上稀に見る大人物であったのだと私は思いたい。
さて、そんな悲嘆にくれるアンナ夫人ではあったがついに転機が訪れる。
アンナ夫人もその時の顛末をわざわざ「救い」という題で一章丸ごと書き残している。では、我々もその出来事を見ていくことにしよう。
だが運命は、その後フョードル・ミハイロヴィチとともに十四年間も享受した大きな幸福から、幸いにもわたしたちを見放そうとはしなかった。いまでもきのうのことのようにその日をおぼえているが、大斎の五週目の火曜日、ほんとうに思いがけなく、わたしたちの人生はいい方向にむかいだした。
その日は、いつものとおり、いやなことではじまった。パーヴェル・アレクサンドロヴィチの意地の悪いたくらみ(家じゅうから鉛筆とマッチが消えうせた)が、わたしの家事の不行届きにさせられて、フョードル・ミハイロヴィチは腹を立て、あわれなフェドーシャをしかりつけた。
そのうちに、あの面倒なお客たちがやってきて、わたしは「ごちそうし」、「楽しませなければ」ならなかった。パーヴェル・アレクサンドロヴィチは例によって、わたしに無礼なロのききようをした。夫は格別物思いに沈んでいたが、わたしともほとんど口をきこうとせず、それがひどく悲しかった。
その日の夕方、わたしたち夫婦はマーイコフ家に呼ばれていた。それを知って、わが家の客たちは、昼食もそこそこに帰っていった。けれども終日の不快さからわたしはひどく頭痛がして、神経がたかぶっていた。
マーイコフ家で新婚生活についてたずねられでもしたら泣き出すかもしれないのがこわかったので、留守をすることにきめた。夫は説得しようとしたが、わたしの断わったのが不満だったらしかった。夫が出かけるとすぐに、パーヴェル・アレクサンドロヴィチは、わたしのわがままが「父」をいらだたせたとなじった。頭痛はほんとうとは思えない、フョードル・ミハイロヴィチをおこらせるために行きたくなかったのだろう、と言う。それからまた、フョードル・ミハイロヴィチはあなたと結婚するなど、なんという「おろかな」ことをしたのだろう。あなたは「だめな主婦」で、「共同の金」を浪費する、などと言った。とうとう、フョードル・ミハイロヴィチは発作がはげしくなったようだが、それはあなたのおかげだとまで言った。そしてひとしきり悪態をつくと、家をとびだしてしまった。
あまりにもひどい悪口は、この場合、器の水をあふれさせる一滴だった。わたしのために病気が重くなったとまでひどい侮辱を受けたことは、いままで一度もなかった。この上なく腹が立って、わたしは悲しくてならなかった。頭痛はますますひどくなり、わたしはべッドに身を投げて、はげしく泣きだした。一時間半ほどたって、夫がもどってきた。マーイコフの家に行っても、わたしがいなくてつまらなかったらしく、中座して来てしまったのだ。家のなかに明りがついていないので、わたしはどこにいるかとフェドーシャにたずねた。
「ベッドで泣いていらっしゃいます」と彼女は声をひそめて答えた。
フョードル・ミハイロヴィチはおどろいて、わたしにわけをたずねた。わたしはできることなら隠しておきたかった。でもあまり熱心にやさしくたずねられるので、心がやわらいで、涙ながらに、どんなに毎日くるしんでいるか、どんなに家のなかでいやな思いをしているかを打ちあけた。
もう前のように、愛されていないのではないかと思うし、あなたも話しあおうとしない、それがどんなに悲しくてつらいか、などとわたしは言った。めったにないくらい涙をながして、夫にやさしい言葉をかけられるとなお涙があふれてきた。わたしは心の悩みのすべてを、疑いのすべてをさらけだした。
気の毒にも夫は、すっかり驚いたようすで、じっとわたしを見つめながら耳をかたむけていた。わたしにたいするパーヴェル・アレクサンドロヴィチの度の過ぎた親切ぶりを見ても、夫は、それがわたしを侮辱するものだとは思ってもみなかったことがわかった。
夫はやさしくわたしをとがめはじめた。どうして自分にたいして包みかくさずに訴えなかったのか、あの義理の息子に苦情を言わなかったのか、そんな失敬なことを即座に言わせないようにしむけなかったのか、と言って。いまでも熱烈に愛しているのに、もう愛していないなどとどうして考えることができたのか、とおどろいたように言い、自分にもこんなごたごたした生活はたえられないと結んだ。
以前も彼のところに親戚の若い連中が来ることは来たが、うちのなかが味けなかったので、ごくたまにだった。それが今では、しょっちゅう来るようになったのはわたしが親切にして、いごこちがいいからだと彼は言った。それに若い人々とのつきあい、にぎやかな会話や議論はわたしにも何よりおもしろいだろうと思ったのだという。以前のようにふたりで話しあえたのがなつかしい、たえずやってくる客のために話し合えないのが残念だ、と彼は言った。
また最近、モスクワに行ってみようかと迷っていたが、こうして話しあっているうちにぜひそうしようと決めたと言った。「もちろん、いっしょに行くことにしようよ。わたしはモスクワの自分の親類のものに引きあわせたいのだよ。ヴェーロチカ(妹)もソーニヤ(姪)も、わたしの話だけでおまえのことを知ってはいるけれど、直接知り合って、好きになってもらいたいのだよ。それに、カトコフにまた前借りをたのんでみようと思う。その金ができれば、ふたりで外国へ行けるだろう。おぼえてるだろう、それがふたりの夢だったことをね。どうして実現できないことがあるだろうか。それからカトコフには、新しい小説のことも相談してみよう。手紙で相談するのはむずかしいから、会ってするほうがいい。たとえ外国へは行けないにしても、モスクワから帰って新しい生活をたてなおし、ふたりともうんざりしているこんなごたごたからのがれるのはむずかしいことではないよ。だから、モスクワに行こう。ね、アーネチカ」
わたしが賛成したことは言うまでもない。フョードル・ミハイロヴィチは、婚約時代とおなじように、やさしく親切で親身だったから、愛が失われてしまったかという恐れや疑いなどは、煙のように消えてしまった。たぶん結婚以来はじめて、わたしたちはだれにもさまたげられずに一晩中、親しく、心をひらいて話しあった。思い立ったからには、さっそくあす出かけることにした。
翌日、身内のもの、とくにパーヴェル・アレクサンドロヴィチは、旅行の話を知ると、びっくりして機嫌がわるかった。だが夫の手もとに金がもう残り少ないのを知っていたので、金策に出かけるのだと思って、あえてとめようとはしなかった。そして別れぎわに、皮肉を言うのを忘れず、「めちゃめちゃになった家事を引きうけて、すっかり片づけておくから」と言った。わたしは気にもせず、言いかえしもしなかった。しばらくでも彼から逃れられるのが、うれしくてならなかったから。
※スマホ等でも読みやすいように一部改行した
みすず書房、アンナ・ドストエフスカヤ、松下裕訳『回想のドストエフスキー』P130-133
ドストエフスキーは基本的には優しい人だと思う。だが、時にあまりに鈍感なのである。
アンナ夫人が泣き崩れているのを見て初めて彼は事の重大さに気づいた。
そして2人は心を開いて話し合い、再び心を通わせることとなった。こうした仲直りはこれから2人の典型的なパターンとなる。2人は窮地の度にこうして話し合い、向き合い、泣き暮れ、和解するのだ。まるで彼の小説のワンシーンである。
こうして2人は晴れてペテルブルクの窮屈な家を脱出しモスクワへ旅に出ることとなった。この2人きりの旅はアンナ夫人にとって非常に幸福なものだったようで、『回想』にも次のように記している。
ぺテルブルグの生活でここ数週間のうちにわたしのなかに芽ばえた夫にたいする或る種の疎外感は、モスクワで跡かたもなく影をひそめ、わたしは婚約のころのように快活で思いやりぶかくなっていた。
夫もぺテルブルグで失いかけていた「以前のアーニャ」をここでまた見つけたと言い、自分には「蜜月」がはじまったのだ、とも言った。
いまになってようやく、ふたりのあいだに自分をこころよく思っていないあの身内さえいなければ、結婚生活を幸せに築くことができるにちがいないことがはっきりわかった。この旅の思い出はいつまでも記憶に残って、その後モスクワに行くたびに、どこでよりも幸福で、心やすらかに、満足に感じるのだった。
※スマホ等でも読みやすいように一部改行した
みすず書房、アンナ・ドストエフスカヤ、松下裕訳『回想のドストエフスキー』P145-146
アンナ夫人が述べるように、二人はここで再び愛を確かめ合った。そしてこのモスクワ旅行を通して、彼らはヨーロッパへの旅を本気で計画することになる。
ペテルブルクへの帰還後、彼らは早速身内の者達にヨーロッパ旅行の計画を切り出した。
すると案の定、兄嫁エミリヤやパーヴェルは猛反対。「私たちにくれる金はどうなる!」「行くならば金を置いてからにしてもらわねば困る!」といつものごとくドストエフスキーにたかり始めるのであった。
こうなるとドストエフスキーは弱い。彼は結局金の普請を断ることができず、せっかくモスクワで前借りできた金のほとんどを親類に渡してしまったのである。
万事休す・・・二人の西欧旅行は夢まぼろしに終わってしまうのか・・・
しかし、アンナ夫人はあきらめなかった。彼女は考え続ける。何か策はないか?どこかに糸口はあるはず・・・
彼女も必死だ。愛する夫ドストエフスキーとの幸福な結婚生活がかかっている。こんなところで負けるわけにはいかないのだ。
そしてついに彼女は閃く!これならば・・・!しかしそれには痛みも伴う。だが彼女にはもう他に選択肢はなかった。
彼女は母から贈られた大切な嫁入り道具を全て売り払うことにしたのである。
そのひとつひとつが思い入れのある大事な品だ。母は許してくれるだろうか。
悩むアンナ夫人だったが、母は「おまえの幸せがあやういのに、どうしようがあるの。おまえとフョードル・ミハイロヴィチとは、いまこそしっかり結びつかなければ、もう決してそうなる時は来ませんよ。できるだけ早く立ちなさい」と背中を押してくれたのだった。何とあっぱれなエピソードだろう。
これですべては決まった。あとは行動するのみである。アンナ夫人はこの計画をドストエフスキーに打ち明ける。
ここから先は再びアンナ夫人の言葉を聞いていくことにしよう。
でもまだ、フョードル・ミハイロヴィチを説得して、賛成してもらう大きな仕事が残っていた。家のなかで聞いてもらうわけにはいかなかった。しょっちゅう誰かに邪魔されるだろうし、パーヴェル・アレクサンドロヴィチは、ドストエフスキー家の若い連中や、いつものとおりの午前中の客が来るのを待っていて、家をはなれようとしなかったから。
さいわい、夫は何かの仕事で出かけなければならなかった。わたしは近所の薬局までお供しましょうと言った。家を出て、わたしはヴォズネセーニエ教会の小礼拝堂に寄りたいとさそった。いっしょに聖母像のまえで祈りを捧げ、ヴォズネセンスキー大通りに出て、それからモイカ川の岸に沿って歩いた。わたしはひどく興奮していて、何から話しはじめていいかわからなかった。夫のほうから助け舟を出してくれた。彼は興奮しているようすに気づいて言った。
「アーニャ、ふたりともあんなに望んでいた外国旅行を気もちよくあきらめてくれたので嬉しいよ」
「でも、外国には行けますわ、いまお話しするもくろみに賛成してくださりさえすれば」と言って、わたしはすかさず話しはじめた。
案の定、夫はわたしが自分の物を犠牲にしようとするのを喜ばず、頭からわたしのもくろみを否定した。わたしたちは言いあって、道におかまいなしに(ずっとモイカ川沿いに歩いて)、家など一軒もない、来たこともないような地区にまで来てしまった。
結婚以来二度目のことだったが、毎日がとてもつらいと告白し、ほんのニ、三カ月でいいからおだやかで幸せな生活をおくらせてほしいとわたしは頼んだ。
そして、いまのような状態では、おたがい夢みた親しい関係が失われるばかりか、すっかり別れてしまわなければならなくなるかもしれない、とはっきり言った。ふたりの愛情と幸福を救ってほしい、と夫にすがるように頼み、こらえきれずにわっと泣き出した。
気の毒にも夫は途方にくれて、どう扱っていいかわからないらしく、あわてて何もかも承知してしまった。あまりにも嬉しかったので、(そこではそう多くはなかったが)通行人にもおかまいなしに、夫に何度もつよく口づけしたくらいだった。
そこで時をうつさず、わたしは夫に総督官房に行って、いつ旅券がおりるかたずねてほしいと頼んだ。夫の旅券のことでは、いつもめんどうなことがあった。政治犯だったことのある夫は警察の監視下におかれていて、通常の手続きのほかに、あらかじめ軍総督の許可を受けなけれぱならなかった。官房には夫の才能にたいへん尊敬をはらっている知合いの役人がいたが、その人はすぐに申請書を出すようにと言い、あす責任者に取り次いでくれると約束してくれた。旅券は金曜までにおりるということだった。
その日、わたしは、どれほど限りないよろこびを感じたか、いまでもはっきりおぼえている。どんなにパーヴェル・アレクサンドロヴィチのばかげたおせっかいを聞いても腹は立たなかった。そんなものは、まもなくおしまいになるのを知っていたから。その日わたしたちは、この外国行きについて、母以外には誰にも打ちあけなかった。母は夕方やってきて、翌日質に入れるために金銀細工、富くじなどを持ちかえった。
翌水曜日、会社の鑑定人がやって来て、家具の評価額を決めていった。同じ日の夕方、身内のものほとんど全部が食事に集まっている場所で、夫は、あさって二人で外国に出かけると告げた。
「パパ、ちょっと意見を言わせてください」とパーヴェル・アレクサンドロヴィチは夫の言葉に茫然としたようすですぐにロを切った。
「意見などいらない!」と夫はどなりつけた。「みんな決められただけの額はもらえるが、それ以上は一文だってだめだ」
「でも、それはこまります!言うのを忘れてましたが、ぼくの夏外套はすっかり流行おくれになって、どうしても新しいのが要ります。それにほかに要ることもありますし……」と彼は言い出した。
「きめられた額以上には全然だめだ。わたしたちはアンナ・グリゴーリエヴナの金で外国に行くのだ。だからそれをどうこうする権利はわたしにはないんだ」
パーヴェル・アレクサンドロヴィチはまだニ、三度も何やかや要求を持ちだしたが、夫はもう耳を貸そうとはしなかった。
食事のあと、身内のものは、つぎつぎに夫の書斎にはいって行った。その場で夫は、のこりは五月一日ということにして、各自に現金でわたした。あとの分は、質に入れてから母が手わたすはずだった。
わたしは夫に言って、パーヴェル・アレクサンドロヴィチが妨害しないように、夏外套の代を追加してくれるよう頼んだ。こんなにしてやっても彼はちっともありがたいとは思わなかった。別れるときにわたしにむかって、わたしの陰険なふるまい(外国行きのこと)はこのままですむものか、秋には「カくらべをしよう、はたしてどちらが勝つかわかりゃしない」と言った。
わたしは嬉しさいっぱいで、みなから浴びせられるどんな毒舌もいっこう気にならなかった。
わたしたちは早々のうちに支度をした。それほど長く行っているつもりはなかったので、家具は質に人れ、そのほかの家財道具は母にあずけ、ほんの身のまわりのものしかととのえなかった。パーヴェル・アレクサンドロヴィチが母に手伝いさせてくれと言ったが、邪魔にこそなれ、助けにはならなかった。ただ読書して教養をつけたいからというので、書斎の家具の一部といっしょに蔵書を彼にあずけることにした。
わたしたちは三カ月のつもりで出かけたのに、ふたたびロシアの地を踏んだのは四年以上もたってからだった。そのあいだには、わたしたちの生活には幾多のよろこばしいことがあった。わたしは神が外国行きの決心をかためてくださったことを永久に感謝している。外国でこそ、わたしとフョードル・ミハイロヴィチとの新しい幸福な生活がはじまり、夫の最後の瞬間まで永つづきしたふたりの親しみと愛情が強固になったのである。
※スマホ等でも読みやすいように一部改行した
みすず書房、アンナ・ドストエフスカヤ、松下裕訳『回想のドストエフスキー』P154-157
それにしても、アンナ夫人の行動力、実務能力には驚くしかない。これでまだ20歳である。
優柔不断なドストエフスキーを説き伏せ、すぐさま旅券の手配を依頼するアンナ夫人はすでに名マネージャー顔負けだ。
そしてドストエフスキーの変化にも注目したい。あんなに身内に甘かった彼が毅然とした態度でキッパリ断ったのである。これは一大事だ。アンナ夫人のおかげでドストエフスキーの中でもこの時変化が起きていたのだろう。そしてもう一点補足したいのは、実はアンナ夫人の『回想のドストエフスキー』では触れられていないがこの時ドストエフスキーは債務監獄に入れられる可能性があったということだ。それを彼は非常に恐れていて、一刻も早く国外逃亡したかったという事情もあったのである。つまり借金取りからの逃亡である。
まあ、何はともあれドストエフスキー夫妻はこうしてヨーロッパに旅立つことになった。最後にアンナ夫人が述べていたように彼らはほんの三カ月ほどのつもりで旅に出た。だが、彼らが帰国するのはなんと4年も先のことになる。これから私はその波乱万丈な4年の旅の軌跡を追っていく。
この旅はドストエフスキーにとって決定的に大きな意味を持つことになった。そしてアンナ夫人との山あり谷ありの結婚生活は現代を生きる私たちにとっても非常に刺激的なドラマでもある。超一級の小説と言っていいほどだ。私はそうした二人のドラマに心底惚れ込みこの旅に出たのである。
では、いよいよ旅を始めよう。最初の地はドイツの首都ベルリンだ。
続く
主要参考図書はこちら↓

次の記事はこちら

前の記事はこちら

ドストエフスキー年表はこちら

ドストエフスキーのおすすめ書籍一覧はこちら
「おすすめドストエフスキー伝記一覧」
「おすすめドストエフスキー解説書一覧」
「ドストエフスキーとキリスト教のおすすめ解説書一覧」
関連記事

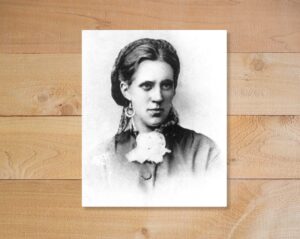











コメント