目次
2人のキリスト教理解から読み解くおすすめ参考書!W.シューバルト『ドストエフスキーとニーチェ その生の象徴するもの』概要と感想
 フリードリヒ・ニーチェ(1844-1900)wikipediaより
フリードリヒ・ニーチェ(1844-1900)wikipediaより
今回ご紹介するのは1989年に富士書店より発行されたW.シューバルト著、駒井義昭訳『ドストエフスキーとニーチェ その生の象徴するもの』です。
ドストエフスキーとニーチェの関係性において書かれた本としてはシェストフの『悲劇の哲学 ドストイェフスキーとニーチェ』が有名です。この本は以前当ブログでも紹介しました。
あわせて読みたい
シェストフ『悲劇の哲学 ドストイェフスキーとニーチェ』あらすじと感想~『地下室の手記』に着目した...
ドストエフスキーの思想を研究する上で『地下室の手記』が特に重要視されるようになったのもシェストフの思想による影響が大きいとされています。そのためシェストフの『悲劇の哲学 ドストイェフスキーとニーチェ』はドストエフスキー研究の古典として高く評価されています。
この本はドストエフスキー論の古典として知られ、今でも読み継がれている名作です。
しかしです。今回ご紹介する『ドストエフスキーとニーチェ その生の象徴するもの』はドストエフスキーとニーチェの関係性を書いた本としてはシェストフを上回るのではないかというくらい面白い一冊でした。これは私にとっても嬉しい驚きでした。こんな面白い本に出会えるなんてと驚いています。
著者のワルター・シューバルトは1897年にドイツで生まれた哲学者です。日本ではほとんど知られておらず、ドイツ本国でもあまり知られていない存在だそうです。というのも、彼はナチスに反対していたためドイツから逃れリトアニアに亡命しなければなりませんでした。そこで苦労しながらも研究を続けこの『ドストエフスキーとニーチェ その生の象徴するもの』を1939年に書き上げました。
しかし1941年に独ソ戦が始まると今度はソ連によって連行されそのまま殺害されてしまったそうです。
ですのでシューバルトは学者時代に常に迫害され続けたため歴史の表舞台に立つこともなく、ひっそりとナチス、ソ連の対立の中でその生涯を終えてしまったのです。
こうした悲運の著者による力作が今回ご紹介する『ドストエフスキーとニーチェ その生の象徴するもの』になります。
ではこの本の特徴を知る上でも著者の言葉を聴いていきたいと思います。この本の第一章には次のように書かれています。
キリスト教的作家であるドストエフスキー、そして反キリスト者の哲学者であるニーチェ、この二人は互いに比較しがたいように思われる。彼らは、それぞれどんな接近もすることのない二つの世界の永遠に対立する二つのタイプであり、共犯証人のように見える。地上の可能性と天上の可能性という人類が選ばねばならない相反する二つの可能性を、彼らはわれわれに差し出してはいないだろうか?そのように思われるのである。
しかし、そのように見るのは誤っている。彼らは、通常、そのように見なされるようなドラマの相手役ではない。彼らは、ともに同じ方向を目ざして歩いたのであり、異なっているのはその距離だけであり、架橋しがたい対立と見えるものも同じ道の残された距離の違いにすぎない。彼らは、ともに同じ問題に苦しむ。彼らはまた、それに対して同じ答えを求めたが、見出された答えは異なっていたのである。
彼らの眼は、異常なまでに、来たるべきものに向けられている。彼らは、その病弱な身体の脆さと引きかえに、予言という神の賜物を手にいれている。より高い世界の照射に対して十分な感受性をもつためには、身体生活が衰えねばならないということが彼らにおいて示される。
彼らにおいて確証されるのは、天才とは感受性だ、というボードレールの言葉である。ひたすら灼熱し、引き裂かれるまでに張りつめた神経は、最も遠く、最も微細なものによってさえも動かされるものとして役立つ。ドストエフスキーについて、「彼の魂は炎のなかにあった」と、その最良の精通者の一人であるべルジャーエフは書いており、そしてニーチェも自ら、こう告白した。
そうだ!私には自分の血統がわかっているのだ!
炎のように、飽くことなく燃えつづけ
私はわが身を焼きつくす。
私の掴むものは、ことごとく火となり、
私の棄てるものは、ことごとく灰となる。
まことに、私は炎なのだ!
〔一八八一年から八ニ年にかけて書かれた「この人を見よ」という題の詩〕
炎こそ、彼らの本質を象徴するものなのだ!それゆえ、このニ人には忘我への、憑かれた状態への、一切の限界と尺度とを爆破せんとする同じ病的な傾向が見られ、彼らに日常世界への出入りを拒むディオニュソス的悲劇の傾向、彼らの生活と苦悩との非市民性がある。例外者であることが彼らの運命なのである。
この運命が彼らを最高の者にまで高め、同時に極限の者となるまで責め苛む。この運命が彼らに希望の光に満ちた頂上を開くのであるが、しかしまた闇に満ちた深渕をも開くのである。
※一部改行しました
富士書店、W.シューバルト著、駒井義昭訳『ドストエフスキーとニーチェ その生の象徴するもの』P5-7
また、このすぐ後の箇所では同じ道を歩んでいたはずのドストエフスキーとニーチェにおける決定的な違いについて次のように述べています。
この二人は人間の欠陥を見、人間の危険を感じとる。彼らは人間に、あまりにも多くの汚点を見すぎるのである。ドストエフスキーは恐ろしいものを多く見、ニーチェは軽蔑すべきものを多く見る。それゆえ、新しい人間が出現しなければならない。新しい人間像への憧憬が彼らの思索と創作の総体である。
そして、彼らは二つの同じ人間像をもとめる。しかし、彼らが見出すものは等しいものではない。合理的なヒューマニズムに飽きたらず、彼らはひたすら人間的なものに悩む。彼らは、人間的なものを超えた何ものかをもとめる。
ドストエフスキーは、ここでも他のところでと同じように、ニーチェを超えてゆき、ニーチェが混濁した予感のなかに迷いこんだり、さまざまな矛盾に巻きこまれたりするようなところで、明るい見通しを手にいれる。
ドストエフスキーが認識するのは、神が存在するときにのみ、人間が存在するということである。人間の理念は神の理念から切り離すことができないのである。人間の生の意味や価値への問い、そしてまた神の問題は共通の形でしか解決することができない。新しい人間像は、それに倣って人間が創造された神的原像を回復せずにはありえないのである。人間をめぐる新しい知は、新しい神の体験と手をたずさえてゆく。新しい人間学は、結局のところ、新しい神学へと注いでゆく。新しい人間をさがすことは、人間のうちに神をさがすことを意味している。人間を高めることは、人間と神的なものとの関係を新たな形で接近させることを意味している。
ドストエフスキーとニーチェの全著作は最深の根拠において神をめぐる戦いであり、そしてこの二人が区別されるのは、一方にとっては、この戦いが明晰な意識となって彼のさがした神は見出されたが、他方にとっては、おのれ自身と神への道とをもはや掴みとることなく狂気のなかへ沈んでしまった、ということだけによっている。
※一部改行しました
富士書店、W.シューバルト著、駒井義昭訳『ドストエフスキーとニーチェ その生の象徴するもの』P13-15
ここでこの本の基本的な立場が明らかになりました。
著者は絶対的な真理を追い求める両者を神との関係性から見ていきます。
さらにこの本では『罪と罰』の主人公ラスコーリニコフや『カラマーゾフの兄弟』のイワンとニーチェの類似についても語っていきます。理性を突き詰めたドストエフスキーの典型的な知識人たちの破滅とニーチェの発狂を重ねて見ていきます。これもものすごく興味深かったです。
この本では興味深い箇所が山ほどあり、正直、本そのものを全部引用して紹介したいくらいの気持ちです。ですがそれをしてしまうと大変なことになってしまうのでそれはあきらめます(笑)
ただ、私自身にとってもこの本は非常に衝撃的なものであり、これからも何度もじっくりと読み返していきたいなと思える本でした。
この本はドストエフスキー、ニーチェの両者を考える上で非常に有益な参考書です。この本がほとんど知られていないのはあまりにもったいないです。ぜひともこの本がもっと広まることを願っています。
以上、「W.シューバルト『ドストエフスキーとニーチェ その生の象徴するもの』2人のキリスト教理解から読み解くおすすめ参考書!」でした。
Amazon商品ページはこちら↓
ドストエフスキーとニーチェ―その生の象徴するもの (1982年)
次の記事はこちら
あわせて読みたい
渡辺二郎・西尾幹二編『ニーチェ物語 その深淵と多面的世界』あらすじと感想~様々な視点からニーチェを...
「ニーチェとは何者なのか。」
これは永遠のテーマなのかもしれません。
読まれる時代、読む者それぞれの違いによって違った姿で現れてくるニーチェ。
この本ではそんな「多面体」というべきニーチェについて考えていく参考書となっています。
ニーチェの生涯や思想面についても簡潔にまとめられていますので、困った時の参考書としても非常に便利な1冊となっています。
前の記事はこちら
あわせて読みたい
ニーチェとドストエフスキーの比較~それぞれの思想の特徴とはー今後のニーチェ記事について一言
ニーチェの言葉には悪魔的な強さがあります。その感染力たるや凄まじいものがあります。
しかし、最近ニーチェ関連の参考書を読んだり、ニーチェ作品を改めて読み返してみると、これまでとは違ったニーチェが私の前に現れてきました。
ニーチェおすすめ作品、参考書一覧記事はこちらです
あわせて読みたい
ニーチェおすすめ作品7選と解説記事一覧~ニーチェは面白い!哲学だけではなくその人生、人柄にも注目です
ニーチェの哲学書と言えばとにかく難解なイメージがあるかもしれませんが、それでもなお現代まで多くの人に愛され続けているのも事実です。難解なだけでなく、やはりそこに何か読者の心を打つような強いメッセージがあるからこそ多くの人に読まれ続けているのだと思います。
今回はそんなニーチェの哲学書の中でも私がおすすめしたい7つの作品とニーチェに関する興味深い解説をまとめた記事をいくつか紹介していきます。
あわせて読みたい
おすすめニーチェ解説書10選~ニーチェとは何者なのか、その思想を学ぶために
この記事では私のおすすめするニーチェの解説書10冊をご紹介していきます。
これから紹介する本を見て皆さんは驚かれるかもしれませんが、一般的に「ニーチェ 入門」と検索しておすすめされる本とはたしかに違うラインナップです。ニーチェ入門の本を探している方にはハードルが高いと思われるかもしれませんが、実際読んで頂ければわかると思いますがとても丁寧でわかりやすい解説書ばかりです。
関連記事
あわせて読みたい
ニーチェ書簡におけるドストエフスキーへの言及について~ニーチェとドストエフスキーのつながりとは
前回の記事で紹介した『ニーチェ書簡集』ではドストエフスキーについて書かれた箇所がいくつも出てきます。今回はそんなドストエフスキーに対するニーチェの言及が書かれている箇所を紹介していきたいと思います。
ドストエフスキーをニーチェとの関係から考えていくという試みをしていく中で非常に興味深い内容がそこにありました。
『ニーチェ書簡集』はニーチェの素顔を知る上でも非常に興味深い作品ですが、ドストエフスキーとの関係を知る上でもとてもおすすめな一冊となっています。
あわせて読みたい
ニーチェ発狂の現場と『罪と罰』ラスコーリニコフの夢との驚くべき酷似とは
1889年1月、ニーチェ45歳の年、彼は発狂します。彼が発狂したというエピソードは有名ですがその詳細に関しては私もほとんど知りませんでした。
しかし、参考書を読み私は衝撃を受けました。その発狂の瞬間がドストエフスキーの代表作『罪と罰』の主人公ラスコーリニコフが見た夢とそっくりだったのです。
あわせて読みたい
ニーチェ『反キリスト者(アンチクリスト)』あらすじと感想~ドストエフスキー「大審問官の章」や仏教...
『アンチクリスト』は西尾幹二が述べるように私もニーチェ作品の中でも特に優れた作品であるように思えます。何より、読みやすい!そしてその思想の強烈たるや!この本はニーチェ作品の中で私の一番のお気に入りの作品です。ドストエフスキーが好きな方には特におすすめしたい1冊です。
また、個人的にこの作品で興味深かったのが仏教とのつながりです。この作品ではキリスト教に対して容赦ない攻撃を浴びせかけますが、仏教に対してはかなり好意的です。なぜニーチェが仏教に好意的だったのかもこの作品で知ることができます。
あわせて読みたい
ドストエフスキーおすすめ作品7選!ロシア文学の面白さが詰まった珠玉の名作をご紹介!
ドストエフスキーといえば『罪と罰』や『カラマーゾフの兄弟』など文学界では知らぬ者のない名作を残した圧倒的巨人です。彼は人間心理の深層をえぐり出し、重厚で混沌とした世界を私達の前に開いてみせます。そして彼の独特な語り口とあくの強い個性的な人物達が織りなす物語には何とも言えない黒魔術的な魅力があります。私もその黒魔術に魅せられた一人です。
この記事ではそんなドストエフスキーのおすすめ作品や参考書を紹介していきます。またどの翻訳がおすすめか、何から読み始めるべきかなどのお役立ち情報もお話ししていきます。
あわせて読みたい
トルストイ『わが信仰はいずれにありや』あらすじと感想~トルストイの真理探究とその結末にニーチェを...
私はトルストイのこの作品を読み始めてすぐ、うっすらとではありますがニーチェ的なものを感じました。
そしてそのうっすらとした予感は確信へと変わることなります。
トルストイはこの作品で教会を批判し、自身の信仰、思想を開陳していきます。
私はそれらトルストイの言葉に、自らの理性によって真理を掴み、それにより自己完成を目ざさんとするニーチェ的な感性を感じたのでありました。
あわせて読みたい
ドストエフスキーの代表作『罪と罰』あらすじと感想~ドストエフスキーの黒魔術を体感するならこの作品
ドストエフスキーがこの小説を書き上げた時「まるで熱病のようなものに焼かれながら」精神的にも肉体的にも極限状態で朝から晩まで部屋に閉じこもって執筆していたそうです。
もはや狂気の領域。
そんな怪物ドストエフスキーが一気に書き上げたこの作品は黒魔術的な魔力を持っています。
百聞は一見に如かずです。騙されたと思ってまずは読んでみてください。それだけの価値があります。黒魔術の意味もきっとわかると思います。これはなかなかない読書体験になると思います。
あわせて読みたい
ドストエフスキーの最高傑作『カラマーゾフの兄弟』あらすじと感想~神とは?人生とは?自由とは?
『カラマーゾフの兄弟』が発表されてから120年。これだけの月日が経っても変わらずに多くの人から愛され続けているのはそれなりの理由があります。
この物語が持つ魅力があるからこそ、読者に訴えかける何かがあるからこそ、こうして読み継がれているのだと思います。
『カラマーゾフの兄弟』はドストエフスキー作品の中でも私が最も好きな、そして思い入れのある作品です。
長編小説ということでなかなか手に取りにくい作品ではありますが、心の底からおすすめしたい作品です。
あわせて読みたい
ドストエフスキーとキリスト教のおすすめ解説書一覧~小説に込められたドストエフスキーの宗教観とは
ドストエフスキーとキリスト教は切っても切れない関係です。
キリスト教と言えば私たちはカトリックやプロテスタントをイメージしてしまいがちですが、ドストエフスキーが信仰したのはロシア正教というものでした。
そうした背景を知った上でドストエフスキーを読むと、それまで見てきたものとは全く違った小説の世界観が見えてきます。
キリスト教を知ることはドストエフスキーを楽しむ上で非常に役に立ちます。
あわせて読みたい
独ソ戦のおすすめ参考書16冊一覧~今だからこそ学びたい独ソ戦
この記事では独ソ戦を学ぶのにおすすめな参考書を紹介していきます。
独ソ戦は戦争の本質をこれ以上ないほど私たちの目の前に突き付けます。
なぜ戦争は起きたのか。戦争は人間をどう変えてしまうのか。虐殺はなぜ起こるのかということを学ぶのに独ソ戦は驚くべき示唆を与えてくれます。私自身、独ソ戦を学び非常に驚かされましたし、戦争に対する恐怖を感じました。これまで感じていた恐怖とはまた違った恐怖です。ドラマや映画、ドキュメンタリーで見た「被害者的な恐怖」ではなく、「戦争そのものへの恐怖」です。
あわせて読みたい
ソ連とナチスの虐殺の歴史を学ぶために~「独ソ戦・ホロコーストに学ぶ」記事一覧
『ブラッドランド ヒトラーとスターリン 大虐殺の真実』という作品は本当に衝撃的な一冊でした。
自分がいかに何も知らなかったかということを思い知らされました。私たちが習う世界の歴史では見えない事実がこの本にはあります。そしてそうした見えない事実こそ、私たちが真に学ぶべき事柄であるように思えます。
混乱を極める現代において、暗い歴史を学ぶことはたしかにつらいことかもしれません。ですが、だからこそこうした歴史をくり返さないためにも苦しくとも学ぶ意味があるのではないかと思います。
ぜひ、これらの記事を読んで頂けたら嬉しく思います。






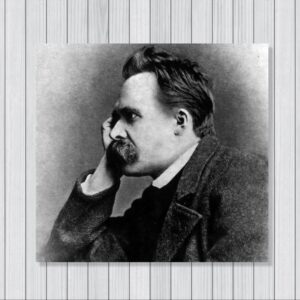














コメント
コメント一覧 (2件)
よく日本の学者にあることなのですがニーチェやこのドフトエフスキートルストイを書き表すとき書いている著者自身が教会へ行ったことがないか殆ど足を踏み入れたことがないのです。神の概念や教会の人間にとっての位置付けを体験しないまま頭で書いてしまうその不思議な勉強の徒はやがてその宗教と生活の意味を誤解をし偏狭な反ナショナリストかおぞましい自然主義者に変わってしまうのです。例えばヨーロッパやアメリカに留学などすると学者達はキリスト教を形として認識し帰国すると信者達の救いや恵みの概念を理解することは殆どありません。日本の学者にとって十字架や教会の建物またその集まりが日本の学者にとってのキリスト教なのです。
ヨーロッパ人が教会へ行かなくなった理由を教会の堕落に結びつけたがる日本の学者が余りにも多すぎるのです。それはニーチェやトルスト、イスピノザ、などを読んでそのように解釈してしまうのです。彼らも言っているように神はどこに存在していますかということなのにです。日本の学者はまずそこから勉強しなくてはならないのです。ヨーロッパ人はそこのところに気ずいたからなのです。逆にアメリカ人は家族単位でよく教会へ行きます。それは教会へ行きさえすれば神に会えると信じているからです。再び聞きますがそこに神はいるのでしょうか?万物の魂に形は存在せず見えないしそれぞれの個人で感じかたが違うということを古代の宗教はそうして存在していたのです。
コメントありがとうございます。
まさに神の問題は本当に重要な問題ですよね。
私もドストエフスキーをこれまで学んできてそのことを強く感じました。
これからも「宗教とは何か」をテーマに学び続けていきますので、今後ともよろしくお願いします。