(1)なぜ今レーニンを学ぶべきなのか~ソ連の巨大な歴史のうねりから私たちは何を学ぶのか

ヴィクター・セベスチェン『レーニン 権力と愛』を読む⑴
前回の記事で紹介しましたヴィクター・セベスチェン著『レーニン 権力と愛』は読んでいてとても面白い本でした。

これまで当ブログでは主に本の紹介とざっくりとしたあらすじや解説を続けてきました。
小説の一部分を紹介することはあっても「『~~』を読む」という形でじっくりとブログで紹介することはしてきませんでしたが、今回からいつもとは少し趣向を変えた記事を始めていきたいと思います。
というのも、これから読んでいく『レーニン 権力と愛』はレーニンその人だけでなく、当時の時代背景まで詳しく知ることができます。そして何より、私たちの生きる世界がどのようなものなのかを解き明かしてくれます。
ソ連の崩壊により資本主義が勝利し、資本主義こそが正解であるように思えましたが、その資本主義にもひずみが目立ち始めてきました。経済だけでなく政治的にも混乱し、この状況はかつてレーニンが革命を起こそうとしていた時代に通ずるものがあると著者は述べます。だからこそ血塗られた歴史を繰り返さないためにも、今レーニンを学ぶ意義があるのです。
この本を一回の記事でざっくりと紹介するだけではもったいない。自分の学びのためにもぜひ形に残しておきたいと思ったのでした。(※もちろん、これまで読んできた本がそれに価するものではなかった、というわけではありません)
ですので、備忘録というわけではありませんがこれからこの本で印象に残った箇所をご紹介していきたいと思います。
では、早速始めていきましょう。
まずはこの本の流れを知るためにも、「はじめに」の文章を読んでいきます。
はじめに
モスクワの赤の広場の脇に、今は亡き共産主義時代のソヴィエト連邦を知る人びとにはおなじみの名所が残っている。
一九二〇年代末に造られた巨大な大理石の囲いの内側に設けられたレーニンの墓所を見学しようとして、人びとが連日、チケットを買うための長い列に忍耐強く並んでいる。待ち時間は果てしなく長いが、見学そのものはあっという間に終わってしまう。
見学者は地下室に入場し、薄暗くて気味の悪いむき出しの廊下を数メートル進んで棺にたどり着く。この墓のなかで、豪華な赤いビロードの上にほぼ九〇年間横たわっている防腐処置を施された遺体を、強力なライトが照らし出している。
混雑は大変なもので、見学者が、この遺体に敬意を表したり、茫然と眺めたりする時間は最大で五分しかない。見学者の一部は外国人。大方の見学者はロシア人である。
そこに葬られている人物がだれであろうと、二一世紀の観光地としては、これは身の毛がよだつような場所だ。ソ連崩壊から二五年が経った今も、ウラジーミル・イリイッチ・レーニンがこれほど多くの群衆を引きつけ続けられるというのは、この上なく奇妙な時代錯誤に見える。
彼が引き起こした大惨事のことはだれもが知っている。彼が奉じた教義を信じている人は、いまやほとんどいない。だが、レーニンはロシアでは今も人びとの関心を引きつけ、愛されてさえいるのだ。
白水社、ヴィクター・セベスチェン、三浦元博、横山司訳『レーニン 権力と愛』p9-10
※一部改行しました

モスクワのクレムリンの観光名所として、レーニン廟は今なお多くの人がそこを訪れています。
観光ガイドブックなどでもここは間違いなく紹介される場所ではありますが、日本人にとってはおそらくあまり興味関心の湧かない場所なのではないでしょうか。かく言う私もロシア革命のことを学ぶまではこのレーニン廟というものについて深く考えたことがありませんでした。
しかし、ロシア革命を学び、その後のソ連時代を知ってからこのレーニン廟のことを考えて見ると、このお墓がとてつもないもののように思えてきました。
何と言っても、実際にレーニンの遺体が防腐処置され、そこで生前と変わらぬ姿で安置され続けているのです。モニュメントがあるとか、墓碑があってそれにお参りするというのではありません。それこそまさに朽ちない永遠の姿のレーニンがそこにいるのです。
ある意味、レーニンは普通の死者としてではなく、神としてそこに安置されることになったのです。一人の指導者が死後神格化され、永遠に生き続ける。そうした意図がこのレーニン廟にはあります。これは宗教的とさえ言えるのではないでしょうか。表向き宗教を排したソ連においてこの事実をどう考えればいいのか、これは宗教を学ぶ上でも非常に興味深いことでした。
プーチンと現在も生きるレーニン
現在のロシア指導者ウラジーミル・プーチンは、この墓を撤去するつもりはない。それどころか彼は、この霊廟が崩壊の危機にさらされていたニ〇一一年、これを修理するため巨額の支出を認めた。形を変えてではあれ、レーニン信仰は生きているのだ。
プーチンの祖父スピリドンはロシア革命のあと、レーニンの料理人を務めていたが、レーニンの遺体を元の場所に残そうとしてきたのは、現大統領の家族への思いゆえではない。その明白なメッセージは、ロシアは過去に常にそうであったように今も、圧倒的で情け容赦ない独裁的な指導者、ロシア語のヴォシチ、つまりボスを必要としているという観念、歴史的な連続性を示すことにあるのだ。
レーニンの墓は、かつては国際主義のイデオロギー、すなわち世界共産主義を象徴していた。その後、それは、よみがえったロシア民族主義の祭壇に変わったのである。
防腐処置を施されているのはレー二ンの遺体だけではない。彼の人間像もまた「保護」されている。旧ソ連で公文書の公開が始まって以来、レーニンに関する大量の新情報が明るみに出たにもかかわらず、彼の人格、動機、意図の再評価は、この三〇年間ほとんど行われてこなかった。
ソ連時代には、レーニンの伝記はすべて聖人伝であり、学校での必読図書だった。学校では、子どもたちはこのソ連国家の創設者を「レーニンおじいさん」と呼ぶように教えられた。ソ連共産党の最後の指導者ミハイル・ゴルバチョフもまた、レーニンを「特別の天才」と呼び、彼の言葉を引用するのが常だった。レーニンはあらゆる面でボリシェヴィキの清廉潔白さの支柱だった。
白水社、ヴィクター・セベスチェン、三浦元博、横山司訳『レーニン 権力と愛』p10
※一部改行しました
レーニン信仰は今も生きています。プーチン大統領もその力を無視していません。
そしてプーチン大統領の祖父がレーニンの料理人を務めていたということも面白いですよね。プーチン大統領とレーニンの不思議なつながりが垣間見えます。
レーニンの今日的な意義
レーニンが自分の禁欲主義的なイメージに沿って作り上げた共産主義世界は、歴史の屑かごに捨て去られたかもしれない。しかし、彼はなおも今日的な意義をもっている。
冷戦の末期、民主主義の理念と新自由主義が勝利した。社会主義とそのさまざまな形態は完全に信用を失墜した。政治的、経済的な問題については、グローバル化した市場がもたらすもの以外の解決策はないように思えた。
だが、ニ〇〇七~ニ〇〇八年の金融危機と景気後退のあと、世界は様相を変えた。西側世界の多くの国で、民主主義プロセス自体への信頼が失われた。数百万の人びとにとって、二世代が基本的な前提と受け容れてきた確かなことども、すなわち、世の中の現実が、おしなべてあやふやになってしまった。レーニンならおそらく、ニ〇一七年の世界を革命期の幕開けとみなしたことだろう。
レーニンがいま、再び脚光を浴びているのは、彼が提出した欠陥だらけの、血塗られた、残忍な、見当違いの解答ゆえではなく、わたしたちがいま、答えを求めているのと同じような問題について、彼もまた同じように答えを求めていたからなのだ。
数百万人の人びと、そして左右両派の危険なポピュリスト指導者たちの一部は、公平な社会の創設、自由と繁栄の維持、あるいは不平等と不正義の是正に、リべラル民主主義ははたして成功したのか、と疑っている。
いま「グローバル・エリート」とか「一パーセント」という言葉が明らかにレーニン主義的な意味で使われている。レーニンの解決策がどこかで再び適用されることはありそうもない。だが、彼が発した疑問はいまも絶えず問われており、同じように血塗られた方法で答えられるかもしれないのだ。
白水社、ヴィクター・セベスチェン、三浦元博、横山司訳『レーニン 権力と愛』p11
※一部改行しました
ソ連の崩壊により資本主義が勝利し、資本主義こそが正解であるように思えましたが、その資本主義にもひずみが目立ち始めてきました。経済だけでなく政治的にも混乱し、この状況はかつてレーニンが革命を起こそうとしていた時代に通ずるものがあると著者は述べます。だからこそ今レーニンを学ぶ意義があるのです。血塗られた歴史を繰り返さないためにも。
レーニンの政治手法
レーニンはクーデターで権力を掌握したが、徹頭徹尾テロによって行動したわけではない。レーニンは多くの面で完全に現代的な政治現象であり、西側民主主義国のわたしたちにも、独裁体制下の人びとにもおなじみの、デマゴーグの一種なのだ。
彼は権力を追求するに際して、何であれあらゆることを人びとに約束した。複雑な問題に、単純な答えを提示した。恥じることなく嘘をついた。彼は「人民の敵」というレッテルをあとで貼ることができるスケープゴートを見分けた。勝つことがすべてであるという観点で自己を正当化した。目的が手段を正当化したのである。
洗練されていると考えられた西側の政治文化のなかで、最近選挙を経験した人なら、だれしもレーニンに思い当たるかもしれない。レーニンは、彼よりも一世紀あとの評論家が言う「ポスト真実の政治」の生みの親なのである。
白水社、ヴィクター・セベスチェン、三浦元博、横山司訳『レーニン 権力と愛』p12
※一部改行しました
レーニンの政治手法は現代にも通じます。この本ではそんなレーニンの恐るべき政治的手腕が語られていきます。この後の記事でも紹介しますのでぜひ読んで頂きたい内容です。彼のような政治家による恐怖政治から身を守るためにも、現代を生きる私たちに必要な知恵であると私は思います。
レーニンの人物像
レーニンは自分のことを理想主義者だと考えていた。彼は怪物でも、サディストでも、卑劣漢でもなかった。人との個人的な付き合いでは、いつも優しく、自分の育ちにふさわしく、中流の上の紳士として振る舞った。彼はうぬぼれ屋ではない。笑うことができ、時としてその笑いを自分自身に向けた。彼は残忍ではなかった。スターリン、毛沢東、ヒトラーとは違って、自分が犠牲にした人物の死の詳しい状況を尋ね、それを味わってみたりすることはない。
いずれにせよ、彼にとって死とは理論的なものであり、単なる数字に過ぎない。レーニンは、他の独裁者たちが好んだような制服や軍服を着ることはなかった。しかし、他の革命家たちとの抗争の年月、さらに手に入れた権力を維持する年月に、敗れた相手に寛大さを示したり、人道的行為を行ったりすることは、それが政治的に役立たない限り、なかった。
彼は、より大きな目的のためなら、敵に対する政治的テロは正当化されるという思想に基づく体制を作り上げた。この体制を完成したのはスターリンだが、その考え方はレーニンのものだ。
レーニンは必ずしも悪人だったわけではないが、ひどい所業を行った。長年彼を崇敬してきた古参同志の一人だが、のちに彼を恐れ、嫌うようになったアンジェリカ・バラバーノワは、レーニンの「悲劇は、ゲーテ風に表現するなら、善を望みながら・・・悪を生み出したことだ」〔『ファウスト』のメフィストテレスの言葉「常に悪を望み、常に善を成す」〕と鋭く指摘している。彼が作り出した悪の最たるものは、スターリンのような人物な自分が亡きあとのロシアを指導する地位に残してしまったことである。
レーニンはしばしば厳格なイデオローグ、共産主義の狂信者として描かれ、ある意味ではそれは正しい。彼はマルクス主義理論を始終、ロにした―「理論なくして革命政党はあり得ない」と言ったことはよく知られている。
しかし、彼がもっと頻繁に支持者に主張した一つの論点がしばしば忘れられている。それは、「理論は導き手であって、聖典ではない」というものだ。
イデオロギーが便宜上の判断と衝突するとき、彼は必ず、教義上の純正さよりも戦術的な道の方を選択した。それで目標に近づくことができるなら、考えをすっかり変えることができた。彼はイデオロギーと同時に、情動に突き動かされていた。剰余価値に関するマルクスの理論への信念と同様に、強力にレーニンを動かしていたのは、皇帝暗殺を企てたとして兄が処刑されて以来、彼に宿った復讐への渇望だった。
レーニンは権力を欲し、世界を変えることを望んだ。彼は四年と少しの間、自らの手に権力を握り、その後、病気のため肉体的にも精神的にも権力を維持することができなくなる。だが、彼が予言したとおり、一九一七年のボリシェヴィキ革命は「世界をひっくり返した」。ロシアも、アジアから南米に至る多くの国々も、それ以降、立ち直っていない。
白水社、ヴィクター・セベスチェン、三浦元博、横山司訳『レーニン 権力と愛』p12-13
※一部改行しました
「レーニンは必ずしも悪人ではない」というのが重要なポイントです。その必ずしも悪人ではない人間が「目的のために手段を正当化し、多くの人を殺めることになった」のです。
レーニンは世界史上の人間で特殊な人間だから私たちとは関係のない問題だと、思ってしまうかもしれません。しかし人間の本質とは何かを考えていく上でレーニンという存在は非常に重大な問題を提起しているように私には思えるのです。
そしてこの引用の後半に出てきた一節に、レーニンの兄が皇帝暗殺を企て、処刑されたという話が出てきます。レーニンがなぜ革命家になったのか、なぜ彼は冷酷なまでに革命を成し遂げようとしたのかのヒントがここにあります。これも後の記事で改めて見ていきたいと思います。
続く
Amazon商品ページはこちら↓
次の記事はこちら

「レーニン伝を読む」記事一覧はこちらです。全部で16記事あります。

関連記事

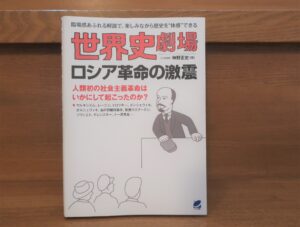









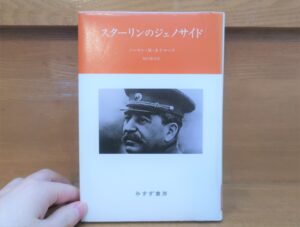

コメント