チェーホフ『可愛い女』あらすじと感想~トルストイ大のお気に入りの作品の驚きの裏話とは

チェーホフ『可愛い女』あらすじ解説―トルストイ大のお気に入りの作品

チェーホフ(1860-1904)Wikipediaより
『可愛い女』は1898年にチェーホフによって発表された作品です。
私が読んだのは中央公論社、神西清、池田健太郎、原卓也訳『チェーホフ全集 11』所収の『可愛い女』です。
早速あらすじを見ていきましょう。
『可愛い女』の主人公オーレニカは、退職八等官。プレミャンニコフの娘で、「優しい、穏やかな眼差の、物静かな、人のいい、同情深い、たいへん健康なお嬢さんだった。彼女の肉づきのいいばら色の頬や、黒いほくろのあるやわらかく白い頸すじや、なにか快いことを聞くときなど、しばしばその顔にあらわれる、善良でナイーヴな微笑を見ると、男たちはこう思うのだった―『うん、悪かないな……』」そういう女だ。
この娘の前に、チヴォリ遊園地の経営者で、劇団の指導者クーキンが現われる(この名は「窮屈な」から作られている)。背の低い、痩せて黄色い顔をした、弱々しいテノールでロをゆがめて話す癖のある男である。(中略)
クーキンは三日も降りこめられ、苛立ってオーレニカにしきりにぐちる。
「オーレニカは黙って、真剣にクーキンのいう言葉を聞いていた。ときどき彼女の眼に涙があふれた。そのうち、ついにクーキンの不幸が彼女の心を動かし、彼女は恋した」
恋の初めが相手の不幸への同情であったことに、この女の恋の本質がある。彼女の愛の対象は初めは父であり、次に叔母であり、その次にフランス語の教師であり、そして今度は不幸な興行師なのである。
「彼女はいつも誰かを愛していたし、愛なしではいられなかった」のである。こうして彼女はクーキンの妻となる。
筑摩書房、佐藤清郎『チェーホフ芸術の世界』P126-127
タイトルにもあります「可愛い女」とは「いつも誰かを愛していたし、愛なしではいられない」オーレニカを指し、この物語は彼女をヒロインに進んで行きます。
上のあらすじでは興行師のクーキンと結婚しました。
彼女は彼を溺愛し、彼女が語る言葉はクーキンとそっくりになっていきます。
他の人たちと話す時も彼女はいつも彼の受け売りの演劇論を語るようになってしまうほどでした。
しかし不幸なことにこの夫はあっさりと死んでしまいます。
絶望に暮れる彼女ですが、しばらくすると今度は材木屋と再婚することになりました。
すると驚くべきことに彼女は演劇のことはすっかり忘れ今度は材木の話しかしなくなります。
そして6年経つとまたまた材木屋の夫も亡くなってしまいます。
さて彼女はどうなってしまうのでしょうか。
やがて、オーレニカは獣医の愛人に納まる。そうなると、今度は獣医関係のことばかリ口にするようになる。有角家畜のペストがどうの、家畜の結核がどうのという獣医たちの話に口をはさむようになる。
「わからないことは言わないようにって、ぼくはあんなに頼んだじゃないか!ぼくたち獣医仲間の邪魔をするなよ」
「でも、ヴォロージェチカ、わたし、なんの話をしたらいいの?」
彼女にとって「意見」とは受け売りのほかにはないのだ。オーレニカの相手に廻った三人の男のなかで、この獣医がいちばんそっけない。この男も、やかて連隊とともにいずこへか転任してしまう。彼が去ると、彼女はまたも完全に自分の意見を失う。
筑摩書房、佐藤清郎『チェーホフ芸術の世界』P127-128
ここで明らかになりましたがオーレニカには自分の意見がないのです。言い換えればエゴ・自己主張がないのです。
愛した相手に献身し、彼女は完全にその人物と一体化してしまう。悪く言えば自分がなく、のめり込んでいるということになってしまいますが、愛した相手に深く献身する姿は読む者に不思議なインパクトを残します。
オーレニカは捨てるべき自我を初めから持たない。意志的に力む必要は少しもないのだ。ごく当り前に、自然に、生れながらの気持のままに振舞っていればよかったのだ。もっとも、そのほかの生き様とて彼女にはなかった。賢者たちが苦悩の中で捨てかねているエゴとか自意識とかを、彼女はもともと持たないのだ。結構なことに、生れながらの菩薩さまなのである。
筑摩書房、佐藤清郎『チェーホフ芸術の世界』P125
ここで注意したいのは西欧世界では自己主張を重んじるということです。「私は私」という主張をしなければなりません。そんな世界において生まれながらにエゴがないというのがこのオーレニカの特徴なのです。
世の「賢女」たちも「愚女」たちも、おしなべて無意識であって、おのれのなかの賢にも愚にも気づいていない。無意識に生きる可愛い女がトルストイの羨望のまとになったのは、彼が人一倍意識的に生きていたからだ。
捨てようにも捨てきれぬ強烈な自我のひとであって初めて、「愚」女を無条件に讃美できたのである。トルストイが『可愛い女』のヒロイン、オーレニカをたたえ、人前で三度も作品を朗読したことは、彼の心の葛藤の歴史からすればごく自然なことなのだ。
筑摩書房、佐藤清郎『チェーホフ芸術の世界』P125
自分の意見を何も持たないというのは一般的な価値観では言えば「愚人」となります。しかしそこにこそ「聖」がある。自我を捨てて他者に献身できることこそ「聖」ではないかとトルストイは感じたのです。
そして興味深いことに、佐藤氏の指摘によるとトルストイは「捨てようにも捨てきれぬ強烈な自我のひと」であったとされています。
たしかにトルストイの伝記を読むと、尋常ではない意志力の持ち主であり、常軌を逸した行動をいくつもしています。晩年の家庭内の不和や家出による死もまさにそれを示しています。
『可愛い女』を大絶賛し他人の前で何度も朗読までしたトルストイ。彼がいかにこの作品を気に入っていたかがうかがわれます。
こうしたところにもトルストイの考える理想像の特徴が見えてきます。
そして実はこれに関して一つ裏話があります。
と言うのもチェーホフはトルストイのような意図で『可愛い女』を書いたわけではなかったのです。
チェーホフはまったく自分の意思のないオーレニカを風刺する意図で『可愛い女』というタイトルにしこの作品を書き上げたのでした。
以前紹介した『箱にはいった男』でチェーホフは自分で何も考えられず、他人の考えたものに盲目的に隷属する人間を批判しました。この作品でもオーレニカに対して批判とまではいかなくとも、トルストイのように彼女を褒めたたえるような意図はなかったとされています。
つまりトルストイはチェーホフの意図とは違ったところでオーレニカに感激し、終生この作品を讃美し続けていたのです。
佐藤氏はこう述べます。
ここで、文学作品における作者の意図と作品との乖離の問題が起る。芸術作品はそれぞれ一定のふくらみを持つ。人それぞれにその振幅の範囲内で、自分流のアクセントをつけて読めるものだ。トルストイのような読み方はけっして邪道とは言えない。作品とは、作者の手を離れたとたん独り歩きをするものだから。それ自身の命を持って。
筑摩書房、佐藤清郎『チェーホフ芸術の世界』P129
ある作品をどのように読むか。
そこに読み手の個性が表れるという好例がこの『可愛い女』とトルストイの組み合わせなのではないかと私は感じました。
今後トルストイの作品を読んでいくことになりますが、チェーホフとの違いを感じながら読んでいくのも楽しみのひとつになっていきそうです。
以上、「チェーホフ『可愛い女』あらすじ解説―トルストイ大のお気に入りの作品」でした。
Amazon商品ページはこちら↓
チェーホフ全集〈11〉小説(1897-1903),戯曲1 (1976年)
次の記事はこちら

前の記事はこちら

チェーホフおすすめ作品一覧はこちら

関連記事











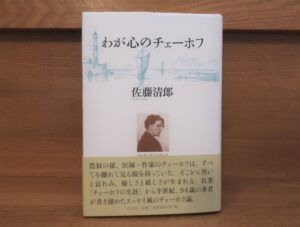



コメント