シラー『群盗』あらすじと感想~『カラマーゾフの兄弟』に強烈な影響を与えたシラーの代表作!

10歳のドストエフスキーが衝撃を受けた戯曲!シラー『群盗』
今回ご紹介するのは1781年にシラー(シルレル)によって発表された『群盗』です。私が読んだのは筑摩書房、実吉捷訳『世界文学大系18 シラー』所収の『群盗』です。この作品はなんと、シラーが22歳の年に書かれた作品で、一躍文壇の寵児に躍り出た出世作になります。

上のタイトルにもありますように、この作品はドストエフスキーが10歳の時、演劇でこの『群盗』を観て生涯忘れえぬ衝撃を受けたとされている作品です。
ドストエフスキー自身、1880年8月18日オズミードフ宛の手紙で次のように述べています。
小生は生まれて十歳の時、モスクワで、モチャーロフを主役としたシルレルの『群盗』を見ました。誓って申しますが、そのとき受けた強烈無比な印象は、小生の精神的方面にきわめてよき影響をおよぼしました。
河出書房新社、米川正夫訳『ドストエーフスキイ全集18 書簡下』P430
また、時代は遡りますが1840年の1月1日、兄ミハイルに宛てた当時19歳のドストエフスキーの手紙には次のようにも書かれています。
兄さんは、ぼくがシラーを読んでいないと書いてきましたね。とんでもないまちがいですよ、兄さん!ぼくはシラーを丸階記し、シラーの言葉で話し、シラーの言葉でうわごとを言っていたんですよ。(中略)
シラーの名は、ぼくにとっては、限りない空想を呼び起してくれる、親密な、一種の魔法めいた響きになりました。
新潮社 工藤精一郎訳『ドストエフスキー全集20 書簡⑴父母兄弟への手紙』P46
ドストエフスキーがいかにシラーに傾倒していたかがうかがわれる手紙ですね。
このように、シラーの作品はドストエフスキーの文学人生にとって非常に大きな影響を与えたとされています。
では早速シラーの『群盗』のあらすじを見ていきましょう
シラー『群盗』のあらすじ
舞台は18世紀中頃のドイツ。
領主の老フォン・モール伯爵とその二人の息子カール・モールとフランツ・モールを中心とした物語です。
領地を離れていた放蕩息子のカールはその放蕩ぶりに父からお叱りを受け、反省の手紙を父の老伯爵に送ります。
しかし密かに継承権を狙う弟のフランツはその手紙を握りつぶし、父を騙して偽の手紙をでっちあげカールに送り付けます。
老伯爵は放蕩息子のカールを叱りながらも、その高潔で善なる性格をよく知っていました。ですので一刻も早くカールと仲直りしたいというのが本心でした。
しかしフランツによる偽の手紙によって、カールは父から断絶されたと思い込みます。
カールは絶望し、そのまま悪友に引きずられ盗賊団の首領へとなし崩し的になってしまうのでした。
カールと老伯爵をうまく引き離したフランツは自らの謀略を進めていきます。
もはや邪魔者以外の何者でもない父を殺すため、「兄カールはあなたのせいで絶望して死んだ」と伝えます。カールを強く愛していた父に精神的なショックを与えて殺そうとしたのです。
そしてフランツは父を無人の塔に幽閉し、自らが跡継ぎとしてその権力を奪うのでありました。
一方その頃カールは盗賊団の首領になっていましたが、彼自身はあくまで義賊でありました。悪をこらしめ、弱いものには手を出さず、むしろ彼らに手を差し伸べるほどでした。
しかし仲間は札付きのごろつきで、カールのあずかり知らないところで多くの極悪非道な行いをしていました。そしてついに彼自身も手を汚さなければならない時がやって来てしまったのです。これが後にカールを苦しめます。
そんなカールがついに自らの領地に帰り、弟フランツの陰謀を知り、自らが置かれた立場を知ることになります。
そして彼は義憤に燃え、フランツと戦うことを決心するのです。
さて、兄カールと弟フランツの兄弟の争いはどうなってしまうのでしょうか。
これが『群盗』のおおまかなあらすじとなります。
ドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』と『群盗』のつながり
ドストエフスキーがシラーの『群盗』との衝撃的な出会いを果たしたのが10歳の時。
そしてドストエフスキー最後の大作『カラマーゾフの兄弟』が書かれ始めたのはそれから45年以上も後のことです。
しかしドストエフスキーの中には幼い頃に受けたあの衝撃が未だに心の内に感じられたのでしょう。
『カラマーゾフの兄弟』にはシラーを思わせる点がたくさん出てきます。
『世界文学大系18 シラー』の巻末解説を引用します。
ドストエフスキーの作品、とくに『カラマーゾフ兄弟』の中には、シラーの痕跡がはっきりと認められる。シラーの名そのものもたびたび出て来る。一例だけを挙げるが、『カラマーゾフ兄弟』の始めのほうにおいて、この小説のライトモティーフが示される、その文句がすでにそうした特徴を示すものである。兄弟の父親がまずイヴァン・フョードロヴィチを指ざして言う。「あれはわしの忰だ。わしにそっくり生き写しだ。あれはわしがひどく尊敬する奴で、いわば、カール・モールだ。だが、あそこにいるわしの忰、ドミートリー・フョードロヴィチ、あいつはちっとも尊敬すべきでないフランツ・モールだ。両方ともシラーの『群盗』の中の奴らでさ。わし自身はところで、この場合、もちろんご主人のモール伯爵だ」。
筑摩書房、実吉捷訳『世界文学大系18 シラー』P443
また、著名なドストエフスキー研究者モチューリスキーによる『評伝ドストエフスキー』にも次のように書かれています。
たしかに「カラマーゾフ兄弟」の筋は、どことなくシラー劇のテーマを思わせるものがある。いんぎんの仮面の下に父親への憎悪を隠し、父の死に道義的に責任のあるイワン、それに父親から自分の命を狙っているのだろうと疑われ、冤罪に打ち拉がれているドミートリー―このふたりは、作品の構成で、『群盗』の敵対しあう兄弟と似た位置を占めている。ドストエフスキーは、シラー劇をまだ子どものころに見たことがあり、名高い役者のモチャーロフの演技を生涯記憶していた。高潔だが放蕩息子のカルル・モールの面影は、ドストエフスキーの想像力のなかで、かっとなりやすく太っ腹なドミートリーと深いかかわりを持っている。「不遜な息子」の人物像をシラーの熱情的ロマンチシズムが染めている。ドミトリーが、このドイツ詩人の「歓喜の頌」を朗誦し、その宇宙的な生命感に酔い痴れるのも理由のないことではない。
筑摩書房 モチューリスキー 松下裕、松下恭子訳『評伝ドストエフスキー』P635
たしかに、シラーの『群盗』を読んでいると、何度も何度もカラマーゾフ的なシーンにぶつかります。
特にカラマーゾフ家の長男ドミトリーに関してはそっくりです。
『群盗』の中からその一部をご紹介します。
下の引用にあるモールこそ、兄のカールのことです。
この場面は盗賊達の集団の中でモールが自分の運命に嘆き苦しみ、その感情を高々と吐き出していくシーンです。モール以外の人物は皆盗賊仲間です。
シュワルツ 日が沈んでゆくあのながめは、じつにすばらしいじゃないか。
モール (そのけしきに見とれながら)英雄はこんなふうに死んでゆくのだな。―あたまがさがるよ。
シュワルツ ひどく感動しているようだね。
モール まだ子供だったころ―太陽のように生きて、太陽のように死にたいと、わたしはいつも考えていた―(苦痛をおさえながら)あれは子供っぽい考えだった。
シュワルツ おれもそうしたいと思うな。
モール (帽子で顔をおおう)あのころはなあ――わたしをひとりにしておいてくれよ、きみたち。
シュワルツ モール、モール。いったいどうしたんだい。―すっかり顔色が変っているじゃないか。
グリム こりゃおどろいた、どうしたんだ。気持でも悪いのか。
モール あのころ、おれは夜のいのりをうっかり忘れると、そのあとどうしてもねむれなかったものだ―
グリム おい、気はたしかか。子供のころのことを考えて、気がとがめるとでもいうのかい。
モール (グリムの胸にあたまをあてる)兄弟、兄弟。
グリム どうした。子供みたいになるな―おい、たのむぜ―
モール 子供だったら―子供にかえれたらなあ。
グリム よせ、よせ。
シュワルツ 元気をだせよ。見ろ、この画みたいなけしきを―気持のいい夕げしきをさ。
モール なるほど、きみ、この世はいかにも美しいね。
シュワルツ そうだ。よく言ったぞ。
モール この大地はいかにもすばらしいなあ。
グリム よし―よし―その調子なら安心だ。
モール (ぐったりとなって)しかもこの美しい世のなかで、わたしはこんなにみにくい人間なのだ―このすばらしい地上で、わたしは人非人なのだ。
グリム やれやれ、どうも。
モール わたしの純潔、わたしの純潔。―みんな、聞いてくれ。だれもかれもが,春のおだやかな光をあびようとして、そとへ出て行った―なぜわたしだけが、天国のよろこびのなかから、地獄を吸いとるのだ。―だれもかれもじつに幸福で、平和の精神によって、みんななごやかに暮らしている―全世界は一家族で、天にはひとりの父があるのに―それはわたしの父ではない―わたしだけがのけ者で、わたしだけが、純潔な者の隊列から、とりのけられた―わたしには、人の子というやさしい名前は、さずかっていないし―恋人のやるせないまなざしに、見つめられることもなく、親友の抱擁を受けることも、けっしてけっしてありはしないのだ。(はげしくうしろへとびしきりながら)人殺しにとりまかれ―まむしにかこまれ―鉄のきずなで、悪徳にしばりつけられ―悪徳というゆらぐ葦に乗って、罪業の墓のなかへ、よろよろとはいってゆく―幸福な世界の花々のまんなかで、泣きわめいているアパドンナというところだ。
シュワルツ (ほかの連中に)わけがわからん。今まで一度だって、こんな様子を見せたことはないんだがね。
モール (うれわしげに)母親の胎内にもどれたらなあ。こじきに生まれてくればよかったになあ。―いや、それ以上ののぞみはないのだ。おお神よ―なれるものなら、その日かせぎの連中のひとりになりたい―そうなれば、こめかみから血がしたたるほど、あくせくはたらこうものを―たった一度のひるねの楽しみを―たったひとつぶのうれしなみだを、手に入れるためにな。
グリム (ほかの連中に)まあ、じっと待ってろ。発作はもうしずまりかけている。
モール あのころは、毎日が楽しく流れていったものだ。―おお、平和の日々よ。わが父の城よ―みどりの、夢多かりし谷々よ。おお、わが幼年の楽園のあらゆる場景よ。おまえたちは、もう二度ともどってこないだろう―二度とこころよいそよ風で、わたしのもえる胸をひやしてくれることはないだろう。―いっしょに悲しんでくれ、自然よ。―あれらは二度ともどってこないだろう。二度とこころよいそよ風で、わたしのもえる胸をひやしてくれることはないだろう。―すぎ去った、すぎ去った。もう取返しがつかないのだ。
筑摩書房、実吉捷訳『世界文学大系18 シラー』P155-156
私はこれを読んだ時、ドミトリーしか感じられませんでした。『カラマーゾフの兄弟』を読んだ方ならきっとわかっていただけると思います。
まあ、ドストエフスキーがシラーの影響を受けてドミトリーを書いているのですから当然と言えば当然なのですが、それにしてもこのドミトリーっぷりには驚かされます。
逆に言えば、おそらくシラーから入った人が『カラマーゾフの兄弟』のドミトリーを読めば「なんてシラー的なんだ」と驚くのでしょう。
それほどまでに似ています。
ドストエフスキーがわざわざ最晩年の最大の大作にこれを持ってくるというのは、やはり並々ならぬ思い入れがあったからこそなのでしょう。
シラーの『群盗』は父親殺し、兄弟殺しのモチーフが用いられています。
ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』もたしかに父親殺しの事件が中心となった物語です。
ドストエフスキーが父親殺しをどう考えたかというのは非常に難しい問題で、今も議論が続いています。
ドストエフスキーがシラーの『群盗』を『カラマーゾフの兄弟』に持ち込んだのも父親殺しという共通のテーマがあったからというのはよく指摘されます。
ただ、ここでは長くなるのでご紹介できませんが、先ほどのモチューリスキーの『評伝ドストエフスキー』では単に父親殺しで共通してたから用いたというよりも、もっと複雑な背景の下ドストエフスキーはこの作品を用いたと推測しています。
いずれにせよ、ドストエフスキーは謎の多い作家であり、簡単には断言できない問題が多々あります。父親殺しの問題はその最たるものです。ここではこれ以上は深入りしませんが、個人的にはもっと深めていきたいテーマであります。
※2022年8月15日追記 このドストエフスキーと父親殺しの問題についてまとめた記事をここに掲載します。ぜひこちらもご覧になって頂けましたら幸いです。

『群盗』は『カラマーゾフの兄弟』とのつながり云々というよりも前に、そもそも読んでいて非常に面白い作品でした。
場面展開もスピーディーで物語から目が離せなくなります。
そして何よりも登場人物達のセリフです。これが格好いい!自分の胸の内に燃え盛る感情を言葉にして吐き出すかのようなセリフ。
シェイクスピアの作品もそうですが、実際に声を出して読んでみると余計にそれが感じられます。そして何より言葉に出すと、より気持ちがいい!(※怪しい人と思われるのでそばに誰もいないときにやりましょう)
そんなことをシラーを読みながら感じたのでありました。これは名作です。『カラマーゾフの兄弟』に関心のある人はもちろんですが、そうではない人もシラーのこの作品を読む価値は間違いなくあります。面白い作品です。おすすめです。
以上、「シラー『群盗』あらすじ解説―ドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』に強烈な影響!」でした。
Amazon商品ページはこちら↓
世界文学大系〈第18〉シラー (1959年)詩・犯罪者・素朴文学と有情文学について・崇高について・世界とは何か・群盗・たくらみと恋・オルレアンの処女・ドンカルロス
次の記事はこちら
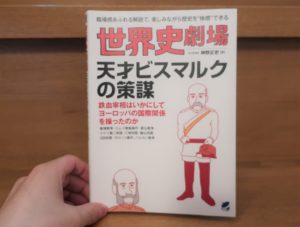
前の記事はこちら

関連記事
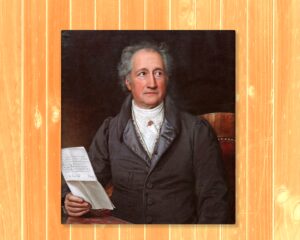


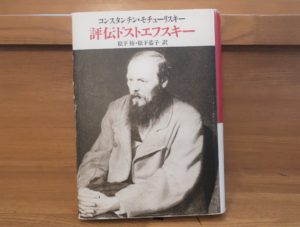

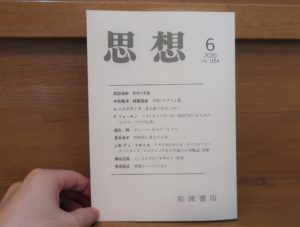







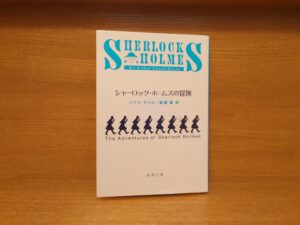
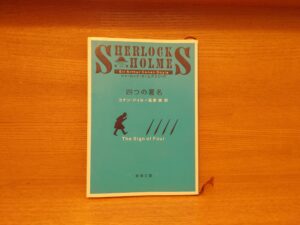



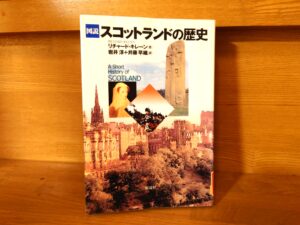
コメント