シェイクスピア『ヘンリー五世』あらすじと感想~ハル王子改めヘンリー五世がフランス征服に挑む!英仏百年戦争を描いた歴史劇

シェイクスピア『ヘンリー五世』あらすじと感想~百年戦争のアジンコートの戦いでイギリスが大勝。ハル王子改めヘンリー五世の治世を描く歴史劇
今回ご紹介するのは1599年頃にシェイクスピアによって書かれたとされる『ヘンリー五世』です。私が読んだのは筑摩書房、松岡和子訳です。
早速この本について見ていきましょう。
百年戦争のアジンコートの戦い(1415年)前後に焦点を当て、イングランド王ヘンリー五世の生涯を描いた史劇。『リチャード二世』、『ヘンリー四世第一部・第二部』に続く四部作の最終作。ヘンリー五世は前作『ヘンリー四世』で、手に負えない少年・ハル王子として登場していた。その若き王子も『ヘンリー五世』では高貴で勇壮な王に成長し、フランスの征服に乗り出す。
Amazon商品紹介ページより
『ヘンリー五世』は前回の記事で紹介した『ヘンリー四世』の続編にあたる作品です。

『ヘンリー四世』で放蕩息子として頼りない姿を見せていたハル王子ですが、前作の終盤で父ヘンリー四世から王冠を受け継ぎ、立派な王になることを誓いました。そのハル王子改めヘンリー五世がどのような王になったかが今作『ヘンリー五世』で語られます。
この作品について巻末の解説では次のように述べられています。
この作品は、高貴で勇壮な英国の王へンリーが対仏戦争に勝利を収め国威高揚をもたらす「英雄叙事詩」である。芝居はアジンコートの戦いを頂点とする両国の駆け引きと戦況を骨子としながらいくつかの喜劇的場面をはさんだ直線的な構造となっており、華やかなトランぺットとドラムの奏でるスピード感溢れる戦場スぺクタクルとして初演以来英国人の間で特に人気を博してきた。最後にへンリーがフランス王女キャサリンに求愛して結ばれる筋立ても、中世ロマンス物語の香りを残し、この芝居の人気の一因となっている。だが、一方でへンリー五世自身は歴史劇の中でも特に評価の分かれる主人公である。英国を勝利に導く英雄的な王であるのか、それとも身内の陰謀者たちを斬りフランス兵捕虜の処刑を命じる冷酷な君主なのか、その人物評については今もって議論が絶えない。
筑摩書房、シェイクスピア、松岡和子訳『ヘンリー五世』P248-249
この作品はイギリスで特に人気で、その理由がライバルフランスとの戦いの勝利による「国威高揚」というのが興味深いですよね。

たしかにこの作品は英仏戦争の空気感がよく出ています。しかも最初はあたふたしていたフランスが後に自信満々になってイギリスを迎え撃とうとするもまさかの惨敗という見事な噛ませ犬っぷりです。ヘンリー五世率いるイギリスの兵力は圧倒的に不利なものがありました。しかし「神の助け」か、奇跡的な大勝利を収めることになります。
劇中では派手なファンファーレや太鼓の音もあり、これは「国威高揚」的な気分になることは間違いありません。イギリス人からするとスカッとすることこの上ない劇と言えるかもしれません。
そして私がこの作品を読んで気になったのはヘンリー五世の王としての苦悩です。『ヘンリー四世』の気ままな「ハル王子時代」と違い、彼は王としての責任に苦悩することになります。
王の責任か!「俺たちの命も、魂も、
筑摩書房、シェイクスピア、松岡和子訳『ヘンリー五世』P148
借財も、俺たちの身を案じる妻も、
子供も、罪も、王の責任にしてしまえ!」か。
王たる者はすべてを背負わねばならない。ああ、厳しい立場、
偉大な地位と同時に生まれた双子の兄弟だ。己の痛みしか
感じられない馬鹿どもの不平不満にいちいち
付き合うのか!王は、庶民が心ゆくまで味わっている無限の心の安らぎを、どれほど捨てねばならないのか!
この辺りのハル王子の成長、いや成熟もこの作品の魅力のひとつだと思います。
また同じくヘンリー五世のセリフで気になるものがありました。以下、フランスのハーフラーという街に降伏を迫るヘンリー五世の言葉です。
ハーフラーの市長はどのような決断をくだしたのか?
筑摩書房、シェイクスピア、松岡和子訳『ヘンリー五世』P96-98
これは余が許す最後の談判だ。
したがって、余の最善の慈悲に身を委ねるか、
あるいは破滅を栄光とみなす者らしく
堂々と戦いを挑み、余に最悪の
行動を取らせるか。なぜなら私は軍人であり、軍人という名こそ
私に最も似つかわしいと思っている、だから
いま一度砲撃を開始すれば、私には
征服半ばのハーフラーから立ち去るつもりは毛頭ない、
街が灰燼に帰するまで徹底的に破壊する。
慈悲の門はすべて閉ざす、するとどうなるか、
肉に飢えた兵士たちは、無慈悲な硬い心をかかえ、
血まみれの手に存分に血を吸わせようとうろつき回り、
良心は広大な地獄なみにゆるみ、お前らの美しく瑞々しい乙女や
花のような赤子たちを、草でも刈るように一刀両断にするだろう。
だが、私に何の関わりがある、たとえ非道な戦争が
悪魔の王者ルシファーのように炎で身を包み、
顔面を泥まみれにして、荒廃と破壊につながる
残虐な所業にふけるとしても?
私に何の関わりがある、お前ら自身のせいで、
この街の純粋無垢な乙女たちが、めらめらと燃える
欲望の手に落ちて強姦されたとしても?
放埒な悪行という馬が全速力で丘を
駆け下りてくるとき、制御できる手綱があるか?
狂ったように略奪に走る兵士たちに命令をくだし、
それを止めようとしても虚しく甲斐はない、
沖の鯨に召喚状を出し、岸まで泳いで来いと
言うようなものだ。だから、ハーフラーの市民よ、
お前たちの街とそこに住む人々に憐れみをかけろ、
いまならまだ私の兵士たちは私の命令に従う、
いまならまだ冷静で穏やかな慈愛の風が
重苦しい殺人、略奪、暴行という
感染力のある不潔な雲を吹き払える。
憐れみを掛けぬなら、よいか、一瞬後にお前たちが
目にするのは、血に飢えた兵士らがよごれた手で、
悲鳴を上げる娘たちの前髪をつかみ闇雲に陵辱する様、
彼らがお前たちの父親たちの銀色の髭をひっ掴んで、
その尊い頭を壁に叩きつける様、
裸の赤子を槍で串刺しにする様だ、
半狂乱の母親たちの吠えるような叫びは
雲を切り裂くだろう、かつてへロデ王配下の残忍な
殺し屋どもに向かってユダヤの女たちが泣き叫んだように。
さあ、返事を聞こうか。降伏してこれを避けるか?
それとも防戦という罪を犯し、破滅を招くか?
これはシンプルに読めば単なる脅しにしか見えないかもしれません。
ですが、
「いまならまだ私の兵士たちは私の命令に従う、
いまならまだ冷静で穏やかな慈愛の風が
重苦しい殺人、略奪、暴行という
感染力のある不潔な雲を吹き払える。」
という言葉を読んだ時、私は「あっ」と思いました。
と言いますのも、「いまならまだ私の兵士たちは私の命令に従う」という言葉が脅しでも何でもなく、本当のことのように思えたからです。私は最近、菊池良生著『傭兵の二千年史』という本を読みました。

こちらは以前当ブログでも紹介しましたが、そこにまさしく百年戦争時代の兵士についての記述があったのです。
私たちは戦争を戦う兵士というと「国家直属の訓練された正規兵」を思い浮かべてしまいます。しかし、そのような国直属の正規軍というのはごく最近生まれたシステムに過ぎません。中世の戦争は傭兵によって戦いが行われていました。
ではその傭兵とはどのようなものだったのか。それがなんと飢えた農民、土地を持たぬ者、はてはならず者まで有象無象の集団だったのです。生き延びるために戦いに身を投じざるをえなかった者たち。それが戦場の大半を占める兵士の実態だったのです。
そもそも「騎士道」なるものが生まれたのも、武人、兵士達の狼藉があまりにひどかったからです。だからこそキリスト教倫理の下「騎士道」なるものを生み出し、その攻撃的なエネルギーの制御を図ったのです。
生きるため、食うために仕方なく戦場にやって来た男たち。そもそもがならず者たちである恐るべき集団です。そんな彼らが飢え、獣のような状態で野放しにされたらどうなるか・・・
その最も有名な大惨事が1527年のローマ劫掠(サッコ・ディ・ローマ)と呼ばれる大事件でした。

キリスト教の聖地ローマが兵士たちに徹底的に略奪、破壊されたこの事件。同じキリスト教徒があろうことかバチカンを徹底的に破壊したというのは信じられないものがありました。そういうことが起こりうるのがこうした傭兵システムなのです。飢えた兵士たちはもはや誰にも止められないのです。
ヘンリー五世の「いまならまだ私の兵士たちは私の命令に従う」という言葉はまさしくリアルこの上ありません。これ以上兵士たちを飢えさせ、怒らせたらもう制御はできない。さらっと述べられた箇所ですが、当地に生きる人たちからすればこんな恐ろしい言葉はなかったことでしょう。
シェイクスピアが生きた時代も当然傭兵による戦争が主流です。その恐ろしさはきっと身に染みて感じていたのではないでしょうか。
『ヘンリー四世』はハル王子とフォルスタッフの丁々発止のやり取りがあったので戦争の重苦しさをあまり感じなかったのですが、この作品ではその悲惨さが顔をのぞかせている感があります。『ヘンリー四世』から直結するこの物語ですが前作とはまた違った空気感の作品であるなと強く感じました。
以上、「シェイクスピア『ヘンリー五世』あらすじと感想~ハル王子改めヘンリー五世がフランス征服に挑む!英仏百年戦争を描いた歴史劇」でした。
Amazon商品ページはこちら↓
次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事


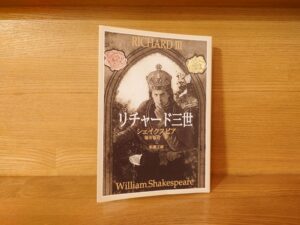












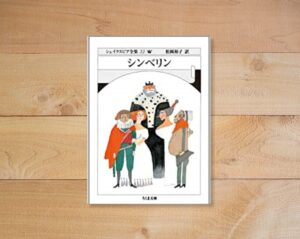
コメント
コメント一覧 (2件)
今、メアリー・スチュアートと、エリザベス・チューダーのカトリック対プロテスタントの、戦いの
物語を読んでいます。
宗教を利用する経済の側面が描かれていますが、人間の欲の深さに怯えます。
コメントありがとうございます。
凄まじい戦いですよね。
歴史において宗教がどのように利用されたかというのは非常に興味深いですよね。人間の欲の問題は本当に根源的だと私も思います。