『隣人が殺人者に変わる時 ルワンダ・ジェノサイドの証言 加害者編』あらすじと感想~加害者は虐殺後何を語るのか
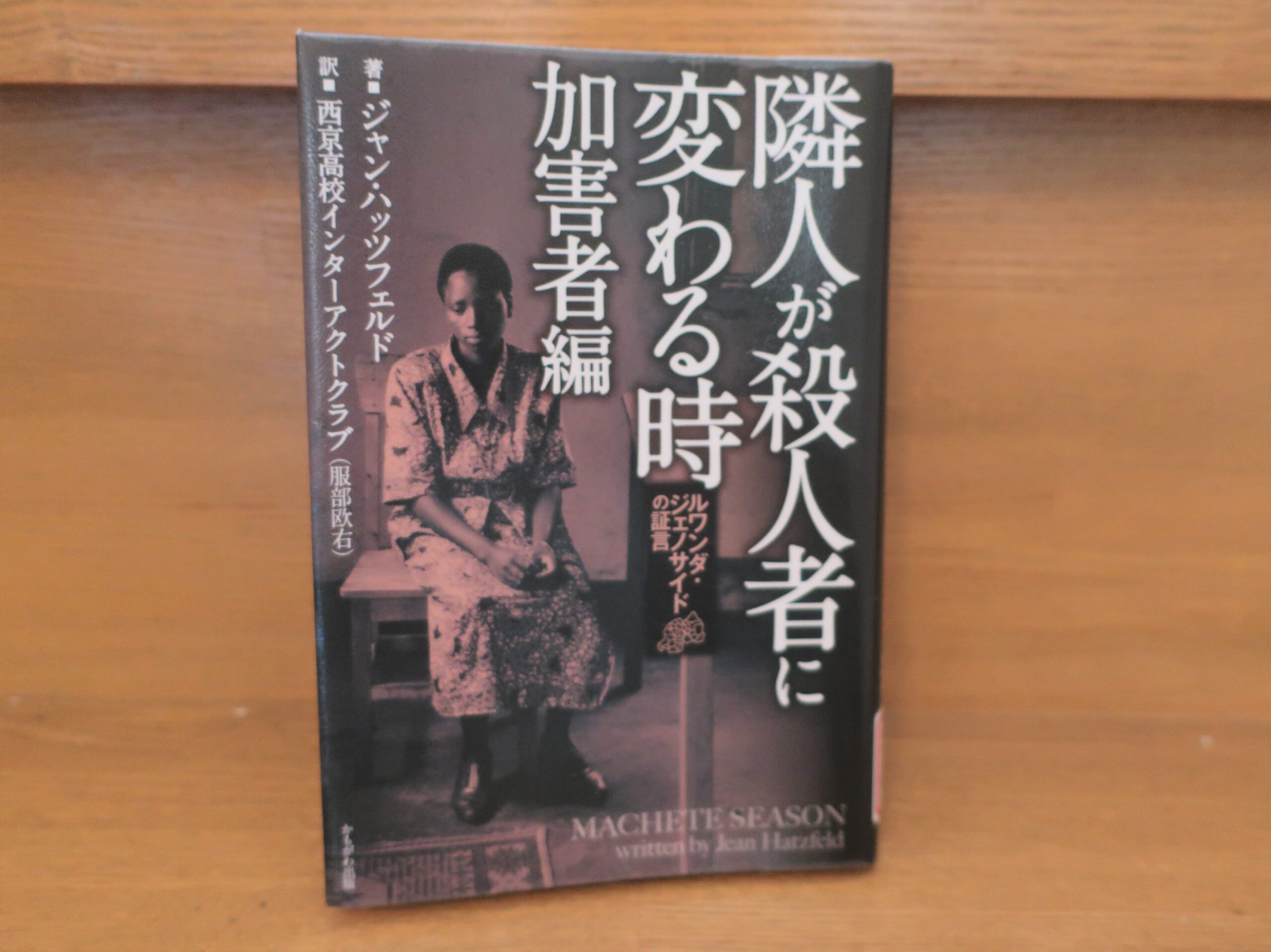
加害者は虐殺後何を語るのか『隣人が殺人者に変わる時 ルワンダ・ジェノサイドの証言 加害者編』概要とは感想
今回ご紹介するのは2014年にかもがわ出版より発行されたジャン・ハッツフェルド著、服部欧右訳『隣人が殺人者に変わる時 加害者編』です。
この本は前回紹介した『隣人が殺人者に変わる時』三部作の第二作目に当たる作品です。
では早速この本について見ていきましょう。
三カ月で八十万人もの犠牲者(当時の人口の一割)を出したルワンダのジェノサイド。その実態を、本書の著者であるフランス人ジャーナリスト・ハッツフェルドは、普通の人々(一般民衆)の証言を綴ることによって、世界に投げかけた。ルワンダの一地方都市ニャマタで虐殺の対象となったツチと、その加害者のフツの双方にインタビューを行い、それを三冊の書に著わしたのである。一冊目(邦題・『隣人が殺人者に変わる時』)は生存者の証言が、二冊目(本書)は殺人者の告白が、そして三冊目(来年邦訳版刊行予定)はジェノサイド後、再び同じ地で暮らすことになった双方の証言で構成されている。
ルワンダ・ジェノサイドの大きな特徴は、その加害者の多くが兵士やプロの殺し屋ではなく、それまで被害者たちと仲良く暮らしていた普通の人々であったことである。ハッツフェルドは、殺し屋と化したフツのあるグループ十人に、ジェノサイド後、刑務所でインタビューを重ねた。それをまとめたものが本書である。前著、「隣人が殺人者に変わる時」では、個々の生存者の証言ごとに各章が設けられていたが、この加害者編では、各章は殺人者たちの告白をもとにまとめられ、そのテーマごとにできあがっている。
これまで被害者に比べ加害者の告白を記した書は少なく、滅多に書店で見かけることはなかった。それは多くの人々の関心を引くテーマではあるものの、加害者にとって告白そのものが裁判上での不利や出所後の生きづらさをもたらすためである。そこでハッツフェルドは、インタビューを加害者の刑の確定後、出所するまでの間に行うことで、この問題点を解決した。それにより加害者たちのあからさまで嘘の少ない発言を得ることが可能になり、本書が生み出されたのである。
かもがわ出版、ジャン・ハッツフェルド著、服部欧右訳『隣人が殺人者に変わる時 加害者編』P324-325
前回紹介した『隣人が殺人者に変わる時―ルワンダ・ジェノサイド生存者たちの証言』ではルワンダの虐殺の生存者のインタビューが収められていましたが、この作品ではそれとは逆に加害者の声を聞くことになります。
正直、読んでいて暗い気持ちになり、胸がむかむかしてきます・・・被害者は全てを失い、生き残った者も絶望的な苦しみを味わい続けています。しかし、それに対し加害者側はどうなのか。この本ではそれを知ることになります。
このことについて訳者解説では次のように語られています。
翻訳を続けていくにつれ、遠く離れたアフリカの赤裸々な告白を綴ったこの著作が、平和な国に生きる我々の心の内奥を探る書でもあることが、徐々に実感されてきた。加害者たちの心の変化が、同じような状況になれば世界中の誰にでも起こりうるように思えてきたのだ。
被害者たちが体と心に大きな傷を負い、ジェノサイド後もなかなか立ち上がれず沈黙を続けなければならなかったのに対し、加害者たちは前向きに自分の将来を考えて早く反省し、早く被害者の赦しを得て、早く元の生活に戻ろうとした。そして彼らは殺人を続けた理由を問われると、「ラジオ放送(マスコミ)に踊らされたから」とか「命令されたから」とか「仲間はずれになるのが恐かったから」とか「略奪で生活が楽になったから」というようなことを述べている。生き地獄を体験し、身内も財産も社会に対する信頼も奪われた生存者の証言と比べて、殺人者の告白はあまりにも軽い。それは自らの心の破壊を食い止めるために、そしてあくまでも普通の人でありたいがために、自分たちの犯した行為を軽く考えるようなったからではないだろうかと著者は述べている。
さらに殺人者たちは、フツとツチの二者間の過去の歴史や時代の流れで、また権力を振りかざす政治家や元宗主国の思惑で、どうすることもできずに「仕向けられた」と言い、「やらされたのだから仕方がない。だから早く反省してやり直したい」と言う。とても利己的で、生存者のことがニの次になってしまっているのは明らかだ。しかしこれは我々普通の人間のほとんどが、戦争などの組織的戦いで殺人を犯した後に、まず考えることではないだろうか。自分を納得させ、周りには赦しを願い出なければならないのだから。
かもがわ出版、ジャン・ハッツフェルド著、服部欧右訳『隣人が殺人者に変わる時 加害者編』P325
「生き地獄を体験し、身内も財産も社会に対する信頼も奪われた生存者の証言と比べて、殺人者の告白はあまりにも軽い」という訳者の言葉は私にとっても非常に印象深いものでした。
そしてこの本を通して私が感じたのは「赦し」とは何なのかということでした。
いくら加害者が謝罪したところで、亡くなった方はもう帰ってきません。生き残った方の心の傷や生活も元通りになるわけがありません。
ですが、加害者は「自分のこれからの生活のため」に被害者に赦しを求めます。
しかも、上の解説にありますように、真に心から悔やんでいるとは到底思えない態度で「赦してくれ」と被害者に求めるのです。そして彼らはほとんど裁かれることなく釈放され、今まで通りに生活を始めるのです。
これは読んでいて精神的にかなり苦しかったです。。
ですが、彼らを単なる極悪人だと片付けるわけにもいきません。
次の記事で紹介する『隣人が殺人者に変わる時 和解への道―ルワンダ・ジェノサイドの証言』でより詳しく語られていくのですが、虐殺に関わった大量の人間をどうするのかという問題は非常に大きな問題です。
これはナチスによるホロコーストも同じです。あまりに多くの人が「仕事」として殺戮に関わってしまいました。誰もが「権力の歯車」として動いたのです。
そうなってしまったら誰がその責任を取るのでしょうか。トップや上層部だけでしょうか。実際に手を下した人はどうなるのでしょうか。それを後方支援していた人はどうなるのでしょうか。虐殺を知っていながら傍観していた人はどうなるのでしょうか。
しかもここルワンダではさらに恐ろしいことに、ツチ族男性の多くが実際にマチェーテ(なた)を握り、殺害に関与し、女性も略奪に加わっています。こうなってしまえば、有罪ではない人間はほとんどいなくなってしまいます。
こうした法的な問題もこの本から考えさせられることになります。
ですがやはり一番強烈なのは、これほどの悪を犯した者自身が『自分たちには「赦し」が与えられなければならない』『新しい生活をしたい』と無邪気に言えてしまうその恐ろしさでした。
この「赦し」の問題については以前紹介した『ルワンダ大虐殺 世界で一番悲しい光景を見た青年の手記』でも出てきました。
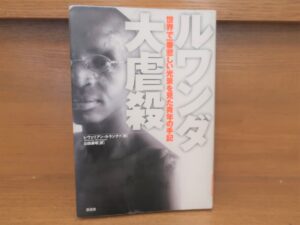
家族を目の前で惨殺され、自身もなぜ生きているかわからぬような傷を負いながらも生き延びたルラングァ氏は「彼らを赦すことはできない」と述べていました。なぜあんな悪行を犯した人間がのうのうと街で生きているのかと怒りをにじませていました。
「赦し」とはそもそも何なのでしょうか。
そもそも誰が誰に対してするものなのでしょうか。被害者?法?国家?神?
加害者が赦されるというのはどういうことなのか。逆に永遠に罰せられ苦しめられることこそ償いなのでしょうか。
この本を読んでいると頭が混乱しぐるぐるしてきます。
この『隣人が殺人者に変わる時』の三部作はあまりに強烈な作品です。
前回の作品に引き続きぜひ手に取って頂きたい作品となっています。
以上、「『隣人が殺人者に変わる時 ルワンダ・ジェノサイドの証言 加害者編』加害者は虐殺後何を語るのか」でした。
Amazon商品ページはこちら↓
次の記事はこちら

前の記事はこちら

ボスニア紛争、スレブレニツァの虐殺を学ぶためにおすすめの参考書一覧紹介記事
関連記事











コメント