ヴォルテール『カンディード』あらすじと感想~最善説への反論、ドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』とのつながりも

ヴォルテール『カンディード』あらすじ解説~最善説への反論、ドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』とのつながりも

今回ご紹介するのは1759年にフランスの啓蒙思想家ヴォルテールによって発表された『カンディード』です。
私が読んだのは晶文社より2016年に発行された堀茂樹訳の『カンディード』です。
早速この本について見ていきましょう。
昔むかし、心優しく純朴な青年カンディードは、美しき男爵令嬢に恋をしたため故郷を追放され、世界各地を転々とする。最善説を唱える恩師パングロスの教えとは裏腹に、行く先々で数々の不幸や災難に見舞われながら、試練と冒険の旅を続ける。果たして天真爛漫な青年は、行方知れずとなった恋人と再会できるのか?世界中で名高い古典『カンディード』が掘茂樹の痛快な訳文で現代に甦る!
晶文社、ヴォルテール、堀茂樹訳『カンディード』より
この作品は主人公のカンディードが世界を旅し、様々な災難や出来事を通して、この世界の善悪とは何か、私たちは何を信じ生きていくのかを探究していくという物語です。
巻末でこの作品についてより詳しい解説がありましたのでそちらも見ていきましょう。少し長くなりますが非常にわかりやすかったので引用します。
『カンディード』の背景
『カンディード』は純然たるフィクションですけれども、後述するように当時の世相をふんだんに取り込み、批判や諷刺の対象としています。のみならず、作品自体が、一七五〇年代にヴォルテールが地上の悲惨に直面して受けた衝撃から生成したといっても過言ではありません。それはどんな悲惨であったか。主要なものに限って、二つだけ挙げておきます。
一つは、ヨーロッパを戦火にまみれさせた七年戦争です。一七五六年五月から、フリードリヒ大王率いるプロイセンがイギリスを同盟国として、フランスと組むオーストリア、ロシア、スウェーデンなどと激突し、これが六三年まで続いたのです。『カンディード』の物語の中で「ブルガリア」と呼ばれているのは、ずばりプロイセンです。「アバリア」は、近年の研究によれば、ヴォルテールの頭の中でフランスでもロシアでもなく、オーストリアを指していたものと思われます。いずれにせよ、当時の軍隊組織の暴力性をコミカルなまでに抉った第2章、遠目には「鉛の兵隊」の行進のようにも見える戦場の実態を序破急のテンポでクローズアップする第3章などは、戦争という人災の「滑稽な」酷薄さを鮮やかに諷刺しています。
もう一つは、一七五五年十一月一日に発生し、約六万人を犠牲にしたと伝えられているリスボン大震災です。当時のヨーロッパ人にとって、巨大地震と津波はまさに驚天動地の天災だったようです。翌五六年にヴォルテールが発表した『リスボン大地震に寄せる詩、あるいは「すべては善である」という公理の検討』はすこぶる悲壮かつ真率なトーンで、災害のもたらしたショックを語ると同時に、地上の世界を「すべての可能世界の中で最善のものである」とする予定調和の世界観―後述する「最善説」のヴィジョン―に対する深刻な疑問を提示していました。数年後の著作『カンディード』でも、とりわけ地震発生時の驚愕と混乱を描く第5章、「異端者火炙りの壮麗なる儀式」(傍点筆者)を語る第6章あたりで、同じテーマが大きく取り上げられることになりました。但し、本書に明らかなとおり、散文である『カンディード』は、詩に表れていた悲壮感ではなく、醒めたアイロニーを前面に出しています。
それにしても、現実界の合理性をドグマティックに信じるタイプの人類が、その形而上学的前提を揺るがす災厄に見舞われて底知れぬ不安に捕らわれたとき、ややもすれば合理主義の倒錯に嵌まり、現実に対して極端に非合理な振る舞いに走りかねないという点についても、一見荒唐無稽な『カンディード』の物語は示唆的です。まさに今日の世界に通じる面があるのではないでしょうか。
晶文社、ヴォルテール、堀茂樹訳『カンディード』P240-242
この作品は実際にヴォルテールが生き、感じた時代を前提に書かれています。
特に1755年のリスボン大地震の影響は甚大でした。
というのも、当時キリスト教世界では「最善説」という考え方が流行していたのですが、それに対して決定的な疑問を感じさせたのがこの大災害だったのです。
最善説についての解説を見ていきましょう。
最善説とは
『カンディード、あるいは最善説』というときの「最善説」は、元のフランス語では「オプティミスム」(Optimisme)です。この名詞は、「最良」「最善」という意味のラテン語Optimusと、ドクトリンを指す名詞を作る働きのある接尾辞ismから成っています。実は、本篇の第一章にも言及されている論壇誌『トレヴー評論』に集うイエズス会士たちが一七三七年に使い始めた造語なのです。ですから、ヴォルテールの生きていた時代における「オプティミスム」の第一義は、今日われわれが了解している「楽天主義」ではありませんでした。そうではなく、神が創造したはずの世界になぜ天災のような物理的な悪、病苦のような身体的な悪、人間を暴力や罪に導く倫理的な悪が存在するのかという問題を解決する―あるいはむしろ解消する―ひとつのドクトリンの謂だったのです。
実際、十八世紀には、宗教的にはカトリックやプロテスタントであった合理主義の哲学者たちが、世界を神の摂理の下にあるものと見る立場からまるごと合理的に説明しようとしていました。なかでも代表的なのが、一七一〇年に『弁神論』(もしくは『真義論』)をフランス語で発表したドイツの哲学者ライプニッツ(一六四六~一七一六年)が主張し、その弟子クリスティアン・ヴォルフ(一六七九~一七五四年)やイギリスの詩人アレキサンダー・ポープ(一六八八~一七四四年)が継承した理論で、それがすなわち「最善説」でした。
この「最善説」によれば、神は完全無欠ですが、神の創造は神のようには完全無欠であり得ず、それゆえ地上世界には悪も散在しています。しかしながら、そんな悪を圧倒的に凌駕する善が優勢であるとされ、そもそもある現象には必ず原因があるという充足理由律が世界を支配している以上、世界は人智の判断を超えて合理的なのであり、全体として予定調和していると断じられます。問題とされる悪も、実は善の成就のために必要な役割を果たしており、いわば「善によってでまる影」(l’ombre portee du bien)のようなものだということになります。このドクトリンの中では、人間の目の高さから見て明白に悪であるものも、もはやスキャンダルではなくなってしまうわけです。
晶文社、ヴォルテール、堀茂樹訳『カンディード』P242-243
この理論から言うと、リスボン大地震も人間が救われるために必要なものと考えられます。たしかに多くの人が亡くなり、生活が破壊されたが、それは最後に人間が救われるために必要な善だったのだと「最善説」は述べるのです。
ですがヴォルテールは言います。地震で亡くなった人は何かそれに価するような大きな罪を犯したというのだろうか。それに、たとえ最後の最後で人類が救われるとして、なぜ彼らが地震で死ななければならなかったのか。なぜ彼らはそんな目に遭わなければならないのか。全知全能の神ならばそんなことをしなくてもよかったのではないか。何が起ころうが「それは最終的な結果のためには善である」で片づけてしまってもいいのだろうかと。
たしかに、全知全能の絶対的なる神がこの世界を作ったとして、なぜ悪が存在しているのかというのはとてつもなく大きな問題です。
ここは多神教的な日本人のメンタリティーではなかなかぴんと来にくい問題ではありますが、キリスト教信仰においては非常に重要な問題です。
ヴォルテールはこうした最善説に対して反論すべく『カンディード』を書いたのでした。
ドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』とのつながり
ドストエフスキー(1821-1881)はロシアの文豪ですので、当然ヴォルテールをはじめとした西洋思想にも通じていました。
その中でもヴォルテールの『カンディード』はドストエフスキーに特に大きな影響を与えたと考えられています。
モチューリスキーの『評伝ドストエフスキー』には次のように書かれています。
ドストエフスキーの控え帳には、一八七七年十二月二十四日の日づけの次のような記事がある。
「覚え書き―わが生涯の。
筑摩書房、モチューリスキー、松下裕、松下恭子訳『評伝ドストエフスキー』P597
一 ロシアの『カンディード』を書くこと
二 イエス・キリストについての本を書くこと
三 回想録を書くこと
四 死後四十日目の追悼の叙事詩を書くこと
(これらは、最新の長篇小説と予定している『作家の日記』の発行を除いても、少なくとも十年はかかる仕事だが、わたしはいま五十六歳だ)」
1877年といえばドストエフスキーが『カラマーゾフの兄弟』を書き始める直前の時期です。その時期にドストエフスキーは「ロシアの『カンディード』を書くこと」をここで述べていたのでした。
実際、『カンディード』で書かれた「最善説との戦い」は信仰における最重要な問題です。なぜこの世界に悪はあるのか。なぜ悪があるのに神を信じなければならないのか。神がないならば善と悪にどんな意味があるというのだろうか。そもそも、私たちは何を信じて生きていけばいいのだろうか。
ヴォルテールの描く主人公カンディードは、世界を放浪し、そこで様々な出来事や災難とぶつかります。地震や戦争、そして『カラマーゾフの兄弟』でも出てくる異端審問官にも出くわします。
カンディードは自分の目でそれらを見、そして世界の善悪の意味、神の信仰について考察していきます。
カンディードは完成された人間ではありません。まさしく不完全で、それにもかかわらず世界を放浪し究極的なものを探究することになる人物です。ですが、不完全であるからこそ彼はより素直な目で世界を見ていくことができるのです。
これは『カラマーゾフの兄弟』の主人公アリョーシャとも重なってきます。アリョーシャも様々な出来事を通して神とは何か、善悪とは何かを感じとっていくことになります。
そして有名な「大審問官の章」の前でイワンがアリョーシャに語る幼児殺しの話や、世の悲惨さも『カンディード』を連想させます。『カンディード』もなぜ全知全能の神がいるのに世界はこんなにも悲惨なことで満ち溢れているのかと問います。

イワンはまさしく、この世界の悪の存在から神への疑問を提出します。それに対しアリョーシャは何を思い、そこからどう動いていくのか、物語はどのような結末を迎えるのか、これは『カラマーゾフの兄弟』を読む上で非常に重要なポイントとなってきます。
ドストエフスキーが「ロシアの『カンディード』」を書きたいと書き残したことの意味は非常に大きいものであるように思います。
『カンディード』で語られる問題を19世紀末のロシアにおいて改めて問い直そうとした。それがドストエフスキーの立場だったのではないかと思います。
『カンディード』は18世紀中頃の作品ではありますが、全く古さを感じない作品です。物語もドラマチックでストーリーにぐいぐい引き込まれます。とても面白い作品でした。
そして『カラマーゾフの兄弟』とのつながりを感じながら読むとこれまた味わいが増してきます。ドストエフスキーファンの方にもぜひおすすめしたい1冊です。
以上、「ヴォルテール『カンディード』あらすじ解説~最善説への反論、ドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』とのつながりも」でした。
Amazon商品ページはこちら↓
次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事

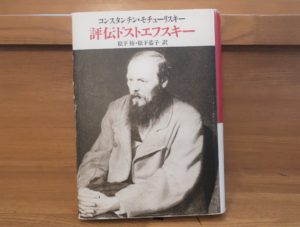













コメント