チェーホフ『曠野(草原)』あらすじと感想~ロシアの大いなる自然を美しく描写した名作!

チェーホフ『曠野(草原)』あらすじと感想~作家チェーホフの覚醒

チェーホフ(1860-1904)Wikipediaより
『曠野』(※訳によっては『草原』という題もあり)は1888年にチェーホフによって発表された中編小説です。
私が読んだのは中央公論社、神西清、原卓也訳『チェーホフ全集 7』所収の『曠野』です。
早速あらすじを見ていきましょう。今回もチェーホフ研究家佐藤清郎氏の言葉を参考にします。
この作品には「ある旅の話」という副題がついている。草原の旅の風物詩である。父親はすでになく、母の手一つで育てられた一人の少年が、伯父にともなわれ、故郷を捨てて勉学のために町に出る途中での、ばらばらな見聞をつづりあわせた作品である。そのほかに、とりたてて小説的筋立てはない。(中略)
ばらばらな風物の印象を、少年の純粋な眼が美しい赤い糸となって、数珠玉をつなぐようにつないでいる。そして、チェーホフの全作品のなかでも、もっとも美しい「散文詩」となっている。
筑摩書房、佐藤清郎『チェーホフ芸術の世界』P42
この作品は故郷を捨てて勉学のために街に出る途中に少年が出会った大いなるロシアの風景(曠野)を描いた作品です。
この作品が生まれた背景が『チェーホフ全集』の巻末にわかりやすくまとめられていましたのでそちらを紹介します。
一八八七年四月、チェーホフはただ一人、故郷タガンローグを訪れ、ここを足がかりに、ドネツ地方一帯を旅行し、ドネツ河沿岸の聖地スゲャトゥイエ・ゴールイ、曠野の町々、コサックの村や部落をたずねてまわった。「わたしはたっぷりと詩想をたくわえた。五年間はこれで足りる」とチェーホフに語らせたこの旅行は、本巻に収録した『コゴメナデシコ』『曠野』などの作品を直接の産物として生みだしたほか、ソビエトの評論家ボゴスロフスキーが指摘するように、本格的な仕事にとりかかろうとする前の精神転換にも役立ったと見てよいだろう。
一八八八年の一月、かつてチェーホフに「才能を濫費せぬよう」忠告した長老作家グリゴローウィチが、滞在中のニースから手紙をよこし、「こまかな短篇を、特に新聞などに手取り早く書くのをやめるよう」、ふたたび説いた時、チェーホフはちょうど『曠野』を執筆中で、次のような返事を送った。
「……お手紙を読み終えたあと、わたしは特に恥ずかしくはなりませんでした。なぜなら、厚い雑誌のための仕事をしているさなかに、お手紙がついたからです。これが、あなたのお手紙の本質的な部分に対する返事です。わたしは大きな仕事に取りかかったのです……」
さらに、ひと月ほどあとで、彼は長兄アレクサンドルにこう書いている。
「……概して、ひどい疲れを感じています。たぶんもう新聞には戻らないでしょう!過去よ、さようならです!スヴォーリンのためには時たま書くでしょうが、そのほかのところは、おそらく縁切りになるでしょう」
そして事実、この巻に収録した短篇『ねむい』を最後の作品として、A・チェホンテという作家は消え去り、「ロシヤに新しい第一級の作家が出現した」とガルシンを感嘆させたチェーホフが、自己のかがやかしい道を着実に歩むことになるのである。その意味で、本巻におさめた各作品は、「大きな飛躍をするための助走」の時期に書かれたものばかりであり、その飛躍の第一歩に相当するのが、『曠野』にほかならない。
中央公論社、神西清、原卓也訳『チェーホフ全集 7』P489-490
この解説にありますように『曠野』はチェーホフが実際に旅した見聞が基になって描かれました。
そして重要なことはこの作品がチェーホフという作家がいよいよロシア第一級の作家として文壇に登場するきっかけとなったという点です。
この頃までのチェーホフは「A チェーホンテ」というペンネームで作品を発表していました。「チェーホンテ」というペンネームが示すようにどこかおどけたようなユーモア作家らしい雰囲気を出していました。
そして彼の作品はお金を稼ぐために雑誌にものすごいペースで投稿した風刺作品やユーモア短編ものが大半を占めていたのです。驚くべきことに年間100本以上の短編を彼は書き上げていたのです。
また、ここがチェーホフのすごいところなのですがその短編ものですら多くの文学者から賞賛を浴びるほどの出来栄えだったのです。
そんな彼がグリゴローヴィッチというドストエフスキーとほぼ同世代の重鎮から「そんな才能の無駄遣いをしないでじっくりと腰を据えて作品を書きなさい」という激励の言葉をもらうことになり、それがこの作品を生み出す原動力になったのです。
それまでのお金を稼ぐために書きなぐるように作ってきた作品とは一線を画した作品、それが『曠野』なのです。
チェーホフが自信を持ってじっくりと書き上げた作品。
だからこそ彼はこの頃から「A チェーホンテ」ではなく、本名の「アントン チェーホフ」の名乗ることになります。
この作品はチェーホフの作家としての目覚めを知る上で非常に重要な作品となっています。
感想
あらすじにもありましたようにこの作品はエゴールシカという一人の少年が故郷から街へと向かう旅の道中を描いた作品です。この作品には何か大きな事件や劇的な筋書きというものはありません。
しかし大いなるロシアの曠野(ステップ)の景色がその景色を初めて見る少年の新鮮な目で描かれることで読者の私たちもその景色に引き込まれていくことになります。
この旅はチェーホフ自身が体験した旅を基にして書かれたものだということは先にも述べました。その体験があったからこそ彼はこの作品にも溢れる詩情(リリシズム)を込めて書くことができたのです。
この作品はあのトルストイも「散文におけるプーシキン」と絶賛しています。それほどこの作品は簡潔かつ美しい詩情に溢れています。
読んでいるとまるでロシアの大平原を描いた絵画を見ているかのような気分になります。それほど風景描写が抜群です。
チェーホフの作家としての第二のデビューを飾るこの作品は非常に興味深いものとなりました。
以上、「チェーホフ『曠野』(『草原』)あらすじ解説―作家チェーホフの覚醒」でした。
Amazon商品ページはこちら↓
次の記事はこちら

前の記事はこちら

チェーホフおすすめ作品一覧はこちら

関連記事





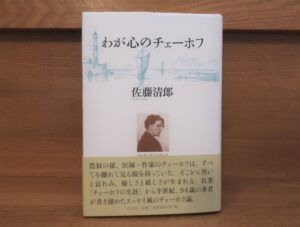







コメント