プーシキン『駅長』あらすじと感想~『カラマーゾフ』のあの名シーンはここから来ていた!?
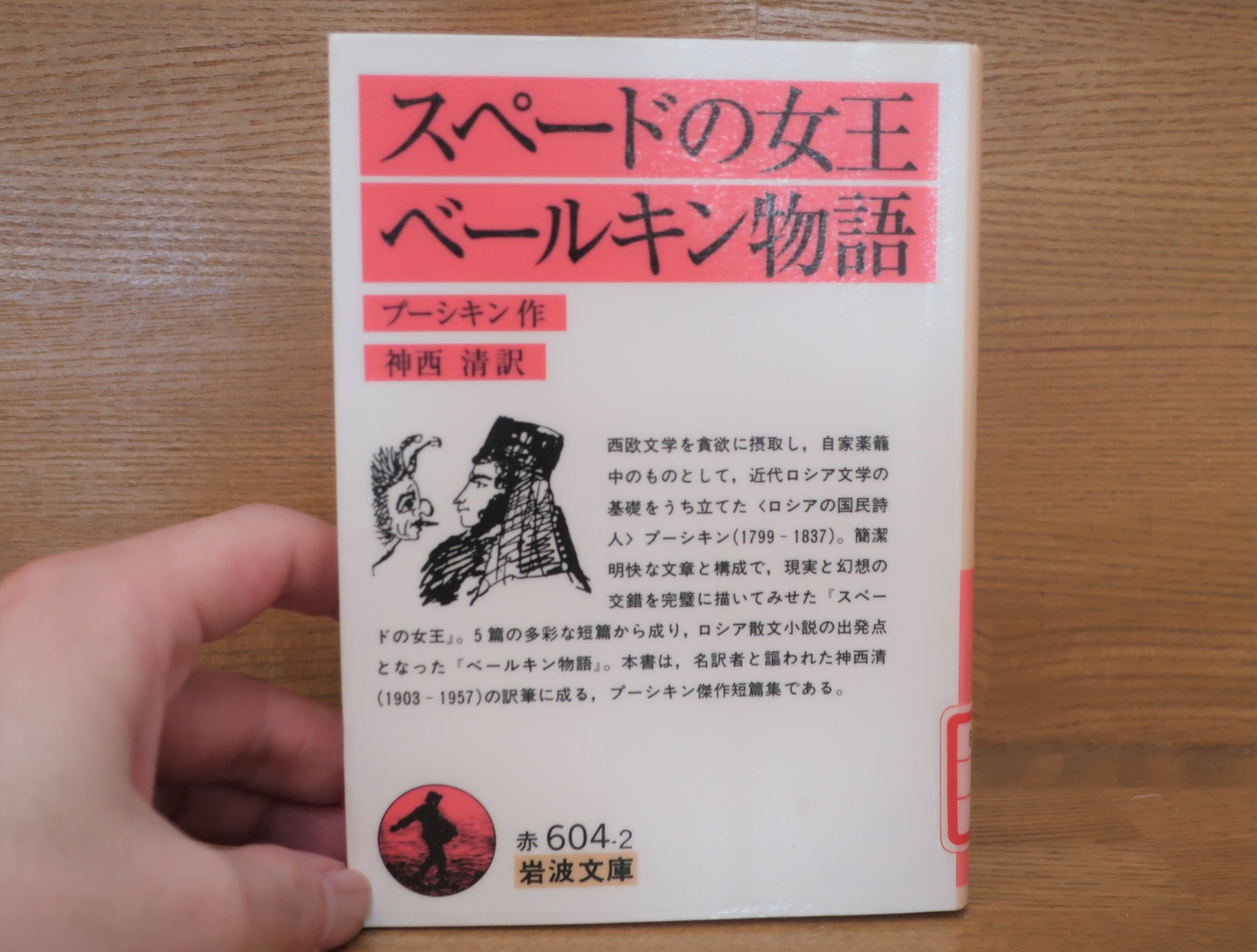
プーシキン『ベールキン物語』所収『駅長』のあらすじと解説

アレクサンドル・プーシキン(1799-1837)Wikipediaより
『ベールキン物語』は1830年にプーシキンによって書かれた短編集で、今回はその中でも特にドストエフスキーとも関係が深い『駅長』を紹介していきます。
私が読んだのは岩波文庫、神西清訳の『スペードの女王・ベールキン物語』所収の『駅長』です。
早速この本について見ていきましょう。
西欧文学を貪欲に摂取し、自家薬籠中のものとして、近代ロシア文学の基礎をうち立てたロシアの国民詩人プーシキン(1799―1837)。「駅長」など5篇の短篇から成り、ロシア散文小説の出発点となった『ベールキン物語』。簡潔明快な描写で、現実と幻想の交錯を完璧に構築してみせた『スペードの女王』。本書は名訳者と謳われた神西清の訳筆に成る、プーシキン傑作短篇集である。
Amazon商品紹介ページより
『駅長』はプーシキン短編の中でも代表作として知られる作品です。この作品が収められている『ベールキン物語』については川端香男里氏の『ロシア文学史』でわかりやすくまとめられていましたのでそちらを引用します。
この年(1830年※上田注)の秋に『ぺールキン物語』を構成する五つの短篇も書かれるが、いずれもロシア短篇小説の曙を告げる傑作である。べールキンなる人物が、「さまざまな人物から聞きおよんだ」実話に基づいて創作した物語集ということになっていて、この仮構のもとにプーシキンはさまざまな文体的実験を試みている。カラムジーンを思い起こさせる「百姓令嬢」、ロマンティックなテーマの「吹雪」、「駅長」、ロマン主義的な恐怖小説のパロディである「葬儀屋」、バイロン風の主人公の不思議な決闘の話を書いた「その一発」、いずれも語り口は多種多様ながら抑制のきいた、形容語や比喩を極力排した明晰な散文の世界をくり広げている。
川端香男里氏の『ロシア文学史』岩波文庫P133
さて、今回紹介する『駅長』は次のような独特な語りから物語がスタートします。
駅長に呪いの言葉を浴びせたことのない人があるだろうか?駅長と口争いをしたことのない人があるだろうか?腹立ちまぎれに、やれ横暴だとか、無礼だとか職務怠慢だとか、そういった類いの役にも立たぬ訴えを書き込むために、あの宿命的な帳簿を出せと彼等に迫らなかった人があるだろうか。彼等を往昔の白洲役人にも比すべき、又は少なくともムーロムの山賊に譬うべき、極悪非道の徒と思わずにいる人があるだろうか?だが公平に考えてみよう。そして彼等の身になって考えるように努めてみよう。そうすれば恐らく、彼等をずっと寛大な眼で見るようになるに相違ないのである。
岩波文庫、神西清訳の『スペードの女王・ベールキン物語』P144
これは現代日本に生きる私たちにとっては何の変哲もない文章のように思えます。
しかし1830年代のロシアにおいてはこの文章は文学史上の大事件として受け止められました。
巻末の解説では次のように書かれています。
『駅長』は一種いい解きがたい謎を含んだ作品である。定説にしたがえば、これは単純に一篇の駅長哀話であって、虐げられた者への同情の文学として、後につづくゴーゴリの『外套』、ドストイェーフスキイの『貧しき人々』などの源流たるの光栄をになうものと考えられている。
岩波文庫、神西清訳の『スペードの女王・ベールキン物語』P243
それまで、小説の主人公として書かれる人物というのはある程度身分がある者だったり、武勇を誇るような者だったのです。しかし『駅長』ではしがない下級官吏である駅長がその主人公となり、その悲しく、みすぼらしい生活が描かれることになります。
当時としてはそれは画期的なことで、これをきっかけにゴーゴリやドストエフスキーが下級官吏を題材にした作品を作っていくことになったほどなのです。
私たちにはなかなかぴんときませんが、物語の誰を主人公とするかというのは暗黙の了解としてたしかに当時のロシア社会にはあったのです。
そして誰を描き、何を描くのかというのがすでに決められていて、その枠中において作家が自由に想像するというのが当たり前の世界だったのです。
しかし、それを打ち壊したのがプーシキンだったのです。
では、この物語の簡単なあらすじを紹介していきましょう。
ある日駅長の家にミンスキイという名の軽騎兵がやってきて、その軽騎兵と駅長は意気投合することになります。
しかしその軽騎兵は言葉巧みに駅長の娘を誘惑しペテルブルクへと連れ去ってしまいます。
美しくて気立てのいい娘を失った駅長はペテルブルクまで追いかけ、娘を返すように懇願するも軽騎兵に金を渡され突き返されてしまいます。
そしてやっとのことで娘を一目見たものの彼女はすっかりペテルブルクでの贅沢暮らしに染まってしまっているのでありました。
打ちひしがれて帰って来た駅長は酒に溺れ、悲嘆と孤独の中で死んでいくのでありました・・・
これが『駅長』の大まかなあらすじです。
実はこの作品、プーシキンの特徴がものすごくわかりやすく表現されている作品としても有名で、アンリ・トロワイヤの『プーシキン伝』にはそのことが解説されています。
少し長くなりますがプーシキンを知る上で非常に重要ですので引用していきます。
プーシキンは、すでに新しい詩をロシアに与えていた。『べールキンの物語』で、彼は未来の世代の散文作家たちに道を開いた。プーシキンの散文は、彼の詩よりもさらに生き生きとしていて、簡潔である。短く、力強い文章。あえて少なくした語彙。その単純さが、一見、当惑させる文の構成。物語の速いテンポは、動詞の的確な選択から得られている。プーシキンは動詞のことを考えて、形容語を捨てている。だから、彼の叙述自体が躍動感にあふれ、力強いのだ。だから、説明自体が行動についてのものなのだ。物語は言葉という外套の下で動き、ぎくしゃくと進んでゆく。そこにちりばめられた一つの形容詞、一つの隠喩、一つのささいな事柄が、このまとまりの中で、ほとんど目もくらむほど重要になる。(中略)
「丈長の緑色のフロックコートに身を包み、色褪せたリボンで吊った徽章を三個ぶら下げた、元気がよくて頑健な五十がらみの男」(『駅長』)
これらの軽快な物語では、人物たちの性格は、彼らの服装とか顔付きと同じくらい簡潔に描かれている。プーシキンは自分の主人公たちを「説明」しようとしない。彼はそれをする役を事件に任せる。こういうわけで、駅長は自分の不幸の代償に数枚のルーブリ紙幣をミンスキイから受け取った。ただ一度だけ、往来で、彼は怒りの涙を流して紙幣を地面に投げつける。では彼は「厳父役」なのだろうか?いいや、彼はしがない身だ。金の値打ちを知っている。彼は自分のような奴にしては少々お殿様のようでありすぎる振舞いをしたことを後悔する。しかし、作者はそのことを全部わたしたちに説明するなどということはしないように心がけている。作者は単にこう言う。「彼は紙幣をくしゃくしゃに丸め、それを地べたに投げつけ、足で踏みつけて立ち去った……。数歩行ったところで彼は立ち止まり、考えた……それから後戻りしてきた……だが、紙幣はもうそこにはなかった。一人の身なりのよい若い男が、彼の姿を認めると、辻馬車の方へ駆けてゆき、御者に『やってくれ!』と叫びながら、馬車に飛び乗った」
この段落は、プーシキンの心理描写の、まさに完璧な見本と言うべきである。主役の心は、その行動によって明らかにされている。人物は、外見から造型されている。しかし、しかるべく選ばれたいくつかの行動や発言によって、この人物はわたしたちに自分の内面の最大の秘密を明かすのだ。『ベールキンの物語』、とりわけ『駅長』は、その凡庸で無知で哀れな主人公をもって、食うや食わずの小役人たちでいっぱいのゴーゴリの短編小説を、ドストエフスキイの痛ましい小説を、ツルゲーネフの幻滅した恋愛牧歌を、そして、来るべきすべてのロシア文学を、予告している。
アンリ・トロワイヤ『プーシキン伝』篠塚比名子訳 水声社P505-506
私はここでトロワイヤの言う、駅長がお金をくしゃくしゃにして踏みつけるシーンを読んだ時思わず声を上げてしまいました。
これはまさしく『カラマーゾフ』のあのシーンじゃないか!と私は驚愕してしまったのです。
かつて私は『カラマーゾフの兄弟』の「スネギリョフがもらった金を踏みつける有名なシーン」を初めて読んだ時、「なんでドストエフスキーはこんなことを思いつけるのだろう!なんて化け物なんだ!」と学生ながらに感動したものでした。
ですがそのシーンに似たシーンがまさにここにあったのです。若い頃から暗記するまでに読みふけっていたプーシキンからこういう風にドストエフスキーはインスピレーションを受けていたのですね。これは衝撃でした。
話は戻りますが、トロワイヤが言うように『駅長』はプーシキンの特徴を知るには最適の作品の一つです。簡潔な文体、そして行動によって表現する見事な心理描写がこの作品にはふんだんに織り込まれています。
『ベールキン物語』は『駅長』の他にも『その一発』『吹雪』『葬儀屋』『百姓令嬢』の四作品が掲載されていて、それぞれプーシキンの魅力が詰まった作品です。
全て短編ですので分量的にも気楽に読むことができるのもありがたいです。
今回は『駅長』を中心にお話しさせて頂きましたが、『ベールキン物語』はとても面白い作品集でした。
以上、「プーシキン『ベールキン物語』『駅長』のあらすじと解説」でした。
Amazon商品ページはこちら↓
次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事














コメント