(6)まとめ~なぜイワンは戦ったのか。戦争という極限状態における兵士の内面を学ぶ意味

キャサリン・メリデール『イワンの戦争 赤軍兵士の記録1939-45』を読む⑹
今回も引き続き、キャサリン・メリデール著、松島芳彦訳『イワンの戦争 赤軍兵士の記録1939-45』を読んでいきます。

今回の記事で「『イワンの戦争 赤軍兵士の記録1939-45』を読む」シリーズは終了になります。この記事では訳者あとがきを中心に、この本のまとめに入っていきたいと思います。
では早速始めていきましょう。
この本の特徴と魅力ー訳者あとがきより
本書は英国の歴史家キャサリン・メリデールによるIvan’s War; Red Army 1939-45,London, Faber and Faber Limited, 2005の全訳です。独ソ戦が舞台ですが、主役はヒトラーやスターリンでも、著名な将軍でもありません。イワンと総称される無名の赤軍兵士たちです。
ソ連はこの戦争で約二千七百万人の軍人、民間人を失いました。ドイツの約五百二十万人、日本の約三百十万人と比べてもその数は際だっています。
モスクワ近郊まで攻め込んだドイツ軍はソ連の領土で多くの民間人を殺りくしました。ヒトラーにとって共産主義者はユダヤ人と同様に、世界から抹殺するべき対象でした。著者が指摘するように、この戦争は領土や権益の奪い合いではなく、相手の全存在を否定する絶滅戦でした。赤軍兵士は自らの命だけでなく、家族の命や財産も含め全てを奪われようとしていたのです。
このような極限状態に置かれた兵士の日常や心理は、従来は歴史の空白領域でした。旧ソ連の秘密主義と歴史の捏造に加え、退役軍人の口が重く、証言は脚色され、あるいは無意識のうちに虚実が入り混じっていたからです。
著者は約二百回に及ぶ退役軍人や証人からの聴き取りに加え、各地に残る一次資料を精査し、イワンの実像に迫っています。それは退役軍人の「沈黙」の背後に目を凝らす作業でした。
本書の最大の魅力は、兵士の肉声を再現するだけでなく、彼らの五感を通じて戦場の日常に迫り、時空を超えて歴史の現場に読者をいざなう力にあります。
「近代で最も苛烈な体制の犠牲者」だったイワンがなぜ、その体制のために命を賭して戦ったのか。「ロシアを救ったものの正体」は何か。勝利の報酬が幻滅と知った時、兵士は現実とどのように折り合ったのか―。
歩兵の網膜に焼き付いた戦友の死や虐殺現場、鼓膜を震わせる爆音、野営地に響くカチューシャの歌、戦車兵の皮膚を焼いた炎を追体験しながら、著者は謎を問い詰めてゆきます。
生死のはざまに露呈する人間の矛盾と「戦争の真実」とは、きっとそのような手法でしか感知できないし、伝わらないのかもしれません。
白水社、キャサリン・メリデール著、松島芳彦訳『イワンの戦争 赤軍兵士の記録1939-45』P449-450
※一部改行しました
『「近代で最も苛烈な体制の犠牲者」だったイワンがなぜ、その体制のために命を賭して戦ったのか。「ロシアを救ったものの正体」は何か。勝利の報酬が幻滅と知った時、兵士は現実とどのように折り合ったのか―。』
名もなきイワンたちこそ体制の犠牲者であったにも関わらず、体制のために彼らは命を賭して戦った。この謎に迫るのがこの本の特徴であり、最大の魅力であります。
多種多様なイワンとソ連のプロパガンダ
戦争は男たちを否応なしに兵士に変えます。しかし、一九四一年六月にドイツ軍がソ連国境を越えた時、イワンに戦う用意はできていませんでした。スターリンが支配する国家にもその準備はありませんでした。
粛清の嵐は赤軍にも荒れ狂い、有能な現場指揮官が足りませんでした。赤軍兵士の四分の三は農村の出身でした。そこは「神と大地」の世界でしたが、一九二九年に始まった強制集団化は、神を葬り、土地を奪い、自営農民(クラーク)を奴隷化しました。
三二年の飢饉で約七百万人が犠牲となり疲弊に追い打ちをかけます。三九年までに農村の世帯数は二千六百万から千九百万に減り、消えた農民のうち約一千万人が死亡したというのです。集団化は「骨に浸透する水分」のように農村に沈殿し「政府を恨む」油断ならない兵士を生みました。
また、ポーランド領だったウクライナ西部やベラルーシ出身の兵士は、ロシア語が不自由でした。命令さえ伝わりません。中央アジアから来た兵士は、無神論の軍隊にあってアラーに祈りを捧げました。泳げない彼らは、渡河戦で真っ先に溺れ死にました。
このように多種多様なイワンに、命懸けで守るべき共通の祖国像は定着していませんでした。スターリン体制は、イデオロギーとプロパガンダ、恐怖の力をもって「ソ連人」として彼らを束ねようとします。
その先兵が「政治指導員」を意味するポリトルクであり、国家保安員会(KGB)の前身である内務人民委員部(NKVD)でした。NKVDは戦いに意義を見出せない兵士同士がささやき交わした会話や、ドイツ軍侵攻を密かに喜ぶ市民の声まで克明にとらえていました。
本書が採録したその記録によって、我々はイワンの心の闇を覗き見るのです。国民の声を封じ込めたNKVDの記録が、名もなき人々の声を後世に伝える一級の資料と化すとは、何という皮肉でしょうか。
戦場で後退する兵士を背後から撃ち殺すのもNKVDの任務でした。この「封殺部隊」はソ連崩壊後のチェチェン紛争で悪夢のように復活します。兵士が戦う理由を確信できない紛争は過去のものではありません。スターリンが依拠した「恐怖」の伝統も生きているのです。
ソ連やロシアの支配構造に深く組み込まれた秘密警察は早くから強い力を持っていました。しかし、ドイツとの戦争を有利に遂行するために活用されたとは言えません。イワンにとっては、皮肉というより悲劇と言うべきでしょう。
白水社、キャサリン・メリデール著、松島芳彦訳『イワンの戦争 赤軍兵士の記録1939-45』P450-451
※一部改行しました
この引用の前半に出てくるように、ソ連では独ソ戦を戦う前から信じられないほどの犠牲を出しています。このことについては以前も紹介しましたので以下の記事をご覧ください。
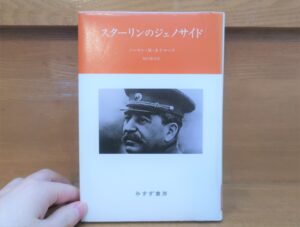


また、ソ連人と言っても、広大な国土を持ち、多種多様な人々で構成されていたソ連において、「単一のソ連人」という考えはなかなか定着しがたいものでした。こうした多種多様さをいかにうまくまとめるかにソ連政府は苦心していたのでした。
前線における兵士の価値観
ドイツの電撃戦の前には、イデオロギーも恐怖の統制もひとたまりもありませんでした。赤軍は総崩れとなり、兵士の命を大量に吸い込む「肉挽き機」と化しました。
赤軍はこの戦争で壊滅と再生を二度繰り返したというのです。開戦時の兵力は五百万人でしたが、一九四一年十二月までの半年で四百五十万人を失いました。この第一世代のイワンには、戦う意味を深く考える余裕も時間もありませんでした。
党が作戦にまで介入する硬直した軍隊にあって、何も分からないままに死地へと追い立てられていきました。この間にドイツは占領地で暴虐の限りを尽くします。第二世代のイワンを突き動かしたのは、家族や仲間を虐殺された怒りでした。
時代と戦争が新しい指導者を登場させます。イデオロギーより能力が必要でした。ヴォロシーロフらに代わり、ジューコフ、コーネフ、チュイコフら新世代の将星が戦争を指導しました。
前線でもポリトルクの影は薄れ、モスクワ攻防戦を契機に赤軍はようやく反撃に出ます。既に負け犬ではありませんが、戦う以外に選択肢のない兵士に、死は最後の最後まで最も身近で切迫した問題でした。
イワンはスターリン体制下に育ち、小さい頃から理不尽な死に囲まれて育ちました。戦場にあって生への執着に身を焼かれながらも、死が不可避であるなら、せめて意味のある死を、と願います。
前線で多くの兵士が入党しました。死に価値を与える「鋳型」が必要だったのです。マルクスやレーニンの教えに帰依したわけではありません。本書にはモスクヴィンというポリトルクが登場します。
彼は典型的な共産主義者でしたが、身分証を失い部隊に戻れなくなります。身元不明の逃亡兵として射殺されると恐れたのです。パルチザンに身を投じ、スターリンへの怨嗟が渦巻く農村に身を隠し、ソビエト体制に疑念を深めますが、共産主義は捨てませんでした。死に意味を与えてくれるものが、ほかになかったからだと著者は指摘します。
前線の価値観とは、このようなものでした。死線をともに越えた戦友や使い慣れた銃に寄せる信頼感のように、戦場の現実に過不足なく寄り添う確かな手触りが必要でした。
前線から遠く離れたモスクワで、スターリンの取り巻きや党官僚が喧伝する現実離れした言葉の遊びとは、およそ異質の感覚です。
しかし、祖国を救うため、生と死を価値あらしめるために兵士が命がけで獲得した哲学は、戦争が終わると国家にも社会にも、そして、あろうことか妻や家族にさえ受け入れられませんでした。
阻害され、拒絶され、官製の英雄像を、ある時は意識的に、ある時は無意識に演じるイワンの悲劇に、著者は冷静な視線を注いでいます。
白水社、キャサリン・メリデール著、松島芳彦訳『イワンの戦争 赤軍兵士の記録1939-45』P451-452
※一部改行しました
いつ死ぬかわからない極限の状態で自分が無駄死にするかもしれないということの恐怖。
「せめて意味のある死を」
この言葉の意味と重みを私たちはこの本を通して考えさせられることになります。
赤軍の暴虐と言葉にならない涙
赤軍は占領地で、殺人、レイプ、略奪と悪の限りを尽くしました。ソ連の公式戦史にも多くの退役軍人の証言にも出てこない惨状を、本書は生々しく再現しています。
救国の英雄、ナチに劣らない残虐な悪魔、始末に負えない酔いどれが、イワンの中にともに棲んでいるのです。戦争の混沌、極限状況の不可解な人間像をそのまま描こうとする著者の姿勢が作品に独特の奥行きを与えています。
著者によれば、ソ連の勝利は「ドイツの敗北」であり、「ロシアの解放」ではありませんでした。戦争の数年で人生の極限を生きてしまったイワンの戦後とは、囚われの歳月だったのでしょうか。
本書には兵士の涙を描く印象的な場面が三つあります。欧州に初めて足を踏み入れ、きれいな家並みを見て泣くイワン。動き出した復員列車で「喪失感」に泣くイワン。長い歳月を経てプロホロフカの戦跡に立ち、無言で泣く老いたイワンの姿です。決して言葉にならない涙の意味こそ作品の主題なのでしよう。
白水社、キャサリン・メリデール著、松島芳彦訳『イワンの戦争 赤軍兵士の記録1939-45』P452
※一部改行しました
この本に書かれた内容は本当にショッキングです。目を反らしたくなるような蛮行が語られます。
ですがそんな地獄のような世界を生きたイワンたちも涙を流していました。
イワンたちの犯した悪行は許されるものではありません。しかしそれをただ弾劾するだけでは何も解決しません。
なぜそのようなことが起こったのか、そしてイワンたちは何に苦しみ、涙を流したのか。このことを突き詰めていくことこそ、同じ歴史をくり返さないためにも重要であると私は感じました。
イワンと日本~私たちと決して無関係ではない独ソ戦
イワンの敵はドイツだけではありませんでした。本書では日本との戦いはごく簡単な記述にとどまっています。ソ連の命運という観点からは、独ソ戦に比べ日ソ戦の比重はごくわずかです。
しかし、日本からみれば、中国残留孤児やシベリア抑留、北方領土問題など、現在も尾を引く問題の原点として格別の意味があります。民族や国民の記憶は、当事者が死んでも消えはしません。ソ連の戦後世代、ロシアの冷戦後の世代にも、イワン伝説は一つの原型として受け継がれています。そして、日本人が描くイワン像は、おそらくその対極にあるようです。
ロシア国民は北方領土問題も、無意識のうちに独ソ戦のプリズムを通して眺めています。侵略を受け国家の存亡を賭けた独ソ戦と、敗戦を覚悟した国を相手に国外で戦った日ソ戦は、様相も事情も異なる戦争でした。戦争におけるソ連の死者総数二千七百万人のうち極東戦線での死者は一万人余です。ロシア国民の記憶の世界では、戦争と言えばヒトラーとの凄絶な戦いのほうが、圧倒的に存在感があります。
今のロシアの為政者が北方領土について「戦争の結果、わが国のものになった」と主張する時、大多数のロシア国民によみがえるのは独ソ戦なのです。
冷戦の敗北、共産主義の敗北である旧ソ連の崩壊を経て、独ソ戦の勝利はロシア国民に残された誇りの源泉として、重みを増してさえいます。イワン伝説は政治的な意味な失っていません。
伝説の深層に分け入り、歴史の伏流に耳を澄ますことでしか、歴史を政治から解放し、戦争や国家、あるいは国際関係という難物はとらえられないのだと、本書は語り掛けているように思われます。今後の日露関係を考えるためにも多くの方に読んでいただきたい作品です。
白水社、キャサリン・メリデール著、松島芳彦訳『イワンの戦争 赤軍兵士の記録1939-45』P452-453
※一部改行しました
私たちは第二次世界大戦におけるロシアというと、終戦直前に満州や樺太をはじめ、北方領土まで侵攻してきたというイメージがあります。
私自身も独ソ戦を学ぶまでロシアは終戦間際になって突然攻撃してきたというイメージしかありませんでした。
しかしそれはあくまで日本から見た視点であり、ソ連から見ればそうではなく、同じように国際政治というより広い視点から見てみるとまた違った相も現れてきます。
ものごとを知るには違った視点からも見てみることが重要であることをこの本は教えてくれます。
おわりに
全6回にわたり「『イワンの戦争 赤軍兵士の記録1939-45』を読む」シリーズを続けて参りました。
紹介しきれなかった内容も多々あります。このブログで紹介したよりもさらに生々しい悲惨な記述がこの本ではたくさん出てきます。
この本を読んで戦争とは人をこんなにも変えてしまうのかと戦慄しました。
この本も非常におすすめしたい作品です。ものすごい本です。今のこうした世界だからこそ重要な一冊であると思います。
次の記事から中世スペインの「異端審問」についてお話ししていきます。ソ連時代の粛清や秘密警察の恐怖、隣人の密告を恐れる疑心暗鬼の世界と驚くべき共通点があります。非常に興味深い出来事ですのでぜひ引き続きお付き合い頂けましたら幸いです。
以上、「『イワンの戦争 赤軍兵士の記録1939-45』を読む」でした。
Amazon商品ページはこちら↓
次の記事はこちら

前の記事はこちら

ソ連兵は何を信じ、なぜ戦い続けたのか「独ソ戦に学ぶ」記事一覧はこちら

関連記事







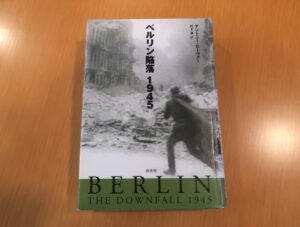







コメント