サンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼とお遍路~巡礼の旅を考える スペイン編⑯

サンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼とお遍路~巡礼の旅を考える 僧侶上田隆弘の世界一周記―スペイン編⑯
前回の記事「サンティアゴ・デ・コンポステーラで聖地の意味について考える スペイン編⑮」では聖なるもののパワーという切り口からサンティアゴ・デ・コンポステーラについてお話しした。

聖なるもののパワーは実際に人間の心身に作用し、歴史を動かしてきた。
そして現在でも多くの人がサンティアゴ・デ・コンポステーラを目指し、巡礼の旅を続けている。
サンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼はスペイン北西部のピレネー山脈の辺りからスタートすることが多い。
この巡礼は実はスタート地点は明確には定められていない。
聖地を目指すルートはいくつもあるのだ。
その中でも人気なのはフランスとスペインの国境付近にあるサン=ジャン=ピエ=ド=ポールという町をスタート地点にした「フランス人の道」というルートだ。
道のりはおよそ800km。
徒歩でおよそ30日間の巡礼路だ。
このルートはアルベルゲと呼ばれる巡礼者用の宿泊施設も多く、ブルゴスやレオンなど、歴史ある街を通りながら巡礼できるため人気なのだそうだ。
さて、サンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼をここまでざっくりとお話ししてきたのであるが、みなさんはこのような思いが頭をよぎったりはしなかっただろうか。
「なんだか、サンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼って四国のお遍路に似てるなぁ・・・」
サンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼と四国八十八カ所のお遍路・・・
国や文化も違えど、やはり「巡礼の旅」という点ではやはり共通点がある。
四国八十八カ所もおよそ1400kmの道のりで徒歩だと50日もかかる長旅だ。
そして旅の途中では宿坊と呼ばれるお遍路さんのための宿泊施設もある。
そして何より1番札所霊山寺から順に回り、最後の88番大窪寺というゴールを目指すという1本の道のり。
四国八十八カ所もサンティアゴ・デ・コンポステーラと同じく、信仰ある者を惹き付け続けている聖なる巡礼だ。
そしてまた同時に、特定の信仰の面だけではなく個人個人の願いの成就、願掛けという側面からも今なお多くの人が足を運んでいる。
ちなみにぼく自身も四国八十八カ所のお遍路が大好きで、学生時代に2周回っている。

レンタカーでのお遍路ではあったがこれを着用してお遍路の札所を巡った。
車でのお遍路でも1週間ほど時間を要する四国八十八カ所。
細いうねうねの山道を走り続けるお遍路は車でもなかなかにハードな旅だ。
だが、旅の間は不思議な高揚感に包まれる。
自分はお遍路をしているのだという事実そのものがなんだかありがたい。
やってみて感じたことだが、巡礼というものにはなんだか不思議な魅力がある。
機会があるならばもう一度行きたいと心の底から思えてしまう。
そんなお遍路の旅であるが、ここでやはり疑問に思う。
「そもそもなぜ人は巡礼の旅に出るのだろうか」と。
「巡礼はなぜ人を惹き付けるのか」
前置きが長くなってしまったが今回の記事ではそのことについて少し考えていきたい。
さて、巡礼の旅とはまず前提としてゴールとしての聖地が存在する。そしてその聖地を目指して旅に出るというのが巡礼のひな型だ。

例えば、人々は自分たちの住むヨーロッパからはるか彼方の聖地エルサレムへと歩き出す。(かつてはすべて徒歩であったが現代では飛行機に乗る)

そして聖墳墓教会というイエスのお墓にお参りし巡礼はフィナーレを迎え、再び自分たちの家のあるヨーロッパへと帰っていく。
つまり日常の生活圏から聖地へと赴き、聖地に着いてからまたいつもの日常へと帰っていく。
これが巡礼の大きな流れだ。
これは当たり前のように思えることではあるが実はこの構造がものすごく重要な意味を持っている。
いや、この構造こそが人々を引き付ける秘密なのだと言っても過言ではない。
一体、これのどこがそんなに重要なことなのだろうか。
それを理解する鍵は「聖と俗」という考え方にある。
「聖」については先の記事でも述べてきたように、「聖なるもの」、そして「聖なる力を持つ聖地」という意味だ。汚れのない清らかな世界、そのような世界を「聖なる世界」と言う。
それに対して「俗」という概念。
みなさんも「俗世間」という言葉を聞いたことがあるのではないだろうか。
「俗」とはまさにその通り、俗なる世界のこと。さらに言うならば私たちの日常の世界のことだ。
日常生活はきれいごとだけでは済まされないことでいっぱいだ。
煩悩が荒れ狂う世界。欲望や怒り、妬み怨み。
「俗なる世界」は「聖なる世界」とは対称的な汚れた世界と言えるのだ。
もう一度おさらいしょう。
巡礼のひな型は、「日常生活→聖地→日常生活」という流れだ。
これは言い換えれば「俗世界→聖なる世界→俗世界」ということになる。
巡礼の旅は一歩旅へと足を踏み出したその瞬間から日常の俗世界を離れることになる。
単に違う場所へ移動するということとは本質的に異なる行動なのだ。
単に物理的に違う場所へ行くのではなく、聖なる世界の領域に入り込むことになるのだ。
さらに巡礼の旅の重要な点は、旅そのものが非日常の聖なる行であるというところにある。
つまり旅そのものが聖なる修行なのだ。
巡礼者は苦しい旅路を続けながらも「自分は神に認められた聖なる修行を修めているのだ。」という感覚を持ち続けることになる。
この感覚は強い自己肯定感をもたらす。
「自分は神に認められている。自分は今間違いなくよいことをしているのだ。」という、俗世界ではなかなか味わうことのできない感覚を巡礼の旅では得ることができるのだ。
そして聖地で聖なるものの根源に触れ、心身を浄化し、罪の汚れを取りさらい、また日常へと帰っていく。
日常へ再び帰ってくるときには、聖なる力で浄化された新しい人間として日常生活を再スタートすることができるのだ。
言い換えるならば巡礼の旅という営みが罪に汚れた人間を浄化し蘇らせ、人間に新たな活力を与えるのだ。
俗→聖→俗という流れはそのような働きを持ち、これが巡礼の旅の根本に流れる命なのだ。
―と、言ってもそれは現代文明が生まれる前の昔の人たちのことの話なんでしょ?
・・・たしかにそうだ。
かつては地獄が本当に存在すると皆が信じていたし、自分が死後どうなるかは生きる上での最大の問題だった。
自分のような罪深い人間はどうしたら地獄に行かなくて済むのか。
これは本当に死活問題だった。
その問題は現代を生きるぼく達には想像もできないくらいのリアリティがあったのだ。
だからこそ皆必死で罪の浄化を願ったのだ。
そして教会も罪の浄化の手段をいくつも人々に提供していた。
それが懺悔であったり、教会のミサであったり、そしてこれまで述べてきた巡礼という行でもあったのだ。
日本でも状況は一緒だ。
日本でも人々は地獄のリアリティに恐れおののき自らの罪に苦しむばかりだった。
だからこそ救いや浄化が心の底から望まれていたのだった。
たしかに今を生きるぼくたちにはそこまでのリアリティを伴った罪の意識はない。
教会やお寺から「これをすればあなたは地獄行きにはなりませんよ」と言われてもなかなかぴんとは来ないだろうと思う。
かつてのような宗教的な意味合いでの巡礼は現代ではかなり失われてしまったが、それでも巡礼は今なお人々を惹き付けている。
それはなぜなのだろうか。
そこにはやはり人間の心が「聖なるもの」を求めているからなのではないかとぼくは思う。
かつてのような特定の宗教教団による信仰の形は失われてしまってきてはいるものの、どうやら人間は「俗世間」を離れた「聖なるもの」を今でも求め続けているのではないかとぼくは思うのだ。
表向きには宗教離れが加速している今、パワースポット巡りや御朱印巡りなどが人々の心を捉えている。
それらも大きな意味では「聖なるもの」を求める気持ちから起こっていることではないだろうか。(もちろん様々な側面もあるが・・・)
そしてお遍路はその最たるものだ。
お遍路をお参りする人はそれぞれ心に強い思いを抱いて巡礼する。
その強い思いを成就するために聖なる旅へと踏み出すのだ。
強い思いさえあればどこを歩いてもいいというわけではない。日本縦断のほうがはるかに距離もあるし時間もかかる。でも、それではだめなのだ。
お遍路だからこそ意味があるのだ。
「聖なるもの」がそこにあるからこそ、人は強い思いを抱いてそこを歩くのだ。
サンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼もまさしくそうだ。
聖なる旅路であるから人はそこを歩くのだ。
かつてのような信仰はもはやなくなってしまったのかもしれないが、「聖なるもの」の力は今なお人々を惹き付け続けているのだ。
さて、ここまでサンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼とお遍路を「聖と俗」という観点からお話ししてきた。
巡礼がなぜ人々の心を捉えるのか、ぼくは今回以上のような観点からお話ししたがもちろんこれが巡礼の全てではない。
様々な要素が絡まって過去から現在にかけて聖地は人々を惹き付け続けている。
サンティアゴ・デ・コンポステーラは「聖なるもの」について考えさせられた場所であった。
続く
次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事



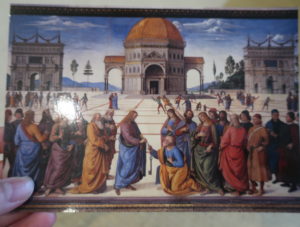
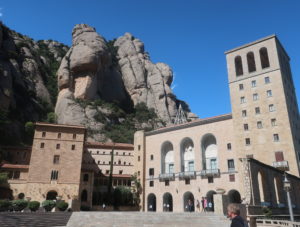




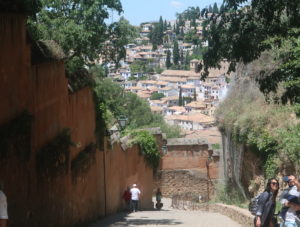



コメント