ルクレーティウス『物の本質について』あらすじと感想~古代ローマのエピクロス派哲学者による驚異の自然科学論!

ルクレーティウス『物の本質について』あらすじと感想~古代ローマのエピクロス派哲学者による驚異の自然科学論!
今回ご紹介するのは1961年に岩波書店より発行されたルクレーティウス著、樋口勝彦訳の『物の本質について』です。私が読んだのは1970年第7刷版です。
早速この本について見ていきましょう。
エピクロスの唯物的哲学の影響を受けたローマの詩人哲学者ルクレティウス(BC94頃〜55)の現存唯一の長詩。エピクロス哲学の原子論的自然観を詳述した科学的啓蒙書として現在無二の史料的価値をもつ作品である。一切の現象を因果関係において把え、原子と空間から成る世界の自然法則を説明して現実の生を楽しむことを教えたこの雄大な長詩は古代の哲学の圧巻である。
Amazon商品紹介ページより

ルクレーティウスは古代ローマのエピクロス派の哲学者です。同時代人にはあのカエサル(前100-44)やキケロ(前106-43)がいます。
私はこのルクレーティウスの『物の本質について』を読み衝撃を受けました。
「2000年以上も前にすでにこんなことを言っていた人がいたのか!」とそれこそ度肝を抜かれました。
上の本紹介に「エピクロス哲学の原子論的自然観を詳述した科学的啓蒙書として現在無二の史料的価値をもつ作品である」と述べられていたように、この作品は科学的思考が書かれた作品です。2000年以上も前の科学的思考とはいかなるものかということをこの本では知ることができます。
この作品では冒頭でいきなり無神論にも近い衝撃的な言葉が語られます。
恐ろしい形相を示して、上方から人類を威しつつ、天空の所々に首を見せていた重苦しい宗教の下に圧迫されて、人間の生活が、誰れの目にも明らかに、見苦しくも地上を腹ばっていた時に、初めてギリシア人の、死すべき一介の人間(エピクーロス)が、不敵にもこれに反抗して、目を上げた。彼こそは、これに反抗してたった最初の人である。
神々のことを語る神話も、電光も、脅迫の雷鳴を以てする天空も、彼をおさえつけるわけにはゆかず、むしろ、かえって彼の精神の烈々たる気魄をますます、かきたてることとなり、その結果、人間として初めて自然の門のかたい「かんぬき」を破りのぞこうと望ませるようになった。従って、彼の精神の活発なカは、何ものといえども征服せざるものなく、世界の果、火とらえる壁をうちこえて遠く前進し、想像と思索とによって、あらゆる無限の世界をふみ歩いた。
その結果、彼が勝利者として我々のために、もたらしてくれたものは、次の点を明らかにしてくれたことである。
即ち、何が出生しうるものであるか、何が出生しえざるものであるか、要するに、おのおのその能力に一定の限度がもうけられているか、また深く根ざした限界があるか、の点を明らかにしてくれたことである。このために、宗教の方がおさえつけられ、足の下にふみにじられてしまい、勝利は我々を天と対等なものにしてくれるに至った。
岩波書店、ルクレーティウス、樋口勝彦訳『物の本質について』1970年第7刷版P12-13
※一部改行しました
「宗教の方がおさえつけられ、足の下にふみにじられてしまい、勝利は我々を天と対等なものにしてくれるに至った。」
今から2000年以上も前にこのような言葉がすでに述べられていたというのは驚きですよね。
そしてさらに次のように述べます。
われわれは一方に、天空の現象に就いて、また太陽や月の運行は如何にして起るか、また地上に生ずるあらゆる現象は如何なる力に由来して起るのか、の点に関して正しい理論をたてる必要があるが、他面特に、明敏なる理性を用いて、たましいは何から構成されているか、精神の本質は何から構成されるか、を検討してみなければならない。
また、病気にかかっている時に、目ざめているわれわれに、あるいはまた、われわれが眠りにうずもれている時に、目の前に見えて、心をオビえさせ、さては死去してその骨が大地に抱かれている故人を目に見、面前にその声を聞くの思いを抱かせるのは、一体如何なる現象であるかを検討しなくてはならない。(中略)
だから、このような精神の恐怖と暗黒とは、太陽の光明や、ま昼の光線では、一掃できないことは必定であり、自然の姿〔を究明すること〕こそ、また自然の法則こそ、これを取り除いてくれるに違いない。
自然の先ず第一の原理は、次の点からわれわれは始めることとしよう。即ち、何ものも神的な力によって無から生ずることは絶対にない、という点である。死すべき人聞は、地上に、また天空に、幾多の現象の生ずるのを見て、その原因が、如何なる方法を以てしても、うかがい知ることができず、これひとえに神意によって生ずるのだ、と考えてしまうが故に、実はかくの如く、誰れしも皆恐怖にとらわれてしまうのである。
従って、無よりは何ものも生じ得ず、ということを一とたび知るに至れば、ひいて忽ちわれわれの追及する問題、即ち、物はそれぞれ如何なる元から造られ得るのかということも、またあらゆる物は神々の働きによることなしに、如何にして生ずるか、という点もいっそう正しく認識するに至るであろう。
岩波書店、ルクレーティウス、樋口勝彦訳『物の本質について』1970年第7刷版P16-17
※一部改行しました
いかがでしょうか。人は科学的思考をしないがゆえに「神意」を持ち出し自ら恐怖に落ち込んでいるのだとルクレーティウスは述べるのです。
繰り返しますが彼がこれを書いたのは2000年以上も前の話です。ちょっと信じられないくらいですよね。
最後にもう一つ彼の言葉を紹介します。ここに出てくるユーピテルはギリシャ神話のゼウスのことです。では読んでいきましょう。
ところで、もし仮りにユーピテルとかその他の神々とかが、恐ろしい音をたてて輝く天界を震駭させるのだとしたならば、又神々が各自思い思いの方向へ火を投ずるのだとしたならば、厭うべき罪を迂濶にも犯した者はすべて皆〔雷に〕打たれ、貫かれた胸から雷電の焔を吐くように—これこそ人類に対する峻烈な訓めであるが—取計うことなくして、寧ろ何ら恥ずべき行いを犯した覚えのない者が、罪のないのに焔に巻き込まれ、天空から来た旋風に突如として包まれ、火にさらわれてしまうことのあるのは一体何故であろうか?
又、何故彼ら神々は淋しい処を狙い、労を徒労に帰せしめるのだろうか?それとも、そう云う時には、神々が腕ならしをして、筋肉を強健にしようと云う時なのだろうか?又神々は何故父なる神〔ユーピテル〕の投槍〔雷電〕が大地に当って鈍るのを黙って見ているのだろうか?何故、彼〔ユーピテル〕自身はこれを黙認し、敵に向ける為に取っておかないのだろうか?
更に、四方晴れわたった空には、ユーピテルは決して電光も、雷鳴も地上に注がないのは何故であろうか?それとも、雲が下って来るや否や、近くから投げ槍〔雷電〕を打つ狙いを定める為に、彼は雲の中へ降りて来るのだろうか?更に、何故海へ落すのか?何だって海を、水の塊りを。泳ぐ原〔海〕を打とうとするのだろうか?
岩波書店、ルクレーティウス、樋口勝彦訳『物の本質について』1970年第7刷版P284
※一部改行しました
「もうやめてあげて!」と言いたくなるほどルクレーティウスは自然現象を冷静に見ていきます。彼はこれら自然現象を「神意」として理解することを徹底的に拒みます。科学的に見ていけばわかるはずだと、この本ではひたすら冷静にその自然現象を見ていきます。この徹底した姿勢は驚くべきものがあります。
ルクレーティウスはエピスロス派の哲学者です。
それに対して後のローマではセネカやエピクテトス、マルクス・アウレリウスなどストア派の哲学者が主流を占めていきます。そしてこのストア派の哲学はキリスト教の思想とも親和性がありましたのでその思想は吸収されていくことにもなりました。
ただ、これまで読んできて想像できますように、このルクレーティウスの宗教観はキリスト教とは決定的に相性が悪いです。「無から生じるものなどありえない」と述べる彼の説はどうやっても受容不可です。
というわけでキリスト教世界ではそこまで重視されることもなく薄れていったのですが、実は後にこの思想がルネサンスに繋がっていくのでありました。
ルネサンスは古代ギリシャやローマの文献がどんどん再発見された時代でした。そしてこのルクレーティウスもその一人です。
彼の自然科学論はまさしくルネサンス以降の人間観を表しているようには見えてきませんでしょうか。
ルネサンス以後急速に発展していく科学的思考。その発展に大きな影響を与えたのがこのルクレーティウスなのではないでしょうか。この作品を初めて読んだ当時のヨーロッパ人たちはそれこそ目が飛び出るくらい驚いたのではないでしょうか。
キリスト教を批判するだけで処刑される時代です。コペルニクスやガリレオ・ガリレイはルネサンスからさらに時代を下った人物です。その彼らでさえその時代風潮に苦しみました。
そんな中ここまではっきりと「神意はない」「無からものは生まれない」と言い切るルクレーティウス。
恐るべき人物が古代ローマにいました。
古代ローマの文化水準の高さに改めて驚いた読書になりました。
以上、「ルクレーティウス『物の本質について』あらすじと感想~古代ローマのエピクロス派哲学者による驚異の自然科学論!」でした。
Amazon商品ページはこちら↓
次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事















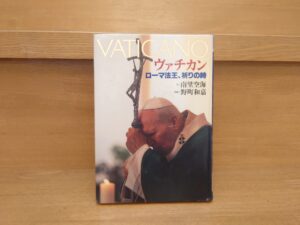



コメント