シェイクスピア『リチャード三世』あらすじと感想~恐るべき悪のカリスマと運命の輪。初期の傑作史劇!

シェイクスピア『リチャード三世』あらすじと感想~恐るべき悪のカリスマと運命の輪。初期の傑作史劇!
今回ご紹介するのは1592年から93年頃にシェイクスピアによって書かれた『リチャード三世』です。私が読んだのは新潮社版、福田恆存訳です。
早速この本について見ていきましょう。
身体に障害を負った野心家グロスター公リチャードは、兄のエドワード四世王が病に倒れると、王権を狙い、その明晰な知能と冷徹な論理で、次つぎに残忍な陰謀をくわだて、ついに王位につく──。魔性の君主リチャードを中心に、薔薇戦争終結へといたる権謀術数の暗部を描き、口を開いた人間性のおそろしい深淵に、劇詩人シェイクスピアが、真っ向からいどんだ傑作史劇である。
Amazon商品紹介ページより
今回ご紹介する『リチャード三世』は前回の記事で紹介した『ヘンリー六世』のまさに続編になります。

前作『ヘンリー六世』の段階ですでにグロスター公リチャードはその悪人ぶりを垣間見せていましたが、本作ではその悪のカリスマぶりを遺憾なく発揮します。
前回の記事でお話ししましたように、『ヘンリー六世』はこの『リチャード三世』のプロローグ的な役割も果たしていました。それによって私たち読者、観衆からすると続きが観たくて観たくてたまらない状態にさせられます。もうシェイクスピアの手のひらで転がされているようなものです(笑)
そしてその勢いのままこの作品を読むと最高に楽しい時間を過ごすことができます。『リチャード三世』を読む助走として『ヘンリー六世』をまずは読むことをおすすめします。
そしてさらに言えば、これら二作品を読む前に陶山昇平著『薔薇戦争』も読むことを強くおすすめします。

『ヘンリー六世』と『リチャード三世』は15世紀にイギリスを二分した内乱、薔薇戦争を舞台としています。この内乱がとにかく複雑なので、大まかにでもその流れを把握しないとシェイクスピアの劇も楽しめません。何せ登場人物も多く、さらには誰がどちらの陣営にいるかもわからないといけません。
ですがざっくりとでもその流れを知っておくとこれらの劇が一気に面白くなります。私たちが信長や秀吉、家康などの戦国時代の物語を楽しんで観るように、当時の観衆たちもこれらの物語を楽しんでいたのです。
というわけで前置きは長くなってしまいましたが、『リチャード三世』は『ヘンリー六世』で劇作家デビューしたシェイクスピアの傑作史劇です。訳者解題でもその人気ぶりについて次のように紹介されていました。
『リチャード三世』はシェイクスピアの極く初期に書かれた歴史劇であるが、初演以来今日まで、上演回数においても、見物の人気においても、後期の悲劇に匹敵するものがある。また、この作品は舞台で成功したばかりでなく、やや饒舌と言ってもよいほど溌剌として流動するせりふの魅力が多くの読者をひきつけ、既に作者生存中、四折本として六度も版を重ねている。
新潮社、シェイクスピア、福田恆存訳『リチャード三世』P211
ここで「やや饒舌と言ってもよいほど溌剌として流動するセリフの魅力」とありますが、たしかにこの作品のセリフには力があります。
リチャードが兄のクレランスを罠にはめて殺そうとしている時の、
さあ、二度と戻らぬ旅路を辿るがよい、お人好しの凡くら、クレランス、俺はお前が大好きだ、だから、すぐにも天国へ送りとどけてやる、天の方で受取ってさえすればな。
新潮社、シェイクスピア、福田恆存訳『リチャード三世』P17
というセリフ。何たる悪党ぶりでしょう。謀略を尽くして身内を殺すことに何の躊躇も感じていません。ですがこの何とも機知に富んだ言い回しがやはりたまりません。最悪な悪人なのはわかっています。ですが我々読者からすればなぜか憎み切れないのです。
そしてリチャードは次から次へと敵を殺し、血にまみれていきます。
ですがさすがに自身の行く末に思うことがあるのかこんなことも後半で述べます。
どこまで行けるか! が、血の流れにここまで踏みこんでしまった以上、あとは罪が罪を呼ぶのにまかせるだけだ、あわれっぽい涙はこの目には宿らぬぞ。
新潮社、シェイクスピア、福田恆存訳『リチャード三世』P146
開き直りのようにも聞こえるこのセリフですが、後の彼の運命を暗示する重要なセリフのようにも私は思えました。
そしてついには実の母にこんなことまで言われてしまいます。
お前がまだ呪われた胎のなかにいるうちに、絞め殺してしまえばよかった、そうすれば、その手で犯した残虐非道の人殺しの邪魔が出来たろうに!
新潮社、シェイクスピア、福田恆存訳『リチャード三世』P161
さすがに実の母にここまで言われてしまうのはあまりに気の毒な気がしてしまいますが、それほどのことをリチャードは繰り返してきたわけです。
たしかに、リチャードの悪行は恐るべきものがあります。ですがこの史劇を読んでいると、それでも彼を「悪のカリスマ」として見てしまう不思議な魅力、いや魔力があるのです。
このことについて訳者は次のように解説します。少し長くなりますがこの作品を楽しむ上で非常に重要なポイントが指摘されていますのでじっくりと読んでいきます。
個人の意思を超えた大きな運命の流れが作品を一貫していて、自分だけはそれから免れていると思っている人物達が、次々にその罠に陥り、彼等が意識の外で不用意に洩した言葉が、必ず自分の頭上に降りかかってくる。そして、自分だけは運命の手から逃れていると、誰よりもそう思っているリチャード、いや、人々の運命を操っているのは自分であり、のみならず自分の運命さえ自由に操れると思っているリチャードが、最後に、最も完璧に、自己の破滅を通して運命の存在証明をするのである。そういう悲劇的アイロニーそのものの表出のために、この劇は書かれているとさえ言える。その点では、非常に論理的であり、同時に、読者あるいは見物の倫理感や心理をも満足させるものとなっている。
そのうえ、リチャードという特異な性格の魅力が、時代を超えた人気をこの作品に与えてきたことも見逃せない。第一に、リチャードは権謀術数に徹したマキャヴェリアンであり、しかも肉体的にはせむしでびっこという醜い姿態の持主である。近代的な心理主義から言えば、彼の見えすいた偽善や嘘に、他の人物たちが、どうして、こうもやすやすと引掛ってしまうのかという疑問が湧くであろう。が、もしそう思ったなら、それは読者が作品を読みそこなっているか、あるいは役者がリチャードを演じきれずにいるか、そのどちらかの場合である。
もちろん、多少強引ではあるが、シェイクスピアは人間心理の現実を無視しているのではない。近代的な心理主義の疑いぶかい目で詮索すれば、シェイクスピアの劇はすべて不自然になってしまう。のみならず、劇というものがすべて造りものになり、登場人物の行為はことごとく愚かしいものに見えてくる。が、この現実の世界では、そんな馬鹿なことがと思われるような詐欺が、易々と成功する。新聞記事で読めば、馬鹿らしいと思うことが、当事者にして見れば、なかなかそうはゆかないのである。その当事者と第三者との差はどこにあるかと言えば、第三者は当事者と違って、自分をだます人間を眼前に見ていないということだ。言いかえれば、その人間の性格の力の働きかけを直接に感じていないということだ。
リチャードを演じる役者は、せりふの行間にその力を表現していかなければならないのだ。シェイクスピアはそれだけの用意をしている。私達は、リチャードの性格に、その第二の魅力として、冗談や皮肉を弄ぶ明るい意識家を見逃してはならない。それは彼の周囲の人間が、その愛嬌によってだまされるということではない。むしろその反対である。リチャードは自分の悪を意識していると同時に、それをあえて他に隠そうとはしていないのである。彼は、いわゆる偽善者のような鈍感な人物ではない。なるほど、手段として偽善の面はかぶるが、そんなときでも、彼のこまかい神経は、自分が偽善を演じていることを自他の目に隠そうとはせず、明るくそれをぶちまけてしまったり、それに気づかぬ相手の鈍感を嘲笑したりする。すくなくとも、自分に向って、それをはっきり意識していることを示さずにはいられぬ皮肉屋である。つまり、彼の偽善は偽悪と紙一重なのだ。
新潮社、シェイクスピア、福田恆存訳『リチャード三世』P222-224
リチャードはたしかに悪人です。ですが彼は幼いころから強い劣等感、身体的な引け目を感じて生きてきました。しかも兄は国王。さらには己の容姿にもリチャードは耐えがたいものがありました。
そんなリチャードが全てをひっくり返す「力」を欲したのです。自らの知略、権謀術数、そして悪を恐れぬ強い精神を総動員してすべてをつかみ取ろうとしたのです。彼は悪を望み、悪をなすことを愛したわけではありません。「力」を得るために、王冠を得るためになせることをやったに過ぎないのです。もちろん、彼の残虐非道な行いは肯定されるはずもありませんが、『リチャード三世』は、己に苦しみ、力を得んと本気でもがき、運命に挑戦した男の物語でもあるわけです。そして最後は自らも運命の手によって破滅していくことは上の解説の通りです。
こうした運命への挑戦、そして破滅という物語があるからこそ大悪党リチャードに私たちはカリスマを見てしまうのではないでしょうか。単なる悪人で収まりきらない魅力がこの男にはあります。
最後に、この作品にまつわる有名な絵を紹介してこの記事を終えたいと思います。きっと皆さんも見たことがある絵なのではないでしょうか。

1878年にイギリス人のラファエル前派の画家ミレーによって描かれたこの絵は、このリチャード三世によって殺されたとされる前王エドワード四世の息子たちになります。
リチャード三世は自らが王となるために、兄の息子たちを根絶やしにしたのです。その息子たちが幽閉され殺されたのがあのロンドン塔でした。そのことを題材として書かれたのが上の絵で、もちろんシェイクスピアの作品にも大きな影響を受けているとされています。

ミレーとシェイクスピアといえばこちらの作品が有名ですよね。『ハムレット』のヒロイン、オフィーリアが川で亡くなるシーンを描いた作品です。
このように、芸術作品にも巨大なインスピレーションを与え続けているシェイクスピア。『リチャード三世』も劇的なシーンや、力強い言葉に満ちた名作となっています。初期の作品とは思えないほどのクオリティーです。
ぜひ、陶山昇平著『薔薇戦争』、『ヘンリー六世』、『リチャード三世』と続けて読まれることをおすすめします。
以上、「シェイクスピア『リチャード三世』あらすじと感想~恐るべき悪のカリスマと運命の輪。初期の傑作史劇!」でした。
Amazon商品ページはこちら↓
次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事
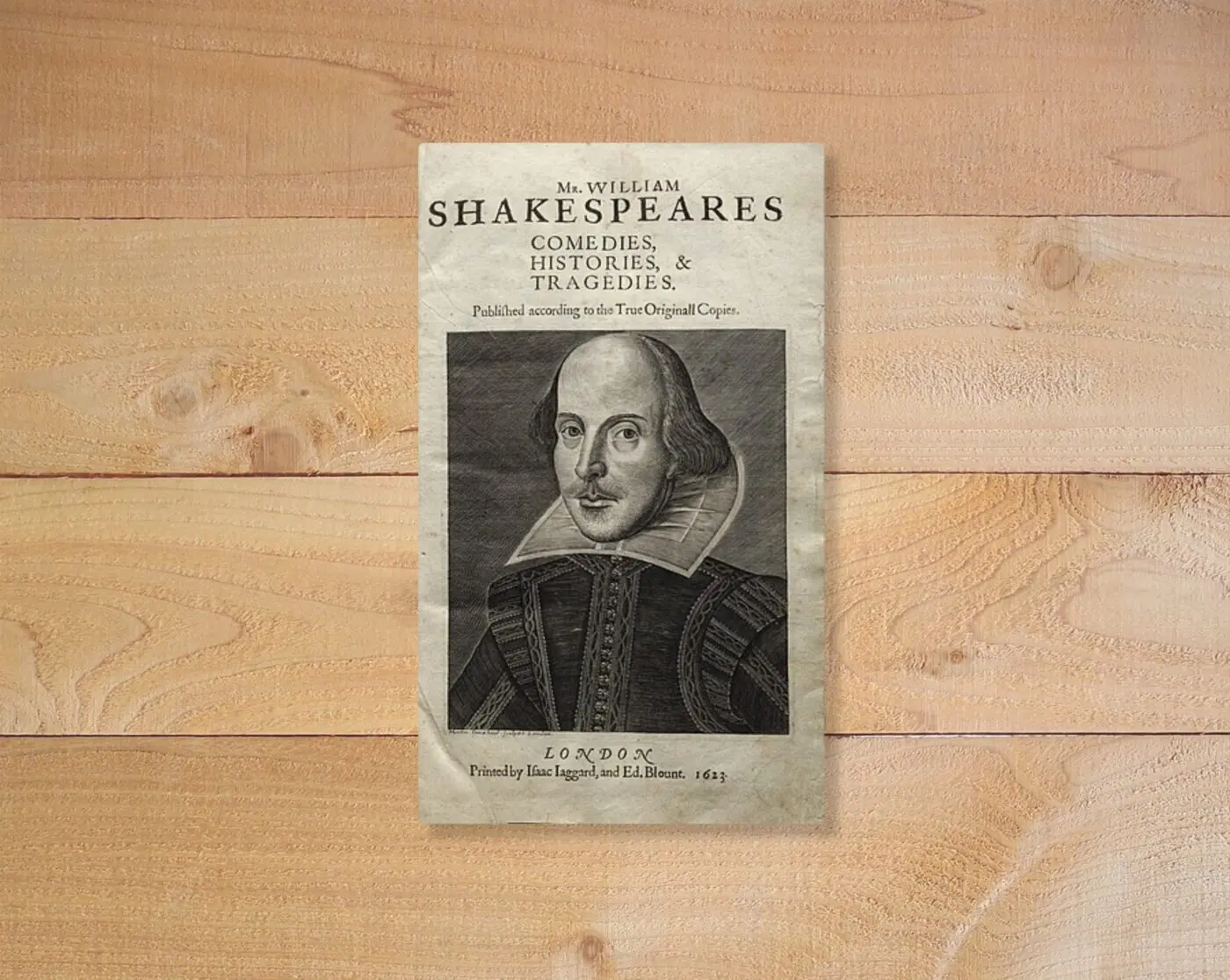
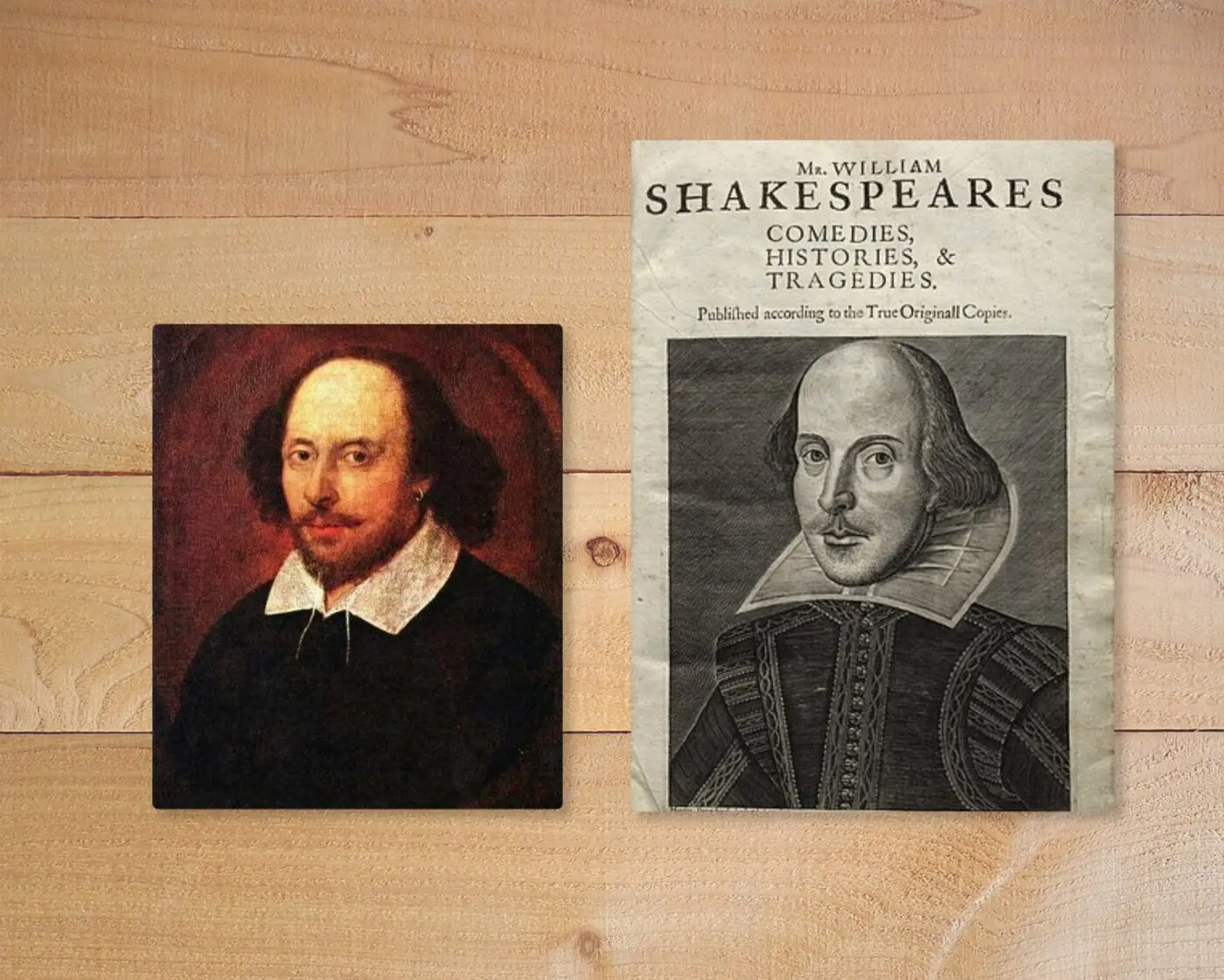







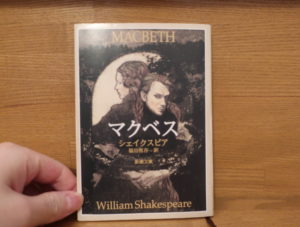
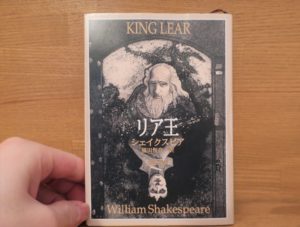



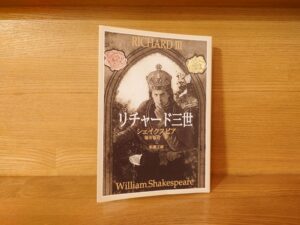






コメント