『ツァラトゥストラ』にニーチェの孤独の寂しさを感じる~「神は死んだ」で有名な代表作

「神は死んだ」で有名なニーチェの代表作~ニーチェ『ツァラトゥストラ』あらすじと感想

今回ご紹介するのは1883年から1885年にかけてニーチェによって発表された『ツァラトゥストラ』です。私が読んだのは筑摩書房版、吉沢伝三郎訳の『ニーチェ全集9、10 ツァラトゥストラ』です。
早速この本について見ていきましょう。
いよいよ本書の第三部において、ある恐るべき深淵的な思想としての永遠回帰の思想がツァラトゥストラによって告知される。神の死という現代のニヒリズムのもとでの生の真の意味とはなにか。ニーチェは現代の人間の危機的状況をニヒリズムそのものへの徹底と、生の瞬間の肯定により主体的に超克することを説く。ニーチェの人間学の精髄が隠された、万人のための運命的な書というべき真の哲学書。下巻には全四部構成のうち、第三部から第四部までを収録。なお、文庫収録にあたっては、最近のニーチェ研究の成果に基づいて訳註を大幅に増補改訂した。
Amazon商品紹介ページより
『ツァラトゥストラ』といえば「神は死んだ」という言葉で有名なニーチェの代表作です。
この本はこれまで私も何度も読んできました。学生時代、院生時代、社会人時代とそれぞれのタイミングで読んだ思い出があります。
ただ、以前の記事でも少しお話ししましたがやはりこの本は危険な書物です。
というのも、既存の秩序を破壊せんとするこの本ではかなり攻撃的な言葉が発せられ、これを読むとそれに感染してしまうということが起こりうるからです。
『ツァラトゥストラ』を読むとなぜか熱に浮かされるような、自分が強くなったかのような気がしてくるのです。正直、読むたびに「自分が他人よりもよく世界を知っている」という気にさせられ、そこから周りを見下してしまいそうな気分になってしまうのです(それは私が若かったからということや、私の読み方が未熟だったせいかもしれません。)
ですが、最近になって様々な参考書や、他の作品を読むことでそんなニーチェへの印象が変わってきました。
この記事では「神は死んだ」という思想や、力への意志、超人、永劫回帰などニーチェの思想についてはお話ししません。専門家でない私がそれら難解な思想を解説するのは不可能です。
ですが、そんな難解な思想のオンパレードである『ツァラトゥストラ』を読んでいていつも強い印象を受ける箇所があります。それが「市場のハエどもについて」という章です。せっかくですのでその中のいくつかを見ていきたいと思います。
すべての偉大なことは、市場と名声から離れたところで起こる。昔から、新しい諸価値の創案者たちは、市場と名声から離れたところに住んだのだ。
のがれよ、わが友よ、きみの孤独のなかへ。わたしは、きみが毒バエどもによってさんざんに刺されているのを見るのだ。かしこへのがれよ、荒々しい強い風の吹くところへ!
きみの孤独のなかへのがれよ!きみは、卑小な憐れむべき者たちの、あまりにも近くに生きた。彼らの、目に見えない復讐から、のがれよ!きみに対して、彼らは復讐にこりかたまっている。
もはや彼らに対して腕を振り上げるな!彼らは数えきれないほどいる。そして、ハエたたきとなることは、きみの運命ではないのだ。
これらの卑小な憐れむべき者たちは、数えきれないほどいる。そして、ただの雨滴や雑草だけが因となって、堂々たる建物が崩壊するにいたった例が少なくないのだ。
きみは石ではないが、すでに多数の点滴によってうがたれた。きみは今後なお多数の点滴によって、砕け、こなごなになることであろう。(中略)
彼らは、まったく無邪気に、きみの血をほしがる。彼らの貧血の魂が血を欲求するのだ―それゆえ、彼らはまったく無邪気に刺すのだ。
しかし、きみ、深い者よ、きみは小さい傷にもあまりに深く悩む。しかも、きみがまだなおりきらないうちに、同じ毒虫がきみの手の上を這いまわった。
筑摩書房版、吉沢伝三郎訳『ニーチェ全集10 ツァラトゥストラ』上巻P95-96
ニーチェは生前、世間からほとんど評価されることがありませんでした。デビュー作の『悲劇の誕生』では学者界から激しい反発を受け、学者としての栄華の道も断たれます。世間からも、学者たちからも彼は理解してもらえない状況だったのです。
誰からも理解されない苦悩・・・そして同時に世の中で繁栄している者たちへの激しい感情・・・
そうしたものがこうしたニーチェの言葉から感じられます。
もう一つこのすぐ後の言葉も見ていきます。ここがまた凄まじいんです。
彼らは、一切のきみの諸徳のゆえに、きみを罰する。彼らがきみに対して心の底から容赦するのは、ただ―きみのもろもろの失策だけだ。
きみは、温和で、心が公正であるから、「彼らにはその卑小な現存在の罪責はない」と言う。だが、彼らの偏狭な魂は考える、「一切の偉大な現存在は罪責である」と。
きみが彼らに対して温和であっても、彼らはやはり、自分がきみに軽蔑されていると感じる。そこで彼らは、きみの恩恵に報いるに、かずかずのひそかな加害をもってする。
きみの無言の誇りは、つねに彼らの趣味に反する。かりにもきみが、虚栄心の強い者となるほど謙虚になるなら、彼らはこおどりして喜ぶ。
或る人間がどういう人間であるかを、われわれが認識すると、われわれは彼をそういう人間として燃え立たせることにもなる。それゆえ、卑小な人間たちに用心せよ!
きみの前では、彼らは自分の卑小さを感じる。そこで彼らの低劣さは、目に見えない復讐と化して、きみに対し、かすかに、またあかあかと燃える。
きみが彼らに歩み寄ると、彼らはしばしば沈黙し、そして、消え行く火から煙が去って行くように、彼らの力が彼らから去って行ったことに、きみは気づかなかったか?
そうだ、わが友よ、きみは、きみの隣人たちにとって、良心のやましさの種となる。というのは、彼らはきみに値しないからだ。それゆえ、彼らはきみを憎み、とかくきみの血を吸いたがる。
きみの隣人たちはつねに毒バエであるだろう。きみにおいて偉大であるところのもの、―そのもの自体が、彼らをいっそう有毒に、ますますハエのようなものに、せずにはおかない。
のがれよ、わが友よ、きみの孤独のなかへ、そしてかしこへ、或る荒々しい強い風の吹くところへ!ハエたたきとなることは、きみの運命ではないのだ。
筑摩書房版、吉沢伝三郎訳『ニーチェ全集10 ツァラトゥストラ』上巻P97-98
これまで、ここはニーチェの攻撃性、孤高の哲学者としての矜持がものすごく表れた箇所のように私には思えていたのでした。
しかし、ニーチェの伝記を読み、その生涯や人となりを知ってから読み返すと、以前とは違う感情が生まれてきました。
ニーチェは誰からも理解してもらえない孤独に苦しんでいたのでないか。理解されたくもないような人たちばかりの現実に苦しんでいたのではないか。この攻撃的な言葉は彼の孤独の苦しさ、寂しさの吐露ではないかとも思えるようになったのです。
実際、『ニーチェ書簡集』を読んでみるとニーチェは友人にその孤独の苦しみについて率直に述べています。

エルヴィン・ローデへ 〔ニース、一八八四年二月二二日〕
ねえ、君、どうしてこうなったのか、僕にはわからない。でも、僕が君のまえの手紙を読んだとき、とくに可愛いお子さんの写真をみたとき、君が僕の手を握りしめながら、僕を憂鬱そうにじっと見つめているような気がしたのだ。そう、憂鬱そうに、まるで君が「僕たちには、まるで別々の世界にでも生きているように、やはり共通するところはほんの少しだなんて、どうしてそんなにとが!昔はね……」とでもいおうとしているかのようにね。
ねえ、僕の好きな人たちが、みんながみんな僕にこんな風なんだ。すべてはすぎ去ったのだ、過去のことも、いたわりも。これからもお互いに会っては、話をするが、それも黙っていないためのこと、―これからもお互いに手紙を書くが、それも黙っていないためのこと。しかし眼差しが本当のことをいってしまうのさ、―(それが僕にはとてもよく聞こえるのだが)―「ニーチェ君、君はいままったくのひとりぼっちなんだぜ!」とね。
実際に僕はいまこんなところまできてしまったのだ。―
この間、僕は僕の道を前進している、もともとこれは一つの旅、ひとつの航海だ。―僕は、数年、コロンブスの都会で生活してきたが、それも理由のないことではない。―
僕の『ツァラトゥストラ』は三幕となって完成した。その一幕は、君はもっているね。後の二幕を、四週間か六週間のうちに、君に送ってあげられればと思っている。一種の未来の深淵、なにか恐ろしいもの、それがことさらツァラトゥストラの至福のなかにね。そのなかの一切は僕自身のもの、それには原型も、対照、いかなる先例もない。そのなかで生きていた者が、別の顔付きをして世界にふたたび舞い戻ってきたのだ。(中略)
失敬したね、こんなことは他人には白状しないつもりだ。でも、君はかつて、僕の言語を喜んでいるといってくれたよね、―そんなことをいってくれるのはただひとり君だけなのさ。―
ともかく僕は、すでにあらゆる詩作には反対して、きびしく自分を虐待してきたけれど、僕の言語をぎりぎりのところまで理解して、詩人でとどまってきたのだ。
ああ、君、僕は、なんと狂気じみた、黙りこくった人生を生きているのだろう!このようにひとりで、ひとりぼっちで!「子供たち」もいるでなし!
僕には好意を寄せてくれたまえ。君には誠意をもっている僕だ。
君のニーチェ
筑摩書房版、塚越敏・中島義生訳『ニーチェ全集別巻2 ニーチェ書簡集Ⅱ 詩集』P21-23
このニーチェの書簡を読んで驚かれた方も多いのではないでしょうか。
あんなに攻撃的で厳しい文章を書いていたニーチェがこんなにもフランクに自分の弱さを吐露している。
『ニーチェ書簡集』を読んでいるとニーチェの素の顔が見られます。私たちがイメージするニーチェとはまるで違う繊細な姿がそこにはあります。ニーチェに対する印象がそれこそがらっと変わるほどです。
そうなってくると、『ツァラトゥストラ』の厳しい攻撃の言葉に「誰にもわかってもらえない孤独の苦しみ」も感じてしまうようになってしまうのです。強い言葉の裏に私はそうしたニーチェの孤独を読んでしまうのでした。
ただ、ニーチェはショーペンハウアーと同じように、世間の俗悪さに対する厳しい批判を加えています。単に自分がわかってもらえないという寂しさから強い言葉を述べたわけではないのは明らかです。人々がより高い精神性を求めることなく、それこそ毒バエのように噛み合っている現実に大きな怒りを表しています。そしてそれを変えるために動くべき学者、知識人もそれに加担している現状。出版業界も、売れなければ見向きもしてくれない。
自分がわかってもらえないという苦しみもさることながら、そうした世の中への絶望、自分の無力が彼の言葉に込められているのかもしれません。ニーチェのこうした思想はショーペンハウアーの『読書について』と非常に重なるものがあります。

今回の記事では『ツァラトゥストラ』にニーチェの孤独を感じるというテーマでお話ししてきました。もちろん、そう私が感じたのは長大なこの作品の一部分からふと私が感じたものに過ぎません。
この本はニーチェの中心思想がふんだんに説かれています。それぞれの箇所で様々な思いが浮かんでくると思います。私自身、初めてこの作品を読んだ時はニーチェの孤独など思いも寄りませんでした。「孤独」よりも「孤高」を感じていたくらいです。今でも「孤高」のイメージは無くなったわけではありませんが、初めて読んだ時とは違った空気を感じるようになっています。
同じ人間でもこうなのですから、それぞれ感じ方が異なるのは当然です。様々な読みができるのもニーチェの魅力なのではないでしょうか。
以上、「『ツァラトゥストラ』にニーチェの孤独の寂しさを感じる~「神は死んだ」で有名な代表作」でした。
Amazon商品ページはこちら↓
次の記事はこちら

前の記事はこちら

ニーチェおすすめ作品、参考書一覧記事はこちらです

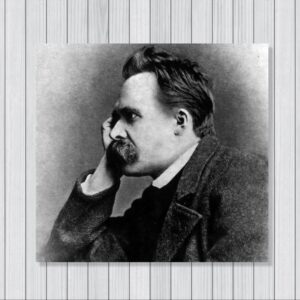
関連記事


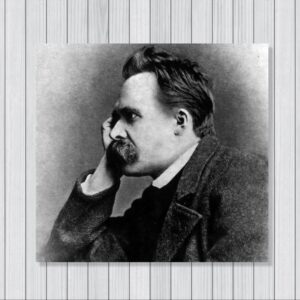







コメント