⒃沙門(シラマナ)とは~ブッダの仲間、ライバルたる自由思想家達の存在と当時のインドの独特な宗教事情について

【現地写真から見るブッダ(お釈迦様)の生涯】⒃
古代インドの新興思想家沙門(シラマナ)とは~ブッダの仲間、ライバルたる自由思想家達の存在と当時のインドの独特な宗教事情とは
前回の記事「⒂なぜ仏教がインドで急速に広まったのか~バラモン教から距離を置く大国の誕生と新興商人の勃興」ではブッダが生きた時代の時代背景をお話ししました。この記事の中でもお話ししましたが、ブッダひとりの力で仏教が広がったわけではありません。時代がブッダを求めていたという社会的な要因も強力に作用していたのです。
そしてこうした時代背景において、ブッダと同じように独自の思想や宗教を世に問うた人達がたくさんいたということも前回の記事でお話ししました。
今回の記事ではこうしたブッダのライバルたちについてお話ししていきます。ブッダの教えのどこが革新的だったのかを知るには他の教えと比べてみるのが一番です。
ただ、今回の記事でも難しい思想問題には踏み込まず、あくまでざっくりと思想の流れを追っていきますので気軽にお楽しみください。学術的に思想内容をかっちり見ていくことも大事ですがまずは歴史の大まかな流れを掴むことが先決です。
というわけで、まずはブッダ時代のインドの独特な宗教事情について見ていきましょう。
自由思想家「沙門」の登場
これまでの記事ではなるべく私自身の言葉でお話ししてきましたが、今回の記事では中村元著『インド思想史』などを引用し、そこから私自身の言葉も交えてお話ししていきたいと思います。と言いますのも、これから引用する箇所があまりにわかりやすい解説なのでぜひそのままの雰囲気を感じて頂けたらと思ったからです。
以下の引用の前半では前回の記事の復習となる解説が語られます。ブッダの教えが受け入れられる土壌が東インドで生まれ始めたその流れを中村先生はここで解説しています。そしてそこから「沙門」という新たな宗教家の誕生と高名な自由思想家六師外道の登場について見ていくことになります。では、早速始めていきましょう。
ガンジス河上流地方に定住していたアーリヤ人はその後次第に東方に進出し、その中流地方に移住したが、それとともに社会的・文化的に大きな目ざましい変動が起こった。
まずアーリヤ人と先住民族との混血が盛んに行なわれた。ここに形成された新たな民族はもはやアーリヤ人の伝統的な風習・儀礼を忠実に遵守しようとはしないで、自由にほしいままにふるまった。
かれらはヴェーダ文化を無視し、アーリヤ系の崩れた俗語(Prakrit)を使用していた。かれらの定住した地方は地味肥沃で多量の農産物を産出したために、かれらの物質的生活は豊かでまた安易となり、物資が豊富になるとともに、次第に商工業が盛んとなり、多数の小都市を成立させるに至った。
最初はこれらの小都市を中心に群小国家が多数併存し、そのうちの或るものは貴族政治あるいは共和政治を行なっていたが、それらは次第に国王の統治する大国に併合されてゆく趨勢にあった。大国の首都は繁栄し、そこには壮大な都市が建設された。
当時はコーサラ(Kosala)・マガダ(Magadha)・アヴァンティ(Avanti)・ヴァンサ(Vaṃsa)の四国が最も有力であった。これらの大国においては王権がいちじるしく伸張し、王族は人間のうちでの最上者と見なされていたが、バラモンは従前ほどの威信をもっていなかった。
また諸都市においては商工業が非常に発達し、貨幣経済の進展とともに莫大な富が蓄積され、商工業者たちは多数の組合を形成し、都市内の経済的実権を掌握していた。
『たとい奴隷であろうとも、財宝・米穀・金銀に富んでいるならば、王族もバラモンも庶民もかれに対して、先に起き、後に寝、進んでかれの用事をつとめ、かれの気に入ることを行ない、かれには快いことばを語るであろう』(MN. vol. 11, p. 85)。
旧来の階級制度は崩壊しつつあった。他方物質的生活が豊かに安楽になるにつれて、ややもすれば物質的享楽に耽り、道徳の頽廃の現象もようやく顕著になった。
こういう空気のうちに生活する人々の眼には、旧来のヴェーダの宗教は単なる迷信としか映らなかった。新しい時代の動きに応じて、唯物論者・懐疑論者・快楽論者・運命論者などが輩出して議論を闘わせた。
また他方では享楽の生活に倦怠を感じ、出家して禅定に専念する行者も多数現われた。この時代に出現した新しい思想家たちを「つとめる人(śramaṇa,samaṇa 沙門)と称する。
かれらに好都合なことには、当時は思想の自由および発表の自由が極度に容認されていた。当時の諸国王や諸都市はしばしば哲人たちの討論会を開いてかれらに自由に対論させたが、いかなる意見を述べても処罰されることはなかった。当時の異端説は原始仏教聖典の中に六十二見としてまとめられているが、その極めて古い詩句のうちにプーラナ、パクダ、ゴーサーラ、ニガンタ・ナータプッタという諸哲人の名がその各自の学説とともに言及され、またその他にアジタ、サンジャヤの二人を加えて「六師」とよぶこともあるが、これらの人々が当時の有力な思想家であった。
この時代に現われた諸教説はインド一般としては〈異端〉とみなされている。そのわけはヴェーダ聖典の権威を真正面から否定したからである。仏教もその興起した当初には、異端説の一つにほかならなかったのである。
※PC、スマホなどでも読みやすいように適宜改行しました
岩波書店、中村元『インド思想史』P39-41
この引用の中頃に出てきた「沙門(シラマナ)」。上の引用では「つとめる人」と書かれていますが、佐々木閑先生の『仏教誕生』では「努力する人」と解説されています。沙門は従来のインドの宗教家バラモンとは異なる存在として現れてきました。では彼ら沙門はバラモンと何が違うのか、そして何を努力するのか、そのことについてのより詳しい解説を中村元著『思想の自由とジャイナ教』から見ていきましょう。
シラマナは従前からの精神的指導者である「バラモン」と相対するものであり、そののちシラマナとバラモンとはインド社会における精神的指導者の二大類型となった。(中略)
では両者の差異がどこにあるかというと、社会的にはバラモンはバラモンの家に生まれた人であり、その家の一員かつ後継者としてバラモン教の儀礼を相続し、尊奉している。
これに反してシラマナは、いかなる階級の人でもシラマナとなることができる。すなわち自分個人の決心でなることができる。
バラモンは旧来の伝統的思想の保持者であったが、これに対してシラマナは当時としては自由思想家であった。
バラモンは古来祭祀をつかさどり、呪術的な性質がいちじるしいが、これに対してシラマナは哲学的な知識をめざし、あるいは神秘的な瞑想静観に耽り、解脱を得ようとして精進した。
仏教の修行者たちはもともとシラマナであった。だから東アジアの仏教では仏教僧のことを「沙門」と呼ぶのである。
※PC、スマホなどでも読みやすいように適宜改行しました
春秋社、中村元『中村元選集〔決定版〕第10巻 思想の自由とジャイナ教』P22-23
なるほど、こう見てみると、沙門(シラマナ)という存在がどのようなものだったかとてもわかりやすいですよね。
そして重要なのは、こうした新興思想家たちが弾圧されることなく自由に議論を交わすことができたという点です。上の引用にもありましたが、当時の東インドでは特にその風潮が強く、王のお膝元で公開討論までさせていたということです。これはよくよく考えてみればものすごいことですよね。
当時の主流の宗教はバラモン教ということで、その国家運営や商業も体面上はバラモン教の世界観に基づき行われていました。ですが沙門たちはそれに真正面から批判を加えます。これはもう「反体制派」と言っても過言ではありません。既存の秩序に対する明らかな挑戦です。普通は弾圧が行われてもおかしくはありません。世界の歴史上、こうした弾圧は幾度となく繰り返されてきました。
しかしその挑戦に対し体制側は弾圧の素振りも見せません。むしろそうした新思潮を歓迎するかのような姿勢でした。実際問題、これまでお話ししてきた通り東インドの王侯貴族や新興商人は既存の秩序を打破する新しい思想を求めていました。だからこそ無数の新興思想家を自由に活動させ、彼らに切磋琢磨させるように場を整えました。こうして有能なライバルたちがしのぎを削る思想の戦国時代が幕を開けることになったのです。
そしてその戦国時代を生きた一人がまさに我らがブッダなのでありました。ブッダは彼ら無数の新興思想家や宗教家の教えと文字通り戦ったのです。
また、こうした思想戦というのは戦いでありながらも相互に影響を与え合うという面もあります。
つまり、「あなたのその説は間違っているのではないか。私はこう思うのだが・・・」と相手に問う時、その時点で相手の思想内容を熟知していなければなりません。相手の思想を熟知した上で「私の思想は〇〇ではない」という自己規定が生まれてきます。極々簡潔に言うと、「あなたはこの世は快楽の世界だと言うが、私はこの世をそのようには思わない」という主張をするにはまず「この世は快楽の世界である」という定義内容をしっかり知っていなければならないということです。そしてその上で「私はそうではなく、この世は苦しみの世界である」と述べていくのです。
ぱっと聞いてみれば当たり前のことのように思えますが、実はこのことは見過ごされがちです。なぜなら、ブッダは圧倒的な存在で、自分一人で仏教を生み出したと考えられがちだからです。もちろん、ブッダは長い修行と瞑想によってこの世の真理を悟りましたが、それも無から生まれたものではありません。当時存在した様々な思想や宗教を摂取し、その思想戦の中でブッダは真理へとたどり着いたのです。ある意味、こうしたライバルたちの存在があったからこそ磨き上げられた思想でもあったのです。こうした意味でも、当時多数出現した沙門の意義は非常に大きなものであると言うことができるでしょう。
そしてこの沙門の中でも特に強い影響力を持ったのが六師外道と呼ばれる6人の思想家でした。「外道」と言いますと日本ではあまりいいイメージを持たれないかもしれませんが、ここではシンプルに「仏教の外の教え」という意味で用いられています。
次の記事ではブッダにも強い影響を与えたこの六師外道についてお話ししていきます。
彼らの思想を知ることで「ブッダは〇〇ではない」ということがよりはっきり見えてきます。何かを定義するときは、「~~は〇〇である」と言うより「~~は〇〇ではない」とした方がより正確な理解へと近づきます。
仮に「人間とは道具を使う動物である」としましょう。ですがこれでは不十分です。なぜなら人間の他にも道具を使う動物が存在するからです。それに対し「人間はヘビではない」としたらいかがでしょうか。これは妥当であると言えるでしょう。そして同じように「人間は鳥ではない」「人間はエラ呼吸ではない」「人間は〇〇ではない」・・・と無限に続き、その集積が人間というものの定義になっていきます。というわけで「ブッダは〇〇である」というより「ブッダは〇〇ではない」ということを見ていった方がよりブッダを知れるのです。
ただ、もしかすると「そんなことを知って何になるのだろう」と疑問に思われた方もおられるかもしれません。
ですが、実はこれこそ仏教の根本思想たる「縁起の思想」や「空」とも繋がってくる考え方なのです。「あるのでもなく、ないのでもない」というわかるようでわかりにくい仏教思想ではありますが、まさにここで大切にされているのは「~~は〇〇ではない」という考え方です。私達は「~~は〇〇である」と定義した途端、その定義に囚われ、思考の幅を狭めてしまいます。そうではなく、枠に囚われない大きな世界認識を仏教では求めていきます。
こうした意味でも「~~は〇〇ではない」という思考方法は非常に重要です。
ブッダの生涯や時代背景とは少し話が逸れてしまいましたが、私がここでブッダのライバルたちを取り上げる理由が伝わったのではないでしょうか。
では、次の記事ではそのブッダの最大のライバルたち、六師外道について見ていきます。
次の記事はこちら

※この連載で直接参考にしたのは主に、
中村元『ゴータマ・ブッダ』
梶山雄一、小林信彦、立川武蔵、御牧克己訳『完訳 ブッダチャリタ』
平川彰『ブッダの生涯 『仏所行讃』を読む』
という参考書になります。
※以下、この旅行記で参考にしたインド・スリランカの参考書をまとめた記事になります。ぜひご参照ください。
〇「インドの歴史・宗教・文化について知るのにおすすめの参考書一覧」
〇「インド仏教をもっと知りたい方へのおすすめ本一覧」
〇「仏教国スリランカを知るためのおすすめ本一覧」
前の記事はこちら

【現地写真から見るブッダの生涯】目次ページはこちら

【インド・スリランカ仏跡紀行】の目次・おすすめ記事一覧ページはこちら
関連記事



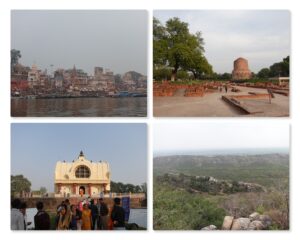











コメント