ゲーテ『イタリア紀行』あらすじと感想~19世紀ヨーロッパ人に絶大な影響を与えた傑作旅行記
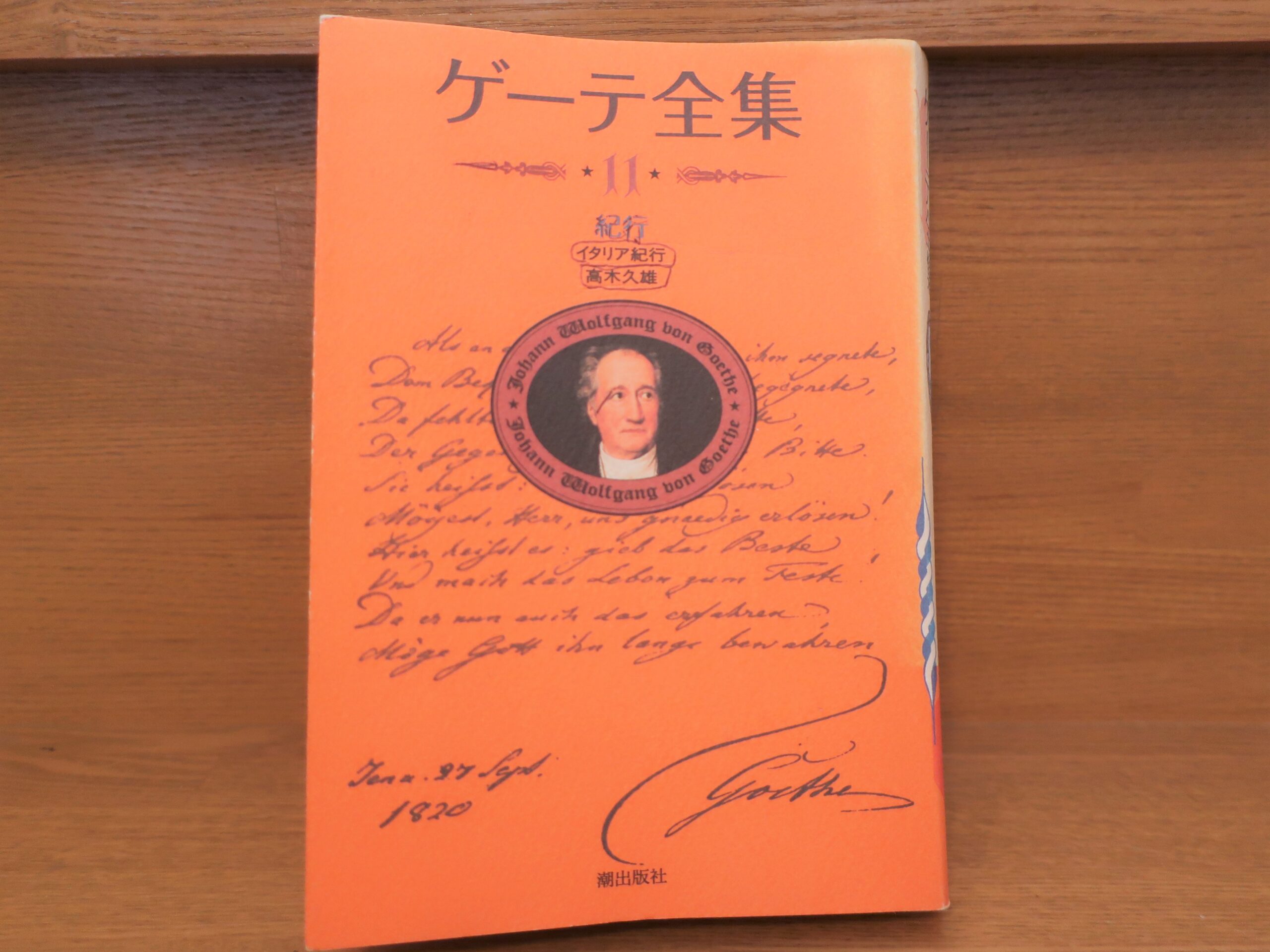
ゲーテ『イタリア紀行』~19世紀ヨーロッパ人に絶大な影響を与えたゲーテのイタリア旅行記!
今回ご紹介するのは2003年に潮出版社より発行された『ゲーテ全集 11 新装普及版』です。

当ブログでもこれまでゲーテについては紹介してきましたが、今回ご紹介する『イタリア紀行』もヨーロッパ人の知識人、芸術家に多大な影響を与えた作品となっています。ゲーテといえば『ファウスト』や『ウェルテル』が有名ですが、この『イタリア紀行』もそれらに劣らず面白い作品です。
では、早速この作品について見ていきましょう。
一七七五年ゲーテがカール・アウグスト公に招かれてヴァイマルに移住してからイタリア旅行までの十年間の生活は、政治家、官吏として多忙をきわめた。彼は顧問官となり、貴族に列せられ、大臣にまでなった。しかし彼の詩的活動の面では、最も沈滞した時期であり、そのうえシャルロッテ・フォン・シュタイン夫人との長期にわたる愛の悩みが加わり、ゲーテはあらゆる方面で行きづまりを感じていた。一方、イタリアはゲーテにとって早くから憧憬の国であり、すでに三度までも足を踏み入れかけながら、とって返した国であり、ミニョンの歌を通じて、あらゆるあこがれと、感性的な美と自由とのシンボルとなっていた国である。―このような情況のなかで敢行されたイタリア旅行は、現在の行きづまりを打開し、人間としても詩人としても新しく生まれ変ろうとする画動と結びつくこととなった。
『イタリア紀行』は当時の日記、書簡等を資料とし、自伝『詩と真実』のつづきとして後になって編纂されたものであるが、その内容は、きわめて多方面な事柄を、きわめて多角的な視野から、しかもパノラマ風に鳥瞰しているので、要約することは困難であるが、ゲーテの自己の再発見ならびに自己形成への欲求が、あらゆる記述の基底音として鳴り響いていることは確実で、その意味でこの作品は、いわゆる「イタリア案内記」とは明確に一線を画している。ヴァイマルの宮廷の狭隘さ、役人の仕事の単調さ、進歩も発展もない住民たち、シャルロッテ夫人との関係の行きづまりといったふうに、いたるところで限界にぶつかっていたゲーテが、まったく新たな外界、つまり新しい自然に接し、新たな人間関係を経験し、未知の社会と文化を摂取し、その浸透によって固有の生活感情の深化、拡大、高揚をはかったのである。その点からすれば、ゲーテ的本性の持ち主でなければ、この旅行記は案内書としては役に立たないといっても過言ではなかろう。
潮出版社、高木久雄訳『ゲーテ全集 11 新装普及版』 P522
前回の記事で紹介した『ゲーテ その生涯と作品』でも次のように書かれていました。

ゲーテの生涯において、イタリア旅行ほど決定的な意味をもった事件はない。この旅行はゲーテを新しい人間に変えた。早世を考えていたころの、いやそれどころか、それまでの生活を続けていくよりはむしろ死んだほうがましだと考えていたころのあの憂鬱は、輝かしい明朗さと人生の喜びの前にあとかたもなく消えていた。社交においてすら深刻な思索から逃れられなかった寡黙な男は、子どものように嬉々としていた。ヴェネチアとナポリの民衆劇場でゲーテの笑い声を聞き、ガルダ湖畔でイチジクを、あるいはヴィチェンツァの市場でブドウを平らげるゲーテを眺めるのは、一服の清涼剤である。ゲーテの五感すべてがふたたび生気を取り戻した。
岩波書店、アルベルト・ビルショフスキ、『ゲーテ その生涯と作品』P463
ゲーテの人生を決定的に転換させるほどの出来事がこのイタリア紀行だったのです。
ヨーロッパを代表する大人物に決定的な影響を与えたイタリアへの旅。ヨーロッパ人は元々イタリアへの憧れを持っていましたが、このゲーテのイタリア紀行によってその熱はさらに高まることになります。
以前当ブログでも紹介したドイツの偉大な作曲家メンデルスゾーン(1809-1847)もその一人です。

彼もゲーテの『イタリア紀行』を読み、実際にイタリアを訪れています。

メンデルスゾーンのイタリア旅行とゲーテについて星野宏美著『メンデルスゾーンのスコットランド交響曲』では次のように語られています。
文学者の立場からメンデルスゾーンのイタリア旅行中の手紙を分析したミラーの論考は示唆に富む。彼の論述を要約しよう。メンデルスゾーンは、イタリアからの手紙の中で「私」をいわば小説中の人物に仕立てつつ、自己の体験を物語るような書き方をしている。とくに、家族あての手紙にはその傾向が強い。(中略)
もう一方で、メンデルスゾーンのイタリアからの手紙には、ゲーテJohann Wolfgang von Goethe (1749~ 1832)の圧倒的な精神的影響が読みとれる。それは文体ではなく、手紙の全体的な雰囲気、考え方と言葉遣いに感じられる。ゲーテの『イタリア紀行』(1816年出版)を直接に引用している部分はもちろん、そうでなくとも、旅行中の体験を報告する際に、メンデルスゾーンは意識的にも、無意識的にもそれを指標としているのである。つまり、彼はイタリアの風景や遺跡、建築や芸術品などを現実に目にする前に、既にゲーテを通して対象についての知識を得、さらには解釈も与えられていた。「彼はイタリア、とくにローマとナポリに滞在中、実はゲーテのイタリアに生きていた」とも言えるのだ。これは。この時期にイタリアに向かったすべての旅行者に多かれ少なかれ共通する傾向であった。
音楽之友社、星野宏美『メンデルスゾーンのスコットランド』P65-6
このメンデルスゾーンのように、18世紀末、19世紀の文化人に与えたゲーテの影響は凄まじいものがありました。
上の解説にもありましたように、ゲーテの『イタリア紀行』は単なる「イタリアの旅ガイド」ではありません。日々の生活に行き詰っていたゲーテが憧れの国イタリアを訪ねたことでその精神が復活し、はるか彼方まで飛躍していったその過程を目の当たりにすることになります。旅行ガイドというよりは非常に精神的な書物になります。
そしてこれがとにかく面白い!ゲーテの意外な素顔も知ることができてとても興味深いです。
ここで紹介したい箇所が山ほどあるのですが、今回はその中でも特に印象に残っている箇所をいくつかここで紹介していきたいと思います。
古代ローマの遺跡を見たゲーテ~この書の特徴を端的に示すゲーテの述懐ーヴェローナにて、1786年9月16日
円形劇場は、古代の重要記念物のうち、ぼくの見る最初のものであり、それはじつによく保存されている!中に入ったとき、それに上部の縁を歩きまわったときはなおさらに、何か偉大なものを見ているような、それでいてじつは何も見ていないような、妙な気がした。事実また、それはからっぽのところを見るべきものではなく、近年ヨーゼフニ世やピウス六世のために催し事が取り行われたときのように、人間がいっぱい詰まっているところを見るべきものである。さすがに群衆を眼の前にするのに慣れていた皇帝も、これにはびっくりされたそうである。しかしこの劇場が全面的に効果を発揮できたのは、最古の時代だけであった。当時は民衆が現在より以上に民衆らしくあったからだ。元来このような円形劇場は、民衆をして自分たちもたいしたものだという気を起こさせ、自分たちの姿を見て自らを楽しませるように作られている。
平らな地面の上で何か見物に値することが起こってみなが集まってくると、いちばん後方にいる連中はありとあらゆる方法で最前列の連中より高くなろうとする。べンチに乗ったり、樽をころがしてきたり、馬車で乗りつけたり、板をあちこちに架けたり、近くの丘を占領したりして、たちまちのうちに噴火口のような形になる。
見世物がたびたび同じ場所で行われると、料金を払える人びとのためには簡単な棧敷が設けられ、あとの群衆は好き勝手に手段を考え出す。このような一般的要求を満足させるのが、ここでは建築家の使命なのだ。建築家はこのような噴火口式のものを人工的に造りあげる。それもできるかぎり簡素に、民衆自身がその装飾となるようなぐあいにする。民衆がそのようにして集まった自らを眺めるとき、彼らは自らにたいして驚嘆せずにはいられなかった。それは彼らが、いつもは自分たちが右往左往し、秩序もそして特別の規律もなしに雑然としているのを見慣れているのに、この頭数も多ければ心も各自ばらばらであちこちと行き迷う動物が、合して一つの高貴な身体となり、一つの統一体にまで定められ、一つの集団にまで結ばれ固められ、一つの精神に生きる一つの形姿となった自らを認めるからである。楕円形の単純な形は誰の眼にもきわめて快く感じられ、一人一人の頭は、全体がいかに途方もなく大きいかを計る尺度として役立つ。いま劇場がからっぽであるのを見ると、尺度がないので、劇場が大きいのか小さいのか見当がつかない。
潮出版社、高木久雄訳『ゲーテ全集 11 新装普及版』 P 31-32
ゲーテがイタリアで初めて古代ローマ時代の円形劇場を見た時の感想がこちらです。
ゲーテは見たものを単に記録するだけにとどまりません。
円形劇場の遺跡に、かつての人々の熱狂を想像し、さらには設計者の目でこの劇場を眺めます。
ゲーテの視野の広さ、感受性の豊かさがこの箇所から感じられます。
単に名所を物見遊山で巡るのではなく、ゲーテはそこから積極的に思索していきます。
この思索の過程が『イタリア紀行』の醍醐味です。こうしたゲーテの旅のスタイルに多くのヨーロッパ人が憧れ、この書を手にイタリアへ旅したのでありました。

ビーバー共和国、ヴェネツィアへ~ゲーテのユーモア
こうして一七八六年九月二十八日の夕方、わが国の時刻にすれば五時に、ブレンタ河から潟へと乗り入れつつ、初めてヴェネツィアをこの眼で眺め、それから間もなくこの不思議な島の町、この海狸共和国に足をふみ入れ、そこを見物することになるとは、やはり運命の書のぼくの頁にすでに書きしるされてあったことなのだ。こうしてまたさいわいにもヴェネツィアはぼくにとって、たんなる言葉、空言の不倶戴天の敵であるぼくをいくたびか不安におとしいれた、うつろな名前ではなくなったのである。(中略)
ぼくは「イギリス女王」という旅館にいい宿を取っている。サン・マルコ広場から遠くないところで、これがこの宿の一番のとりえである。部屋の窓は高い家並のあいだにある狭い運河に面し、窓のすぐ下には弓なりの橋がかかっていて、その向うには狭い賑やかな小路がある。こんなところに宿泊しているのだが、ドイツ行きの小包ができあがるまで、また町の見物にあきてしまうまで、しばらくここに滞在することになるだろう。これまでいくたびかあれほどまでに渇望していた孤独を、いまこそほんとうに味わうことができる。なぜならば、だれひとり知る人もない雑沓のなかを押しわけて行くときほどに、しみじみと孤独を覚えることはないからだ。ヴェネツィアでぼくを知っている人間はおそらくたった一人だろうし、その人にも、すぐには出会うことはないだろう。
潮出版社、高木久雄訳『ゲーテ全集 11 新装普及版』 P 51

ゲーテは干潟に大量の杭を打って作られたこの街をビーバー共和国とユーモア込めて呼んでいます。
言葉の響きもいいですよね。ゲーテのユーモアや言葉選びの抜群のセンスを感じます。
そして上の言葉の後半の「孤独」について語られた箇所も味わい深いですよね。
「雑踏の中でこそ孤独を感じる」というゲーテの言葉。
それまで役人として息の詰まる生活をしていたゲーテの心からの実感がここに表れています。
ヴェネツィアの干潟でカニを見て喜ぶゲーテ
今夕サン・マルコの塔へ登った。先日は満潮時における潟の壮観を眺めたので、干潮時におけるへりくだった姿も見たいと思ったからだ。潟についての正しい概念を得たいと思うときは、この両方の姿を結び合わせることが必要である。以前は水面のあった所に、いまはいたるところ陸地が現われるのを見るのは奇妙な感じである。島はもはや島ではなく、美しい運河によって縦断されている大きな灰緑色の沼沢地のところどころが、いくぶん高くなっているにすぎない。沼地の部分には水生植物が生えていて、干潮と満潮とがたえずそれをむしったり掘り返したりして、植物を少しもそっとしておかないにもせよ、植物の生長によってその土地は徐々に高くなっていくにちがいない。
話をもう一度、海のことに返そう。今日ぼくはここで海蝸牛、陣笠貝、小蟹の暮しぶりを見て心から楽しんだ。生物とはなんと貴い、すばらしいものだろう!なんとよくその状況に適応し、なんと真実に存在していることであろう!自然についてのわずかなぼくの研究にもどんなに役立ち、それを続けることはいかに喜ばしいことか!しかもそれは報告し得ることなのだから、ただ感嘆詞をならべて友人たちをいらいらさせることはすまい。(中略)
小さな食用蝸牛、殻が一つの陣笠貝、その他の動いている生きもの、ことに小蟹など、海中の棲息者が潮流にのってやってくる。しかしこれらの動物はなめらかな防波堤に付着するかしないうちに、もう海は押しよせたときときと同じように一進一退しながらふたたび引きはじめる。初めこれらの動物の群は、どういうことになるのか見当もつかず、塩分を含んだ海水が戻ってくるのをいつも期待している。ところが潮は戻ってこないし、太陽は照りつけてたちまち乾燥させる。そこでいまや退却が開始される。この機会に小蟹は獲物を探す。円い体と二つの長い鋏から成るこの生き物の身振りほどに奇妙で滑稽なものはほかにない。つまりそれ以外の蜘蛛のような脚は目につかないのだ。細長い腕を竹馬のようにつかって悠々と歩いている。そして陣笠貝が甲殻に身を隠して移動を開始するやいなや、突進していって鋏を甲殻と地面との狭い隙間に突っこみ、屋根をひっくり返して、中のかきをごちそうになろうとする。陣笠貝のほうはゆっくりとその道を進むのだが、敵の接近に気づくと直ちにしっかりと石に吸いつく。すると蟹は小さな屋根のまわりをめぐって奇妙な身振りをするのだが、それがいかにも愛嬌があって、お猿さんのようだ。しかし蟹にはこの軟体の小動物がもっている強力な筋肉を打ち負かすだけの力はない。この獲物はあきらめ、別の歩いているやつをめがけて急ぐ。そこで前の貝はゆっくりと進行をつづける。どの小蟹もその目的を達したのをぼくは見なかった。この蟹の群がニつの斜面とその間の階段をそっと這いおりてゆく、その退却の様子を幾時間も観察していたのだが。
潮出版社、高木久雄訳『ゲーテ全集 11 新装普及版』 P 75-76
ドイツの内陸で過ごしていたゲーテにとって、南の暖かな海がどれだけ嬉しいものであったかがここから伺えます。
干潟にいるカニの描写はさすが大巨匠。よくぞここまで生き生きとカニの姿を描写しているなと驚くばかりです。
幸せそうに何時間もカニを見ているゲーテ。偉大な文学者の意外な一面を見れたような気がします。
憧れのローマに着いたゲーテ
ローマに着いたゲーテはそれまで自分がどれほどローマに憧れていたかを次のように表現しています。
そうだ、この数年間それは一種の病気のようなものとなり、それを癒すことのできるのは、この地を実際に眺め、この地に身をおくこと以外にはなかった。いまでこそ白状もできるのだが、ついには一冊のラテン語の書も、一枚のイタリアの風景画さえも、もはやこれを眺めるに堪えなくなった。この国を見たいという欲望は、成熟の度を越していた。
潮出版社、高木久雄訳『ゲーテ全集 11 新装普及版』 P 102-103
ゲーテのローマへの憧れ度合いはかなり煮詰まっていました。その憧れの地ローマにゲーテはついに到着したのです。この『イタリア紀行』ではそんなゲーテの喜びの日々を知ることができます。ゲーテの豊かな感性をもって綴られるローマ滞在は非常に刺激的です。この記事では紹介できませんが、バチカンの圧倒的な芸術を目にしたゲーテの言葉はぜひ読んで頂きたい箇所となっています。


「偉大なものはうつろいやすいという感想がおさえがたく心にせまってきても、ぼくたちは意気消沈する必要はない。」~ゲーテの歴史観、人生観
偉大なものはうつろいやすいという感想がおさえがたく心にせまってきても、ぼくたちは意気消沈する必要はない。むしろ、過ぎ去ったものが偉大であったことがわかれば、ぼくらはそれに鼓舞されて、自分も何か意義ある仕事をしなくてはと思うようになる。そしてそれがたとえまた廃墟と化したとしても、将来ぼくたちの後継者をして、ぼくらの祖先がそのためにけっして骨身をおしまなかった高貴な活動へと奮起させることになるのだ。
潮出版社、高木久雄訳『ゲーテ全集 11 新装普及版』 P 379-380
これはゲーテの第二次ローマ滞在中、サンピエトロ大聖堂やバチカンの芸術を見た後に語られた言葉です。
私たち日本人にとっても諸行無常という考え方はとても身近ですよね。どんなに権勢を誇っていてもいつかは衰え、時の流れに消えていく定め・・・
もしあらゆることがそうであるならば、なぜ今大きな苦労や努力をして大変な事業を起こさなければならないのか。偉大なる文化や芸術、建築を築こうとも、いずれ消えてしまうなら何の意味があろうか。
何かを極めようとする人間が必ずぶつかるであろうこの問題にゲーテも直面していました。
しかしゲーテはローマで上のような答えにたどり着くのです。
たとえ廃墟と化してもそれは決して無意味ではないとゲーテは断言します。
こうしたゲーテの信念が吐露されるのもこの旅行記の魅力です。バチカンの芸術について詳しく語られた後にこの言葉は出てきます。そうした流れの後でここを読むとさらにその味わいは増します。ですのでぜひ、この『イタリア紀行』を読み通してこの箇所を味わって頂けたらなと思います。私はこの箇所を読んで鳥肌が立ちました。ゲーテ、格好良すぎます。ヨーロッパ人がこの旅行記に憧れたのももっともだと感じました。
おわりに
ゲーテの『イタリア紀行』はヨーロッパの文化人に絶大な影響を与えました。
この作品が「旅行記もの」の傑作と言えることは間違いないです。
そして『イタリア紀行』を読んで感じたのは、やはりゲーテは詩人であるということ。
あまりに豊かで繊細な感受性。
彼は目に見たもの、聞こえてくるもの、感じられるもの全てに開かれています。普通の人なら気づきもしないようなことに熱心に感じ入り、美しくも情感たっぷりな言葉でそれを歌い上げます。
詩人の心、感受性豊かな心というのはこういうことなのだなということを感じさせられます。
この旅行記はある意味芸術家の心構えを知ることができる書と言えるかもしれません。目の前にある世界をどのように感じていくのか、その奥底に潜む秘密にいかに分け入っていくのか、その過程を記した書物がこの『イタリア紀行』なのではないかと思います。
ゲーテの『イタリア紀行』に憧れたヨーロッパ人が、彼のように思索しようと旅に出たのも頷けます。ヨーロッパ最大の文学者、詩人であるゲーテの影響力の源泉をこの作品で感じられたように思います。
また、ゲーテ以前においてもグランドツアーと呼ばれる貴族の教養旅行は確かに存在していました。

グランドツアーはイタリアの古典文学や芸術、歴史を学び教養を高めることを目的とされたものでした。そしてそれだけではなくそこへ至るまでの道中でフランス、ドイツ、オーストリアなども通り、その国の政情も学んだり、政治的、商業的なつながりを得ることも考えられていました。
ゲーテの旅も、ある意味こうしたグランドツアーのひとつと考えることもできます。
ですが、ゲーテはこのグランドツアーの教養的な面を決定的に押し進めたのではないかと思います。
18世紀末、19世紀以降においてのイタリア旅行はもはやゲーテと切り離すことはできなくなりました。それほどゲーテの『イタリア紀行』はヨーロッパに影響を与えたのでした。
この作品はゲーテの感受性の秘密も知れるおすすめな作品です。また、上でも紹介しましたがカニを見て喜ぶゲーテという意外な素顔も観ることができます。人間ゲーテを知れるのもこの作品の嬉しいところです。
非常におすすめな作品です。
以上、「ゲーテ『イタリア紀行』~19世紀ヨーロッパ人に絶大な影響を与えた傑作旅行記」でした。
Amazon商品ページはこちら↓
次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事


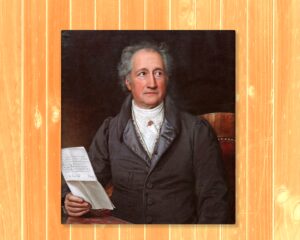












コメント