目次
クラクフ旧市街のシンボル、聖マリア教会~聖母マリア信仰と一神教 僧侶上田隆弘の世界一周記-ポーランド編②
先の記事でも少しだけご紹介したが、旧市街の中央広場にはこの街のシンボルたる聖マリア教会がある。
この教会は1222年に建てられ、聖母マリアの祭壇が中央に飾られていることで有名だ。
建物の外にあるチケット売り場で入場券を購入する。
およそ300円ほどの値段だ。ポーランドは物価が安いので観光するのにも非常に助かる。
さて、聖マリア教会に入場してみよう。
外から見ても圧倒的な大きさだったが、中の様子は一体どのようになっているのだろうか。

そこには色鮮やかで豪華な世界が広がっていた。
中央の祭壇は残念ながら修復中であったが、それを取り囲む装飾の美しさも圧倒的だ。
一つ一つに恐ろしく手をかけているのがわかる。
そして特徴的なのは天井の高さだ。
首を限界まで反らさないと天井まで見えてこない。
壁面はステンドグラスで装飾され、外からの光がガラスの色を通して差し込んでくる。
天井は尖ったアーチ状をした形になっている。
天井に施された絵も精緻を極めている。

視線を横に向けると、大きな柱に沿って祭壇が供えられている。
目線と同じ高さにこれだけの装飾があると、なかなかの迫力だ。
エルサレムの時と違ってそれほど多くの観光客がいるわけではない。
そのため、落ち着いて見学することができた。

先ほどよりも後方からの眺め。
上の方にはイエスの十字架の像が飾られている。
そう。この教会は聖母マリアを崇拝する教会。
メインの祭壇に祀られているのは、イエスではなくイエスの母、マリアなのだ。
残念ながら修復中で中央祭壇のマリア像を目にすることが出来なかったが、イエスの十字架像との位置関係は非常に興味深い。
イエスが手前に来て、その奥の主祭壇が聖母マリア。
イエスを通してマリアを見るという構図。
まるで「イエスは聖母マリアのおかげでこの世に生まれることができた。マリアこそ私達の救いだ」と言っているかのようだ。
キリスト教は一神教だ。
よって、他の神様は祈ってはならない。
で、あるにもかかわらず神の子イエスよりも聖母マリアの方が人々から慕われるということがキリスト教圏では往々にして見られることなのだ。
ぼくにとってこれは非常に興味深い。
一神教であるはずのキリスト教徒がイエス以外の人にお祈りをしている。
また、聖母マリアだけでなく、「聖人」という形でも多くの人が崇拝されている。
最近の例だと、マザーテレサもその聖人の列に加えられている。
他にも、スペインではイエスの直弟子聖ヤコブが国の守護聖人として崇められている。それが世界的にも有名なサンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼のきっかけとなったほどだ。
あわせて読みたい
カトリック巡礼の聖地、サンティアゴ・デ・コンポステーラに到着 スペイン編⑭
サンティアゴ・デ・コンポステーラはスペイン北西部の大西洋岸近くの街。
ここはカトリックの巡礼地として有名で、バチカンとエルサレムをはじめとするカトリック三大聖地の一つに数えられている由緒ある聖地として知られています。
旧市街中心部を歩いてみるとラッパのような音色の伝統音楽が聞こえてきます。
この街はまるでお祭りのような雰囲気が漂っています。
この記事ではそんな聖地を散策していきます。
唯一なる神の他に、それぞれ得意分野を持った聖人がいる。
国を守る聖人、病気を治す聖人、学問の聖人、その他諸々の聖人が地方ごとに無数に存在する。
そして人々は自分の願いに合わせた聖人にお祈りするのだ。
ん?これはどこかで聞いたような話ではないか・・・?
そう。日本のお寺や神社の祈願と原理は一緒なのだ。
ぼくはこのことが何より興味深い。
一神教というものの定義が壊れかねないこのあり方でもなお、やはり神を信じる一神教であるという懐の広い柔軟なあり方。
もちろんカトリックとプロテスタントによって解釈は異なるであろうし、同じカトリックやプロテスタント内でも考え方は分かれるだろう。
だがいずれにせよ、聖母マリア信仰が世界中で重要な位置を占めているのは事実に他ならない。
なぜ聖母マリアがそれほどまでに信仰を集めたのか。
ぼくはまだ勉強不足なので正確なところはわからない。
ただ、イメージとして、威厳ある父親像である神、それに対して全てを受け止める慈悲深き母としてのマリア。
苦しみにあえぐ人々はどちらに慰めを求めるだろうかというのは、一つの鍵になるのではないだろうか。
聖母マリアの信仰は今後のテーマの一つとして日本に持ち帰ろうと思う。
続く
※2021年9月18日追記
本日更新したヨハネ・パウロ二世『救い主の母』カトリックにおけるマリア信仰の意義を解説した1冊の記事の中で聖母マリアの意義についてお話ししましたので興味にある方はぜひご参照ください。
あわせて読みたい
ヨハネ・パウロ二世『救い主の母』あらすじと感想~カトリックにおける聖母マリアの意義を解説した1冊
この本は文庫本サイズで150頁弱の非常にコンパクトな作品ですが、その中でヨハネ・パウロ2世が丁寧に聖母マリアの意義について語ってくれます。マリア信仰を考える上で非常にわかりやすい解説で、とても参考になりました。この本もおすすめです。
次の記事はこちら
あわせて読みたい
クラクフ聖マリア教会の高層建築と鳴り響くラッパの音 ポーランド編③
前回の記事に引き続き、クラクフ旧市街の聖マリア教会について、もう少し考えていきましょう。
改めて紹介しますが、この教会は1222年に建てられ、塔の高さは82mにもなる堂々たる建築です。
今回の記事ではこの教会にまつわるエピソードをご紹介していきます。
前の記事はこちら
あわせて読みたい
ポーランド入国とクラクフ散策~旧市街とユダヤ人地区の街並み ポーランド編①
クラクフはポーランド南部の都市で、聖マリア教会を中心とする旧市街はコンパクトにまとまって非常に観光しやすい街として知られています。
クラクフは11世紀中ごろから16世紀末までポーランド王国の首都として栄え、プラハやウィーンと並ぶ文化の中心だった街。
そして、ポーランドの首都ワルシャワが東京に例えられるのに対して、このクラクフは京都に例えられます。
第二次世界大戦ではワルシャワがナチスによって壊滅させられたのに対し、クラクフは奇跡的に破壊を免れました。そのため中世からの古い町並みが現在も残っています。
関連記事
あわせて読みたい
ポーランド旅行記おすすめ記事一覧~アウシュヴィッツを訪ねて【僧侶上田隆弘の世界一周記】
アウシュヴィッツは、私の中で「宗教とは何か、人間とは何か」という問いを考える上で絶対に行ってみたいと思っていた場所でした。
私はユダヤ人が建国したイスラエルという国を見た直後にこの国を訪れることになりました。これはアウシュヴィッツを考える上で非常に重要な意味があったと私は感じています。
ポーランド編ではそんな私が目で見て、全身で感じたアウシュビッツを僧侶ならではの視点でお話ししていきます。
あわせて読みたい
死の収容所アウシュヴィッツを訪れる①~ホロコーストから学ぶこと ポーランド編④
2019年4月14日。
私はポーランド最大の目的地、アウシュヴィッツに向かいました。
幸い、朝から天候にも恵まれ、前日までの凍てつくような寒さも少し和らいだようだ。
クラクフのバスターミナルからバスでおよそ1時間半。
アウシュヴィッツ博物館前で降車します。
この記事では私のアウシュヴィッツでの体験をお話しします。
あわせて読みたい
死の収容所アウシュヴィッツを訪れる②~ナチスとユダヤ人の処遇 ポーランド編⑤
ナチスがユダヤ人をどのように扱ったのかというのは博物館の展示でも大きなテーマとして取り上げられています。
「人間の本質が極めて特異な形で現れたのがホロコースト。」
エルサレムの「ヤド・ヴァシェム」でガイドさんが言っていた言葉です。
だからこそ、ここアウシュヴィッツで学んだことを「ここで悲惨なことがあったのだ」で終わらせてはなりません。
あわせて読みたい
アウシュヴィッツのガス室で感じた恐怖~「普通であること」の恐さに戦慄する ポーランド編⑥
アウシュヴィッツに実際に行って、私はどんな思いを抱くのだろうか。
旅の前にはそんなことをよく考えていた。
では、実際私はここに来て何を感じたのか?
それは「何も感じないこと」の恐怖であった。アウシュヴィッツは「普通の場所」だった。だがそのことに私は戦慄を感じたのでした
あわせて読みたい
アウシュヴィッツと『歎異抄』~親鸞の言葉に聴く ポーランド編⑦
アウシュヴィッツはあまりに強烈な体験だった・・・
しばらくは何もする気が起きませんでした。
いや、何もできなかったと言う方が正しいのかもしれません。
ですが、そんな空っぽになってしまったかのような頭の中に、ふとよぎるものがありました。
「さるべき業縁のもよほさば、いかなるふるまいもするべし」
そう。以前エルサレムのホロコースト記念館、ヤド・ヴァシェムの記事でもご紹介した『歎異抄』の言葉でした。
あわせて読みたい
ユダヤ教の聖地~嘆きの壁に触れる イスラエル編③
オリーブ山からエルサレムの街を眺めた私は、いよいよ城壁内の旧市街へと足を踏み入れます。
そして私が最初に訪れたのはユダヤ教の聖地、嘆きの壁。
私はここで不思議な感覚を感じたのでありました。
あわせて読みたい
ユダヤ教の安息日、エルサレムの嘆きの壁の祈りに心が震えた! イスラエル編⑨
ユダヤ教徒にとって、毎週金曜夕方から土曜日の夕方までは安息日あるいはシャバットと呼ばれる特別な1日。
そしてシャバットの夜、すなわち金曜の夜は嘆きの壁でのお祈りはピークを迎えます。
というわけで、私もその夜、嘆きの壁に行ってみることにしたのでした。
そしてそこで私はその祈りに度肝を抜かれたのでありました。この記事ではその時の体験をお話ししています。
あわせて読みたい
美しきモルダウとカレル橋~橋に並ぶ聖人たちのルーツとは チェコ編⑨
ヴルタヴァ川(モルダウ)の美しさや橋そのものの美しさがフォーカスされがちなカレル橋でありますが、あえてそこに並ぶ聖人達に目を向けてこの記事ではお話ししていきます。
カレル橋は本当に美しい。そしてそこから見る眺めも素晴らしい。
ですが、それだけではなく、プラハにはたくさんの思想的な思惑が至る所に秘められています。
カレル橋にも実はそのようなエピソードがあるということを知り、私はますますこの景色を好きになるのでありました。





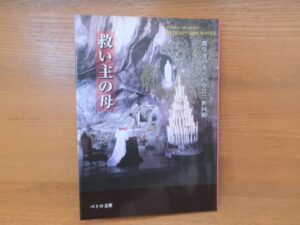












コメント