矢羽々崇『「歓喜に寄せて」の物語〔改訂版〕』あらすじと感想~年末恒例のベートーヴェンの『第九』の秘密に迫る1冊!

矢羽々崇『「歓喜に寄せて」の物語ーシラーとベートーヴェンの『第九』』概要と感想~年末恒例の名曲の秘密に迫る1冊!
今回ご紹介するのは2019年に現代書館より発行された矢羽々崇著『「歓喜に寄せて」の物語〔改訂版〕ーシラーとベートーヴェンの『第九』』です。
早速この本について見ていきましょう。
「ベートーヴェンの第九」として誰もが知っている名曲「歓喜に寄せて」。映画「バルトの楽園」で描かれたように大正時代から日本でもおなじみのこの名曲には秘められた歴史があった。ドイツ文学史・近代史の流れの中で名曲の歴史に新たな光を当てる。
Amazon商品紹介ページより
品切れが続いていたロングセラー待望の増補改訂版です!
年末の風物詩としても有名な「ベートーヴェンの第九」。

この本ではそんなベートーヴェンの『第九』とシラーの「歓喜に寄せて」の関係についてかなり詳しく見ていくことになります。
著者はこの本について次のように述べています。少し長くなりますがこの本についてわかりやすく説かれている箇所ですのでじっくり見ていきます。
べートーヴェンの『第九』は、式典となると好んで演奏される。一ハニ四年の初演以来、世界中で幾度となく演奏されている。そして日本では、年末の『第九』は、恒例行事ともなっている。その正確な回数や聴衆の数は把握できないほどだ。「日本の第九」は、世界的に見ても不思議な行事なのだ。
これほどまでにポピュラーな曲なのだが、この交響曲は発表当時から批判も多かった。それは曲の長さに関してであり、器楽曲と声楽の組み合わせに関してだったり、詩の作者フリードリヒ・シラー(一七五九~一八〇五年)に対する冒漬だと感じた人もいた。各人がなんらかの「ちぐはぐさ」を感じたのだ。
祝祭的な空間や雰囲気で演奏される高揚感が、ベートーヴェンの『第九』の特徴の一つだとすれば、実は合唱のもとにある詩にもその高揚感ははっきりと読みとることができる。それはフリードリヒ・シラーがフランス革命直前の一七ハ六年に発表した「歓喜に寄せて」である。しかし、シラーの詩に対しても、熱狂的な賛辞がある一方で、具体的に何が言いたいのか分からない、まとまりがない、という批判も多かった。後のシラーもこの詩を批判的に見ている。
このように、シラーの詩「歓喜に寄せて」にも、べートーヴェンの『第九』にも、そして壁崩壊の際のコンサートにしても、波立つような高揚感がある一方で、その根底には何かちぐはぐなものが隠されている。
本書の一つの目的は、この高揚感と隠された「ちぐはぐさ」を立ち止まって考えてみることである。なぜ日本で『第九』がこれほどまで人気があるのか。なぜここまで評価がはっきりと二分されるのか。バーンスタインらはべートーヴェンの何に共感したのか。べートーヴェンはシラーの詩に何を読みとったのか。シラーはこの詩に何を託そうとしたのか。こうした糸を歴史的にたどることで、二十一世紀に生きる私たち自身のあり方にも光があてられることを願っている。
現代書館、矢羽々崇『「歓喜に寄せて」の物語〔改訂版〕ーシラーとベートーヴェンの『第九』』 P5-6
とてつもない高揚感と隠されたちぐはぐさ・・・これがベートーヴェンの『第九』の特徴であると著者は述べます。この本はシラーの「歓喜に寄せて」もかなり詳しく見ていきます。その詩の成立過程やその意味するところ、そしてそれがどのように受容されていったかも知ることができます。これほどシラーについて詳しく書かれている本はかなり貴重です。ドストエフスキー関係でシラーの『群盗』に興味を持った私にもこれはありがたいことでした。

そして著者はもう一つこの本の目的を語ります。
本書のもう一つの目的は、シラーやベートーヴェンの生きた時代を捉えることである。ハインリヒ・ハイネは、ヨハン・ヴォルフガング・ゲーテ(一七四九~一八三二年)が生きた時代を「芸術の時代」と定義し、ゲーテの死をもって、こうした時代が二度と来ることはないと断じた。シラーの詩はこの芸術の時代の出発点の一つであり、べートーヴェンの交響曲はその終焉を印す作品の一つといえる。
この芸術の時代は、私たちの時代につながる芸術の考え方、芸術家のあり方、読者や聴衆のあり方が生まれた時代である。例えば、芸術は芸術家の内面から生まれるオリジナルのものだという思想。芸術に身を捧げる、自由業としての芸術家という職業。自分の趣味にもとづいて作品の善し悪しを判断し、本を買ったり、コンサートにでかける人びとの誕生。こうした現代につながる芸術をめぐる世界が、この一七七〇年ころから一八三〇年ころにかけて作られた。そしてこの歴史の切断面を、シラーやべートーヴェンは生きた。
この時代は、社会的にも激動の時代であった。一七八九年七月のバスティーユ襲撃にはじまるとされるフランス革命は、ヨーロッパ全体の政治地図を塗り替えた。それまでの絶対主義王制が危機に瀕し、民主主義の松明が掲げられた。ナポレオンの登場により、民族主義が芽ばえ、ナポレオンの没落とともに王政復古の時期を迎える。しかし民主主義の火は、隠れたかたちでも燃え続けていた。
ドイツでこの激動の時代を生きたのは、ゲーテやシラー、べートーヴェンにはとどまらない。哲学ではカント、フィヒテ、へーゲル、シェリングが活躍した。音楽ではハイドン、モーツァルト、シューべルトも忘れられない。文学では、ノヴァーリスやホフマンなどのロマン派の詩人たち、あるいはへルダーリンもいた。美術でも画家のルンゲやフリードリヒ、建築家のシンケルなど。ドイツの芸術を代表するような人びとがきら星のようにならぶ時代だった。
彼らにはある共通点がある。それは、現実の矛盾や困難を、現実の政治ではなく、芸術や思想を通して克服しようとしたことだ。彼らはナイーブなほどに、芸術や思想の可能性を信じていたのである。この純粋さは「歓喜に寄せて」や『第九』にも表れていて、その根元的な力ともなっている。この芸術を信じた時代の光と影は、人を強く引きつける力がある。
現代書館、矢羽々崇『「歓喜に寄せて」の物語〔改訂版〕ーシラーとベートーヴェンの『第九』』P6-8
この本でまたありがたいのはこうした時代背景への眼差しがある点です。
ベートーヴェンがこの曲を生み出した背景には何があったのか。そして同時代人たちはその時何を思い、どんなことをしていたのか。
これは私にとって非常に興味深いものがありました。
特にゲーテはやはりこの時代を象徴する王のような存在です。私も彼のことが非常に気になります。
ベートーヴェンやシラーが活躍した時代背景を知ることはゲーテを学ぶことにも繋がってきます。
この本はベートーヴェンの『第九』とシラーの「歓喜に寄せて」を軸に、当時のヨーロッパ世界の思想や文化まで考えることができる素晴らしい一冊です。
この本に書かれている意外な事実や興味深い話をここで紹介できたらいいのですが分量的にも大変なことになってしまうのでここまでとさせて頂きます。
また、この本とは別にハーヴェイ・サックス著『〈第九〉誕生 1824年のヨーロッパ』もベートーヴェンの『第九』について論じられた作品になっています。

こちらはヨーロッパの時代背景により特化した本で、シラーについての解説はやはり 『「歓喜に寄せて」の物語〔改訂版〕ーシラーとベートーヴェンの『第九』』 の方が充実しています。
どちらも読み応えのある素晴らしい作品ですが、読みやすさ、面白さの点では 『「歓喜に寄せて」の物語〔改訂版〕ーシラーとベートーヴェンの『第九』』 を個人的にはおすすめしたいなと思います。
どちらもチェックして頂けたらなと思います。二冊ともとても興味深い作品でした。ぜひおすすめしたいです。
私も生でベートーヴェンの『第九』を聴きたくなりました。
以上、「矢羽々崇『「歓喜に寄せて」の物語〔改訂版〕ーシラーとベートーヴェンの『第九』』年末恒例の名曲の秘密に迫る1冊!」でした。
Amazon商品ページはこちら↓
【改訂版】「歓喜に寄せて」の物語: シラーとベートーヴェンの『第九』
前の記事はこちら

関連記事
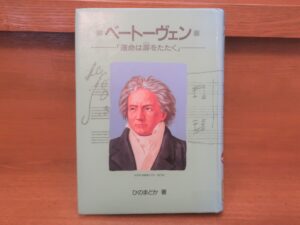












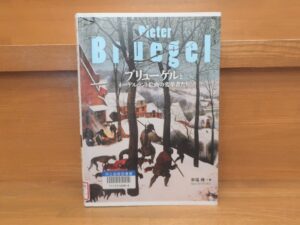

コメント