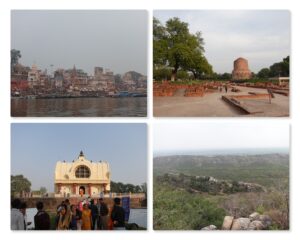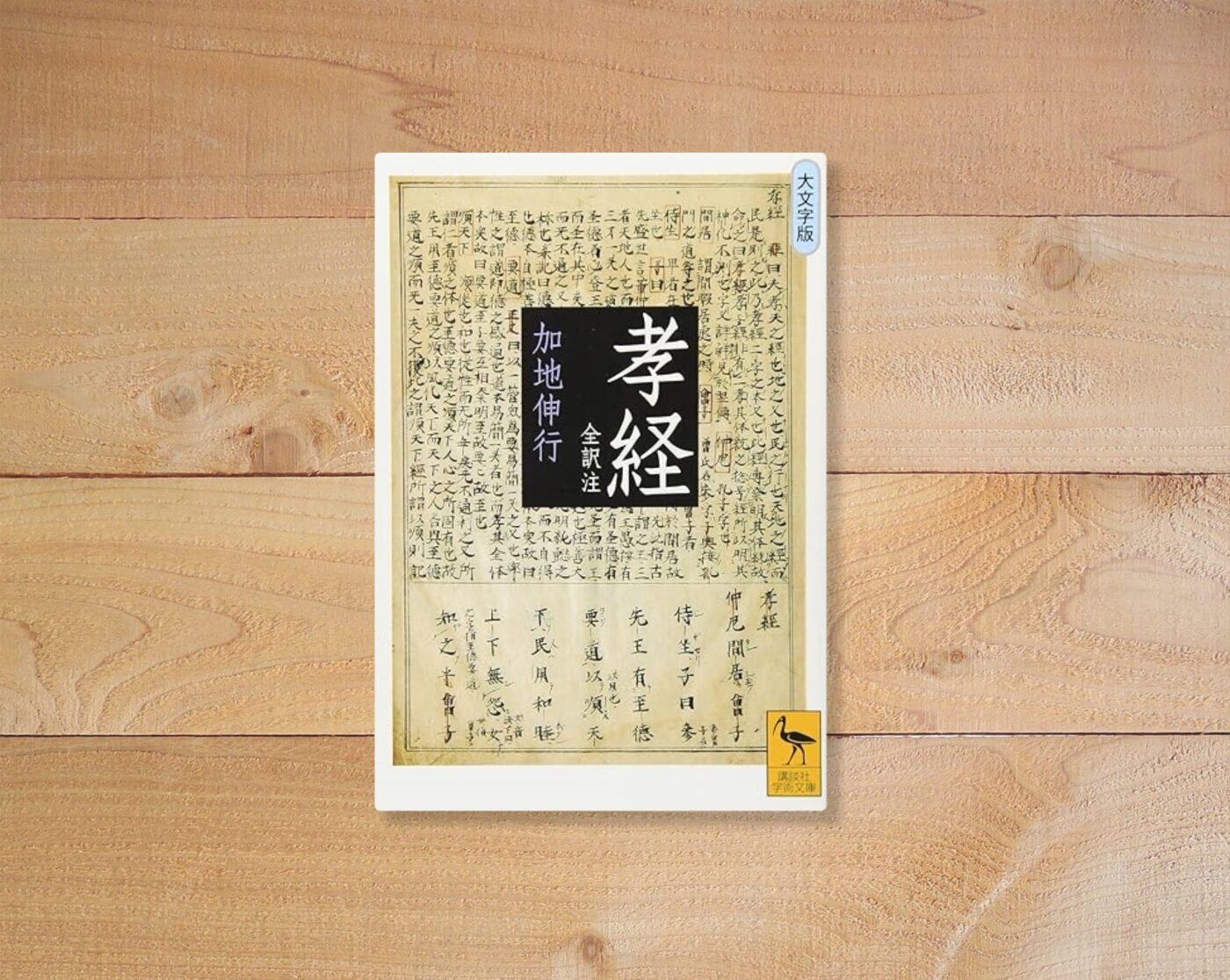金谷治『死と運命 中国古代の思索』概要と感想~中国における死生観はどのようなものかを知るのにおすすめ

金谷治『死と運命 中国古代の思索』概要と感想~中国における死生観はどのようなものかを知るのにおすすめ
今回ご紹介するのは2022年に法藏館より発行された金谷治著『死と運命 中国古代の思索』です。
早速この本について見ていきましょう。
「死の深淵へと一歩一歩と近づいてゆく、こののっぴきならない生命とはいったい何なのか」。孔子、孟子、老子、荘子、荀子等の言葉をてがかりに、中国古代における死、運命、欲望に関する思索を討尋し、生存の意味を追求する。
Amazon商品紹介ページより
本書『死と運命 中国古代の思索』は中国における死生観を学ぶのにおすすめの参考書です。
この本について著者はあとがきで次のように述べています。
生死は大事である。運命もまた重大である。軽々しくロにすべきことではなくて、生涯をかけてじっくり考えてゆくべき問題であろう。おこがましくも、そういう大事を表題にしてこの書を出すことになった。(中略)
考えてみれば、自分の幼少年期、いったい何人の死人の顔を見たことか。数え年の三歳のときに母を失ってから十六歳で父を失うまで、兄と姉、そして身近い親戚の人々まで加えて。母のことはまったく記憶にない。記憶の初めは四歳のときの長兄の最期であった。東京で学んだあと、田舎に帰って二十九歳の若さで逝った兄の死顔は、白くゆがんでこわばっていた。幼年のあいだ、近親者の死をまったく経験しないで過ごしたという人はたくさんいるだろう。やはり、しあわせな人々というべきであろうか。反対に、私以上にたくさんの、そしてきびしい不幸にあった人もいるであろう。私はそのことによって自分をとくに不幸だと感じてはいないが、幼年期のこの経験の有無はその人の人生観に大きな影響を及ぼすであろうという考えを、おし止めることはできない。私の死に対する親近感は、まずこのあたりに原因があるのだと思う。
さて、もう一つは、二十歳をすぎてからの戦争体験である。大陸に渡って一年、とくに戦闘らしいことはしなかったが、たびたび低空からの機銃掃射をうけて親しい友人を目の前で殺された。すでに「知命」の章でも述べたように、危うい命びろいは二度あった。枕を並べた昼寝の友が、一瞬にしてその胸を射ぬかれたとき、そして、揚子江の夜の船で、その甲板が血みどろの死傷者で満たされたときである。あのバリバリと来た雨のような弾丸が、どうしてすぐそばに寝ている自分にはあたらないで隣の友にあたったのか。あの甲板の夕涼みから、なぜあの瞬間に友を離れて自分だけが船室に降りたのか。これは説明のしようがない。人はこういうとき、運が良かったのだという。運が良いも運が悪いも、要するに、それはなんでもない単なる偶然のいたずらである。しかし、その偶然をうける人の側からすれば、死と隣りあわせにいる境涯で、どうしても運命というものに想到せずにはおれない。この体験にまた自分を運命や死の問題に近づけた原因であろう。肉食でない日本人は、一般に生命への執着は薄いとも言われるが、そうだとしても、これは私のとくべつな感懐である。
法藏館、金谷治『死と運命 中国古代の思索』P237-240
ここで語られるように、本書は著者の人生体験もにじみ出ている魂の一冊です。この本では中国における死生観、運命観はどのようなものだったのかということを原典を丁寧に読み解きながら解説していきます。正確なテキスト読解だけでなく著者の人生体験も共に語られますので、私達一般読者にとっても心に刺さる作品となっています。
そんな本書の中でも特に印象に残った箇所をここで紹介したいと思います。
かつて、私は一人の生化学者と死の問題について語りあったことがある。その時、「生きているものには必ず死がある」と言った私のことばに対して、その人は「アミーバーは死なない」と抗弁した。それはたえず分解をくり返して形を変化させ、そうすることによって生命を維持しているのだという。私はすかさず「その個体の分裂が、その個体としての生命の喪失ではないのか」と言うと、彼は「なるほど、そうも言える」とうなずいた。細胞組織の変化につれて分裂がくり返されるところに、個体の死と生とがある。全体としてみれば、確かに生命は永続しているように見える、いやほんとうに持続しているというべきかもしれない。しかし、壊れた形はすでに過去のものである。
法藏館、金谷治『死と運命 中国古代の思索』P30-31
私はこの箇所を読んでハッとしました。アメーバの細胞分裂は不死なのか否か。細胞分裂は「同じもの」が二つ出来上がることなのか、分かれたもの、元からあったものの区別はどうなのか。これは考えたこともありませんでした。
ですがよくよく考えてみれば私たち人間の身体も細胞分裂、あるいは細胞の生成によって成り立っています。そして体内には無数の菌が生きていてその相互作用で私たちは生きています。しかもその細胞や菌は今この瞬間も生き死にし続けています。そんな変わりゆく「細胞レベルの生死」と私達ひとりひとりの命をどう結び付けて考えるのか。私たちは自分が「今生きている」と思っていますが、もし細胞分裂も生の持続なのだとしたら、私たちの子に引き継がれた遺伝子はやはり私達の生存だと言えるのではないか。となると私のこの体が死んで滅びても違う形で生き続けているということになるのか、いや、そもそも自分が死ななくてもすでに子供や孫の中に私が生きている、さらに言えば、自分の中に親や先祖が生きているということなのか。
話はかなりややこしくなってきましたが、アメーバの細胞分裂の話から私自身様々なことを考えさせられました。著者はここから『荘子』の思想からこの問題を解説してくれるのですが、このように私達読者をハッとさせるようなポイントが本書ではいくつも出てくることになります。
私自身、このアメーバの件でトーマス・マンの傑作『魔の山』を思い出すことにもなりました。

私はこの作品でも「生命とは何か」ということを強烈に問われた経験があります。生命と非生命は何が違うのか。石ころと私達生命体の間にはどんな深淵があるのか。なぜ私達には熱、つまりエネルギーがあるのか。そしてそれはそもそもどこからやってきたのか。その始まりはどのようなものだったのか。どうして石ころのような非生命体から私達のような熱を持つ生命体が生まれるのだろうか。そんなことをこの本で感じたのでありました。私は職業柄もあるのかもしれませんが、やはりこうした死生観に強い関心があるようです。
そしてもう一つ本書においてぜひ紹介したい箇所があります。少し長くなりますが重要な提言なのでじっくり読んでいきます。
『老子』の解釈をめぐって、あれこれと死の問題を考えてきたのであるが、最後に蛇足ながら一言をつけ加えることにしたい。それは、人生とは死ぬためにあるということである。奇矯なことばであるから、それが絶対であるなどとは言わない。しかし、少なくとも死ぬということが、あるいはさらにくだけて言えば安らかに死んでいけるということが人生の一つの重要な目標であることは、首肯されるであろう。若い時の苦労が老後のためだということは、現実的な立場においても言える。その時その時の人生もたいせつであるに違いないが、それは一時的なその場かぎりのものでなくて、やはり人生の総体にかかわるものとして重要なのである。そして、人生の終局に、心安らかに死を迎えることができるというのは、確かに一つの理想である。(中略)
『荘子』の大宗師篇には、
われわれを働かせるために生が与えられ、われわれを安らがせるために老年がもたらされ、われわれを息わせるために死がもたらされる。ということばがある。生きることは苦しいことであり、やがて老年になって安らぎがおとずれ、死によって完全な休息に入るという。生の苦しさは死の安息にむけての楷梯であり、老年の安らぎは死に入る前の準備である。生と死とは一連のものとしてとらえられ、生の営みは死を指向するものとしてある。まさに人生は死のためにあるのである。根源の世界に帰って、そこで永遠の新しい安息の生命を獲得するために、人は人の世を美しく過ごさねばならない。
いづくへか帰る日近き心地して この世のものの懐しきころだれの作かは覚えないが、心に残る歌である。
法藏館、金谷治『死と運命 中国古代の思索』P32-34
「人生とは死ぬためにある」
この言葉を私達がどう捉えるか。そこに個々の死生観がかかってきます。本書を読めば著者の言わんとすることがもっとはっきりと伝わることでしょう。
そして最後にもう一つだけ紹介したい箇所があります。
すべての生き物にとって死はさけられない。死は生命の消滅である。とすれば、生きとし生けるものが死に対して懼れを抱くのは、蓋し当然である。死に対する懼れがないのは死を考えないからである。しばらくの生の充実に安眠をむさぼっているからである。死の懼れを自覚したとき、そこからはじめて生死の問題は発足する。生を絶ちきるものとしての死とは何か。いや、避けようとしても避けられない死の深淵へと一歩一歩と近づいてゆく、こののっぴきならない生命とはいったい何なのか。
まず、死を懼れるとき、はじめて生命をいとおしむ心がおこる。かけがえのない生命、それを大切にしようとする心、そして、そこに生命を養い生命を尊重する養生ないし貴生の立場が生まれる。
法藏館、金谷治『死と運命 中国古代の思索』P36-37
そうです。全ては死から始まるのです。だからこそ「生死観」ではなく「死生観」なのです。
私は僧侶として葬儀や年忌法要などに携わっていますが、やはり死の問題があるからこそ私達の生が問われてくるのです。葬式仏教と揶揄されることもありますが、厳粛な死の現場に携わらずして仏教はありえないと私は考えています。私はむしろそこにこそ仏教の役割があると信じています。
身近な人の死を通して私達自身の生死が問われてくる。死と向き合うからこそ生が問われ、私達の生き様が変わってくる。死生観を考えるというのは私達人間にとってあまりに根本的な重大問題なのではないでしょうか。
受験勉強や仕事に役立つ実学が大切なのはもちろんなのですが、こうしたことを学ぶことも人生において大事なことなのではないかと私は考えています。
本書はそうした死生観について学べる素晴らしい参考書です。私達日本人にも大きな影響を与えた中国思想を題材に死生観を見ていく本書は非常に刺激的です。ぜひおすすめしたい一冊です。
以上、「金谷治『死と運命 中国古代の思索』概要と感想~中国における死生観はどのようなものかを知るのにおすすめ」でした。
Amazon商品紹介ページはこちら
次の記事はこちら
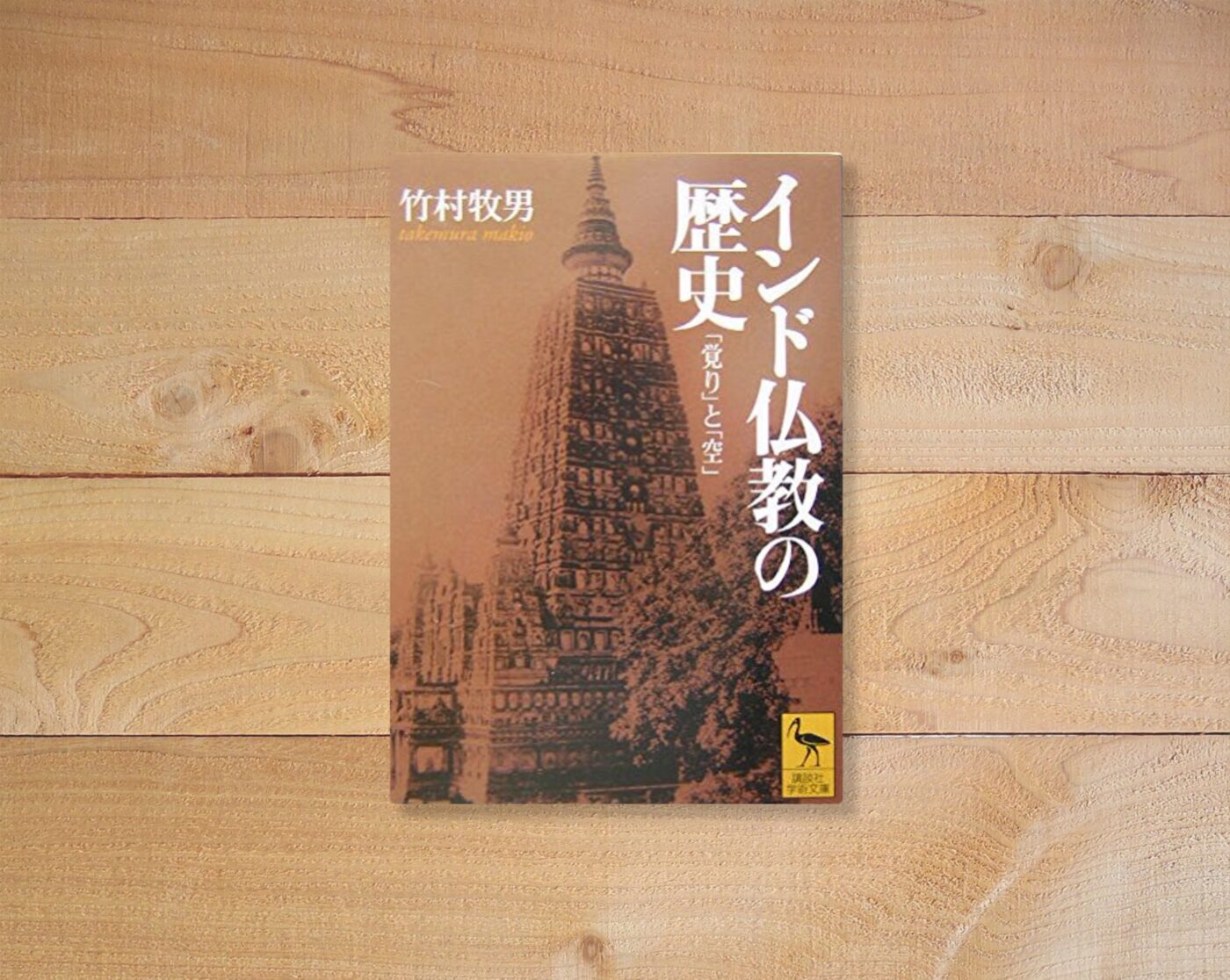
前の記事はこちら

関連記事