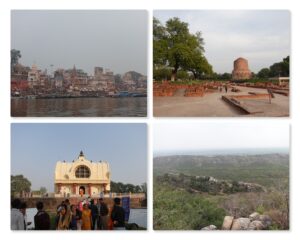赤塚忠『易経』概要と感想~中国思想における易とはどのようなものかを知るのにおすすめの解説書。インドの宗教観との比較も!
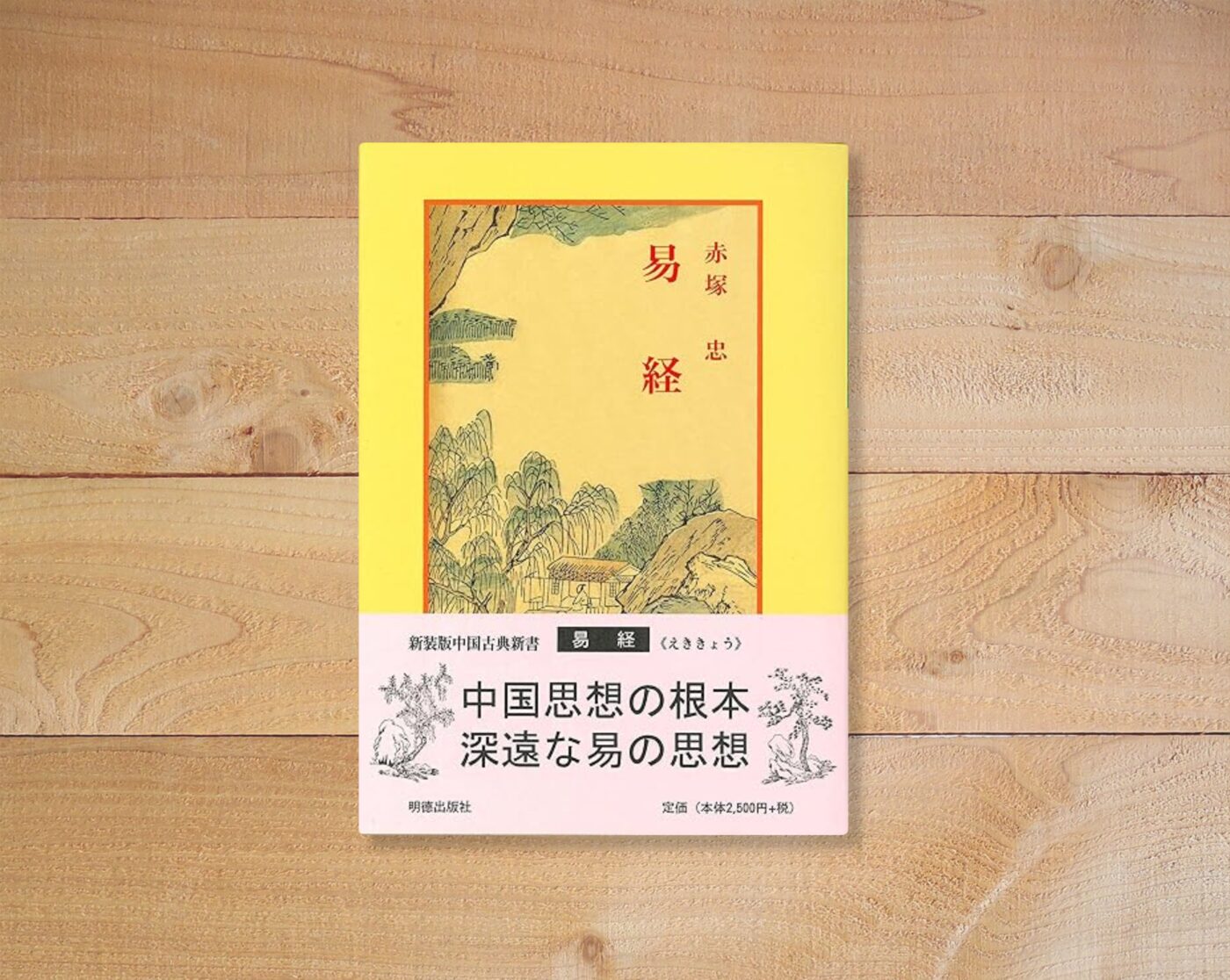
赤塚忠『易経』概要と感想~中国思想における易とはどのようなものかを知るのにおすすめの解説書。インドの宗教観との比較も!
今回ご紹介するのは1974年に明德出版社より発行された赤塚忠著『易経』です。
早速この本について見ていきましょう。
五経の一。古くは、周易・易と称する占いの書で、万物の変化と論理の因果関係を説く。本書は、凡ての経文と繋辞伝、及び説卦伝の重要な所を解釈し、易は当たるかを考え、著者の見解を述べる。
Amazon商品紹介ページより
前回の記事「下見隆雄『礼記』概要と感想~原始仏教と中国思想の『礼記』は似ている?儒教の根本聖典を読んで驚く」では四書五経のひとつである『礼記』について見ていきましたが、今回の記事では『易経』について学べるおすすめの解説書をご紹介します。
中国の占いといえば「当たるも八卦、当たらぬも八卦」といういわば慣用句のような言葉もあるくらいですが、この「八卦」というのもこの『易経』から来ているものになります。
そしてこの『易経』は単なる占いのレベルにとどまるものではなく、中国人の思想体系に大きな影響を及ぼしていたのでありました。
本書冒頭ではまずこの『易経』における「易」とは何なのかということが解説されます。その最初期における「易」は「運命にもて遊ばれる人間が、それに対処する吉凶をあらかじめ知ろうとするうらないの聖書」だったと著者は述べますが、そこから哲学的、思想的に発展していたことが解説されます。
そして私の中で特に印象に残ったのが次の箇所です。
古代人は、ものごとを極端化し単純化して考える。『易』はその典型である。
さて、人間について観察すると、右手に対する左手、頭に対する尻、腹に対する背のように相対する両面から成っている。身体ばかりでなく、人間の感情も、喜びの反面の悲しみ、安楽の反面の苦痛のように相対的であり、また経験も、信頼と背反、和合と離散、正と不正、征服と服従、強者と弱者のように相対的現象にみちている。そればかりでなく、男と女、健康と病気,吉(幸運)と凶(不幸)、生と死のように人間の生存がすでに相対的なのである。厳密にいえば、悲しみでも喜びでもない平静さ、だいたい健康だが時に病気にかかるように、そのどちらにも属さないか、またその中間のいくつかがあるはずであるが、古代人はそれを両極に分け、むしろ生があればこそ死があり、苦悩があればこそ安楽があるように、両極が相関連して存することによってものごとが展開していると考えた。とくに自然現象に至っては、そのことが明白だとした。明に対する闇、日に対する月、暑さに対する寒さ、東に対する西、南に対する北のように、両極があってこそ、日々・四季・宇宙などの展開があるのだ、と。
そこで、古代人はすべての現象、物や事は相反し相対立する両極の二大要因から成っており、しかもその相互交錯によって変化し展開しているとし、その一方の要因を陽(もと明るさ、日ざしの意)または陽気と名づけ、他方を陰(暗さ、日かげの意)と名づけた。陽(陽気)は、明るさ、熱さ、剛さ、強さ,活潑、喜び、善など、要するにすべての積極的な現象を成立させる共通の要因であり、これに対し、陰(陰気)は、暗さ、冷たさ、柔かさ、弱さ、静止、悲しみ、悪など、要するにすべての消極的現象を成立させる要因である。もめごとをこのような両極の相互関係で捉えるのは、人間の考え方の基本型であろう。
明德出版社、赤塚忠『易経』P9-10
なるほど、こう言われてみると、「易」が単なる占いではなく、一種の世界観であることがわかります。世界をどう捉えるのかというのはそのまま宗教へとつながっていきます。『礼記』でもその礼のひとつひとつからその宗教観が見えてきたように、この『易経』でもそうしたものが感じられてきました。
そしてこの陰と陽の組み合わせが八卦というものになり、さらに八卦と八卦と組み合わせて六十四卦となり複雑な世界にも対応できるようになっていったことを本書では知ることになります。
本書ではその八卦の組み合わせをひとつずつ見ていくことになるのですが、これが思いのほか面白く、含蓄深かったのが印象に残っています。著者もこうした『易』について次のように述べています。
占いの書である『易』に哲学的深昧を与えたのは、魏の王弼であるといわれているけれども、それは王弼以前から哲学化されるべきものを備えていたのである。というのは、『易』が漢代に五経の一つとなり、その後中国学術の重要な位置を占め、知識人の思想・生活に深く浸みこんだという伝統的事実をさすのではない。それもあずかって力のあったことに相違ないが、もっと根本的な理由がある。
その第一は、『易』が運命達観の書であることである。『易』は、その名が象徴しているように、すべてのものごとは流動する。非運も幸運に転じ、泰平も争乱となり、繁栄も衰落に連なることを根本信条とし、ことにどんな艱難にも打開の運が開けることを示して、運命を甘受しながら、それなりの努力を怠らないことを説いている。そういう運命を達観して、いたずらに焦躁らない「楽天知命」(繫辞伝上)を教えている。この忍耐強い生命力は、中国の民族性とも連なるものである。(中略)
自分の意志ではどうしようもない他人のことや社会的現象は、古代の用語によれば、「命」つまり運命である。他人との日常的交渉はともかくとして、人間が長期の生活を確信をもって営んでゆくには、その運命のうちに永久的・普遍的理法、いわゆる天道・天理を見出して、これに則り、これを利用しなければならない。その理法の探究が、中国哲学の道である。その理法は、探究の度合いに応じて深浅・広狭の差がある。『易』の理法は、神明に依存するものであって、それ自体が哲学的であるとはいえないが、その探究の方向を示唆するものであった。
第二は、すでに六十四卦についてみてきたように、人間現象の観察があり、その現象の分類があり、ことにその現象を素朴ではあるが根本的な陰陽則によって分析し説明していることである。その観察は一面的であり、その分析は経験的であるよりも独断的であるけれども、なお人間現象への関心を高めるものである。撃辞伝上に「富有これを大業といふ。日新これを盛徳といふ。生々これを易といふ」とあるが、確かに「易」は強靭な人生の営みを教えるものである。
また、「易」には、これもすでにみて来たように、道徳説が展開されている。それは、儒家説・道家説に通ずるものもあり、庶民的道徳もある。もちろん、これらは、ある時代に限定されるべき道徳律ではあるが、こうして人間現象を分類し、分析し、道徳律を布いていることは、道徳律を探究する鼓舞になるであろう。(中略)『易』は、少なくとも、その運命の達観とあいまって,日常的諸事象に通ずる実践的理法の知見を立てようとするものであった。
明德出版社、赤塚忠『易経』P133-134
この箇所は仏教を考える上でも非常に重要です。
「『易』が運命達観の書であることである。『易』は、その名が象徴しているように、すべてのものごとは流動する。非運も幸運に転じ、泰平も争乱となり、繁栄も衰落に連なることを根本信条とし、ことにどんな艱難にも打開の運が開けることを示して、運命を甘受しながら、それなりの努力を怠らないことを説いている」
これはまさに仏教における諸行無常の教えと重なってきます。諸行無常、一切皆苦の娑婆の世界の中でいかに生きるかを問うた仏教。それを髣髴とさせる内容です。
そして次の、「人間が長期の生活を確信をもって営んでゆくには、その運命のうちに永久的・普遍的理法、いわゆる天道・天理を見出して、これに則り、これを利用しなければならない。その理法の探究が、中国哲学の道である」という箇所に私は注目せずにはいられませんでした。
中国においては天道、すなわち世界の真理は「これに則って、利用すべきものである」というのです。世界の真理はあくまでこの世を生きるための智慧としての理法なのでありました。ここに古代インドの宗教観との違いがあるように思えました。
古代インドにおける法はあくまで神々の法です。そしてその神々に儀式や奉納をすることで人間達に恵みをもたらします。また、インドにおいては輪廻転生の世界観がありますが、この苦しみの輪廻転生のループから抜けるために究極なる真理がありました。「今の現世をうまく生きるために利用する法」という発想はインドにおいては希薄です。
中国思想は極めて実体的で現実的、合理的とよく言われますが、この『易』における世界観においてもそれはまさに反映されているようです。
苦しみの現世から解脱を目指すインドの宗教観と現世を徹底的に生きようとする中国の宗教観。この違いを思わず感じることとなりました。
前回の記事で紹介した『礼記』でもインドとの比較をさせて頂きましたが、やはりここまで土壌が違うとそこに根付く宗教や文化もかなり変わってきます。そうした中でインドから仏教が中国に流伝してきたというのはやはり意識せねばならないなと思います。
中国思想のベースとなった四書五経を学ぶのは実に刺激的です。まさかここまでインドと比べながら学べるとは思っていませんでした。やはり比べてみるのは面白いですね。これまで意識していなかったことも改めて見えるようになってきました。
今回ご紹介している赤塚忠著『易経』は経の本文だけでなく解説も充実していますのでぜひおすすめしたい一冊となっています。ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。
以上、「赤塚忠『易経』概要と感想~中国思想における易とはどのようなものかを知るのにおすすめの解説書。インドの宗教観との比較も!」でした。
Amazon商品ページはこちら↓
次の記事はこちら
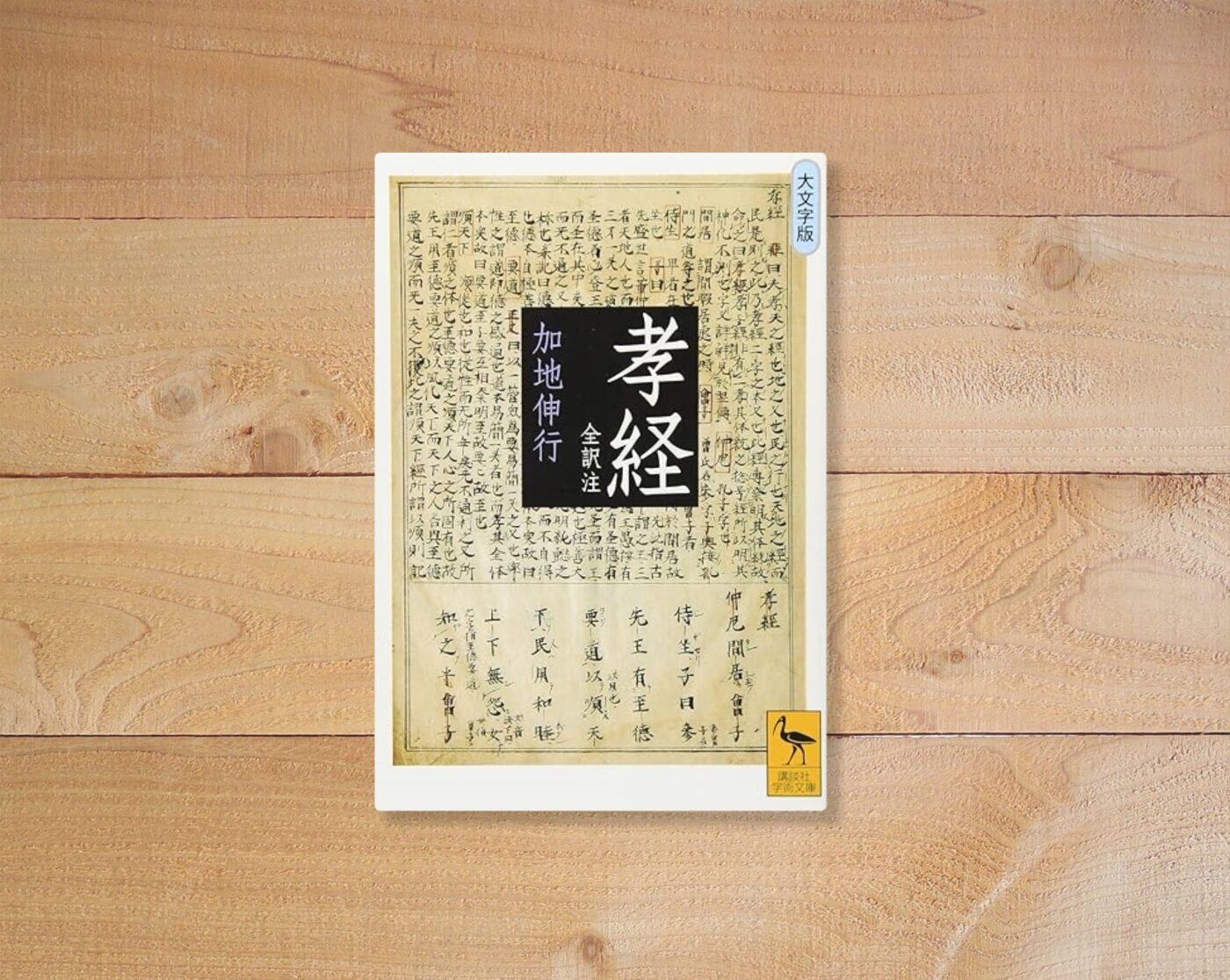
前の記事はこちら
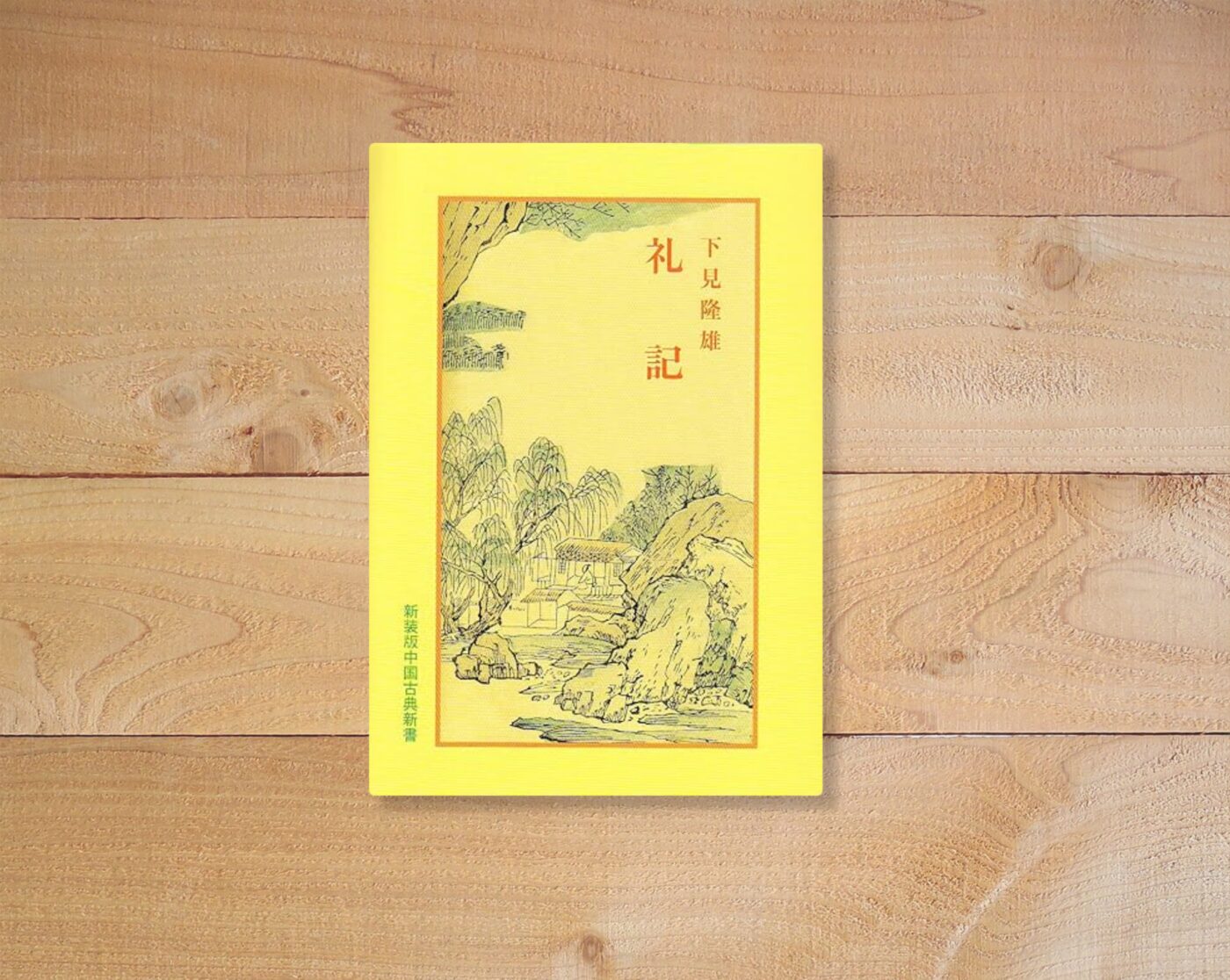
関連記事