顔之推『顔氏家訓』あらすじと感想~読書の効能や意義について。乱世の中国六朝を生き抜いた知識人の教えとは。

顔之推『顔氏家訓』あらすじと感想~読書は必ず力になる。乱世の中国六朝を生き抜いた知識人の教えとは。
今回ご紹介するのは2018年に講談社より発行された顔之推著、林田愼之助訳の『顔氏家訓』です。
早速この本について見ていきましょう。
6世紀末、王朝の興亡が繰り返された中国六朝時代に、一族流浪の困難を乗り越えて、粱、北斉、北周、隋と4代の王朝に仕え、学問を家業とした名門貴族として生を全うした顔之推。彼が子孫のために書き残した『顔氏家訓』は、家族の在り方から子供の教育法、文章論、養生の方法、仕事に臨む姿勢、死をめぐる態度に至るまで、人生のあらゆる局面に役立つ知恵に満ちている。その英知が分かり易い現代語訳で甦る。
Amazon商品紹介ページより
本書の著者顔之推(531-590頃)は乱世の中国に生きた名門貴族です。しかし、名門貴族とはいえ次々と王朝が変わる中国の乱世にあっては、官僚として生き抜くだけでも実に厳しいものがありました。
この顔之推と『顔氏家訓』について本書冒頭では次のように解説されています。
『顔氏家訓』は六世紀末、わが国でいえば聖徳太子の命をうけた小野妹子が遣隋使となって中国に渡った時代、顔之推によって著わされた家訓書である。(中略)
顔之推は乱世を生き抜いた苦渋の人であった。祖国の滅亡という悲劇を目の当たりにした後、北方異民族に拉致され、その王朝に漢民族官僚として仕えて生涯を閉じている。その数奇な体験をいかして人間らしく生きる知恵を、この家訓のなかにつむいでいるためか、そこには訓戒の堅苦しさがない。『顔氏家訓』が話題性にとんで、興趣ある随想録となっているのはそのせいであろう。それだけではない。歴史書ではとうてい伝えられなかった南北朝社会の生活の実態、当時の風俗・文化の様態を多岐にわたっていきいきと描き出しているという意味でも、『顔氏家訓』は一級の歴史資料である。
講談社、顔之推、林田愼之助訳『顔氏家訓』P3-4
私が本書を手に取ったのは以前当ブログでも紹介した川勝義雄著『魏晋南北朝』がきっかけでした。

この本の中で顔之推が南北朝貴族を代表する存在のひとりとして紹介されていたのでありました。当時の中国は乱世でありながらも文人貴族の存在が不可欠な時代でありました。いかに軍人がその武力を頼りに王朝を立てようとも文人貴族の存在がなければその地を統治することができなかったのです。これが中国の歴史の特徴であると川勝義雄著『魏晋南北朝』で学ぶことになりました。
ここではこれ以上詳しくはお話しできませんが、中国においては学問を積んだ教養ある人間が重視され、その才覚によって行政が行われるという土壌があったのでした。その典型例として読書や学問を重んじた顔之推が紹介されていたのでありました。
上の引用の後半にも述べられていたように本書『顔氏家訓』は当時の生活の実態や官僚達の生きる術を知ることができる貴重な歴史書です。というわけで私も当時の時代精神を知るために本書を手に取ったのでありました。
そして実際に読んでみてやはり印象に残ったのは顔之推が語る読書についての家訓でありました。
せっかくですのでここでその言葉をいくつか紹介していくことにしましょう。
学業は身を助ける
梁王朝の全盛時代、貴族の子弟は、学問の教養が欠けている者が多かった。「馬車に乗って落ちなければ、著作郎。ご機嫌いかがですかと挨拶語が書ければ、秘書郎」という諺ができたほどである。
かれらが衣服に香を焚きこみ、顔を剃り、白粉をぬり、紅をつけ、長轅の車に乗り、高歯の屐をはき、碁石模様のついた四角い座布団に座し、斑糸で飾ったクッションによりかかり、趣味の品々を左右にならべて、ゆったり出入りする様子は、神仙もかくやと思われたものである。
そして、明経科の試験には人の答案をたよりにして、朝廷の宴席では人手を借りて詩を賦し、そのときはそれで立派なご仁としてまかりとおったのである。ところが争乱の後は世の中がすっかり変わり、官吏の選考には、昔の情実関係はなくなった。当路の実権者には、昔の仲間がただの一人も見つからなかった。もともと身についた技能はなく、世に役立つはずはなかった。聖人ならば、下賎な衣をまとっても、心に珠を抱くが、珠などあろうはずもなく、虎の皮衣を失って本性をあらわし、枯木のよう突っ立ち、水涸れの小川のように干からび、戦乱の国をさまよい、溝のふちに行き倒れて死ぬのが落ちだった。そうなったら最後、ほんとうに無能な人物というほかはなかった。
学業を身につけている者は、たとえどこに行っても安定している。戦乱以来、俘虜の憂き目にあった人は数々あったが、代々の平民でも、『論語』『孝経』ぐらいの書物を読めるというだけで、人の師匠となったものである。昔からの家柄でも、書籍を読みこなせない連中は、耕作か牧童でもやるほかはなかった。こうした実例をみれば、どうして学問に勉めはげまないでおられようか。もしも数百巻の書物を家蔵できていれば、永久に平民に落ちぶれることはない。
講談社、顔之推、林田愼之助訳『顔氏家訓』P63-64
梁王朝後半から末期は貴族の退廃が目立ち、弛緩した空気が漂っていたことが森三樹三郎著『梁の武帝 仏教王朝の悲劇』や岡本隆司著『物語 江南の歴史』でも語られています。そして突然の戦乱によって国が崩壊するという恐るべき運命が待ち受けていました。その空気がこの文章からも伝わってきます。
しかしそんな絶望的な状況でもしっかり学問や研鑽を積んでいればこそ乱世を生き抜くことができたと彼は述べるのです。もちろん、想像を絶する苦難を耐えなければなりませんでしたが、死屍累々の世界の中で彼は生き延び、家を守り切ったのです。その説得力たるや大きなものがあることでしょう。
そして次の言葉も印象的です。
父兄はいつまでもあてになるものではなく、郷国はいつまでも続くものではない。いったん異郷に流浪してしまえば、保護する人もないので、自力で自分の生活を守るほかはない。
諺は、「千万両の金を蓄えるよりも、一芸を身につけるにこしたことはない」といっている。諸芸のなかでも、習い易く、しかも価値が高いのは、読書にすぎるものはない。世人は賢愚を問わず、誰でも多くの人を識り、見識を広めたいと思っているのに、書物を読みたがらない。これは、腹いっぱい食べたいと思いながら、料理を作ることを怠り、暖かい着物を身につけたいと願いながら、着物の仕立てを怠るようなものだ。
さて読書する人は、古代文化の創造者、伏義、神農以来、この広い宇宙で、幾多の偉人を知り、幾多の事件を見たであろうか。書物を読む人間の前では、人生の成敗、善悪はもとより、天地は何もかくすことができず、鬼神も何もかくすことはできない。
講談社、顔之推、林田愼之助訳『顔氏家訓』P65
「腹いっぱい食べたいと思いながら、料理を作ることを怠り、暖かい着物を身につけたいと願いながら、着物の仕立てを怠るようなものだ。」というのは何ともズバリな例えですよね。
そして読書をすることで古代の偉人や歴史を知ることができるという点を彼は強調しています。彼はまさしくいつ何が起きるかわからない戦乱の時代に生きていました。そんな中ひとつでも判断を間違えば死が待っています。かつての偉人や出来事を多く知るということは、状況判断の材料を持つということにほかなりません。様々な状況に対応するには知識と経験が必要です。そうした意味でも読書が乱世を生き抜く大きな力となったと彼は述べるのです。これは説得力がありますよね。
ですが顔之推は単に読書すれば「万事良し」と述べているのではありません。次のような注意もしています。
学問とは自分を充足させるためにするものだ。それなのに、世間では、数十巻ばかりの書物を読んだからといって、それを鼻にかけて高慢になり、先達をしのいだとして、仲間を見下げたりする者をみることがある。そんな人間は人々から仇敵のように憎まれ、悪鳥のように嫌われる。書物を読んでも、こんなふうになるぐらいなら、無学であったほうが、よほどましである。
講談社、顔之推、林田愼之助訳『顔氏家訓』P67
これは私も肝に銘じたいと思います。何のために読書をするのか、それが問われるのです。そして顔之推は次のように続けます。
「古の学ぶ者は、自分のためにする」(『論語』憲問篇)ので、学問を修めて自分の不足するところを補おうとした。「今の学ぶ者は、人のためにする」(『論語』憲問篇)ので、他人を説得するための種を仕込もうとする。昔の学者が人のために学問したのは、正しいことをして世の中に役立ちたいからである。今の学者が自分のために学問するのは、身を修めて出世したいがためである。
さて学問するということは、植物を植え育てることに似ている。春にはその花を賞で、秋にはその実りを収める。文章を作ったり論じたりするのは、学問における花を賞でることに相当し、身を修め行いを善くするのは、学問における秋の実りを収めることにある。
講談社、顔之推、林田愼之助訳『顔氏家訓』P67-68
孔子は、「学問すれば、俸禄は自然についてくる」(『論語』衛霊公篇)といったが、近頃の人は無益な勉強に精を出している。おそらく、それは、孔子のいう「学べば」の業のうちに入らないだろう。
そもそも聖人の書なる経書は、人を教導する手段である。だから経典の文章に熟練し、あらましの意味がわかっていて、そこから平素の言行の指針が得られるならば、それで人間としては充分である。『孝経』の一句である「仲尼居る」の解釈に二枚分もの注釈をつける必要はない。孔子が起居された部屋や講義をされた講堂が今どこに残っているというのだ。こんな下らぬことを論議して人を説得できたとしても、なんの役に立つというのであろうか。
光陰惜しむべし、逝く水は返らぬ。当然のことだが、要点だけを博く読破して機微をつかみ、実務の効果に役立てねばならぬ。学問と実務が立派に兼ね備わっていれば、わしは結構なことだと思っている。
講談社、顔之推、林田愼之助訳『顔氏家訓』P71-72
「そもそも聖人の書なる経書は、人を教導する手段である。だから経典の文章に熟練し、あらましの意味がわかっていて、そこから平素の言行の指針が得られるならば、それで人間としては充分である。『孝経』の一句である「仲尼居る」の解釈に二枚分もの注釈をつける必要はない。」
これは現代でも特に通ずるものがあるのではないでしょうか。
「学問と実務が立派に兼ね備わっていれば、わしは結構なことだと思っている。」
これぞまさに学問と実務を両立し、乱世を生き抜いた顔之推だからこその金言であります。
そして私としてはこの「光陰惜しむべし、逝く水は返らぬ。当然のことだが、要点だけを博く読破して機微をつかみ、実務の効果に役立てねばならぬ。」という言葉もぐっときます。そうです。「時は金なり」。何かを極めようと勉強するにしても、とにかく時間が足りないのです。私もよく言うのですが、自分が3人いたらいいのにと本当に思うのです。まあ、3人いたとしても「あぁ、もっと本を読みたい」と今度は9人いることを願い、それでも足りなくてもっともっとと求めてしまうことでしょう。
それほど私たちに与えられた時間というのは限られたものです。そんな中、専門家でもないのに「『孝経』の一句である「仲尼居る」の解釈に二枚分もの注釈をつける必要はない。」のです。細かいところに入り込みすぎる時間は私たちには存在しないのです。
官僚として激務であったろう顔之推もまさに時間の大切さを身に染みて感じていたことでしょう。
だからこそ要点を把握し、その機微を掴むことを勧めるのではないでしょうか。ただ、この機微を掴むというのがまた難物で、ただ単に本を流し読みするだけでは体得できるものではありません。やはり地道な勉強も必要なのではないでしょうか。
そして最後にもうひとつだけ彼の言葉を紹介しましょう。
晩学のすすめ
人は幼少の時期が精神が集中していて鋭敏であるが、成長してからは、思慮が散漫になりがちだから、教育は早めにして機を逸してはならない。
わしは七歳のときに、「霊光殿の賦」(後漢の王延寿の作)を暗誦し、今まで、十年に一度おさらいするだけだが、やっぱり忘れてはいない。二十歳以後に暗誦した経典は、一カ月もほうっておくと、もう駄目になる。
しかしながら、人間には不遇や逆境に陥ることがあって、そのために青年時代に学問する機会を失ってしまうことがあっても、なおあきらめずに晩学すべきである。
孔子も、「五十歳になって易を学ぶことができれば、わたしの一生は重大な過失がないものとなるだろう」(『論語』述而篇)といっている。魏の武帝や袁遺は老いてますます学問に熱心であったが、これはみな若いうちから学び始めて、老いてなお倦まざる者である。
曾子は七十歳から学問を始めて、名を天下に馳せた。荀子も五十歳になって斉に遊字して大学者となった。漢の公孫弘は四十余歳で、『春秋』を読み、そのおかげで丞相(総理大臣)にまでのぼった。漢の朱雲も四十歳にして初めて『易経』と『論語』を学び、晋の皇甫謐は二十歳で初めて『孝経』『論語』を教えてもらった。彼らはみなのちに大儒となった。いずれも初めは迷いがあったが、のちになって学ぶことの必要性に気づいたのである。
世間の人で、成人となり、結婚しても学ばないでいる者が、もう遅いと思い込み、ぐずぐずして、前に立ちはだかる壁を破ろうとはせずにいるのは、愚かなことである。
幼時から学ぶ者は、朝日の光にたとえられ、年老いて学ぶ者は、夜道の提灯にたとえられるが、それでも目をつむったままなにも見ようとしない連中より、はるかに賢明である。
講談社、顔之推、林田愼之助訳『顔氏家訓』P68-69
学びは若い頃からするのがベストだが、年を取ってからでも遅くはないと勇気づけてくれる顔之推。彼の言葉は現代人たる我々にも響いてくるものがあるのではないでしょうか。
本書『顔氏家訓』ではこのような「読書のすすめ」だけでなく、生活や実務に関する様々な訓戒が語られます。
そしてこうした知識人貴族の代表たる顔之推の意義について川勝義雄は『魏晋南北朝』で次のように述べています。少し長くなりますが中国の歴史を考える上で非常に重要な指摘ですのでじっくり読んでいきます。
右の文章は、大混乱の渦中を生きぬいた知識人が、故郷からも親戚からも離れたさすらいの孤独の中で、学問と教養の必要性をあらためて確認し、生きることとは読書学問にありとの信念をますます固めていったようすを、痛いほどわれわれに示している。
そこでは、読書によって「古聖王の道」を学び、文明の基礎とその伝統を護持することが、すなわち具体的に生きること、職を得て身分を維持することに、そのまま直結してゆくのである。そのような知識人の意識は、社会が郷村共同体を解体させ、親族共同体からさえ個人が放出される方向に動けば動くほど、そして、そのような社会の荒波の中に個人が翻弄されればされるほど、単家族を最後のよりどころとして、ますます強烈に自覚されていったのであった。
このような意識は、顔之推に特殊なものではありえない。かれと同時代の知識人たちは、同じような環境に生きて、多かれ少なかれ同様の意識を心の中にもっていたにちがいない。『顔氏家訓』という作品は、同時代人の意識の少なくとも一面を、あざやかに反映するものと見てよいだろう。そしてまた、この作品が多くの人びとに読みつがれていったことは、そのような意識の広がりを示すなによりの証拠である。それは、乱世における中国の知識人の強靭さをまざまざと示すと同時に、この乱世が終わったあとの、新しい世界における知識人のあり方に対する指標でもあった。
文化的な先進地域を統合した北周ー隋帝国は、顔之推と同様な考え方をもつ知識人たちを、その傘下に組み入れて、かれらの積極的な協力をひきだす方策を考慮しなければならなかった。また、バラバラになった社会の中で、無数に生じている小集団の有力者たちを、顔之推が示したような読書人にしたて、国家社会の秩序を安定させるために、それらの新しい知識人を手足として役だてることは、統一帝国にとっても必要なことであった。そのような状況から生みだされた制度が、六世紀末、隋の文帝の治世に創始された科挙にほかならない。
科挙という試験制度は、応募者の出身を問わず、試験によってすぐれた読書人を選抜し、及第者に為政者の職と身分を保障する制度である。それは、まさに顔之推がいうように、読書によって「古聖人の道」を学ぶことが、そのまま職を得て身分を維持することにつながるという読書人理念を、国家的規模で実現しようとするものである。顔之推の見方と、科挙制度のねらいとはまったく一致する。
そのような見方を生みだし、そのような制度を発想させる事態が、この当時すでに存在していたのである。
講談社、川勝義雄『魏晋南北朝』P422-424
『顔氏家訓』が「乱世における中国の知識人の強靭さをまざまざと示すと同時に、この乱世が終わったあとの、新しい世界における知識人のあり方に対する指標でもあった」というのは非常に重要な指摘です。だからこそ私は本書を手に取ったのでありました。
当時の中国社会の雰囲気を掴むためにも本書は非常に大きな意味を持っています。また、古代中国の偉人が勧める「読書」についても知れる本書は私にとっても実に興味深いものがありました。
ぜひぜひおすすめしたい作品です。
以上、「顔之推『顔氏家訓』あらすじと感想~読書の効能や意義について。乱世の中国六朝を生き抜いた知識人の教えとは。」でした。
Amazon商品ページはこちら↓
次の記事はこちら

前の記事はこちら

関連記事


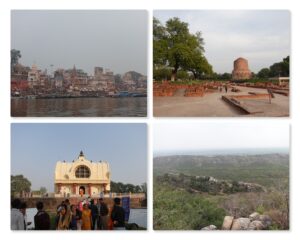





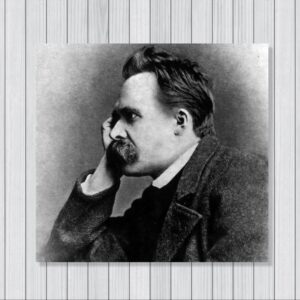









コメント