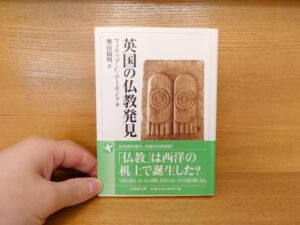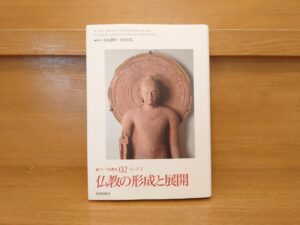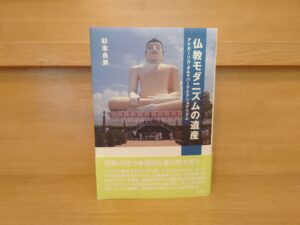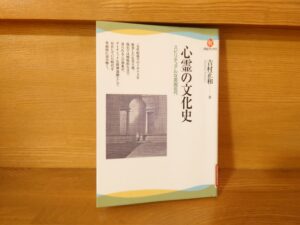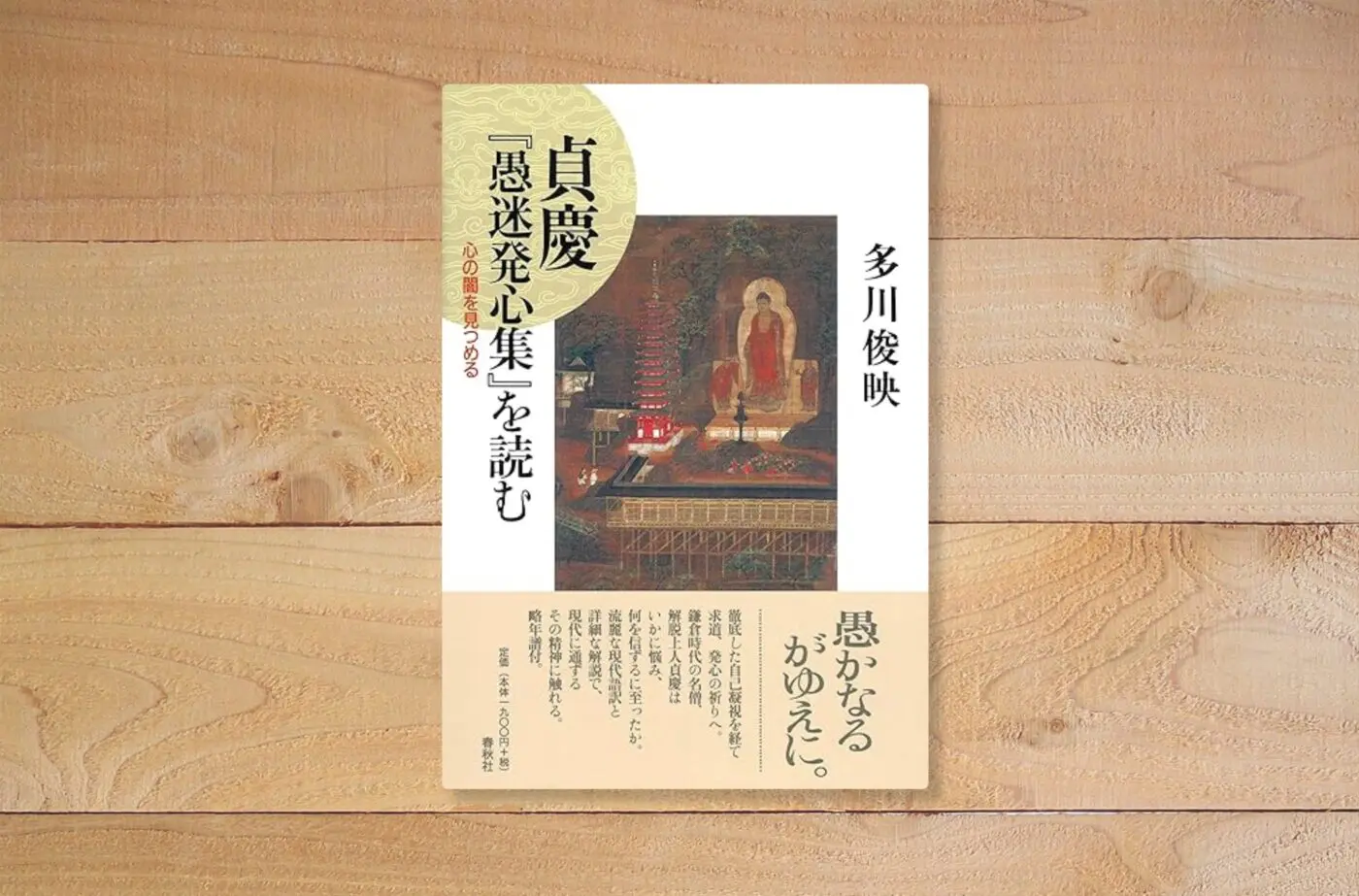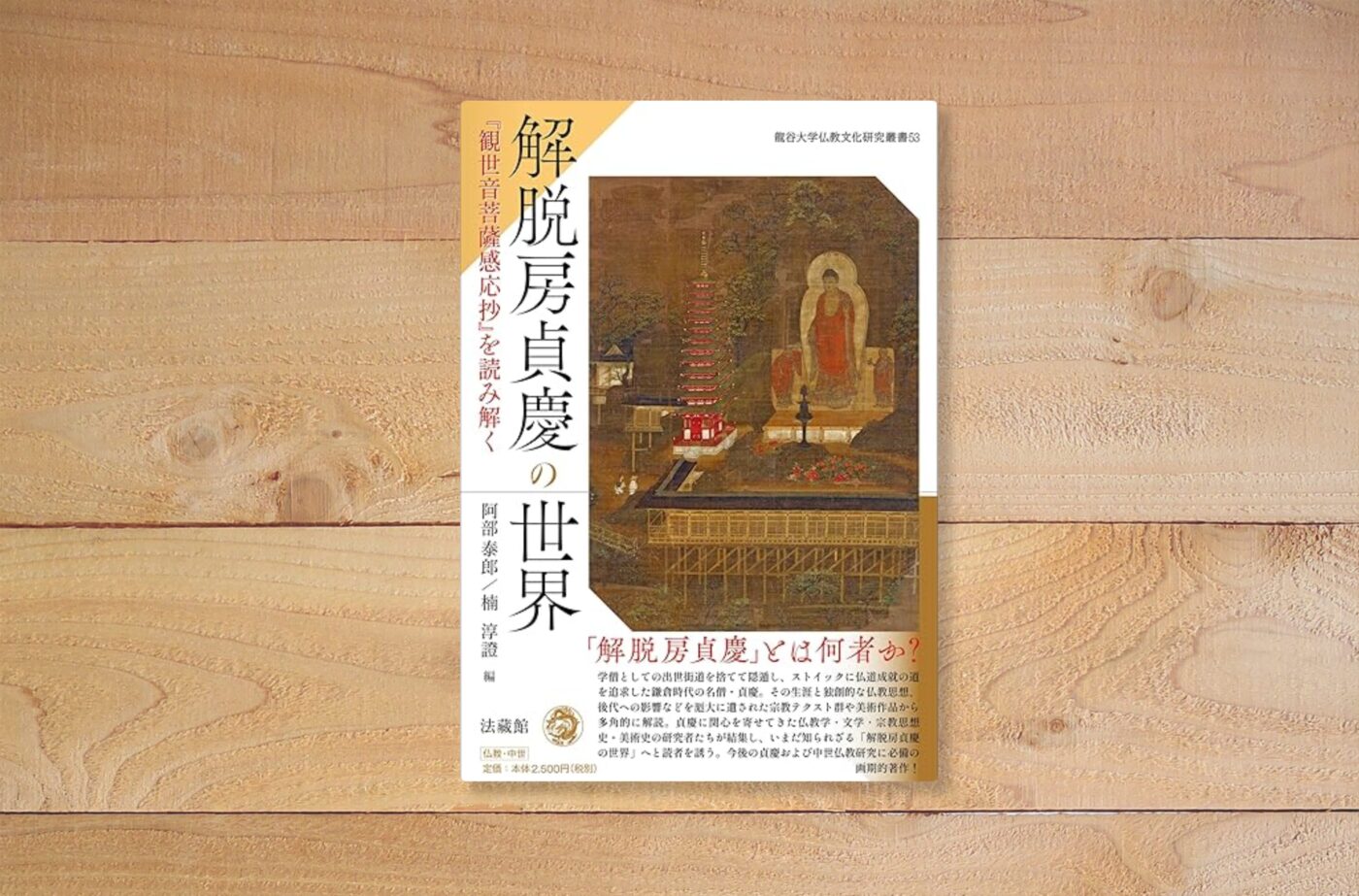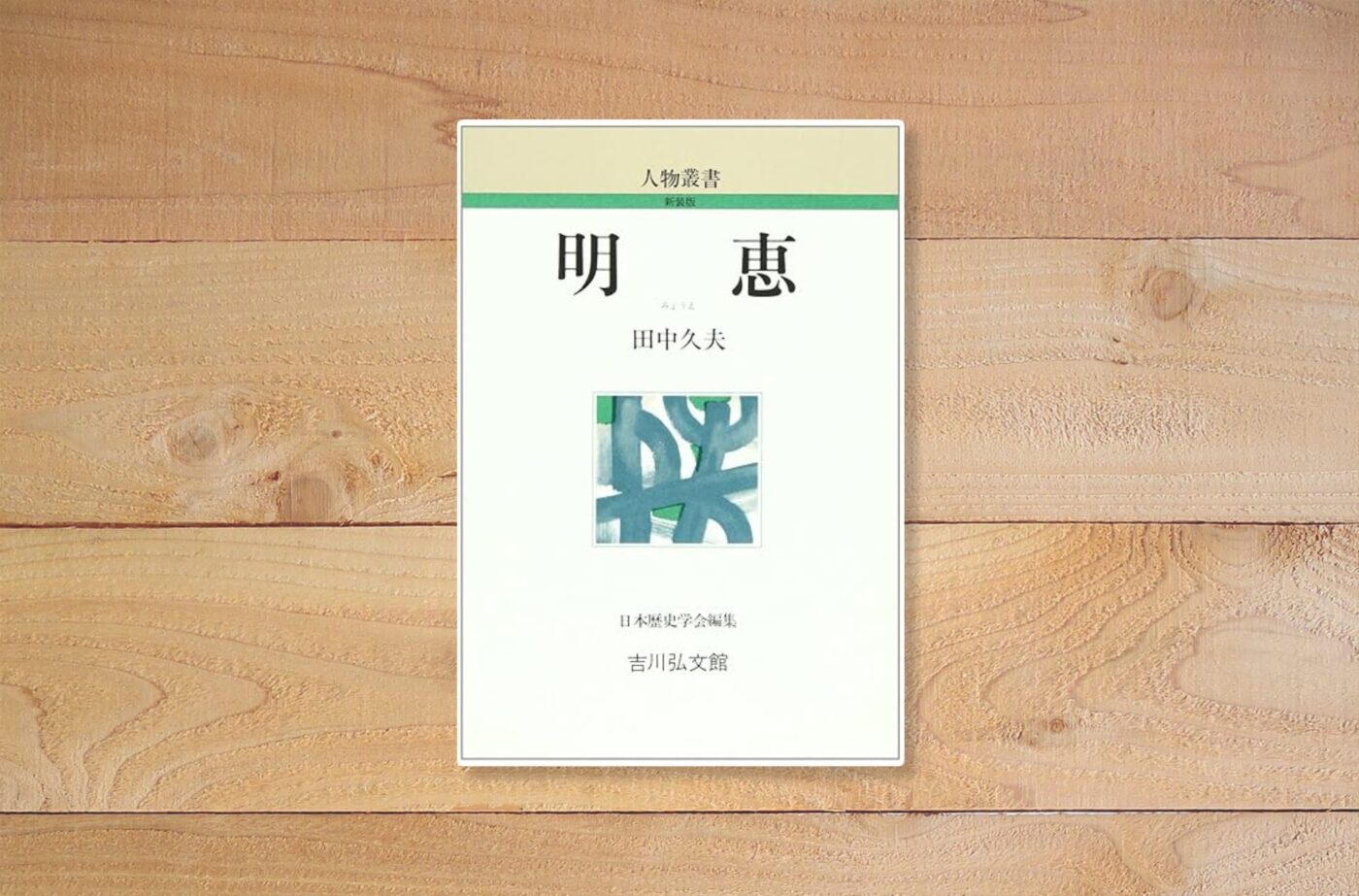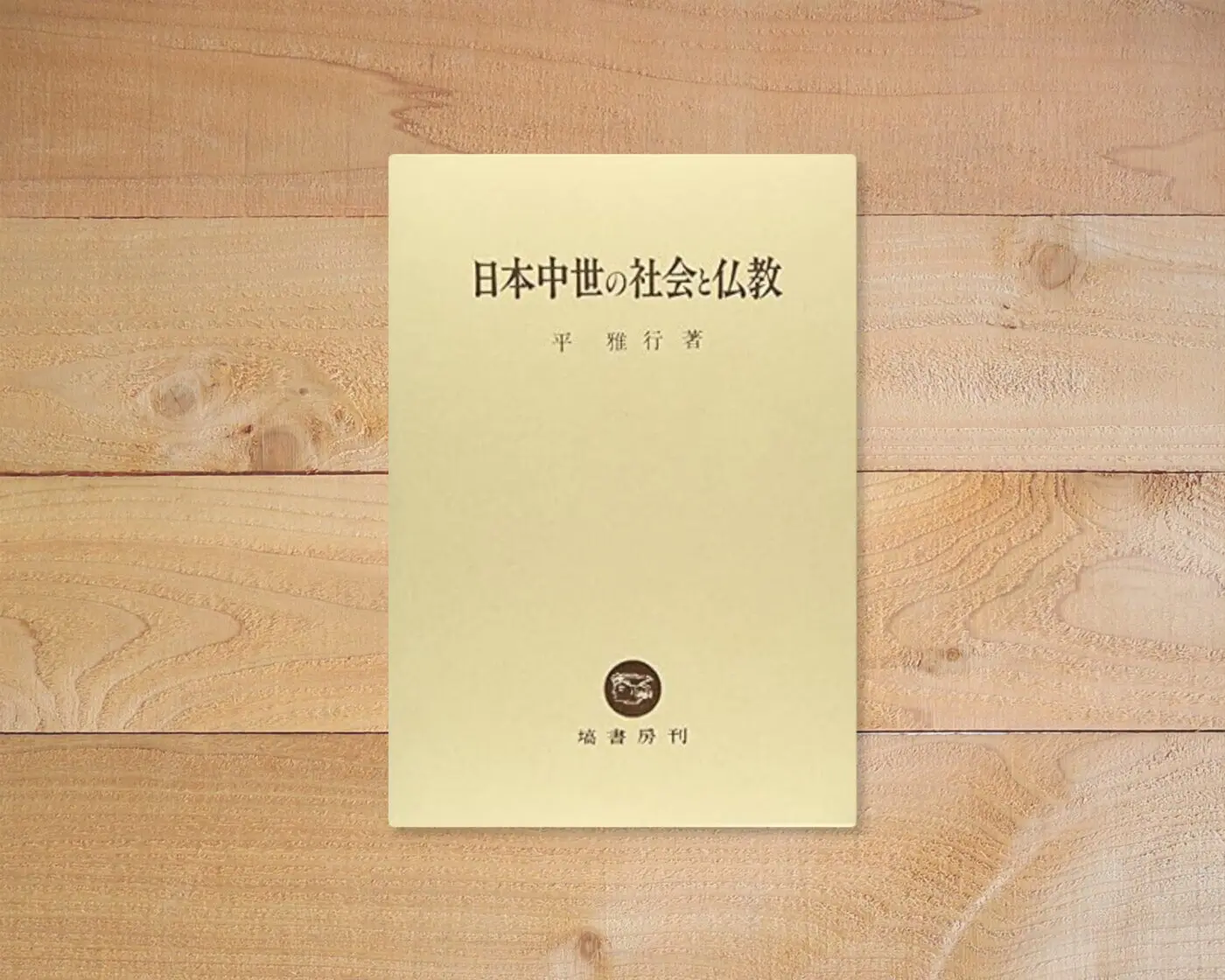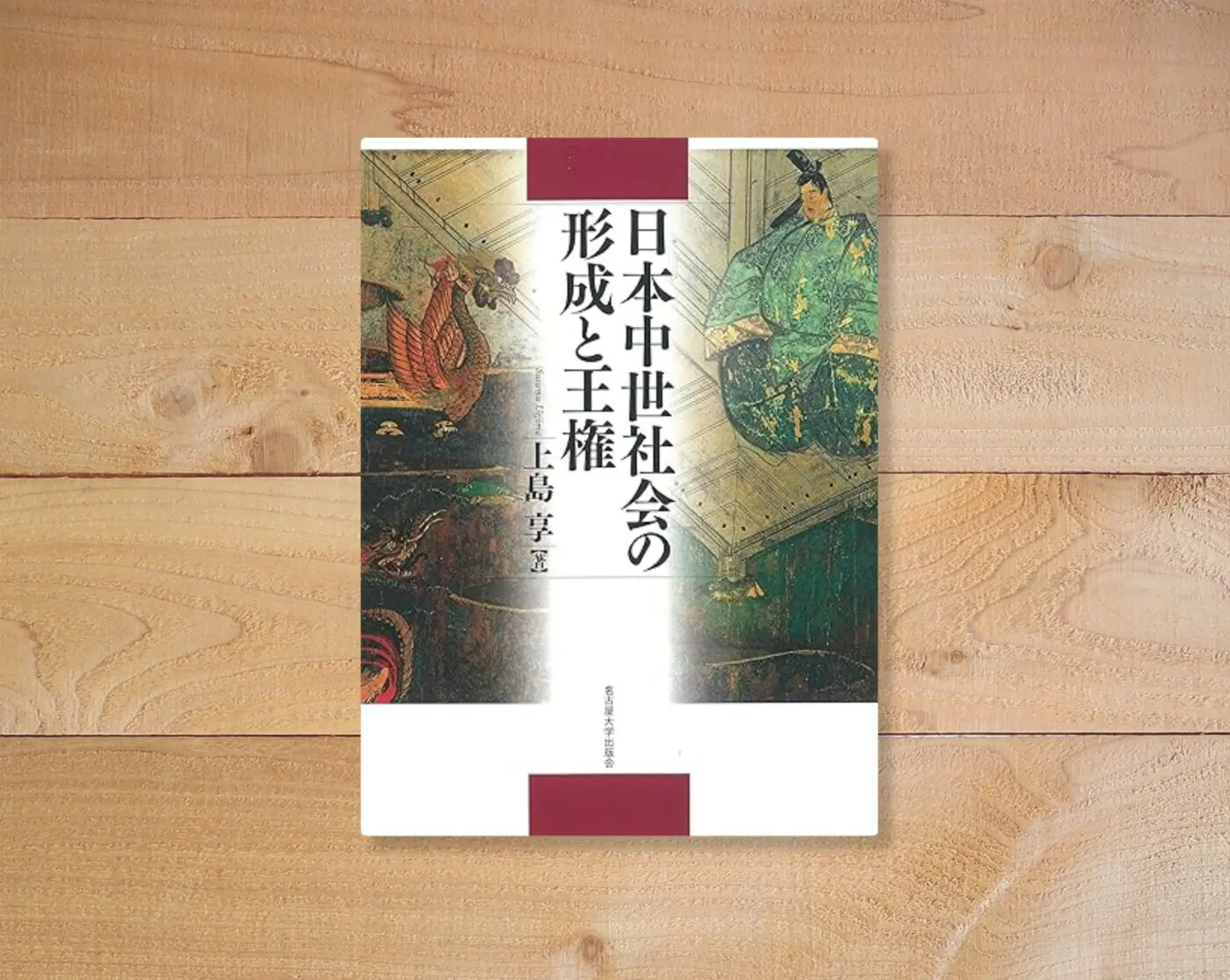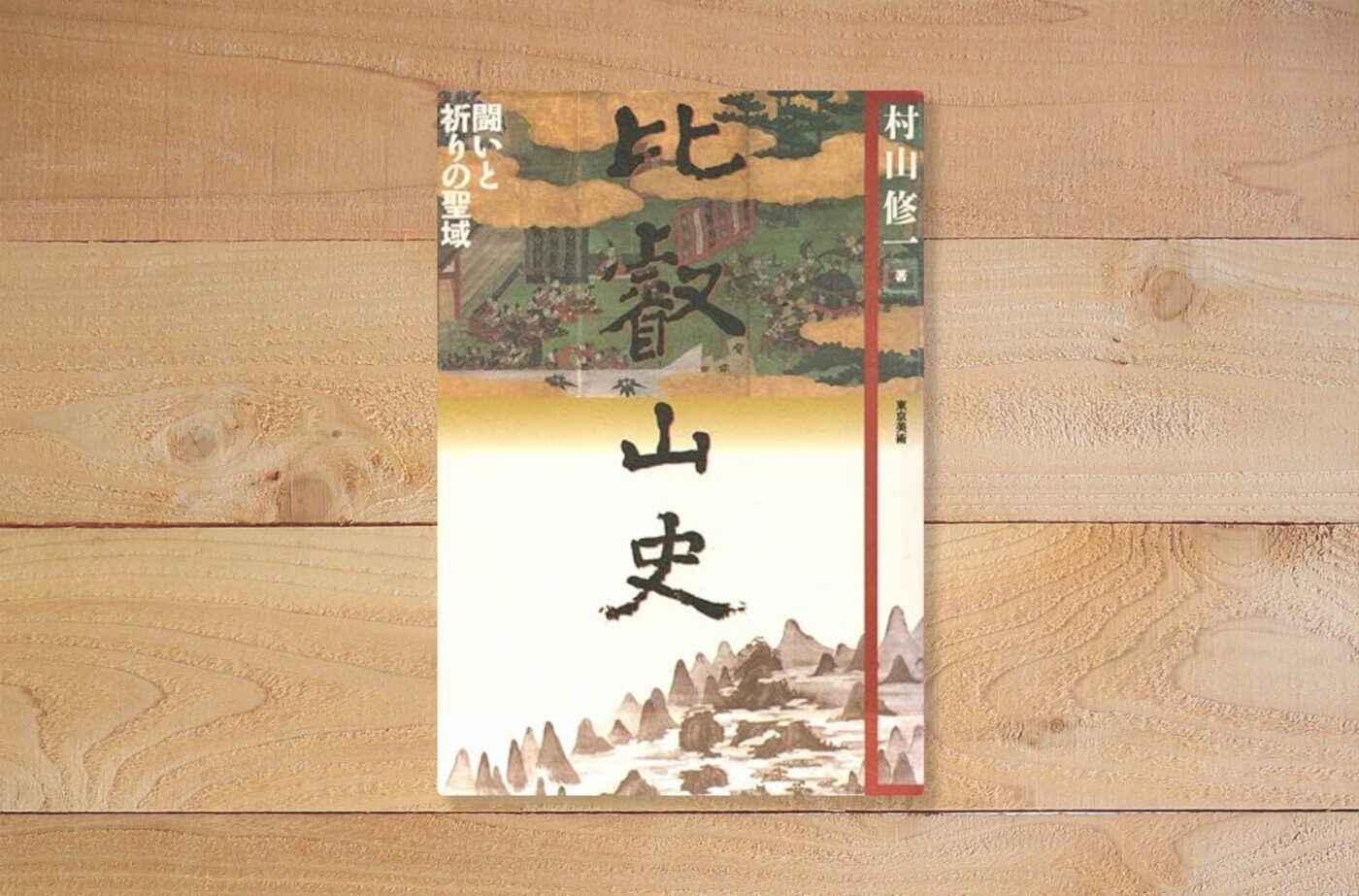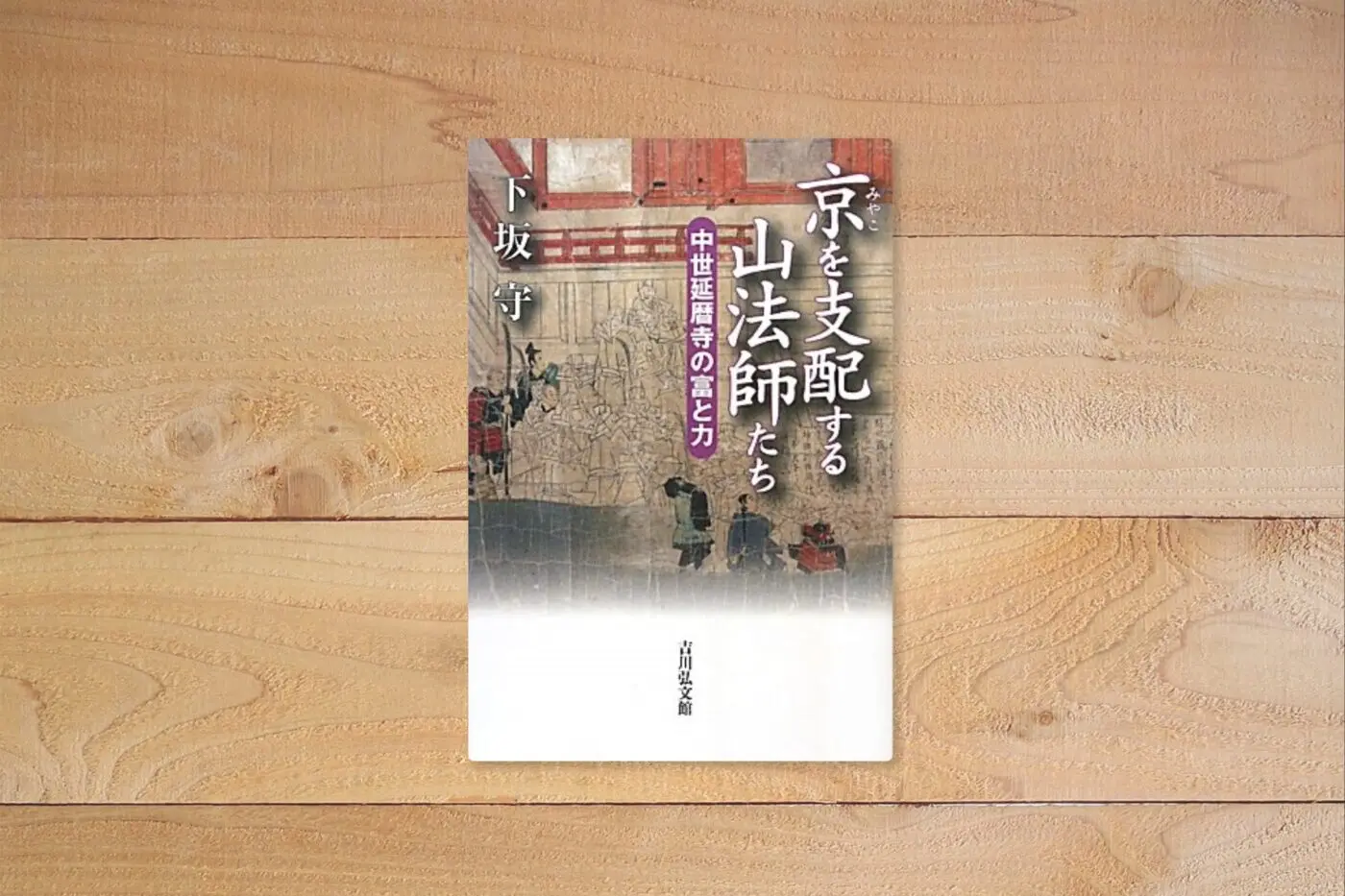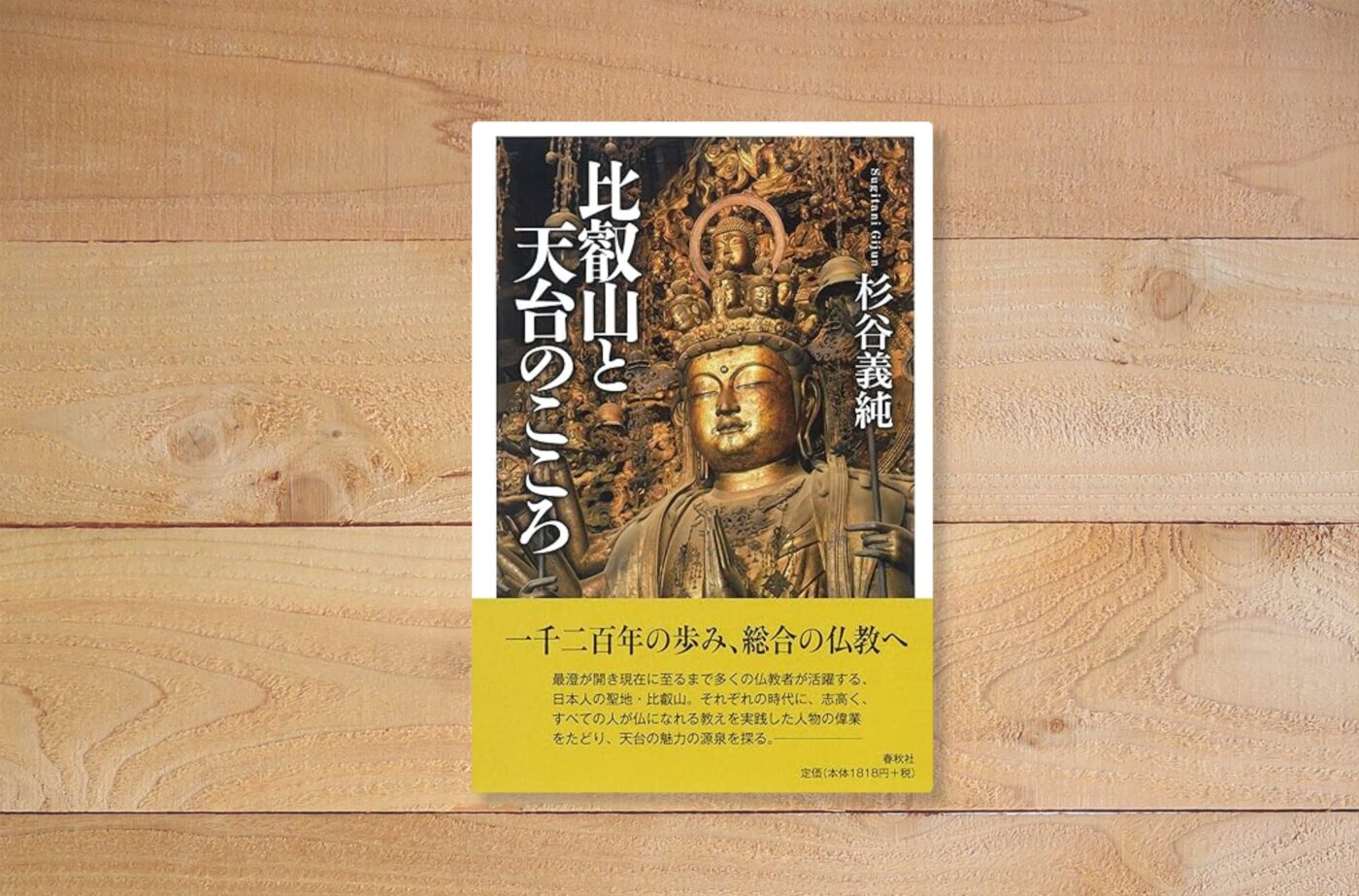山田奨治『東京ブギウギと鈴木大拙』あらすじと感想~近代仏教の大家の知られざる家庭生活を知れる刺激的な一冊
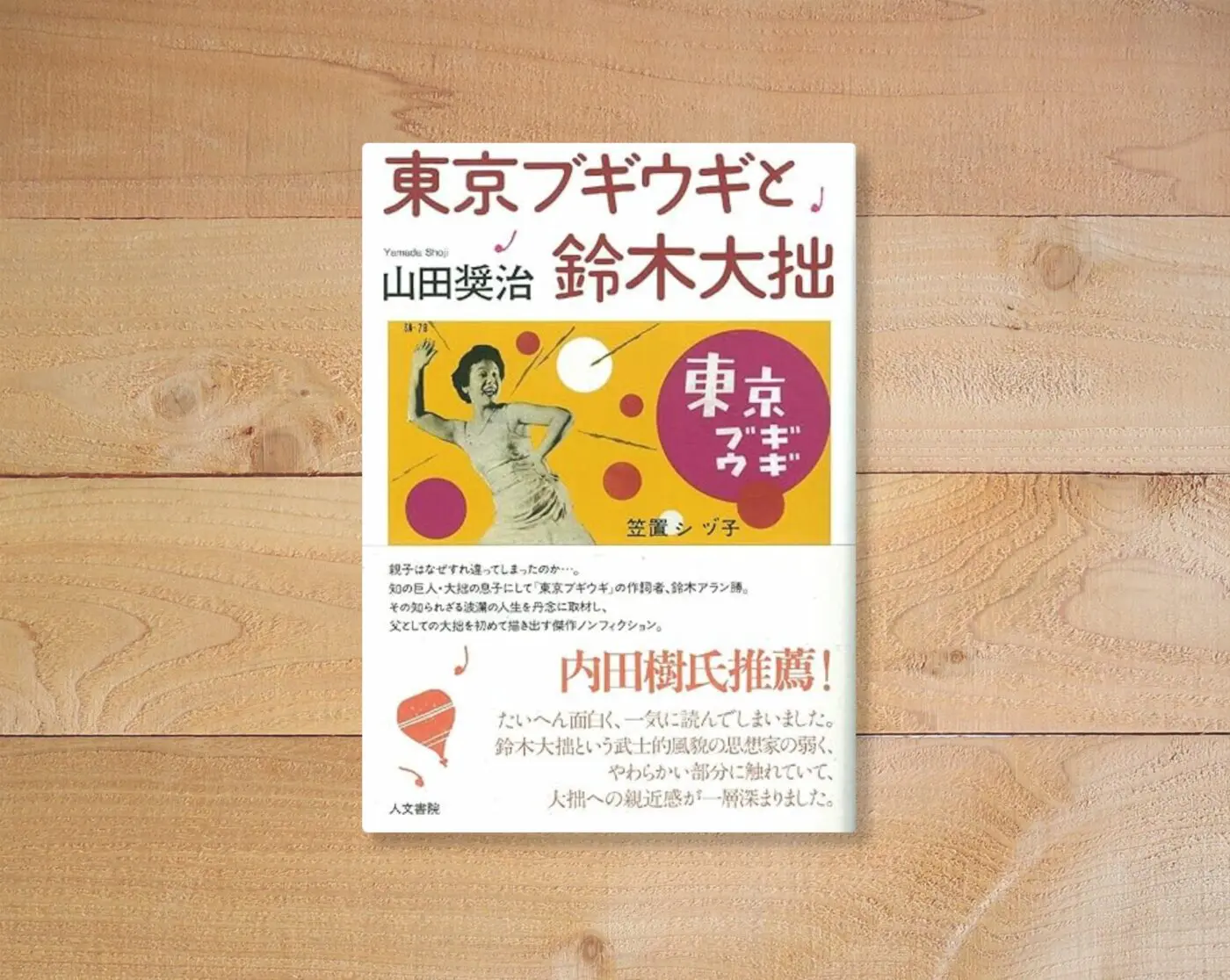
山田奨治『東京ブギウギと鈴木大拙』あらすじと感想~近代仏教の大家の知られざる家庭生活を知れる刺激的な一冊
今回ご紹介するのは2015年に人文書院より発行された山田奨治著『東京ブギウギと鈴木大拙』です。
早速この本について見ていきましょう。
親子はなぜすれ違ってしまったのか…。知の巨人・大拙の息子にして「東京ブギウギ」の作詞者、鈴木アラン勝。その知られざる波瀾の人生を丹念に取材し、父としての大拙を初めて描き出す傑作ノンフィクション。「ここには成人したアランの、大拙の仕事に対するみかたが明確にあらわれている。父がやっているような日本の精神文化や伝統的なことは、彼にとっては「骨董品的存在」なのだ。それはそれとしてこれからも存在するだろうが、現代社会が求めるものとは異なる。自分は父とは違う道を行く――これがアランの意思だったと思う。」(本書より)
Amazon商品紹介ページより
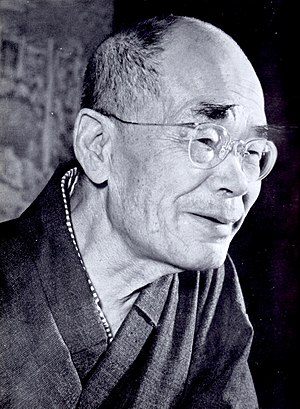
本書のタイトルにもある鈴木大拙は世界で最も有名な日本人仏教学者と言っても過言ではない人物です。現在でも日本の禅や仏教文化を西洋に広めた第一人者として知られています。私達僧侶業界においても知らぬ人がいない大人物です。特に有名な著作として『日本的霊性』があり、親鸞の『教行信証』の英訳も出版しています。
そんな伝説的な偉人鈴木大拙についての意外な事実が掘り起こしていくのが本書『東京ブギウギと鈴木大拙』という作品になります。
東京ブギウギといえば数年前の朝ドラ『ブギウギ』で話題になりました。
今やクリアアサヒのCMのイメージがあるかもしれませんが、笠置シヅ子の『東京ブギウギ』は時代を象徴する楽曲として爆発的なヒットとなりました。そしてなんとこの曲の作詞を担当したのが何を隠そう、鈴木大拙の息子鈴木勝(通称アラン)なのでありました。
これには私も驚きました。あの鈴木大拙にこのような大きな仕事をした息子がいたとは全く知らなかったのです。しかも仏教学者としてとても固いイメージがあった大拙の息子が芸能関係の仕事をしていたというのも意外でした。
ただ、私がこうしたことに驚いたのもある意味必然でした。
なぜなら、鈴木大拙にこうした息子がいたことがこれまでほとんど語られていなかった、いや黙殺されてきた事実があったのです。本書冒頭でこのことについて次のように述べられています。
アランは無名のひとではなかった。戦後を代表する歌謡曲「東京ブギウギ」(一九四七)を作詞し、「スゥイングの女王」と呼ばれた歌手の池真理子(一九一七-二〇〇〇)とかつて結婚していた。ところが、一時代を代表する歌を世に送り出したにもかかわらず、アランの記録は少ない。大拙にアランという養子がいたことについて、多くを語るひともいない。大拙の周囲にいる者にとって、アランは触れたくない存在になっていた。アランのことを「不肖の息子」と呼ぶひともいた。
それには理由があった。アランは、分別盛りのはずの四〇歳代に、週刊誌沙汰になる事件の主役になってしまったのだ。
アランのことを孫引きではなく書いたひとは、そう多くはない。林田久美野の『大叔父』は、大拙の近くに永く仕え、そしてアランの許でもあったという著者によるものである。それだけに、アランについても大拙の私的な面についても、類書のないほど多くの証言を含んでいて、本書もそれを貴重な引用文献にしている。
久美野は同世代のアランを子どもの頃から知っていた。その久美野は、軽率ないい方は慎みたいとはしながらも、アランが道を踏み外すような人間に育ってしまったことは、「やはり家庭環境に問題があったと推察せざるを得ません」と書いている。当時の父親はだれも似たり寄ったりだったとしながらも、「自分の研究時間を削ってでも子供と遊んでやる、子供と接していて時を忘れるといった父親ではなかったと思います」とも久美野はいう。
研究者のほとんどは、アランのことを黙殺している。大拙をアランとの関係から考えようという意欲もない。そんななかで、仏教学者の横山ウェイン茂人(一九四八一)は、短いがかなり踏み込んだアラン評を書いている。
大人になってから、アランの多才な面が素晴らしく発揮され、優雅で自由な人となった。アランが父親である鈴木先生を尊敬し、大事にしてきたのに対し、鈴木先生はアランに対し閉鎖的な立場を取ったのは事実です。それは実に残念な事です。というのは、先生が自分の息子から「謙遜」の教訓を単び得たかもしれません。(松ケ岡文庫編『鈴木大拙没後四〇年』、以後、『没後四〇年』)
これは大拙の没後四〇年の記念出版物に収められた文章だ。横山はアランの人生を評価し、大拙の父親業を批判しているとも受け取れる。横山は大拙の英文日記を翻刻した学者でもあり、松ケ岡文庫が所蔵する一次資料に接する機会は、ほかの研究者よりも格段に多い。アランは大拙を尊敬していたのに、大拙は閉鎖的だったと、その横山が断言している。(中略)
アランの記録は本当に少ない。もし彼が大拙の志を継ごうとする子であったなら、もっと多くのことばがいまの世に遺されていたに違いない。
大拙が遺したことばは幾千万とある。全集だけでも四〇巻もあり、それに入っていない文献も相当な量あるとみられる。松ケ岡文庫には、大拙の膨大な原稿や日記、蔵書がいまでも大切に保管されている。世界各地の図書館や個人のもとにある、未だ知られていない記録もあるに違いない。それらすべてをじっくり読もうとしたら、たとえ一生を費やしても時間が足りない。
饒舌な父よりも、ことばを遺すことができなかった息子の声が聴きたい。この破綻したようにみえる父子関係には、何か大事なメッセージが隠されているように思う。期待通りに育たなかった子に親はどう接するべきなのかーこの普遍的なテーマに、大拙も苦悩していた。それを研究者は読み損なってきたのではないか。
臨済宗の高僧・西村恵信(一九三三ー)は、大拙の優れた評伝『鈴木大拙の原風景』(一九九三)で、「およそ偉人の伝記は、その目撃者である直接の弟子たちによって記録されるのが常であるが、その場合、多く過大の粉飾がなされ、いたずらな神話化が行われるのが普通である。それらがもう一度非神話化されてこそ真に客観的な真実性が浮き彫りにされてくるというものであろう」と、弟子筋が書いた大拙伝を暗に批判している。大拙の門下ではない西村は、偉人の神話化に与しない立場を取りながらも、同書ではアランのことにはほとんど触れていない。大拙の半生を詳細に復元した研究でありながら、西村がアランについて書かなかったのは、なぜなのだろうか。
ある人物をよき人間として描くためには、隠さなければならないこともあろう。世の大拙伝にとっては、アランがそれだったのかもしれない。しかしそれでは、大拙の生涯の大事な一面がみえなくなってしまう。アランの存在をしっかりとみすえることで、大拙の違った側面がわかるはずだ。大拙のことばの端々にあらわれていた、子への思いや悩みも浮き上がってくる。(中略)
偉大すぎる親を持った子の苦悩、ままならぬ子を持った親の葛藤、「東京ブギウギ」の歌詞を書いた鈴木アラン勝を知ること、鈴木大拙をもっとよく知ることー情熱にかられて無軌道な行動をするドン・キホーテのような知の旅に、読者をしばしお連れしたい。
人文書院、山田奨治『東京ブギウギと鈴木大拙』P12-17
「期待通りに育たなかった子に親はどう接するべきなのかーこの普遍的なテーマに、大拙も苦悩していた。それを研究者は読み損なってきたのではないか。」
「偉大すぎる親を持った子の苦悩、ままならぬ子を持った親の葛藤」
まさにこれは普遍的なテーマですよね。この本は鈴木大拙という人物を知らなくとも楽しめる一冊ですが、仏教関係者に特におすすめしたい作品です。
昭和の仏教の偉人や先生には破天荒なエピソードが数多く伝わっていますが、それを現代を生きる私達がどう捉えるべきなのかも考えさせられます。
また、本書の著者山田奨治氏には『禅という名の日本丸』という著書もあるのですがこちらもおすすめです。この本も鈴木大拙をはじめとした近代日本仏教の実態を明らかにする衝撃の一冊です。
この本の主題そのものは鈴木大拙ではありませんが、日本における禅のイメージを決定づけた『弓と禅』がこの本のメインテーマとなります。
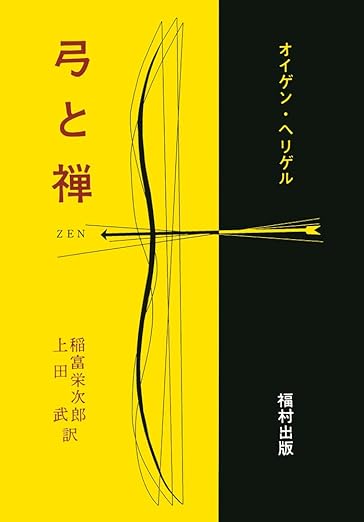
1956年に日本で発刊されたオイゲン・ヘリゲルの『弓と禅』は、日本文化と禅の関係性を述べた名著として圧倒的な評価を受けてきた作品です。私もこの本を禅と武道の関係性を説いた古典としてかつてこの本を読んだことがあります。
しかし、この禅の名著とされてきた『弓と禅』が実は禅とはほとんど関係のないものだったのです。
本書ではそんな驚くべき事実が暴露されます。これはもう衝撃以外の何物でもありません。日本文化とは何ぞやという命題がそもそもひっくり返るほどの大事件です。本書のまとめに書かれた次の言葉は特に印象的です。
「~こそ日本文化を代表するものだ」と、世間に流通している言説は、その成り立ちを一度は疑ってみたほうがよい。ハイ・カルチャーからサブ・カルチャーまで、文化のあらゆる領域で、昔もいまもおなじようなことが起きている。
弘文堂、山田奨治『禅という名の日本丸』P346
そうです。まさに「禅こそ日本文化を代表するものだ」という言説こそ、戦後に作られたものだったのです。私達は日本文化を伝統あるものと思い込んでいますが、実はその文化こそ近年構築されたものだったということが多々あるのです。
『東京ブギウギと鈴木大拙』でも鈴木大拙が伝説化され、都合の悪いものを消しながらイメージが作られていたことが明らかにされましたが、これは大拙だけの問題だけでなく、日本におけるあらゆるジャンルにもその可能性があるのです。まさに「創られた伝統」です。「はるか昔から日本人が受け継ぎ大切にしてきた」と私達が思い込んでいるものがはたして本当にそのようなものなのかという恐ろしい事実が浮かび上がってきます。
『禅という名の日本丸』にはそうしたある種戦慄の事実が書かれています。これは僧侶の方にぜひ読んで頂きたい驚異の名著です。
『東京ブギウギと鈴木大拙』と合わせて読まれることをおすすめします。
以上、「山田奨治『東京ブギウギと鈴木大拙』あらすじと感想~近代仏教の大家の知られざる家庭生活を知れる刺激的な一冊」でした。
Amazon商品紹介ページはこちら
次の記事はこちら
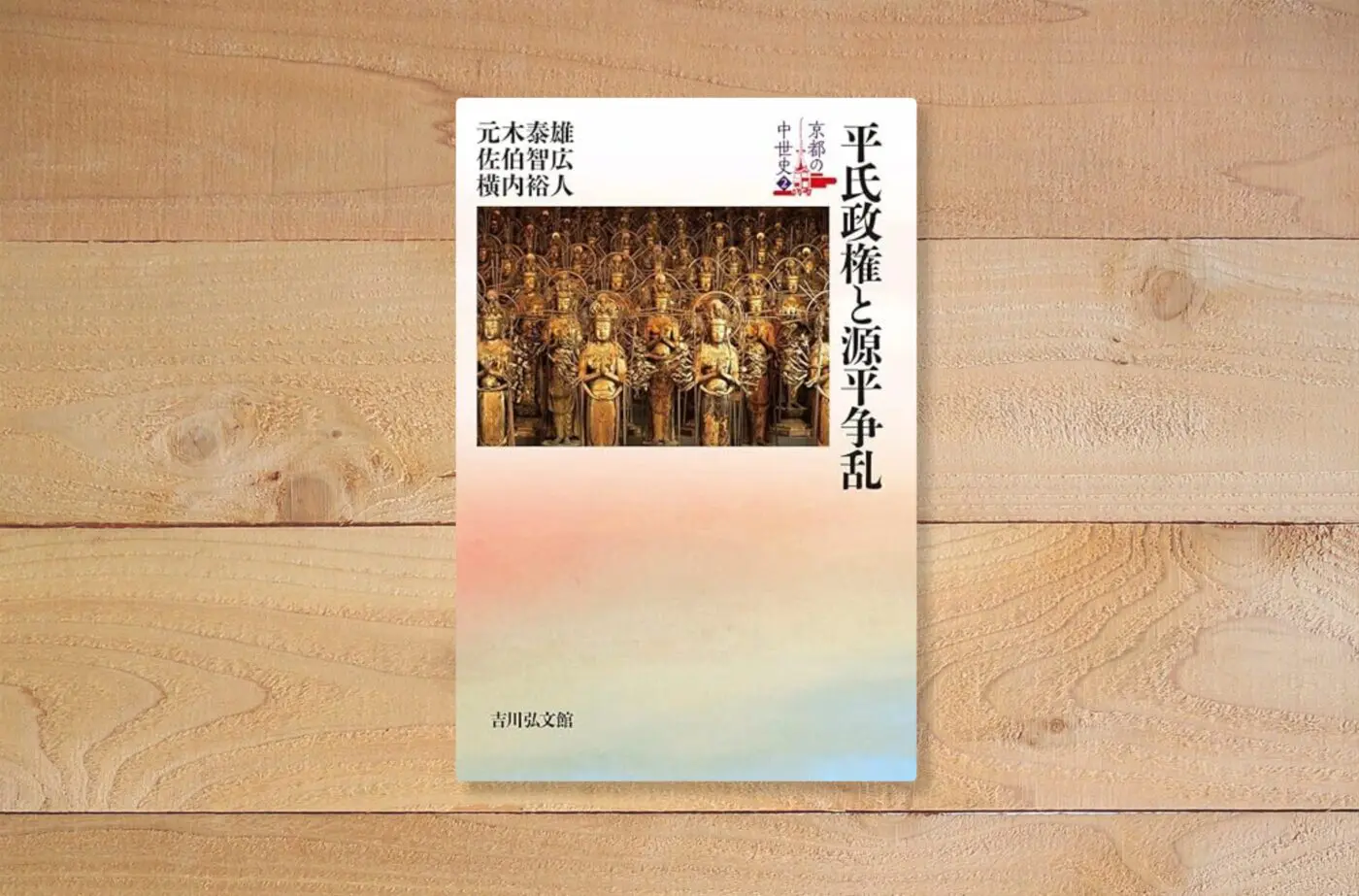
関連記事