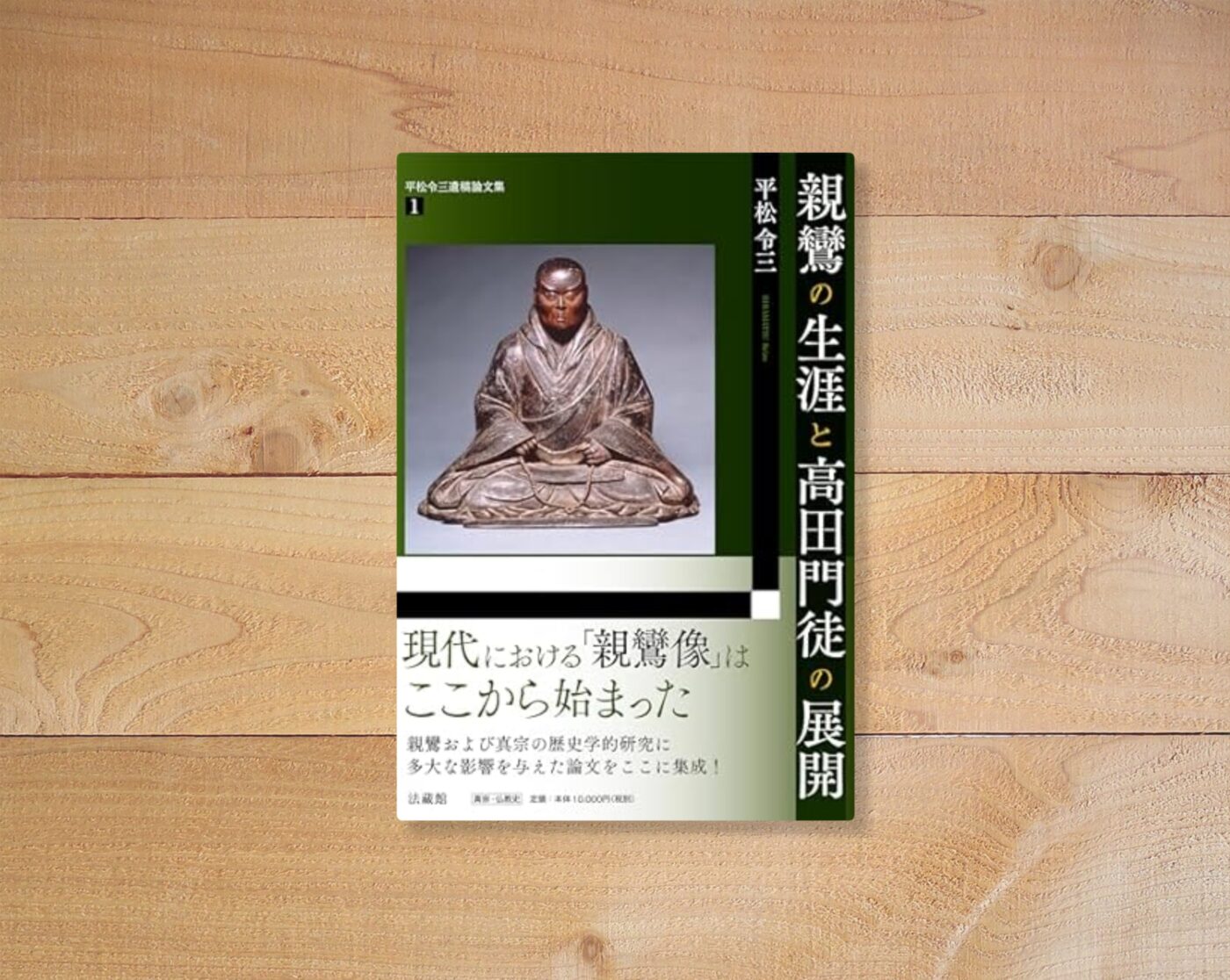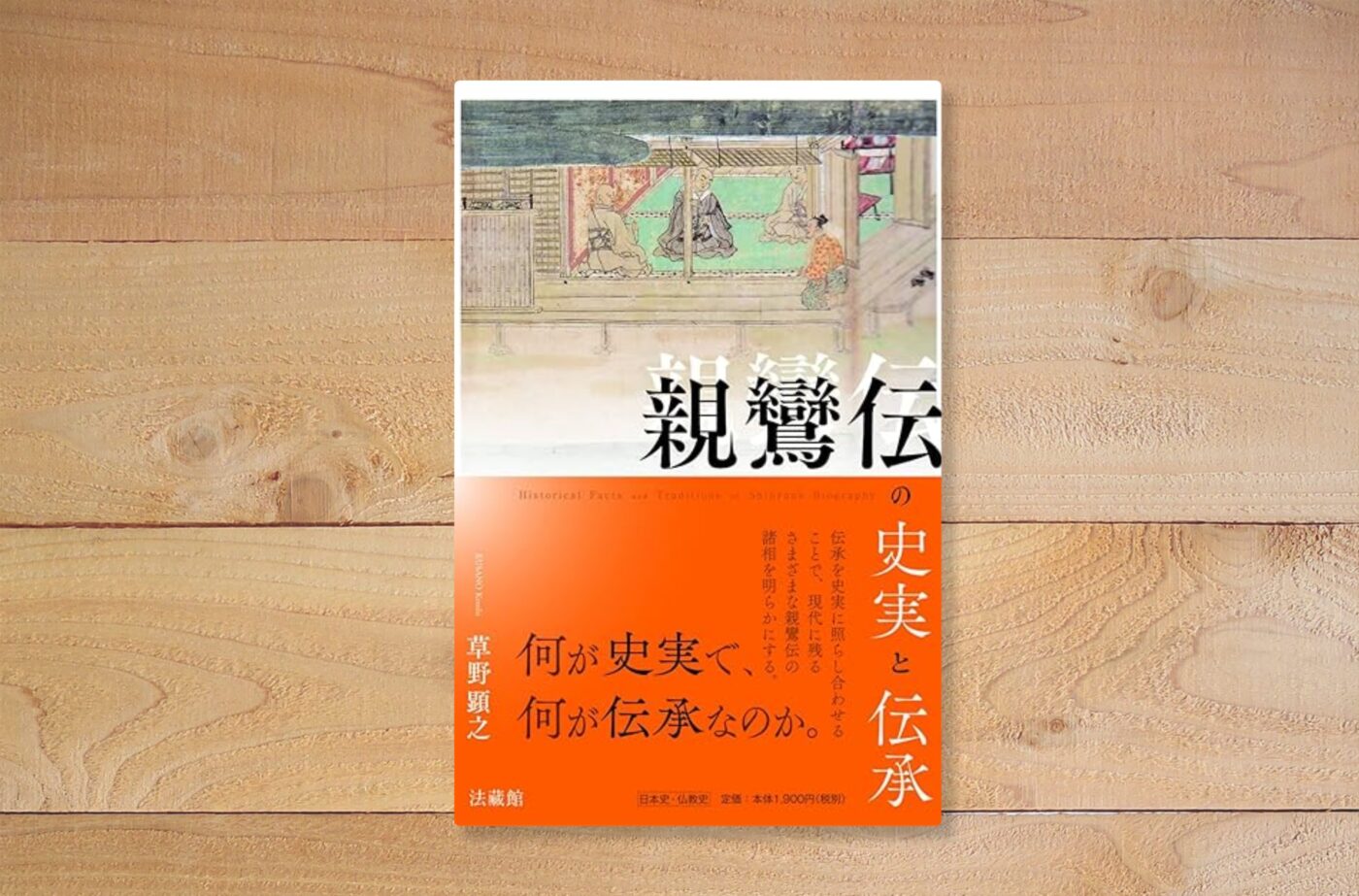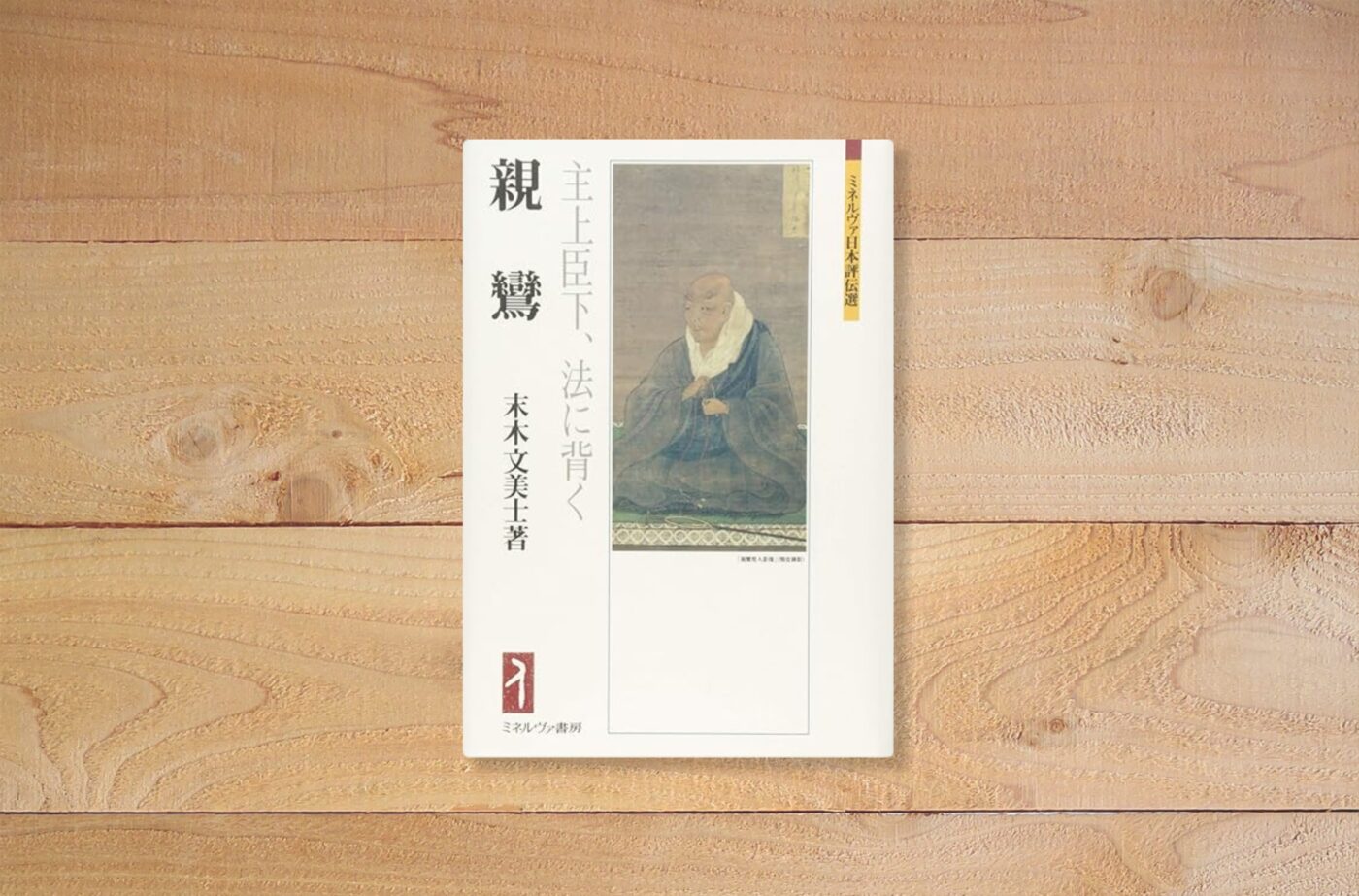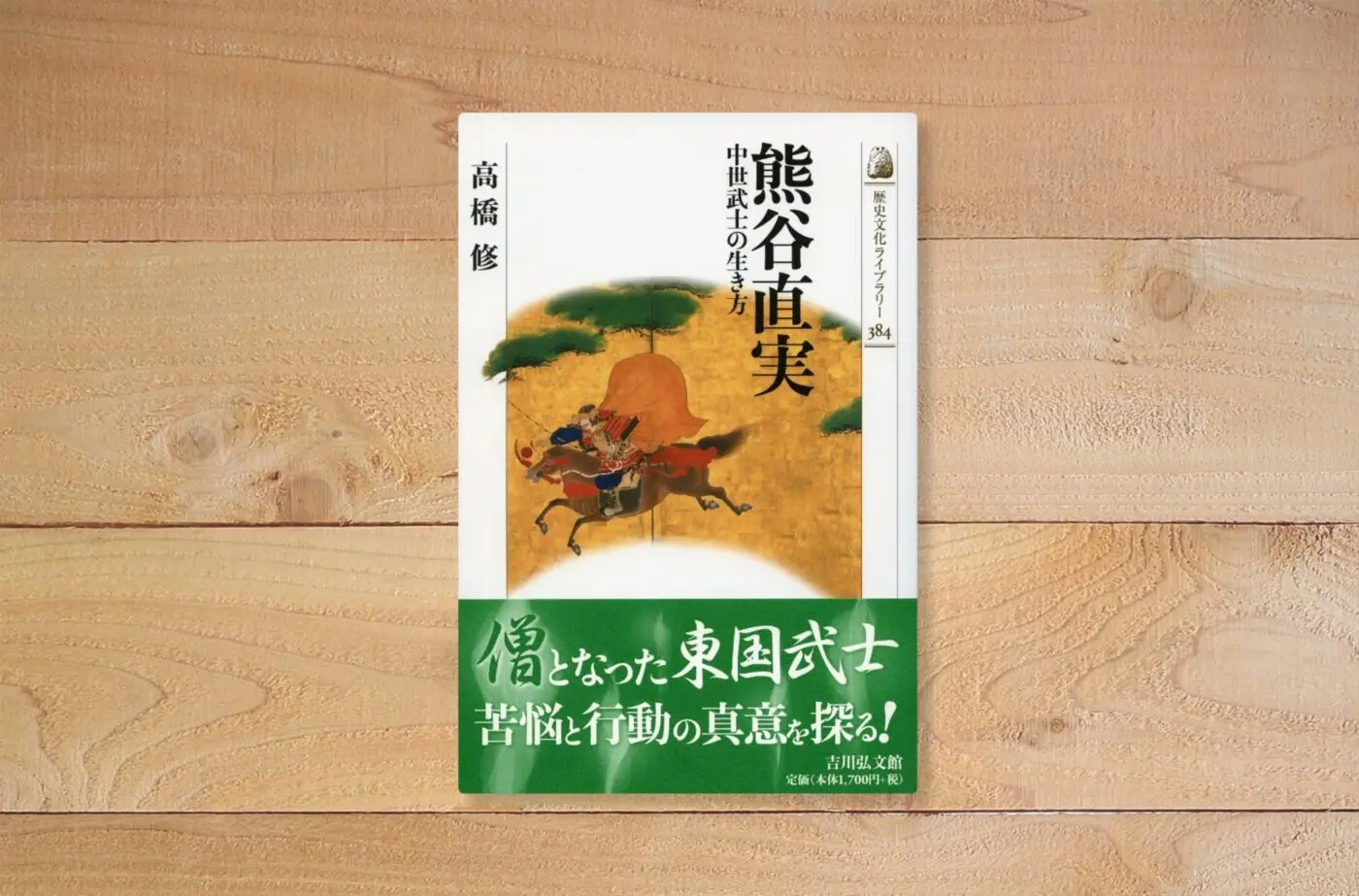西岡常一、小原二郎『法隆寺を支えた木[改版]』あらすじと感想~木の奥深さに驚くこと間違いなしの名著!日本人にとって木はどんな存在だったのか
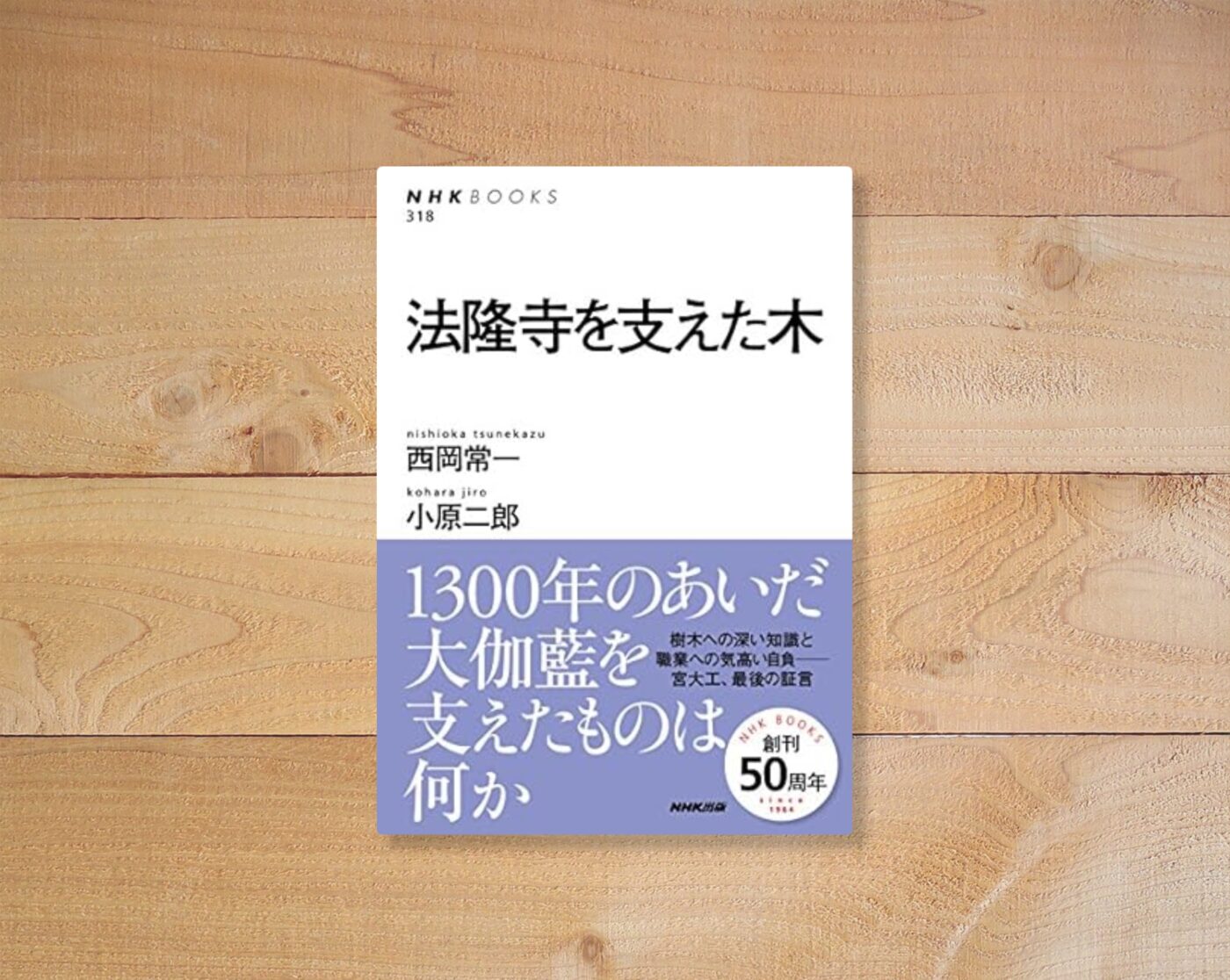
西岡常一、小原二郎『法隆寺を支えた木[改版]』あらすじと感想~木の奥深さに驚くこと間違いなしの名著!日本人にとって木はどんな存在だったのか
今回ご紹介するのは1978年にNHK出版より発行された西岡常一、小原二郎著『法隆寺を支えた木』です。私が読んだのは2023年改版第4刷版です。
早速この本について見ていきましょう。
やっぱりヒノキ 1000年超えても大丈夫!
1978年の初版から40年にわたり90回を超える増刷を重ねたロングセラーを読みやすく改版! 貧窮にめげず一子相伝の「宮大工」を生きた西岡氏と、軍隊帰りの厳しい姿勢で農学を究めた小原氏がタッグを組み、世界遺産・法隆寺の奇蹟を解き明かした力作。近年英訳され、欧米の研究機関でも読まれるようになった。ヒノキが生んだ「世界最古の建築物」の謎を易しく解説する、不朽の名著!
NHK出版商品紹介ページより

法隆寺は世界最古の木造建築として有名ですが、私は以前、この木造建築が近年に至るまで修理や改築を何度も繰り返したものと思い込んでいました。しかし最近このお寺の歴史を改めて学んで驚きました。なんと、法隆寺の木は1300年前から変わらず美しい姿を保ったままだというのです!もちろん全ての木が最初のままというわけではありませんが主要な柱部分など1300年も前の木がそのまま残っているというのは改めて考えるととてつもない事実ですよね。
本書はそんな驚異の木材たるヒノキについて深く学べるおすすめ解説書となっています。

この画像はタイワンヒノキという台湾の山奥にある巨大なヒノキなのですが、かつて日本にもこうした樹齢1000年超の巨大なヒノキが生えていたそうです。法隆寺はもちろん、東大寺や薬師寺などもこうした樹齢1000年超の巨大なヒノキを用いて建設されています。
ただ、平安末期にはすでにこうした巨木はほとんど日本では切り倒されてしまい、1180年の東大寺焼き討ち後の再建事業は大変な苦労があったそうです。大仏勧進職の重源は遠く周防国(山口県)の山奥まで木を探しに行ったとされています。
そして現代に至り薬師寺の再建ではもはやこのような巨木は日本に残されていなかったため、上のような台湾の巨木を輸入するという運びになったのでした。しかし間もなく台湾でもこうした貴重な巨木の伐採は禁止され、現在ではもはや樹齢1000年超の巨大ヒノキを材木利用することは不可能となっています。
本書ではこのヒノキがなぜ古代建築において重宝されたのか、なぜ1000年経っても無事に残り続けているのかということを学ぶことができます。
私達は法隆寺や薬師寺などの美しい伽藍に心奪われますが、材木そのものについて考えることはなかなかありません。ですが、この材木にこそ古代人の心が宿っているとしたらどうでしょう。伽藍を成立させている木の秘密を知れば、お寺に対する見え方がまた変わること間違いなしです。
本書は私達に新しい視点をくれる実に刺激的な一冊です。
紹介したい箇所が山ほどあるのですが、私の中で特に印象に残った箇所をここで紹介します。
いうまでもなく、木はかつて生命を持っていた細胞の固まりであって、生長のあとを示す木目が、造形材料としての一番大きな特徴になっている。年輪の幅は、樹齢、土壌、気温、湿度、日照などの記録であるから、その中には一年ごとの木の歴史が刻み込まれているわけである。
高温多湿の条件に恵まれた熱帯地方の樹木は年輪をつくらない。年中生長を続けることができるからである。生長期に洪水や旱天に見舞われたり、葉を害虫に食われたりすると生長は止まるが、回復するとふたたび生長を続けるので、一年間に二つの年輪ができる。これが重年輪である。つまり木目は幾星霜の風雪を耐えた木の履歴書なのである。人間にもまた年輪がある。それは精神の中に刻み込まれるから、樹木のように形としてあらわれないが、その人の経験と生きる努力の中から生まれて来た記録である。
だからわれわれは、木の年輪の複雑な紋様の中に、自然と人間との対話を感じ取る。それが木肌の魅力の最大のものといえよう。だから木は、人によって生かされ、人によって使い込まれたとき、本当の美しさが出て来るのである。これは使うほど汚くなって行くプラスチックとは正反対のものである。
日本人は木の香の新しい白木を好むだけではない。ときがたてばやがて灰色にくすんで来る木肌を、こんどは「さび」といった独特の世界観の対象にして、別な立場から賞でるが、それは木がもともと生物材料で、切られて板になったのちも、なおあばれたり狂ったりして、生きものの動きをするところに心をひかれるからである。
NHK出版、西岡常一、小原二郎『法隆寺を支えた木』P126-127
この箇所を読んで私はハッとしました。2023年にスリランカで体験した出来事を思い出したのです。

この記事の中でお話ししたのですが、私たち日本人は興福寺の阿修羅像のような、灰色がかった仏像によりありがたさを感じることが多いのではないでしょうか。

それに対しスリランカでは歴史ある古いお寺であっても仏像は色鮮やかに塗られ、まさに最近作られたかのような雰囲気です。この「古寺と新品のような仏像のコントラスト」に私はとまどったのでありました。
こうしたスリランカでの体験を通して私は改めて日本人と仏像の関係性について思いを馳せることになりました。
ただ、なぜ日本人が古い仏像を尊ぶのかということに関しては私の中でなかなか仮説以上のものは出てきませんでしたが、その有力な手掛かりが上の引用になるのではないかと思います。
特に最後の「木がもともと生物材料で、切られて板になったのちも、なおあばれたり狂ったりして、生きものの動きをするところに心をひかれるからである」というのは大きなポイントです。
自然と共に生きてきた日本人ならではの感性ですよね。木も人間と同じ生き物である。それは木を切り倒して仏像となった後も変わらず生き続けている。だからこそ長い歴史を経ても生き続けるその仏像に心が惹かれるのではないか。
「この永遠に生きる仏像としてのいのち」というのは金子啓明著『運慶のまなざし 宗教彫刻のかたちと霊性』でも語られていたことでした。運慶は永遠に生き続ける存在として仏像を彫り続けていたのです。だからこそ、「壊れたら新しく作り直したらいい、塗り直せばいい」という発想にならないのです。そこに込められた「いのち」を大切に扱う。そしてそれが生き続けていることそのものに手が合わさる。こうした歴史が日本にあるのではないでしょうか。
本書でも、
日本では彫刻に木材を使った割合が非常に多く、その数において九十パーセントをこえる。このように木彫が多いということは、世界にその比を見ない
NHK出版、西岡常一、小原二郎『法隆寺を支えた木』P177
と述べられるのも驚きですよね。私達は木造の仏像が身近にあるのが当たり前のように生活していますが、これは世界でも類を見ないことなのだそうです。これは言われてみないとわからないことですよね。やはり私達が木彫りの木造を好んでいるというのは日本人ならではの文化現象なようです。その大きな要因として、私達と自然、特に木との関係があることを本書では考えていくことになります。
普段なかなか考えることのない視点から私達の宗教心、文化を見ていける本書は実に刺激的です。45年も前に出版された本ですが、時代を超えて今もなお響き続ける名著であることは間違いありません。ぜひおすすめしたい作品です。
以上、「西岡常一、小原二郎『法隆寺を支えた木[改版]』あらすじと感想~木の奥深さに驚くこと間違いなしの名著!日本人にとって木はどんな存在だったのか」でした。
Amazon商品紹介ページはこちら
次の記事はこちら
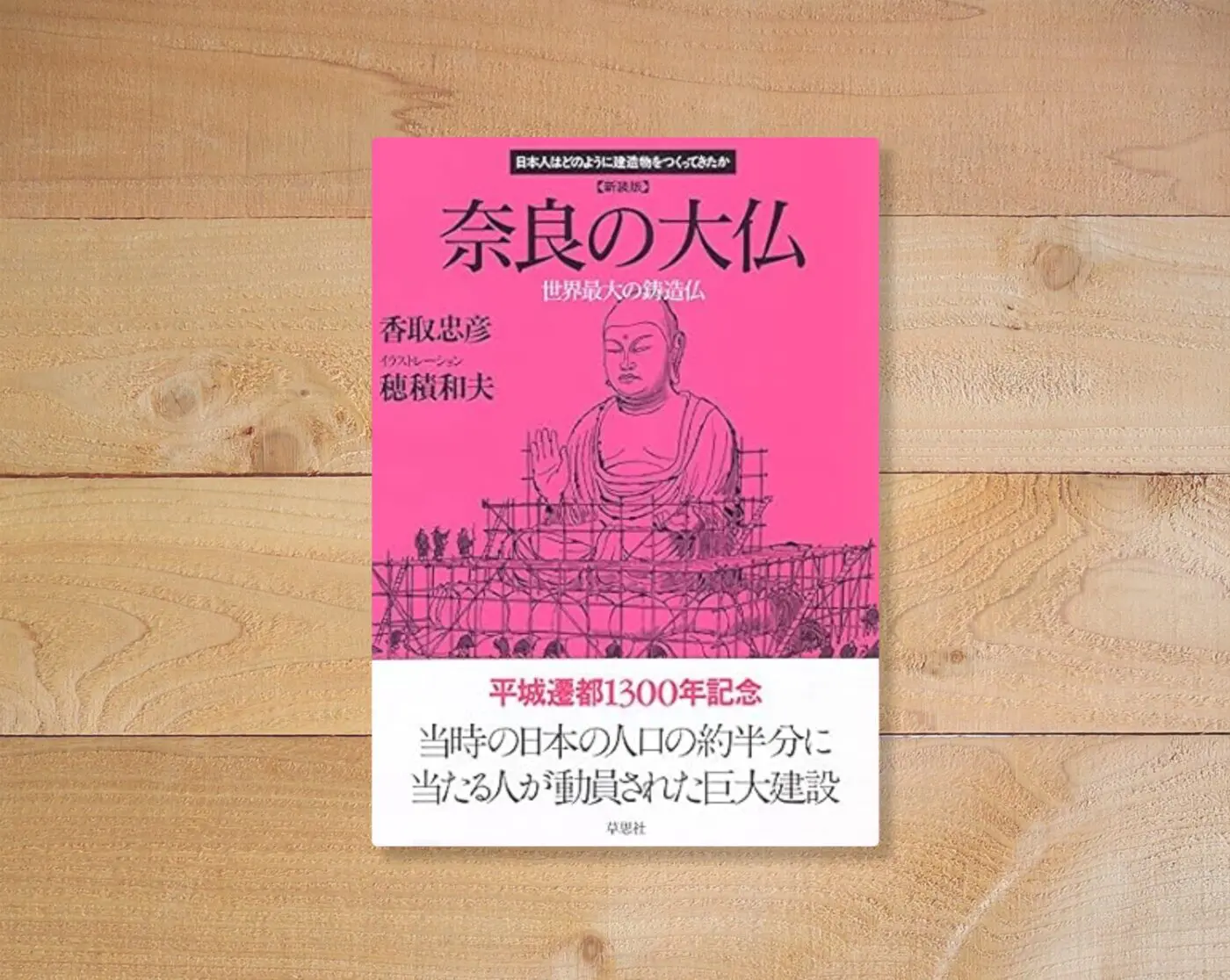
前の記事はこちら
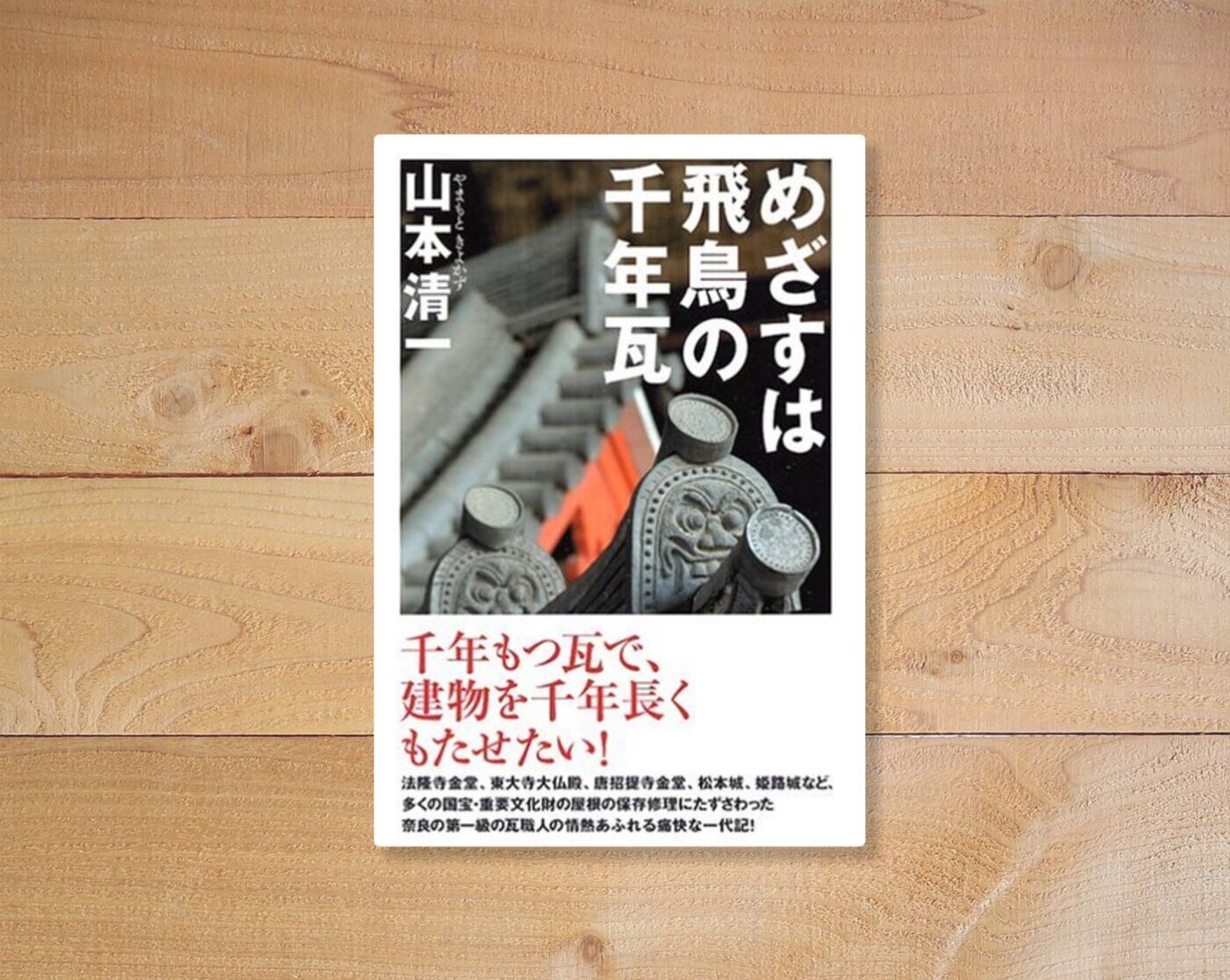
関連記事
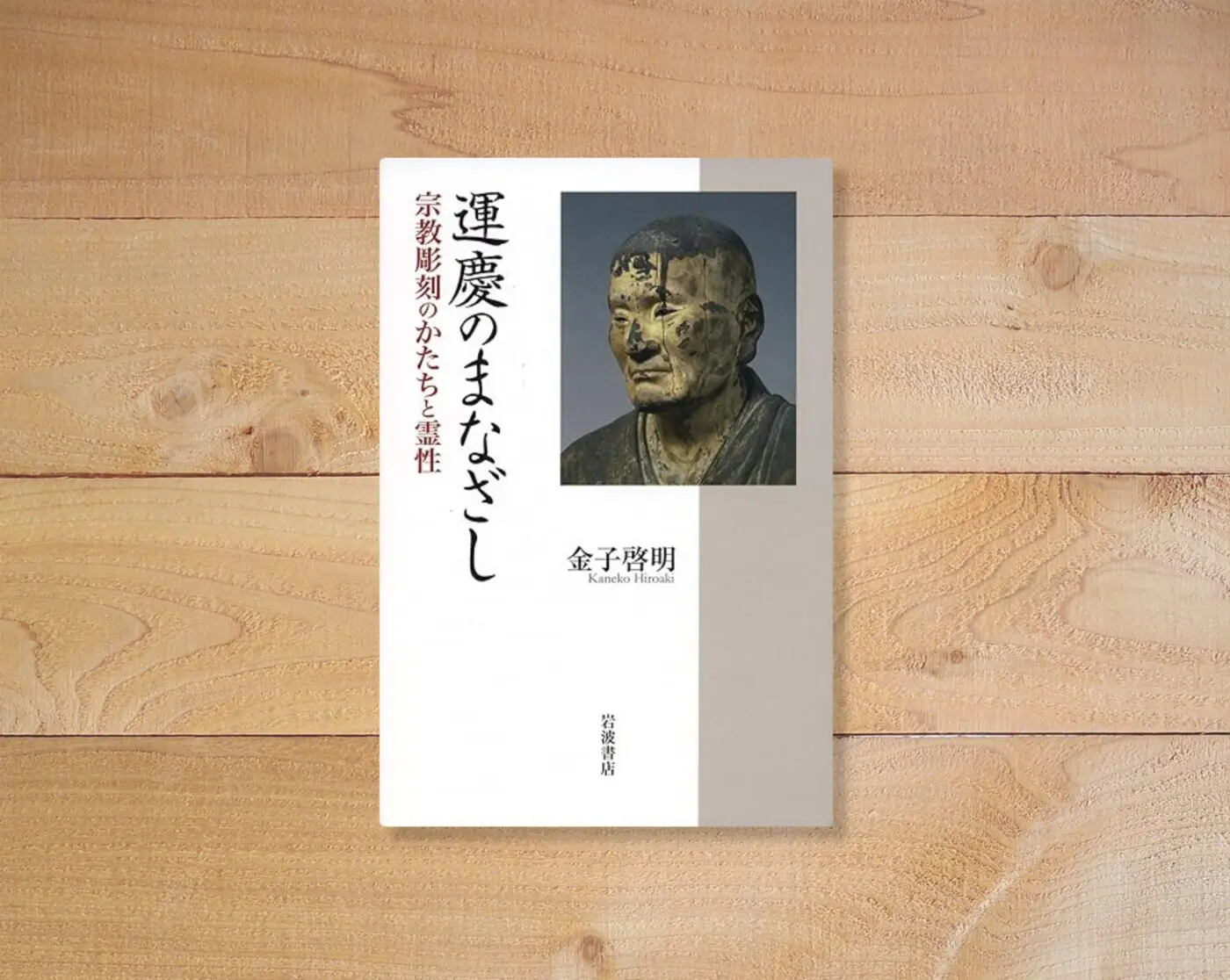
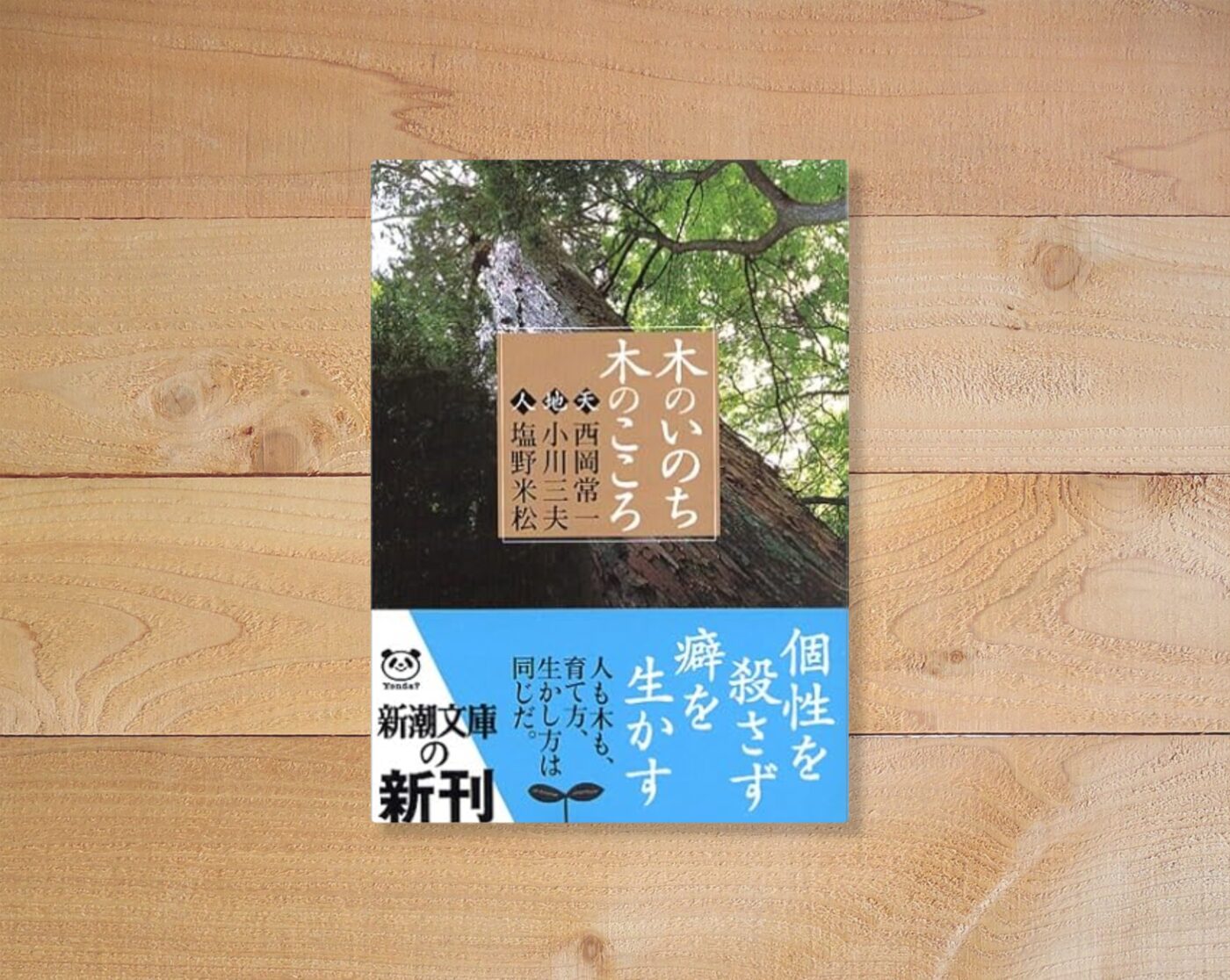
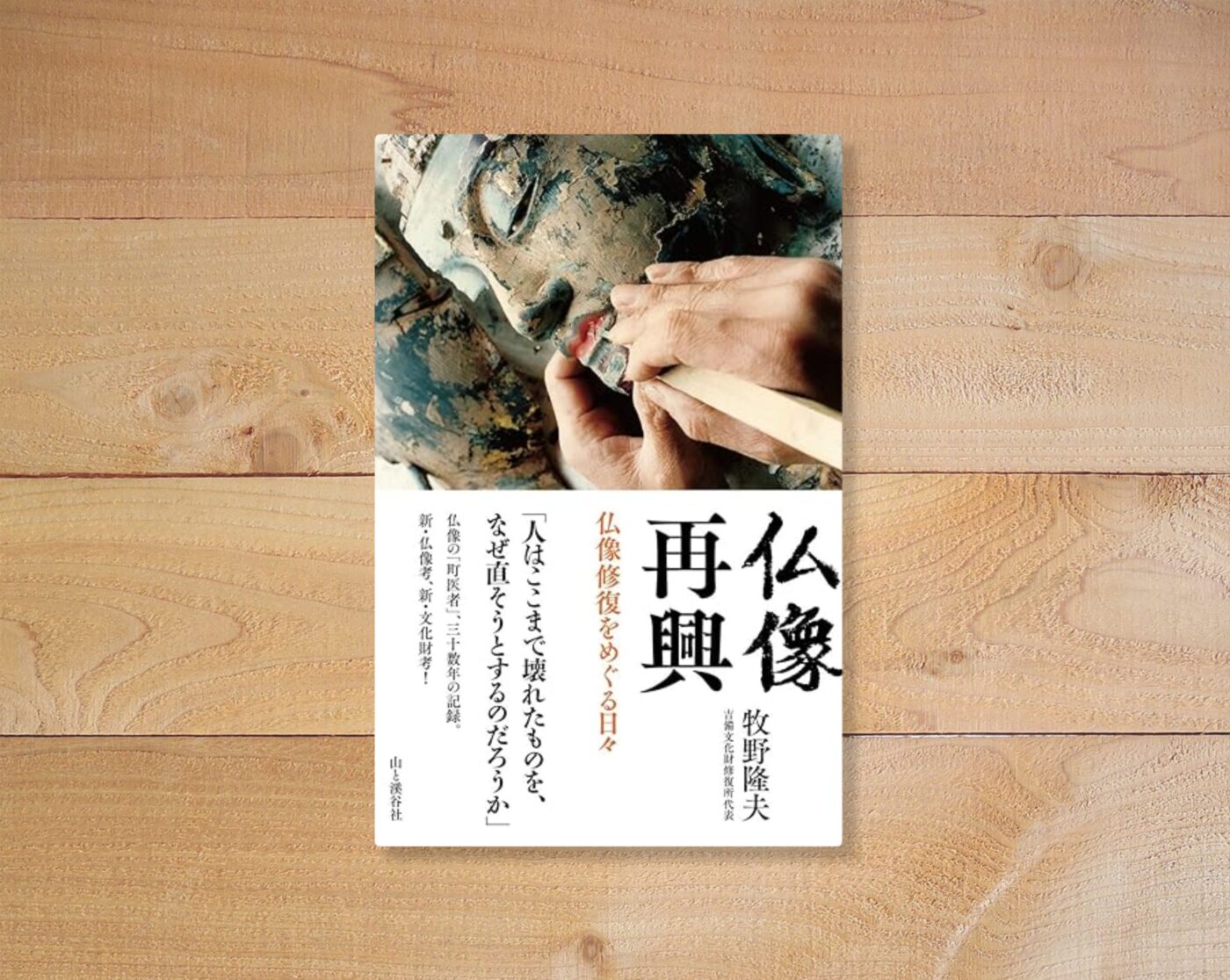
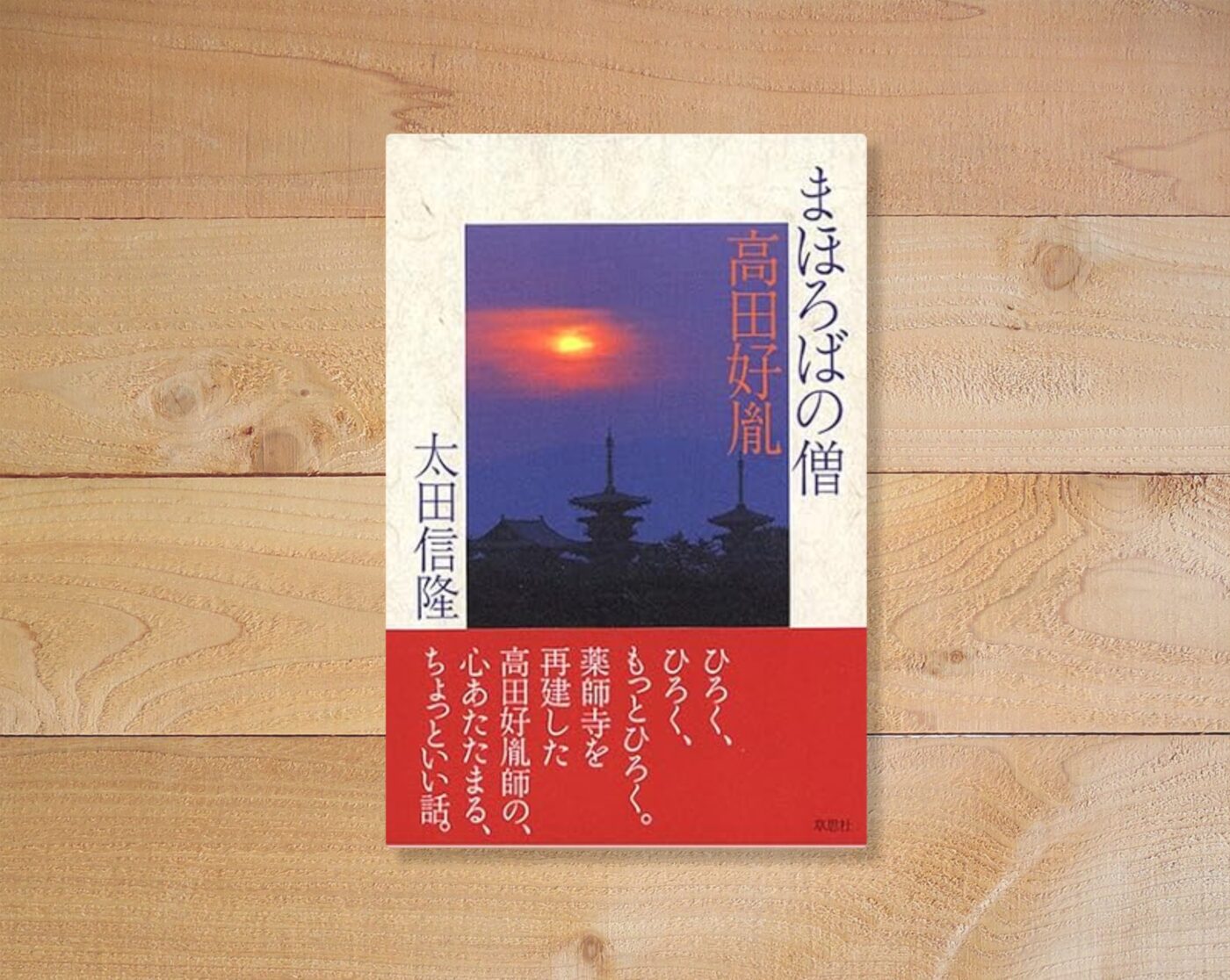
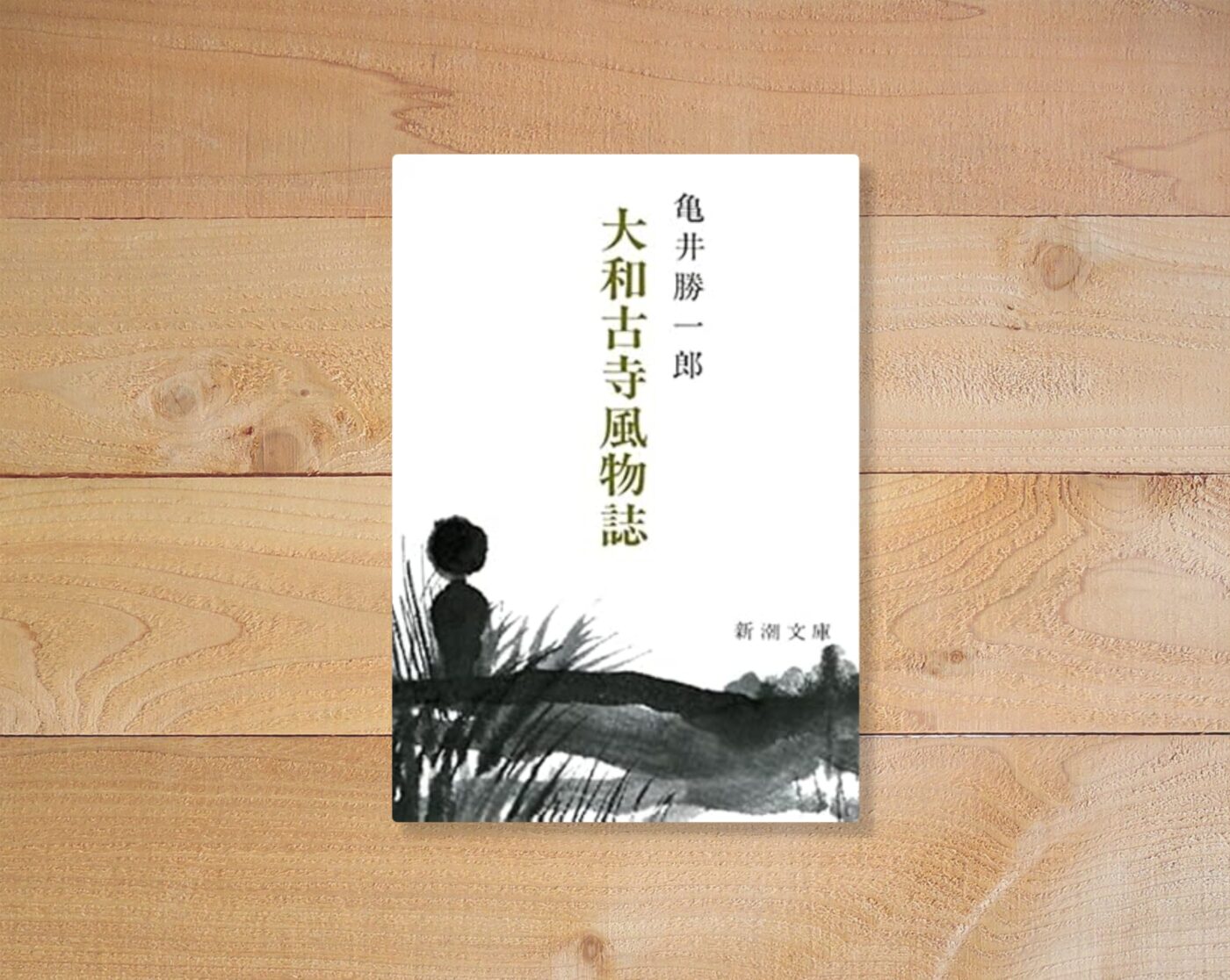
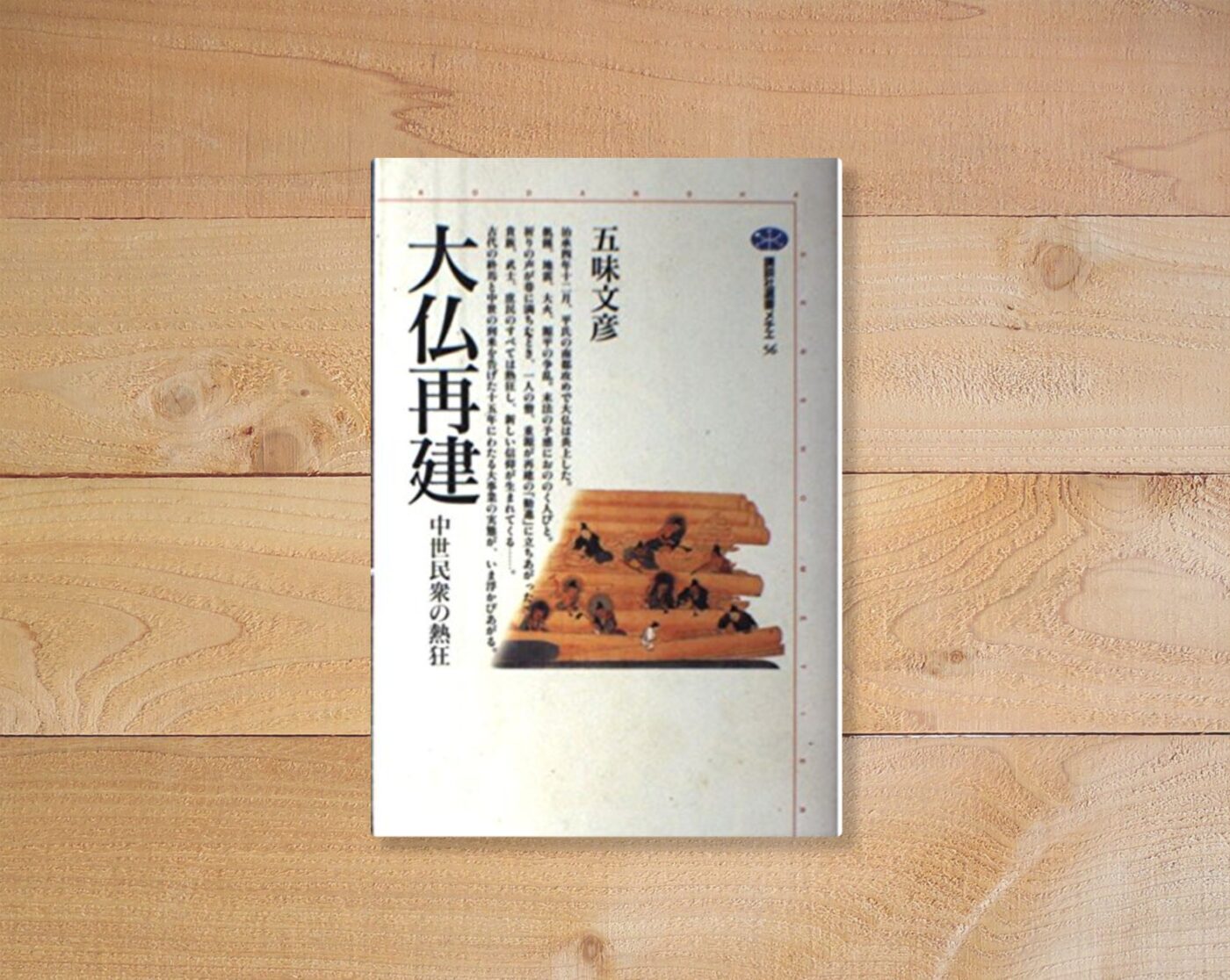
![法隆寺を支えた木 [改版] NHKブックス](https://m.media-amazon.com/images/I/51TbPdeuHhL._SL160_.jpg)