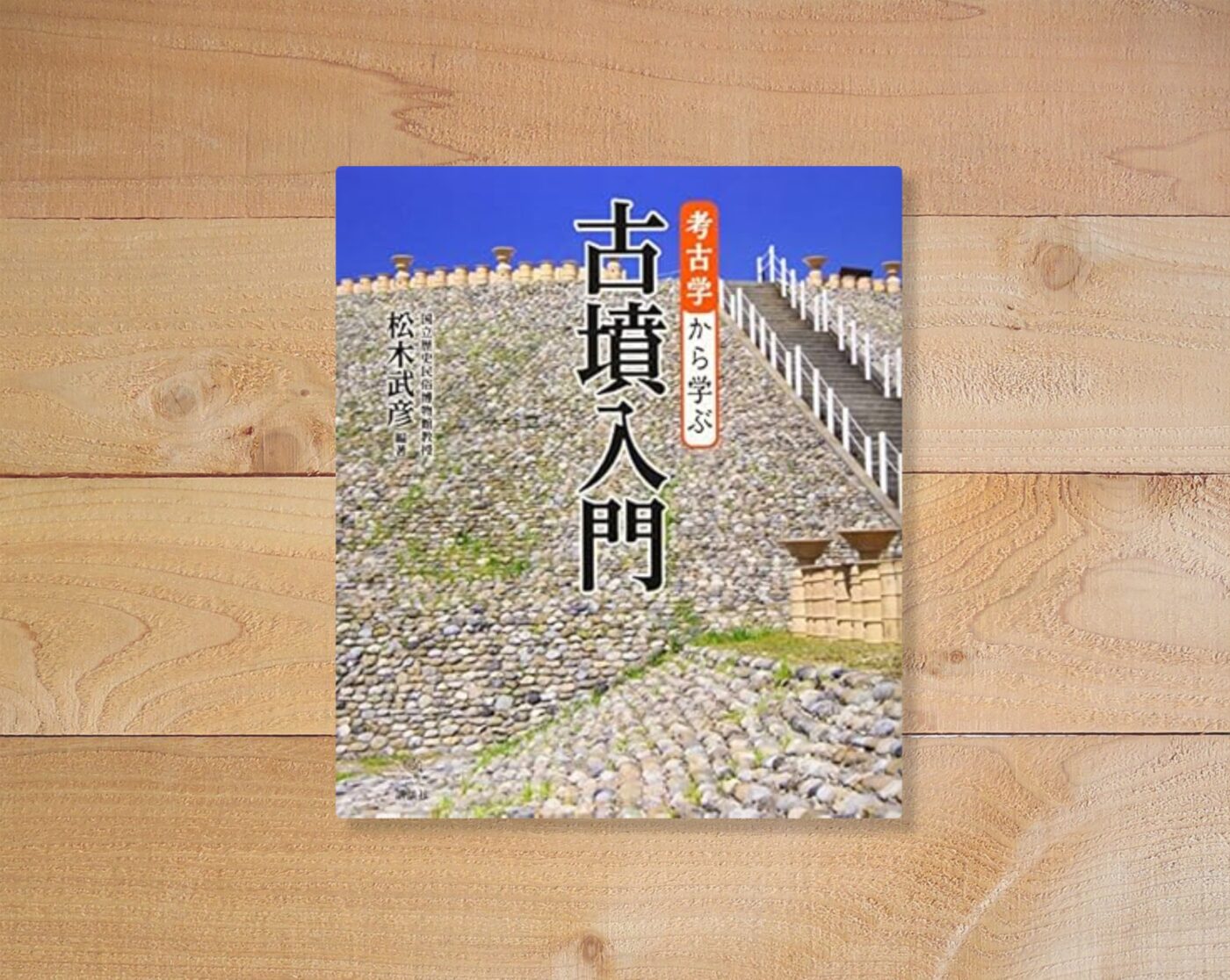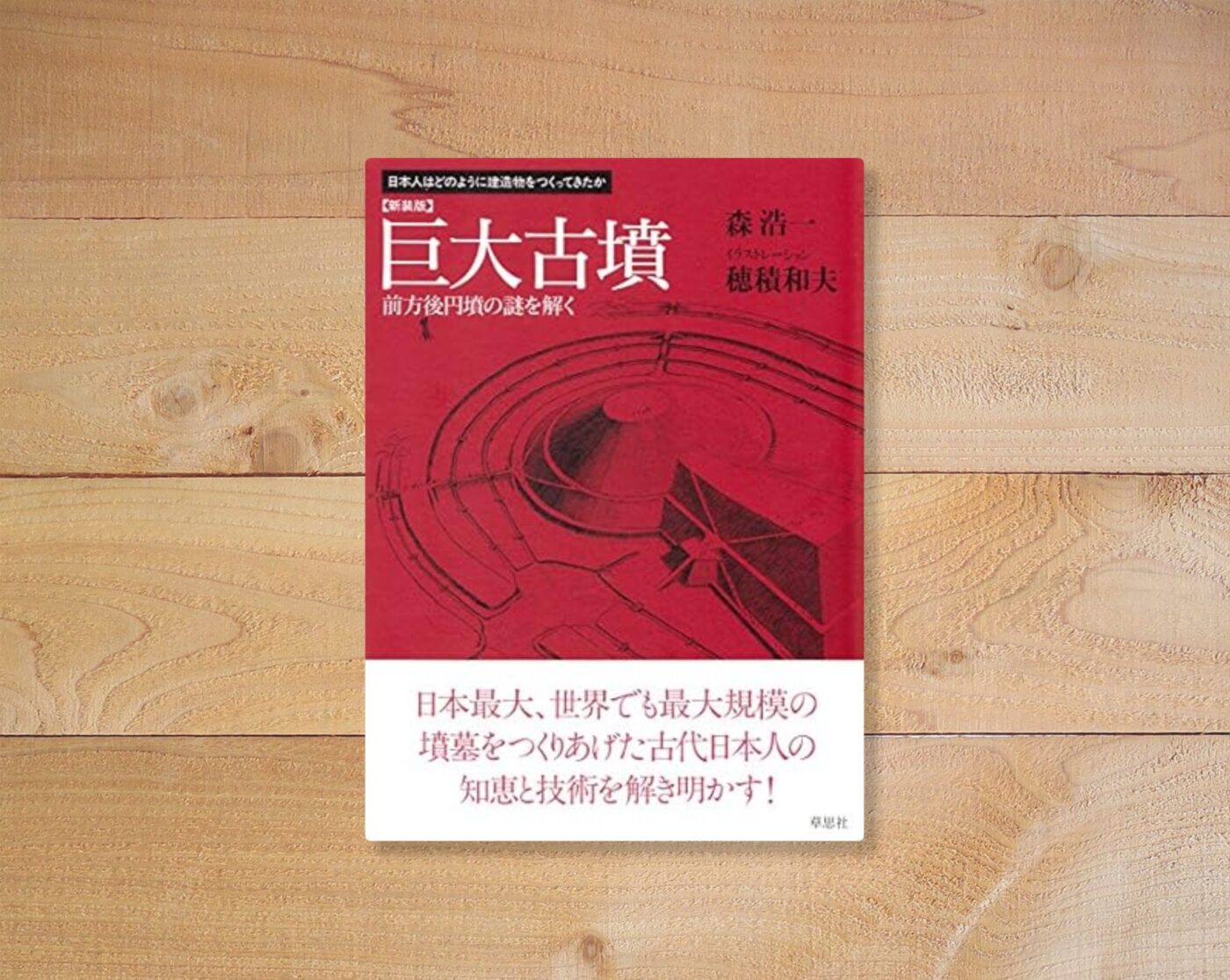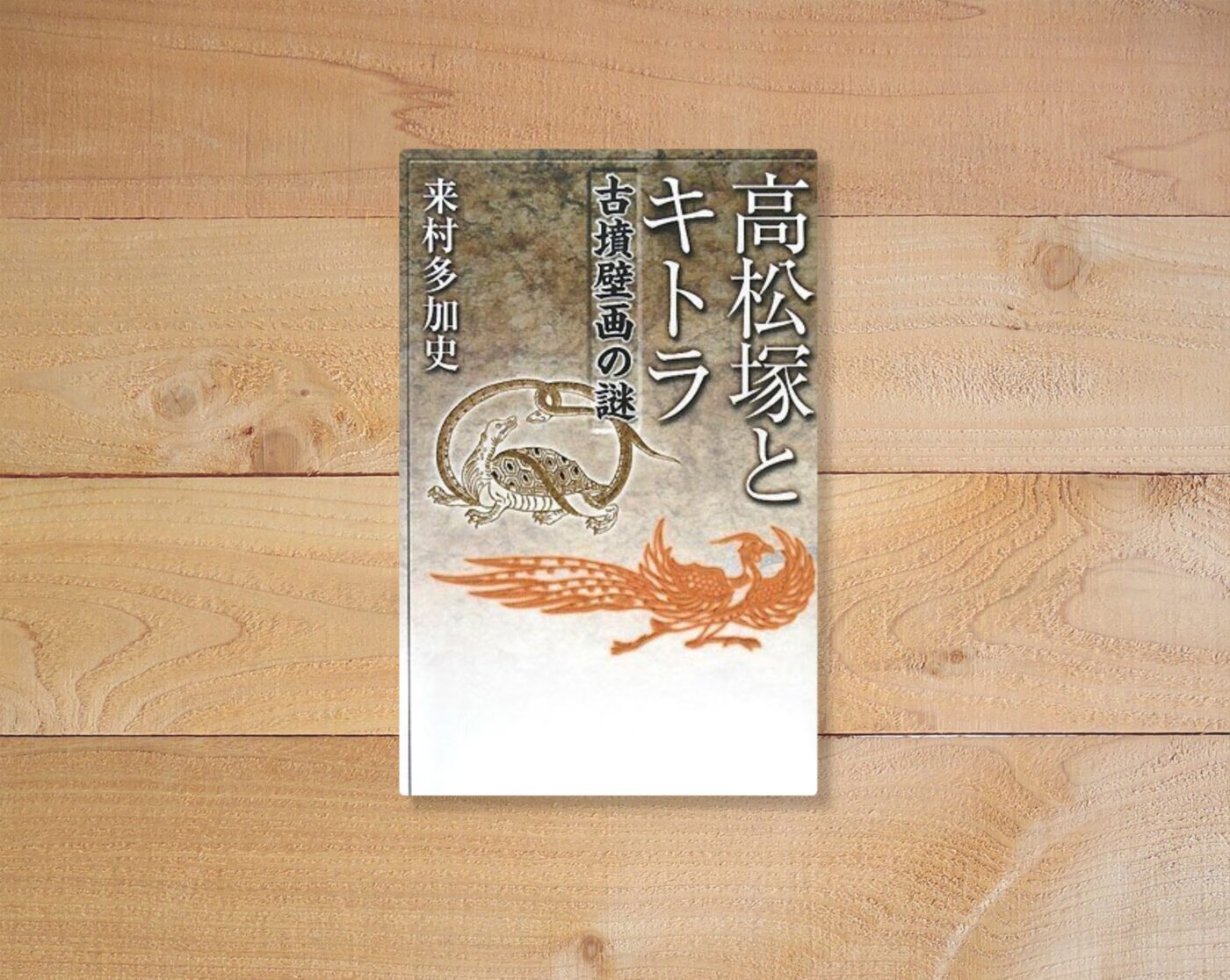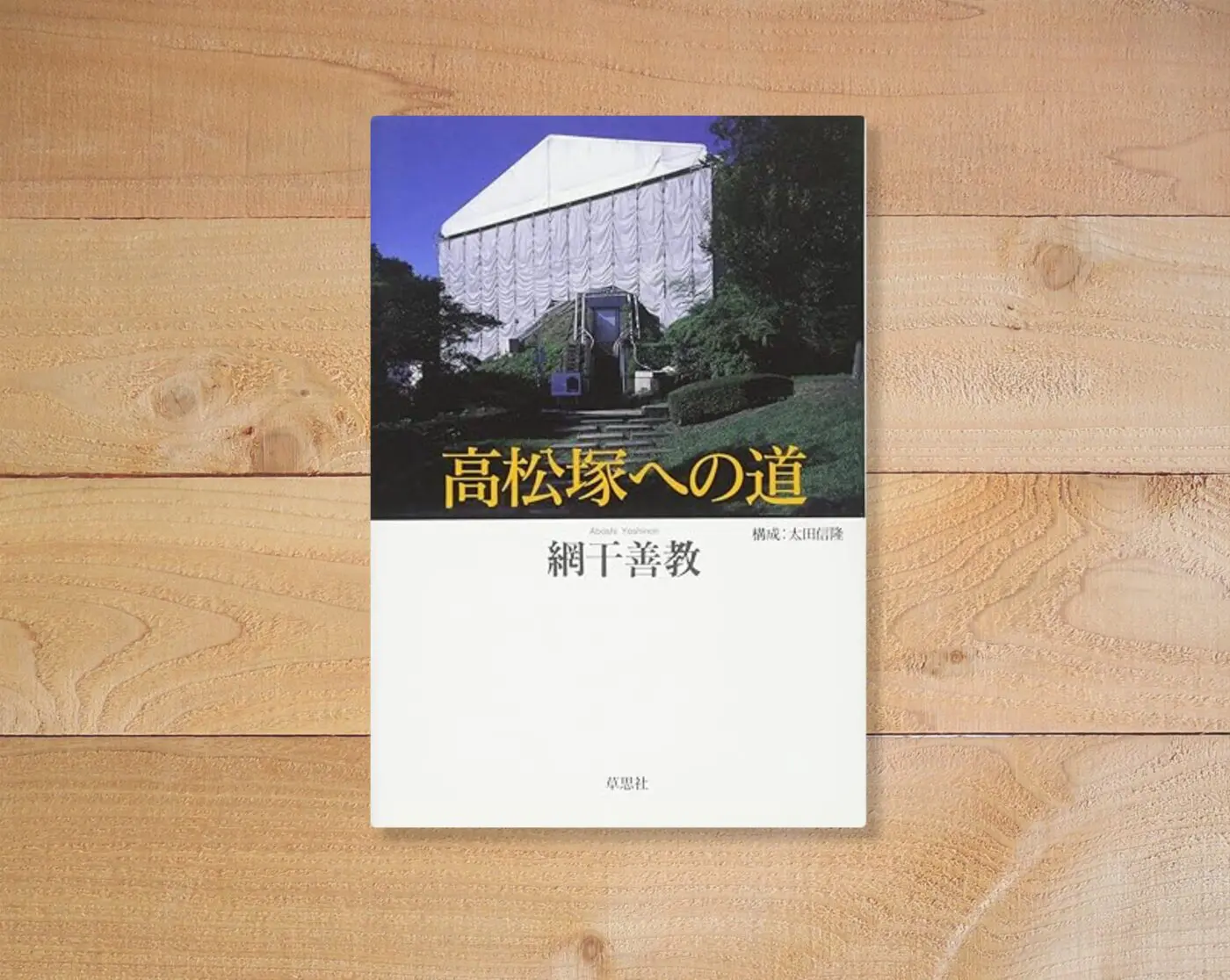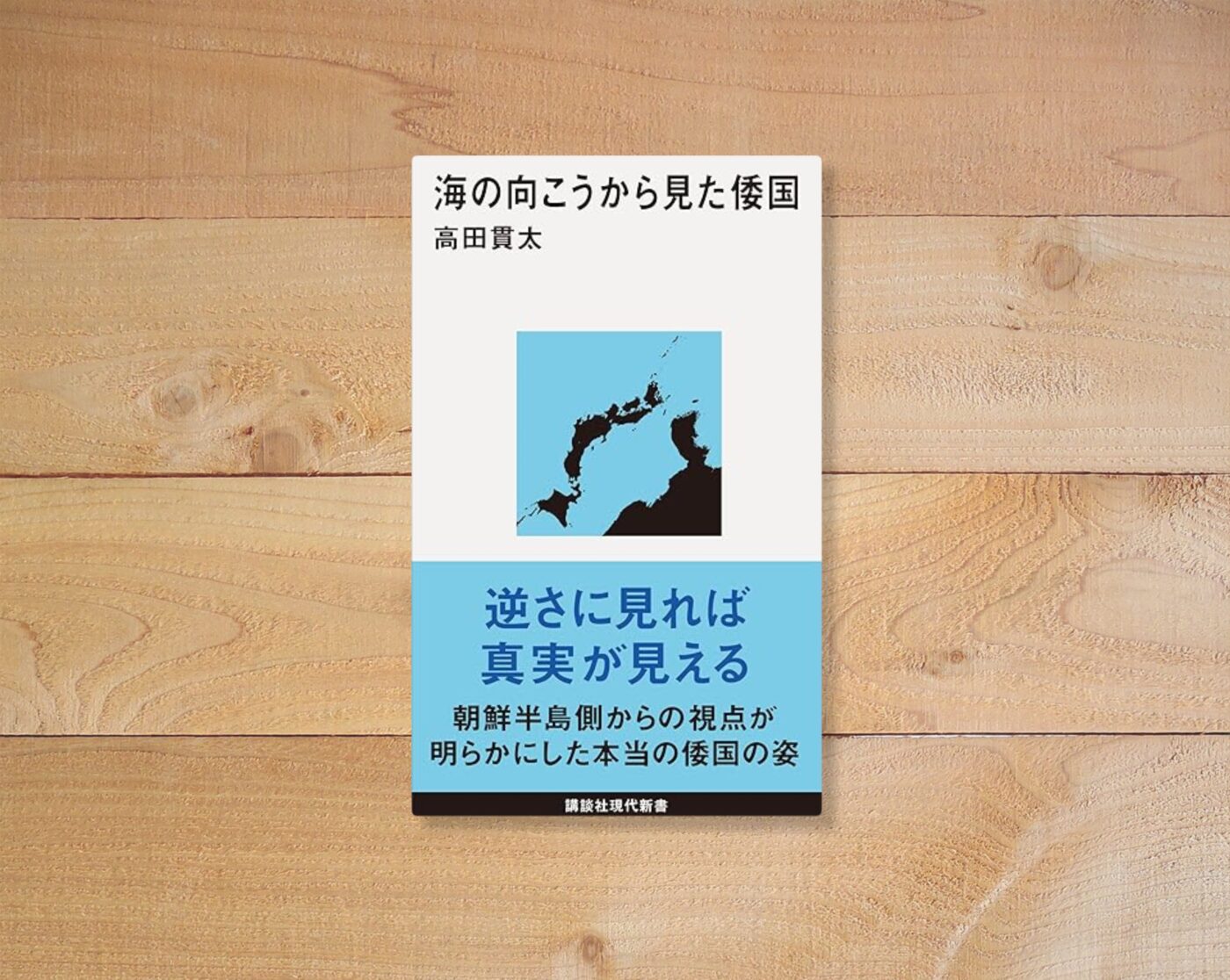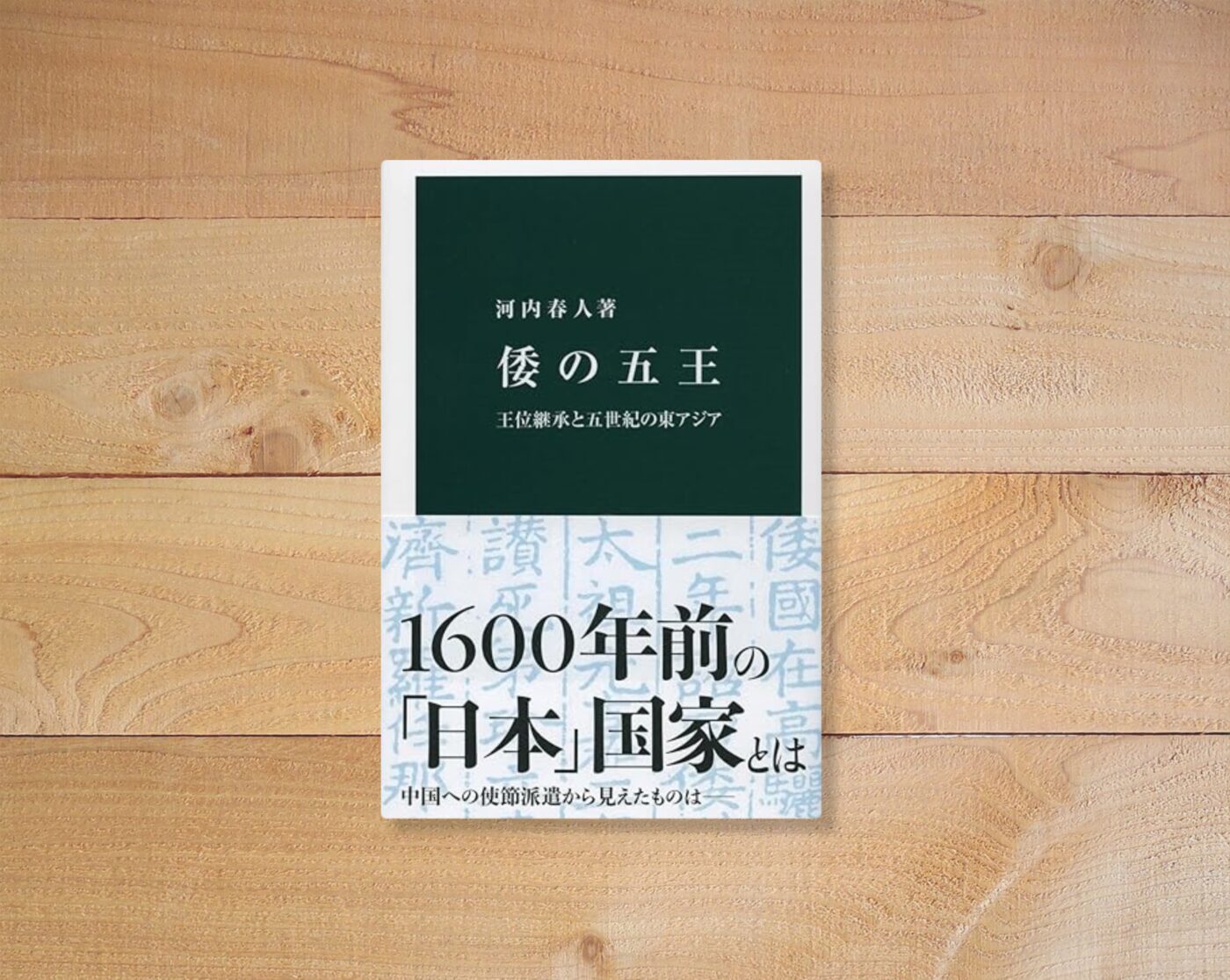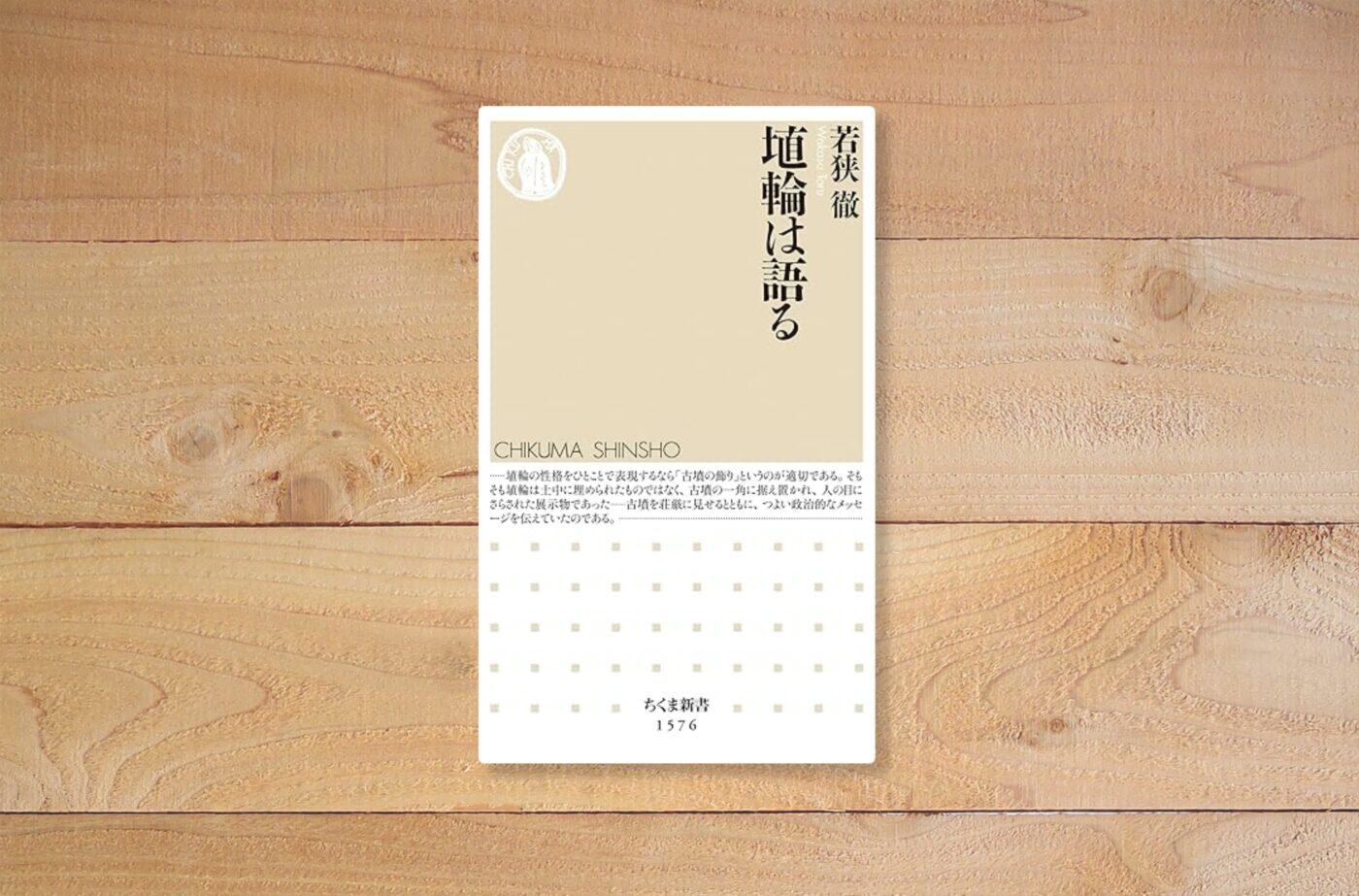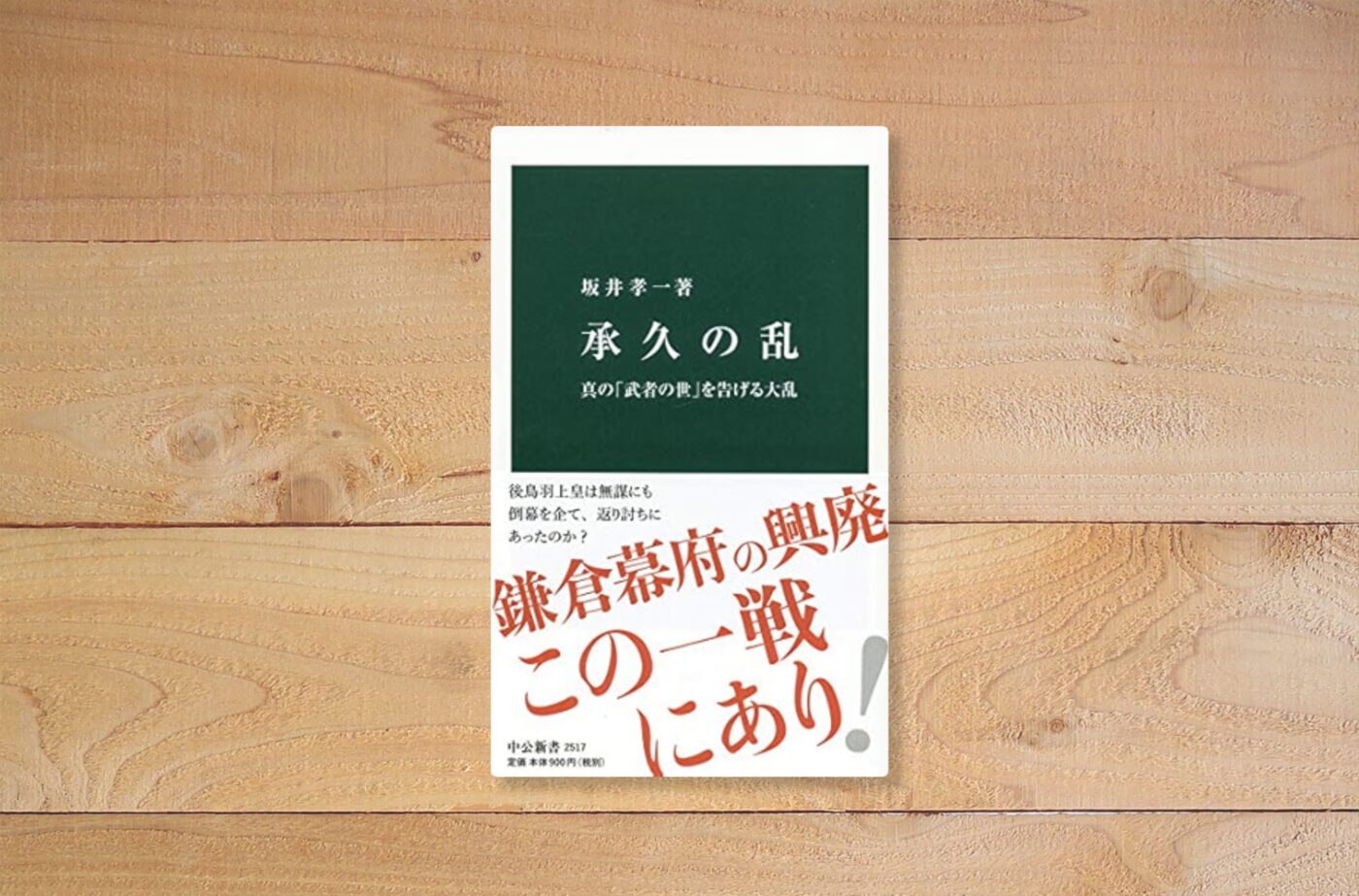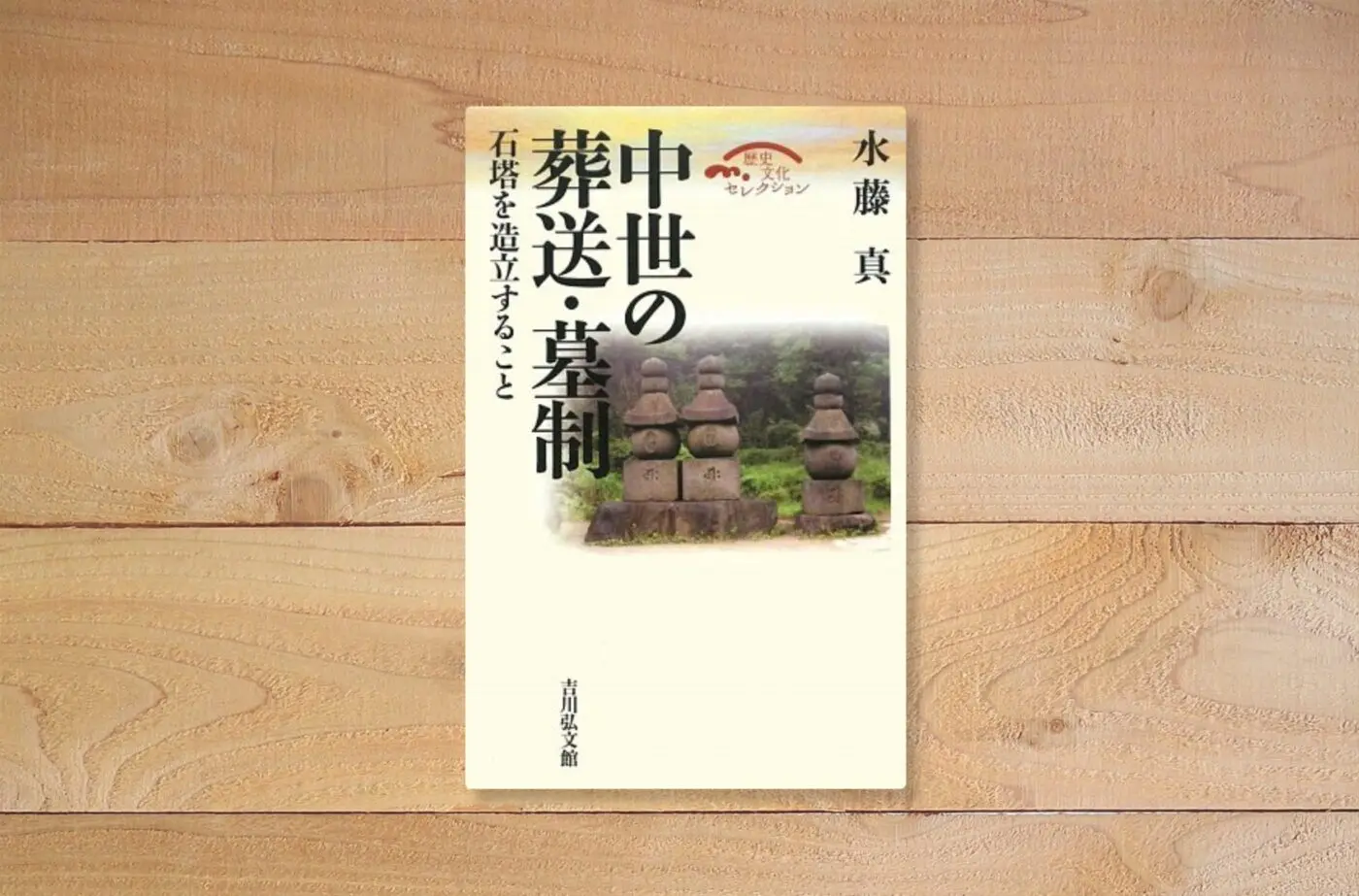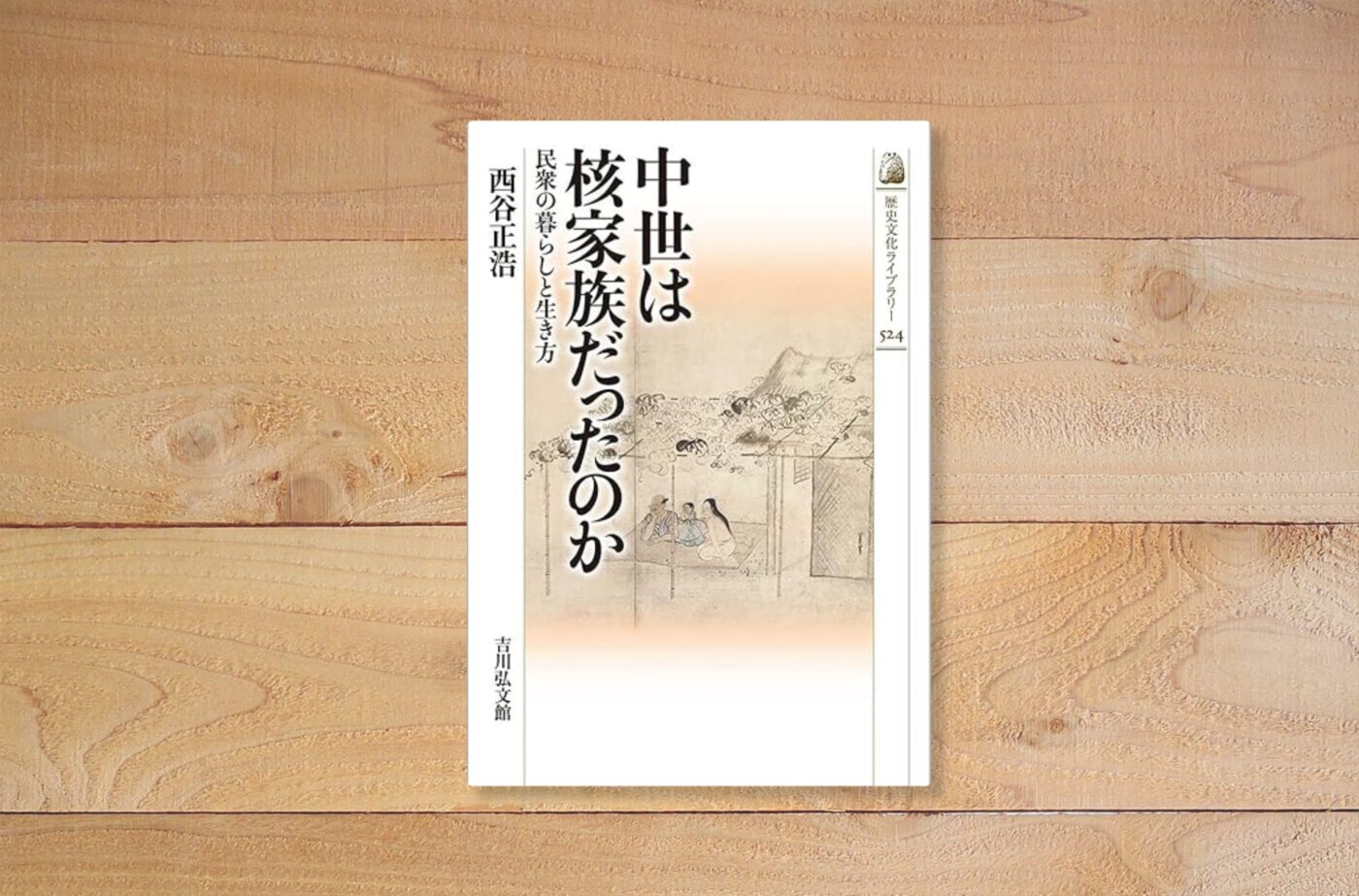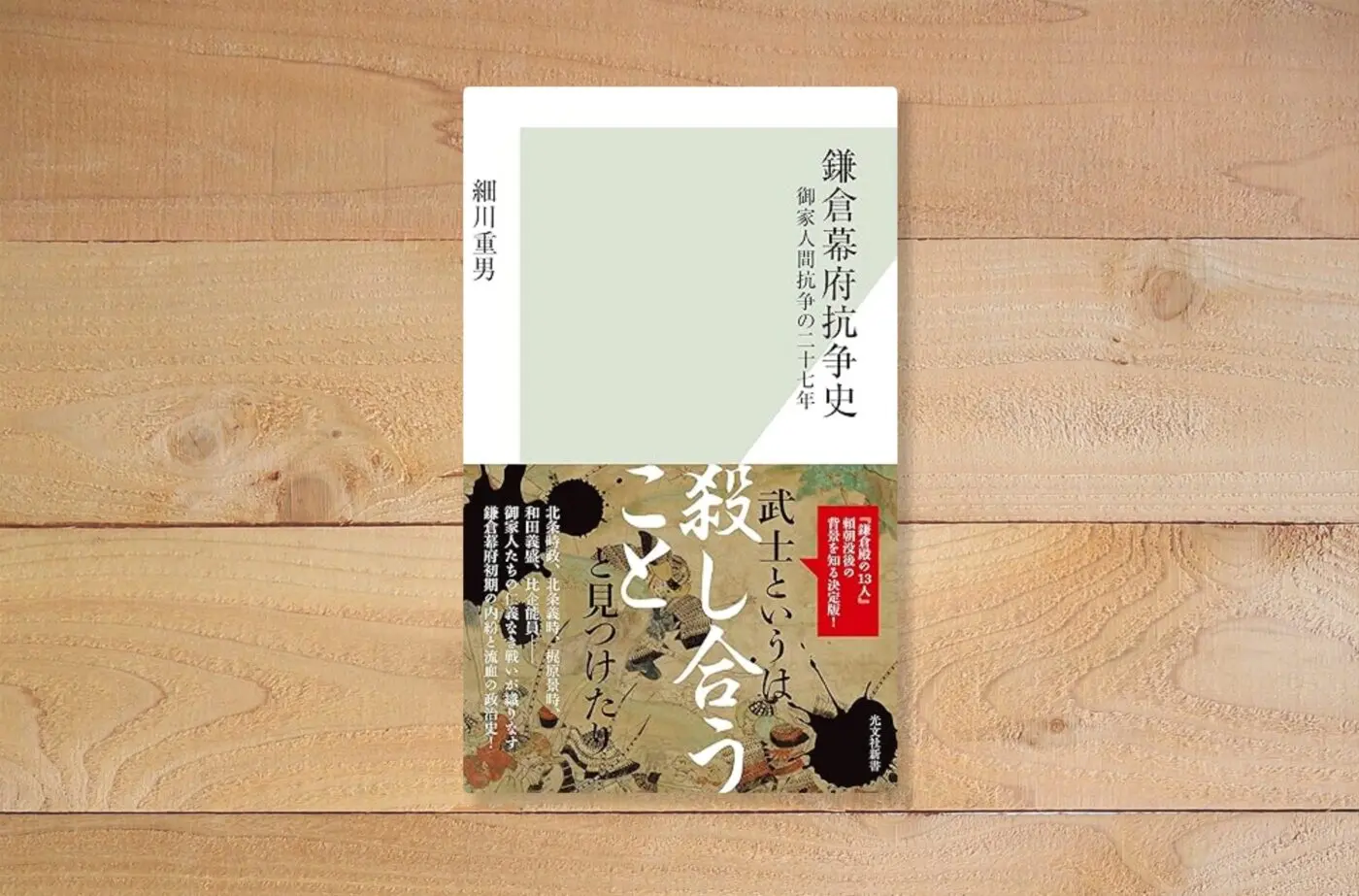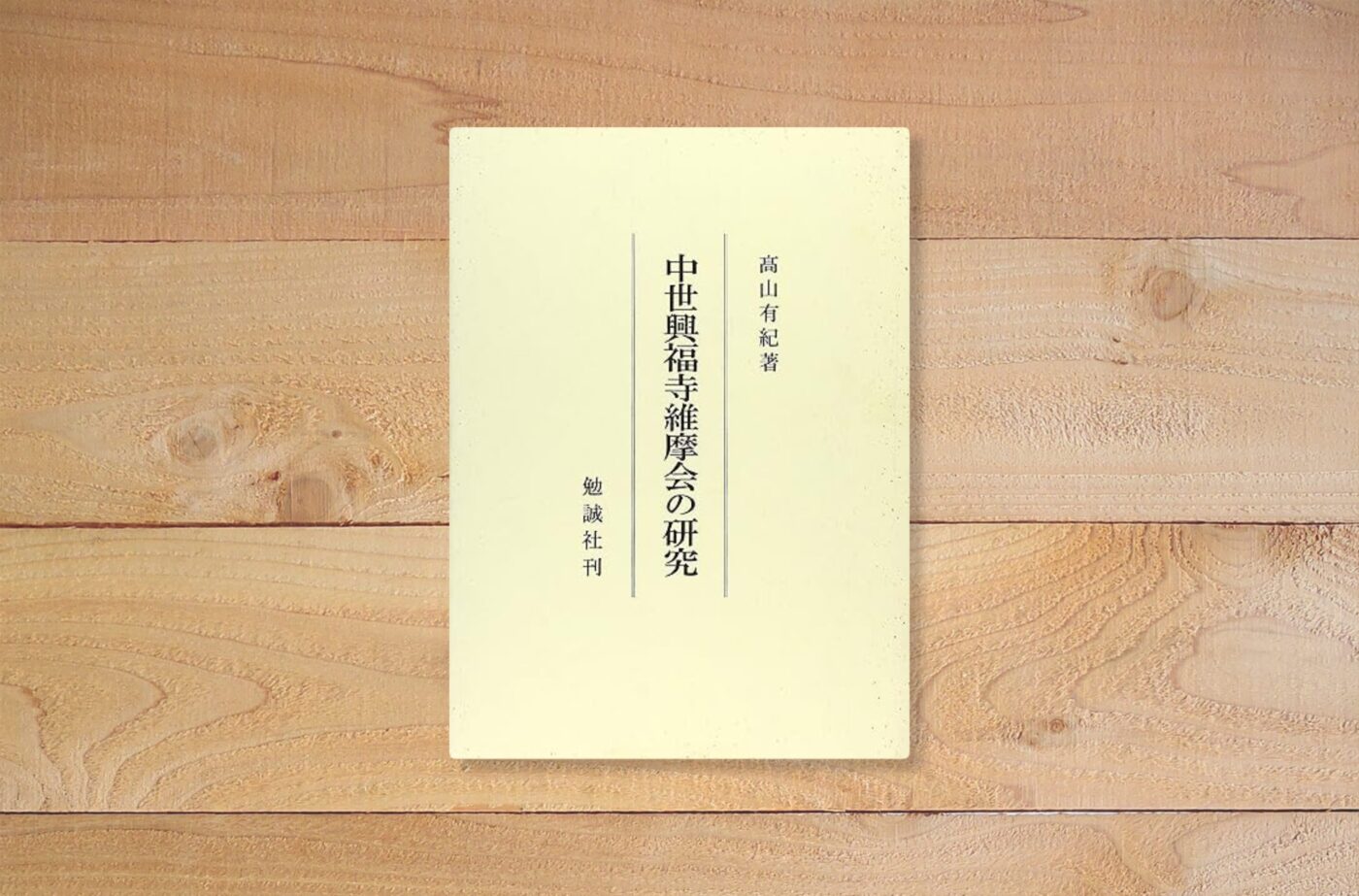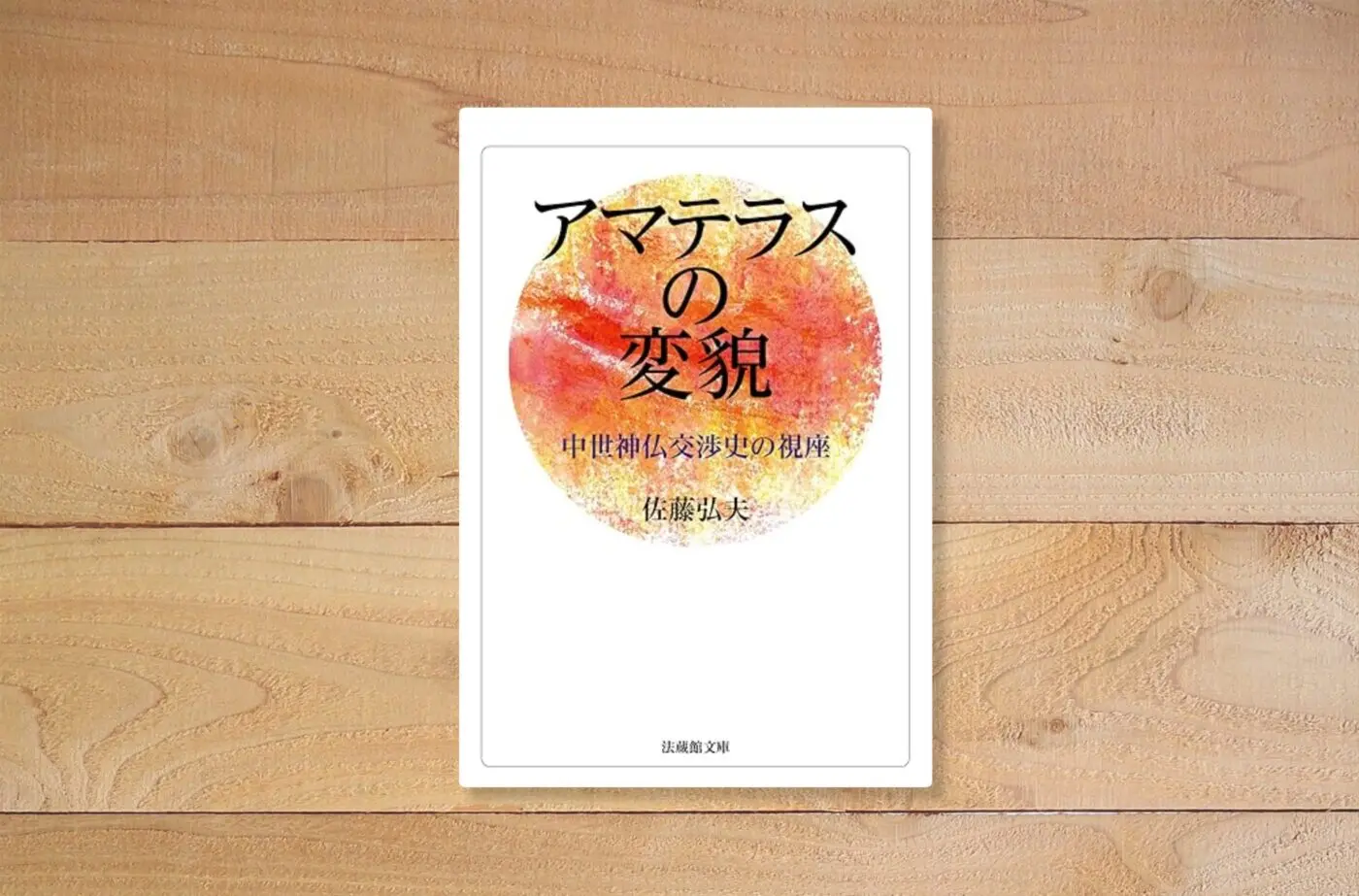松木武彦『未盗掘古墳と天皇陵古墳』あらすじと感想~古墳発掘の現場に生きる考古学者の仕事を知れる刺激的な一冊!
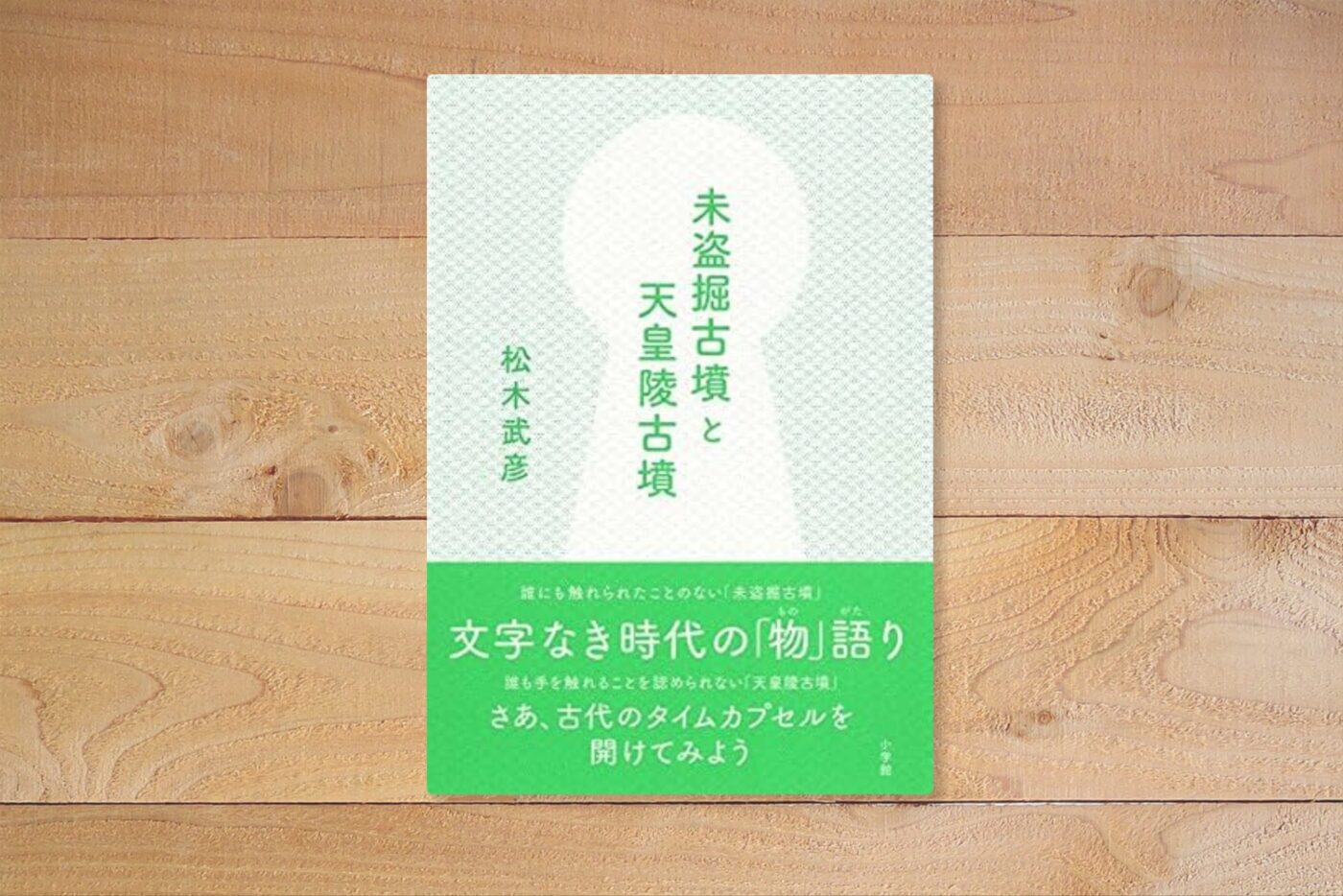
松木武彦『未盗掘古墳と天皇陵古墳』あらすじと感想~古墳発掘の現場に生きる考古学者の仕事を知れる刺激的な一冊!
今回ご紹介するのは2013年に小学館より発行された松木武彦著『未盗掘古墳と天皇陵古墳』です。
早速この本について見ていきましょう。
発掘すべきか否か? 古代のタイムカプセル
古墳は、その大部分がのちに掘り返され、埋葬品の多くが持ち出されています。それを「盗掘」といいます。しかし、数年に一度、盗掘されていない古墳が見つかることがあります。それが「未盗掘古墳」です。
未盗掘古墳は、つくられた時の状況がそのまま保たれています。そのため、そこに葬られた人物や葬った人びと、一緒に葬られた品々、葬る方法や技術、そしてそれを生み出した社会などについての豊かな手がかり(情報)を、万全の形で入手することができます。
この本は、そのような未盗掘古墳の説明に始まり、著者が発掘に関わった滋賀県の雪野山古墳と岡山県の勝負砂古墳という二つの未盗掘古墳について、発掘の経緯や発掘によって分かったことを紹介します。そこから得られる情報量は、盗掘されている古墳と比べてはるかに膨大なのです。
このように古墳の発掘は、古代社会を知るのに可欠な営みですが、近年では「より技術が発達しているであろう未来の考古学に託すため」という名目から、古墳を発掘しない傾向が強まっています。それに対して著者は、「掘れない古墳」の代名詞である天皇陵古墳の問題も挙げて、古墳を発掘することの学問的・社会的意義を論じます。【編集担当からのおすすめ情報】
Amazon商品紹介ページより
著者の松木先生は、数年に一度しか発見されない未盗掘古墳をこれまでに二度も発掘しています。未盗掘古墳のことを誰よりも知る考古学者だからこそ書ける、「未盗掘古墳の魅力」が満載です。
本書の著者松木武彦氏は私が古墳にはまるきっかけとなった『考古学から学ぶ古墳入門』の著者でもあります。
『未盗掘古墳と天皇陵古墳』というタイトルだけを見るとかなり難しそうな本のように思えますが、これがとにかく面白い!古墳発掘の現場に生きる著者だからこそ知れる現場の雰囲気や古墳にまつわる様々なエピソードを聞くことができます。
百聞は一見に如かず。冒頭の文章を読んでいきましょう。ここからしてすでに一般読者にも読みやすい松木先生の語り口を堪能することができます。
日本に現存する古墳の数はおよそ一六万基。南は鹿児島県から北は北海道の南部まで、古墳は日本の津々浦々にその姿をとどめている。神社の数が約八万、コンビニエンスストアは約五万だというから、お宮の約二倍、コンビニの三倍以上の数の古墳が、私たちのまわりには存在することになる。すでに破壊されて消え去った古墳も、現存の古墳の数と同じくらいかそれ以上あったとみられるから、いまのお宮やコンビニよりもはるかにたくさんの古墳に、往時の人は囲まれて生活していたことになる。
したがって、古墳時代の人びとは、精神的にも経済的にも、古墳と切っても切れない日々の営みを送っていた。そういう意味で、「古墳時代」という言い方はまさに当を得ている。古墳作り、古墳まいり、古墳のある風景に、老若男女、王侯貴族から庶民まで、身も心もどっぷりとつかっていた時代を、私たち日本人は過去にもっていたのである。しかもこの時代は、地域によって時期的なずれはあるが、日本各地でおよそ二〇〇年~四〇〇年もの長いあいだを占めた。その後の日本の社会や文化に、深く、濃密な影響力をとどめた時代である。
にもかかわらず、私たちは古墳について、どれほどのことを知っているのだろうか。古墳は、現代の日本人に対して、どういう意味をもっているのだろうか。どんな言葉とともに、私達は一六万基の古墳を、子孫に伝えていけばいいのだろうか。あまりにも身近にありすぎて、多くの人は気にもとめないような存在だが、日本列島の過去の人びとが国土に残したものとしては群を抜いて際立った遺産が、古墳である。もっと多くの方々に、古墳を知り、訪ね、感じ、考えていただきたいという思いが、この本を書く出発点となった。
とはいえ、しかつめらしい理念をいくら振りかざしても、古墳への関心をもったり、新たにしてくれたりする人はいないだろう。だとすれば、古墳に対する世間の関心を引き出すためには、古墳のどんなところに光をあてればよいのだろうか。そんなことを考えたたきに思いあたったのが、未盗掘古墳と天皇陵古墳である。
古墳について報道されるとき、「未盗掘」と「天皇陵」は、人の目をとらえるキャッチフレーズのような力をもっている。考古学についてよくいわれるロマンの源泉として、千数百年まえの世界が密封されたタイムカプセルとして。あるいは皇室の先祖がまつられたとされる聖域として、世界最大級の古代建造物として。そこには古墳の、現代社会での位置づけや、日本人にとっての意味や、子孫に残す価値の由来などが、もっとも純粋な形で凝縮されているにちがいない。それらを眼前に引き出してはっきりと見定めるために、この二つのキャッチフレーズをそれぞれ冠した古墳のことをくわしく解剖してみようというわけである。
一見、関係の薄そうな「未盗掘古墳」と「天皇陵古墳」だが、この両者には、いまや両者にだけ共通するひとつの性質がある。「発掘してはならないもの」という、政治的・社会的な制限だ。この制限のことについては本文でくわしく述べるが、その制限の当否を突きつめると、とどのつまり「発掘するとはどういうことか」という問いにいきあたる。私たち発掘者に対し、この問いを真っ向から突きつけるもっとも大きな二つの力として、両者を並べることには道理があるのである。
私は、その一方の未盗掘古墳を発掘するという禁を、二度もおかしてしまった「悪い」考古学者である。一度目は滋賀県東近江市の雪野山古墳で、もう一度は岡山県倉敷市の勝負砂古墳だ。しかし、悪人には悪人なりの弁明がある。本書の最後の部分では、この弁明のなかに、「発掘するとはどういうことか」という問いに対する答えをちりばめてみようと思う。弁明に対する裁きはみなさんにゆだねるしかないが、本書が古墳や発掘について考えるきっかけとなってくれれば、うれしいことである。
小学館、松木武彦『未盗掘古墳と天皇陵古墳』P3-5
いかがでしょうか。何だか古墳が面白そうに感じられませんか?
実際、本文を読み進めていくと興味深い事実が次から次へ出てきます。プロの考古学者のお仕事とは何たるかも知れる本書は実に刺激的です。
そして本書では『海の向こうから見た倭国』の著者である高田貫太先生も登場します。若き日の高田先生は松木武彦氏の下で未盗掘古墳の現場に参加していたのです。実は私がこの本を読んだのは高田貫太先生の本がきっかけでした。私は高田先生の著書が大好きで、実際に渡来人研究のために最近対馬や韓国を訪れたほどです。その高田先生の著書でこの『未盗掘古墳と天皇陵古墳』が言及されていて、ぜひその本を読んでみたいと思い手に取ったのでした。

この本ではそうした若き研究者の育成問題についても語られます。未盗掘古墳や天皇陵古墳の発掘は現在タブー視されがちですが、研究者の育成のために果たす大きな役割が見過ごされている点を指摘しています。
実践の現場がなければ研究者を育てることができない。研究者が育たなければ今後研究を継承していくこともできなくなってしまう。こうした危機意識を著者は本書で語っています。
本書はタイトルこそ難しそうではありますが、中身はものすごく面白いドキュメンタリーのように読めてしまう素晴らしい名著です。
ぜひぜひおすすめしたい一冊です。
以上、「松木武彦『未盗掘古墳と天皇陵古墳』あらすじと感想~古墳発掘の現場に生きる考古学者の仕事を知れる刺激的な一冊!」でした。
Amazon商品紹介ページはこちら
次の記事はこちら
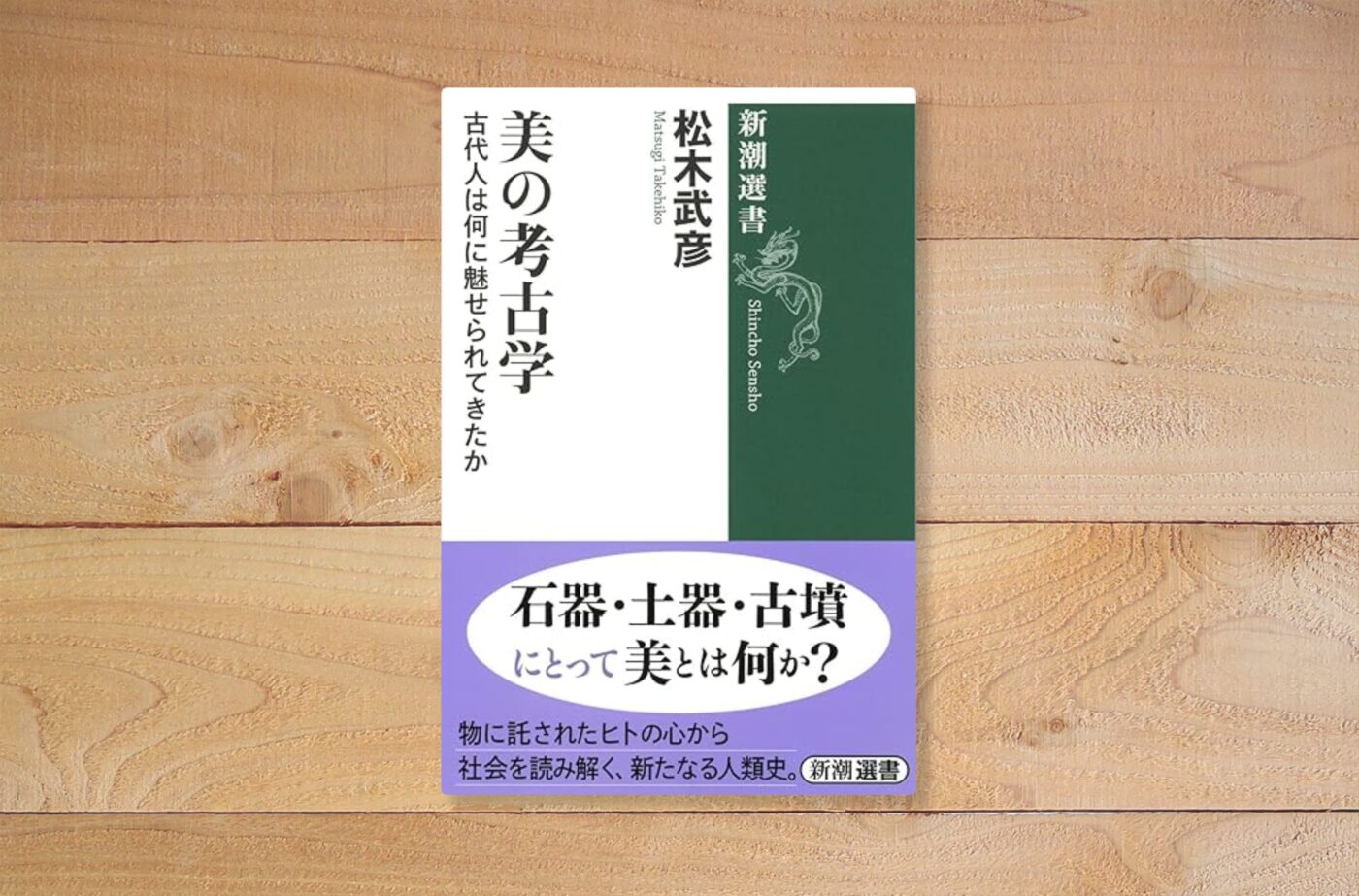
関連記事