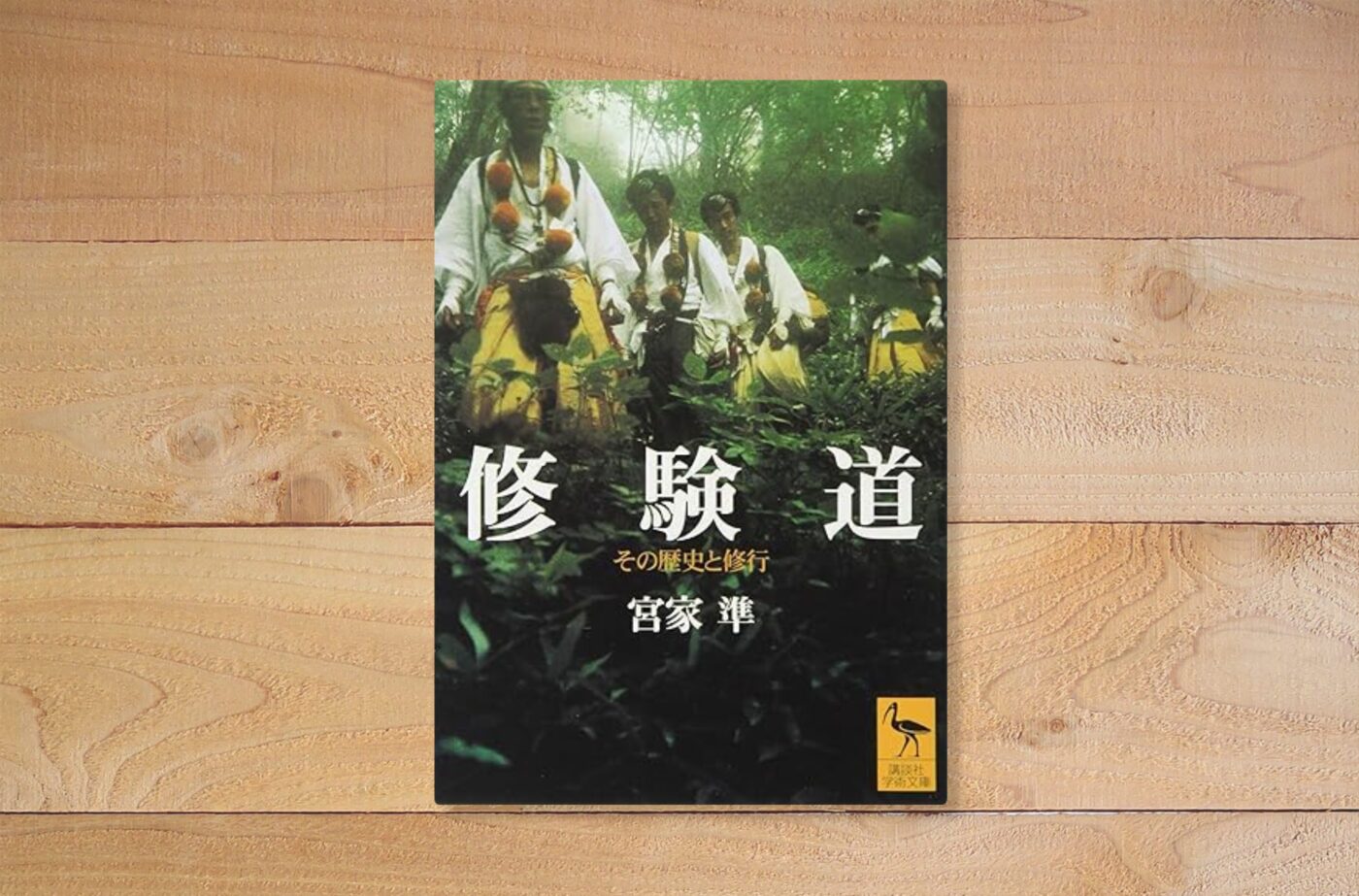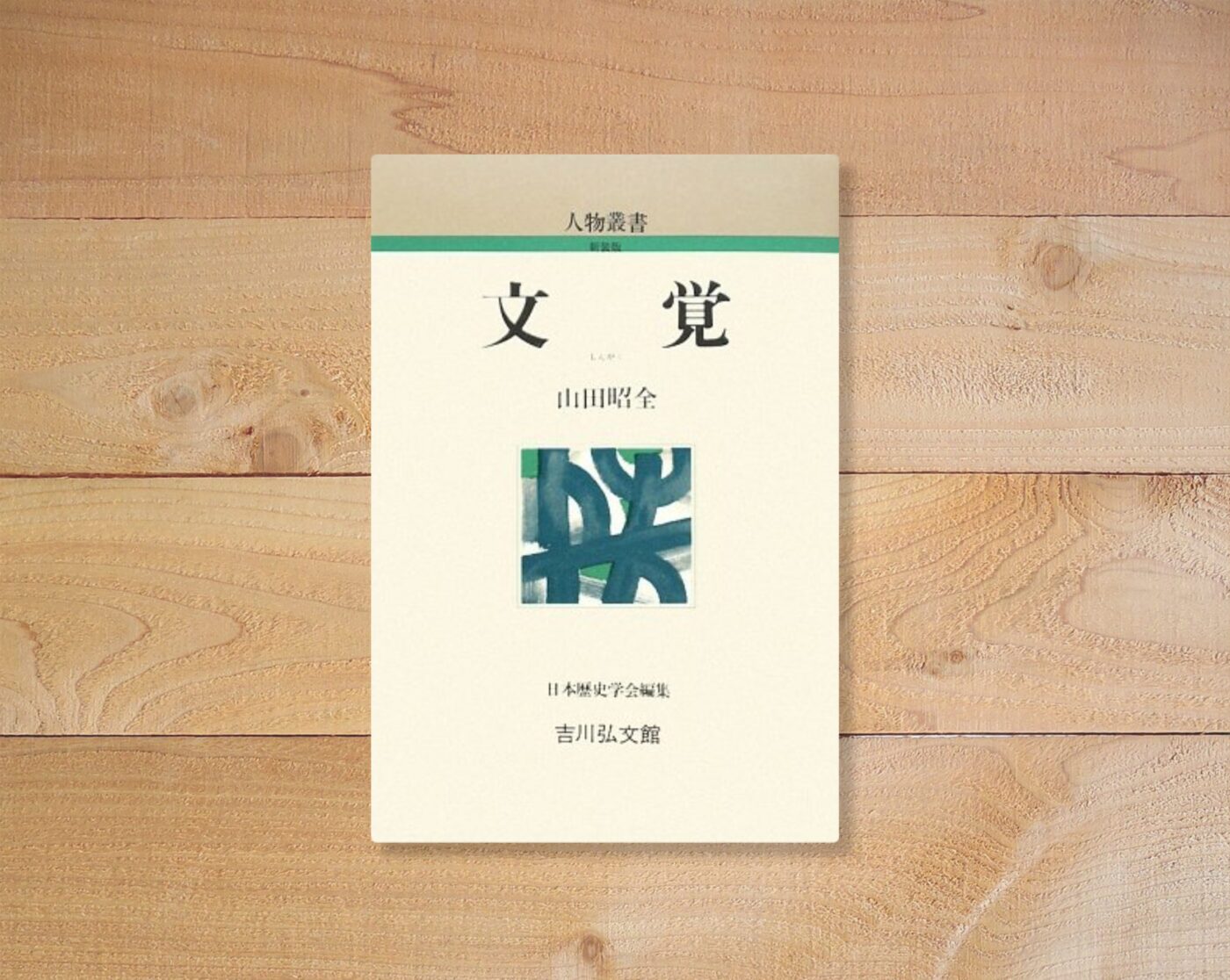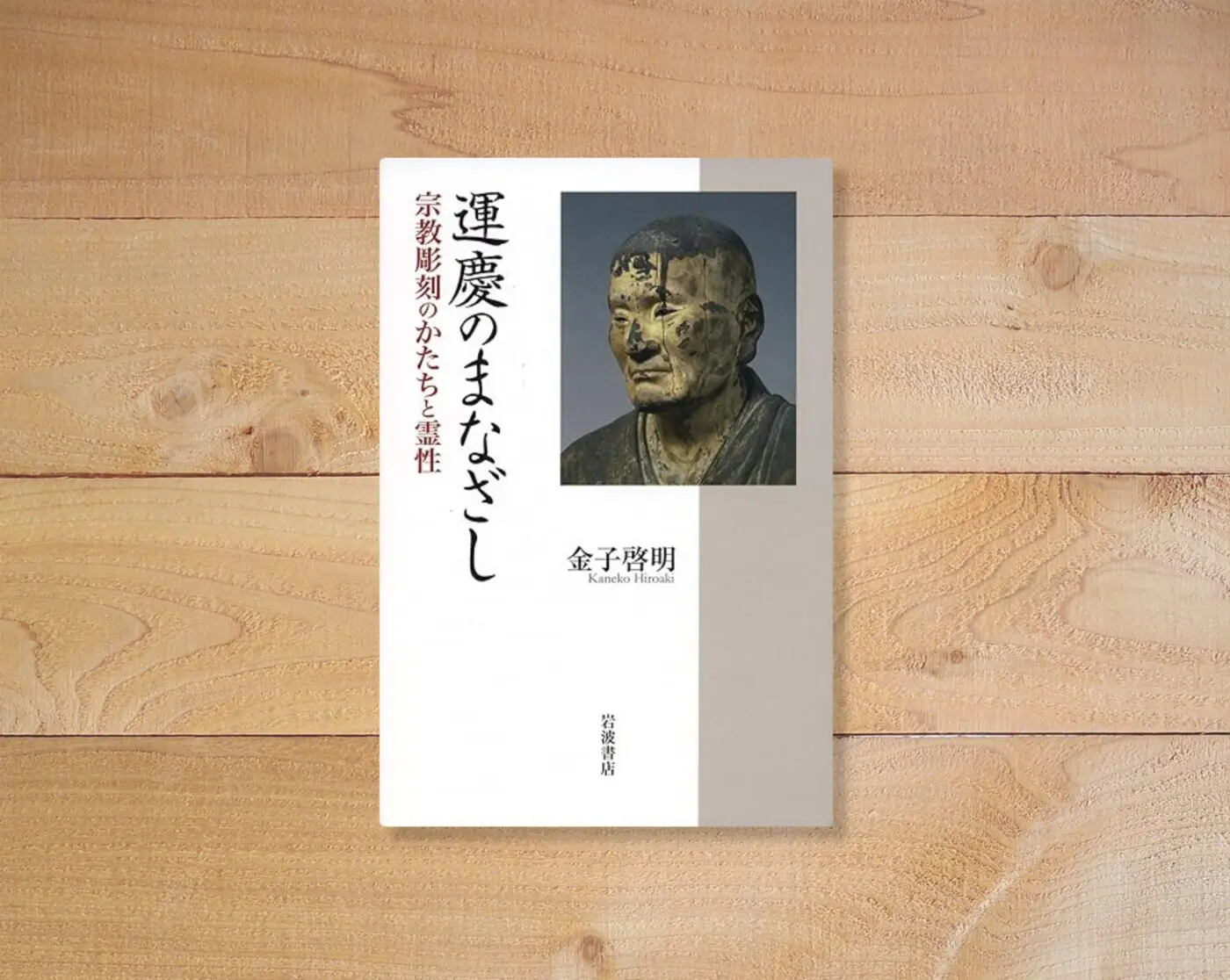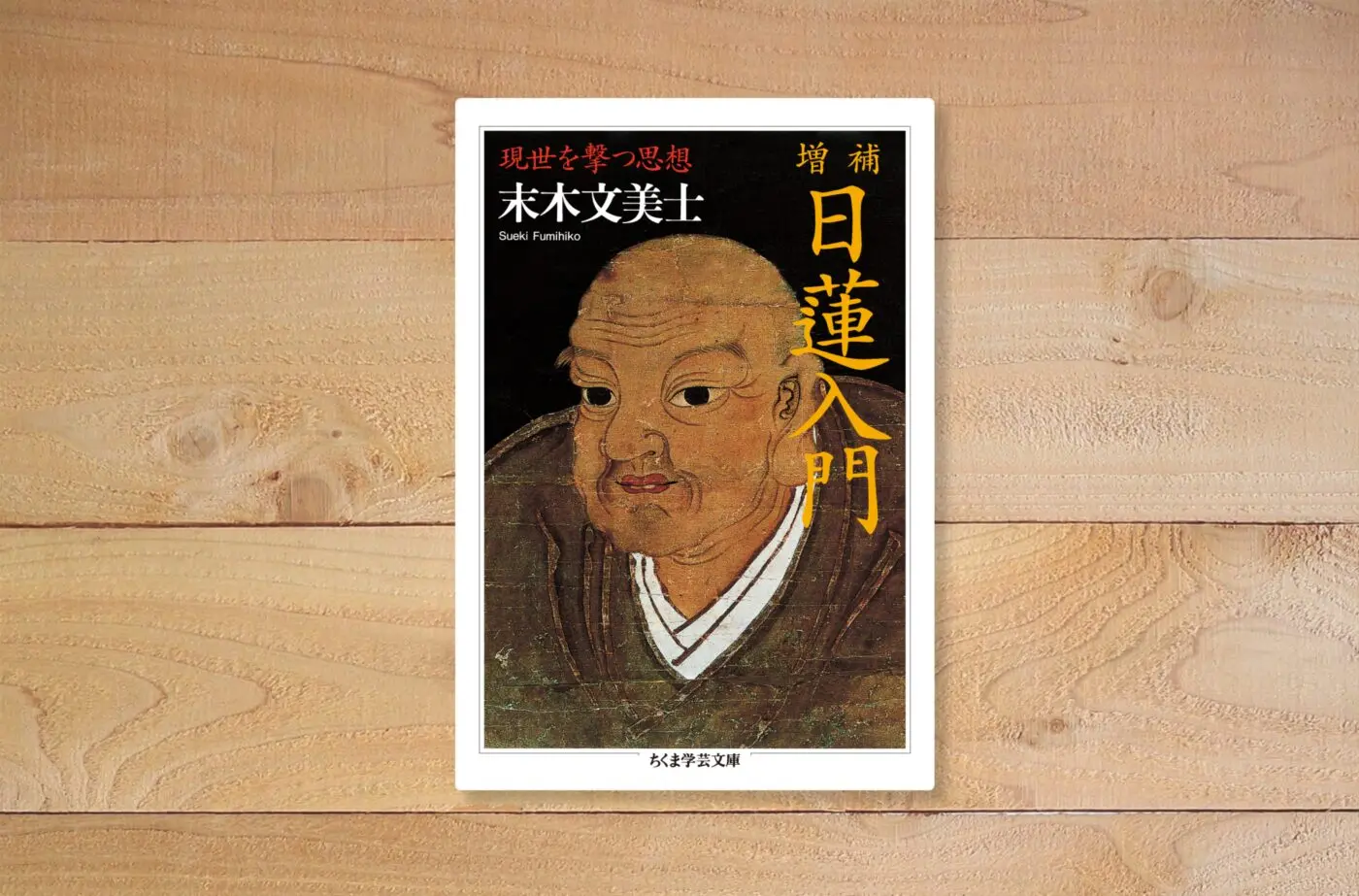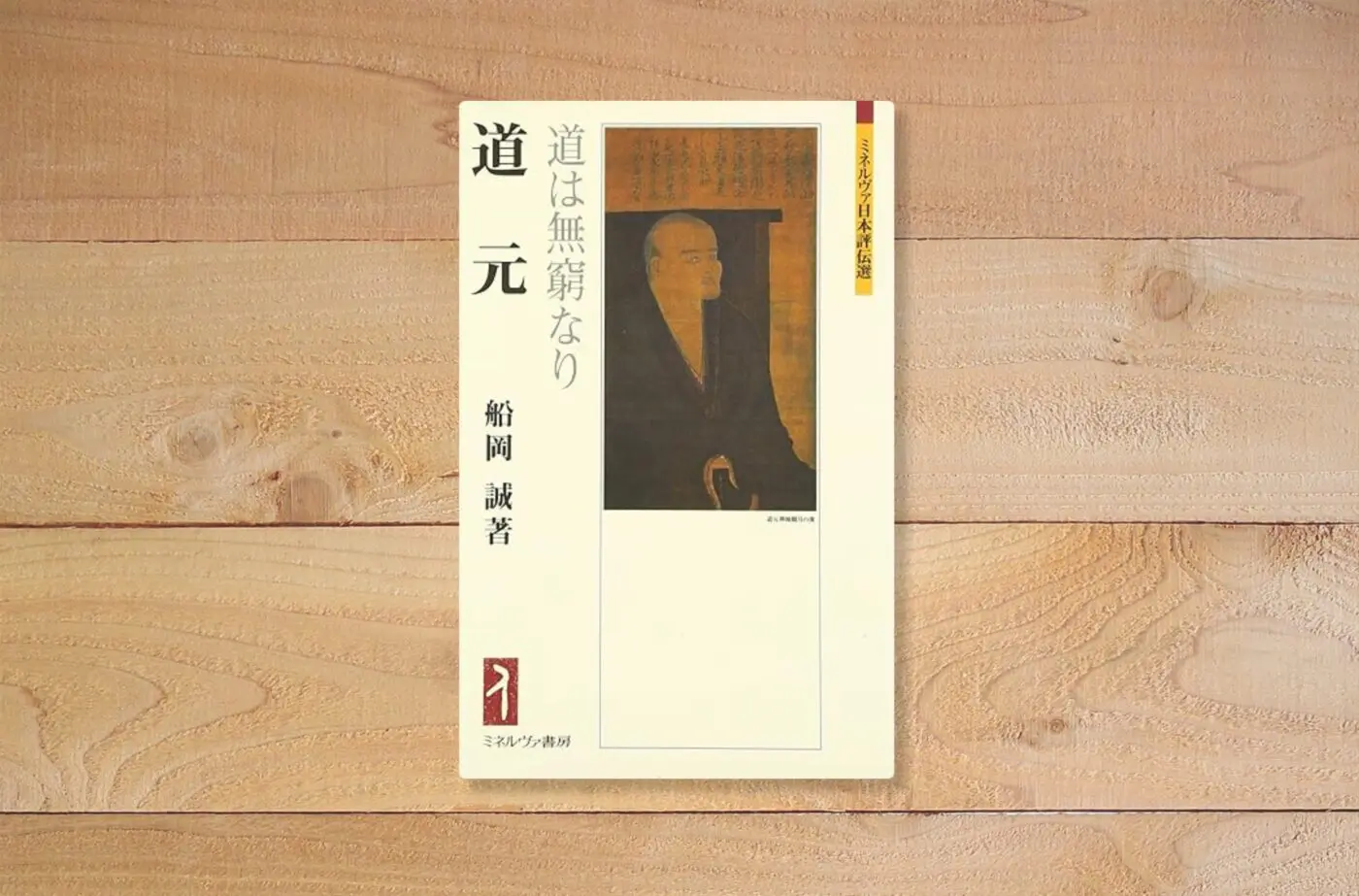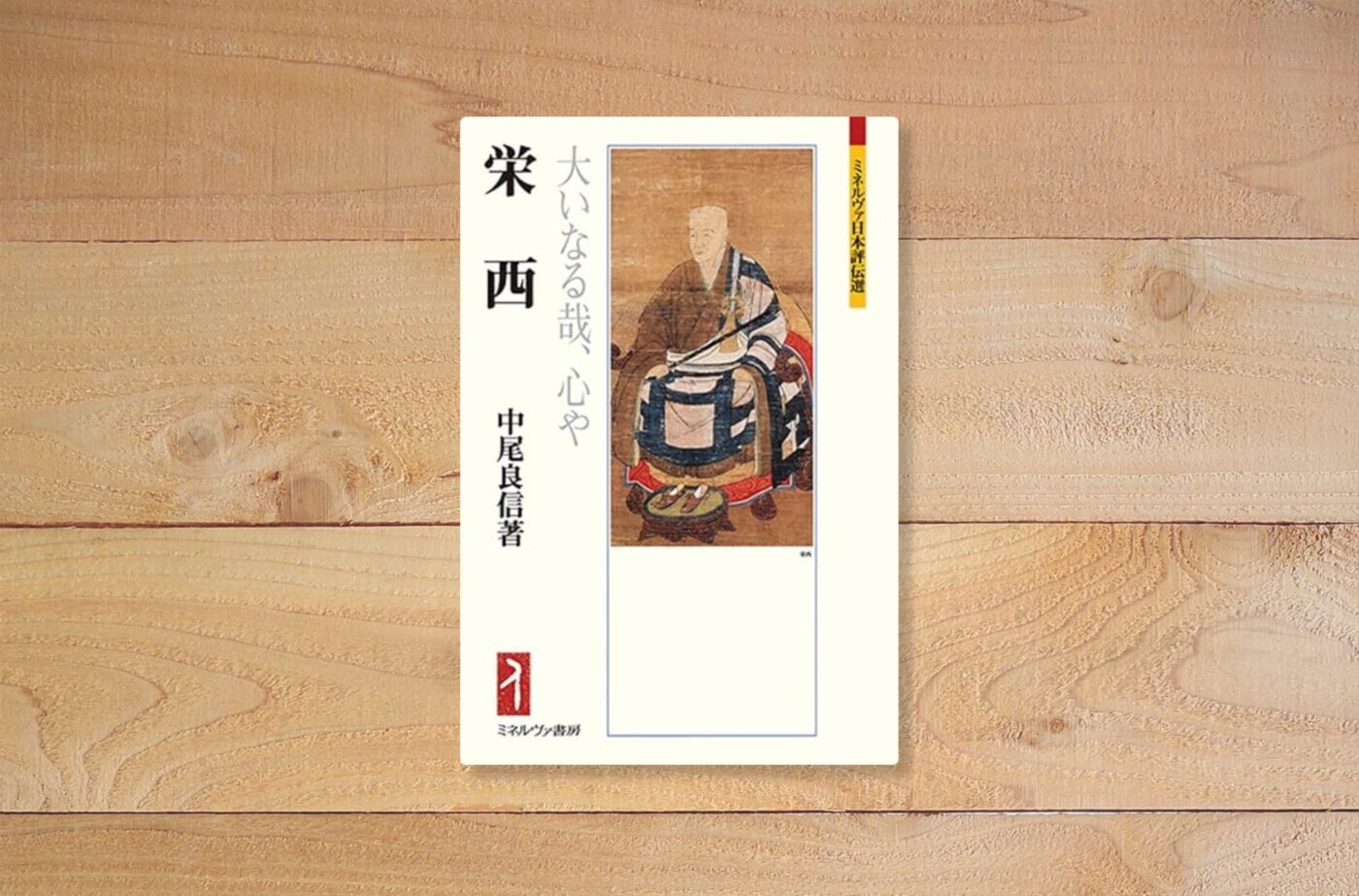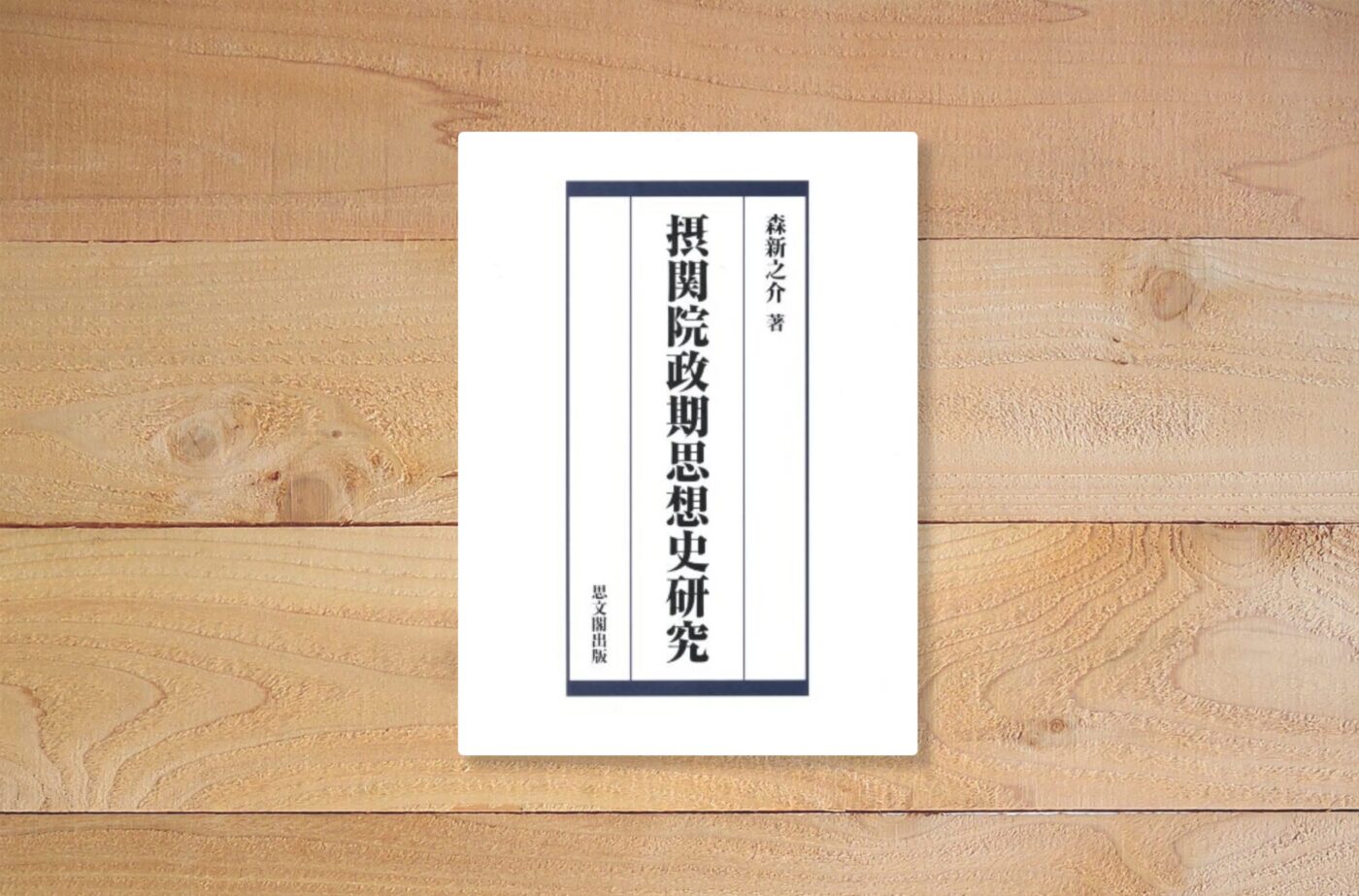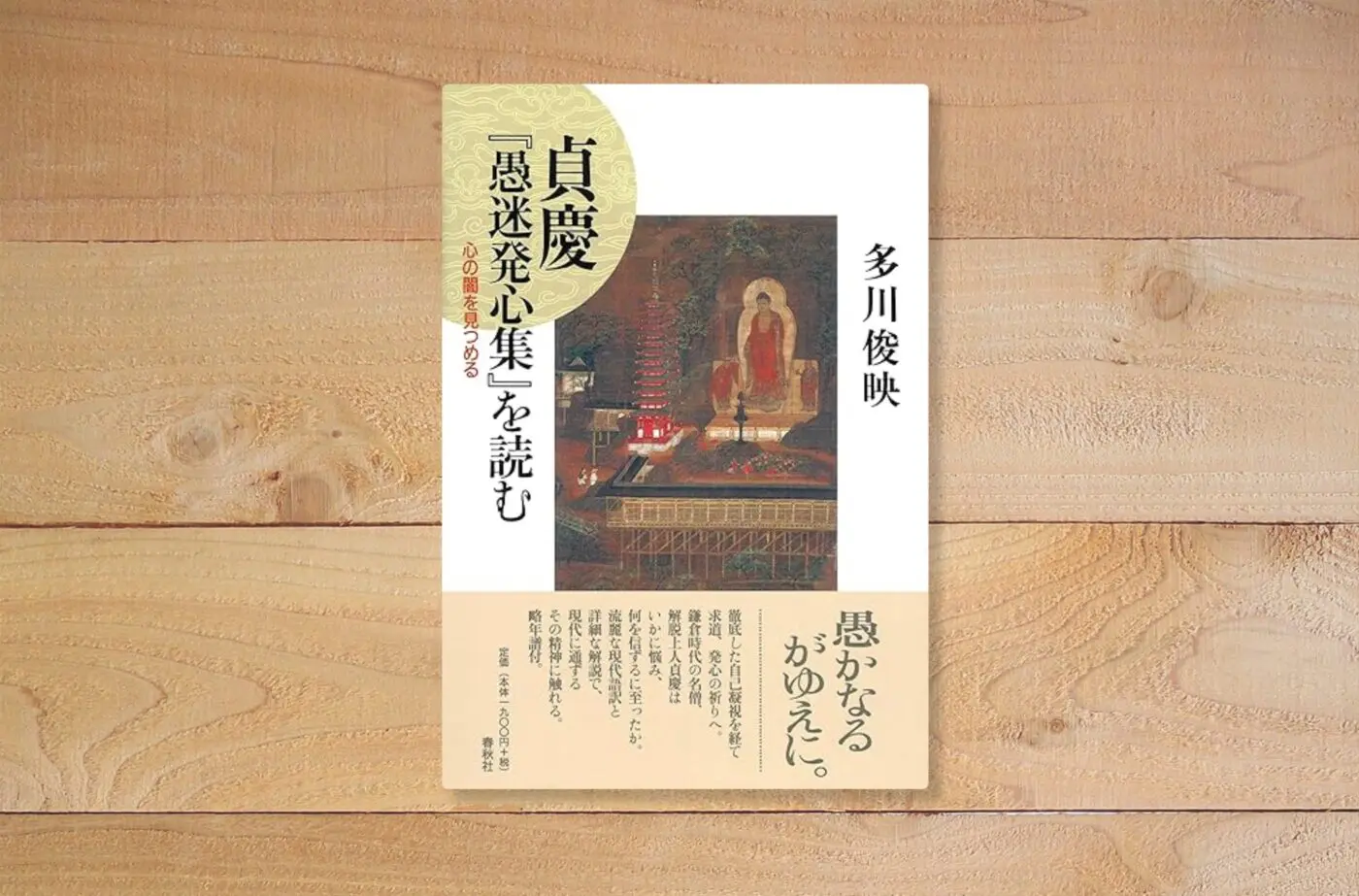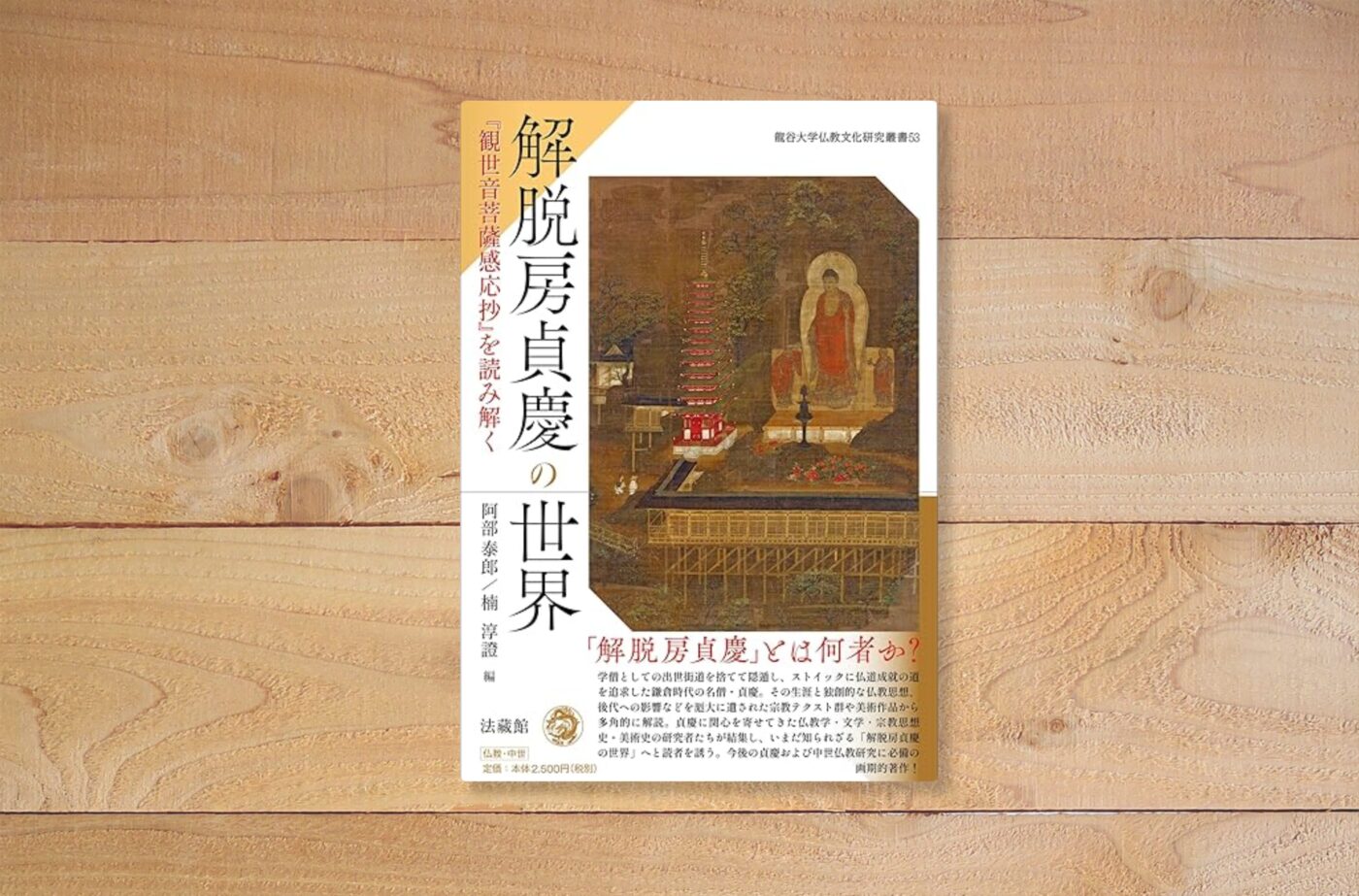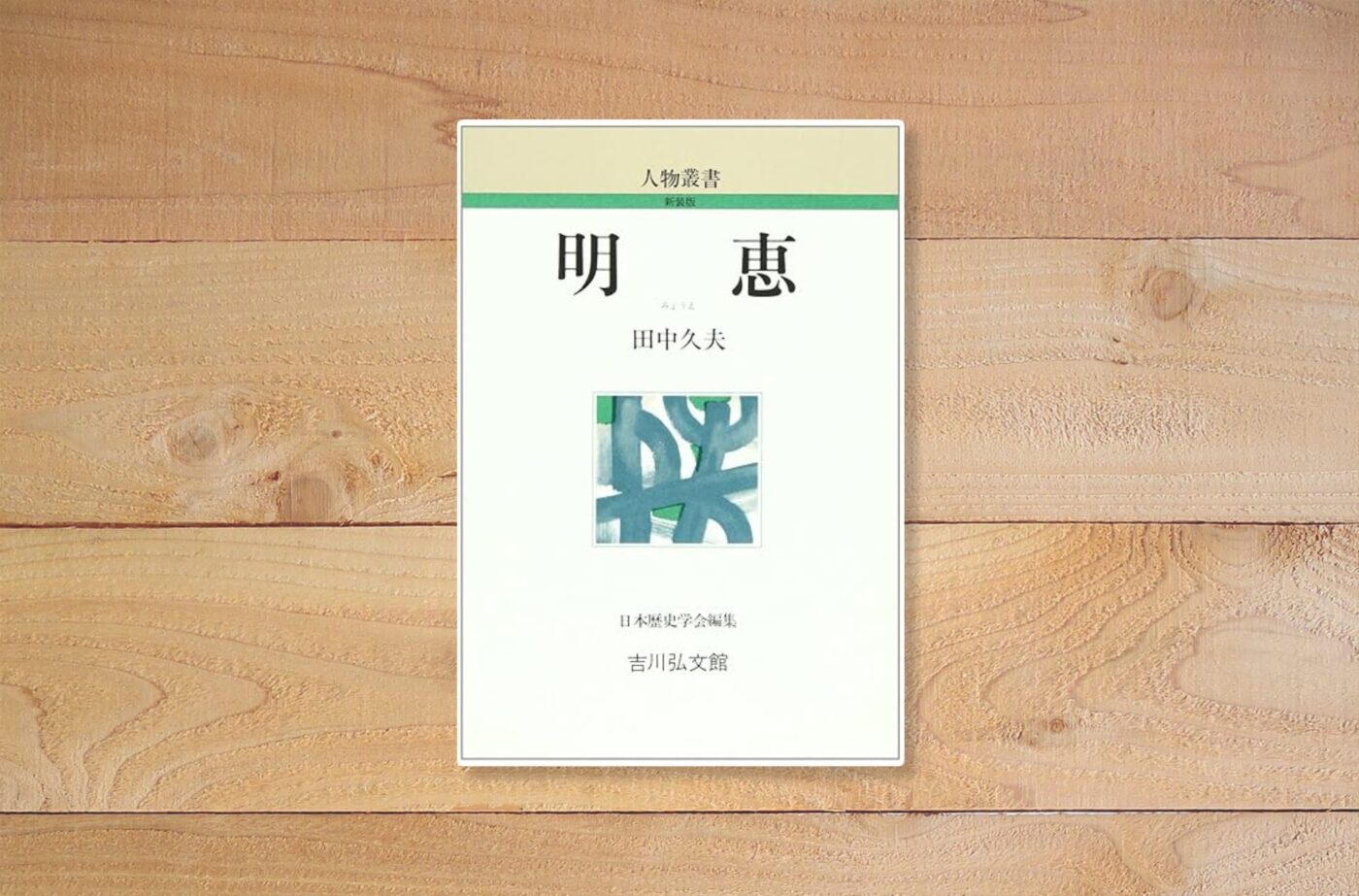五来重『熊野詣』概要と感想~死者の国、浄土信仰の聖地としての熊野を知るのにおすすめ参考書

五来重『熊野詣』概要と感想~死者の国、浄土信仰の聖地としての熊野を知るのにおすすめ参考書
今回ご紹介するのは2004年に講談社より発行された五来重著『熊野詣』です。
早速この本について見ていきましょう。
院政期の上皇が、鎌倉時代の武士が、そして名もなき多くの民衆が、救済を求めて歩いた「死の国」熊野。記紀神話と仏教説話、修験思想の融合が織りなす謎と幻想に満ちた聖なる空間は、日本人の思想とこころの源流にほかならない。仏教民俗学の巨人が熊野三山を踏査し、豊かな自然に育まれた信仰と文化の全貌を活写した歴史的名著が、待望の文庫化。
Amazon商品紹介ページより

本書『熊野詣』は世界遺産にも登録されている熊野古道の歴史を知るのにおすすめの参考書です。
この本の魅力は何と言っても著者の素晴らしい語りにあります。その雰囲気を味わうためにも「はじめに」の文章をご紹介します。少し長くなりますが、熊野とは何かを知る上でも非常に役立つ箇所ですのでじっくり読んでいきます。
熊野は謎の国、神秘の国である。シュヴァルツ・ワルトともいうべき黒い緑の森と、黒い群青の海。その奥にはなにかがかくされている。海と山と温泉の観光地なら、日本中どこにでもある。しかし熊野にはほかのどこにもない何かがある。南紀のあの明るい風光の奥にはこの世とは次元のちがう、暗い神秘がのぞいている。
熊野は山国であるが、山はそれほど高くはないし、森も深くはない。しかしこの山は信仰のある者のほかは、近づくことをこばみつづけてきた。山はこの秘境にはいる資格があるかどうかをためす試練の山であった。ただ死者の霊魂だけが、自由にこの山を越えることができた。人が死ねば、亡者は枕元にたてられた樒の一本花をもって熊野詣をするという。だから熊野詣の途中では、よく死んだ親族や知人に会うといわれた。これも熊野の黒い森を分ける山径が、次元のちがう山路ー死出の山路と交叉するからであろう。私も那智から本宮へむかう大雲取越の険路で、死出の山路を分けすすんでいるのではないかという幻覚におそわれた。尾根道であるのにじめじめとうすぐらく、黴くさい径であった。草に埋もれたその径には手の込んだ敷石が延々とつづいていた。その中世のめずらしい舗装道路は、中世人が「死者の国」にあこがれる執念のかたまりのようにおもわれた。
日本には滝が多い。そのなかで那智の滝はながめる滝ではなくて、瞑想する滝である。あの天地のくずれるように、さくなだりに落ちる水音は、われわれの頭のなかから雑念をたたき出して、次元のちがう世界を思考させる。われわれは頭を垂れて、滝にうたれるように神秘にうたれるのである。あの滝を前にして酒を飲むものもなければ、放歌するものもない。中世の滝籠行者たちはあの水音のなかに、神の啓示や怪異の声をきいたという。それも次元のちがう世界からの呼び声であろう。昭和の現代でも、那智大社のお滝本祈祷所の宿直神官は、夜中怪異の声になやまされて眠れないので、宿直をやめたという。
那智の滝の神秘は大滝の水源をさかのぼって、二之滝、三之滝とすすむにつれていよいよ深まる。髑髏がごろごろしていたという念仏の滝もある。川筋が曲がるたびに、向こうから大蛇か竜があらわれてきそうな渓谷である。そこに身をおくだけで戦慄を禁じえない谷の奥で、花山法皇は何故一人で千日の山寵りをしたのであろうか。それは大滝で現世から断絶された、次元のちがう世界への執念がなければ、とてもできることではない。私が法皇の行在所址へのぼって行こうとすると、道のまん中に五尺にあまる大蝮が悠々と横たわって、棒で追っても、闖入者よ去れ、といわんばかりに私を見上げて動こうともしなかった。
熊野の海はかつて補陀落渡海という水葬や入水往生のおこなわれたところである。熊野は山ばかりか海の彼方にまで「死者の国」があった。三山信仰の秘賾はこの「死者の国」であり、「蟻の熊野詣」も「死者の国」すなわち他界へのあこがれにほかならなかったのである。しかし近世以降、熊野神道は仏教からの離脱とともに「死者の国」からも脱皮した。これは近世の国学を背景にした惟神の神道、あるいは明治以後の国家神道の立場からは当然であろう。しかしその熊野神道も、本宮、新宮、那智の三山ともに、御祭神の神格や鎮座次第に定説がなく、当惑している現状である。
私はあえて熊野を「死者の国」とよぶ。それは宗教学的にいえば、死者の霊魂のあつまる他界信仰の霊場だったからである。これが熊野の謎をとく秘鑰であって、三山信仰の秘密も、熊野詣の謎もこれによってとかれるだろう。熊野は紀州ばかりでなく、出雲にもある。しかしこれも一方から他方へ移ったというのでなく、死者の霊魂が山ふかくかくれこもるところはすべて「くまの」とよぶにふさわしい。出雲で神々の死を「八十隈手に隠りましぬ」と表現した「くまで」、「くまど」または「くまじ」は死者の霊魂の隠るところで、冥土の古語である。これは万葉にしばしば死者の隠るところとしてうたおれる「隠国」とおなじで、熊野は「隠野」でもあったろう。
熊野は中世には浄土信仰のメッカになるが、これも「死者の国」を仏教の「浄土」におきかえたまでである。そして熊野三山に奉斎される神々も、のちにくわしくのべるように死者信仰にふかいかかわりをもつ神々が多い。神は死の穢をきらうのが常識であるが、民俗学に裏付けられた現代の宗教学は、日本人の神観念の成立を、死霊から祖霊へ、祖霊から神霊への霊魂昇華説で説明する。したがって熊野三山の神々が死者信仰の影をのこしていても、なんら不思議ではない。
熊野の魅力は、海と山と温泉の風光の美とともに、宗教と歴史の奥行のふかさにある。ふみしめる石磴の一段一段にも、見上げる老杉の一本一本にも信仰と歴史が息づいている。熊野の黒い森と青い海にかくされた謎をかみしめながら、日本民族の幽玄な心と悠久の歴史を思いたいものである。
講談社、五来重『熊野詣』P1-7
いかがでしょうか。この箇所を読んでいるだけでも熊野に興味が湧いてきますよね。私もぜひ現地に行ってみたいという気持ちでいっぱいです。
また、浄土真宗僧侶である私にとって熊野と浄土信仰の繋がりについても非常に興味深いものがあります。死者の世界たる熊野がどのように形成され受容されていったのかを考察する本書は実に刺激的でした。
熊野に興味のある方にぜひおすすめしたい一冊です。
以上、「五来重『熊野詣』概要と感想~死者の国、浄土信仰の聖地としての熊野を知るのにおすすめ参考書」でした。
Amazon商品紹介ページはこちら
次の記事はこちら
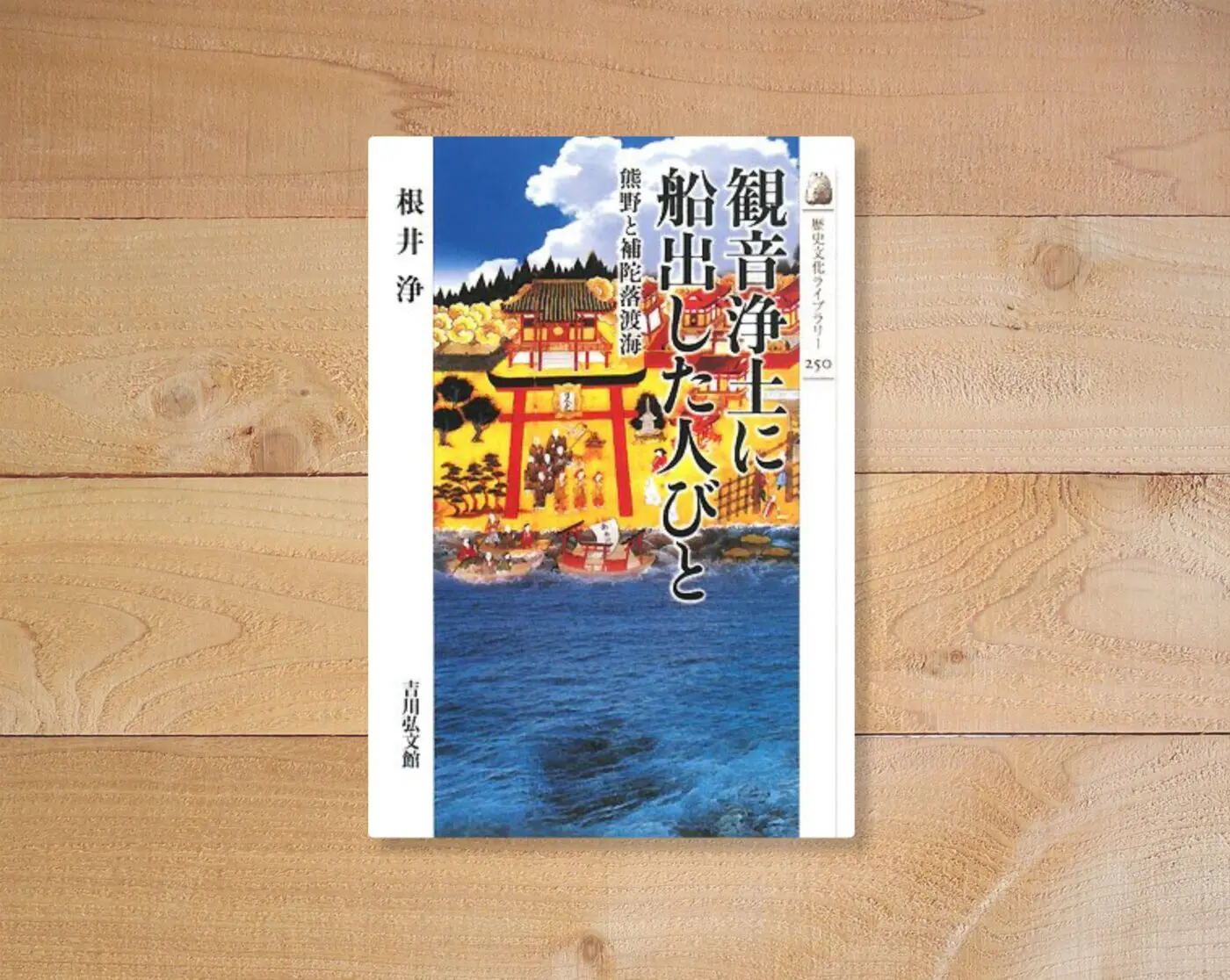
前の記事はこちら
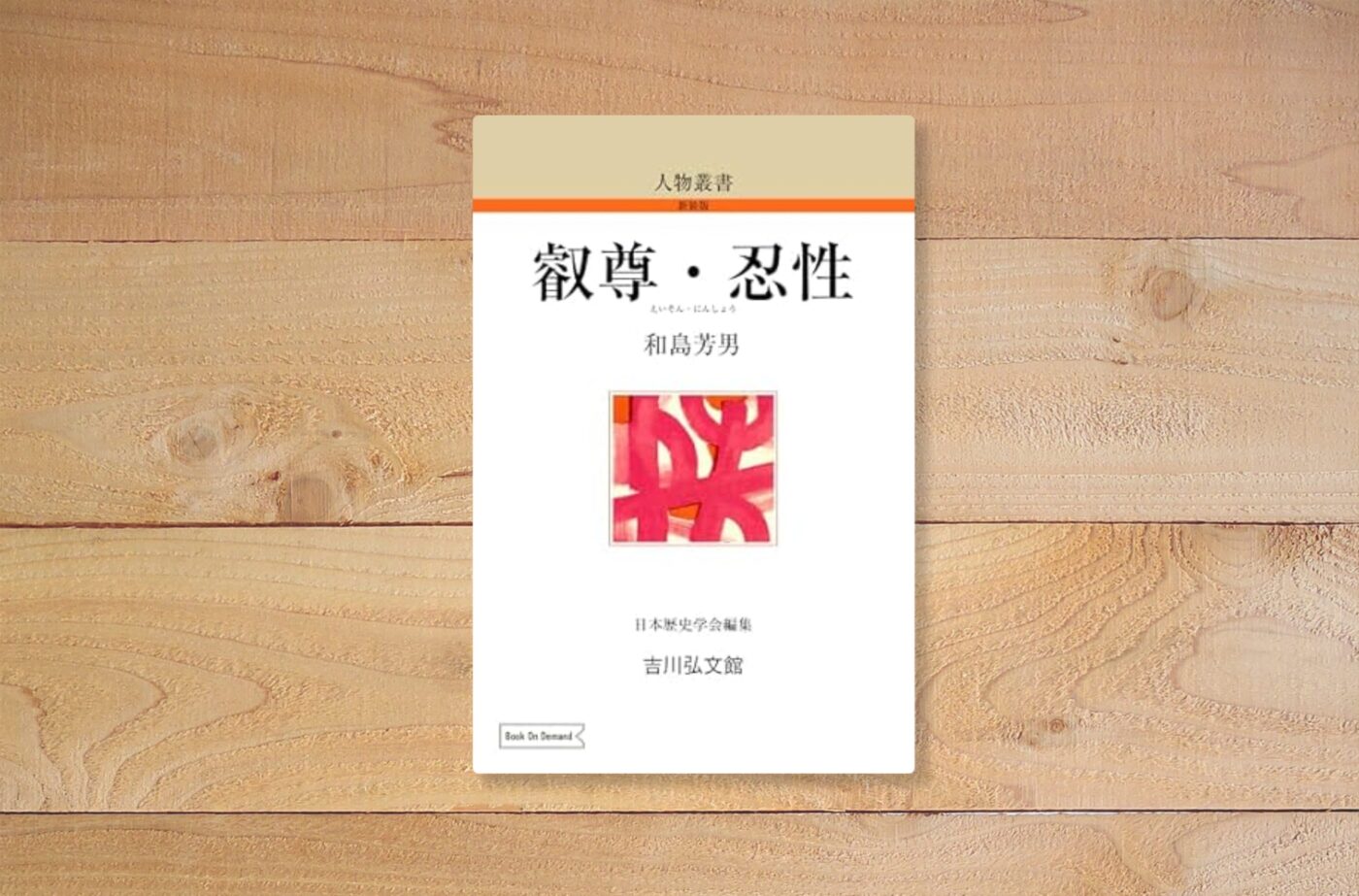
関連記事