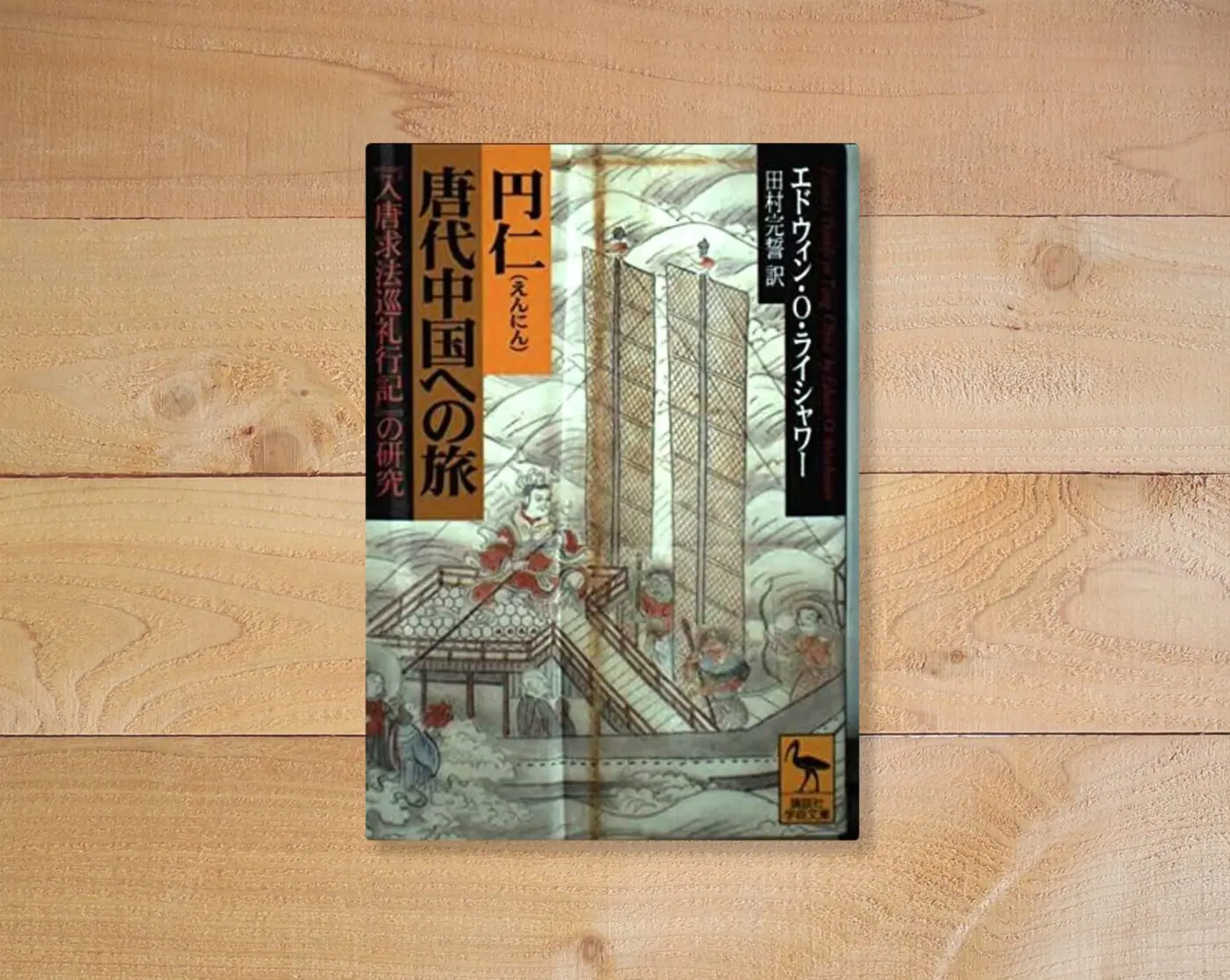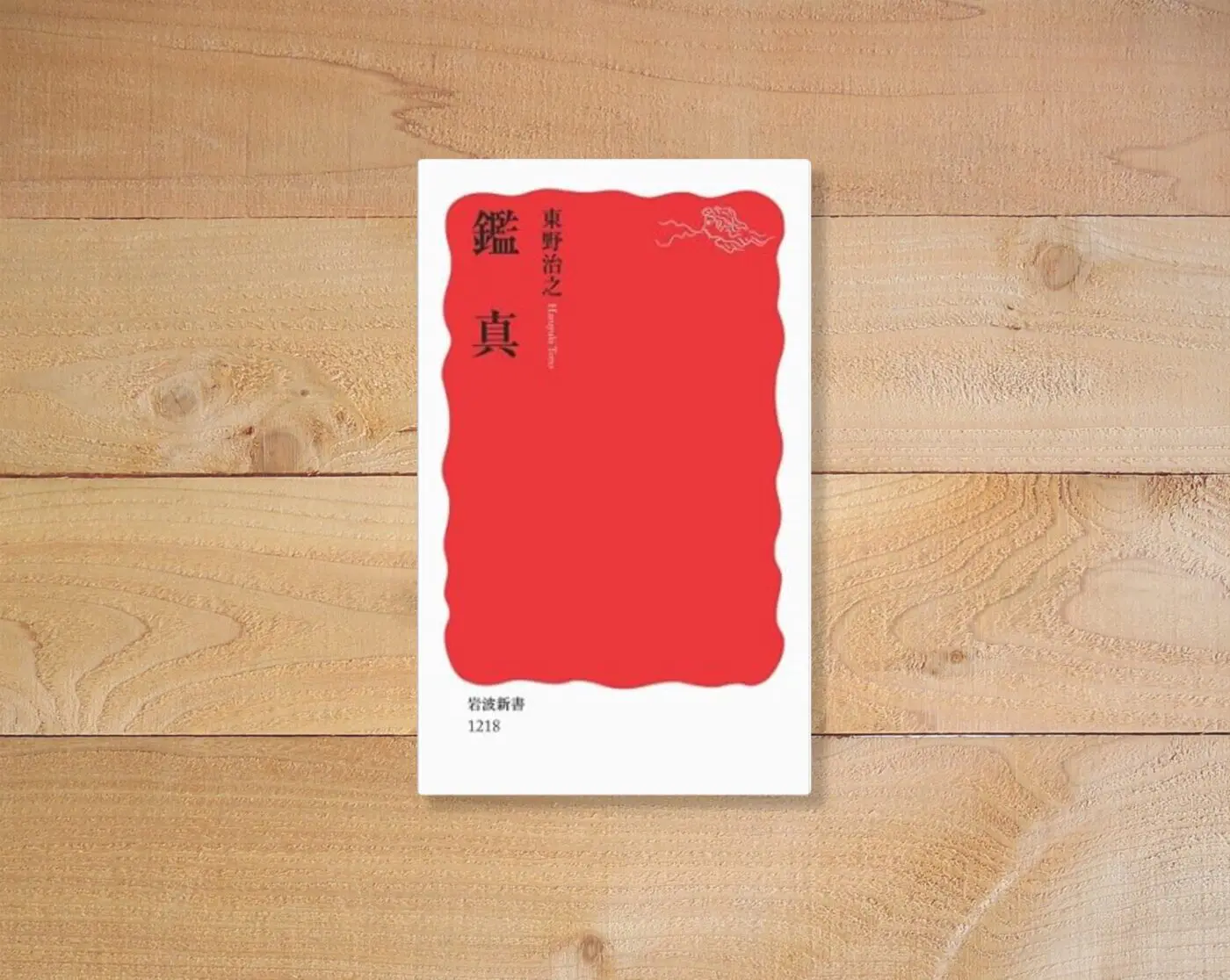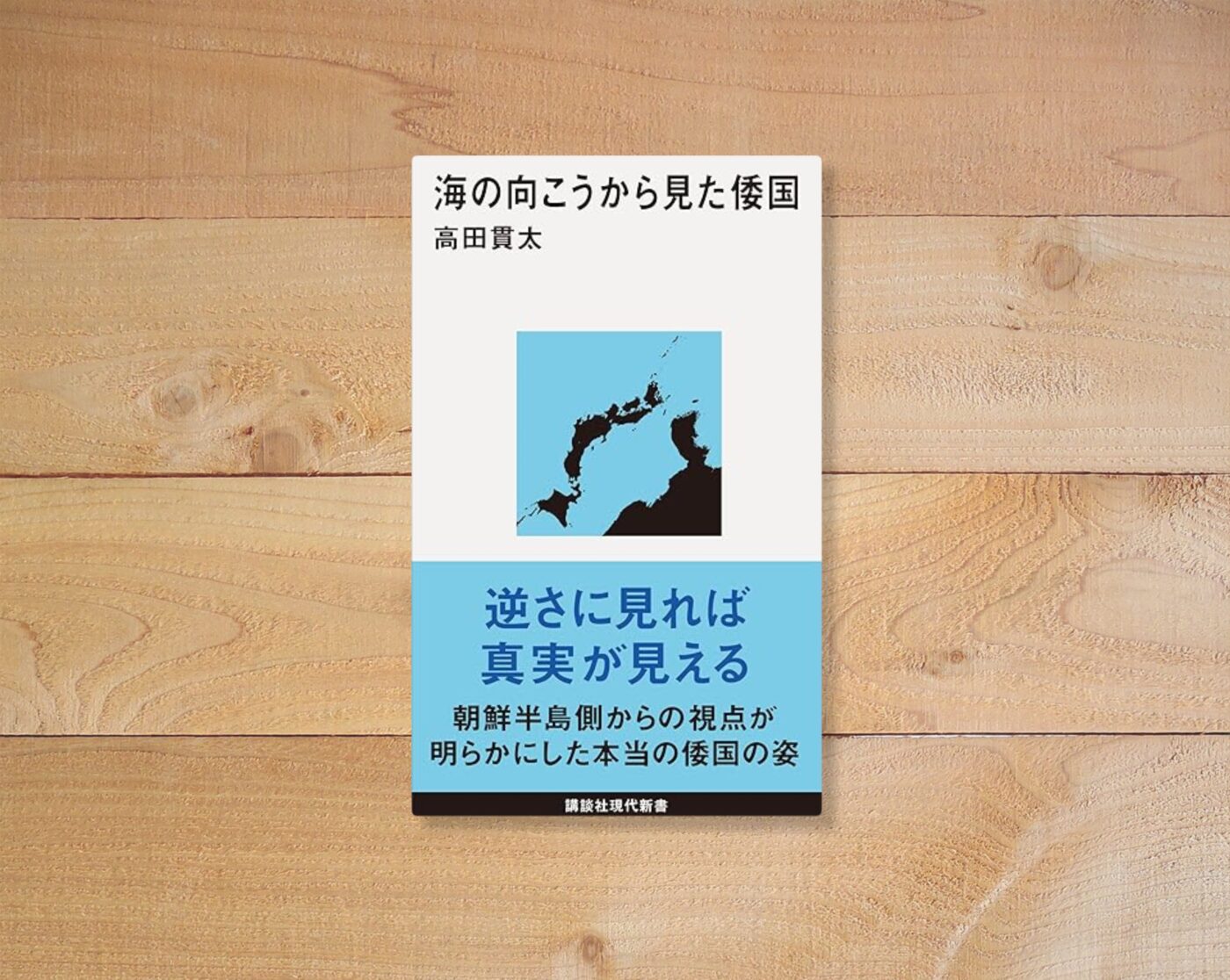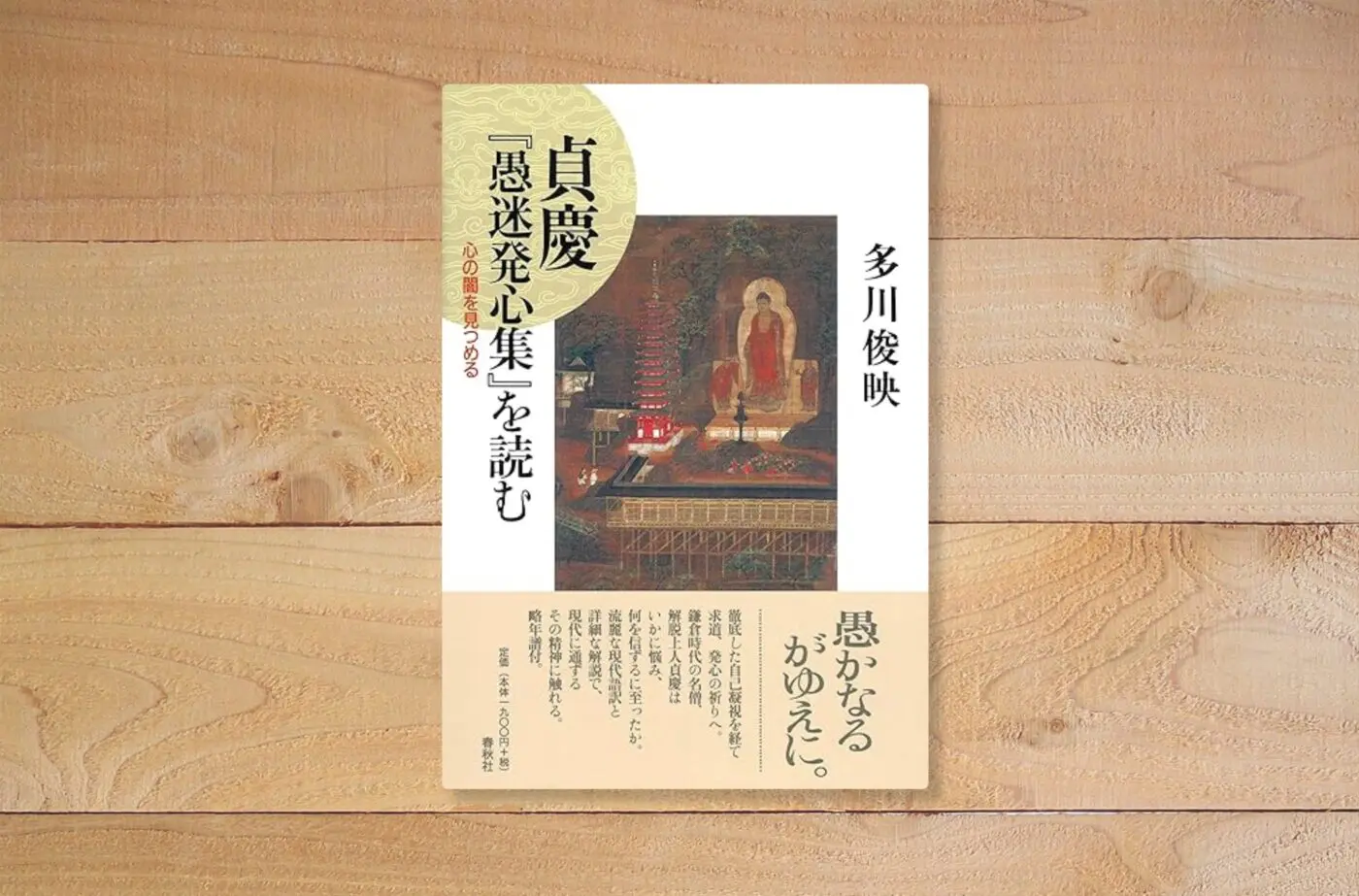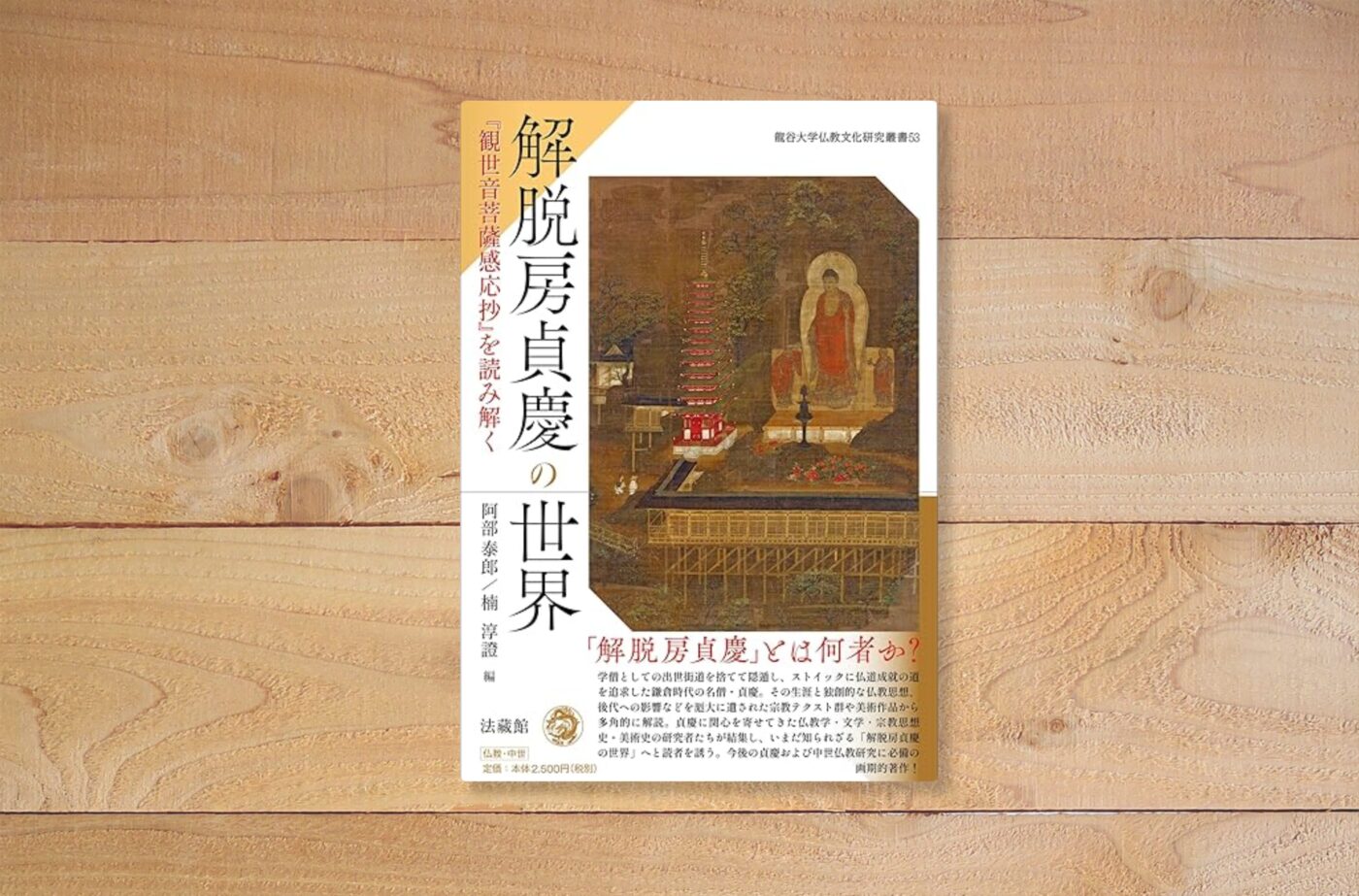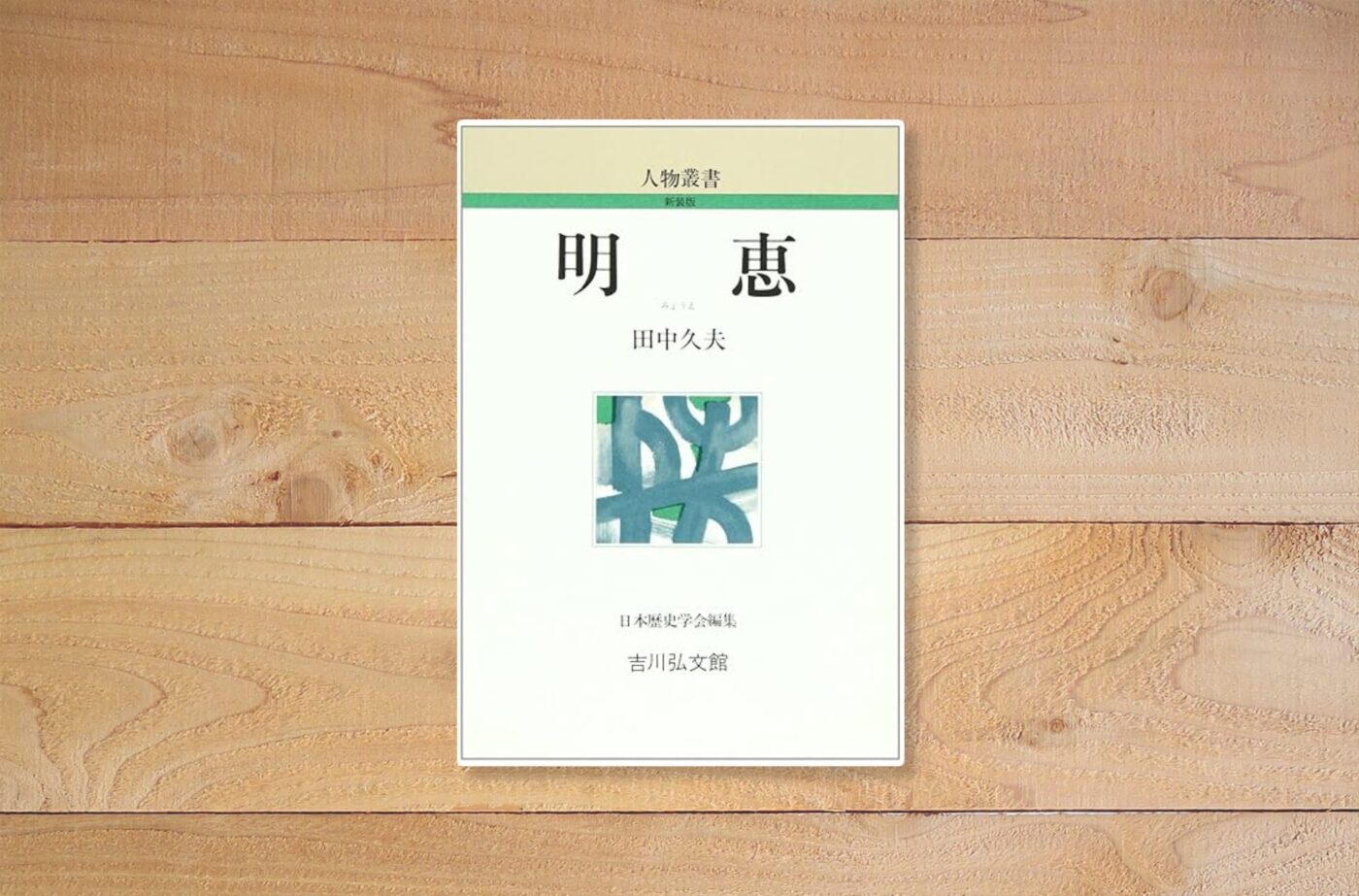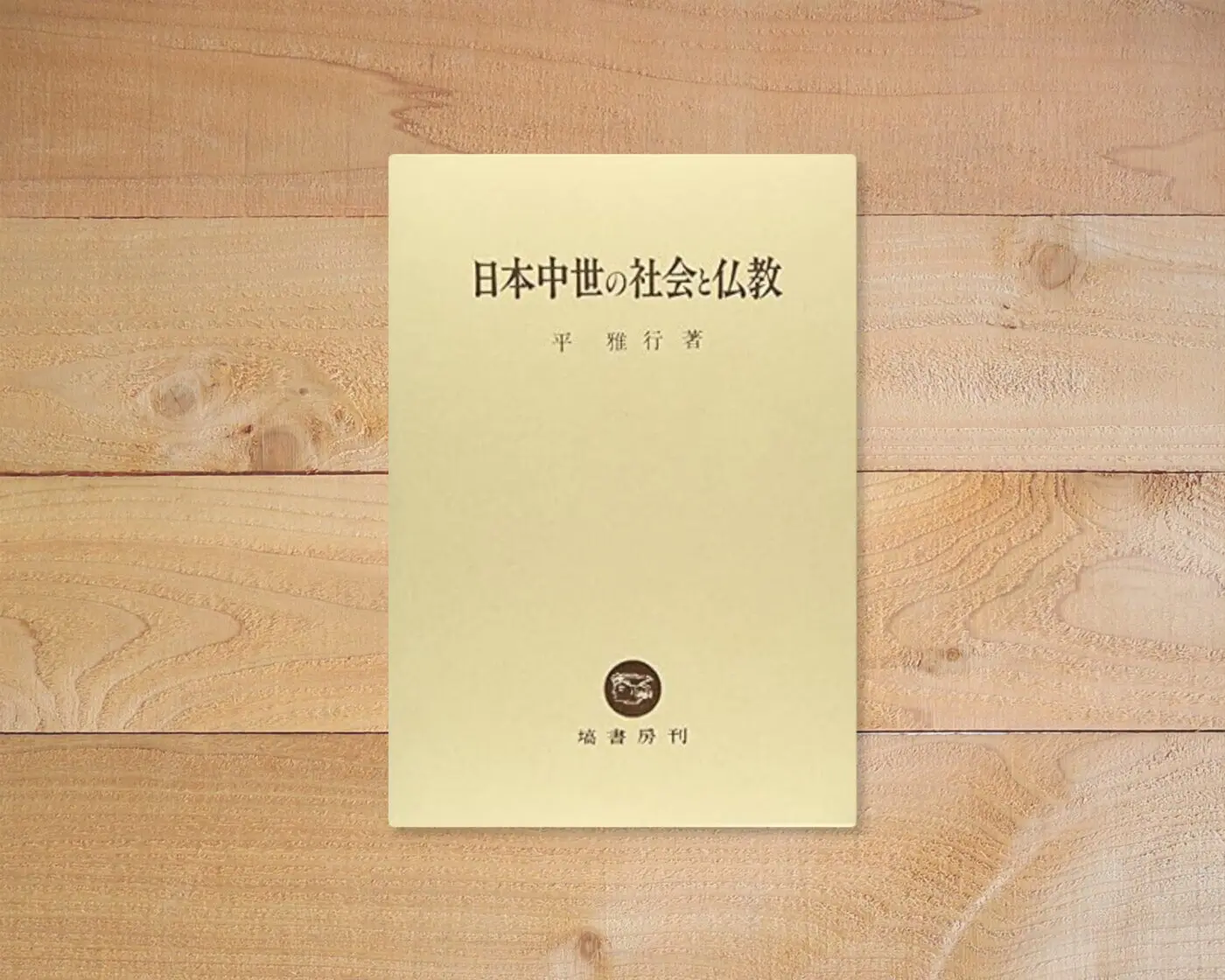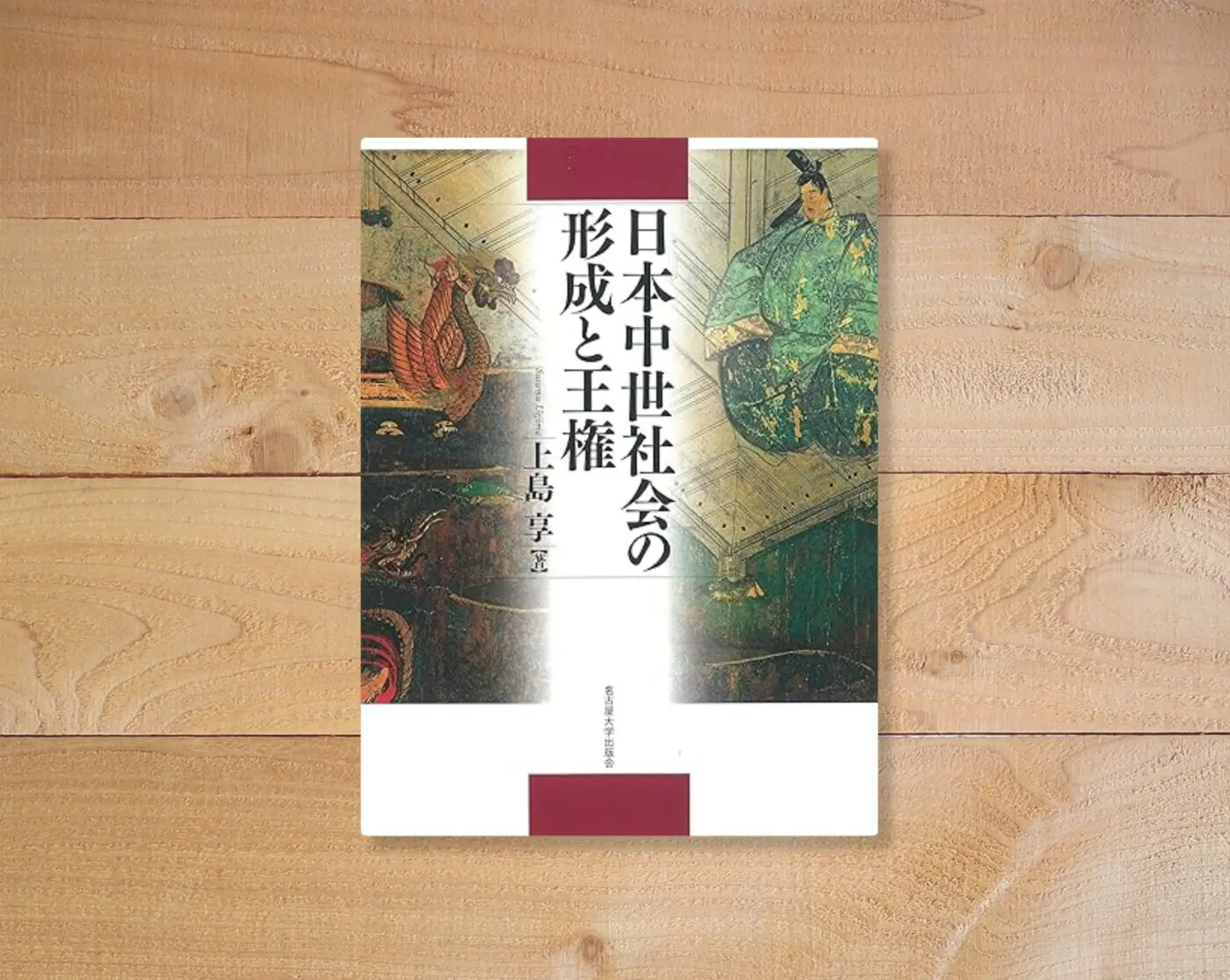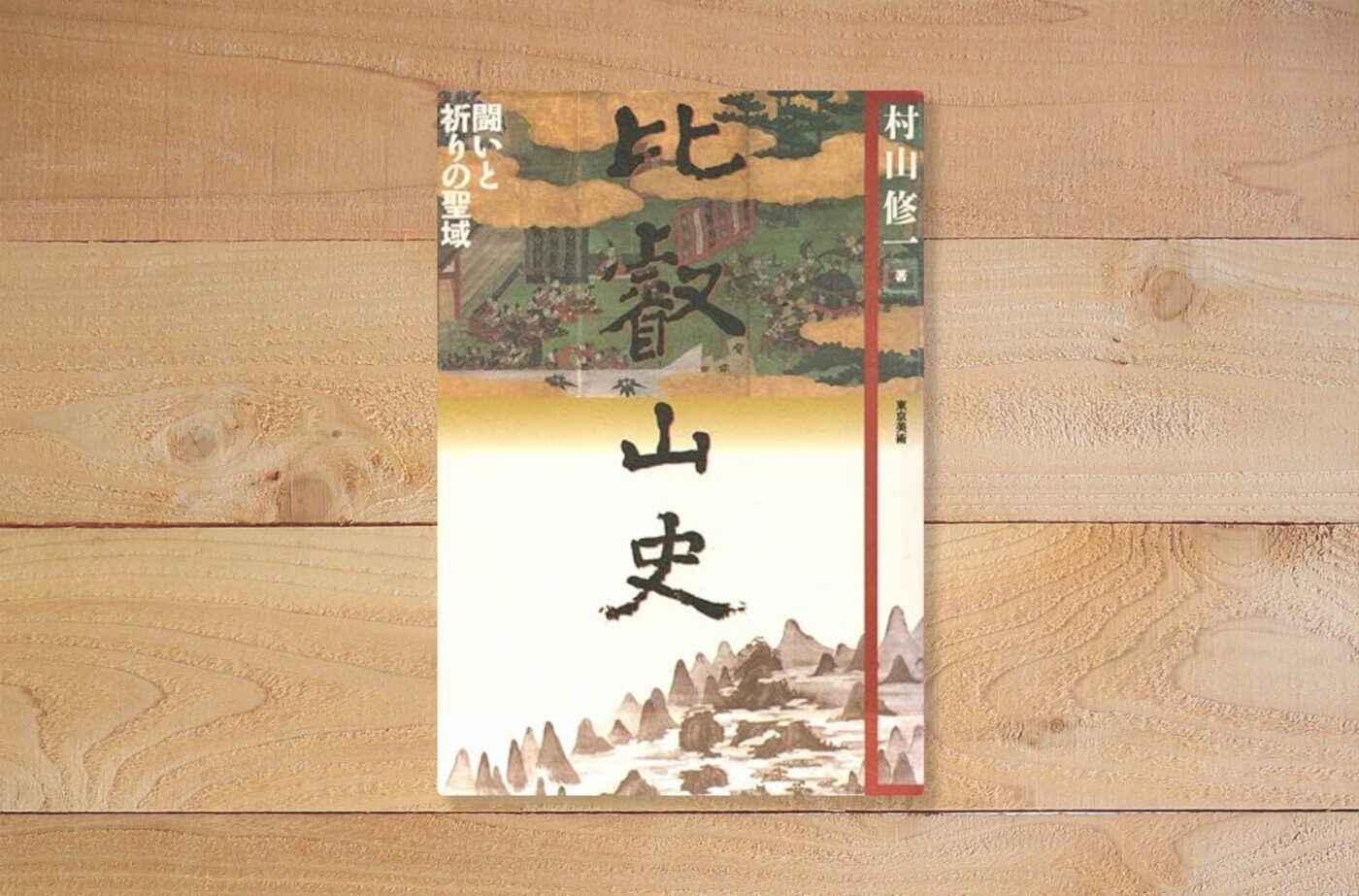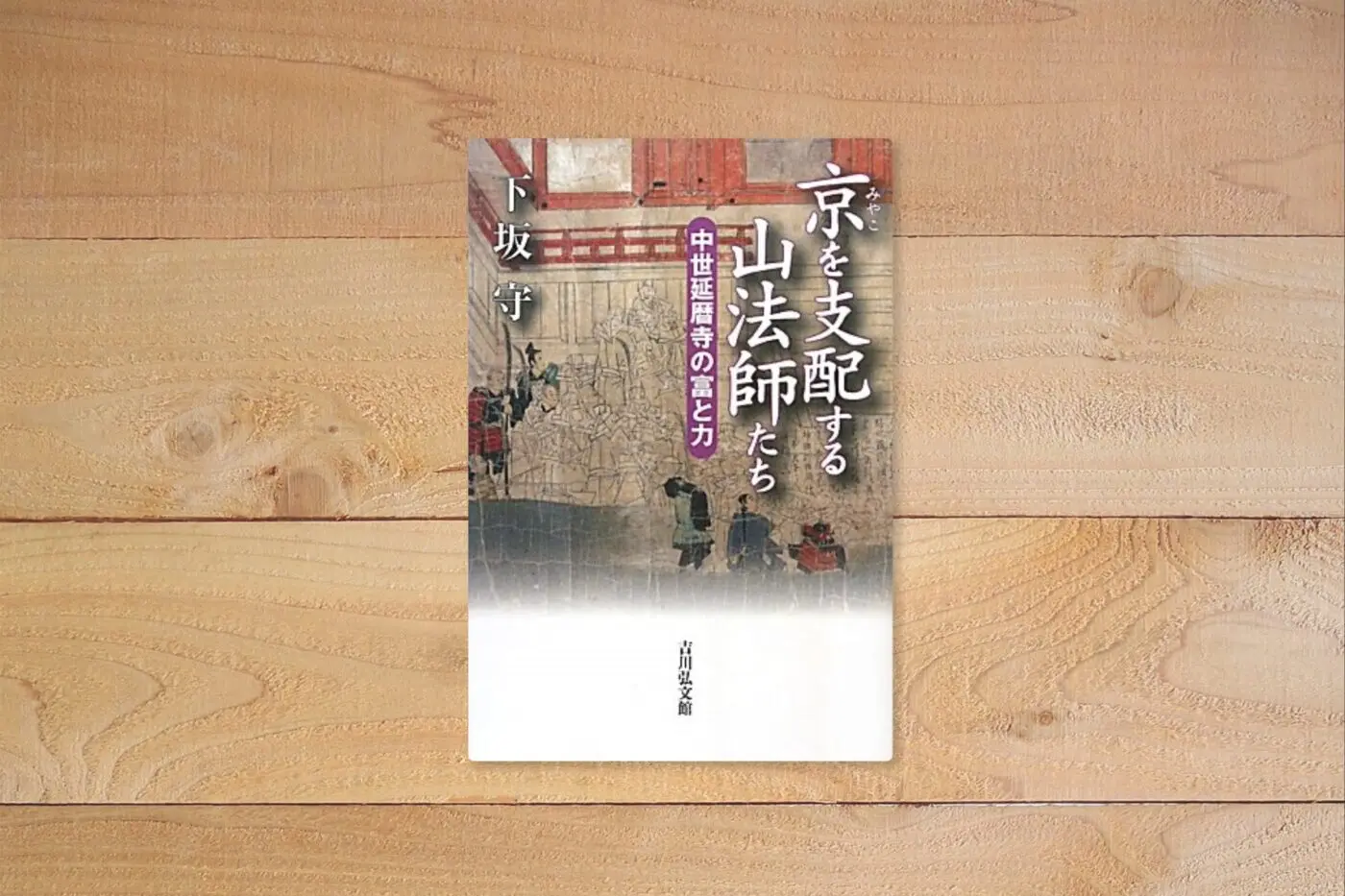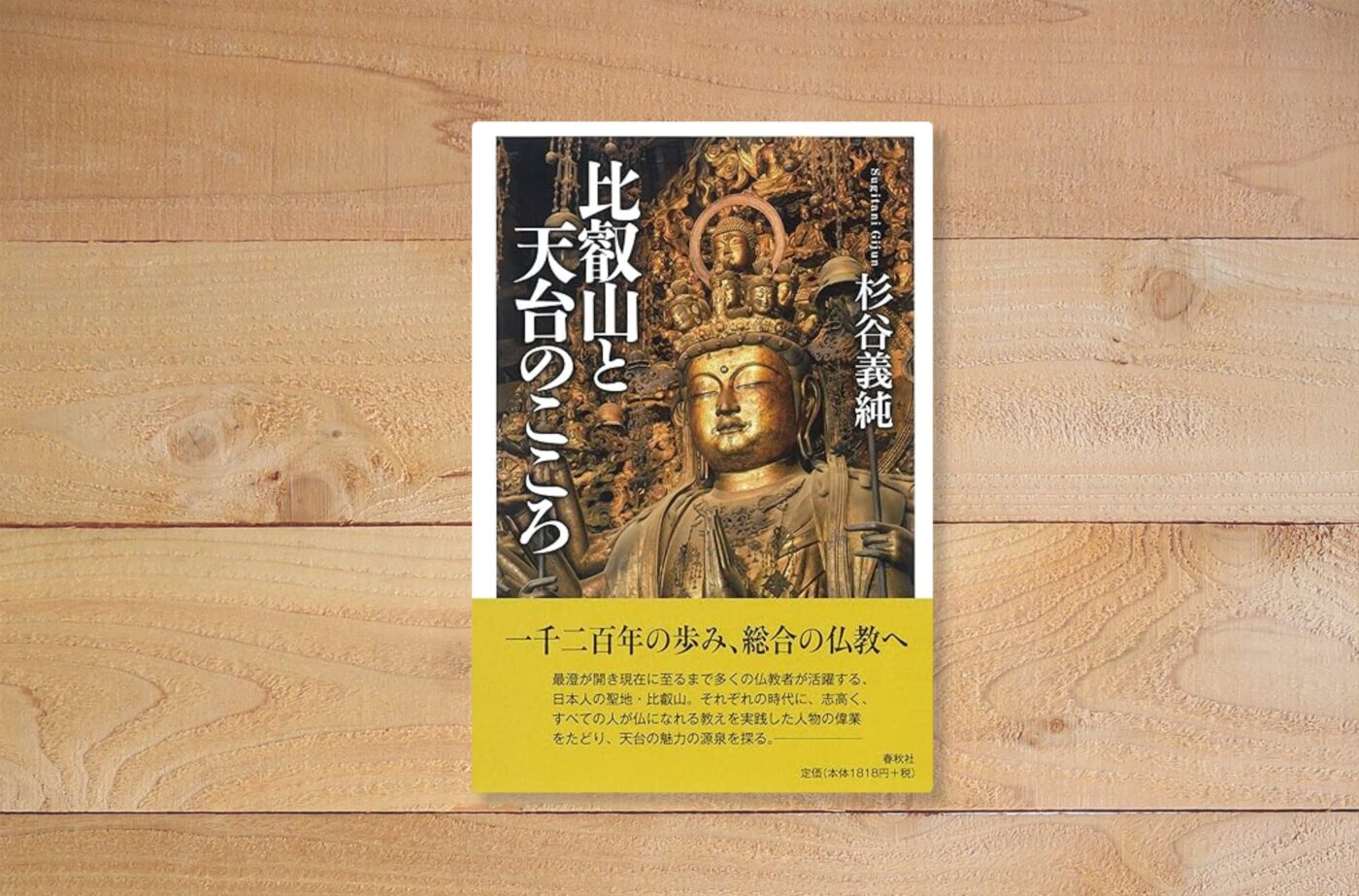榎本渉『僧侶と海商たちの東シナ海』あらすじと感想~遣唐使の実態と僧侶たちの留学事情を知れるおすすめ参考書!
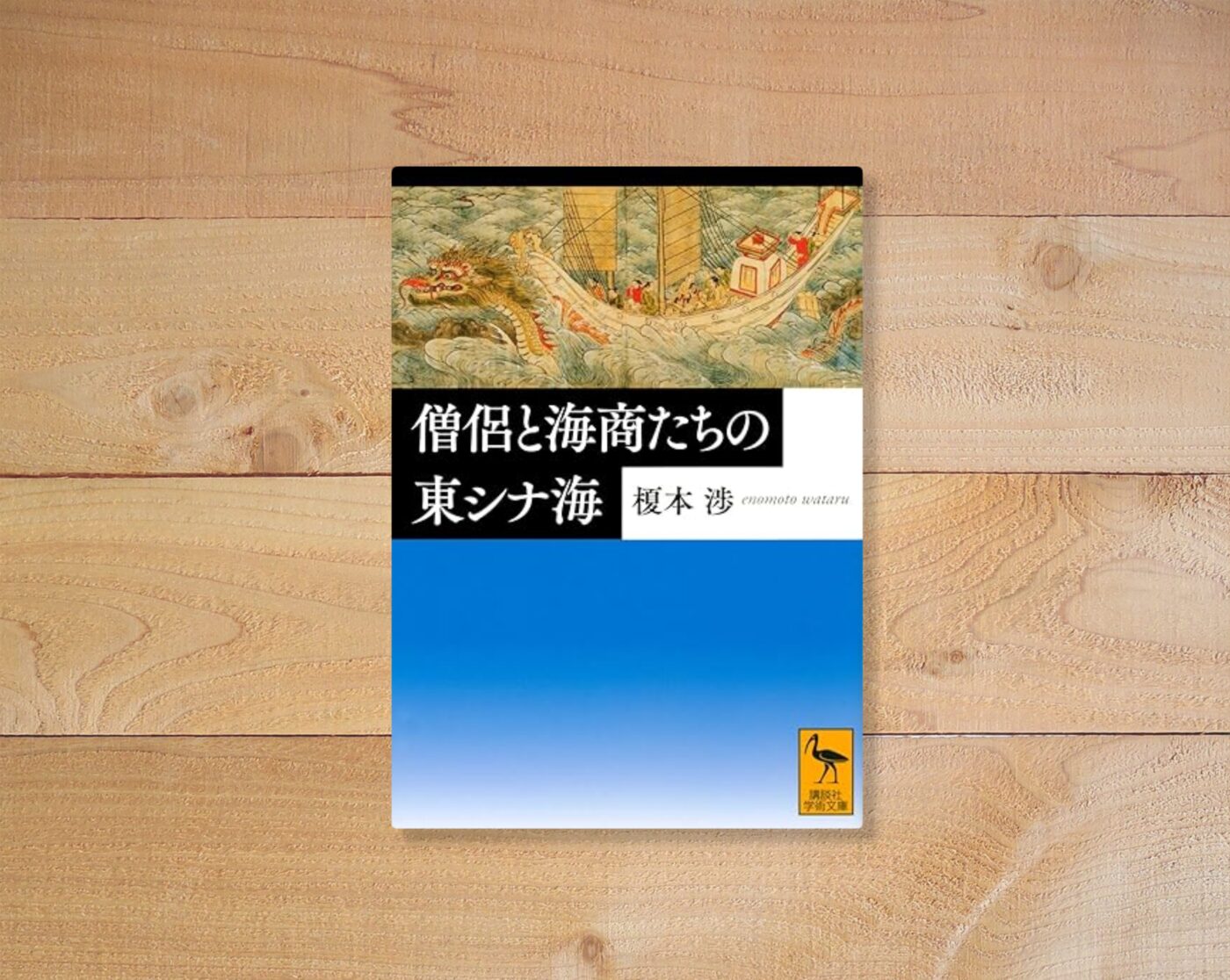
榎本渉『僧侶と海商たちの東シナ海』あらすじと感想~遣唐使の実態と僧侶たちの留学事情を知れるおすすめ参考書!
今回ご紹介するのは2020年に講談社より発行された榎本渉著『僧侶と海商たちの東シナ海』です。
早速この本について見ていきましょう。
■知と富がドライブするダイナミックな中世史!■
「894年遣唐使廃止」は日本を変える出来事ではなかった!
列島を取り巻く大海原をたくましく乗り越え、「外」と日本を繋ぎ続ける人たちがいたのだ。
利を求め、危険を顧みずに海を闊歩する海商たちと、
彼らの助けを得て、最新の知識を求めて大陸へ渡ろうとする僧侶たち。
史料に数多く残された僧たちの足跡を辿ることで、海域交流の実相に迫り、歴史世界としての東シナ海を描き出す!従来の「日本史」の枠を超えて、より広く深く歴史を知る一冊。
Amazon商品ページより
本書は日本仏教の歴史を考える上で非常に重要な視点を与えてくれる名著です!
まず、上の本紹介の『「894年遣唐使廃止」は日本を変える出来事ではなかった!』という言葉からして衝撃的ですよね。
894年の遣唐使の廃止は、あくまでその時の遣唐使を出さないということであって、そもそも最後の遣唐使は838年のことでありました。つまりすでに60年近くも送られていなかったことになります。だからこそ『「894年遣唐使廃止」は日本を変える出来事ではなかった!』のです。これには思わずなるほど!と思わずにはいられませんでした。
本書の前半部分でこうした遣唐使の実態が語られるのでありますが、読んでいて私も驚くことばかりでした。そもそも遣唐使なるものが20年、下手すれば30年に1回ほどのスパンで送られるかなり限定的な交流だったということ。一度留学生として渡航した場合次の帰国のチャンスが次の遣唐使船が来た時、つまり20年から30年後という途方もなく長い期間を覚悟しなければならなかったという事実。
これまで私は日本史や仏教史の本を読んできましたが、この帰国便を得る困難について考えたことがなかったことを本書を読んで気づかされました。入唐僧として有名な最澄、空海にしても、唐に行った事実は頭に残っても、帰ってくる時の遣唐使のシステムについてまでは想像すらしてこなかったというのが正直なところです。
基本的に遣唐使船は唐に着いてから1年後に、公務を終えた遣唐使を連れて帰っていきます。その時に一緒に帰ってくるのが短期留学僧です。最澄はまさにこれでした。最澄は短い期間しか唐に入れなかったため、泣く泣く勉強を切り上げて帰って来たと言われますが、もしこの時帰っていなかったら次に帰るチャンスは次の遣唐使船を待たねばなりません。つまり2、30年後です。もしこの時最澄が帰っていなかったら日本仏教の姿は全く別のものになっていたことでしょう。仮に無事2、30年後に帰ったとしてもその時すでに最澄はかなりの高齢です。そんな高齢の僧にエネルギッシュな活動はなかなか無理はあります。そう考えると最澄が早く帰って来れたというのはある意味幸運なことだったことでしょう。
では一方空海はどうだったかと言いますと、これまたすごい!
空海は本来20年以上留学して学ぶはずであったのですが、恵果和尚から密教の奥義を伝授されると、密教布教のため日本に帰ることを決意します。入唐して2年経った806年のことでした。
ここであれ?と思う方もおられるかもしれません。遣唐使船は1年経つと日本に帰ってしまうのでは?
そうです。最澄を乗せた遣唐使船は帰ってしまっていました。しかし遣唐使船団は全部で4隻あります。804年段階で唐にたどり着いたのは第1、第2船のみで、これが最澄たちと一緒に帰った船になります。
そして残りの船はどうなったかというと第3、第4船の2隻は遭難してしまっていたのでした。その第4船が遅れて何とか唐に到着し、その帰りの便に空海が乗って来たのではないかとされています。これは学術的にも諸説あるようで私には何とも言えませんが、空海の強運ぶりが感じられるお話です。もしこの遭難船がいなければ空海は20年以上も日本に帰ることができず、日本での活躍もなかったかもしれません。やはり空海は何か持っています。
また、838年の最後の遣唐使の一団にいた円仁についても非常に興味深いエピソードがあります。円仁は自らの求道のため帰りの遣唐使船に乗らずに違法に唐に滞在することを選びました。円仁はどうしても唐の仏教聖地で研鑽を積みたかったのです。ただ、帰りの遣唐使船を逃せばもはや日本に帰る術はありません。しかもこれは事実上最後の遣唐使。もはや日本に帰ることをあきらめたのかと思いきや、この頃に東シナ海で大きな歴史の変化が訪れていたのです。
それが本書タイトルにもある海商の存在です。唐、朝鮮、日本をまたにかける大規模な商業船が生まれ始めていたのです。円仁はこの商船の力を借りて日本に帰国したのでありました。
本書ではこうした商船の存在が日本の歴史にどのような影響を与えたのかを見ていきます。特に鎌倉、室町時代に禅宗僧侶が大挙して中国に渡り、様々な交流をしていたその流れは非常に興味深かったです。
仏教を海商との繋がりから見ていく本書は新たな視点をくれるすばらしい参考書です。ぜひぜひおすすめしたいです。
以上、「榎本渉『僧侶と海商たちの東シナ海』あらすじと感想~遣唐使の実態と僧侶たちの留学事情を知れるおすすめ参考書!」でした。
Amazon商品紹介ページはこちら
前の記事はこちら
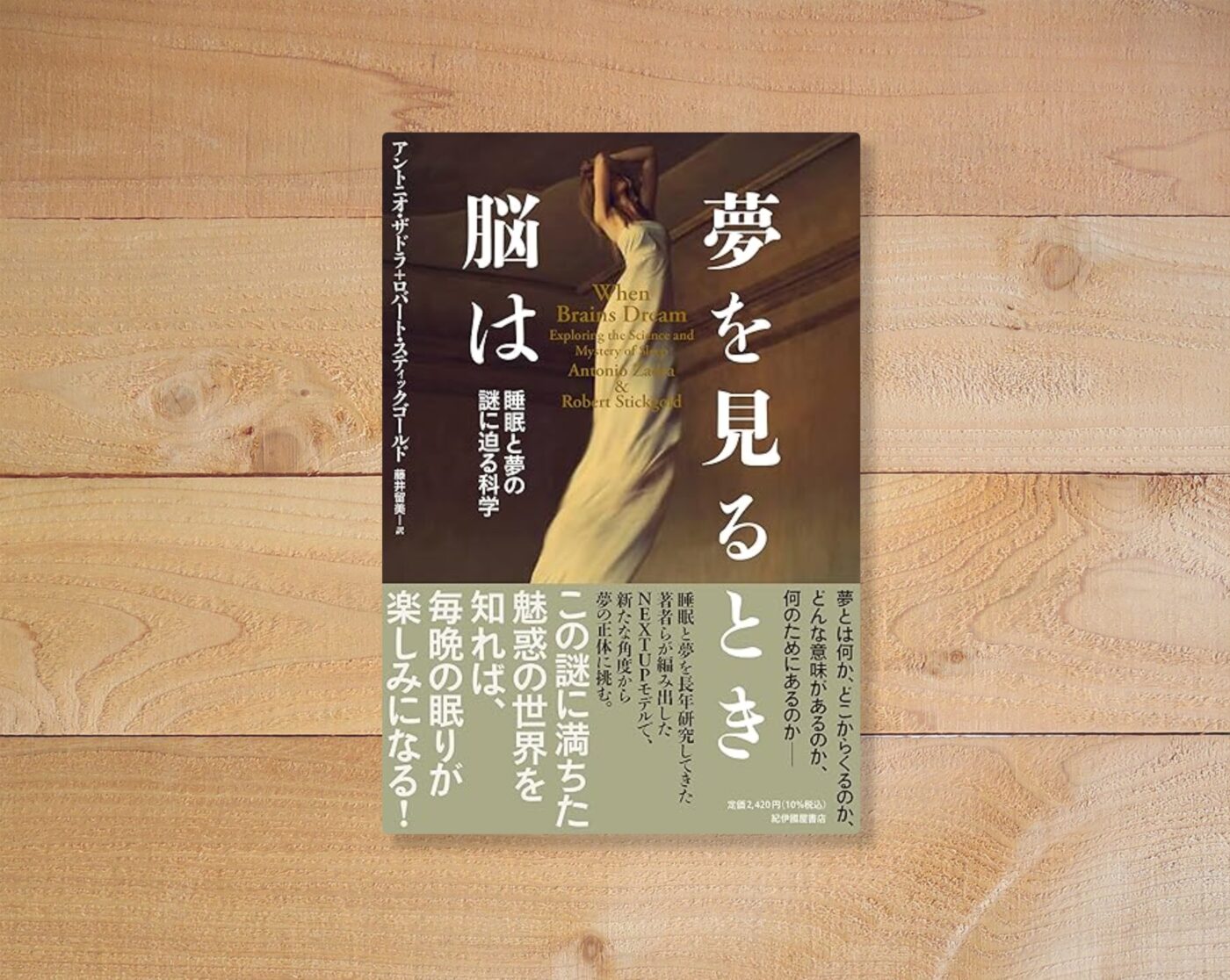
関連記事