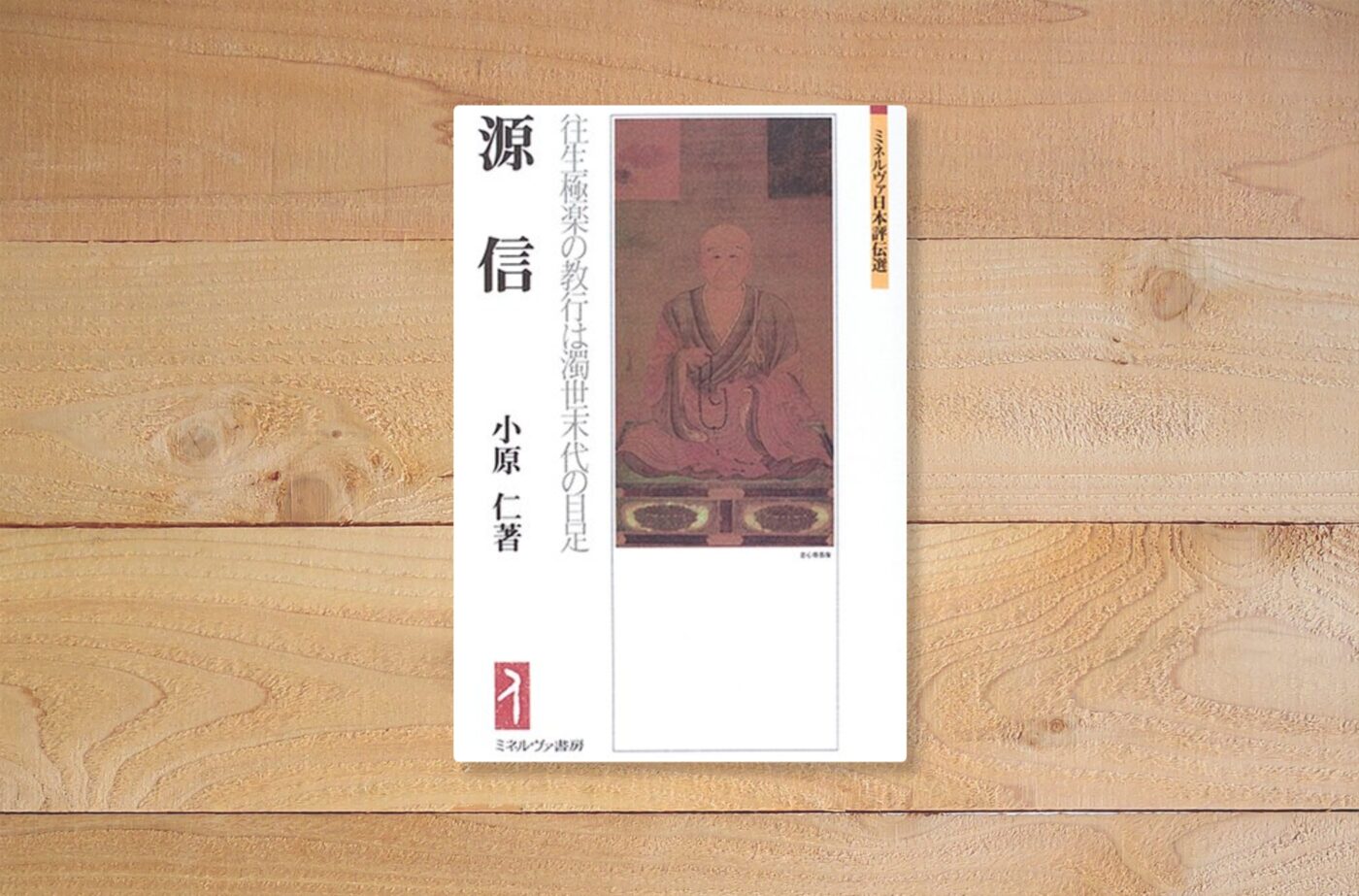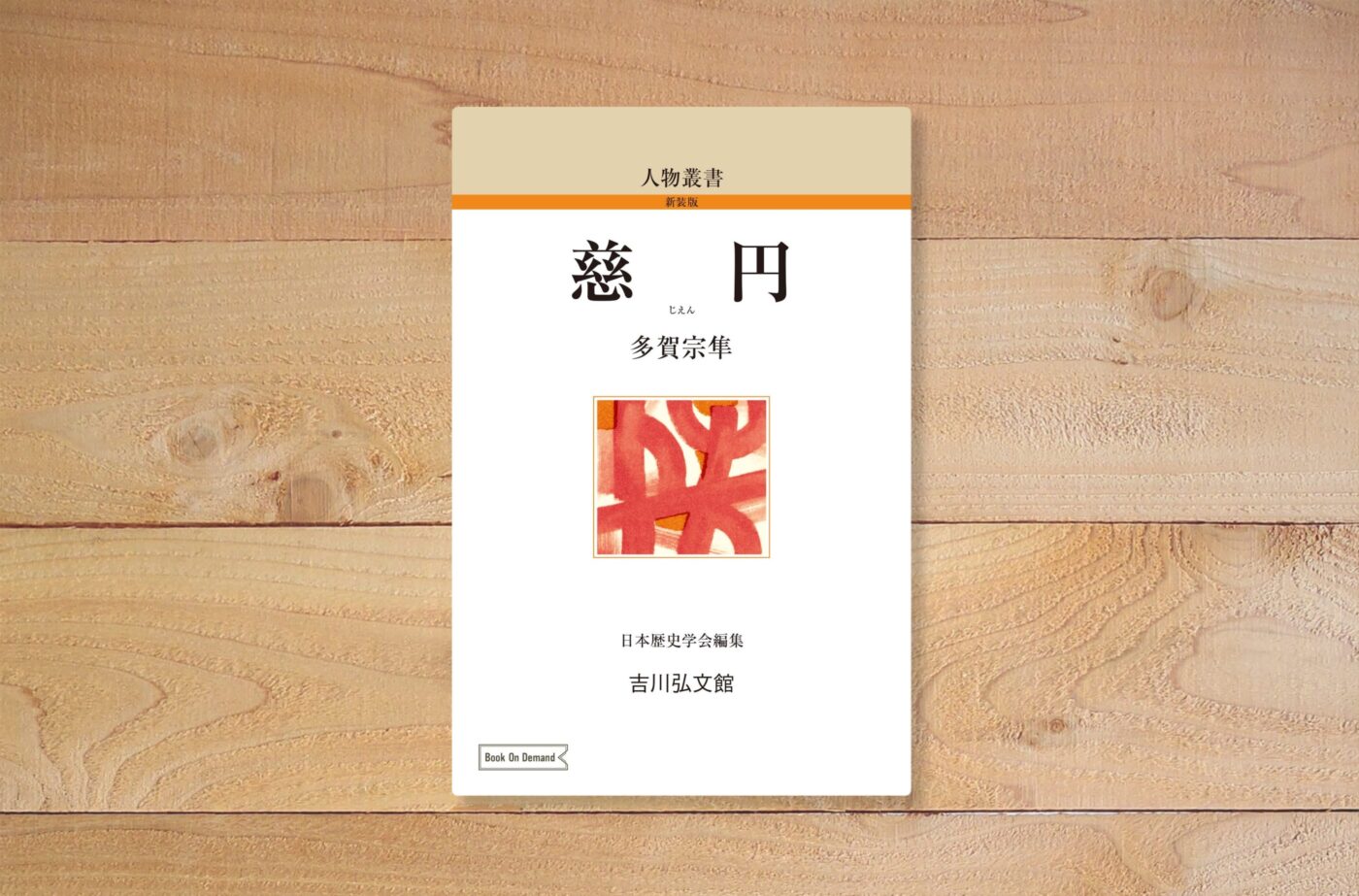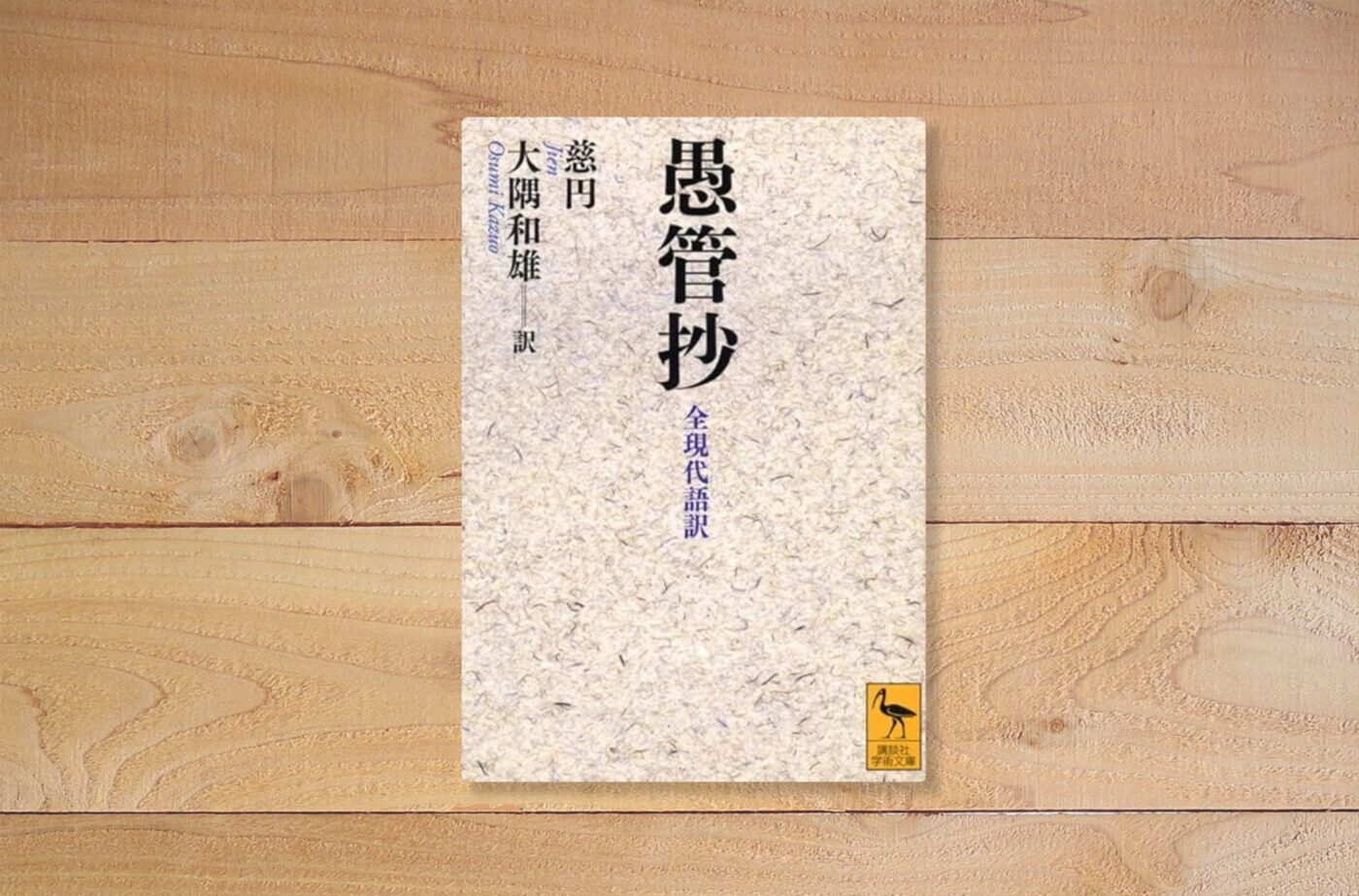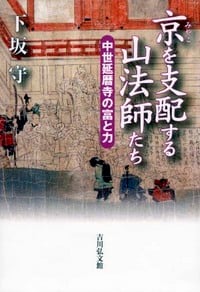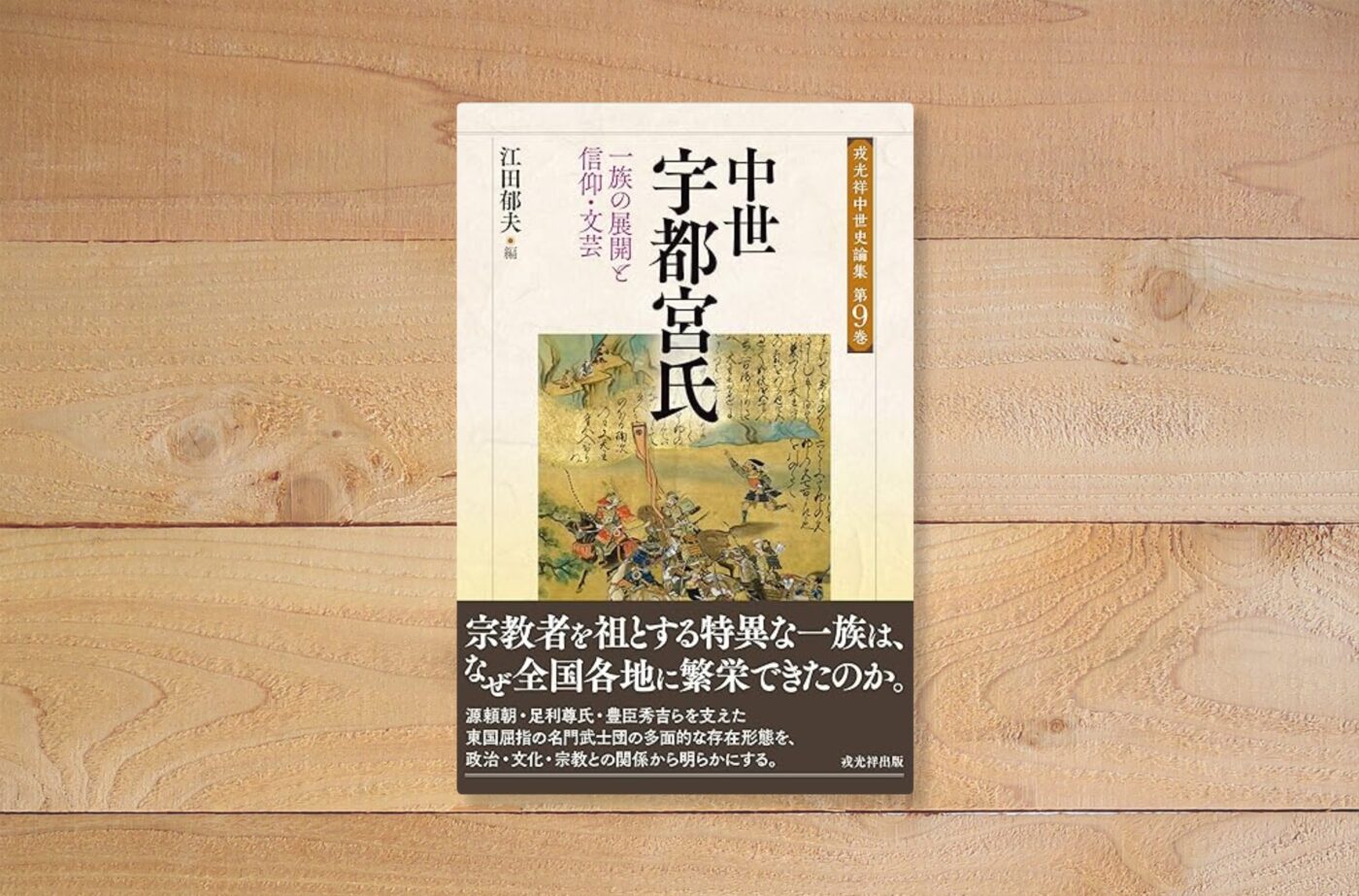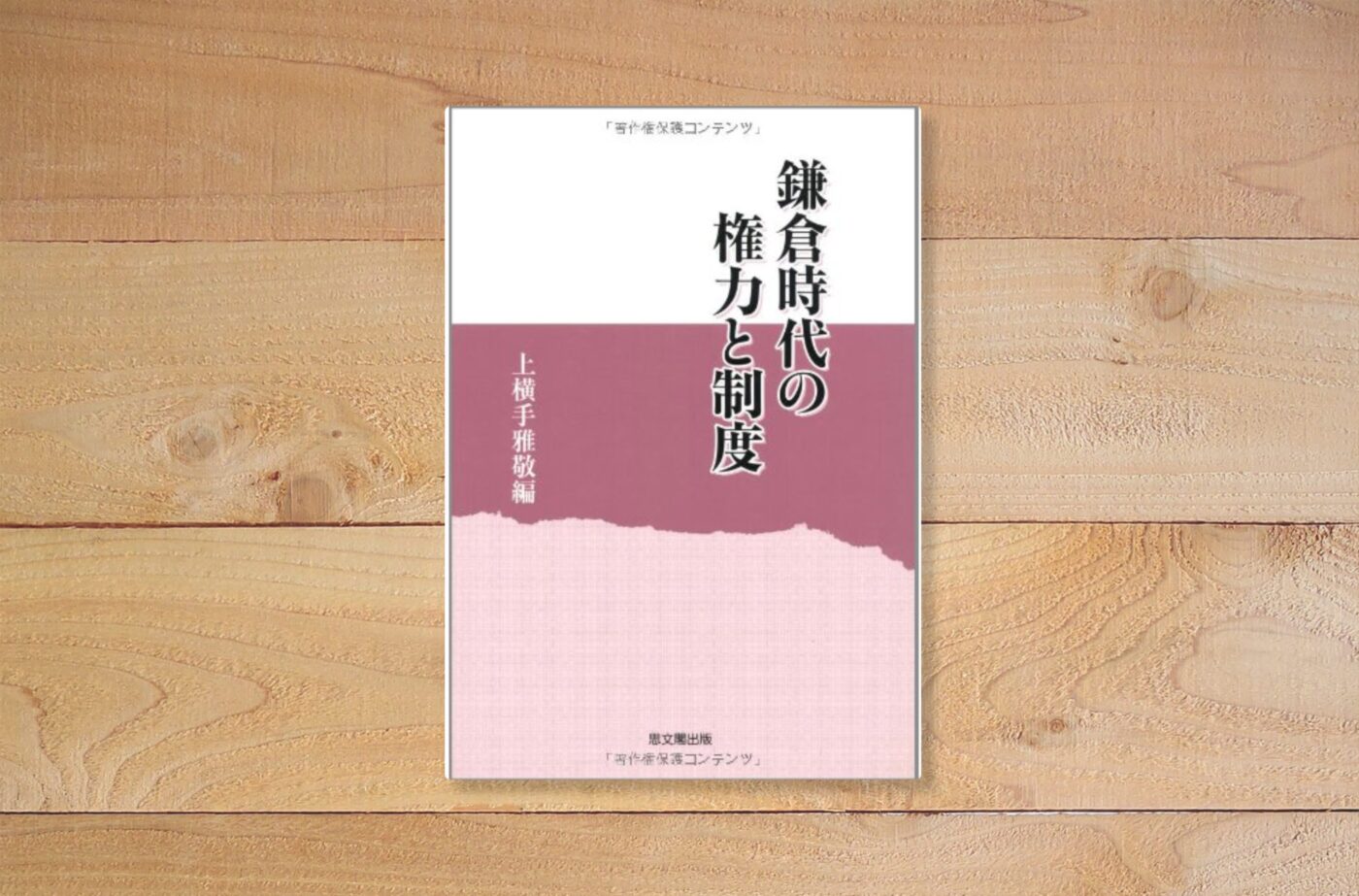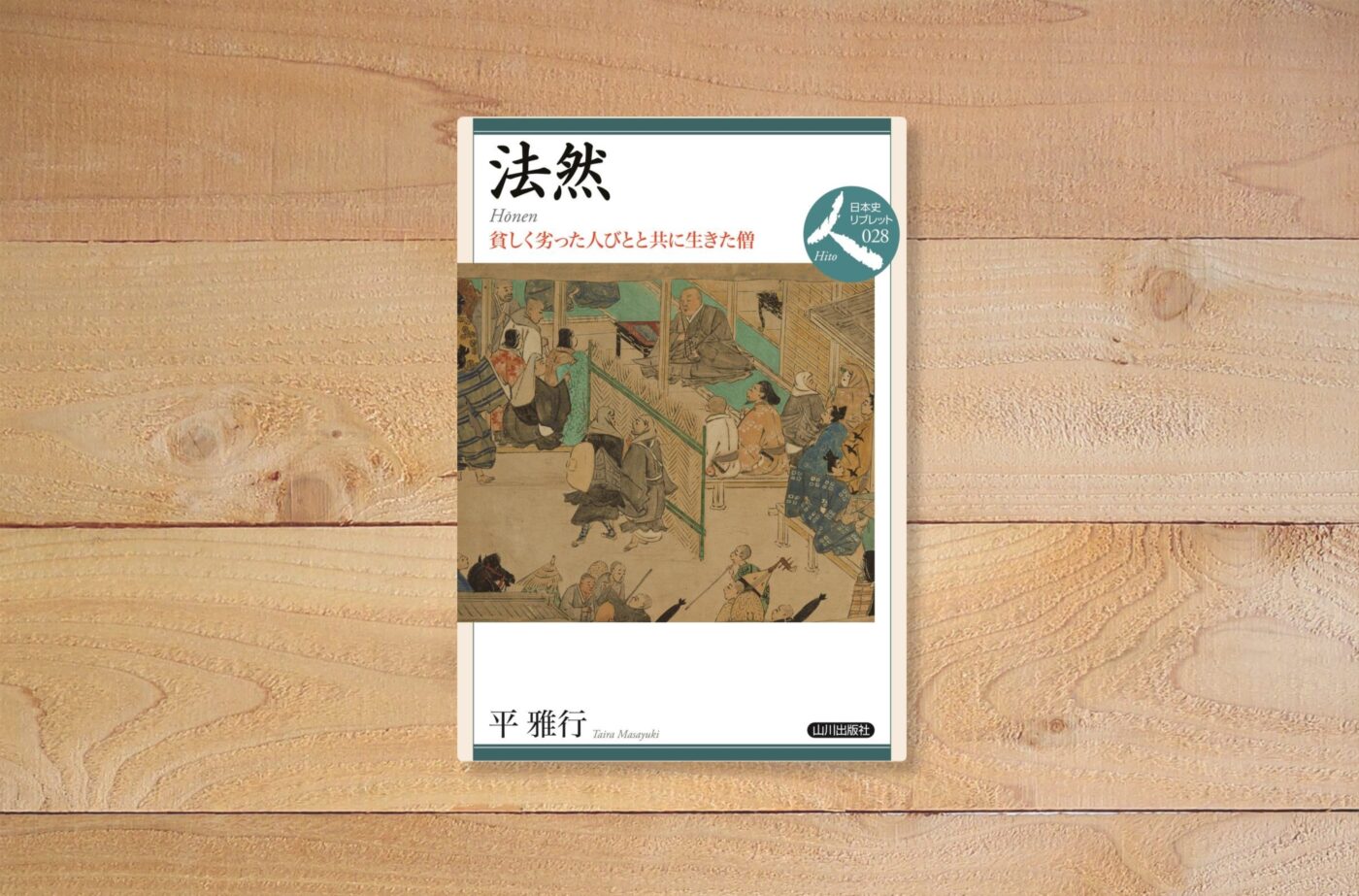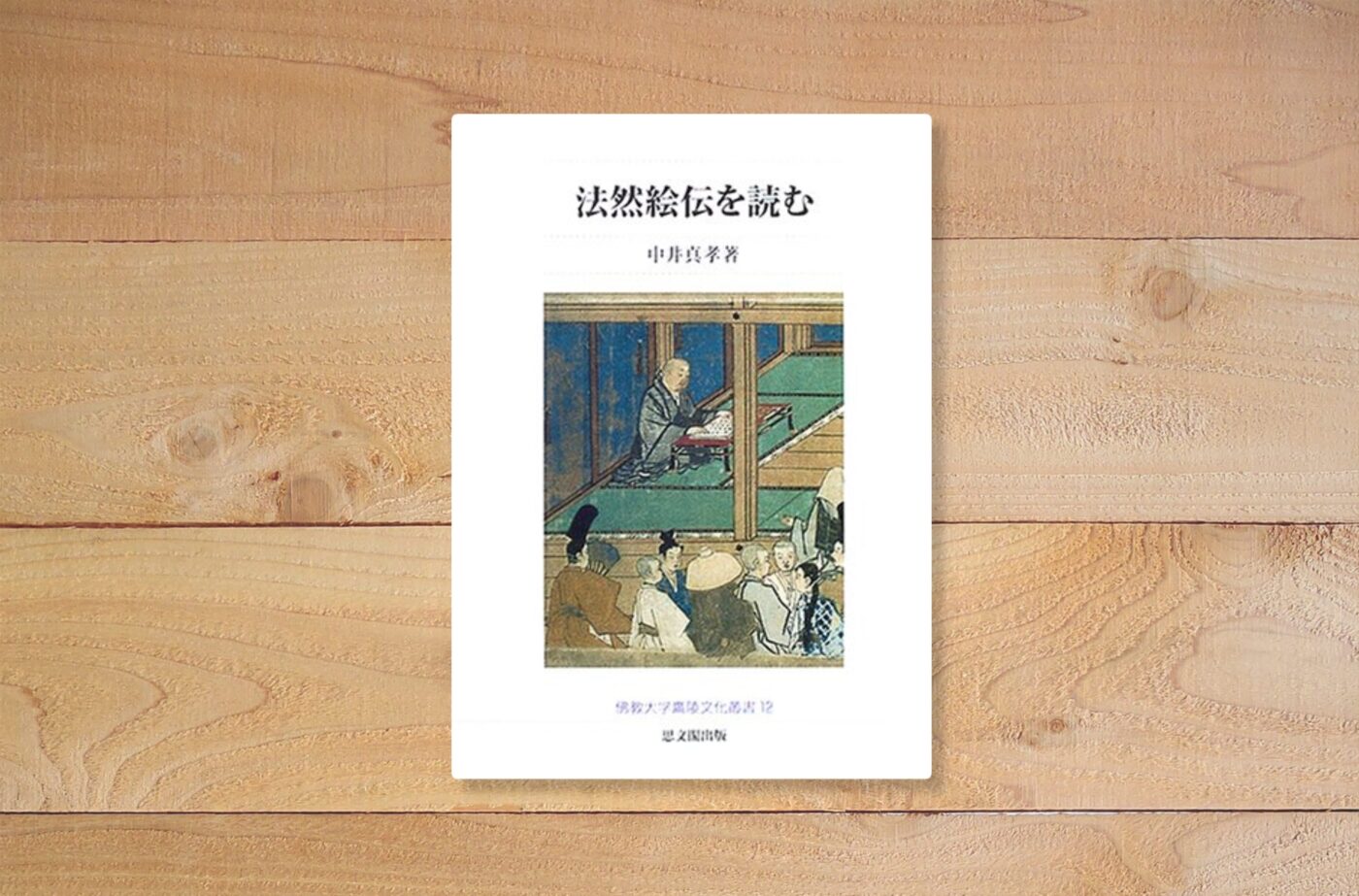下坂守『京を支配する山法師たち』概要と感想~比叡山と経済界の繋がりを知れる刺激的な一冊!

下坂守『京を支配する山法師たち 中世延暦寺の富と力』概要と感想~比叡山と経済界の繋がりを知れる刺激的な一冊!
今回ご紹介するのは2011年に吉川弘文館より発行された下坂守著『京を支配する山法師たち 中世延暦寺の富と力』です。
早速この本について見ていきましょう
白河上皇に「三不如意」の一つといわしめた「山法師」の嗷訴(ごうそ)。比叡山延暦寺が、中世を通じ権力の一角として力と富を持ち続けたのはなぜか。中世都市坂本を繁栄させ、神輿(みこし)振(ふ)りをもって、朝廷・幕府に自分たちの要求をつきつけ、戦乱を生き抜いた寺僧たちの姿から世俗権力としての実態を解明。延暦寺が果たした政治的・社会的な役割を浮き彫りにする。
吉川弘文館商品紹介ページより
本書『京を支配する山法師たち 中世延暦寺の富と力』は比叡山の僧兵の歴史やこの寺の政治経済的な強さの背景について知れるおすすめ参考書です。
この本について著者は次のように述べています。少し長くなりますが、日本仏教を考える上で極めて重要な提言がなされている箇所ですのでじっくり読んでいきます。
天仁元年(一一〇八)三月三十日、新月の夜、京都の人々はかつて見たことのない風景を目のあたりにする。「星の連なる如く」輝く光が、漆黒の比叡山の山影をゆっくりと下りてくる風景である(『中右記』)。以降、中世を通じて都人がくり返し恐擢し見上げなければならなくなるその光の正体は、「嗷訴」のために京都をめざす延暦寺の衆徒(寺僧)たちがかかげる松明の灯りであった。
嗷訴とは中世、寺社の僧侶や社司が仏力・神威をかざして集団で朝廷・幕府に押しかけ自らの要求をつきつけた行為をいう。そして、数ある寺社の嗷訴のなかでも、朝廷・幕府がもっとも恐れたのが、「南都北嶺」すなわち奈良の興福寺と近江の延暦寺の嗷訴であった。
無理を押し通すことを「山階道理」(『大鏡』五)といい(山階寺は興福寺の初名)、白河法皇(一〇五三―一一二九)が世の中で意のままにならない「天下三不如意」の一つに「山法師」をあげたという話し(『平家物語』)など、当時の人々が両寺の嗷訴にいだいていた畏怖の念を示す逸話には事欠かない。いうまでもなく「山法師」とは延暦寺の衆徒を指す。
本書はそのような嗷訴の実施主体であった中世の寺社がどのようなものであったかを探ろうとしたものである。具体的には比叡山延暦寺をとりあげ、そこでの「衆徒」と呼ばれた寺僧集団の活動を追うなかで同寺が果たした歴史的な役割について考えた。
延暦寺が中世を通じてわが国における最高の宗教的権威として存在したことはよく知られている。戦国時代にわが国を訪れたイエズス会の宣教師ルイス・フロイスは、同寺の絶大なる権威について次のように記している(フロイス『日本史』「五畿内篇」I)。
(延暦寺は)日本の最高の大学であったのみならず、都の政治に関して絶対的支配権を持っており、同所にはおびただしい寺院があり、非常に尊敬され、かつ学問と信心によって高名な仏僧たちも少なくなく、古来、つねに歴代の国王から深く敬われて来た。そして日本で流布している既存の宗教以外の教えを都の市街で弘めることは、比叡山の允許と承認なくしては絶対にできないことであった。
フロイスのいうところは、「都の政治に関して絶対的支配権」を持つという点を含めて、想像以上に正確である。
しかし、これまでの研究では、中世、延暦寺がどうしてそこまでの権威を保持しえたかについて十分にあきらかになっているとはいえない。その理由はただ一つ、中世における武家(武士)の力をあまりにも過大に評価し、それとは逆に寺社の力をあまりにも過小に評価してきたことにある。
中世、人々はこの世の安寧の源泉を「仏法(寺社)」と「王法(朝廷)」の支え合いにあると考えていた。仏教(寺院)の宗教的な威力と、王権(朝廷)の神聖性が互いに助け合うことで世の中の平和が保たれるという、この「仏法・王法相依」の考え方からすれば、寺社と朝廷こそが中世の世界の理念の主人公であり、武家は脇役にすぎなかった。武家の活躍にのみ目を奪われることなく、かの時代、寺社の果たした役割を正しく評価すれば、その頂点に君臨していた延暦寺がいかに大きな存在であったかは、自ずからあきらかになってくるはずである。
また、延暦寺の中世に限っていえば、同寺を現実に動かしていたのが衆徒と呼ばれた僧侶の集団であったことを明確に認識してこなかったことが大きい。延暦寺では最澄(七六六ー八二二、伝教大師)の弟子義真が初めてその地位を朝廷から認められた「(天台)座主」が同寺を統括する最高位の職であり、それは現代に至るまで変わらない。しかし、教学面の一部を除けば、中世、現実に寺を運営していたのは衆徒であり、この点をしっかりと押さえることなくして中世の延暦寺は語れないからである。
衆徒は比叡山上に三院(三塔)と呼ばれた東塔・西塔・横川の三つの地区に分かれて居住していた。三院はさらにそれぞれいくつかの「谷」に分かれ、延暦寺全域を表現するのにしばしば「院々谷々」という言葉が用いられるのはこのためである。
衆徒は「院々谷々」を日常的な生活・修学の場としていたわけであるが、彼らはその共同体を「衆議」と呼ばれる合議によって運営していた。その厳格さは「衆命」(『祇園執行日記』正平七年〈一三五二〉五月二十日条他)に背いたものに対しては、寺からの追放等の厳しい「衆勘」(『公衡公記』正和四年〈一三一五〉五月二十一日条)が加えられていることからもあきらかである。また、衆徒の結束力の強固さは、彼らが集団の喜悦・鬱情を表現して、「衆悦」(『建内記』文安元年〈一四四四〉四月十七日条)、「衆鬱」(『山門事書』)等といった言葉を保持していたことからも十分うかがい知ることができる。
本書では、天仁元年(一一〇八)三月に比叡山の夜空を焦がした嗷訴の火が、どのようにしてフロイスのいう「都の政治に関して絶対的支配権」にまでたどり着くに至ったのかを、衆徒の活動をさまざまな観点からみていくなかで考えていきたい。
吉川弘文館、下坂守『京を支配する山法師たち 中世延暦寺の富と力』Pⅲーⅵ
いかがでしょうか。この箇所を読むだけで驚かれた方も多いのではないでしょうか。
まず「これまでの研究では、中世、延暦寺がどうしてそこまでの権威を保持しえたかについて十分にあきらかになっているとはいえない。その理由はただ一つ、中世における武家(武士)の力をあまりにも過大に評価し、それとは逆に寺社の力をあまりにも過小に評価してきたことにある」という点は見逃せません。
本書では比叡山延暦寺の権力基盤、経済基盤がどこにあったのかを詳しく見ていきます。特に上でも強調されていた嗷訴とはいかなるものだったのかという解説は非常に興味深いです。なぜ朝廷や幕府は嗷訴をここまで恐れなければならなかったのかというのは非常に重要な問題です。実は単に神罰が恐ろしいからという迷信的な理由だけではなかったのです。
また、「延暦寺では最澄(七六六ー八二二、伝教大師)の弟子義真が初めてその地位を朝廷から認められた「(天台)座主」が同寺を統括する最高位の職であり、それは現代に至るまで変わらない。しかし、教学面の一部を除けば、中世、現実に寺を運営していたのは衆徒であり、この点をしっかりと押さえることなくして中世の延暦寺は語れないからである」という点も重要です。
私達は天台座主というと比叡山全体を統括するボスのようなイメージを持ってしまいがちですが実は事はそう単純ではありません。実際に比叡山を動かしていたのは衆徒であり、天台座主も彼らのコントロールに苦慮していたという事実があります。つまり、天台座主の指示で嗷訴が起きたり、山内の騒乱が起きていたわけではないということです。ここを見誤ると比叡山を含めた日本仏教史の見え方ががらっと変わってしまうことになります。本書ではこの件に関しても詳しく解説がなされます。
本書は私達の常識やイメージをことごとく覆すとてつもない名著です。私も度肝を抜かれっぱなしでした。そのひとつひとつを紹介するととてつもない分量になってしまうのでそれもできません。
そして本書の中心主題のひとつである嗷訴ですが、これは比叡山麓の坂本日吉大社の神輿を延暦寺根本中堂に担ぎ上げ、そこから雲母坂を下って京都の朝廷に行進していくものでありますが、私もこの雲母坂を歩いてきました。


写真のように狭くて険しい山道でありますが、ここが比叡山から京都への最短ルートです。回峰行者や親鸞聖人もこの山道を通って京都へ下っていきます。この登山道については「比叡山登山記(京都修学院~延暦寺)~親鸞聖人も歩いた雲母坂ルートを追体験!」の記事で詳しくお話ししていますのでぜひこちらもご参照頂けましたら幸いです。
本書は比叡山と政治経済の問題について衝撃の事実を知れるおすすめ参考書です。ぜひぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。
以上、「下坂守『京を支配する山法師たち』概要と感想~比叡山と経済界の繋がりを知れる刺激的な一冊!」でした。
Amazon商品紹介ページはこちら
次の記事はこちら
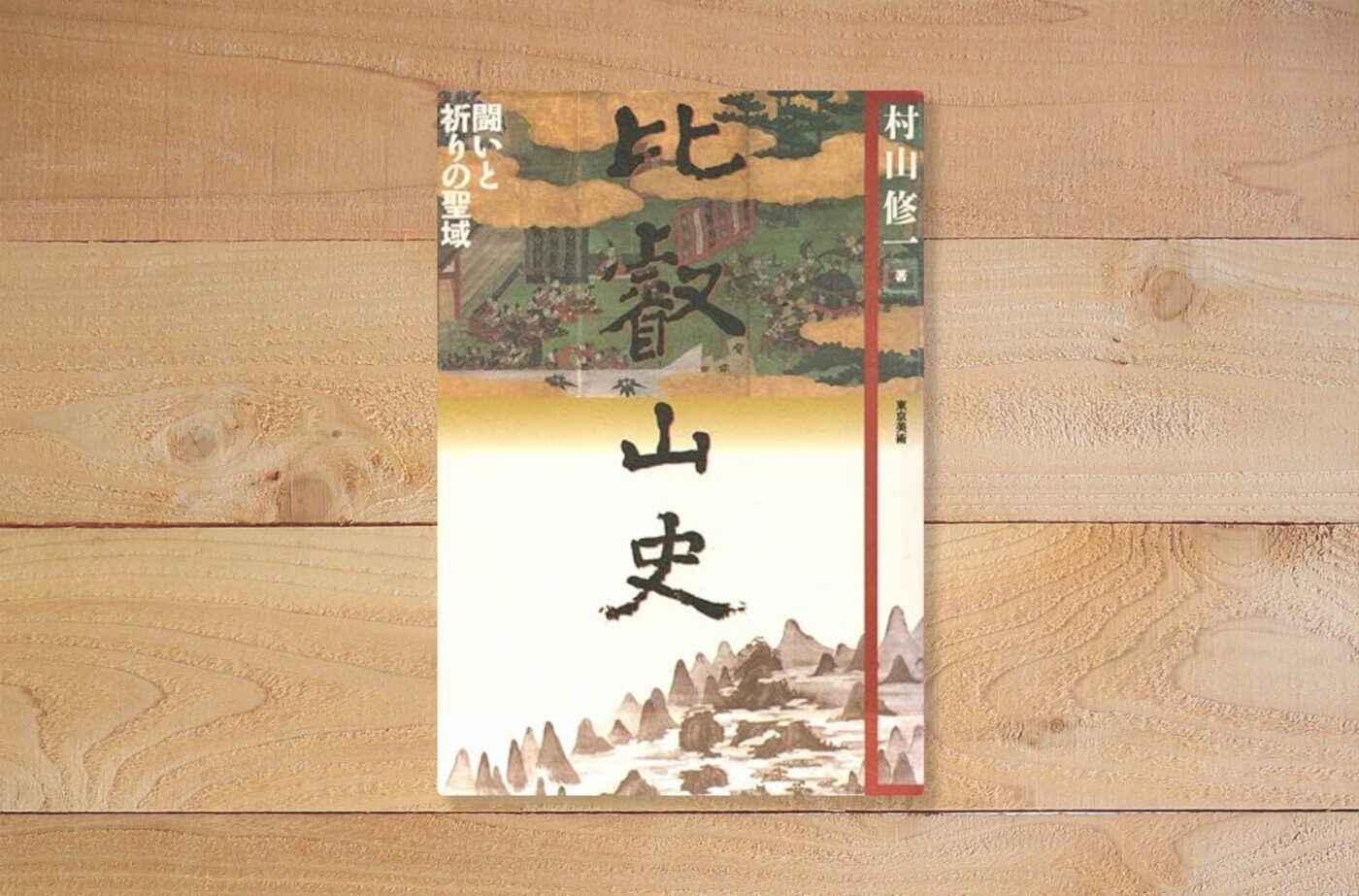
前の記事はこちら
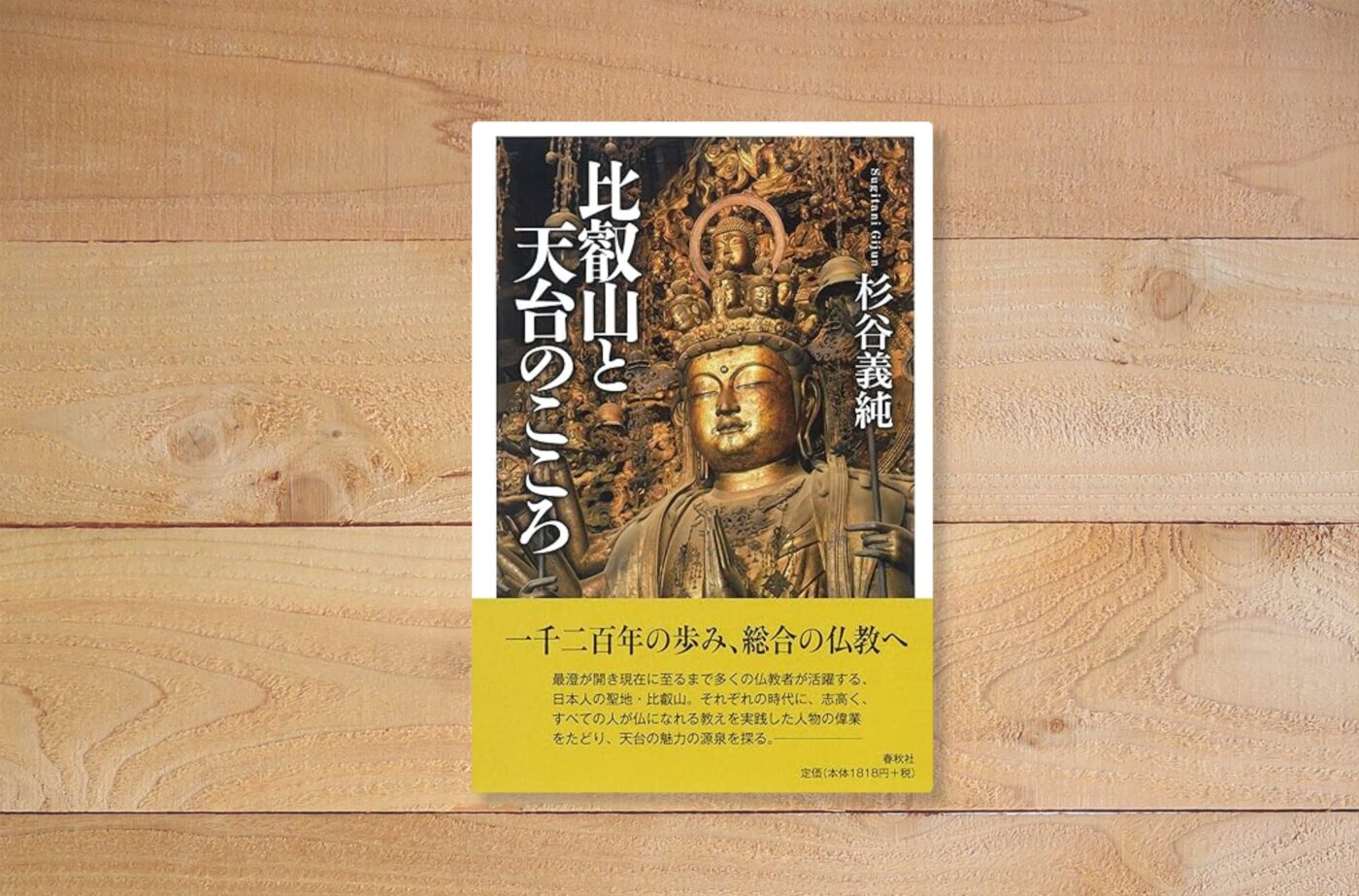
関連記事