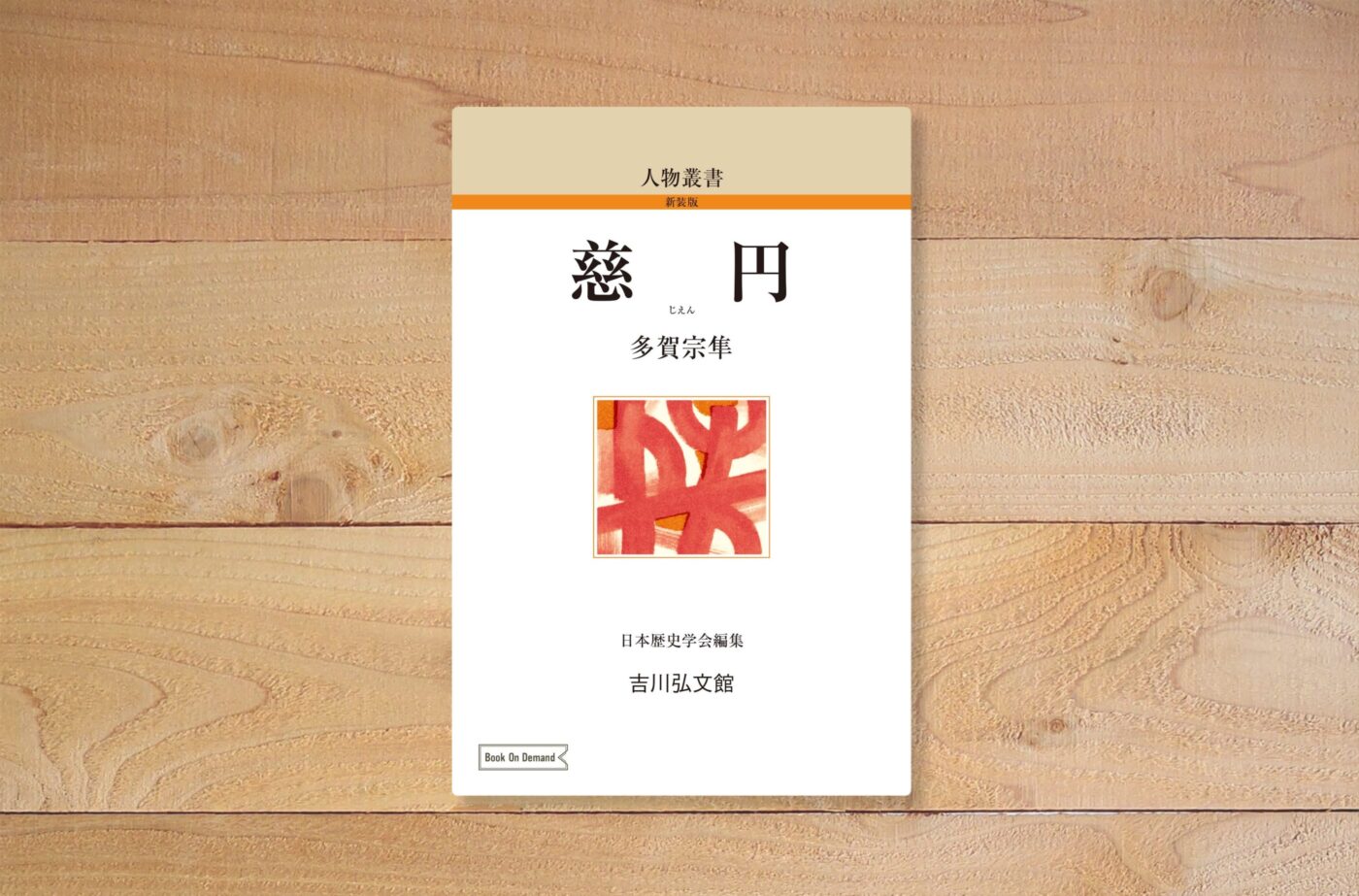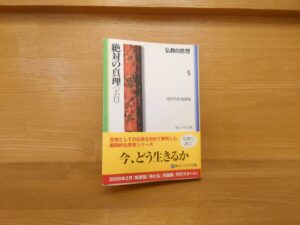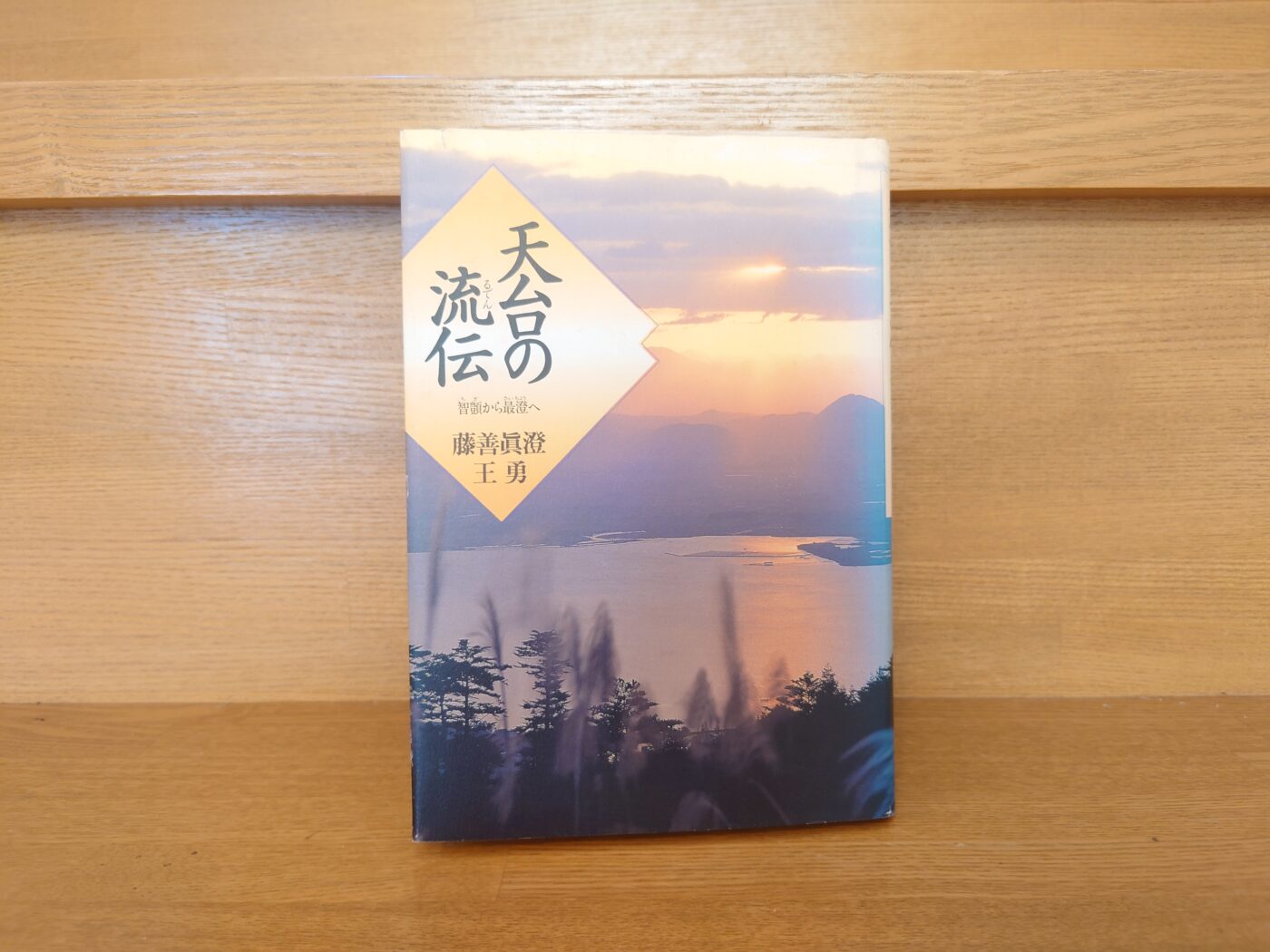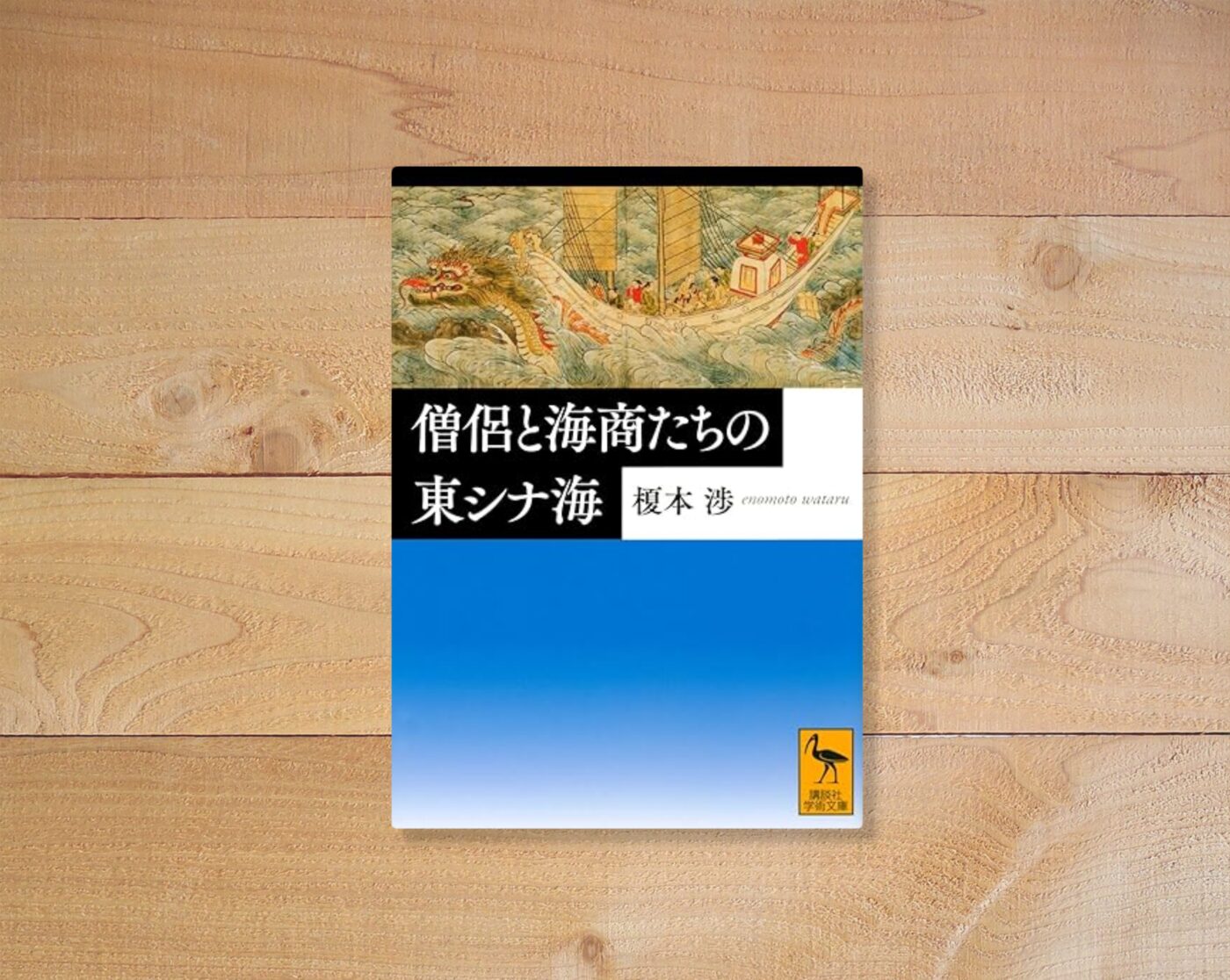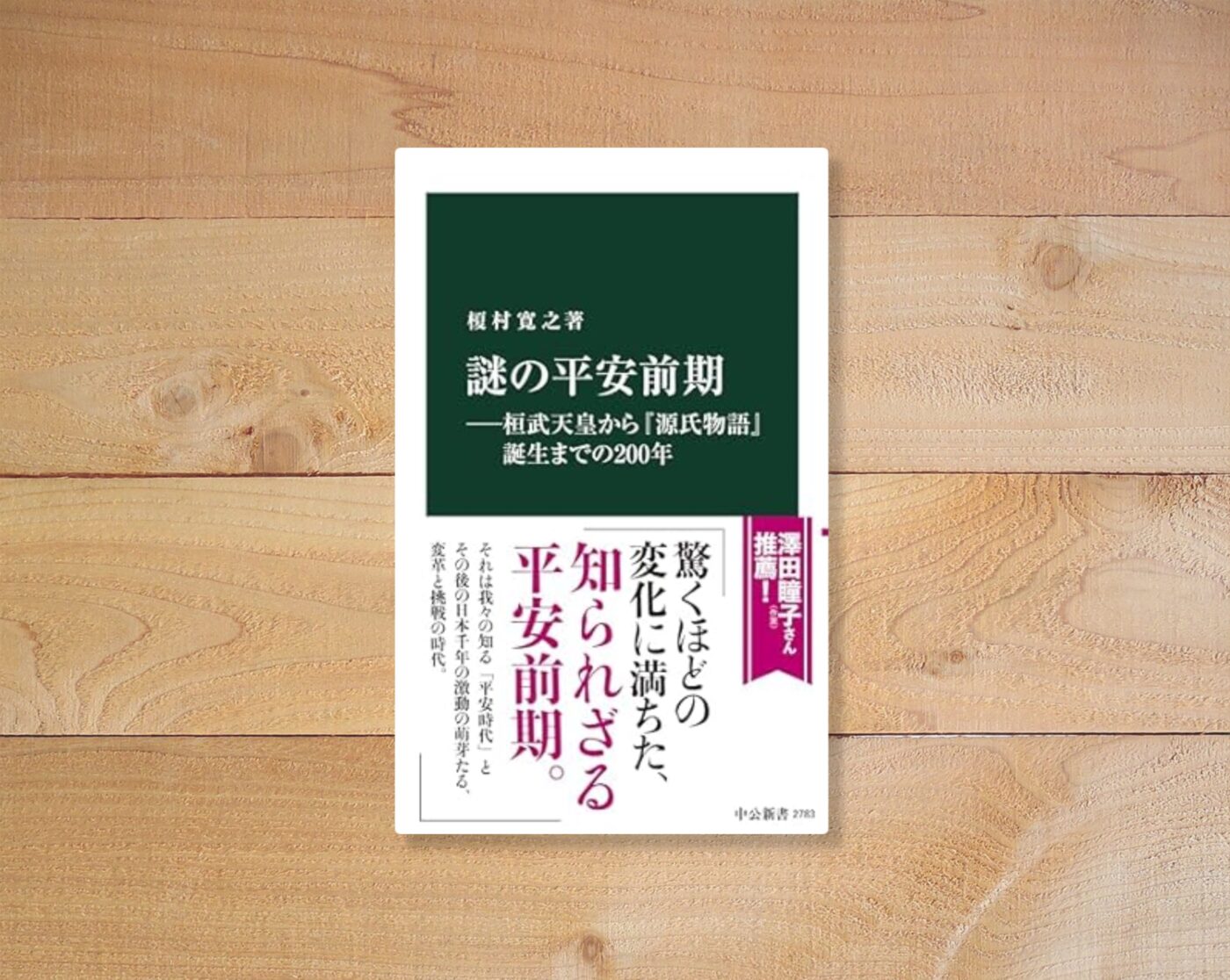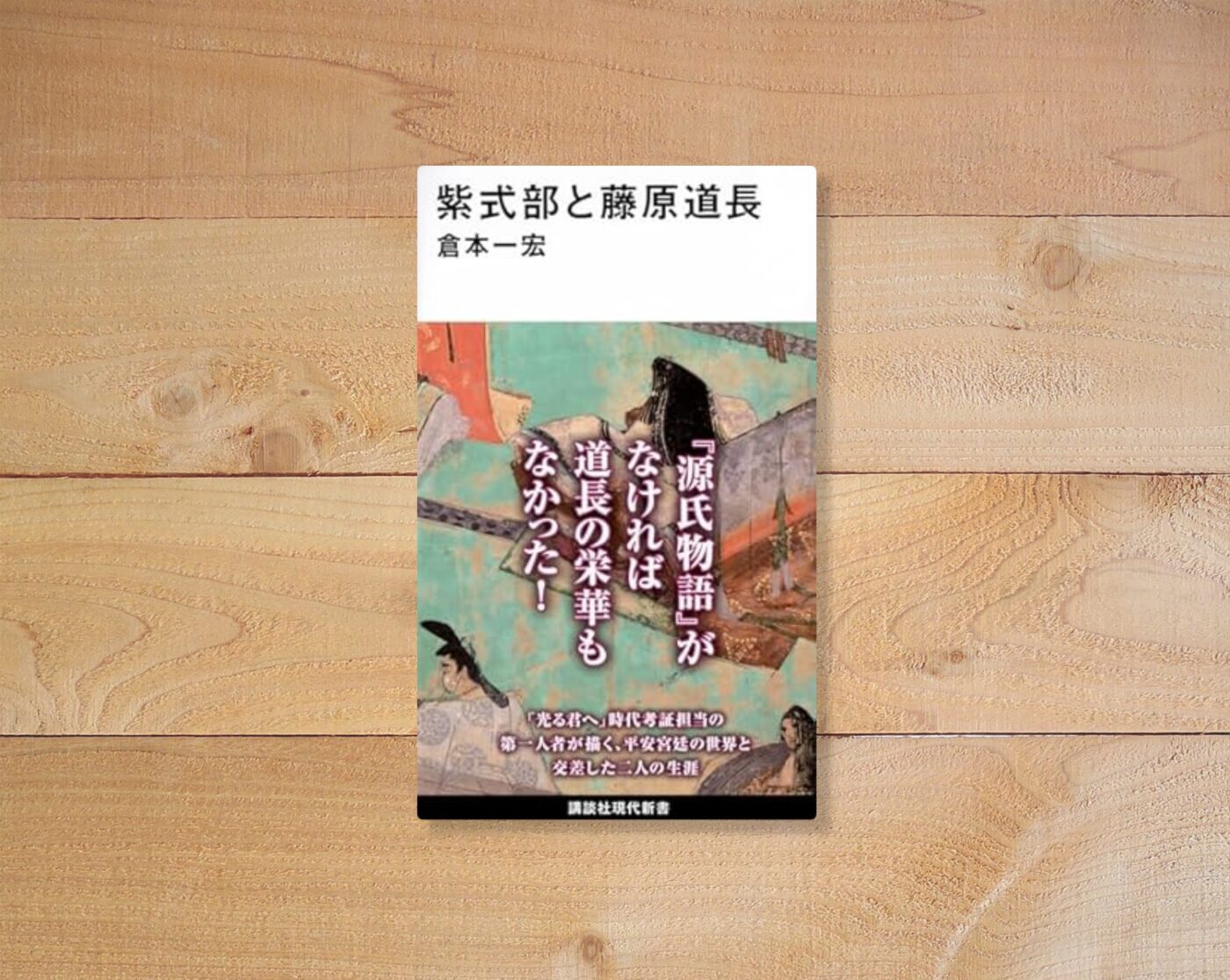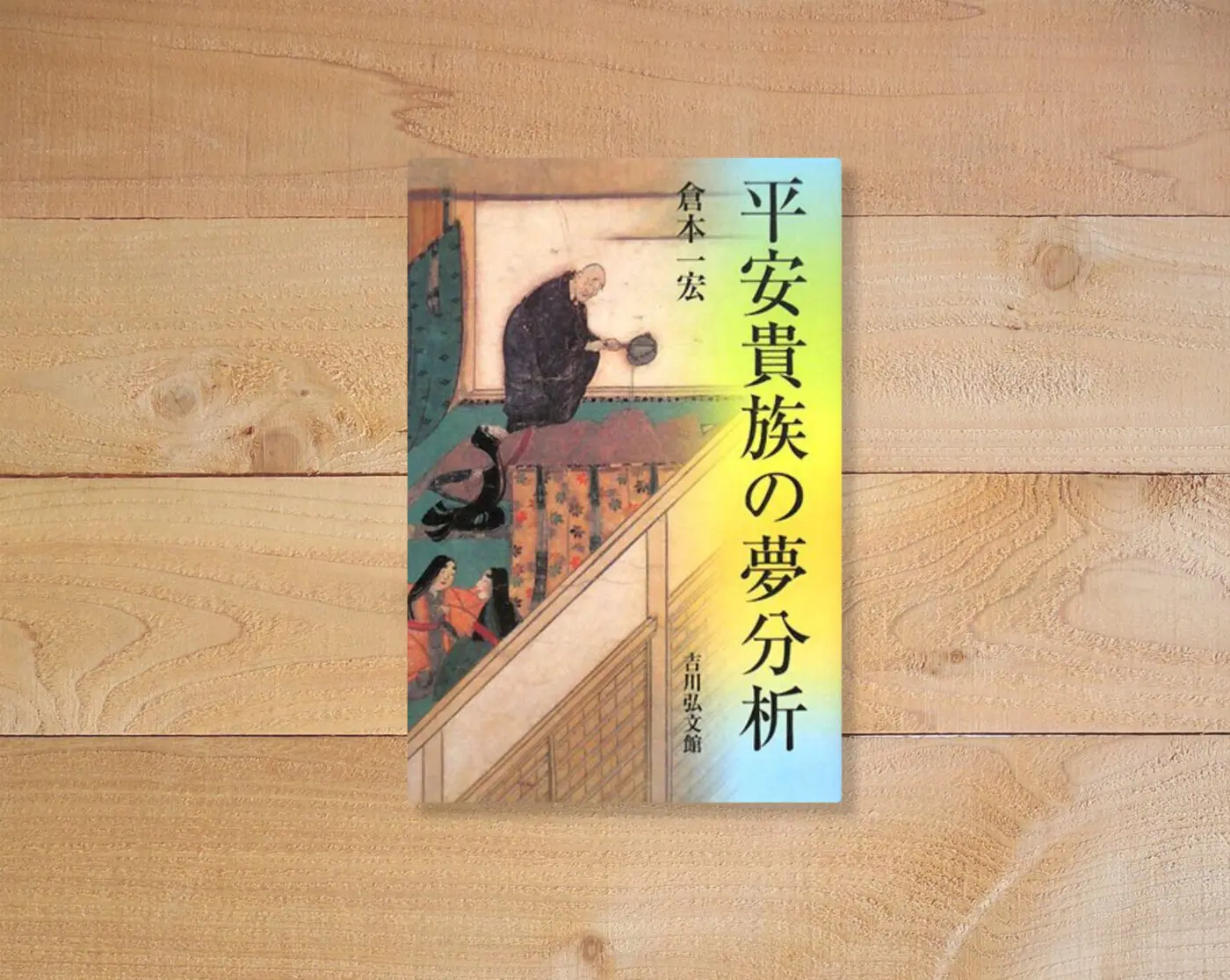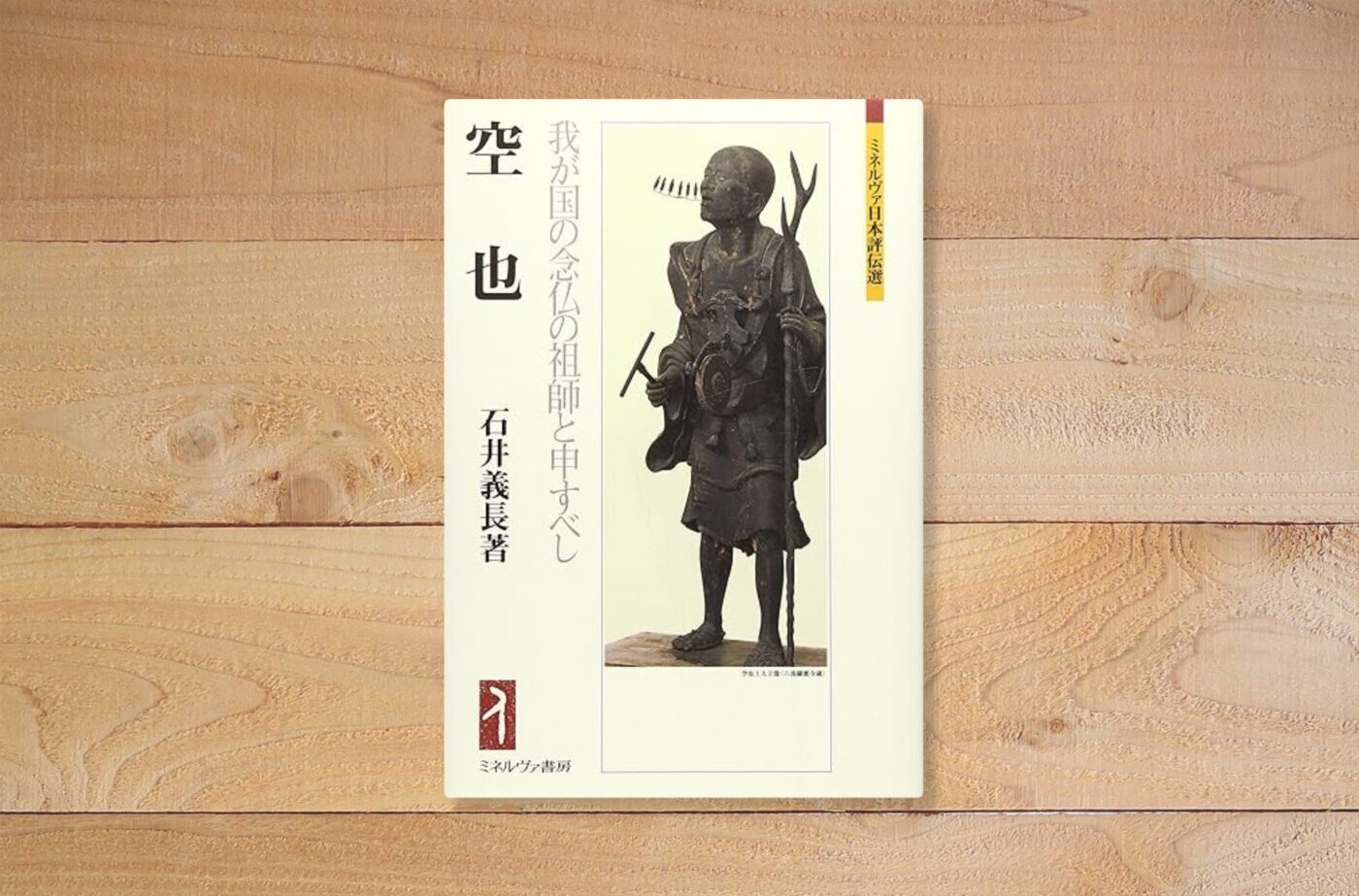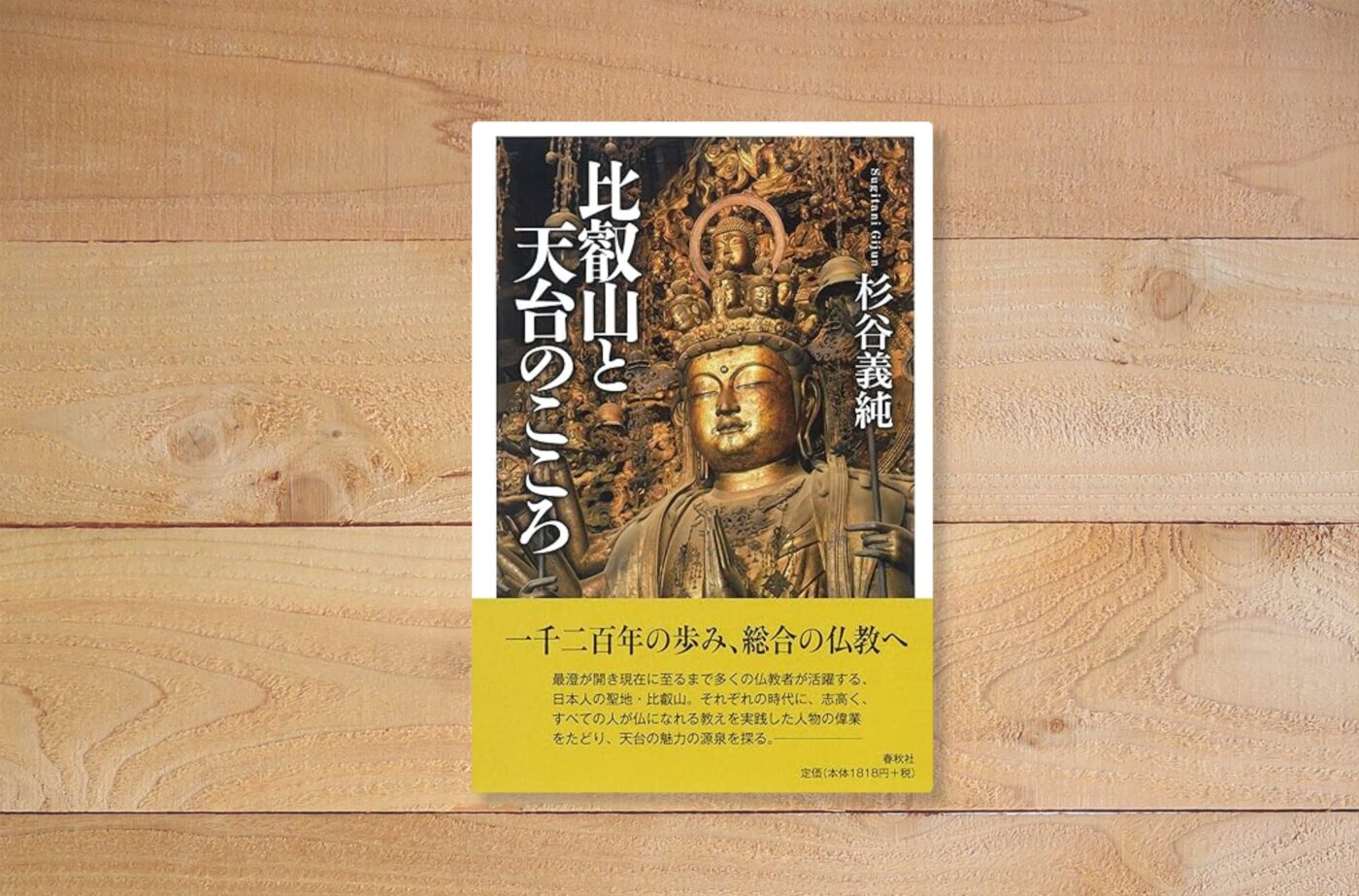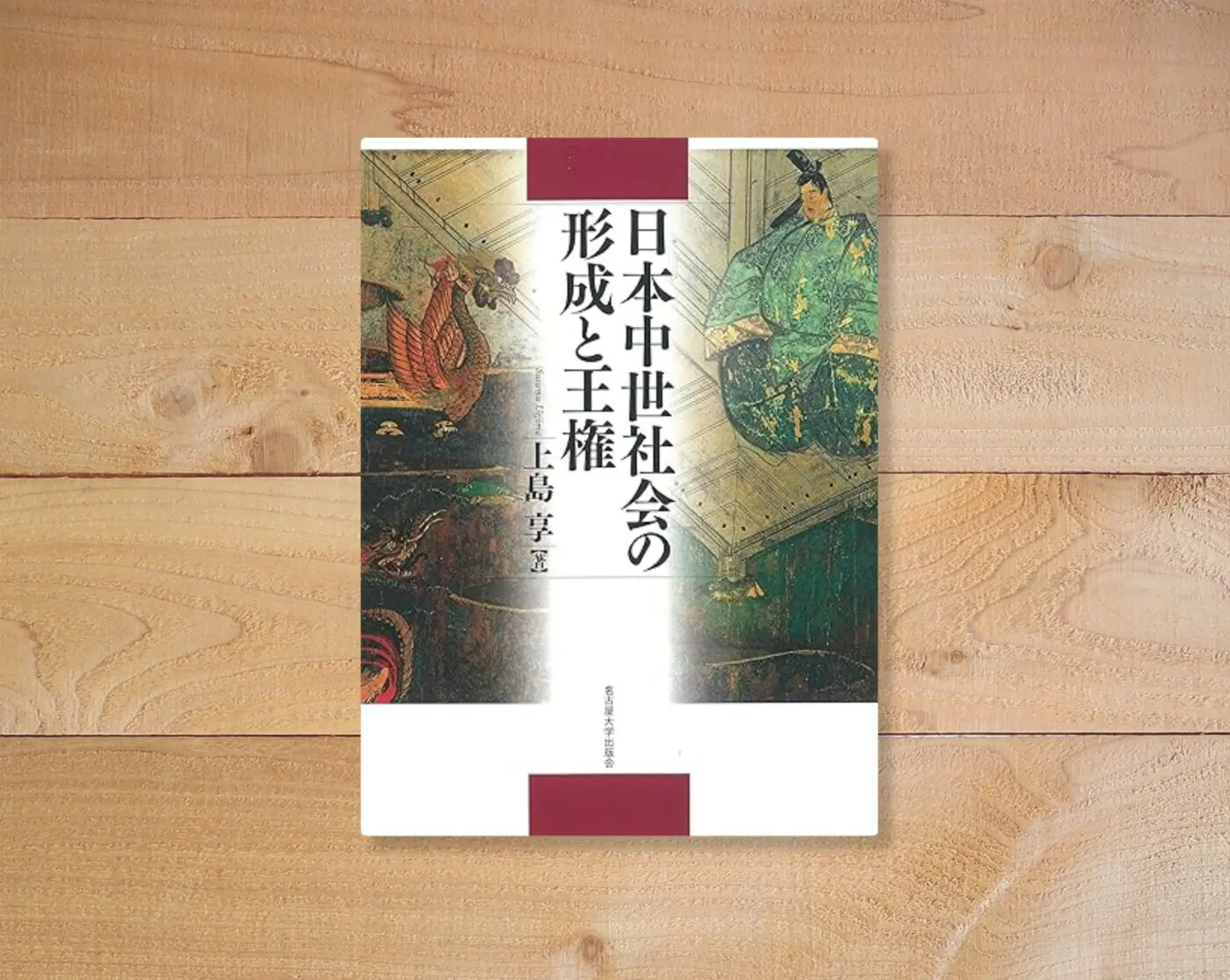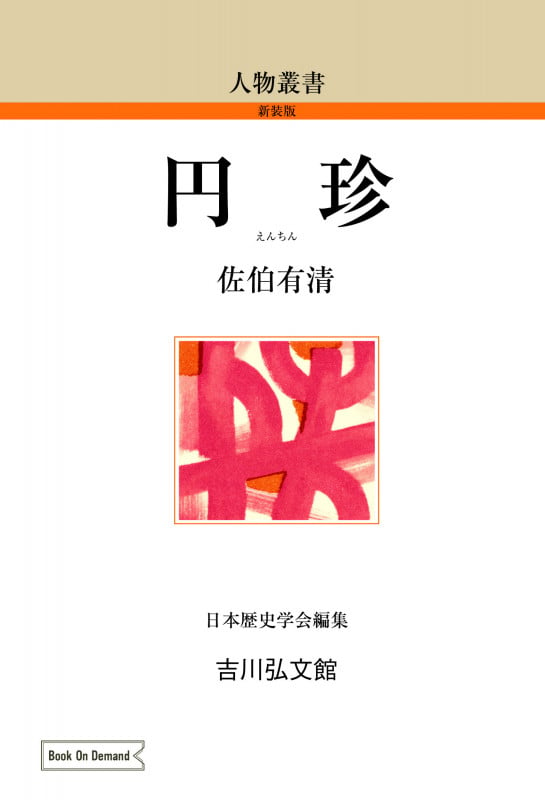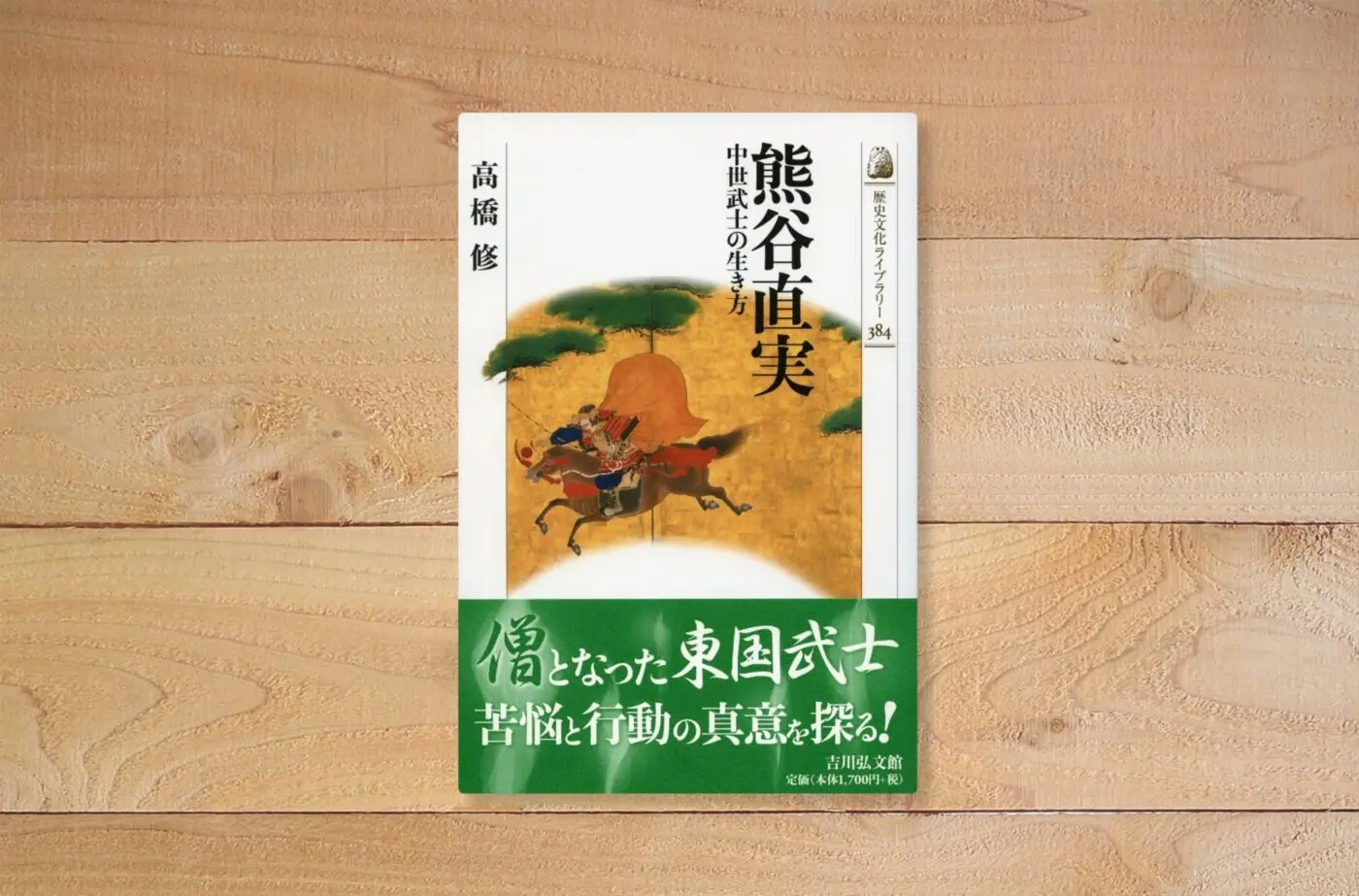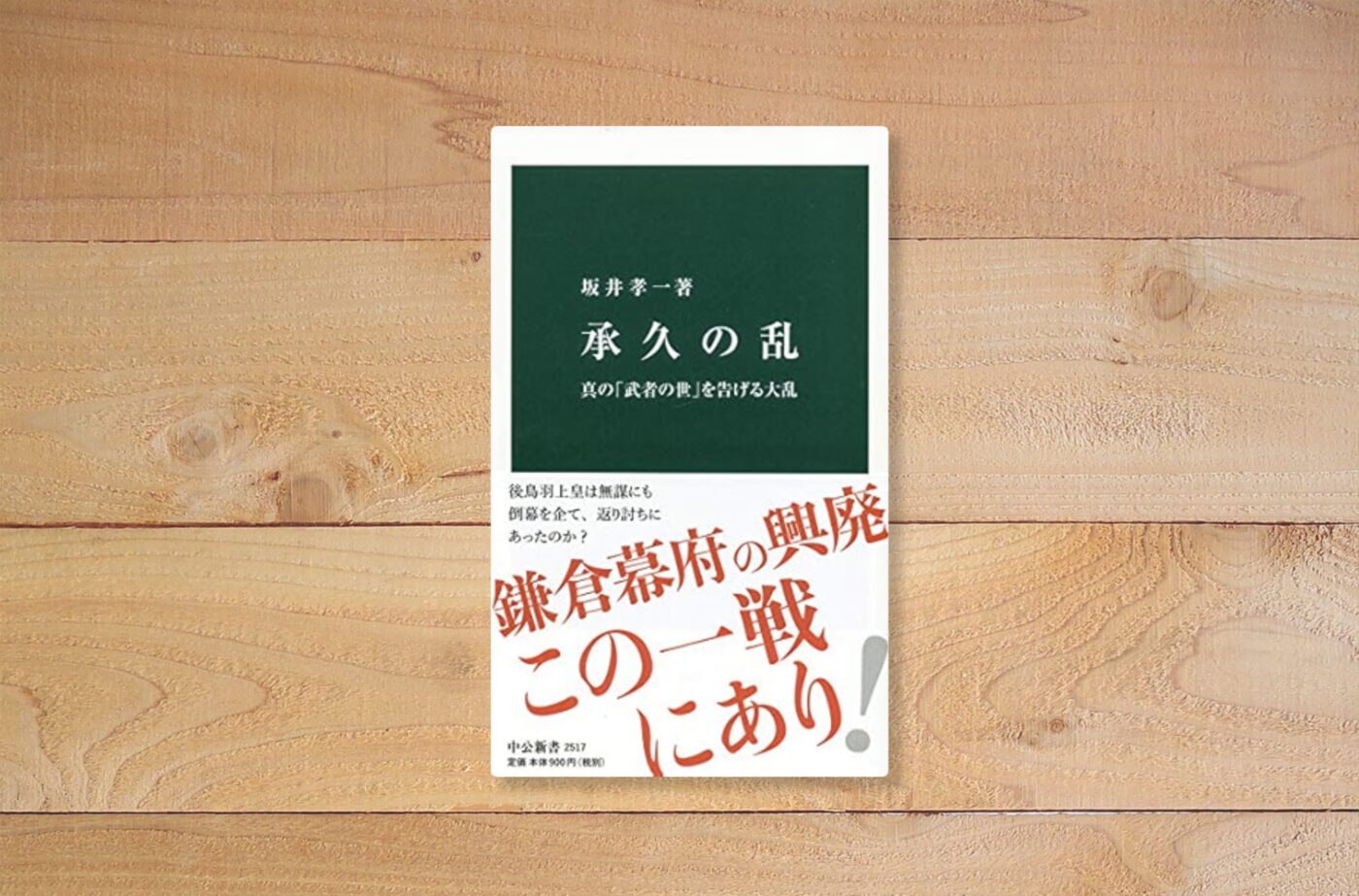佐伯有清『円珍』概要と感想~比叡山寺門派の祖となった傑僧のおすすめ伝記

佐伯有清『円珍』概要と感想~比叡山寺門派の祖となった傑僧のおすすめ伝記
今回ご紹介するのは1990年に吉川弘文館より発行された佐伯有清著『円珍』です。
早速この本について見ていきましょう。
諸宗や僧侶を批判し経典の蒐集校勘と園城寺復興に努めた、5世天台座主寺門派の祖、智証大師伝
吉川弘文館商品紹介ページより

本伝記の主人公智証大師円珍は天台宗の寺門派の祖であり、比叡山麓の三井寺(園城寺)とも深い繋がりがある天台僧です。

円珍といえば円仁・円珍と言われるように、円仁と対で語られることの多い僧侶です。
円仁については以前当ブログでも紹介したライシャワー著『円仁 唐代中国への旅』という本がおすすめなのですが、この円仁、円珍に共通するのは二人とも仏法の奥義を極めるために唐に渡ったという点にあります。
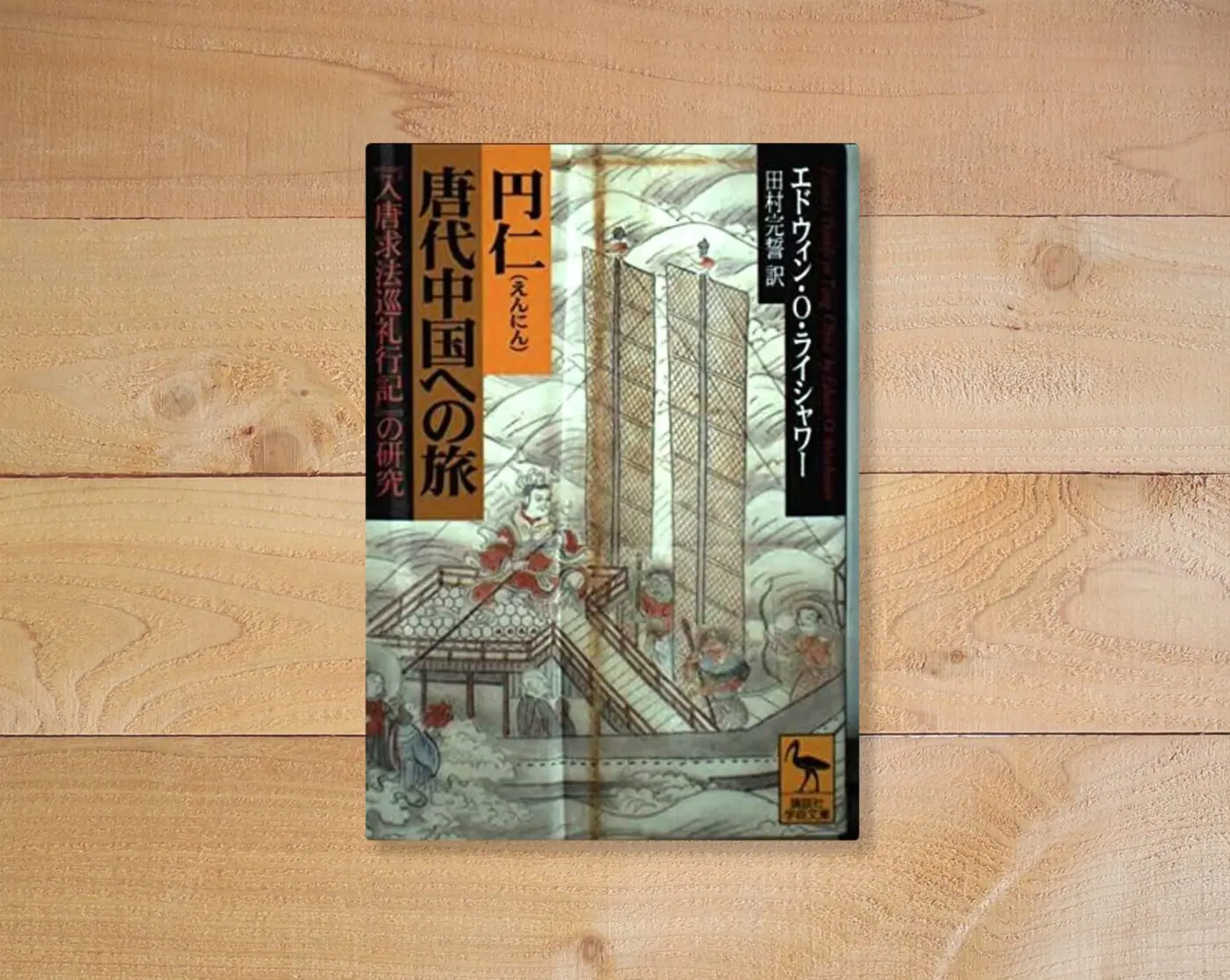
ただ、唐に渡ると一言で言っても、実はその渡航方法や現地での生活にはかなり違いがあります。本書『円珍』でもそのことはかなり詳しく解説されるのですが、唐に渡って仏法を学ぶというのはどういうことなのかということを本書でも詳しく学ぶことができます。
さて、本書について著者ははしがきで次のように述べています。
智証大師円珍(八一四ー八九一)は、宗祖の伝教大師最澄(七七六ー八二二)と師兄の慈覚大師円仁(七九四ー八六四)のあとを受け継いで、天台宗の発展に力を尽した高僧として、ひろく世に知られている。
円珍の生涯を顧みて、人びとの心を強く打つのは、円珍が比叡山に登ってから終始、情熱をもって求法につとめ、たゆまぬ修学に明け暮れ、また熱心に経典・経疏の蒐集にはげみ、あわせて諸書の比較研究に精を出したことであろう。このような円珍の非凡な特質には、仏教教義の論弁において、いずれの論者をも容赦しない弁舌をふるい、また論著において、同宗の者といえども激しい口調でもって論難することがともなっていた。その舌鋒は鋭く、またその筆鋒は他者を圧倒する勢いを持っていた。円珍みずからも晩年になって、論弁の激しさを「抜舌大獄の因」をなしたと語り、激越な文章を指して「鬼語を吐く」と書いた。したがって円珍は、こうした性格から、性に合わない円載のような人物を終生憎悪し、名声を求めて入唐しようとした済詮に対して、口を喋んでしまうのであった。その生きざまは、潔癖の一語に尽きる。良し悪しは別として、円珍は、人間味の豊かな学僧として、大きな魅力をもってわれわれの前に蘇ってくる。
極論すれば円珍の宗教活動は、時の権勢者藤原良房とともに始まり、良房とともに終ったといえる。良房なくしては、円珍の六年にわたる入唐求法の旅は実現しなかったし、その求法の成果である真言・止観両宗の弘伝の公認もありえなかった。そのいずれもが、良房の政権下で展開されたきびしい政治の動向と深くかかわっていた。こうした観点からの叙述とあわせて、本書では円珍の入唐求法のなかで生じた留学僧円載との確執と、従僧豊智(智聡)の離反などの問題を新しい視点から記述してみた。円珍の「入唐行歴」が、三章にわたっているのは、そのためである。
後世のわれわれにとって、まことに有難いことは、円珍と縁の深い園城寺に、円珍関係の生の文書類が多く残っていることである。貴重な文化財が園城寺に豊富に伝えられたのは、非常事態の時にただちに持ち出せるように万全の備えが整っていたためである(小山田和夫「智証大師円珍関係文書の話」『園城寺』第四九号)。園城寺は、いく度となく無残な焼き打ちにあった。その炎をかいくぐって、貴重な文化財が今日に伝えられたのは、園城寺を守る人びとのなかに、円珍に対する崇敬の念が格別に厚かったからである。それと同時に、古くは園城寺が危機に直面するたびに、天台密教の修験者たちが異常な力を発揮して、貴重な物品の安全を図ったらしいことが指摘されている。さらにまた火災のさいに実際に文化財を運びだす「馬借集団」が園城寺と特別な関係のもとにあったからではないかという興味深い推論もある(田中日佐夫「園城寺の不可思議さ」『園城寺』第四五号)。
いずれにしても、園城寺を中心に多くの円珍に関係する第一級の史料が伝世されたことによって、円珍の行実を、われわれはかなり詳細にたどることができる。かぎりのある紙数では、そのすべてを円珍の伝記に書き込むことは不可能である。本書に盛り込むことができなかった二、三の問題は、「円珍と上毛野滋子」(『日本歴史』第五一〇号)や「円珍と山王院蔵書目録」(『成城文芸』第一三二号)と題する論文として発表されることになる。さきに公刊した基礎研究『智証大師伝の研究』とともに、それらの小論をあわせ参照していただれば幸いである。
吉川弘文館、佐伯有清『円珍』P5ー7
ここで語られるように、本書を読んでいくと驚くほど「激しい」円珍の姿を知ることになります。やはり歴史に名を遺す偉人は違います。まさにカリスマ。こうした規格外の人間だったからこそ歴史を変えてしまうほどのインパクトを残すことになったのでしょう。
そして私が本書を読もうと思ったのが、実は比叡山内部における壮絶な争いの歴史に興味があったからなのです。
後に当ブログでも紹介していきますが親鸞聖人が比叡山に居られた頃、つまり平安末期の比叡山は円仁派(山門派)と円珍派(寺門派)の対立が極めて危険な水域となっており、実際に武器を交えた戦争に発展しています。しかもそれが何度もです。上の引用にもありましたように互いの寺を焼き討ちするほどの徹底した戦いでした。
こうした比叡山上での抗争は当時の仏教界の堕落として語られがちでありますが、事はそう単純ではありません。その抗争の火種はすでに円仁、円珍在世時から存在していたのです。それにそもそもそうした状況を堕落と呼ぶのは適切ではないのではないかとすら私は様々な歴史書を読みながら感じました。いずれこのことについては他の本紹介を通してお話ししたいと思います。
さて何はともあれ、私はこうした背景を知るために本書を手に取ったのでありました。
もちろん、円珍から平安末期までは200年近くありますので直接的にはこの本ではそのことについては解説されません。あくまで円珍の生涯が本書のメインテーマです。ですが親鸞聖人がおられた頃の比叡山を知る上でもその背景を知ることができる本書は非常に貴重です。
円珍というカリスマの巨大な人生を知るのに本書はとてもおすすめです。ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。
以上、「佐伯有清『円珍』概要と感想~比叡山寺門派の祖となった傑僧のおすすめ伝記」でした。
Amazon商品紹介ページはこちら
次の記事はこちら

前の記事はこちら
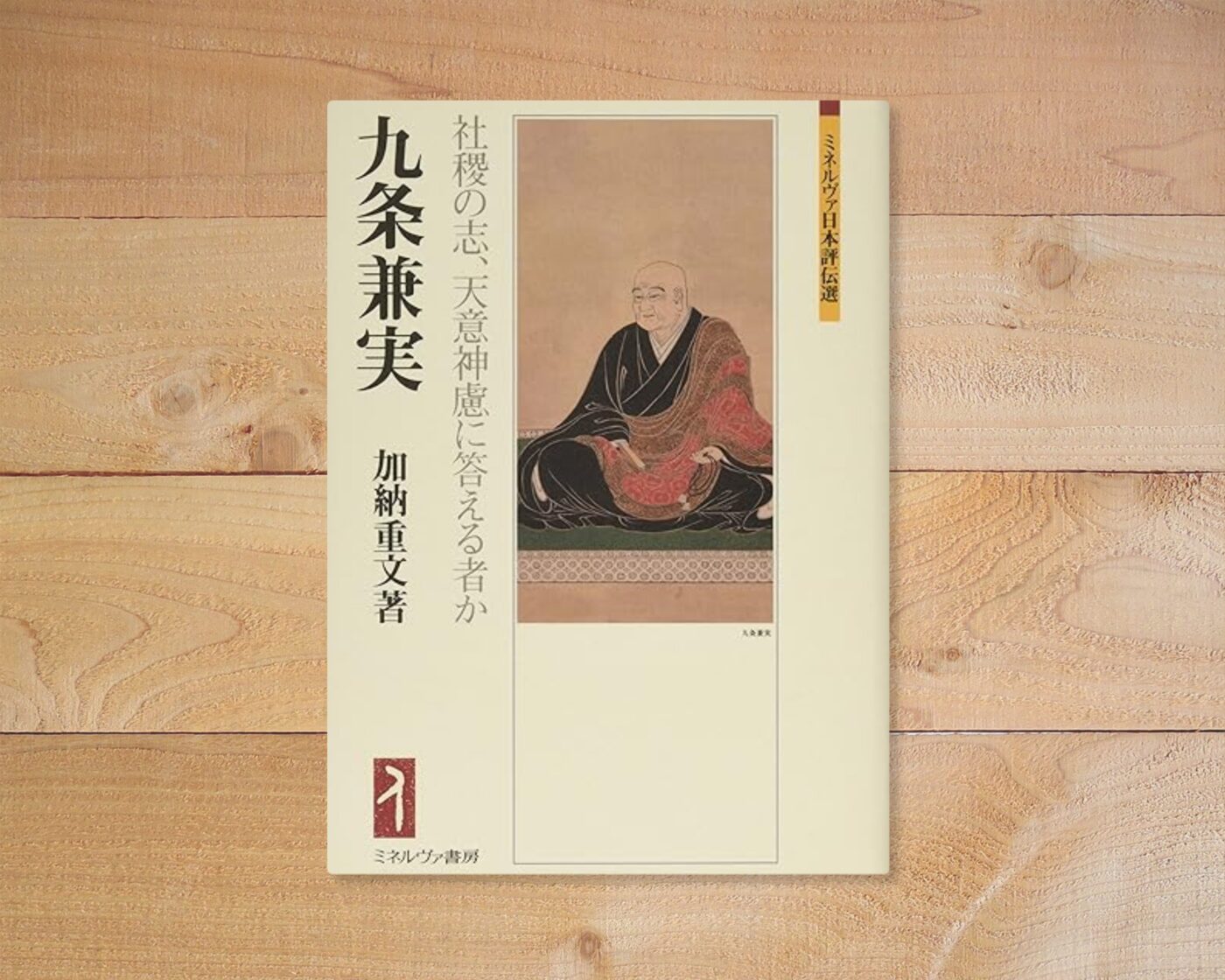
関連記事