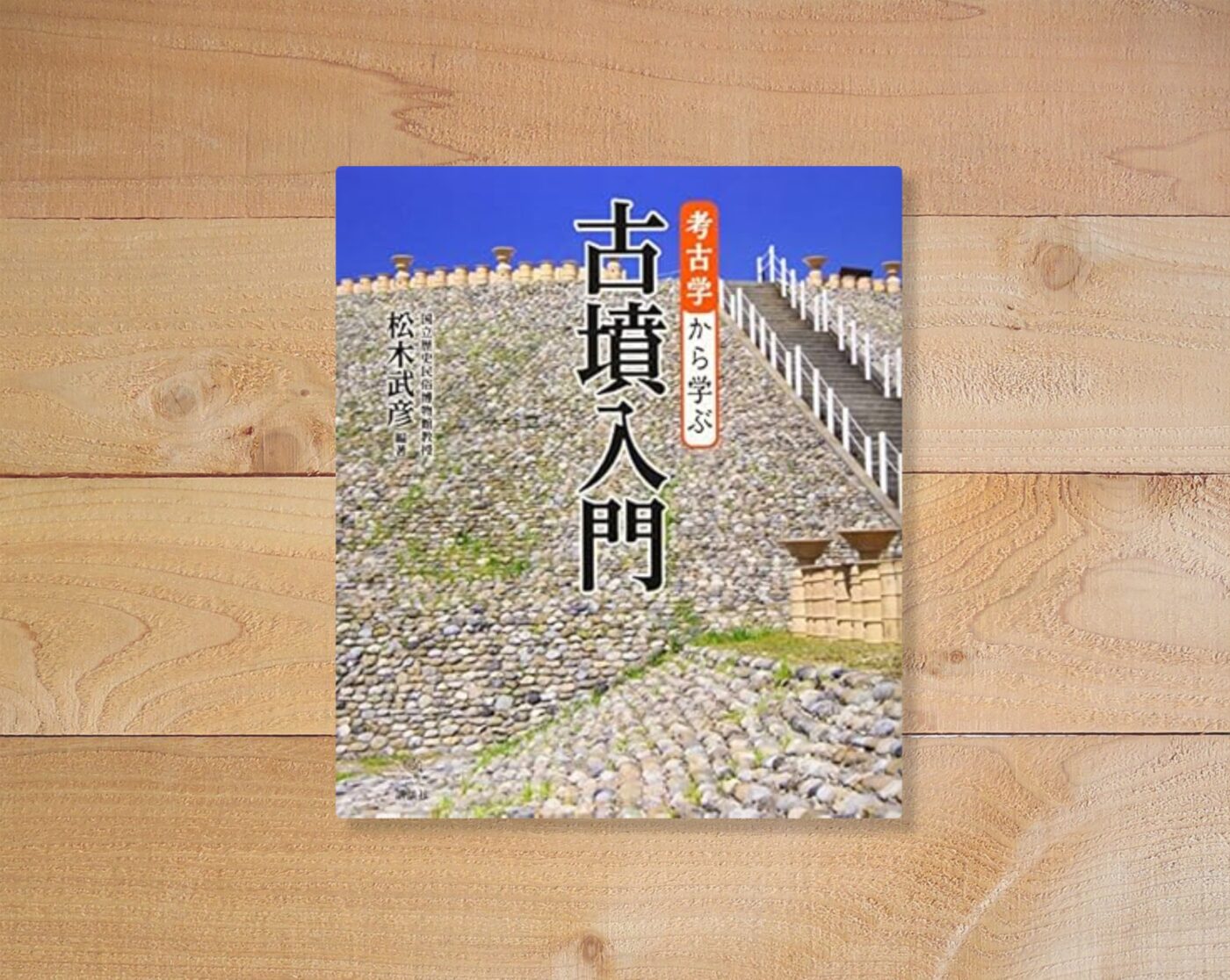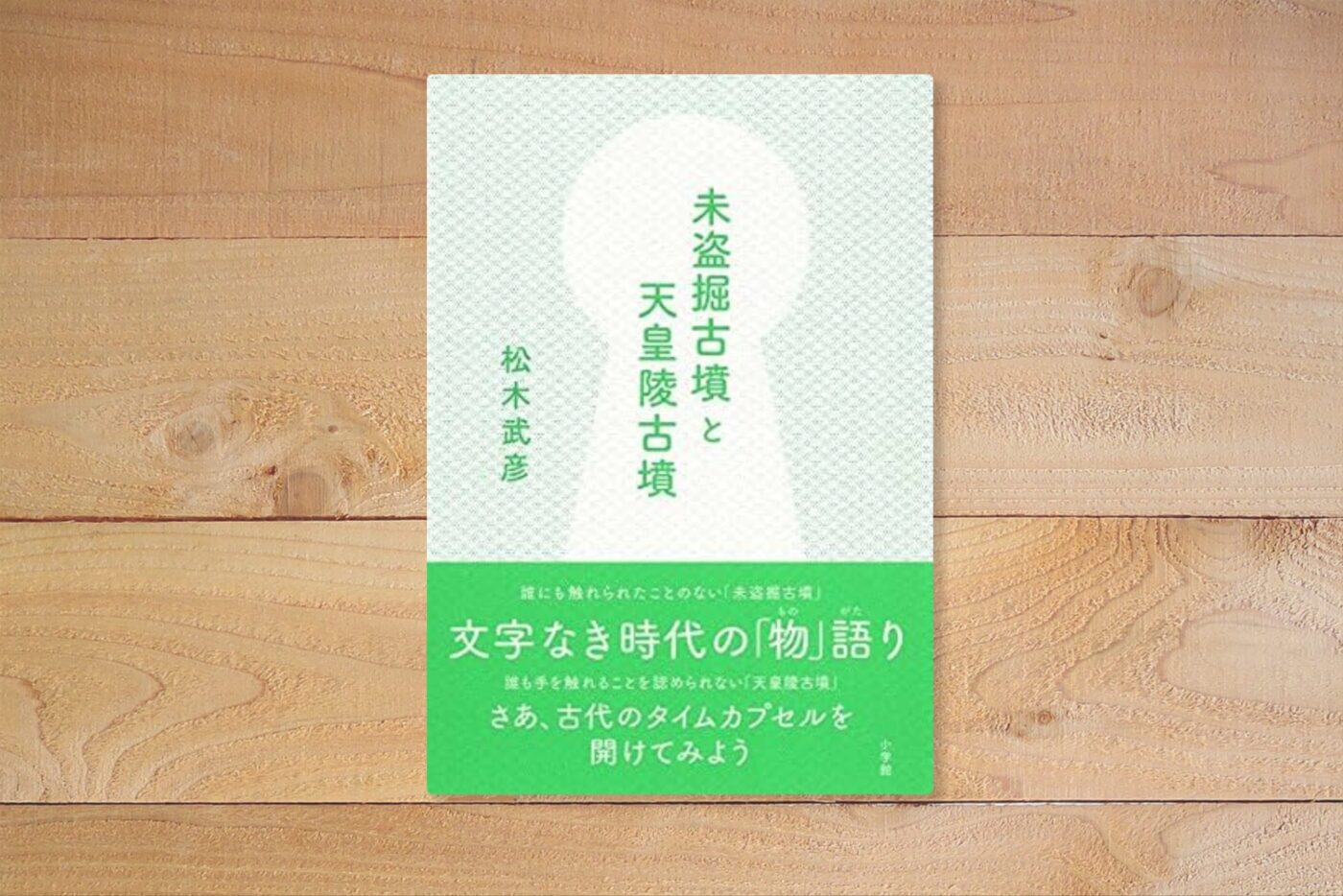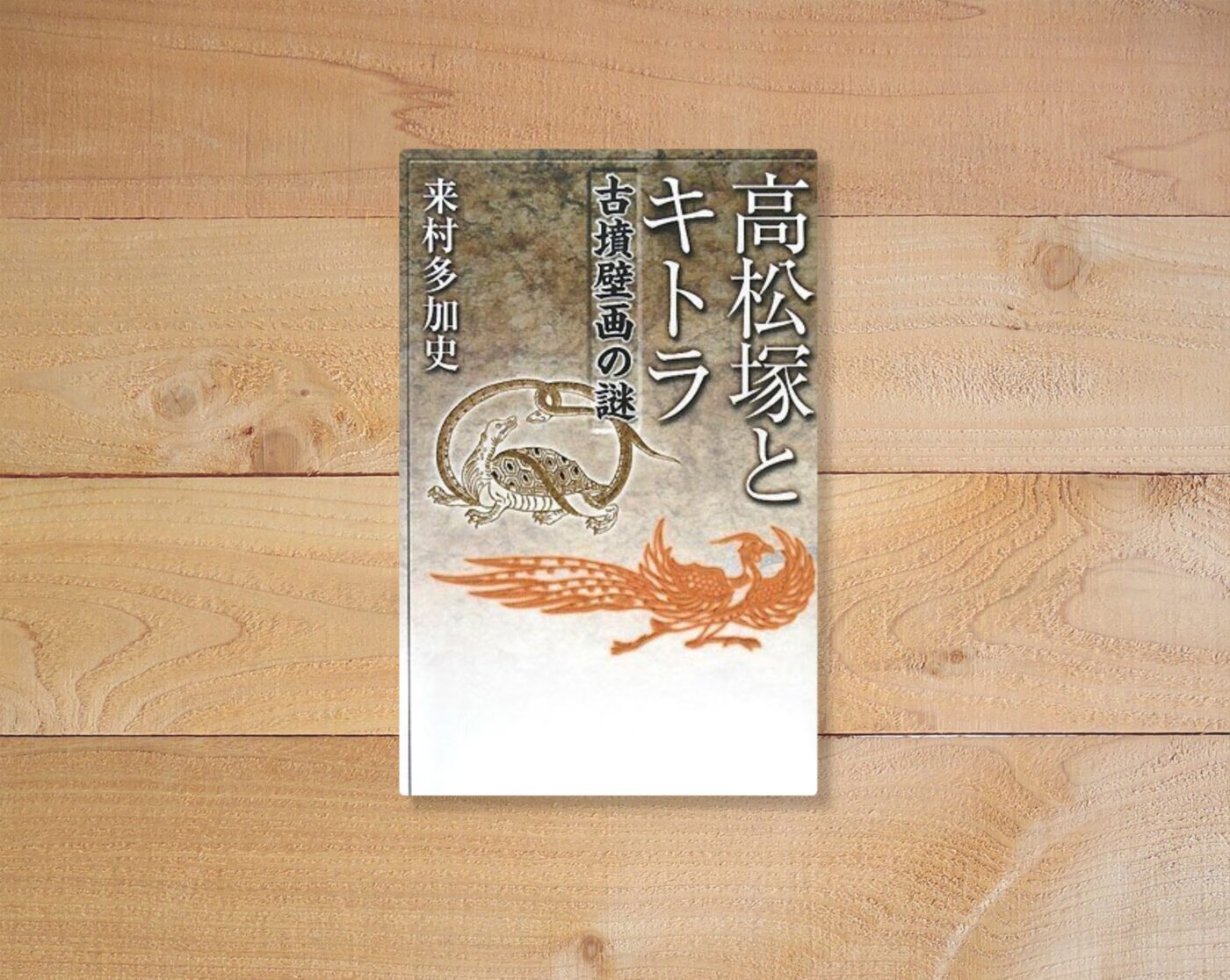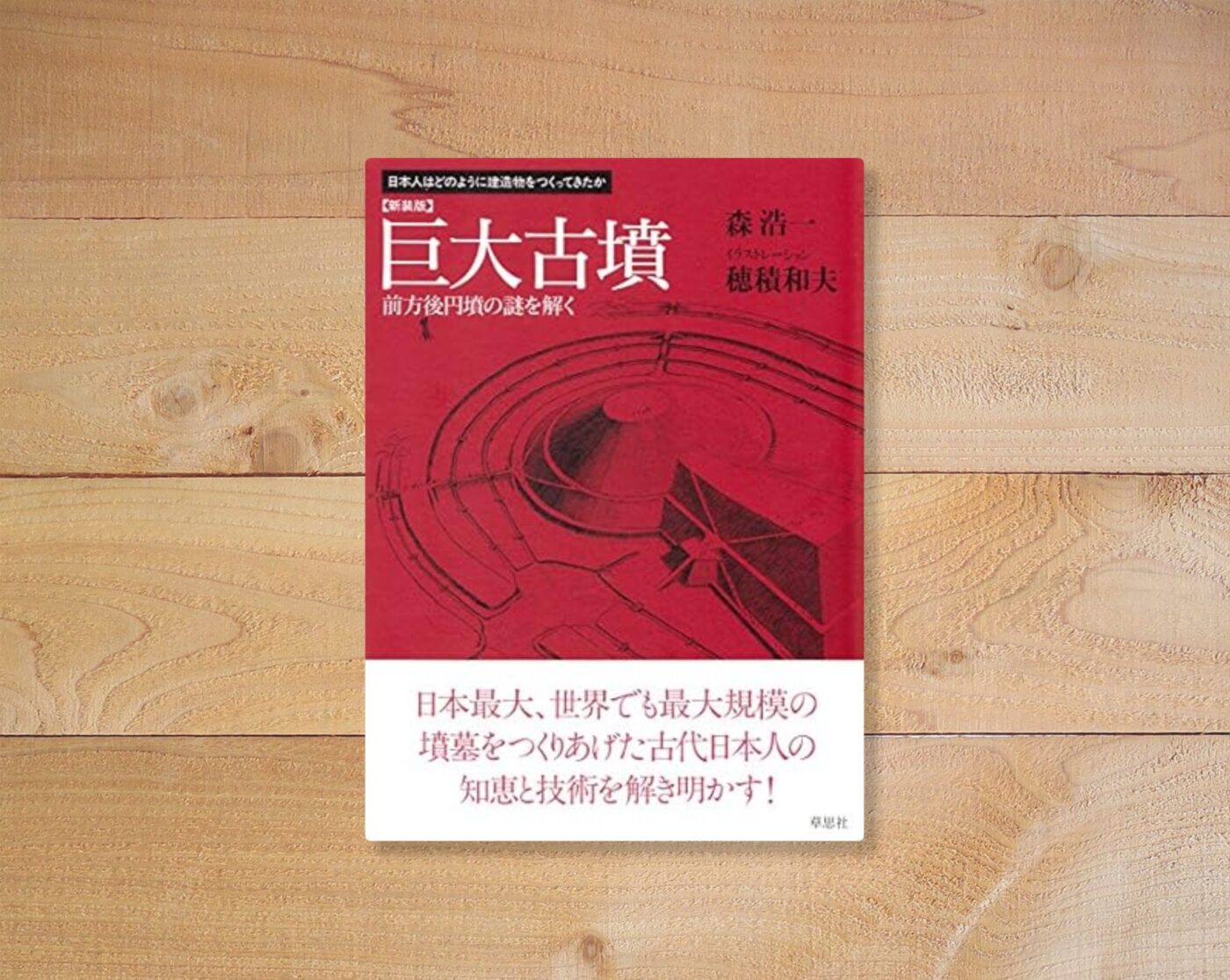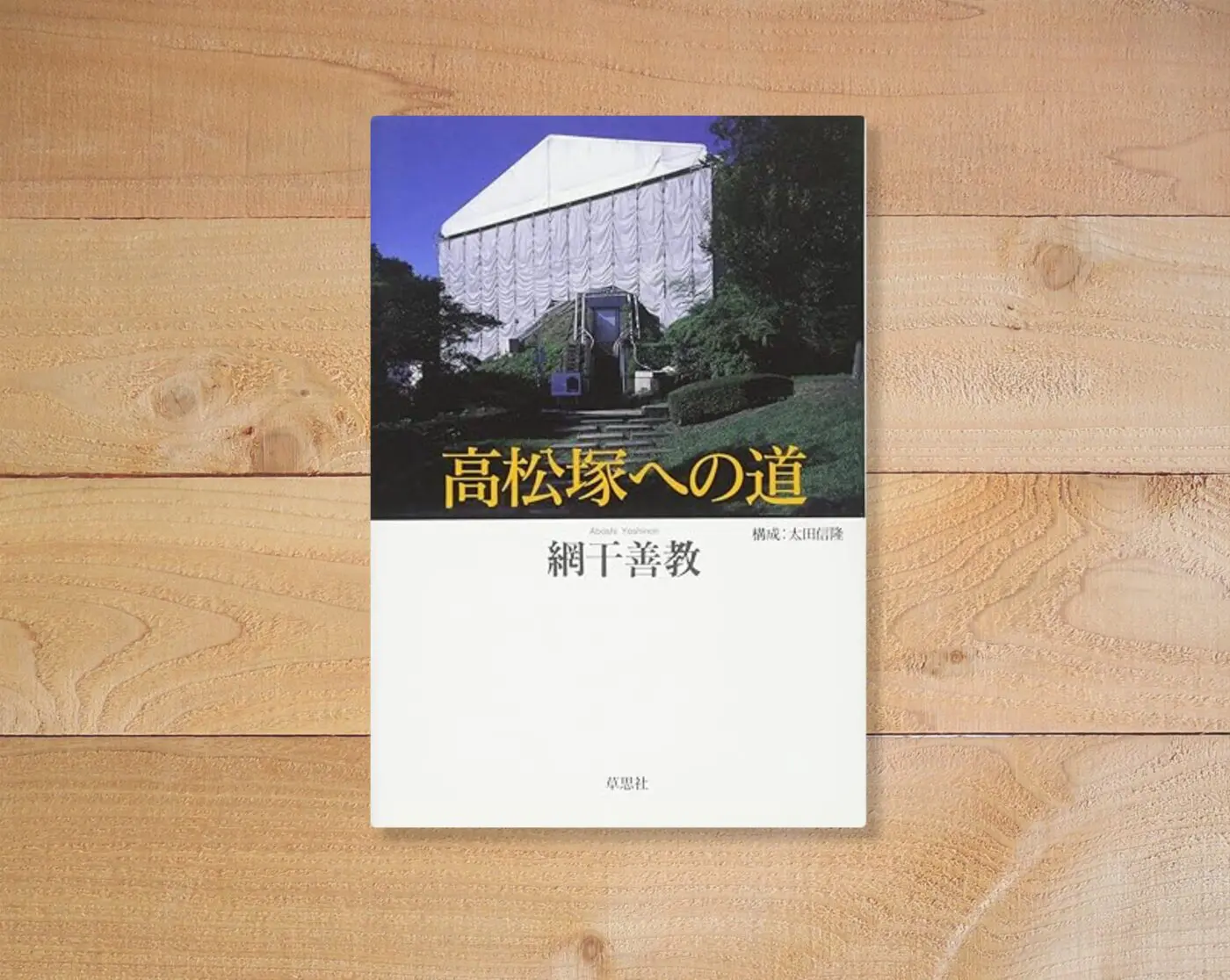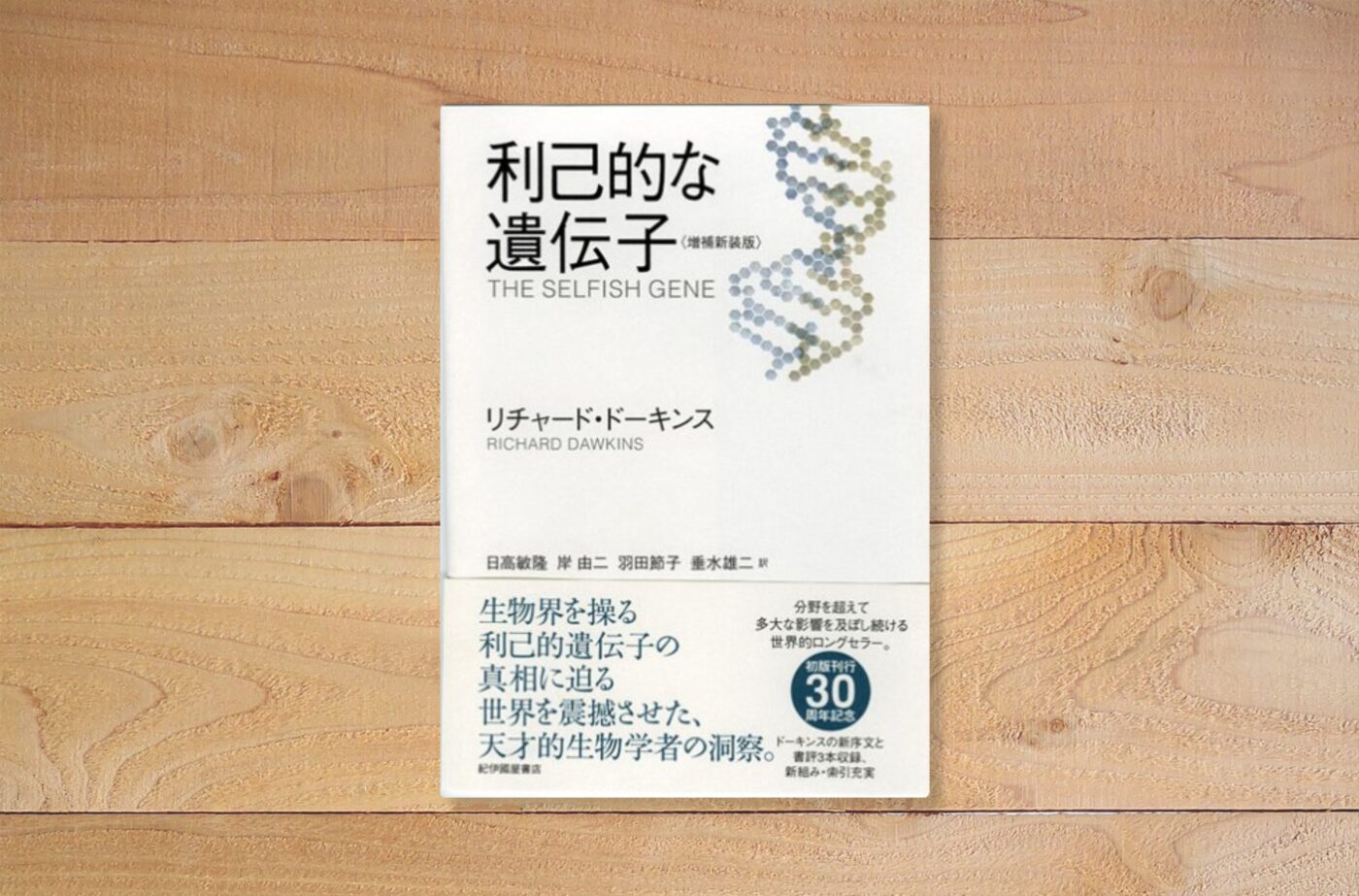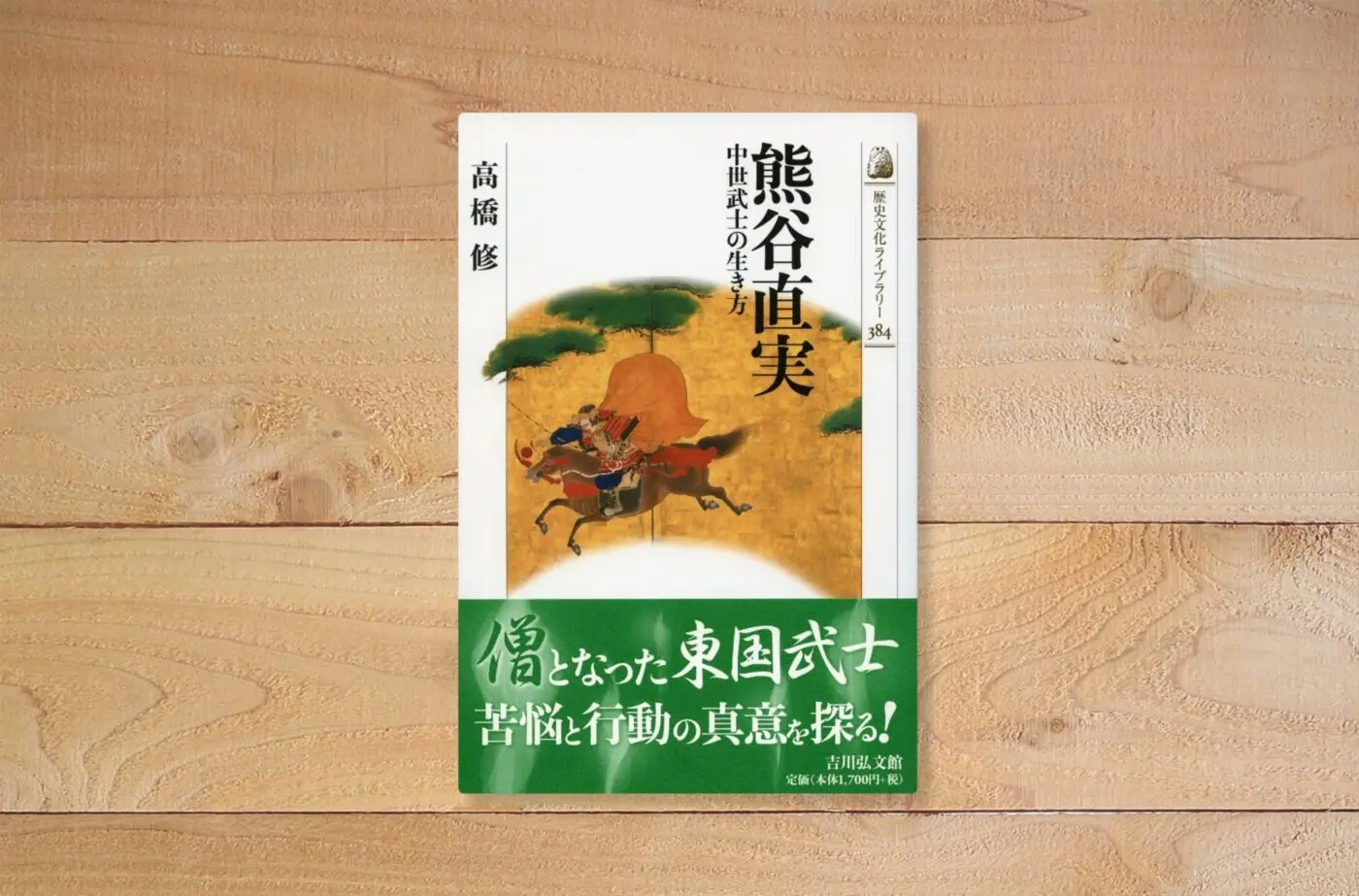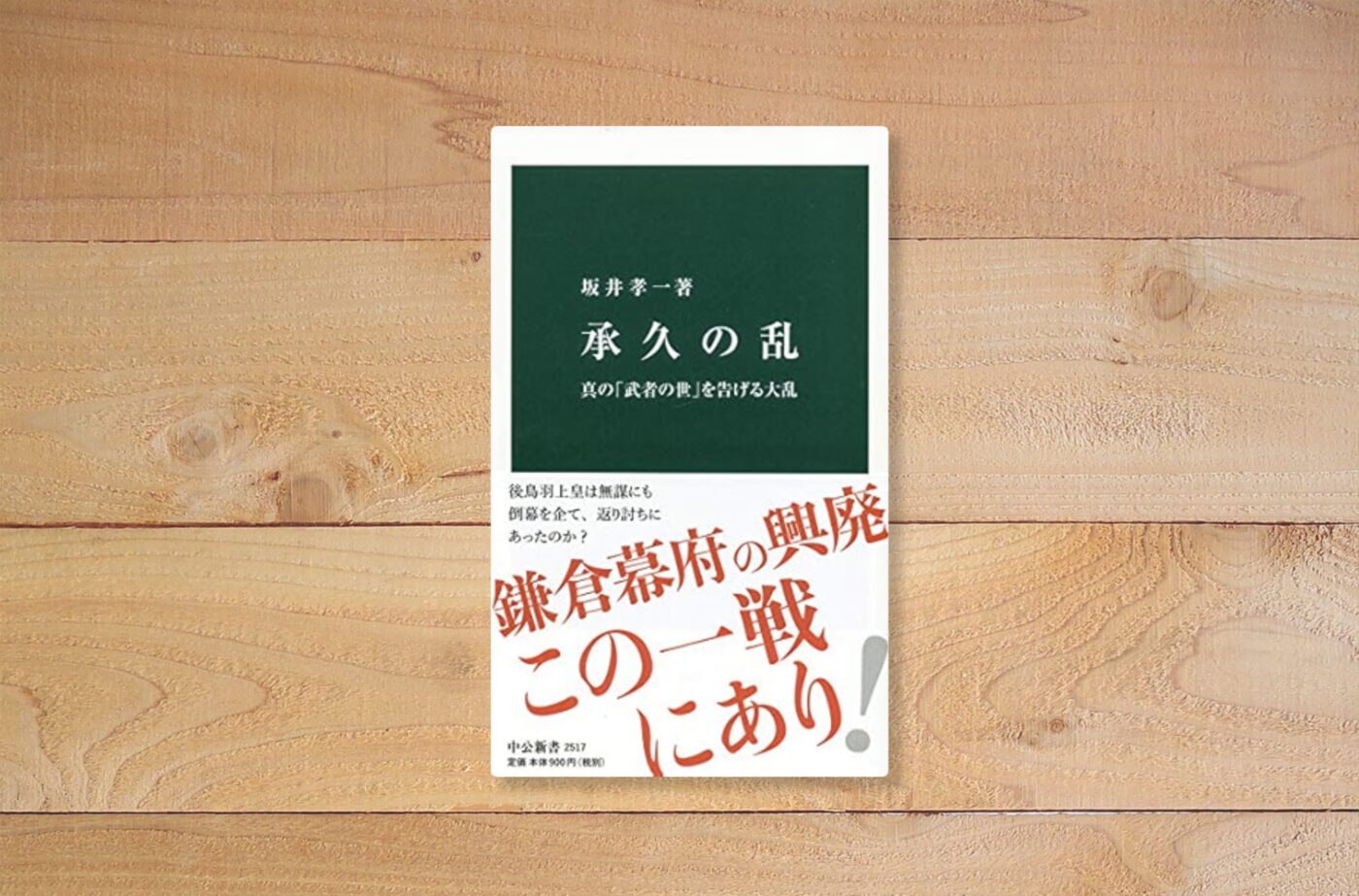松木武彦『人はなぜ戦うのか 考古学から見た戦争』概要と感想~戦争は人間の本質なのか。考古学的視点から見た刺激的な考察

松木武彦『人はなぜ戦うのか 考古学から見た戦争』概要と感想~戦争は人間の本質なのか。考古学的視点から見た刺激的な考察
今回ご紹介するのは2017年に中央公論新社より発行された松木武彦著『人はなぜ戦うのか 考古学から見た戦争』です。
早速この本について見ていきましょう。
弥生時代に入って農耕社会の成立とともに、「先進文化」としての戦争が到来した。食糧をめぐるムラ同士の争いは、やがて組織化され、強大な軍事力をともなった戦争として展開する。武器で傷つけられた人骨、副葬された膨大な武器、巨大古墳など、考古学の発掘成果をもとに列島の人々の戦いの様相を明らかにする。
Amazon商品紹介ページはこちら
欧米の新しい研究動向を踏まえ、ヒトの心の働き、政治権力の発生など、広く人文・社会科学的視野から戦争のメカニズムを探究し、古墳時代以前を総合的にとらえる野心的な文明論。

今作『人はなぜ戦うのか 考古学から見た戦争』の著者はこれまで当ブログでも紹介してきた『考古学から学ぶ古墳入門』や『未盗掘古墳と天皇陵古墳』、『美の考古学 古代人は何に魅せられてきたか』の著者でもあります。
松木武彦氏は私達が知っているようで実は知らない古墳時代の世界をわかりやすく教えてくれる素晴らしい先生です。私も松木氏の著書『考古学から学ぶ古墳入門』に撃ち抜かれすっかり古墳時代にハマってしまった人間です。
本書はそんな松木氏による刺激的な考察を聞けるこれまた素晴らしい名著となっています。
「人間はなぜ戦うのか」
これは私達人間における根源的な問いのひとつです。
私達の生きる日本においては「縄文時代までは戦争がなかったが弥生時代になって稲などが保存されるようになり、そこから富の収奪のため戦争が始まった」という説がよく語られます。
本書ではこの「常識」と言えるほど人口に膾炙したこの説について考古学的知見から検証を加えていきます。
本書冒頭では松木氏はこう述べています。少し長くなりますが非常に重要な指摘がなされていますのでじっくりと読んでいきます。
農耕社会になると、なぜ戦争が生み出されるのだろうか。この問いについて、歴史学の世界で古典的になされてきた説明はこうだ。農耕は、狩りや漁携や採集よりもたくさんの生産物を得ることができる。うまくいけば、人びとが食べてもまだあまる食糧の余裕ができる。これは、そのまま貯蔵されるにせよ、他の品や財貨と交換されるにせよ、富だ。農耕社会ではこうした富ができやすいから、その奪い合いが引き金となり戦いが激化するのだ、と
これに対し、人類学の世界では、農耕社会になってまず認められるのま、なによりも人口の急激な増加で、それこそが戦争発生の条件になったと考える人が多い。私もその賛同者のひとりだ。ではなぜ、農耕社会に突入すると人口が急増するのだろうか。
まず、農耕社会でおもなかてとされる穀物は、栄養があって消化もよく、成人や老人の余命を長くし、子どもや赤ちゃんの死亡率を低くする。つまり、平均寿命を延ばす。
さらに、穀物からすぐれた離乳食を作ることができるので、赤ちゃんの乳離れが早くなり、結果としてひとりの女性が一生に産むことのできる子どもの数は多くなる。すなわち、出生数が増加する。
また、集団が移動して生活する狩猟社会では、子どもは、足手まといとなって集団の中に多く置いておけないのに対し、年中ひとところに定住して暮らす農耕社会では、幼い子どもたちが何人いても問題はない。しかも、かれらが少し大きくなれば、草とりなどの簡単な作業の担い手として貴重な労働力となる。このことも、子どもの労働にほとんど頼れない狩りや漁携と大きく違う点だろう。同じことは、老人についてもいえる。つまり、定住がもたらす安定した生活様式が、たくさんの弱者の存在を許すのだ。
右のような要因により、農耕社会に突入した当初は、順調にいけば人口はウナギのぼりでふえる。このことは多くの事例で認められている。人口がふえたからには、それを養えるだけの穀物を得るために、耕地を次々と広げていかなければならない。だが、それには物理的な限界があり、いずれは人口に対する耕地の、つまりは食糧の不足が生じてくる。ある年に日照りが続いたり、洪水が起こったりすると、事態はもっと深刻だ。予定していた収穫ができなくなり、人びとはたちまち飢餓の危険にさらされる。
たくさんの食糧源をもった狩猟・採集の社会なら、そのうちの一つ二つがだめになっても、ほかの食糧源でおぎなうことができる。しかし、穀物の実りにほとんどの労働力をつぎ込んだ農耕社会では、その穀物がだめになったとき、それをおぎなうべきほかの食糧源は、細ってしまっているのがふつうだ。たとえば、縄文人の胃袋を満たしたドンクリ類が実っていた森林を、弥生人は切り払って水田にした。かつてはみんなが知っていた狩りや漁撈のノウハウも、限られたものになっただろう。もとへ戻ろうとしても、姿を大きく変えてしまったのちでは、もう無理なのだ。
このように、農耕社会は、短期的にみれば、年ごとにおどろくほどたくさんの収穫が約束される、いっけん魅力に満ちた社会に映る。けれども、何世代ものちのことまで見通せば、土地や水といった食料生産を支える資源の欠乏や、気候不順による飢餓の危険など、避けられない大きなリスクをはらんだ社会ともいえる。
このような、単一の資源に大きく依存し,環境の変化に対する耐性の少ない生産システムの成立が、農耕社会で始まる戦争の根本的な経済条件を作った可能性が高い。すなわち、農耕社会で生じる右のような危機に面したときのリアクションの一つとして、戦争が始まったとみられるのである。人口増加や凶作によって、長期的に、または一時的に不足した資源を力ずくで押さえることが、農耕社会における、もっとも根本的な戦争の動機といえるだろう。
さらにもう一つ、生活形態の変化からくる戦争の誘因が考えられる。農耕社会は、定住生活を営み、大きな労働力をつぎ込んで、まわりの原野を開拓して耕地にする。耕地は血と汗の結晶であり、命をつないでくれる食糧のみなもとだから、それを守る意識は、狩りや採集の社会のテリトリーを守る気持ちよりも何倍も真剣で強烈なものになるはずだ。つまり、耕地のような明確な不動産が現れたことが、人びとの排他的な防衛意識を強め、争いを激しくさせた大きな原因となったにちがいない。佐原氏も近年、農耕に加えて定住という現象を、戦争発生の要件として重視している。
このように考えると、さきに例外としてあげた、狩りを主とする社会でありながら戦をおこなっている例についても、多少の説明ができる。四〇〇〇~五〇〇〇年前の東シべリアの例はわからないが、北アメリカ北西海岸の先住民は、非常にめぐまれたサケの漁場のおかげで定住生活を営み、人口密度も高く、またそれがために、漁場に対するそれぞれの集団の排他的な規制も高かったようだ。つまり、定住、人口の多さ、資源の集中とそれに対する排他性、という点で、農耕社会に似かよった条件をもっていたのである。
したがって、戦争が多いか少ないかは、厳密にいうと、農耕社会か、狩猟・漁撈・採集の社会かという違いに決定されるのではない。耕地やめぐまれた漁場のような、かての大半をそこに頼るメインの食糧源をもって定住する社会か、さまざまな食糧源からかてを取得し、あまり定住しない社会かといった、資源や生産のありかたと生活様式のタイプの違いが、戦争の多い少ないに関係している可能性が高い。前者のような社会に農耕社会が圧倒的に多く、後者のような社会に狩猟・漁撈・採集社会の大半が当てはまることが、見かけ上、農耕社会かそうでないかによって戦争の多い少ないが決まっているように映るのだろう。
中央公論新社、松木武彦『人はなぜ戦うのか 考古学から見た戦争』P20-24
いかがでしょうか。驚かれた方も多いのではないでしょうか。
戦争はこれまで通説のように語られていた「富の蓄積とその収奪」ではなく「人口増加や凶作によって、長期的に、または一時的に不足した資源を力ずくで押さえることが、農耕社会における、もっとも根本的な戦争の動機といえる」と松木氏は述べています。
こう見てくるとこれまで世間で議論されて来た「人間には元来戦争をする本能があるのかどうなのか」という問題についても違った見方が出てきますよね。
農耕や定住生活によって人口が増えたところに環境変化が起こると飢餓状態になる。そこで食糧確保のための争いが始まった。
これはまさに平安末期から鎌倉時代の源平争乱でも当てはまりますし、室町から戦後期に関しても気候変動で穀物が不作であったこととも繋がります。なるほど、戦争は人間の根源的な本質というよりも環境要因にも大きく左右されると言えそうです。
本書ではこうした「なぜ人は戦争をするのか」という問題についてひとつひとつ丁寧に考察していきます。これは実に刺激的な名著です。ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。
以上、「松木武彦『人はなぜ戦うのか 考古学から見た戦争』概要と感想~戦争は人間の本質なのか。考古学的視点から見た刺激的な考察」でした。
Amazon商品紹介ページはこちら
次の記事はこちら
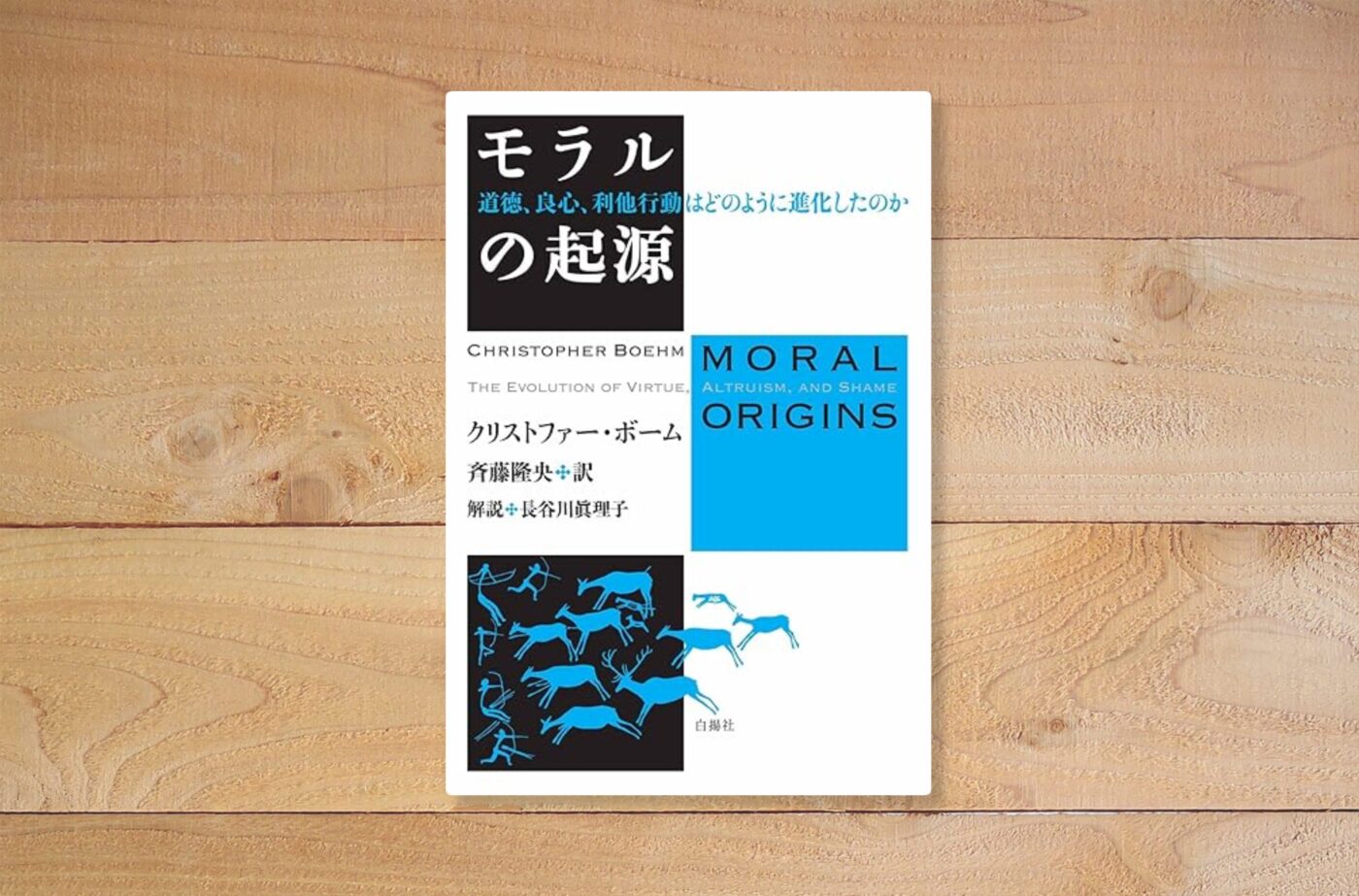
前の記事はこちら
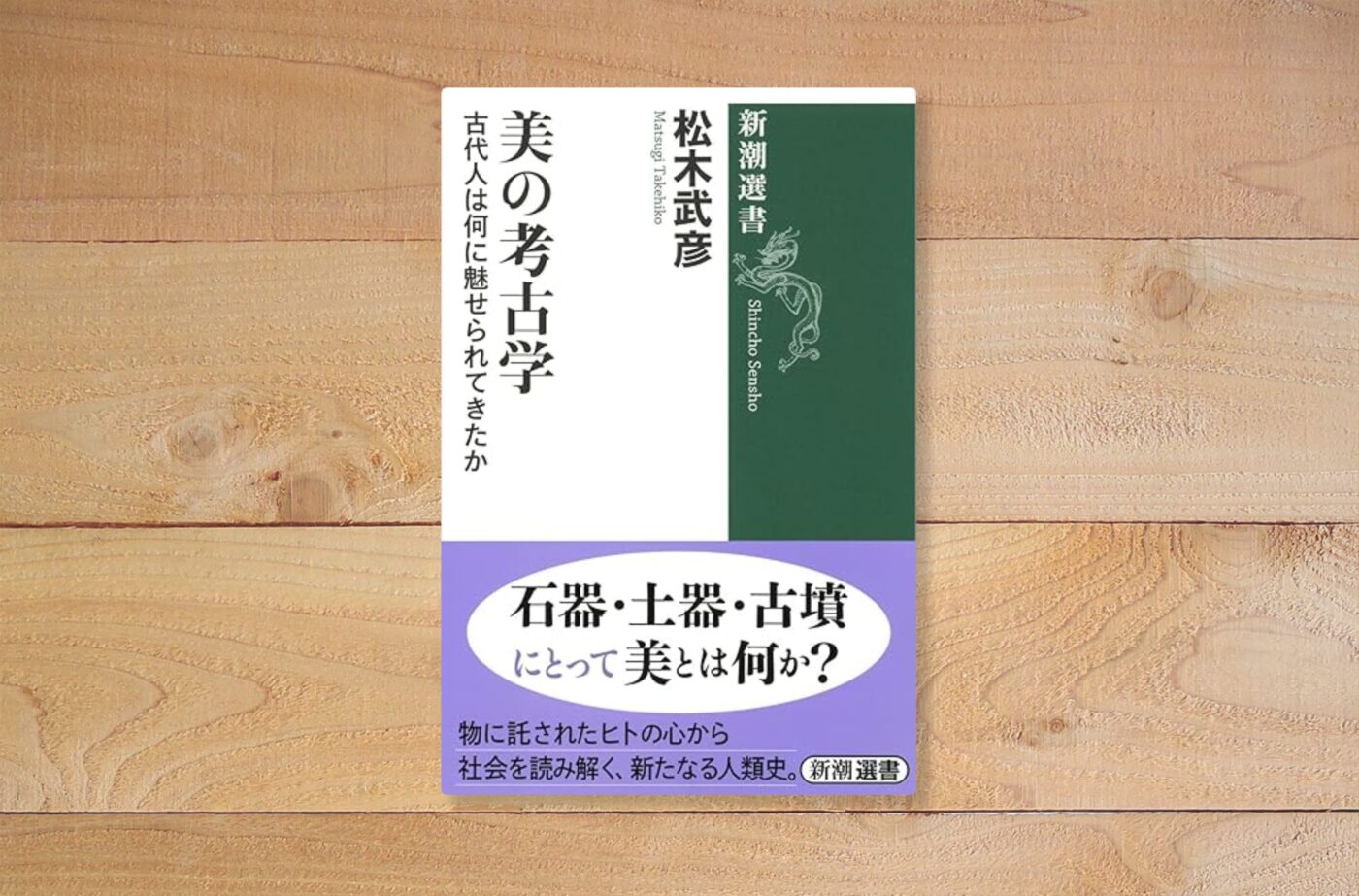
関連記事