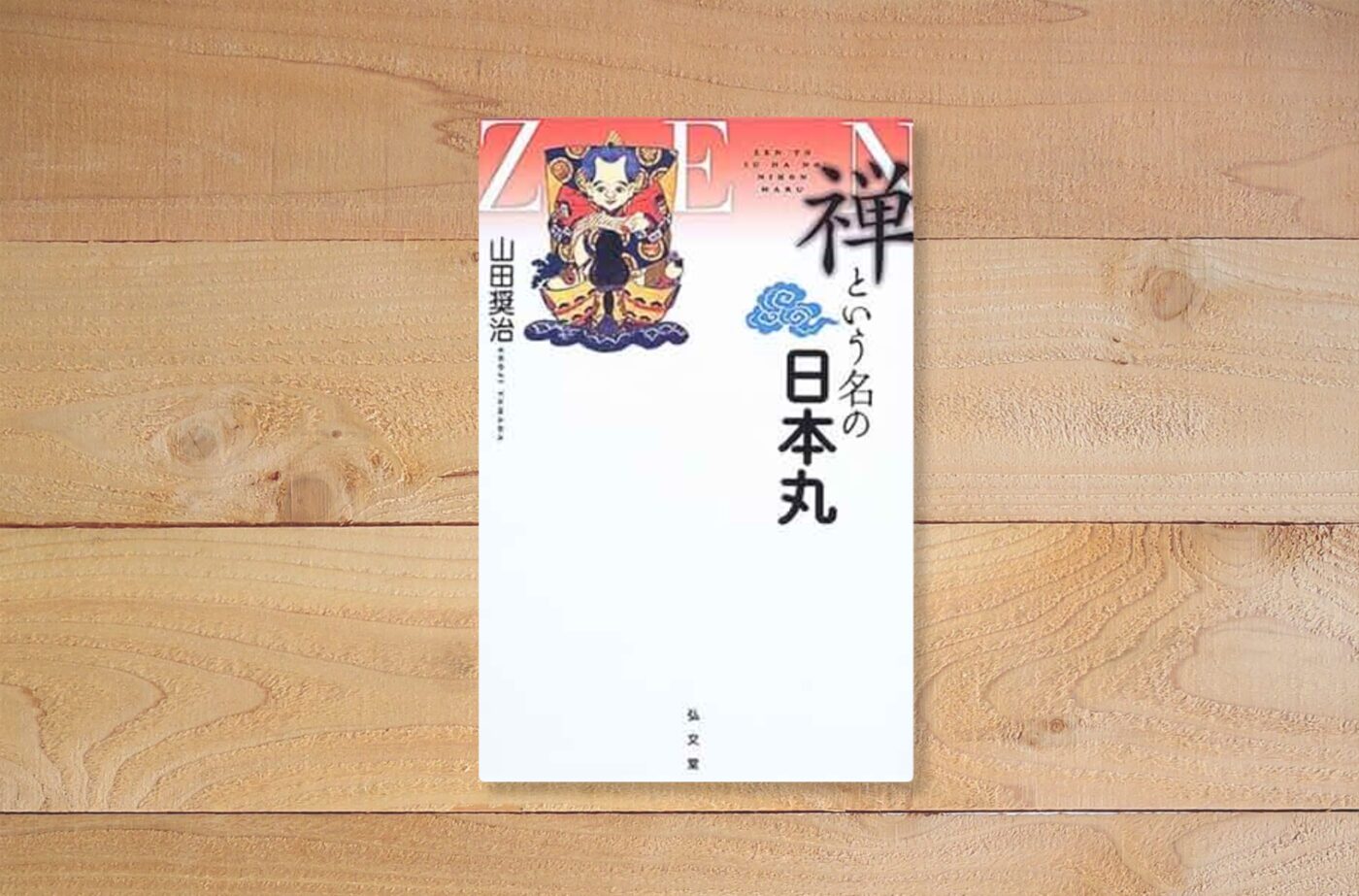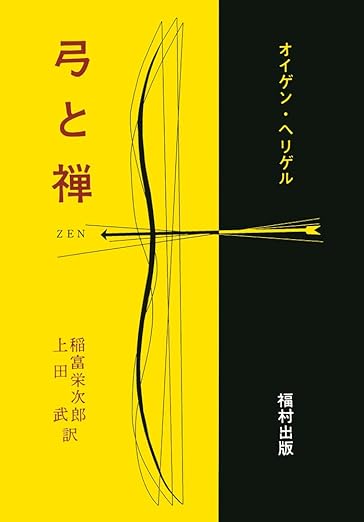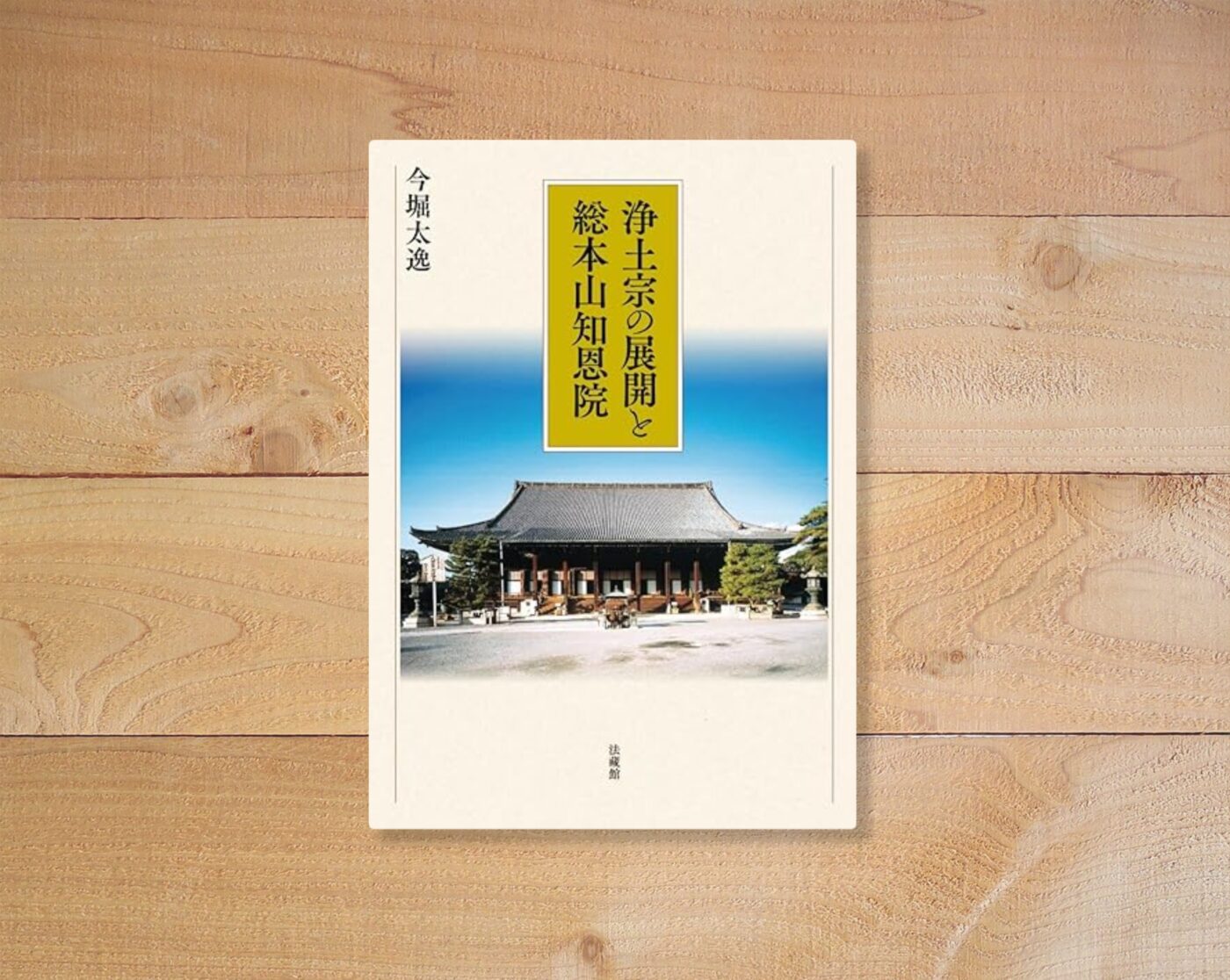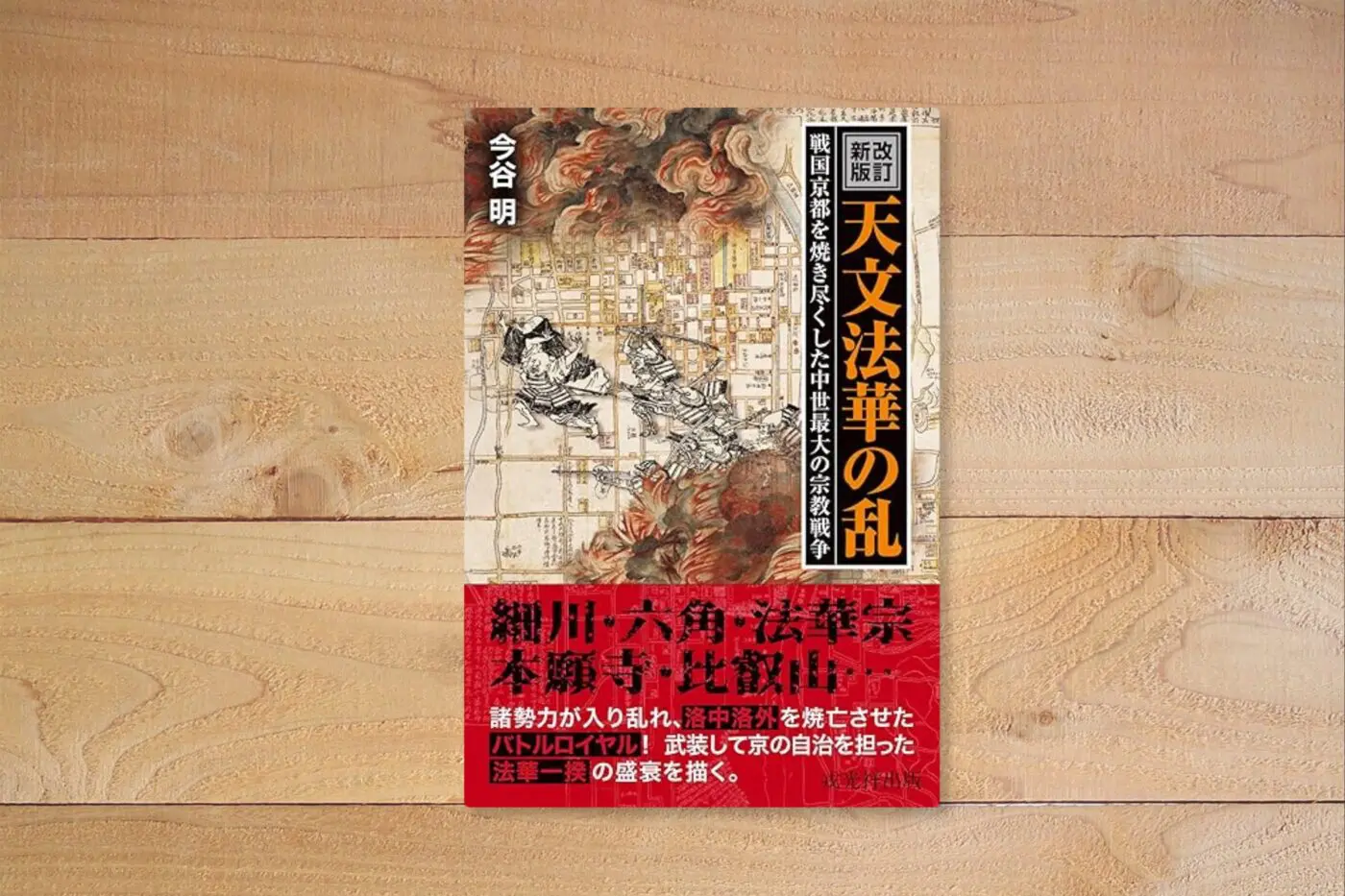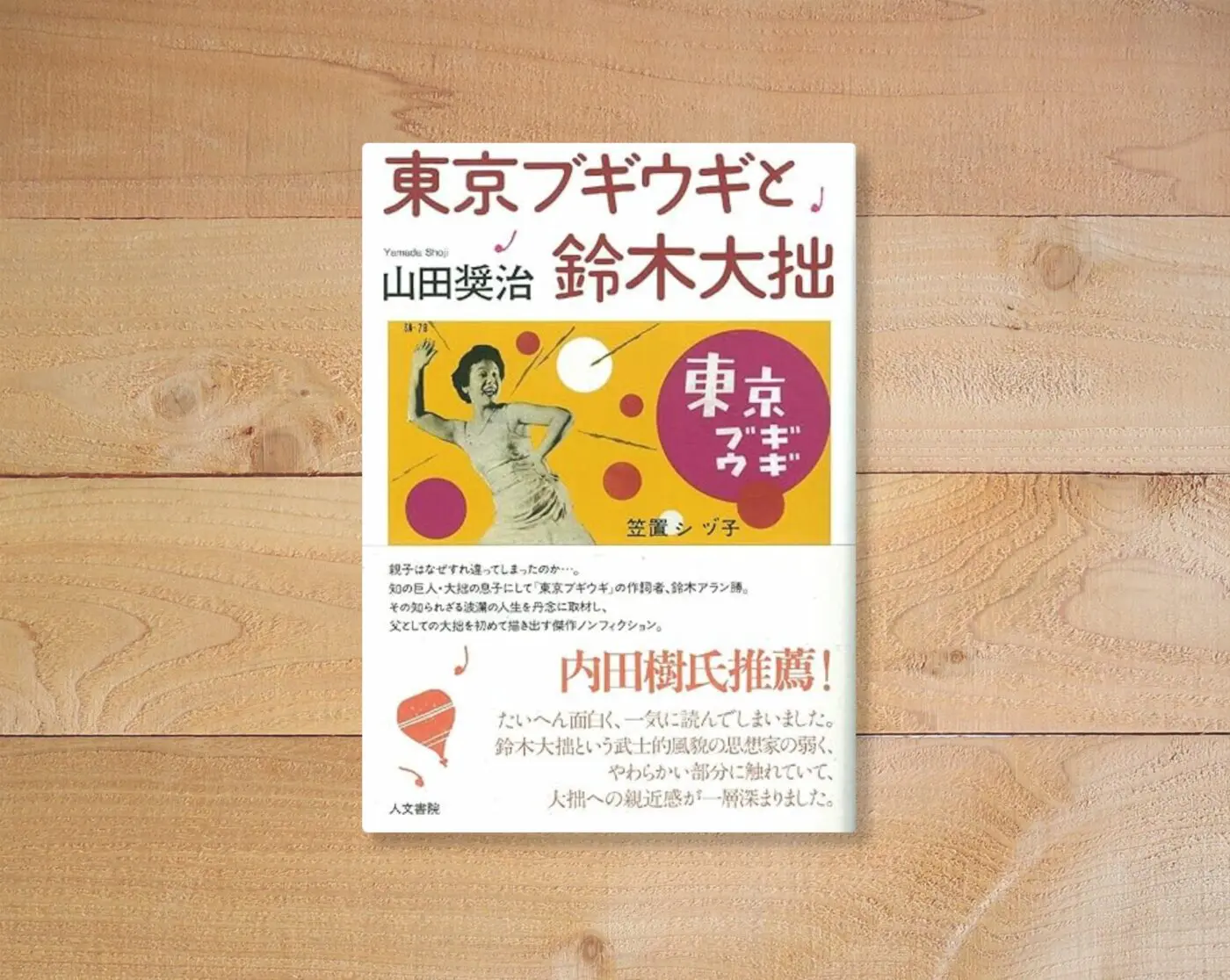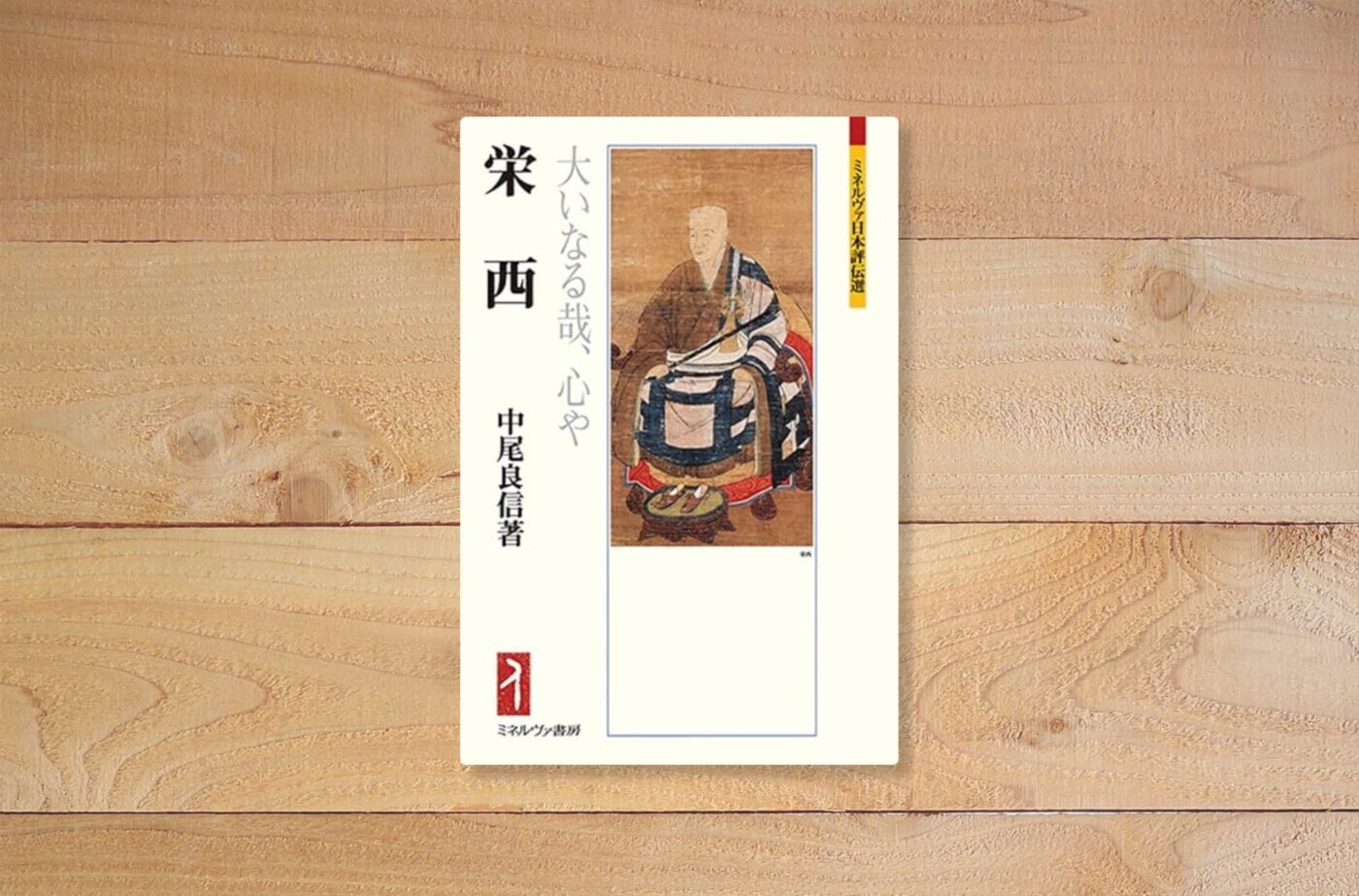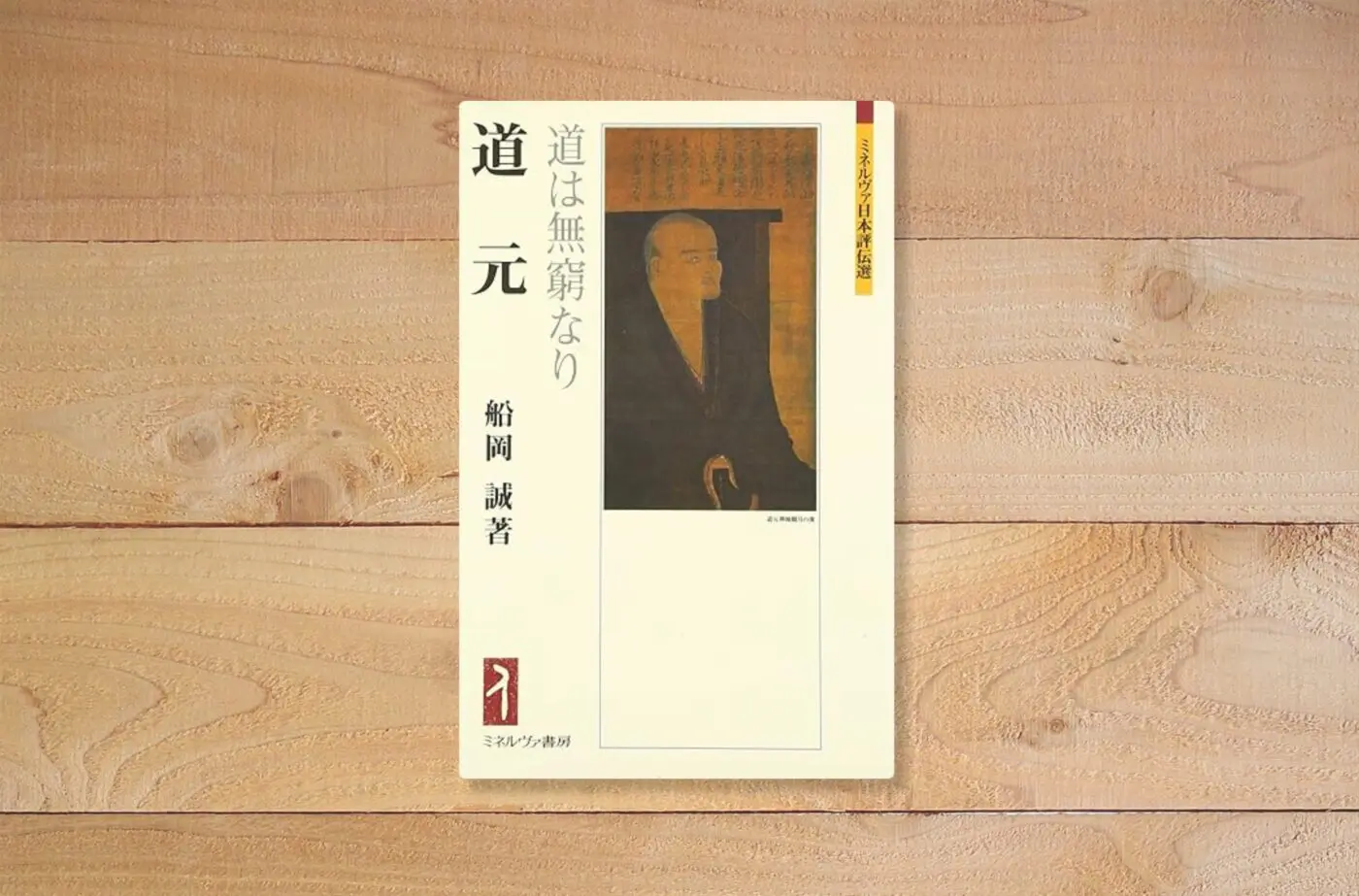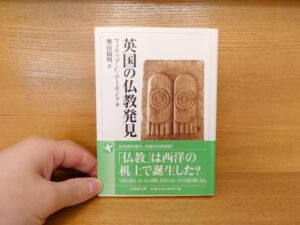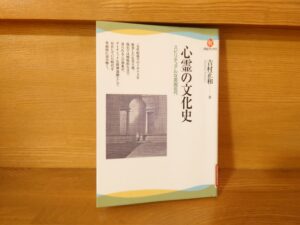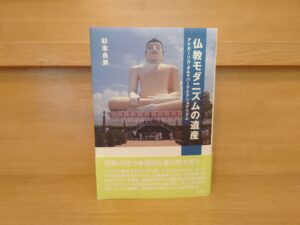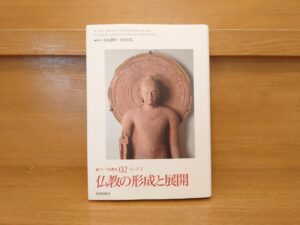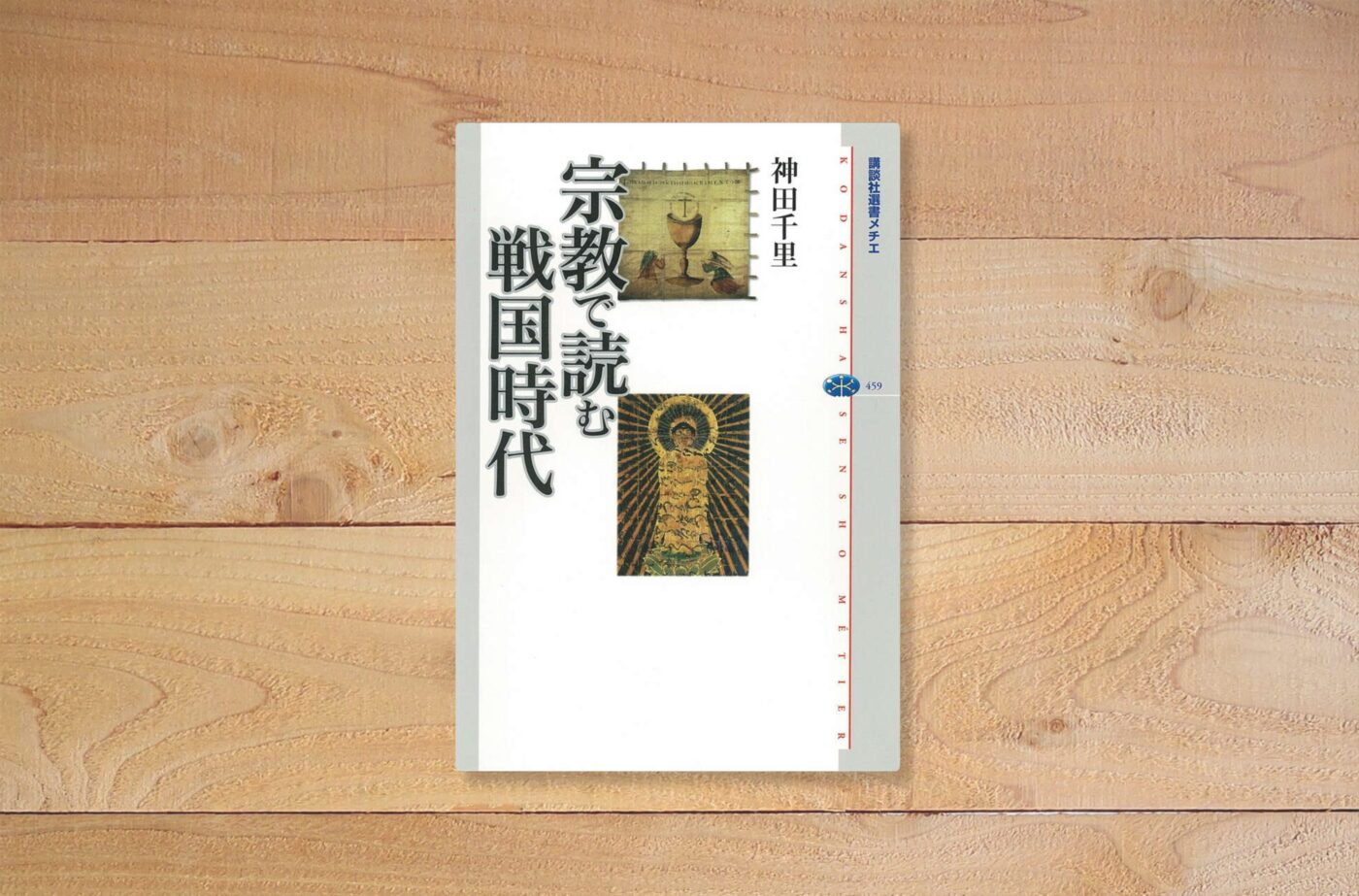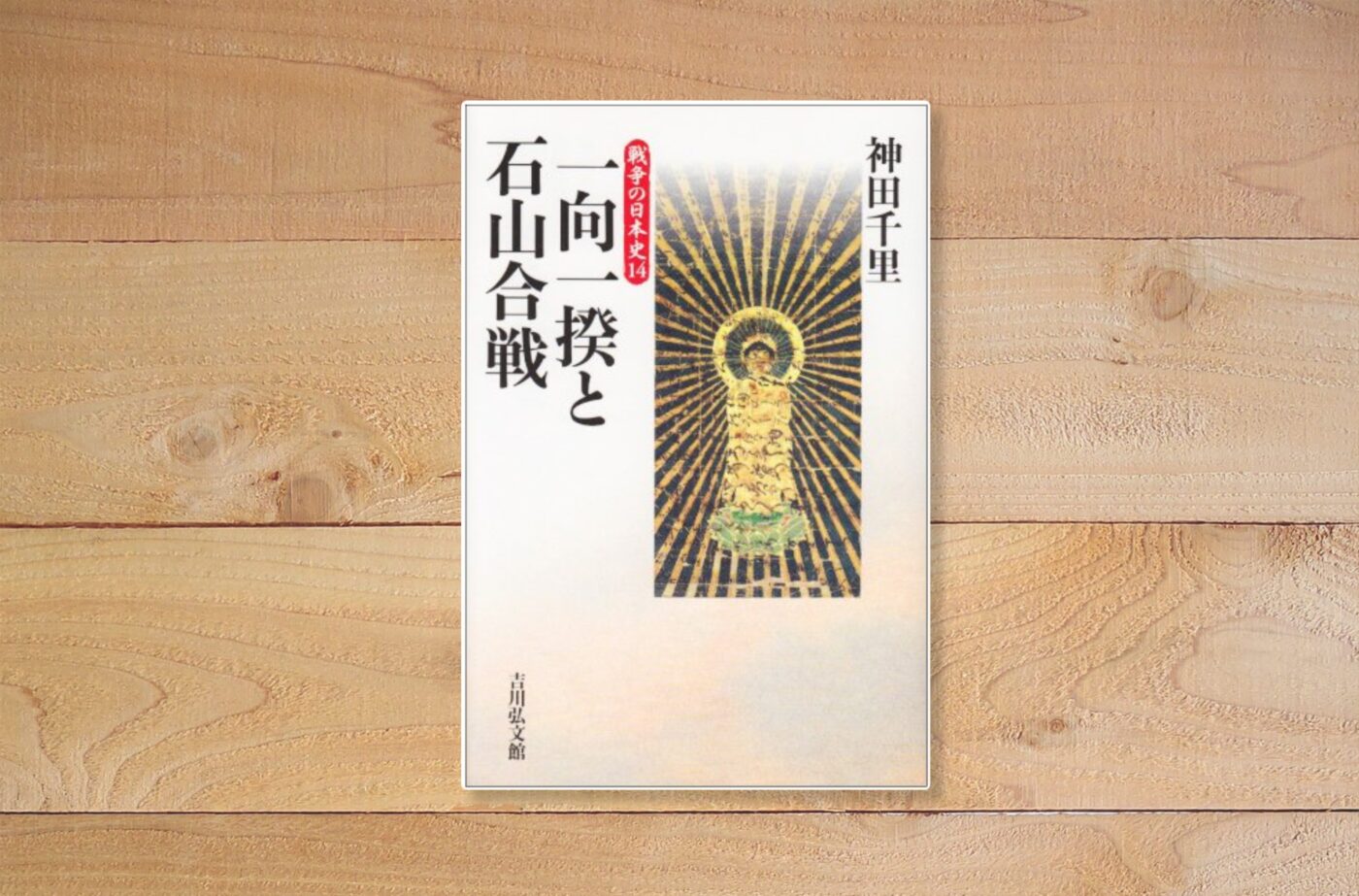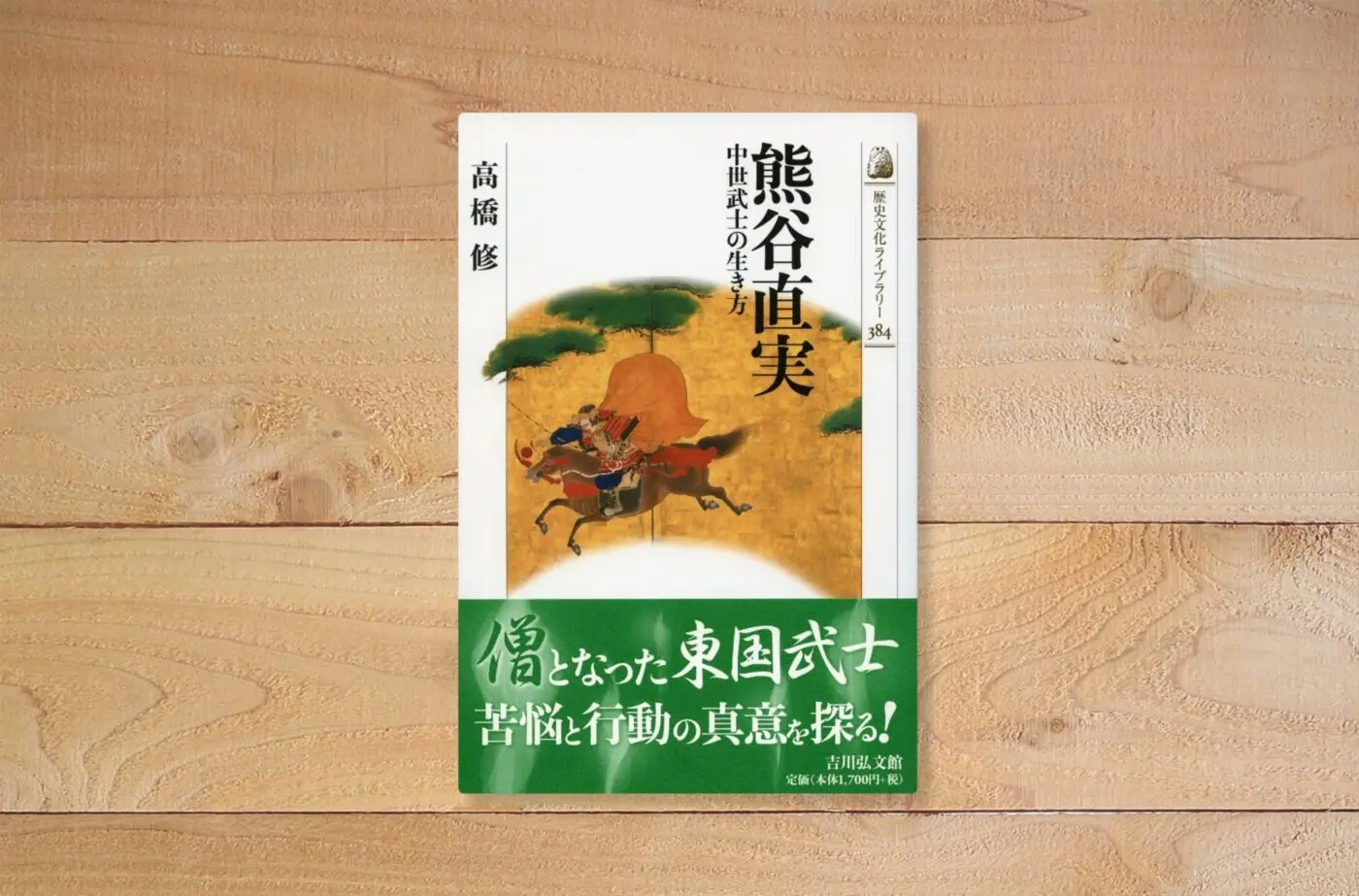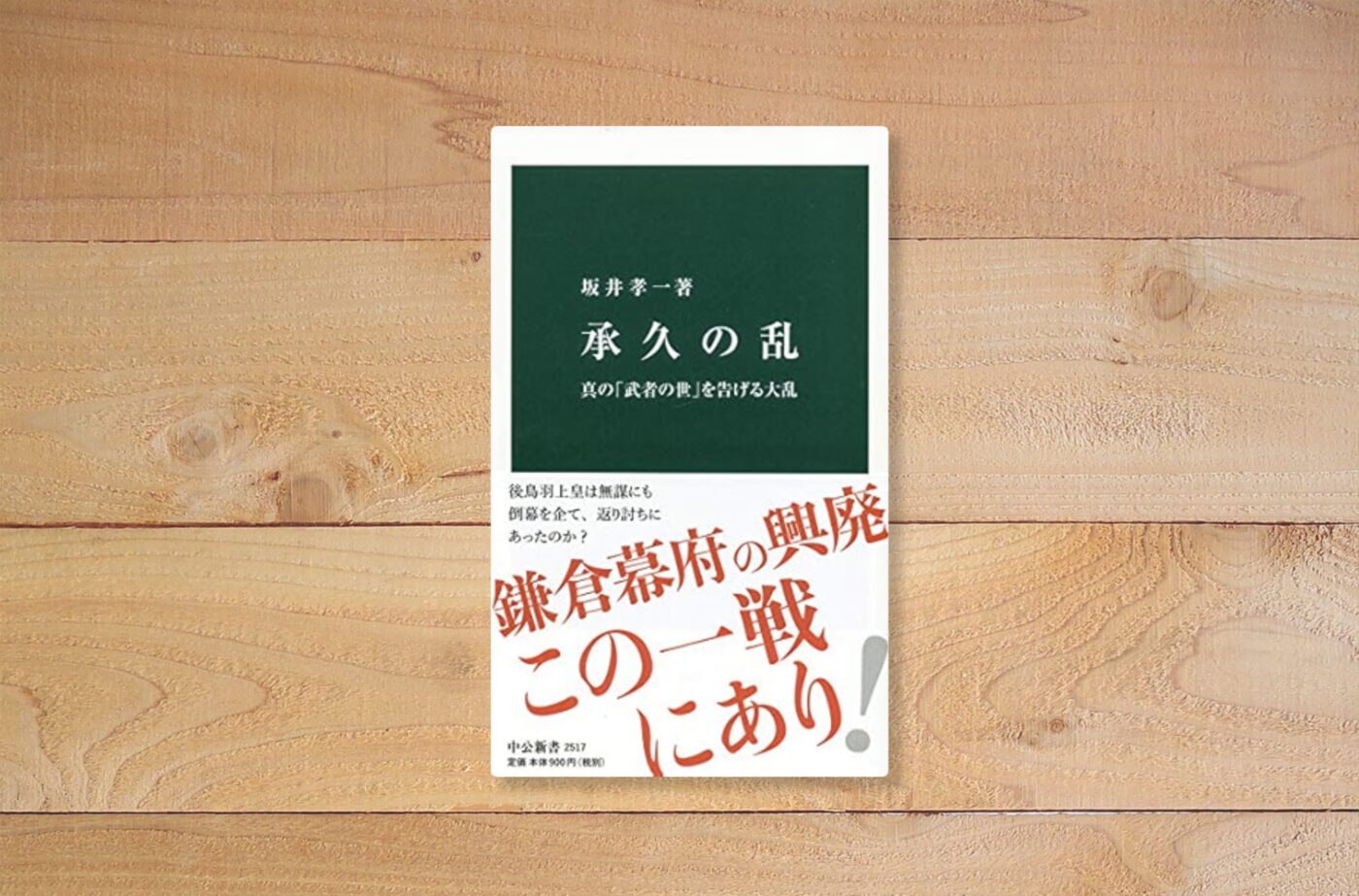目次
山田奨治『禅という名の日本丸』あらすじと感想~『弓と禅』は禅ではなかった⁉日本文化の幻想を暴露する衝撃の一冊
今回ご紹介するのは2005年に弘文堂より発行された山田奨治著『禅という名の日本丸』です。
早速この本について見ていきましょう。
「弓道」「石庭」「禅」という日本文化の代表的な題材をもとに、意表をつく視点から日本人のセルフ・イメージを探る。
日本文化論の古典として、いまなお読み継がれる大ロングセラー、ヘリゲル著『弓と禅』。誤解ともいうべき「日本文化」のイメージを世界中に流布させた「名著」は、どのように作られていったのか? ヘリゲルのナチス時代の資料をも発掘しながら、真相にせまる知的発見の書。
日本文化の情報がどのように外国に伝わり、それが日本にどのように環流して、日本文化そのものを組み替えたかという本書のテーマを、著者は、龍安寺の石庭についても論じ、日本を代表する知識人たちが、訪れる人もまばらな寂れた庭を、世界的に「有名」にしていったプロセスとして描き出す。
鏡に映った「日本人」を追究する、知的エンターテインメント。読み出したらとまらない。
弘文堂商品紹介ページより
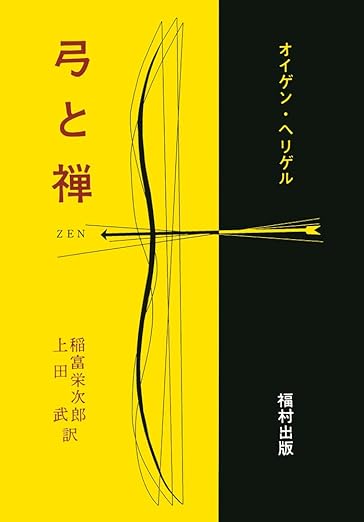 Amazon商品紹介ページはこちら
Amazon商品紹介ページはこちら
1956年に日本で発刊されたオイゲン・ヘリゲルの『弓と禅』は、日本文化と禅の関係性を述べた名著として圧倒的な評価を受けてきた作品です。私もこの本を禅と武道の関係性を説いた古典としてかつてこの本を読んだことがあります。
しかし、この禅の名著とされてきた『弓と禅』が実は禅とは関係ないものだったとしたら?
本書ではそんな驚くべき事実が暴露されます。これはもう衝撃以外の何物でもありません。日本文化とは何ぞやという命題がそもそもひっくり返るほどの大事件です。本書のまとめに書かれた次の言葉は特に印象的です。
「~こそ日本文化を代表するものだ」と、世間に流通している言説は、その成り立ちを一度は疑ってみたほうがよい。ハイ・カルチャーからサブ・カルチャーまで、文化のあらゆる領域で、昔もいまもおなじようなことが起きている。
弘文堂、山田奨治『禅という名の日本丸』P346
そうです。まさに「禅こそ日本文化を代表するものだ」という言説こそ、戦後に作られたものだったのです。私達は日本文化を伝統あるものと思い込んでいますが、実はその文化こそ近年構築されたものだったということが多々あるのです。
以前当ブログでも紹介した『東京ブギウギと鈴木大拙』でも鈴木大拙が伝説化され、都合の悪いものを消しながらイメージが作られていたことが明らかにされましたが、これは大拙だけの問題だけでなく、日本におけるあらゆるジャンルにもその可能性があるのです。まさに「創られた伝統」です。「はるか昔から日本人が受け継ぎ大切にしてきた」と私達が思い込んでいるものがはたして本当にそのようなものなのかという恐ろしい事実が浮かび上がってきます。
『禅という名の日本丸』にはそうしたある種戦慄の事実が書かれています。ぜひこれは僧侶の方に読んで頂きたい驚異の名著です。
『東京ブギウギと鈴木大拙』と合わせて読まれることをおすすめします。
以上、「山田奨治『禅という名の日本丸』あらすじと感想~『弓と禅』は禅ではなかった⁉日本文化の幻想を暴露する衝撃の一冊」でした。
Amazon商品紹介ページはこちら
禅という名の日本丸
次の記事はこちら
あわせて読みたい
今堀太逸『浄土宗の展開と総本山知恩院』概要と感想~知恩院側から見た親鸞や浄土真宗を知るのにおすすめ
本書では知恩院側から見た法然、親鸞、重源の姿や知恩院そのものの歴史を知ることができます。
私達真宗僧侶がなかなかアクセスできない視点で語られる内容は実に刺激的でした。浄土宗について知りたい真宗僧侶の方にもぜひぜひおすすめしたい一冊です。
前の記事はこちら
あわせて読みたい
今谷明『天文法華の乱』概要と感想~1530年代京都で起きた宗教戦乱の実態に迫るおすすめ参考書
本書は私達の常識を覆す衝撃的な1冊です。
室町、戦国期はとにかく複雑です。なぜ京都で日蓮宗が急拡大し、1536年に京都を焼き尽くす大事件が起きるほどになってしまったかということには多種多様な背景が絡んできます。まさに宗教は宗教だけにあらず。本書ではそんな複雑怪奇な政治経済、時代背景を時系列に沿って読み解いていきます。
関連記事
あわせて読みたい
山田奨治『東京ブギウギと鈴木大拙』あらすじと感想~近代仏教の大家の知られざる家庭生活を知れる刺激...
鈴木大拙には知られざる、作詞家の息子がいた・・・!
この本にはある種戦慄の事実が書かれています。ぜひ僧侶の方に読んで頂きたい驚異の一冊です。
あわせて読みたい
中尾良信『栄西』概要と感想~臨済宗の開祖のおすすめ伝記!密教と禅を共に修した意外な姿とは
本書では栄西がもたらした禅仏教を「鎌倉新仏教」単発のものとして見るのではなく、これまでの時代の流れと連続したものとして見ていきます。
特に栄西が禅仏教だけでなく従来の密教の教えも重視していた事実には驚きました。「栄西=禅宗の開祖」というイメージを持たれる方も多いと思いますが、実は彼の仏教は禅だけではなかったのです。むしろ従来の密教と禅を融合させこれまでの仏教と融和的な方向で布教をしていたのでありました。
あわせて読みたい
船岡誠『道元』概要と感想~曹洞宗の開祖道元のおすすめ伝記!謎多き偉人の生涯とは
本書の主人公は曹洞宗の開祖として有名な道元です。
道元も比叡山に数年ほど学んでいますが、そこから栄西教団の下に入り、宋への渡航も果たしました。しかし栄西の臨済宗とは異なる道を歩んでいきます。
道元といえば「只管打座」というひたすら禅に没頭する仏道を広めたことで知られていますが、この道元の生涯を様々な歴史資料から追っていくおすすめ伝記が本書『道元 道は無窮なり』になります。
あわせて読みたい
F・C・アーモンド『英国の仏教発見』あらすじと感想~仏教学はイギリスの机上から生まれた!?大乗仏教批...
この本を読むと、「原始仏教に帰れ。日本仏教は堕落している」という批判が出てきた理由がよくわかります。これまでどうしても腑に落ちなかった大乗仏教批判に対して「ほお!なるほど!そういうことだったのか」という発見がどんどん出てきます。この批判が出てくる背景を追うととてつもない事実が浮かび上がってきます。これは最高に刺激的な一冊です。
あわせて読みたい
吉村正和『心霊の文化史 スピリチュアルな英国時代』あらすじと感想~スリランカ仏教に影響を与えた神智...
心霊主義といいますとオカルトチックで怪しいイメージもありましたが、実は産業革命や世界的な合理主義の流れから生まれてきたという興味深い背景を知ることができる本書は非常に刺激的です。
スリランカを学ぶ上でも非常にありがたい作品でした。
あわせて読みたい
杉本良男『仏教モダニズムの遺産』あらすじと感想~スリランカ内戦はなぜ起こったのか。仏教ナショナリ...
仏教国スリランカにおける仏教とは一体何なのか。
私達が想像する仏教の世界とは全く異なる世界がここにあります。
宗教とは何かを考える上でも本書は非常に興味深い内容が満載の素晴らしい作品です。
あわせて読みたい
『新アジア仏教史02インドⅡ 仏教の形成と展開』概要と感想~仏教のイメージが覆る?仏教学そのものの歴...
私達が当たり前だと思って享受していた〈仏教学〉が日本の仏教思想や文化とは全く無関係に生まれたものだった。
この本を読めば〈仏教学〉というものがどんな流れで生まれてきたのか、そしてそれがどのように日本にもたらされ、適用されることになったのかがよくわかります。
あわせて読みたい
神田千里『宗教で読む戦国時代』概要と感想~戦国時代の人々が共有していた「天道」とは何か。私達の常...
戦国時代における宗教とはどのようなものだったのかを学ぶのにこの本は必読と言ってよいほど素晴らしい参考書でした。
しかもこの本でも私達の常識を覆す驚きの説が語られます。特に「天道」という当時の日本人が広く受け入れていた考え方についての考察はあまりに衝撃的でした。
あわせて読みたい
神田千里『一向一揆と石山合戦』概要と感想~一向一揆は作られたイメージだった!?本願寺教団急拡大の背...
戦国時代の一揆といえば浄土真宗門徒による一向一揆というイメージが私達にはありますが実はこれが後世に作られた説話だったとしたらどうでしょう。戦国当時としては「一向一揆」という言葉がほとんど使われず、真宗門徒による一揆という観念すら乏しかったのだそうです。では、なぜ「この時代に一向一揆が頻発し、歴史に大きな影響を与えた」と私達は教えられることになったのでしょうか。そうしたからくりが本書で明らかにされます。これには私も驚きました。