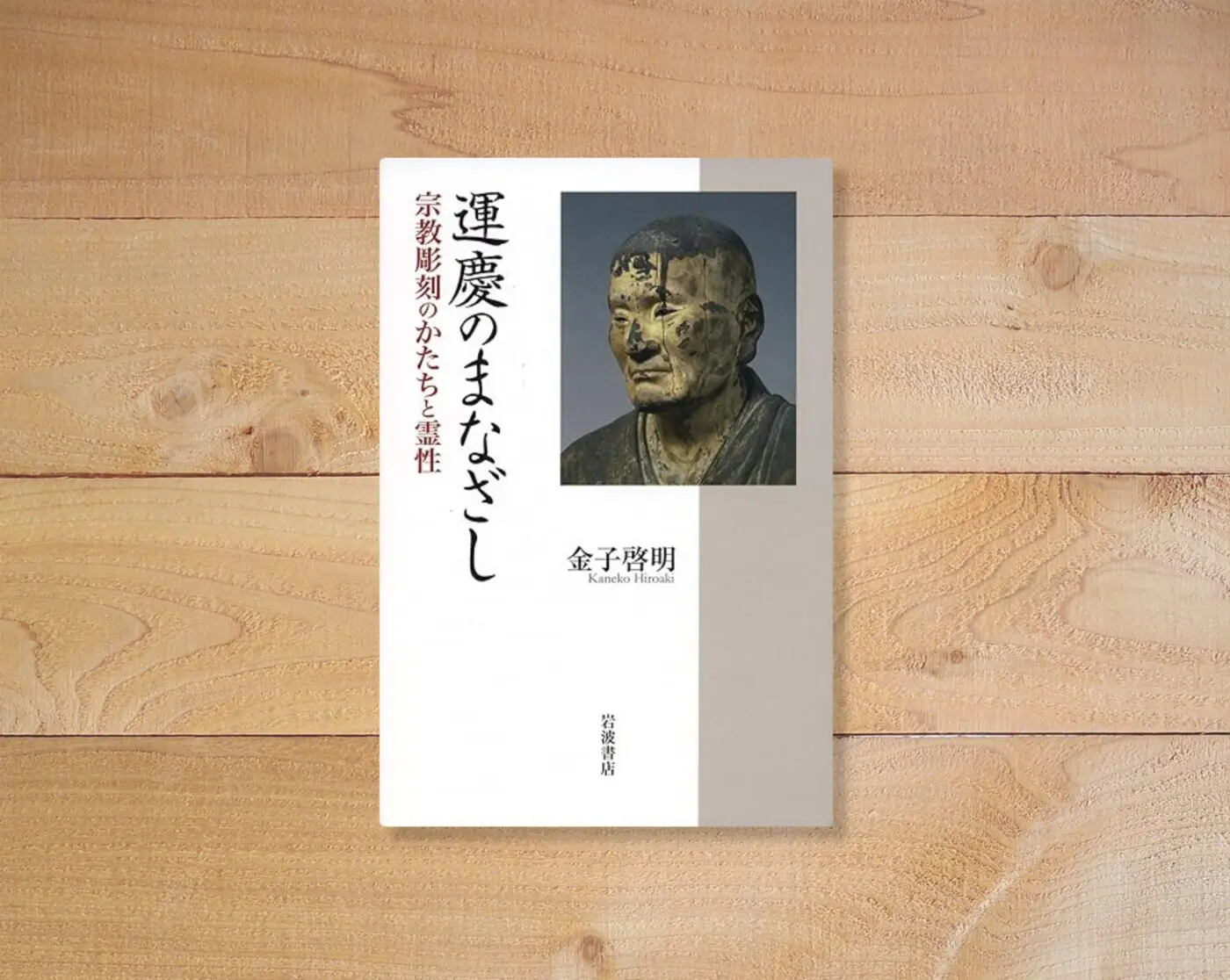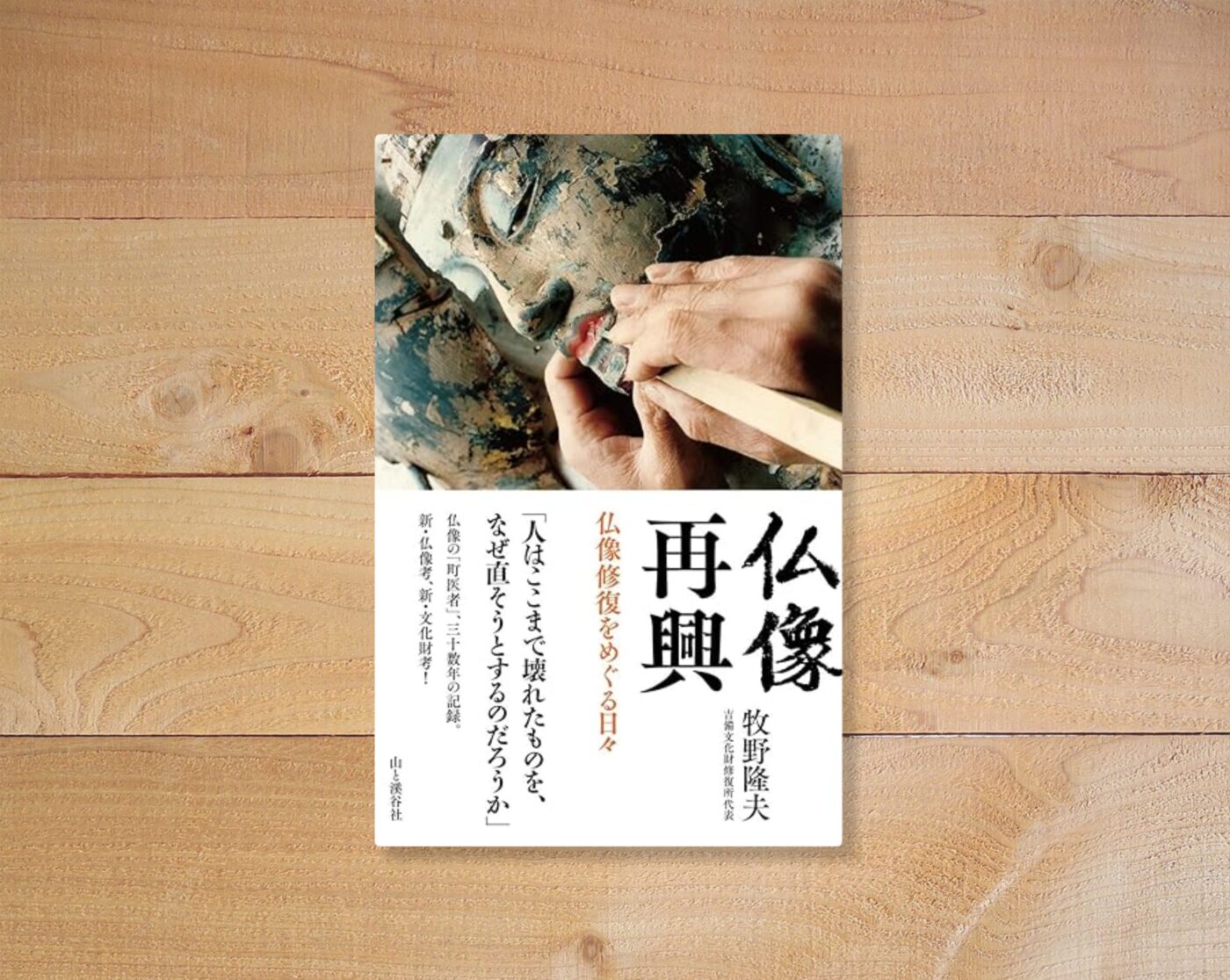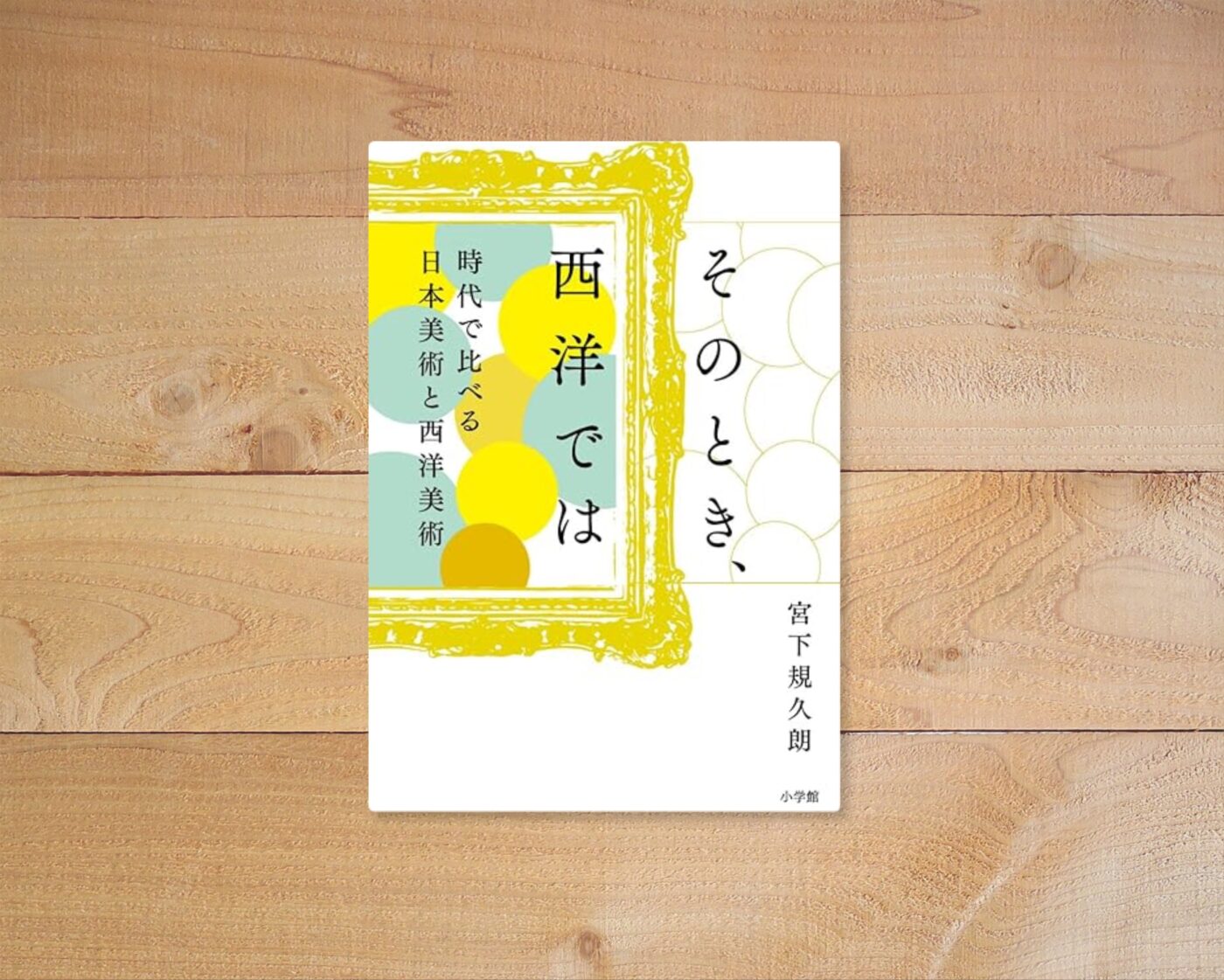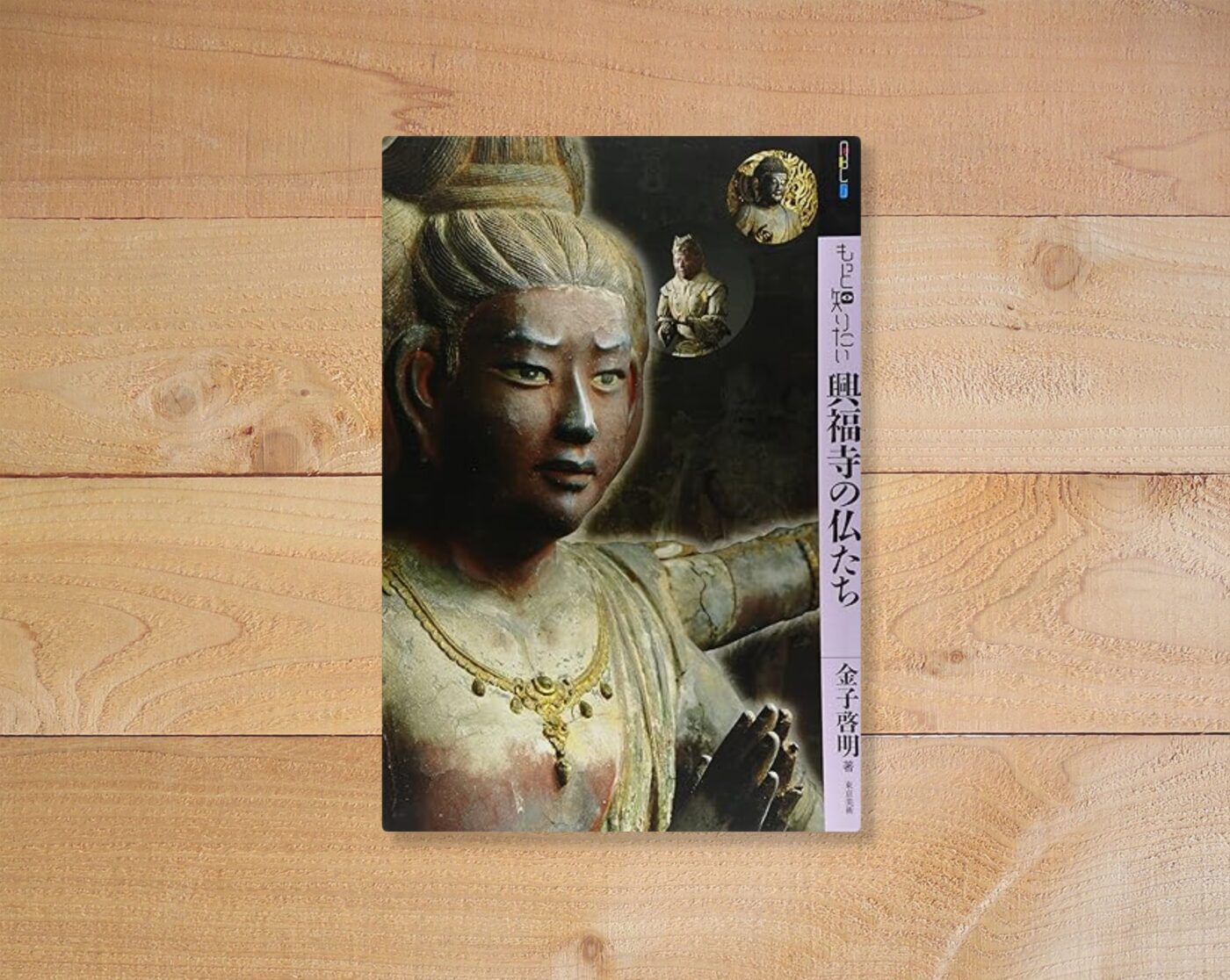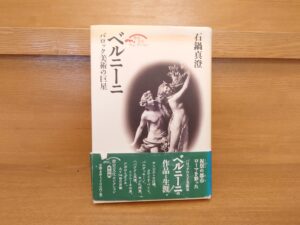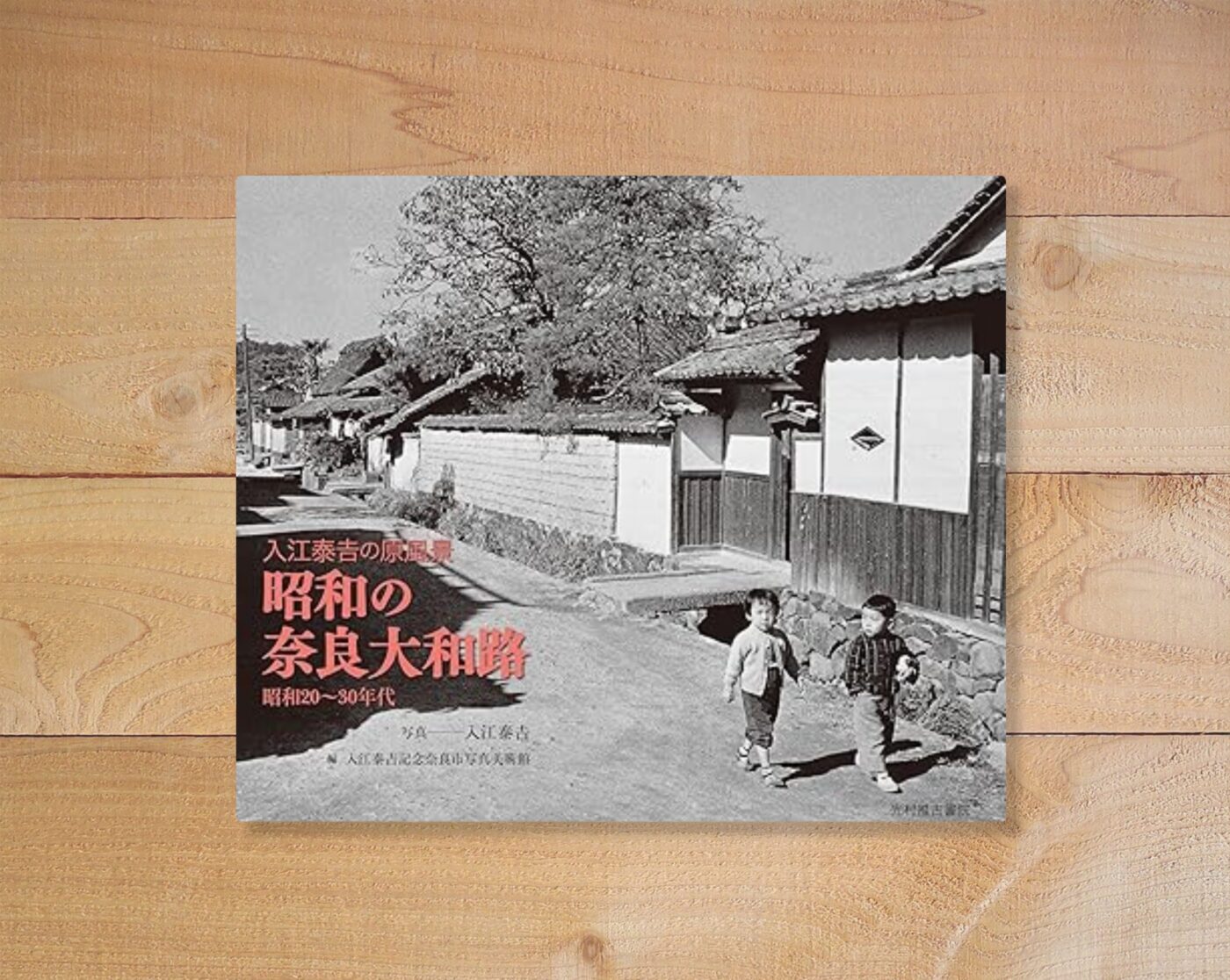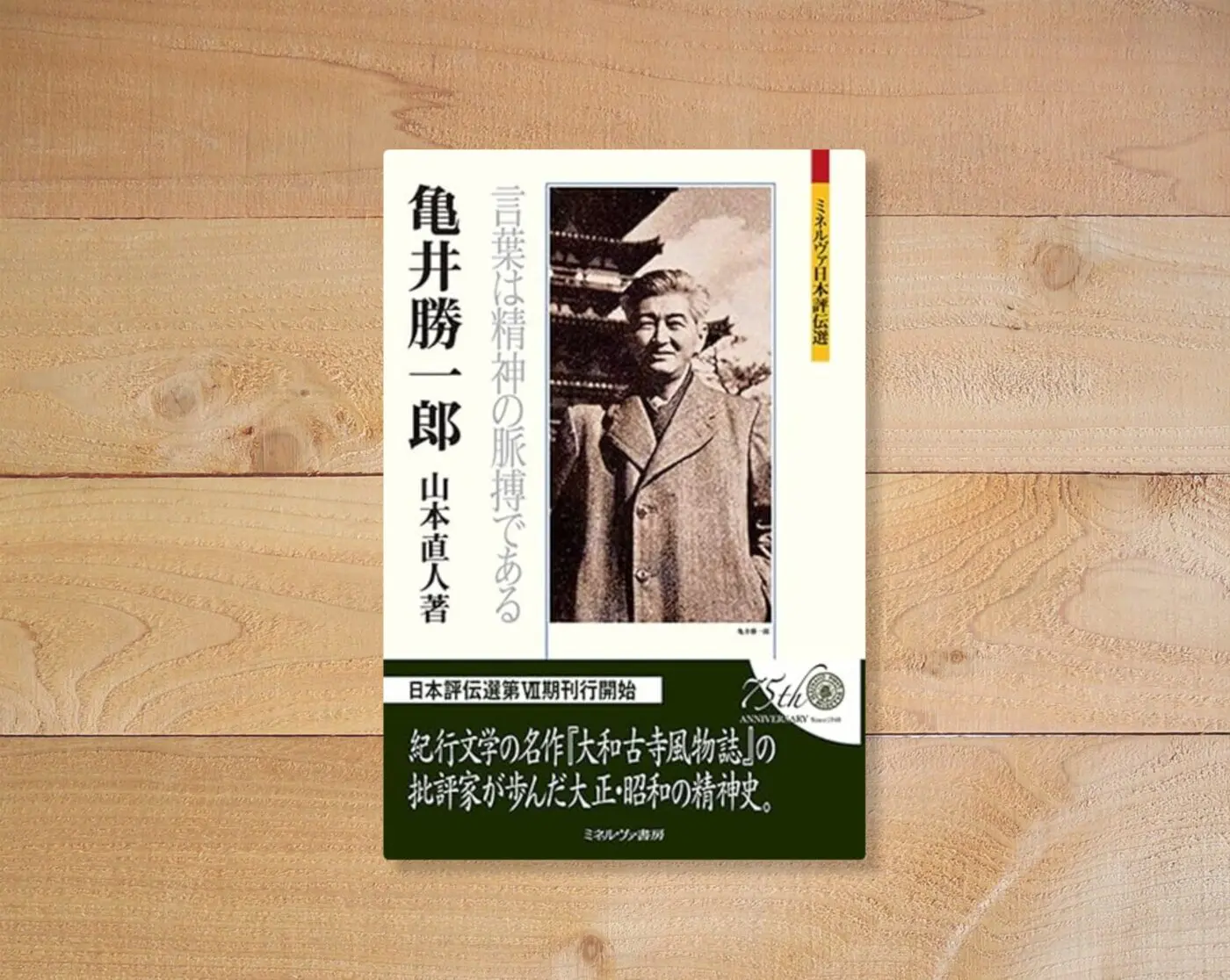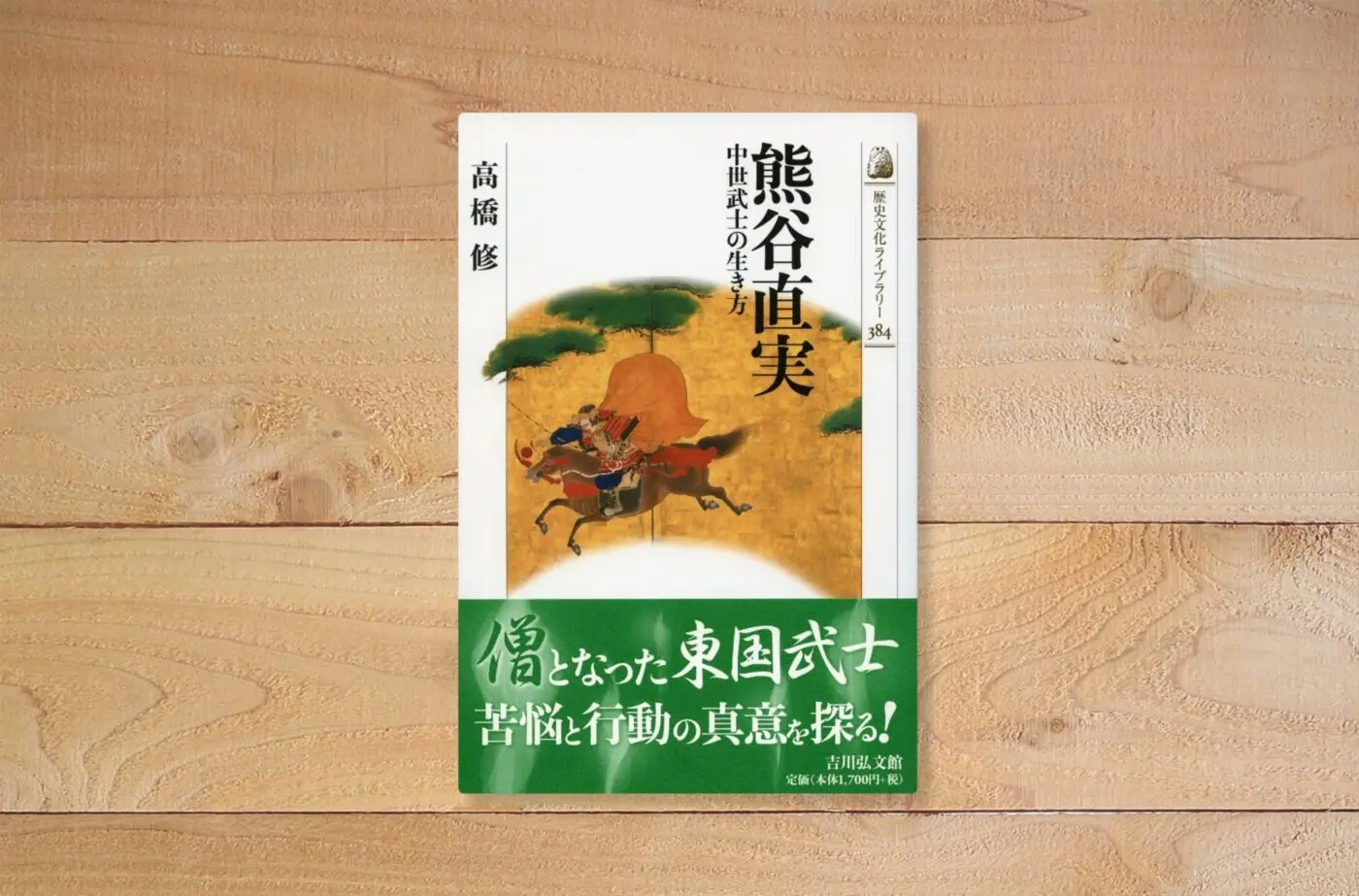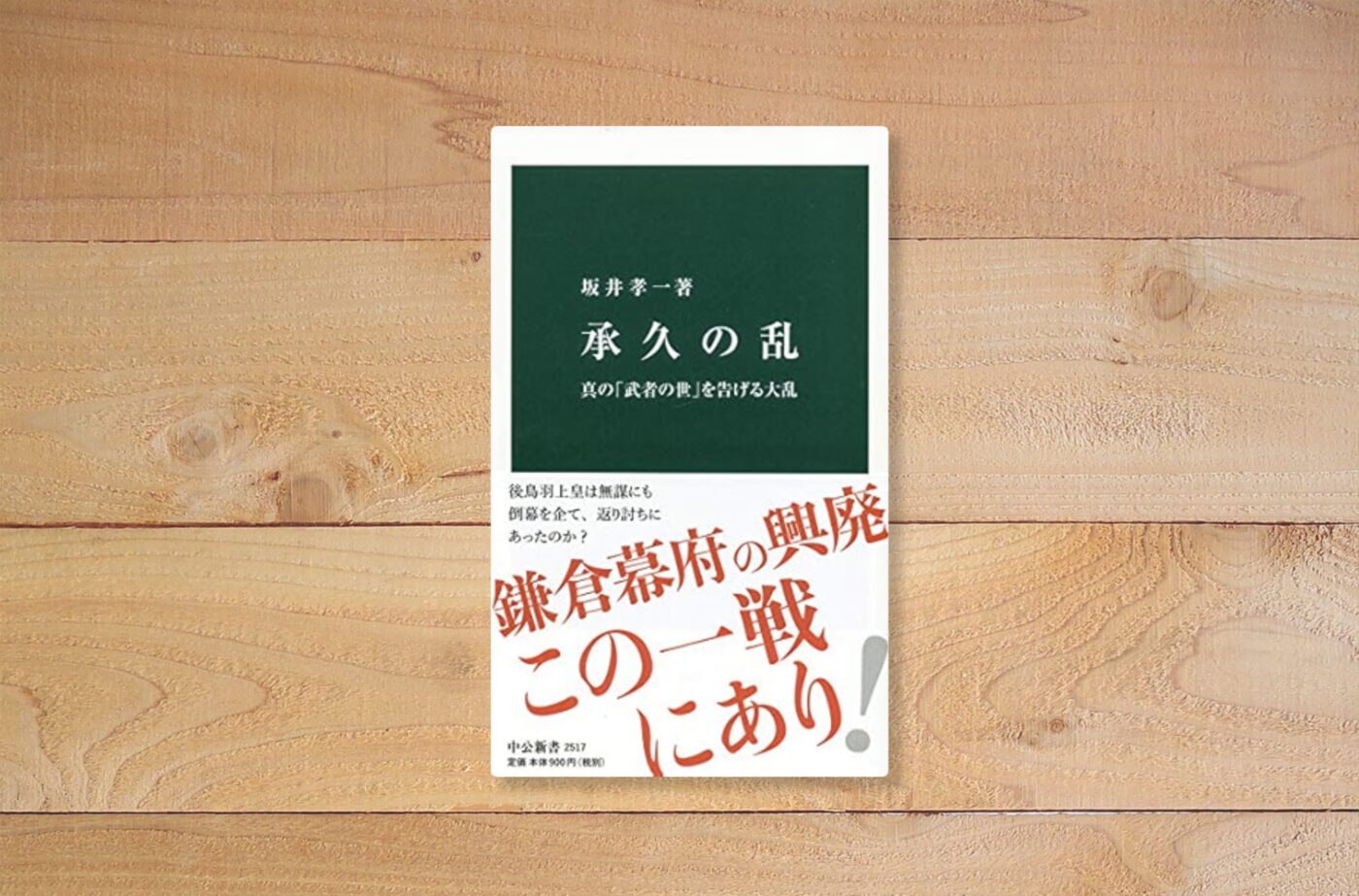碧海寿広『仏像と日本人 宗教と美の近現代』あらすじと感想~仏像は日本人にどう見られてきたのか。その歴史の流れを知るのにおすすめ!
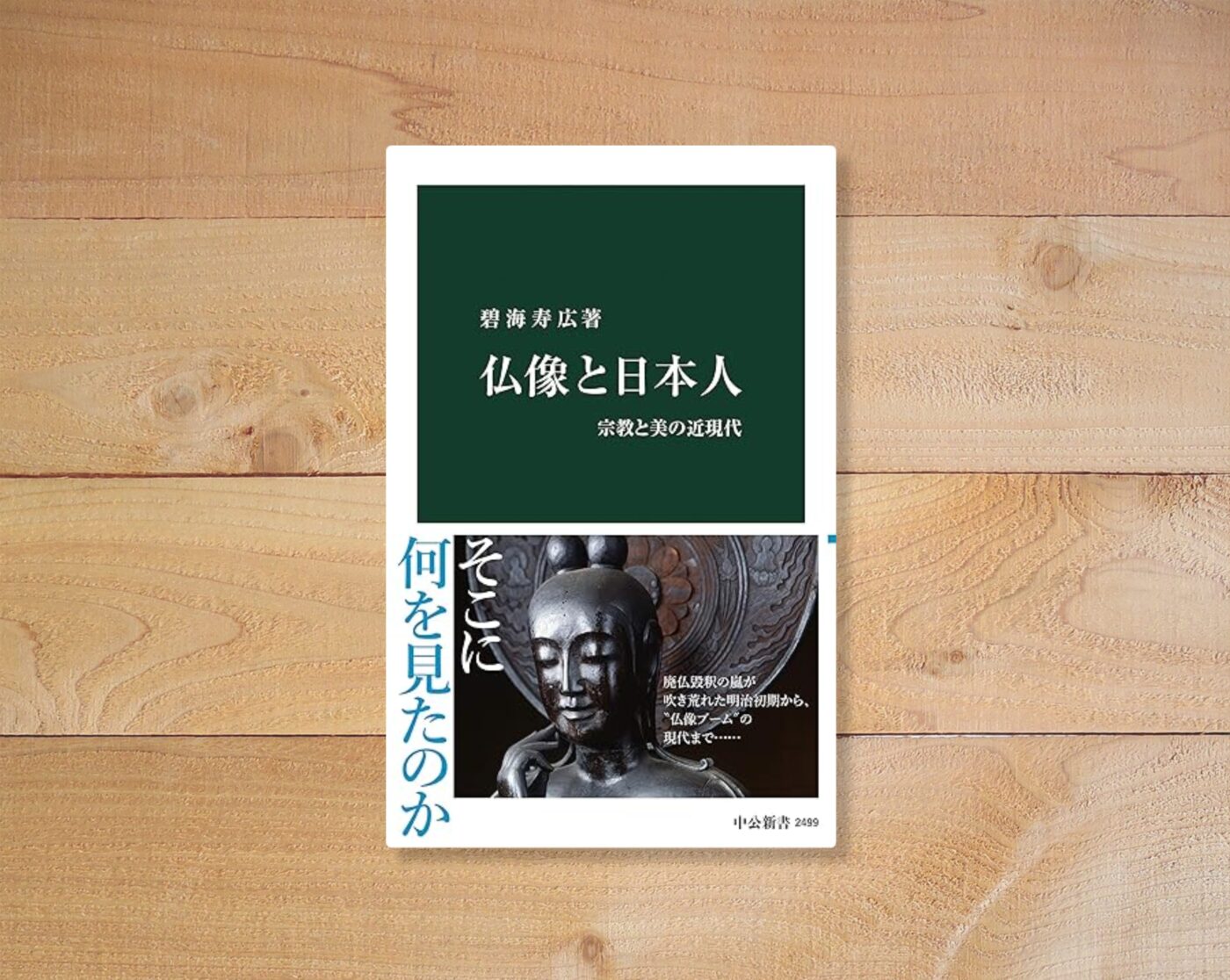
碧海寿広『仏像と日本人 宗教と美の近現代』あらすじと感想~仏像は日本人にどう見られてきたのか。その歴史の流れを知るのにおすすめ!
今回ご紹介するのは2018年に中央公論新社より発行された碧海寿広著『仏像と日本人 宗教と美の近現代』です。
早速この本について見ていきましょう。
仏像鑑賞が始まったのは、実は近代以降である。明治初期に吹き荒れた廃仏毀釈の嵐、すべてに軍が優先された戦時下、レジャーに沸く高度経済成長期から、“仏像ブーム”の現代まで、人々はさまざまな思いで仏像と向き合ってきた。本書では、岡倉天心、和辻哲郎、土門拳、白洲正子、みうらじゅんなど各時代の、“知識人”を通して、日本人の感性の変化をたどる。劇的に変わった日本の宗教と美のあり方が明らかに。
Amazon商品紹介ページより
「日本人にとって仏像とは一体何なのか」
本書はこのストレートな疑問に答えてくれるおすすめの参考書です。
私がこの本を手に取ったのは前回の記事で紹介した亀井勝一郎著『大和古寺風物詩』がきっかけでした。
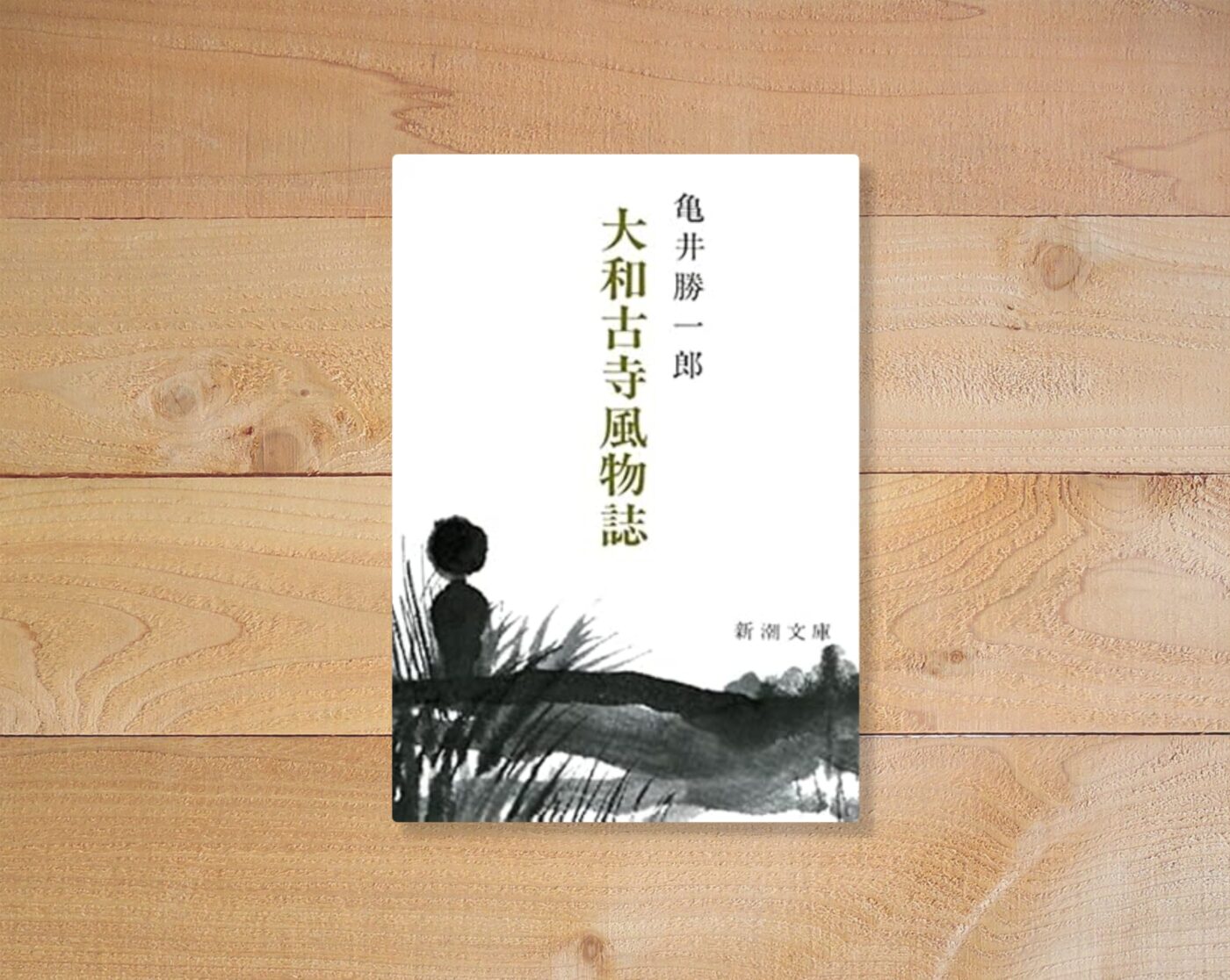
亀井勝一郎はその本の中で「仏像は芸術鑑賞か信仰の対象か」という問題を提起しました。亀井は「教養的な芸術鑑賞」のために仏像を見るべきではないとこの本で述べます。仏像は信仰の対象であり、そうした信仰から切り離して芸術作品としてのみ取り扱おうとするあり方は間違っているのではないかと述べるのです。
この指摘は私の中に強烈なインパクトを残しました。
亀井がその本を書いたのは1943年のことです。この頃にはすでに仏像が教養の対象として博物館に展示されるという現象がすでに一般化されていたようです。そしてその風潮に大きな影響を与えたのが岡倉天心とフェノロサ、そして『古寺巡礼』で有名な和辻哲郎だったのでした。
仏像におけるこうした時代の流れについてもっと知る方法はないだろうか。何かよい本はないだろうか。そう思っていた矢先に出会ったのが本書『仏像と日本人』だったのでありました。
そしてまえがきや目次を見た段階ですでに私はガッツポーズです。本書はまさに私の求めるものが完璧に網羅されていたのです。
せっかくですので本書のまえがきを読んでいきましょう。この本の雰囲気や主題を感じるのにうってつけの文章です。
仏像は日本の至るところに存在する。たとえば路傍の石仏だ。全国津々浦々、道を歩く途半で地蔵などに出会う。しばしば、花が供えられていたりもする。仏像に、誰かが何かを祈っているのだろう。どこにでもある風景だ。
一方、博物館や美術館にも仏像はよく展示されている。奈良時代や鎌倉時代の仏像の前で、人びとはそれらの歴史的な位置づけを学び、あるいは造形上の魅力を語り合う。顔がとても美しいとか、写実的な表現だとか、いろいろと語り合う。こちらも、よくある光景だろう。
日本の仏像をめぐる、ありきたりの風景と光景。だが、この二つには、決定的な背景の違いが存在する。前者は、仏教が古代の日本に伝来してから後、広く見られるようになった風景である。それに対し、後者は明治以降とりわけ戦後になり、ようやく普及した光景である。つまり両者のあいだには、近代にもたらされた歴史的な断絶があるのだ。
その断絶をつくった最大の要因が、美術という考え方である。近代以降、西洋的な美術鑑賞の文化が日本に輸入され、やがて、仏像もまた美術品ととらえる風習が形成される。その結果仏像を信仰対象として拝むのではなく、美術品として鑑賞し語る人びとが増えた。本書が詳しく論じるのは、こうした仏像をめぐる近代以降の変化である。
もっとも、近代以降の変化によって、仏像が宗教や信仰の世界から美術の領域へと、一挙に連れて行かれたわけでは、もちろんない。仏像を信仰対象として拝む人は、いまもたくさんいる。のみならず、仏像を美術品として鑑賞しながら、なおも宗教性をともなう経験をする人びとも出現してきた。本書は、こうして美術と宗教のあいだで揺れ動く、近現代の日本人の心模様を追跡する。そして、そこに見出される、新しい宗教性の諸相を明らかにしていきたい。(中略)
仏像鑑賞は現代日本で、それなりにポピュラーな文化である。その文化が普及するまでには、仏像をめぐる多くの日本人の意欲的な行動があった。彼らは何を思い、何を感じ、そして何を信じながら、その文化の形成に携わってきたのか。著者とともに探究し、そこで得られた知見を、今後の私たちが仏像あるいは美や宗教と、どのような関係を結んでいくのかを考える際、役立ててもらえれば幸いである。
中央公論新社、碧海寿広『仏像と日本人 宗教と美の近現代』Pⅰーⅴ
この本ではまず明治の廃仏毀釈に入る前の前近代、特に江戸時代の寺院事情が語られます。この江戸時代の段階ですでに仏像と民衆の関係性が変化していました。今も行われている秘仏の特別公開や聖地巡礼の先駆けはすでにこの時代に始まっていたのです。さらに厳しい政治情勢の中で寺院それぞれが生き抜くために様々な方策を練っていたのが江戸時代だったという驚きの事実が語られます。檀家制度で守られていたどころか江戸時代の寺院は幕府からの支援も削減され、経済的に厳しい状況にあったというのが実情だったようです。
そして廃仏毀釈の嵐の中で岡倉天心とフェノロサの登場で仏像を巡る空気が変わってきます。廃仏毀釈によって悲惨な目に遭っていた仏像や寺院が文化遺産として認識されるようになっていきます。
そこからさらに和辻哲郎や亀井勝一郎など、文学者の影響も詳しく見ていくことになります。私としてはこの辺りが一番興味関心あるポイントでしたので、この本の解説は非常にありがたいものがありました。時代背景をしっかり追いながら大きな視点で日本人の仏像受容の歴史を見ていくことができます。
そして本書では現代にまで至るその後の仏像受容についても語られるので通史としても非常にわかりやすいものとなっています。「なるほど、そうして今こうなっているのか」という爽やかな読後感を得ることができます。
「日本人にとって仏像はどのような存在なのか」というのは、なかなか思いつかない疑問ですよね。仏像の存在が当たり前すぎて素通りしがちなこの問いですが、いざ自分にとってどうなのかと問われるとなかなか奥深い問いだと思います。本書はその問いを考える上で貴重な手掛かりを与えてくれる実に素晴らしい参考書です。
新書ということで手に取りやすいというのも嬉しいポイントです。
仏像に興味のある方にぜひおすすめしたい一冊です。
以上、「碧海寿広『仏像と日本人 宗教と美の近現代』あらすじと感想~仏像は日本人にどう見られてきたのか。その歴史の流れを知るのにおすすめ!」でした。
Amazon商品紹介ページはこちら
次の記事はこちら
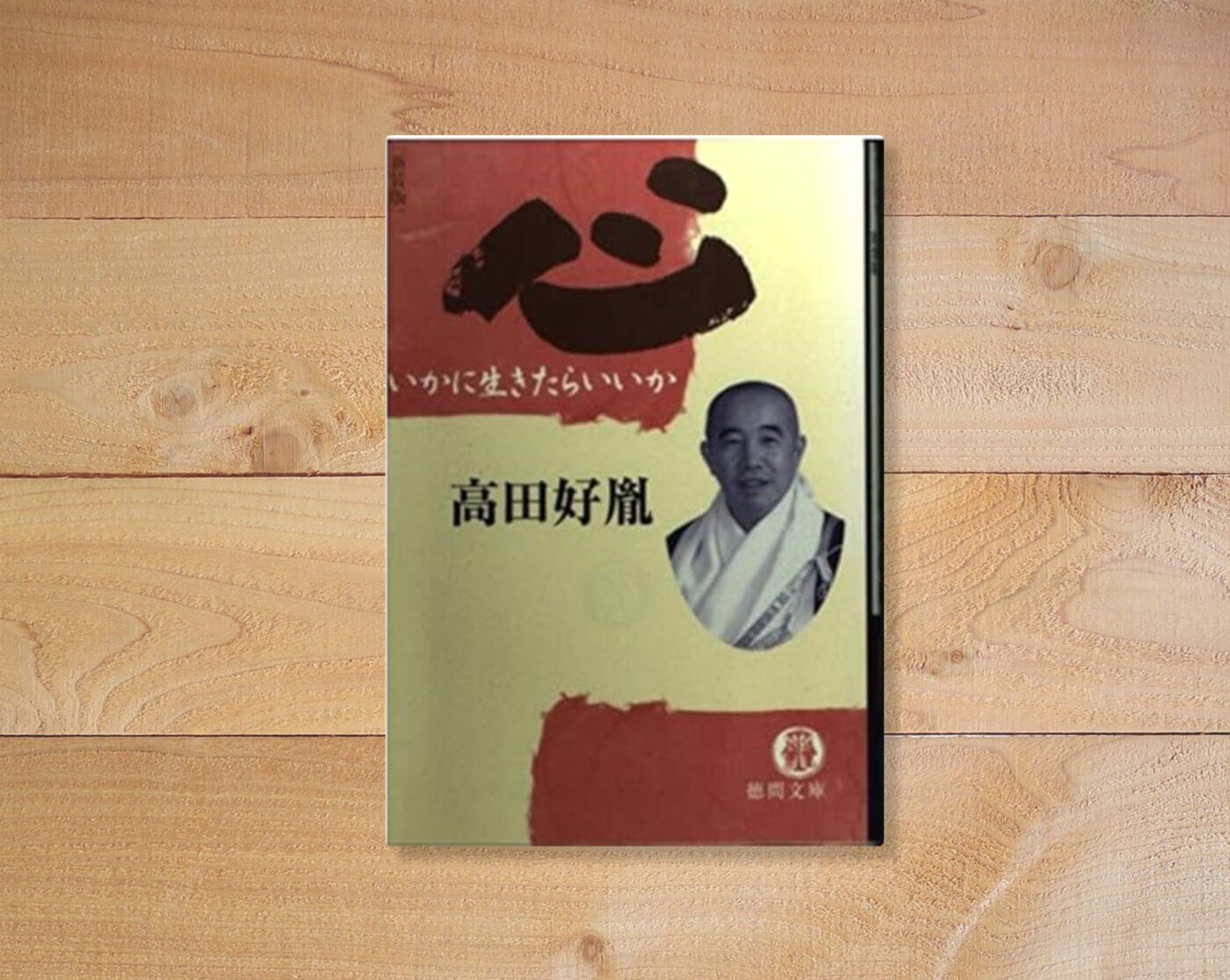
前の記事はこちら
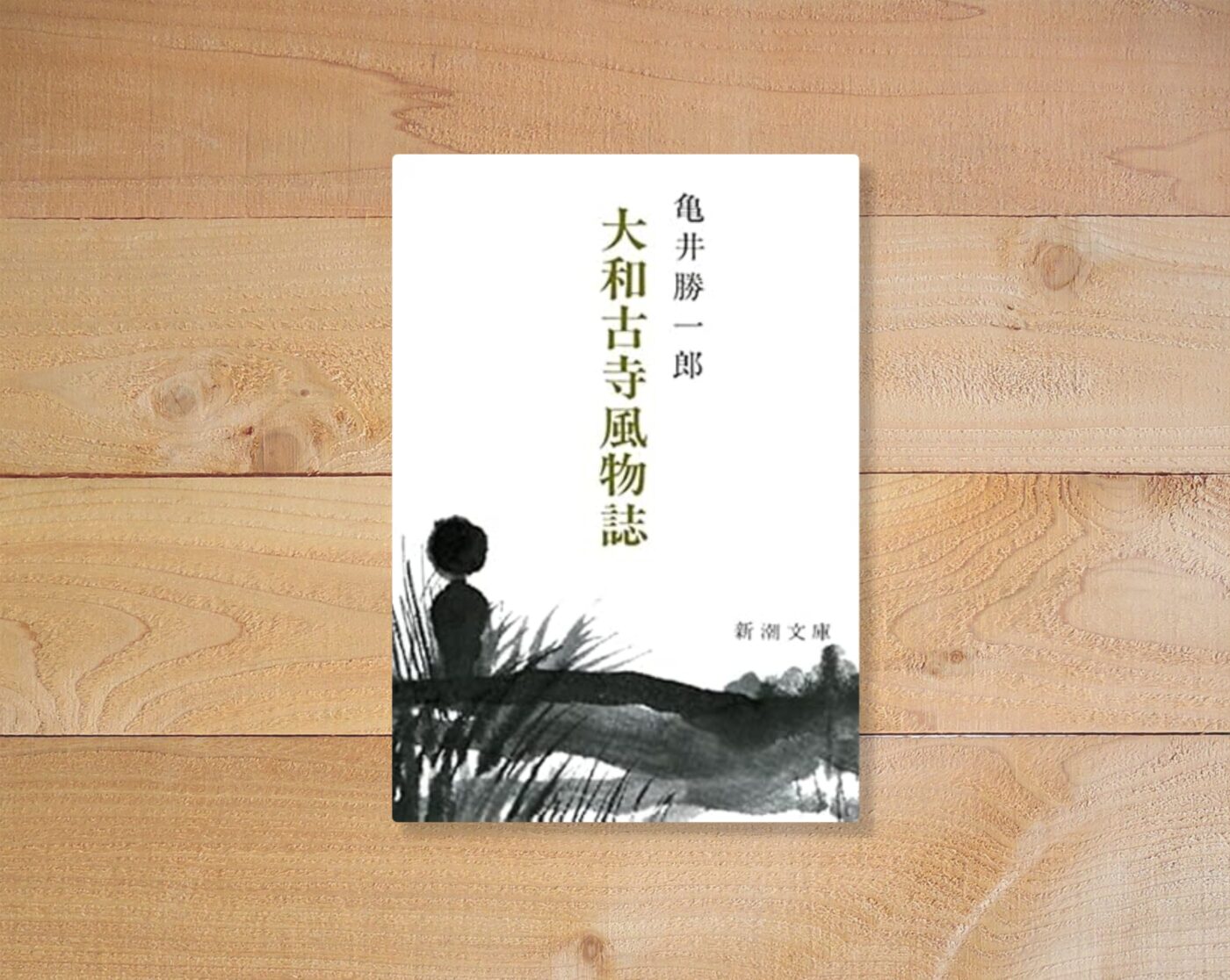
関連記事