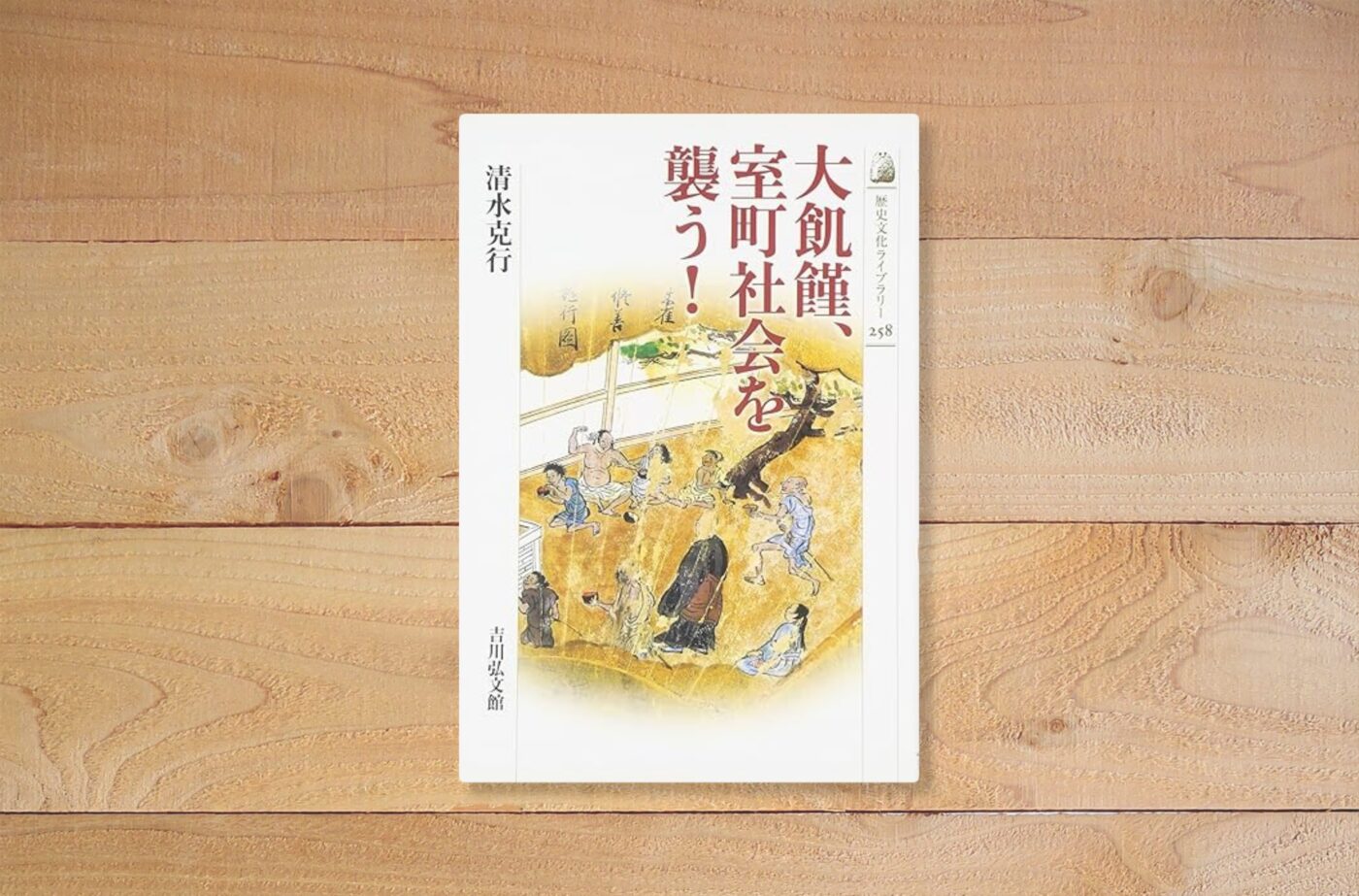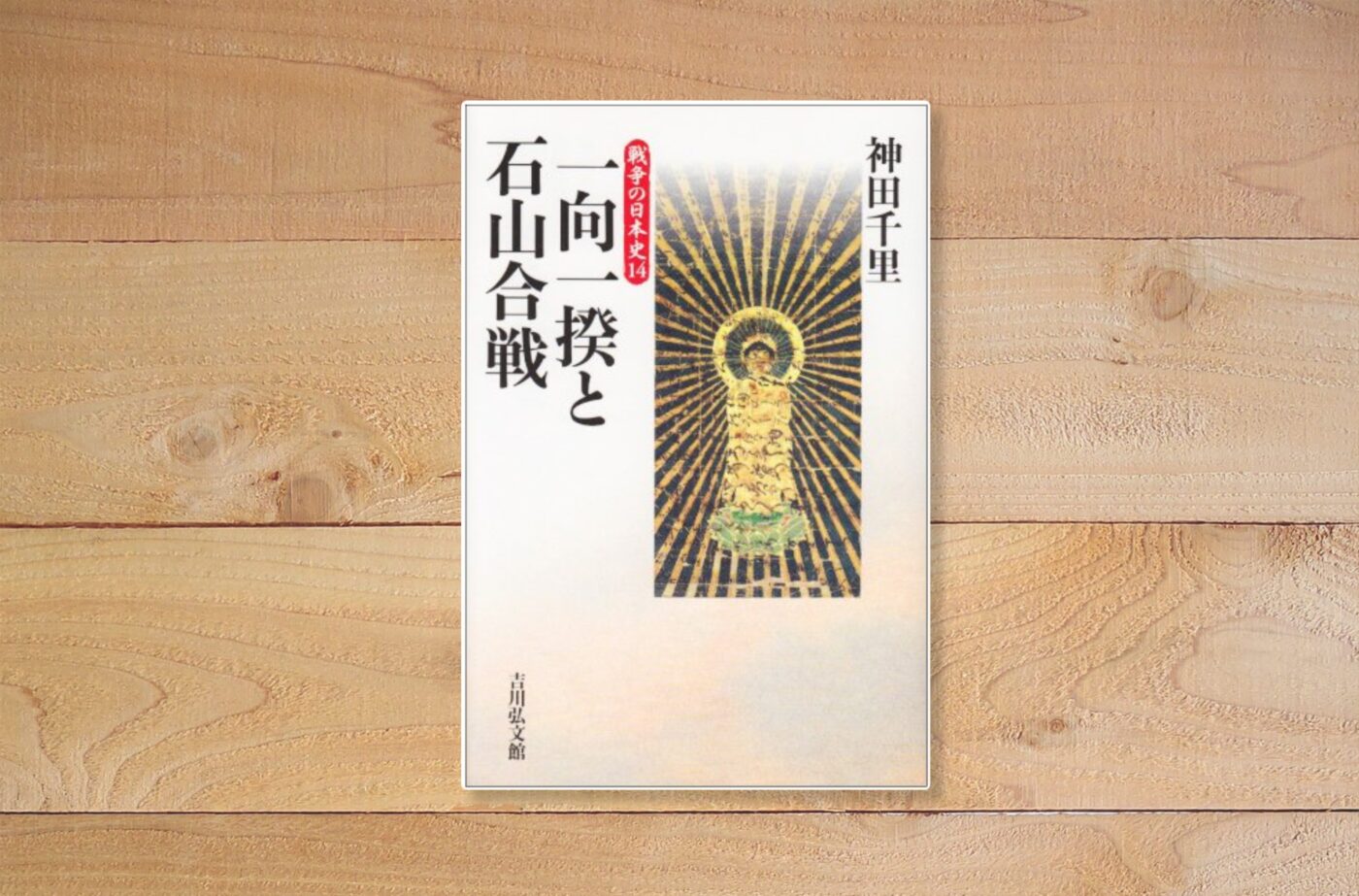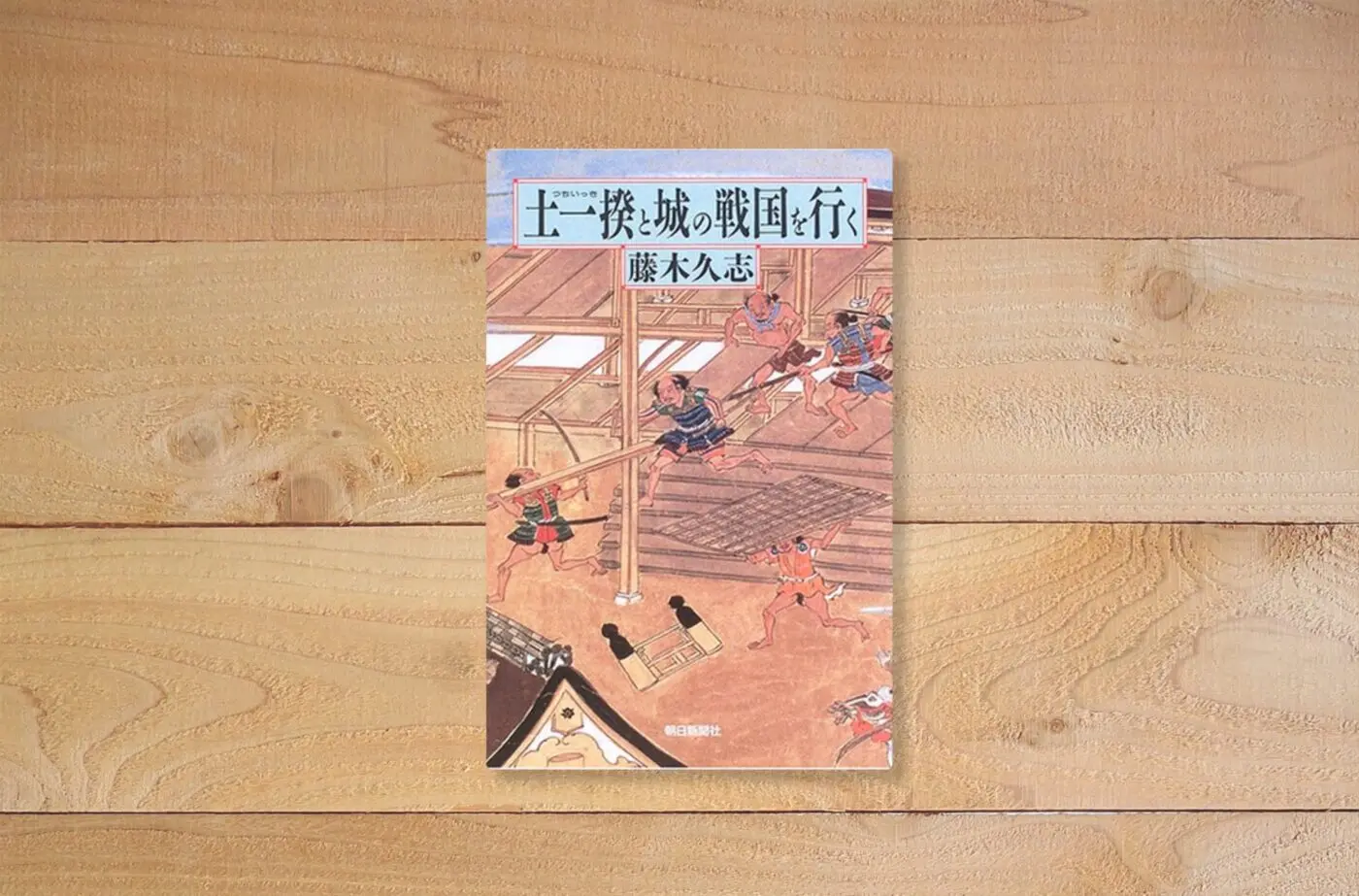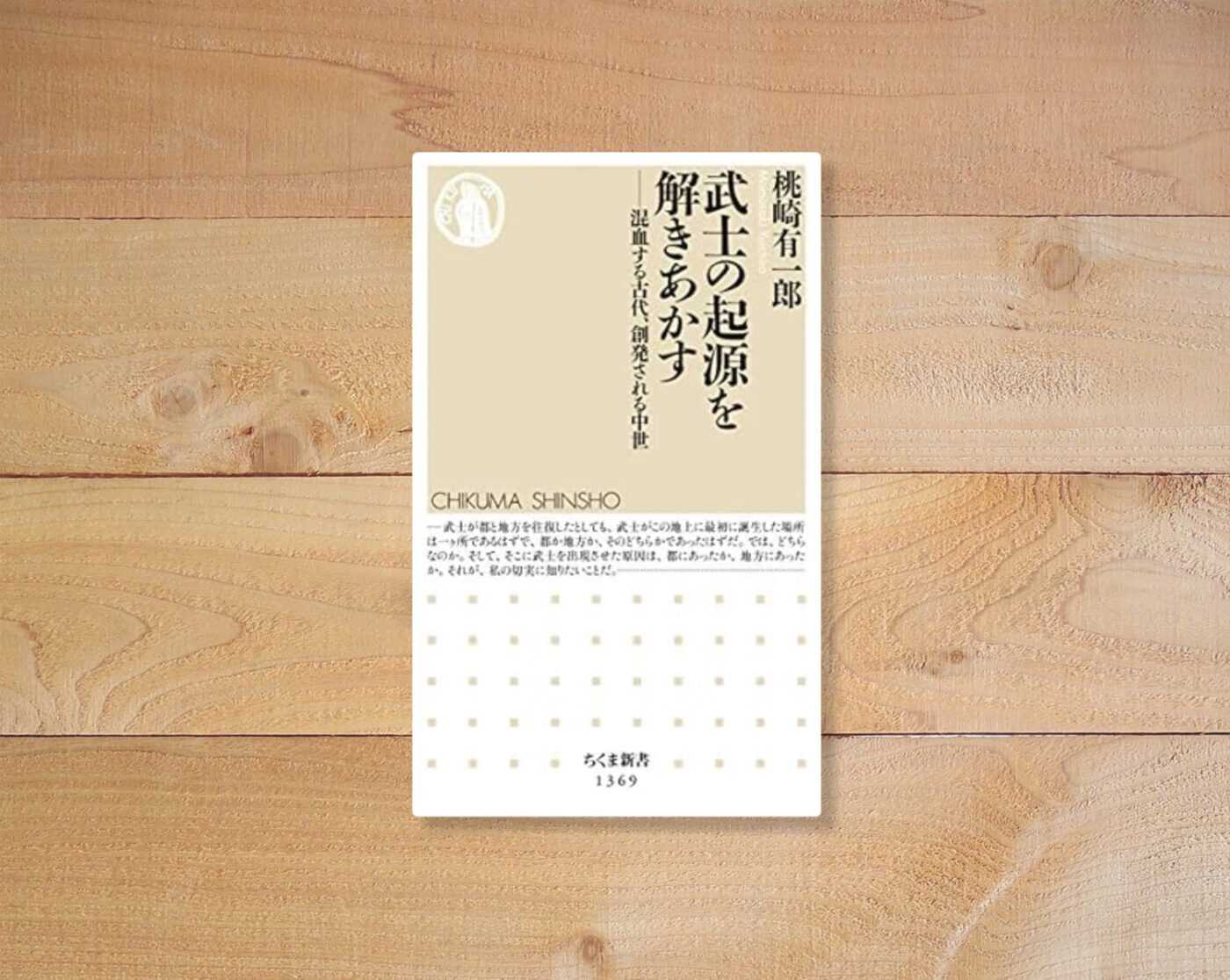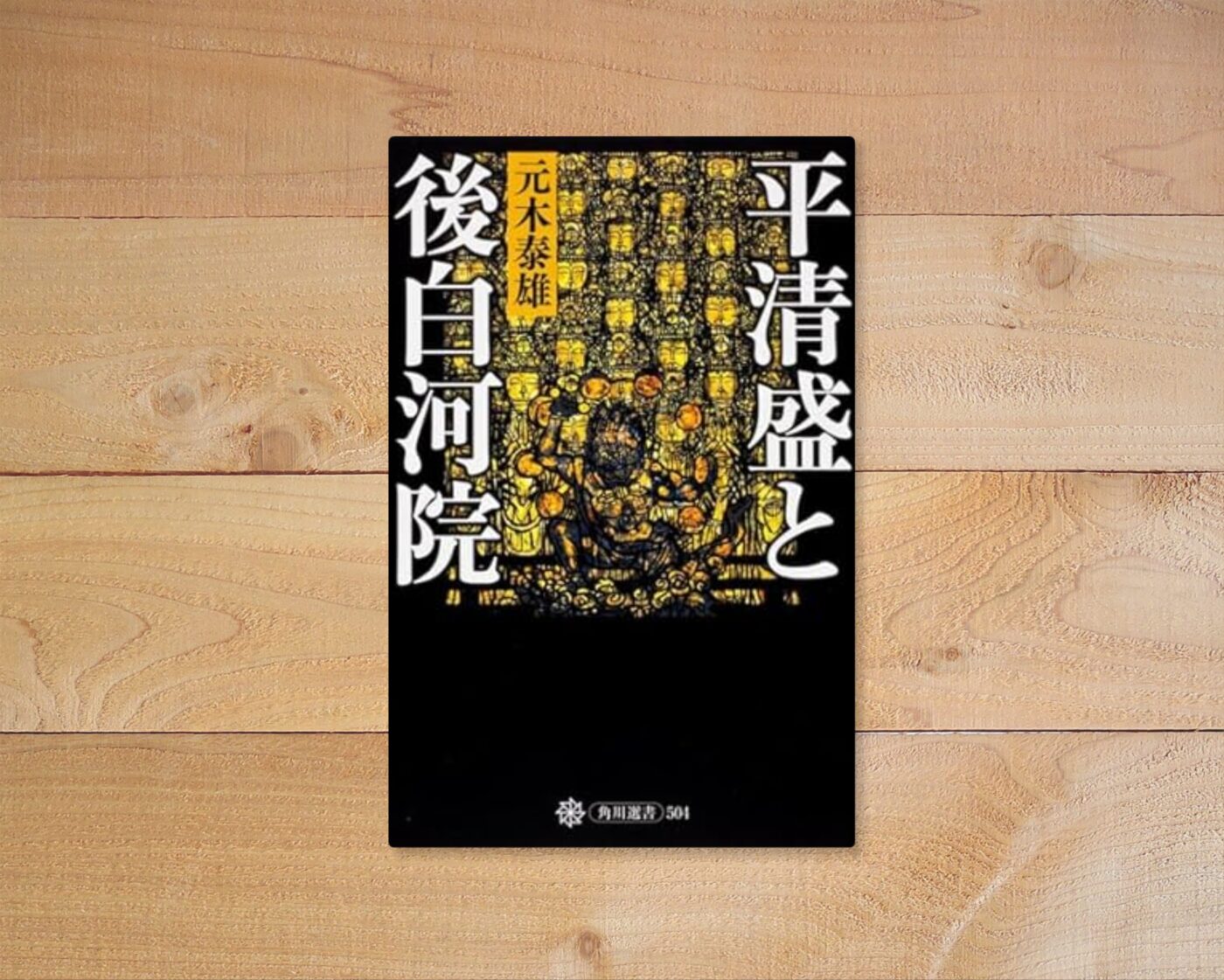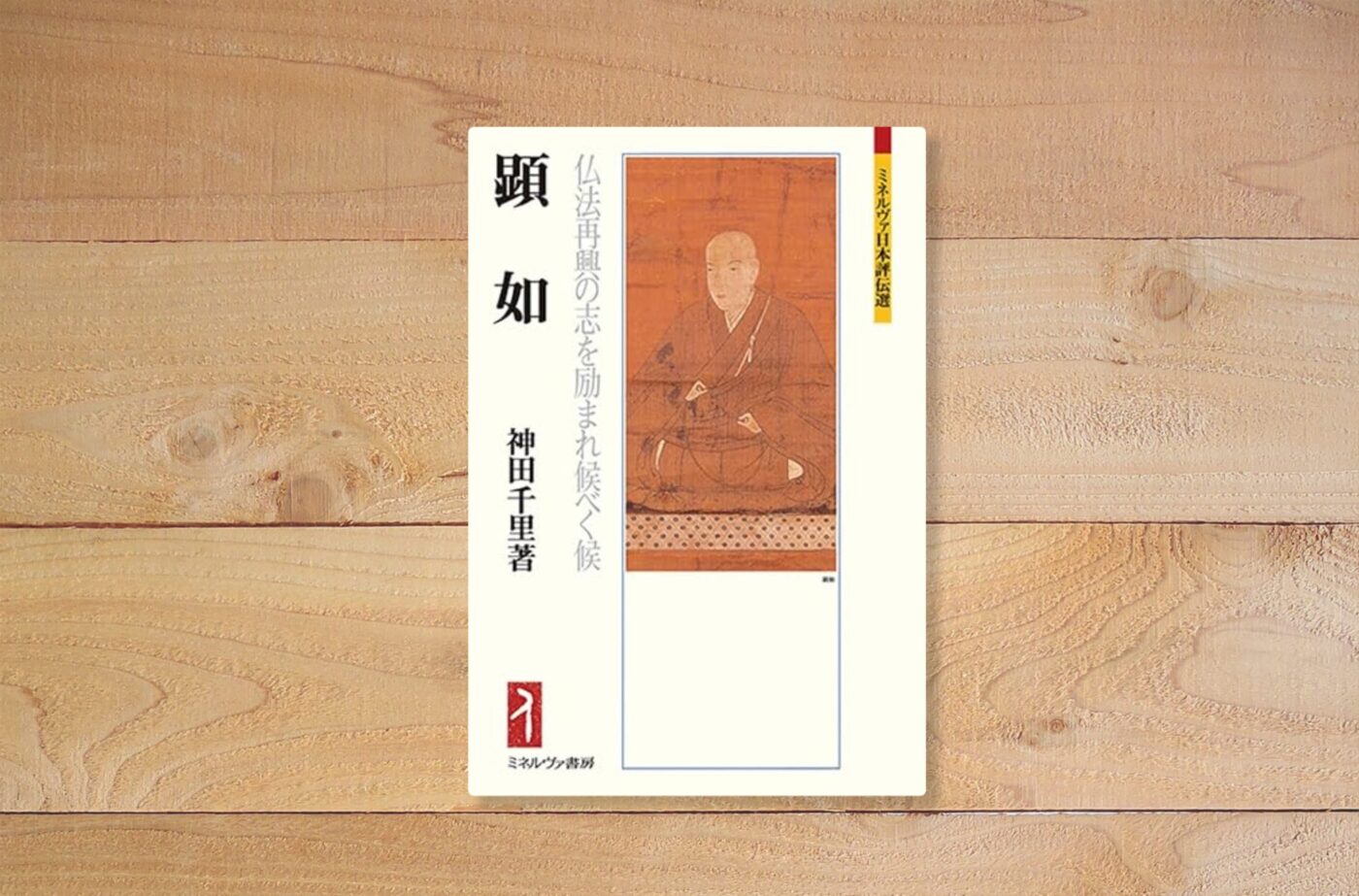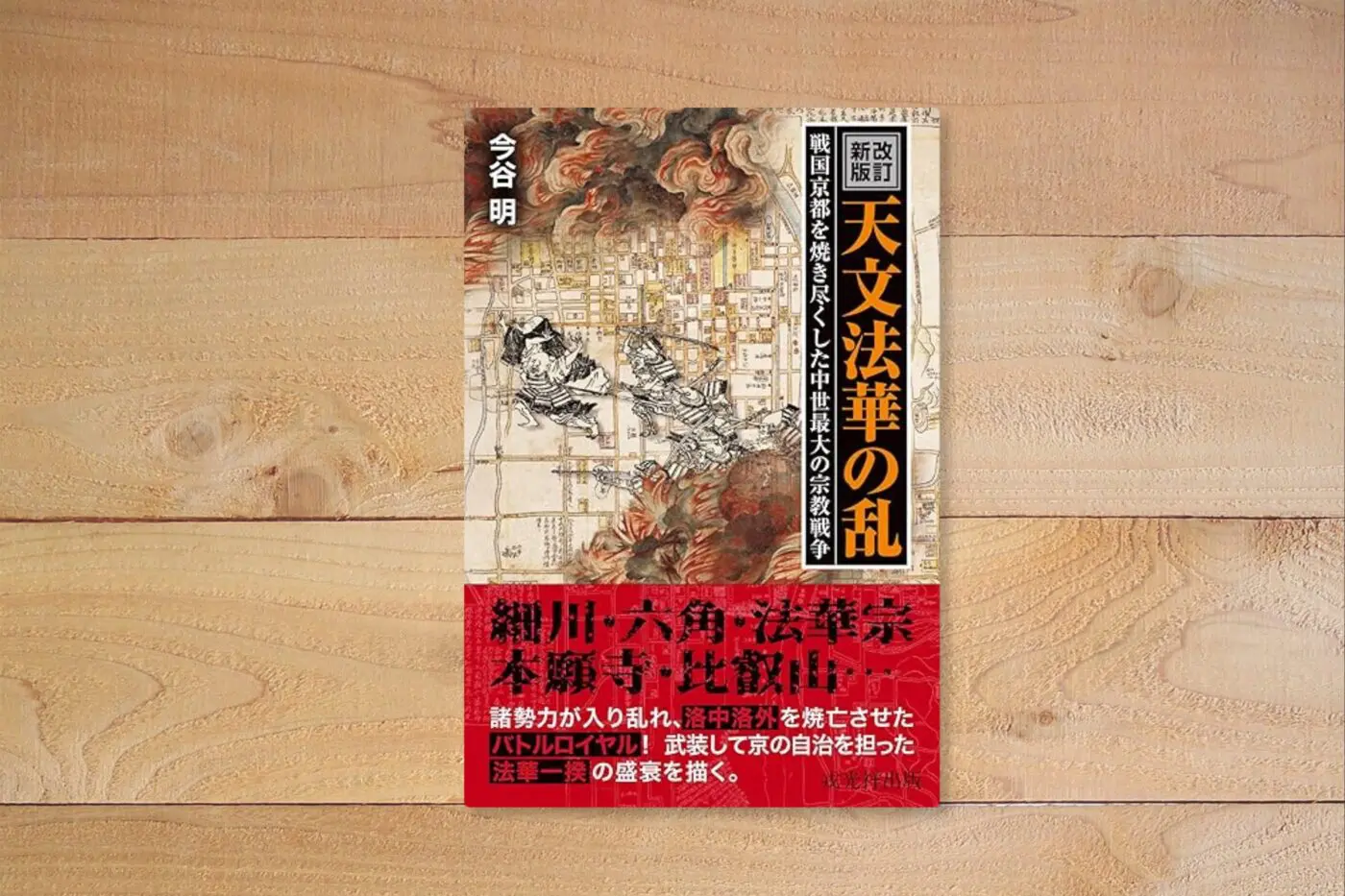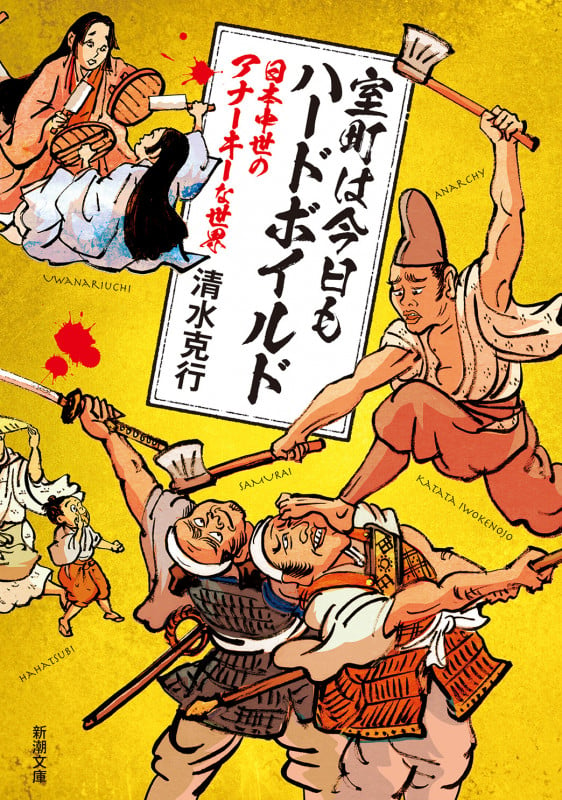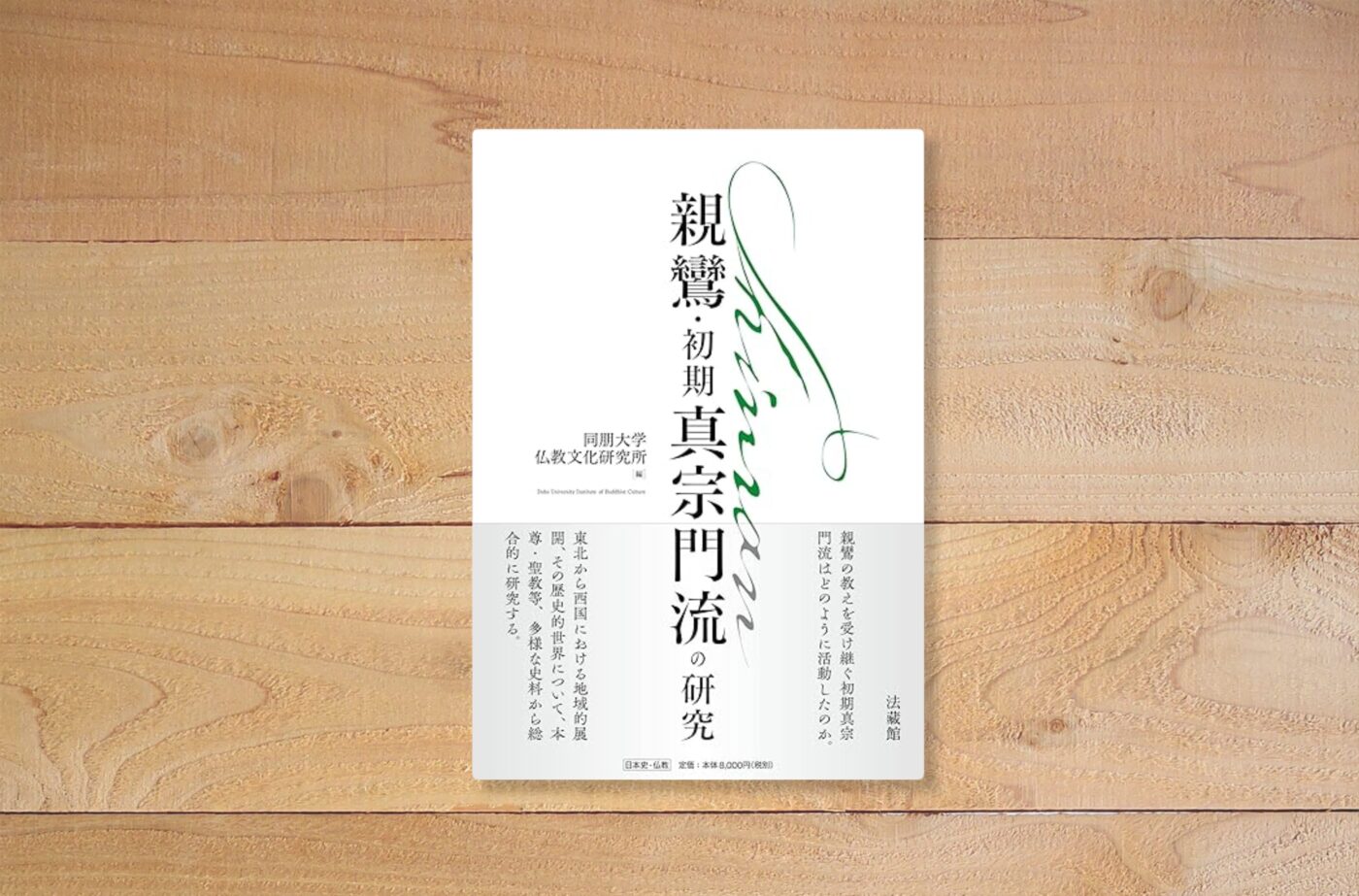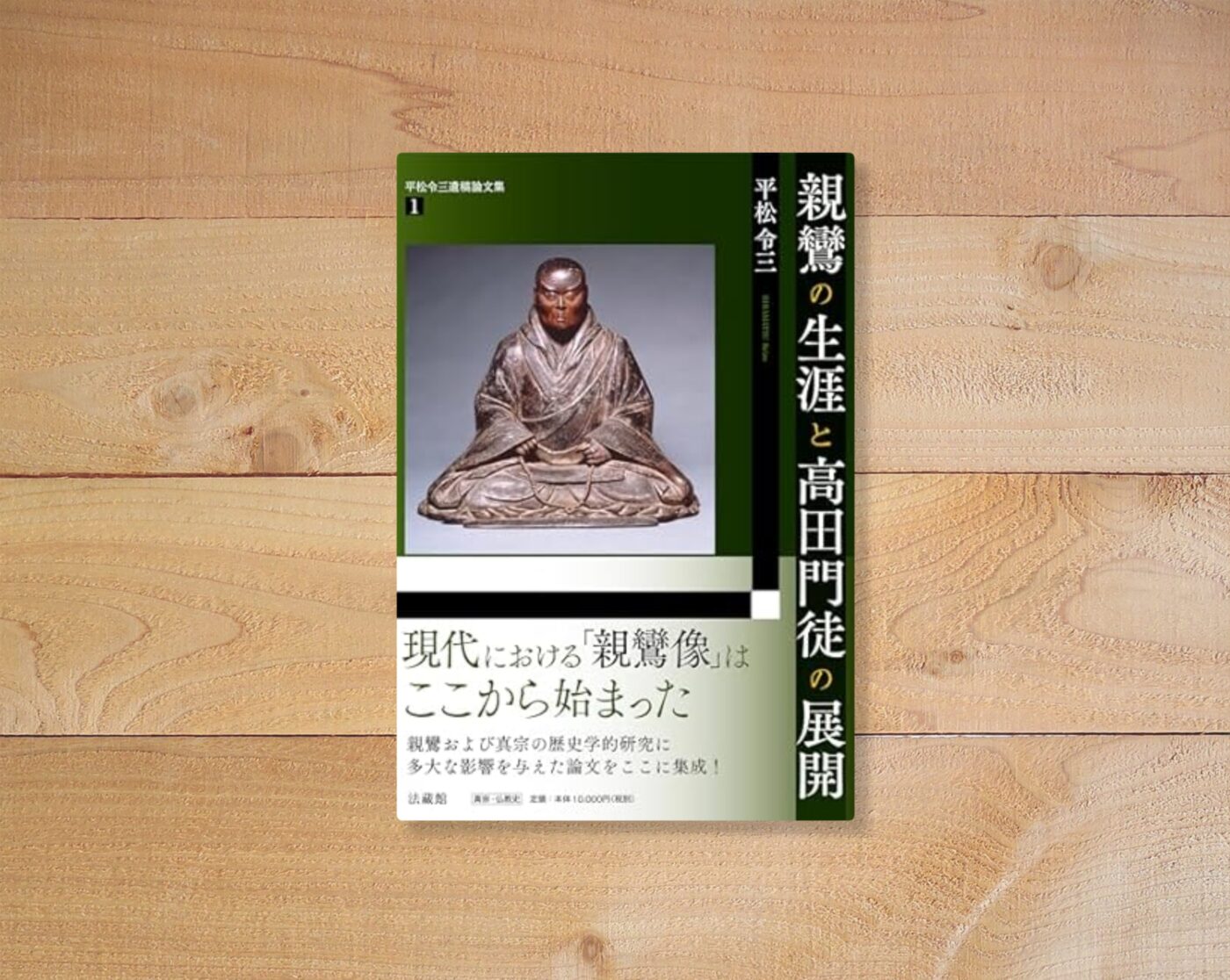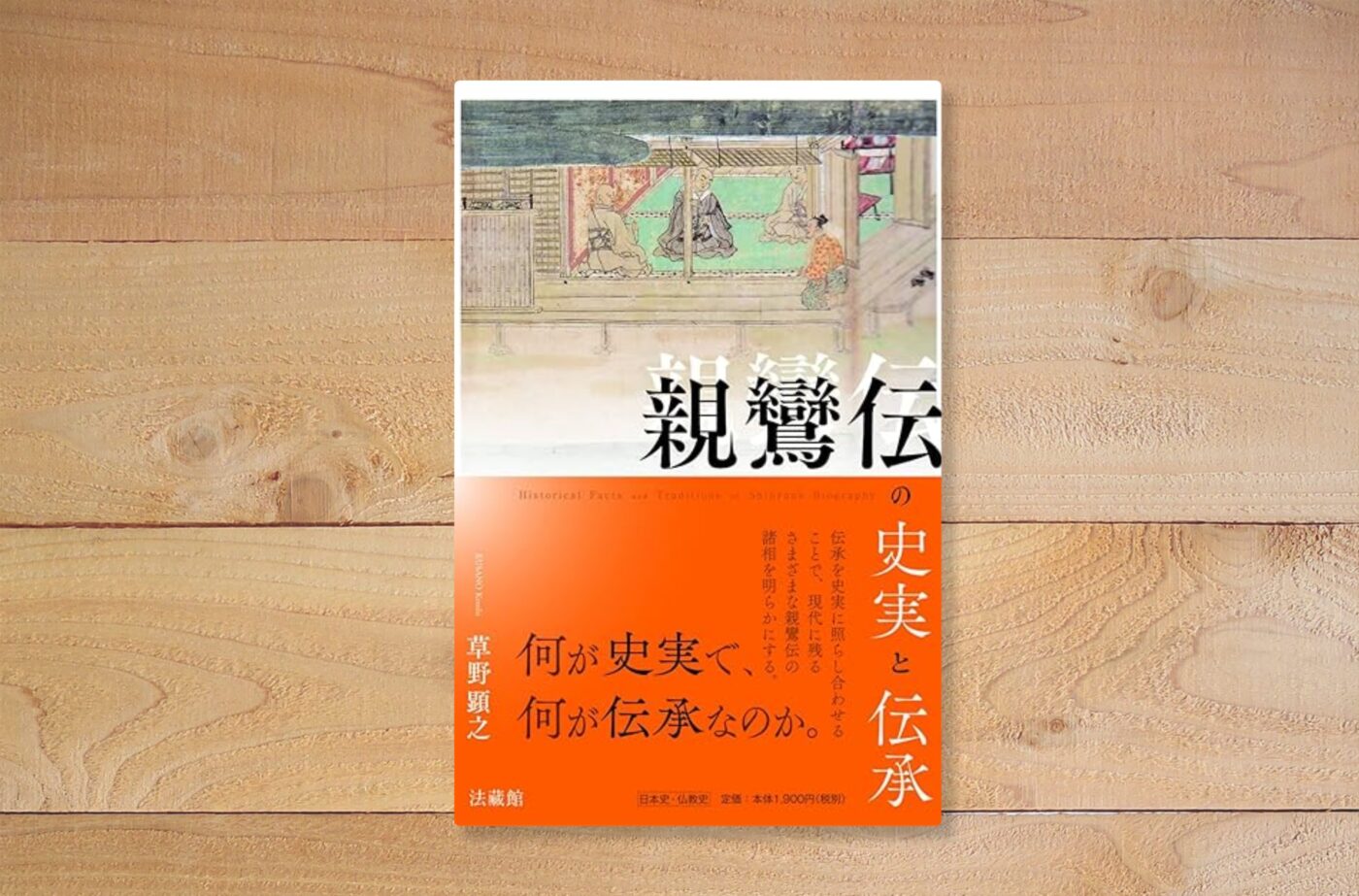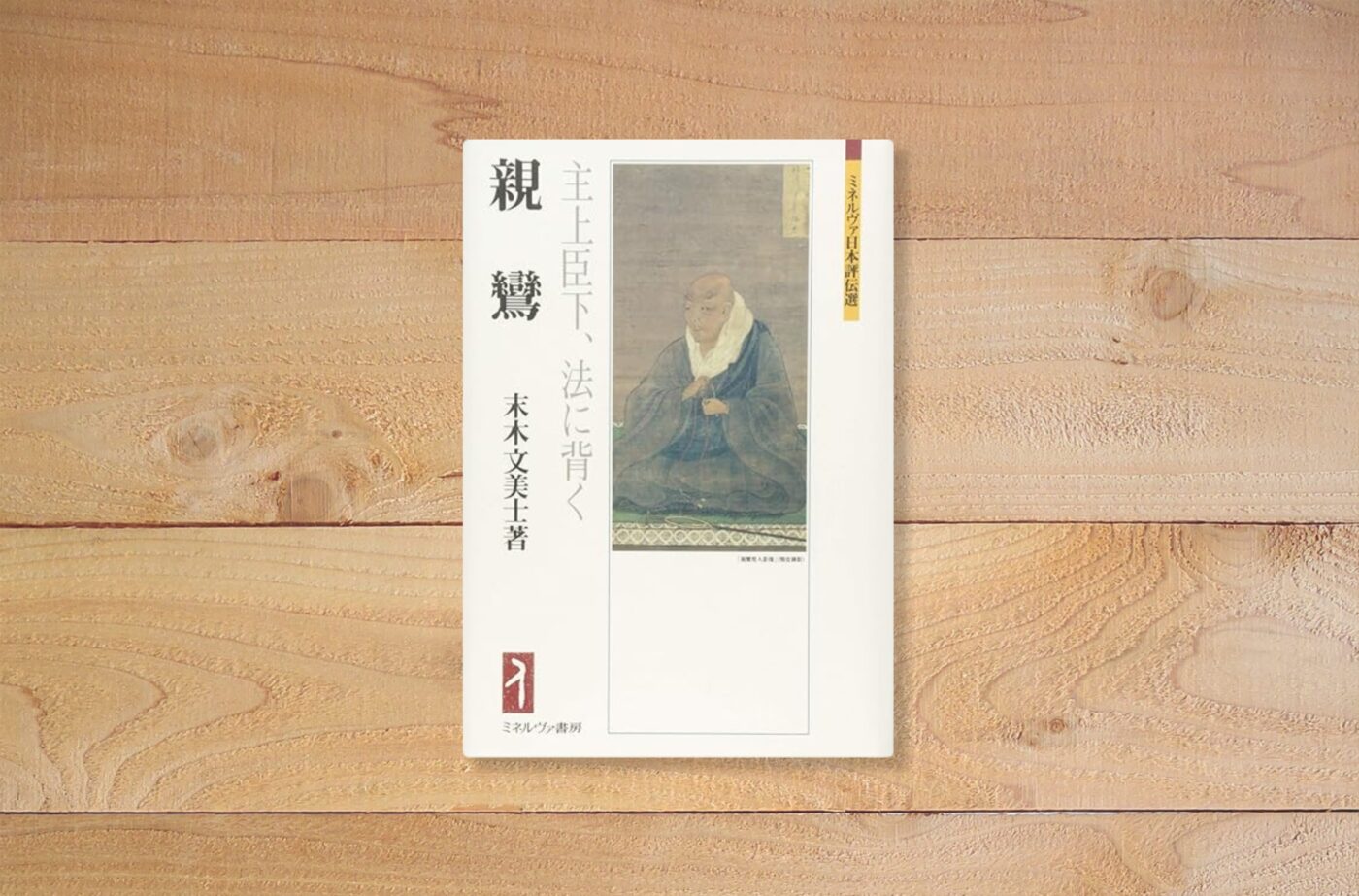清水克行『室町は今日もハードボイルド』概要と感想~私達の常識を覆す衝撃の1冊!面白すぎです!
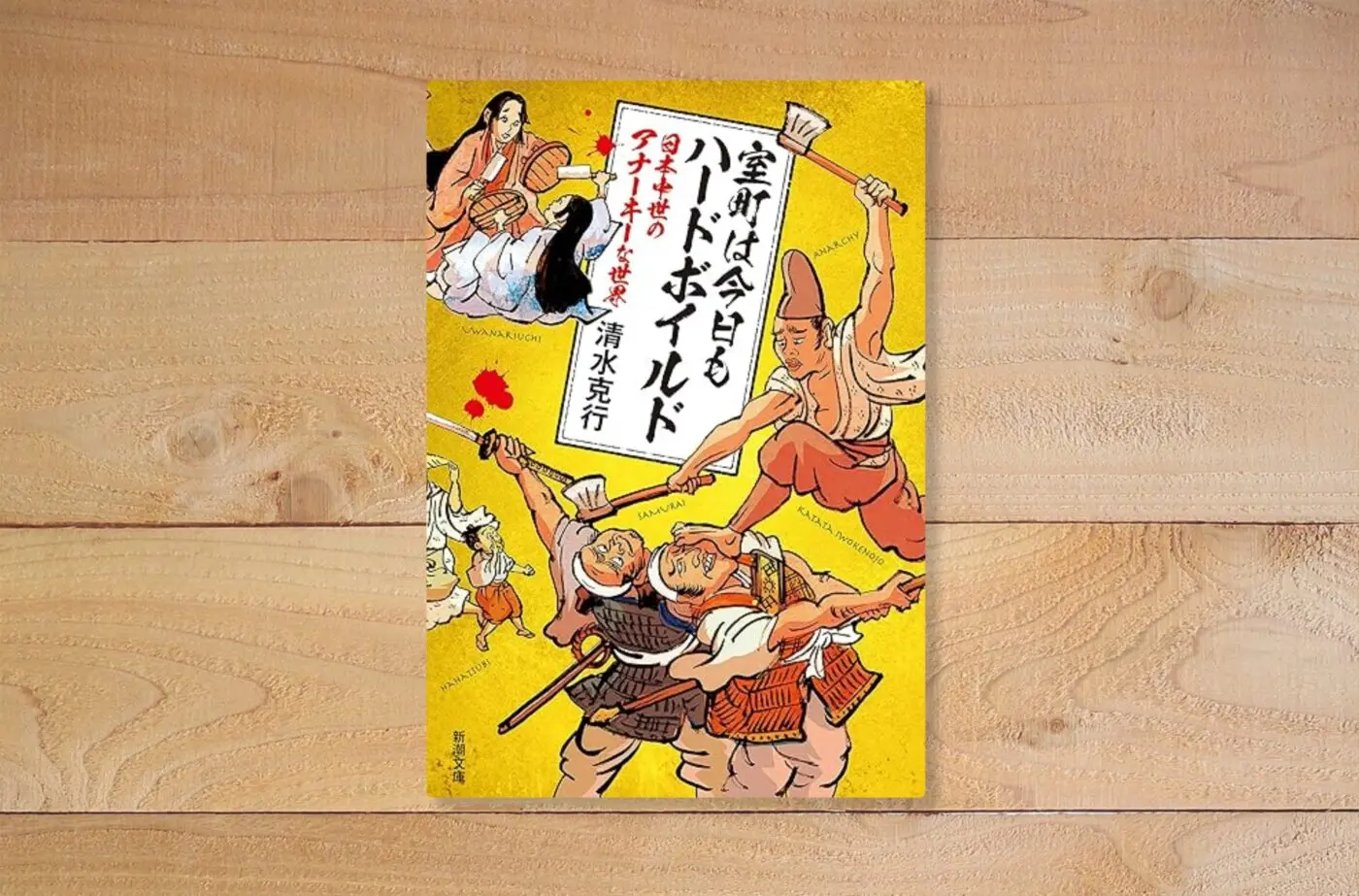
清水克行『室町は今日もハードボイルド 日本中世のアナーキーな世界』概要と感想~私達の常識を覆す衝撃の1冊!面白すぎです!
今回ご紹介するのは2024年に新潮社より発行された清水克行著『室町は今日もハードボイルド 日本中世のアナーキーな世界』です。
早速この本について見ていきましょう。
日本人は昔から温和なんて大ウソ! 盗みは即死刑、僧侶はデスノートで武士を呪い殺し、ゲス不倫には家を襲撃して破壊。暗殺、切腹、えげつない悪口……。私たちが思い描く「日本人像」を根底から覆す、荒々しく図太く、自由に生きる室町人たち。現代の倫理観とは程遠い中世という“異世界”を知り、常識に囚われがちな私たちの心を解放する! メディアで話題沸騰‼ 「室町ブーム」の火付け役による痛快・日本史エンタメ!
Amazon商品紹介ページより
この本は私達が驚くような内容が次々と語られる一冊です。
室町時代がいかにアナーキーで暴力的でハードボイルドだったか。エンタメ感の強いタイトルや表紙とは裏腹に著者は資料に基づいた学術的な内容を楽しく解説していきます。本紹介で「日本史エンタメ」と紹介されているように、本書は一般読者でも楽しく読めるように構成されています。著者の語るエピソードもくすっとしてしまうユーモアもたっぷりで非常に読みやすいです。
本書について著者は「はじめに」で次のように述べています。少し長くなりますが、この箇所を読めばすでにこの本の面白さが予感できる素晴らしい前書きですのでじっくりと読んでいきます。
二〇一五年に小中学校の「道徳」が教科に格上げされ、教科書も検定教科書が使用されるようになった。あるとき、その小学「道徳」教科書の一部を見る機会があったのだが、意外に日本史上の人物の言行が多く採り上げられていることに驚いた。
山上憶良、良寛、二宮尊徳、吉田松陰、坂本龍馬、野口英世、杉原千畝、などなど。
はたしてこれらの人物が「道徳」教科書に採り上げる価値のある人物かどうか、さらにいえば、そもそも「道徳」という教科が必要あるのか、という問題はあるのだが、それはひとまず措いておこう。むしろ私が面白いと思ったのは、ここで採り上げられている人物が、いずれも古代・近世・近代に活躍した人物ばかりで、私が専門とする「中世」の人物は誰一人紹介されていないということ、だった。
そこで紹介されている人物は、いずれも質実、家族愛、立身、学究、憂国など、わが国で「道徳」的と考えられている徳目に合致する逸話や発言を(それが事実であったかどうかはともかく)残している者たちである。それに対して、まことに残念ながら、私に馴染みのある中世の人びとは、おおむねそうした徳目とは無縁、もしくはそれらの希薄な者たちだったのである。教科書作成者がそれを意図的に行っているとしたら、それはそれで優れて鋭敏な配慮と思わざるをえない。たしかに中世を生きた人びとのなかには「道徳」的な人物は少ない。というよりも、むしろ、そうした私たちの既存の「常識」や「道徳」の埒外にあることが、中世人の最大の特徴であり魅力なのである。
本書で扱う日本の「中世」とよばれる時代は、一般的には平安時代後期(院政期、一一世紀後半)から始まって、鎌倉・南北朝・室町時代を経て、戦国時代の終わり(一六世紀中頃)まで、をさす。それぞれ、平清盛の政権や鎌倉幕府、室町幕府、戦国大名など、武士権力が大きな力をもった時代である。だから、この時期を「武士の時代」とイメージする人も多いだろう。しかし、現実には、この時期には武士だけではなく、天皇や公家、僧侶や神職たちも同じく支配階層として君臨していた。
東国に鎌倉幕府がある一方で、西国には天皇を戴く公家政権が存在し、地方社会は彼らが支配する荘園によって分節化されていた。また、中世の終わりには、各地に戦国大名が割拠して、それぞれの支配地域を独立国として支配していたことは、ご承知のとおりである。そのうえ、庶民たちは「村」や「町」を拠点にして、独自の活動を展開していた。そこでは幕府法、公家法、本所法(荘園内の法)、村法など、独自の法秩序があり、幕府法が村法より優位ということは必ずしもなく、それぞれ等価に併存していた。それを考えるなら、中世は、日本の歴史のなかでも前後に類がないほどに〝分権〟や〝分散〟が進行したアナーキー(無秩序)な時代だったといえるだろう。
さらにいえば、彼らは、自分の利益を守るために「自力」で暴力を行使することを、必ずしも〝悪〟とは考えていなかった。やられたらやり返す。場合によっては、やられてなくてもやり返す。しかも、そうした衝動の発露を美徳とするようなメンタリティーを、彼らは持ち合わせていた。それは武士だけに限ったものではなく、僧侶や農民にまで通底するものであって、彼らは常日頃から刀を身に帯びて、往来を閥歩していた。加えて、彼らは同じ仲間が蒙った損害を、みずからの痛みとして受け止め、万一、仲間が他の誰かによって傷つけられたときは、寺院や村をあげて集団で報復に乗り出す。それは、もう立派な戦闘行為という他ない。歴史教科書をみると、この時代は「〇〇の変」とか「××の乱」といった政変、戦乱が目白押しだが、それは史書に名をとどめたほんの一部の話であって、当時の社会では、現実にはそこかしこの様々な階層の間で、無数の無意味で名もない「変」や「乱」が巻き起こされていた。中世は、日本史上、最もハードボイルドな時代なのである。
そんなアナーキーでハードボイルドな価値観をもった人びとが、現代の「道徳」教科書に載せられるわけがない!「朕が新儀は未来の先例たるべし(私の違法行為が将来の新ルールとなるのだ!)」(後醍醐天皇)とか、「よき友、三つあり。一つには物くるる友、二つには医師、三つには知恵ある人(友達にすると良いのは、物をくれる人、医者、知恵のある人)」(兼好法師)、「いづれの御方たりといへども、ただ強き方へ随ひ申すべきなり(我々はどちらでも、ただ強いほうに味方するのだ!)」(和泉国熊取荘の荘民)といった彼らの「名言」が「道徳」教科書に載る日は、今後も決して訪れることはないだろう。
リーダーの主導のもと社会が統御されることもなく、異質で多様な価値観が拮抗して、先行きが見えない物騒な時代ー。しかし、それは考えようによっては、特定の「主役」や、予定調和の「筋書き」や、お説教じみた「教訓」のない、躍動的な群像劇の時代ともいえる。また、彼らがまったく非常識で、非道徳的だったかといえば、そんなことはない。彼らには彼らなりの「常識」や、彼らなりの「道徳」があって、みなそれに従って行動していた。現代に生きる私たちの「常識」や「道徳」と、彼らの信じるそれが異なるだけであって、実は両者のあいだには優劣はないのだ。それどころか、ときには彼らの側の「常識」や「道徳」のほうが、私たちが奉ずるそれよりも優れていることすらある。中世を生きた人びとの魅力は、同じ日本列島に住みながら彼らが私達の「常識」や「道徳」から最も遠いところにいる存在であるという点にあり、彼らの社会を学ぶ面白さは、そんな私たちが安住している価値観を揺るがす破壊力にあるといえるだろう。
新潮社より発行された清水克行著『室町は今日もハードボイルド 日本中世のアナーキーな世界』P3-7
いかがでしょうか。アナーキーでハードボイルドな中世世界・・・。何とも刺激的な響きですよね!
また、後半の「また、彼らがまったく非常識で、非道徳的だったかといえば、そんなことはない。彼らには彼らなりの「常識」や、彼らなりの「道徳」があって、みなそれに従って行動していた。現代に生きる私たちの「常識」や「道徳」と、彼らの信じるそれが異なるだけであって、実は両者のあいだには優劣はないのだ。それどころか、ときには彼らの側の「常識」や「道徳」のほうが、私たちが奉ずるそれよりも優れていることすらある」という指摘は非常に重要です。
私達はつい現代を生きる私達の価値基準で中世を見てしまいがちですが、時代が異なれば常識も道徳も全て異なります。しかし私達はついついそれを忘れてしまう・・・。
これは浄土真宗の開祖親鸞聖人を学んでいる私にとっても非常に重要なポイントでした。室町時代ほどではなくとも親鸞聖人が生きた平安末期から鎌倉時代初期も同じようにアナーキーでハードボイルドな時代だったはずです。そうした前提の下親鸞聖人の生きた社会を考えていかなければなりません。
そして室町から戦国期にかけて本願寺教団は急速に発達していきますが、その時代背景となった究極にアナーキーな世界を本書では学ぶことができます。浄土真宗の本ではなかなか知ることのない世界をこの本では目の当たりにできます。本願寺教団がなぜこの時期に急発展したのかを考える大きなヒントとなりました。これはぜひおすすめしたい一冊です。ものすごく面白い本でした!ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか、
以上、「清水克行『室町は今日もハードボイルド』概要と感想~私達の常識を覆す衝撃の1冊!面白すぎです!」でした。
Amazon商品紹介ページはこちら
室町は今日もハードボイルド 日本中世のアナーキーな世界 (新潮文庫)
次の記事はこちら
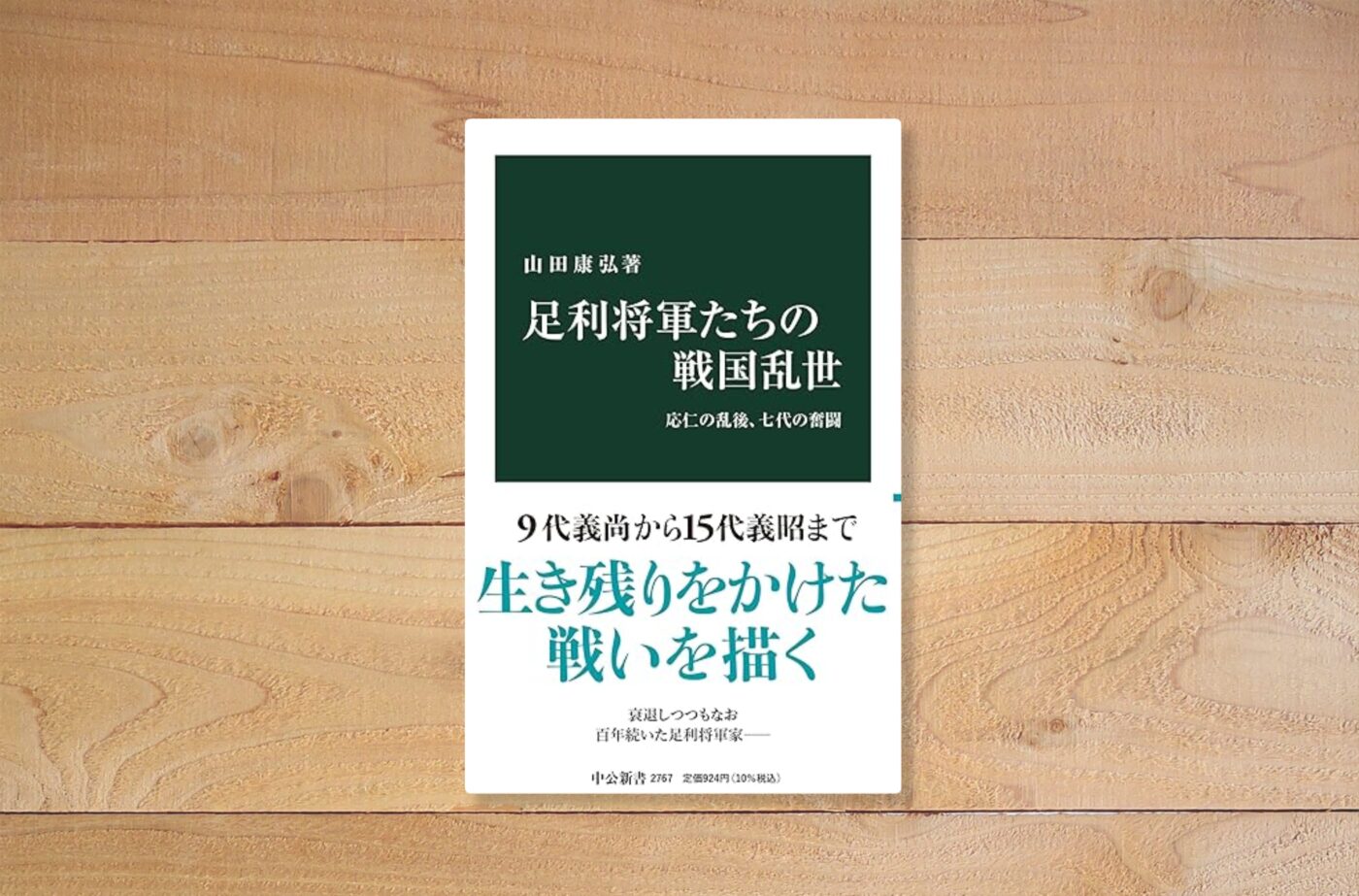
前の記事はこちら
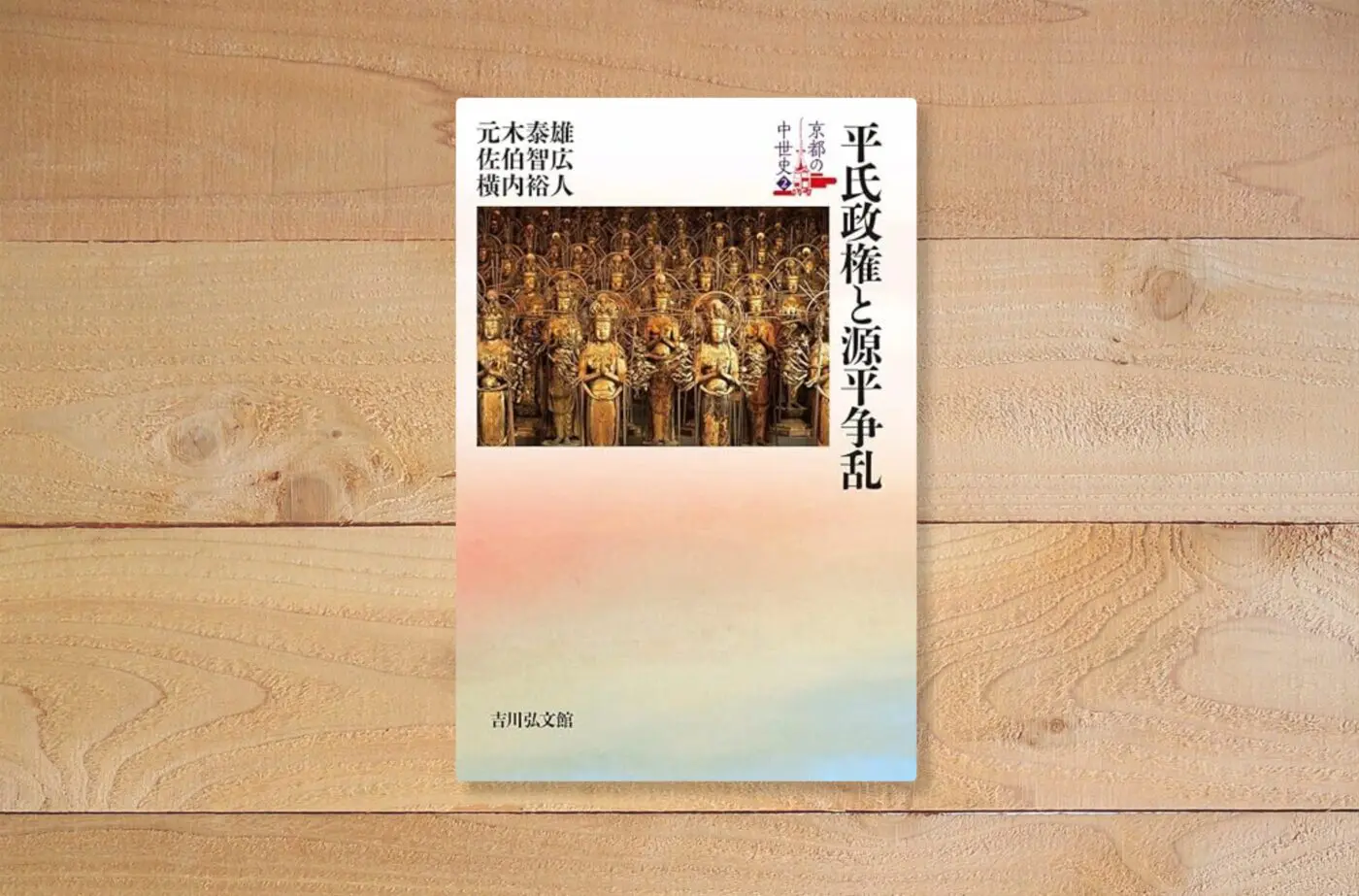
関連記事