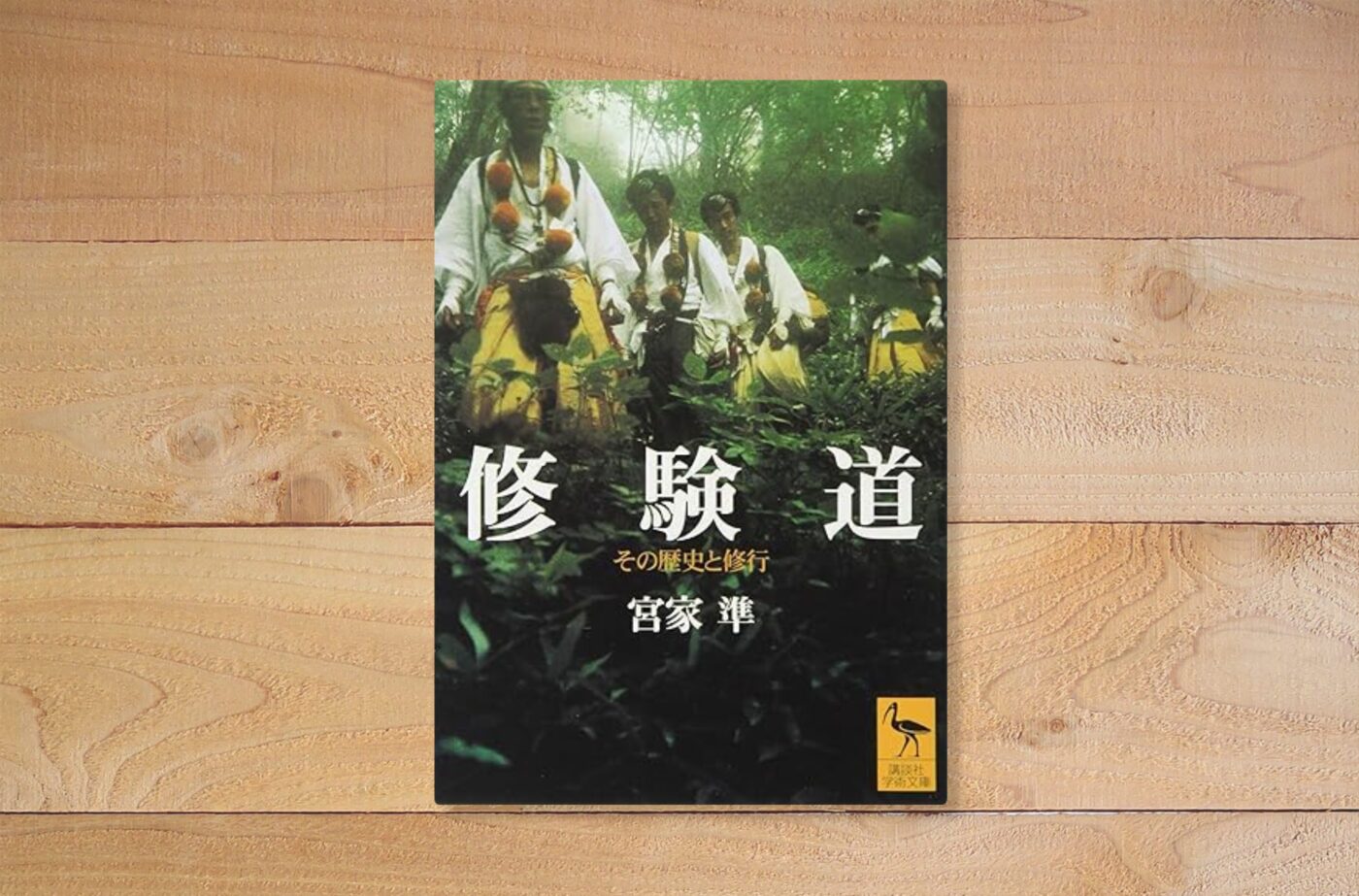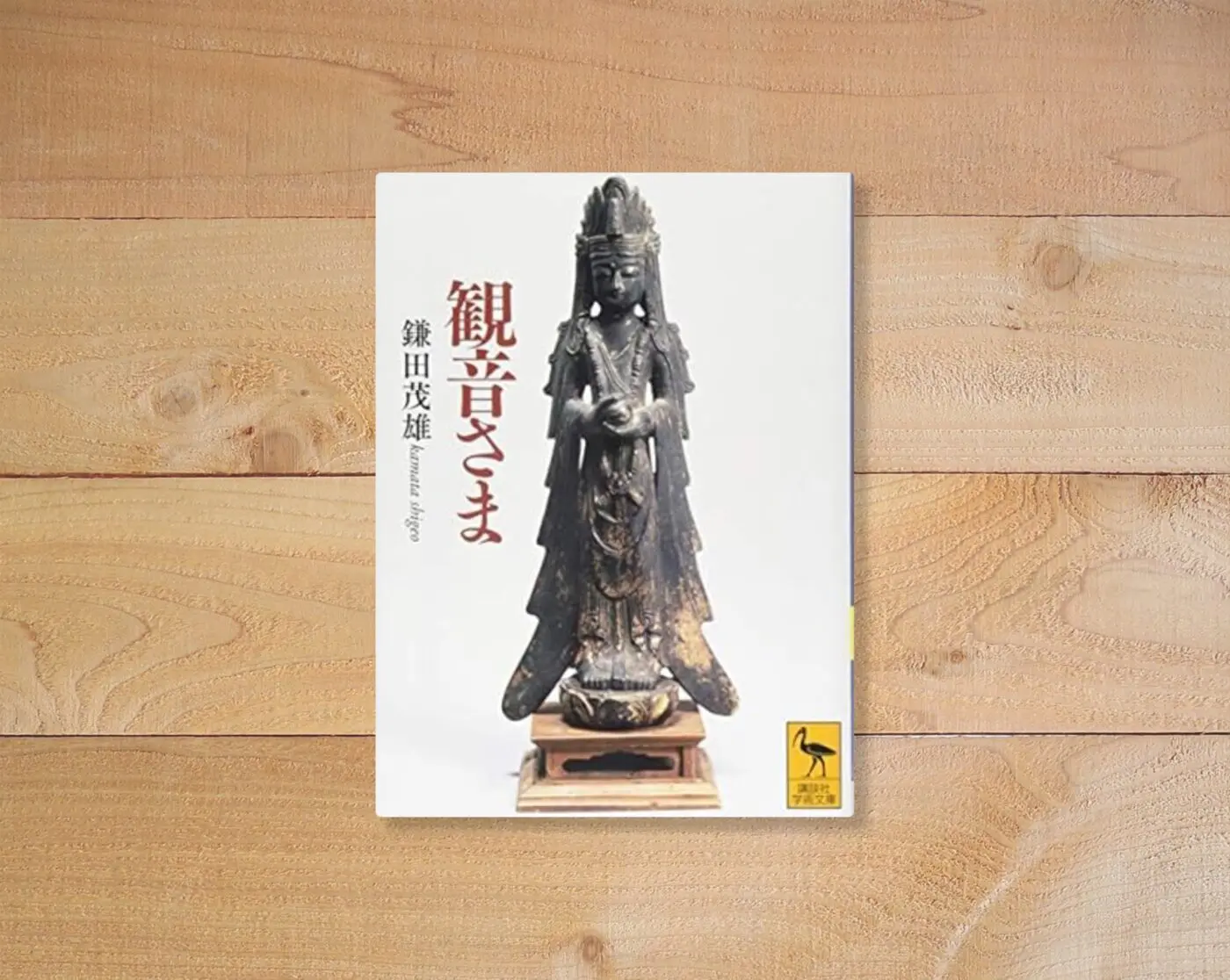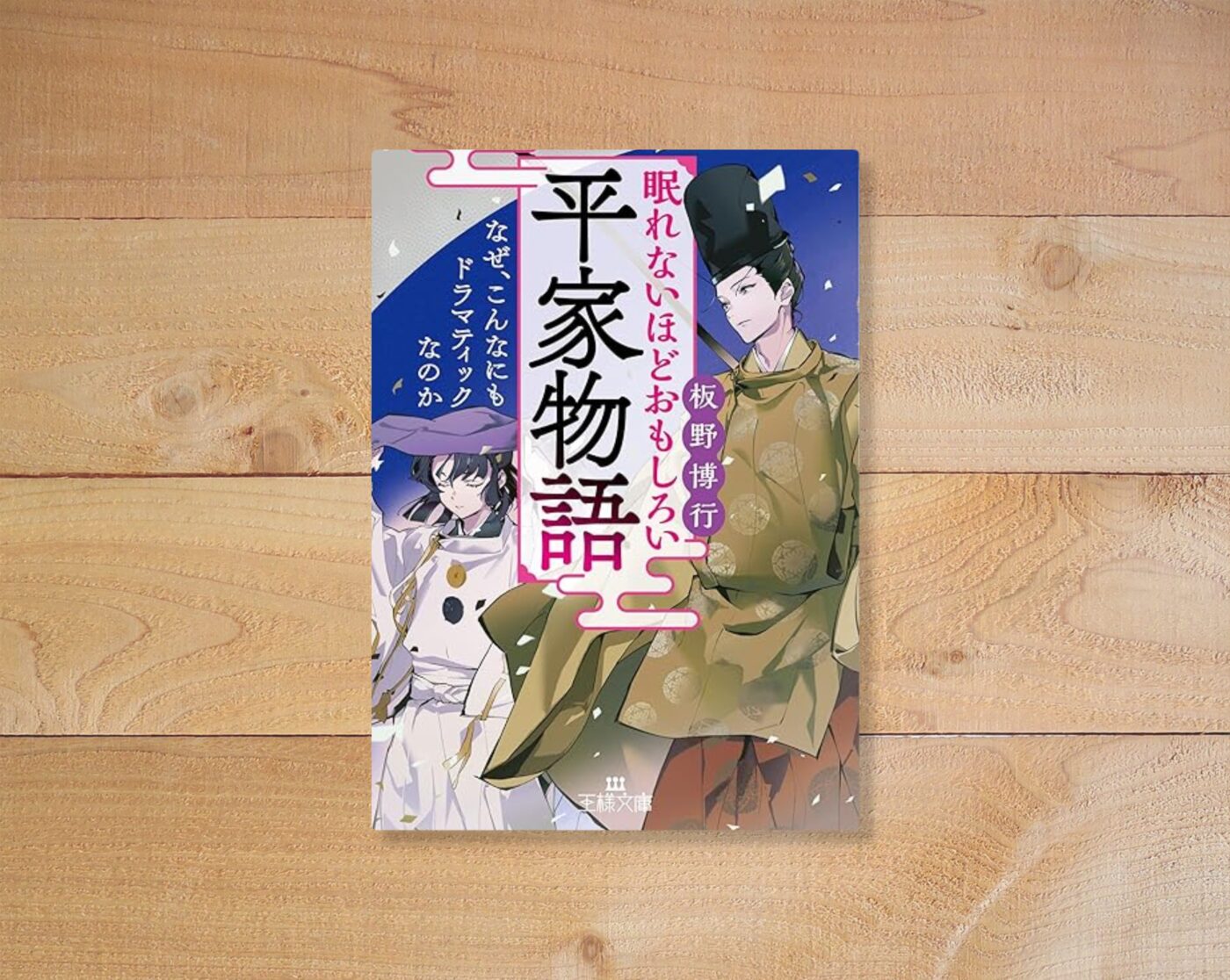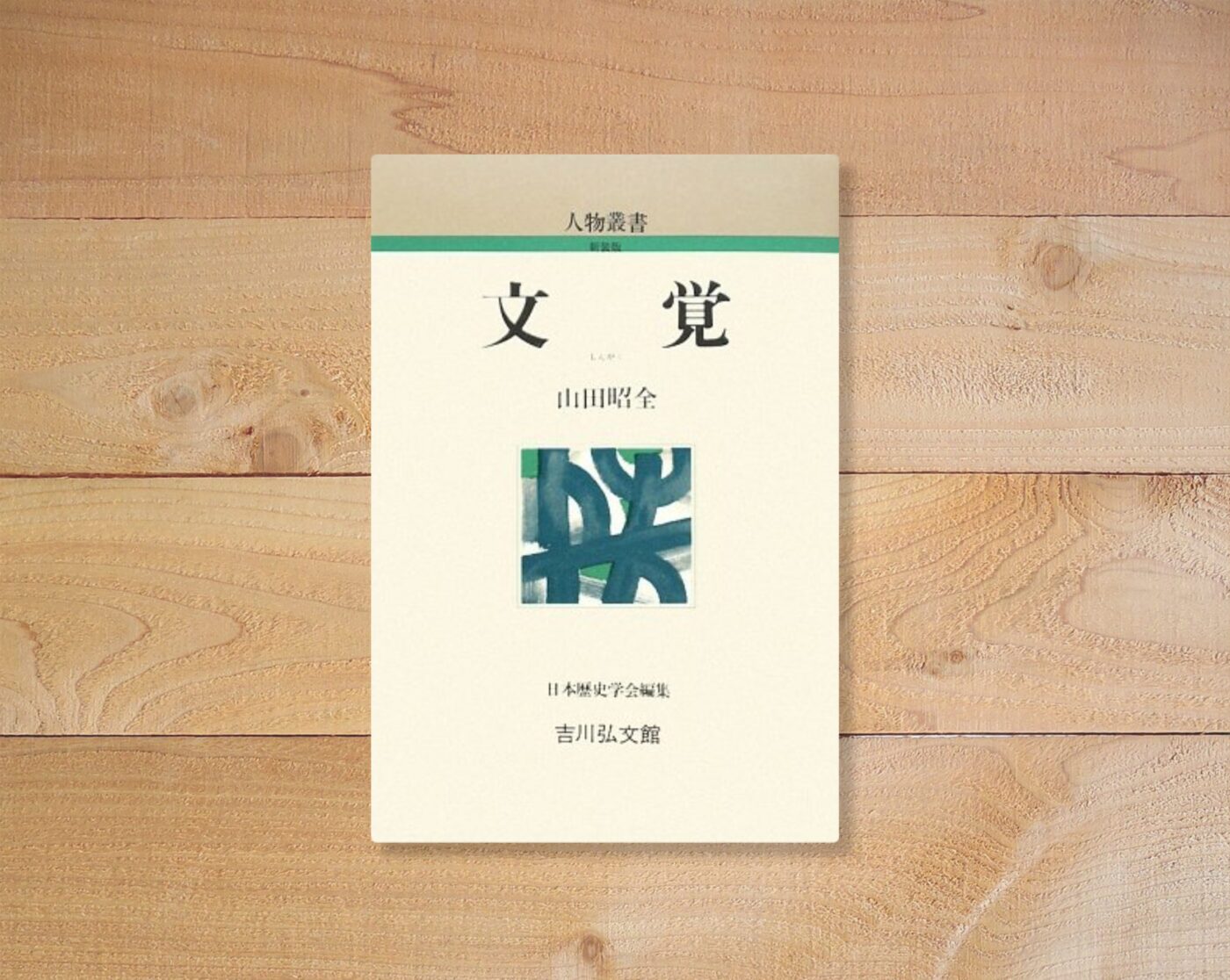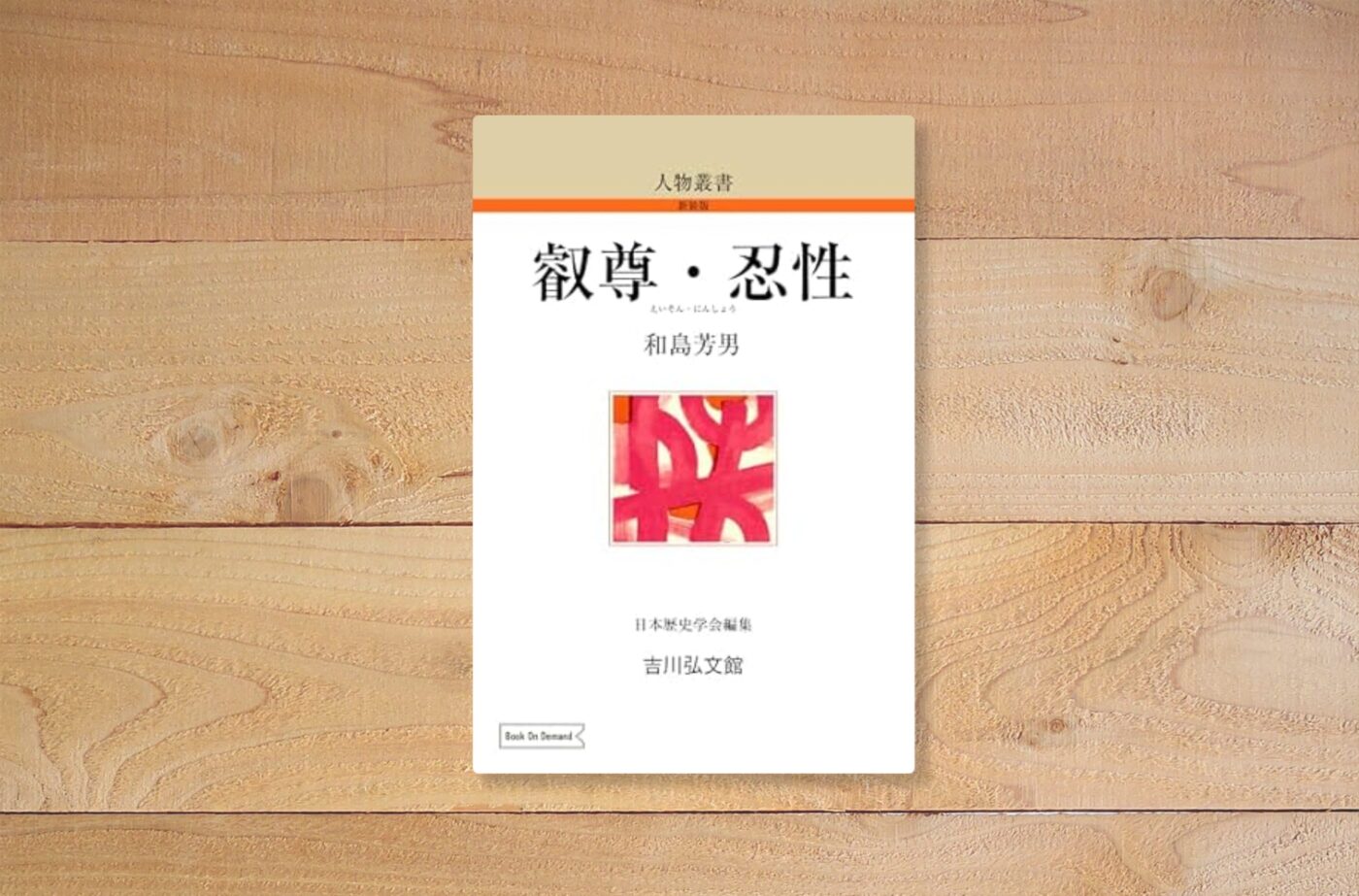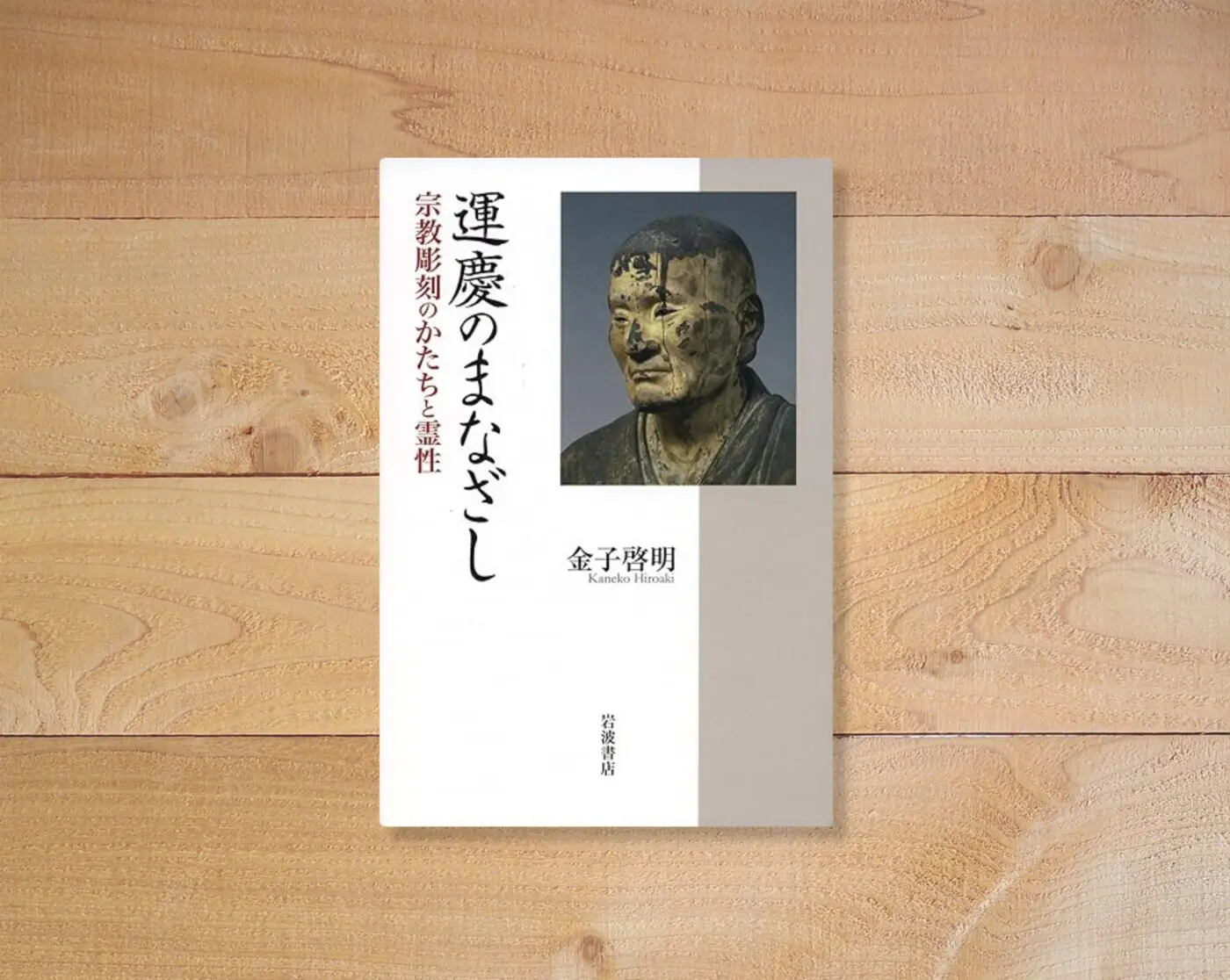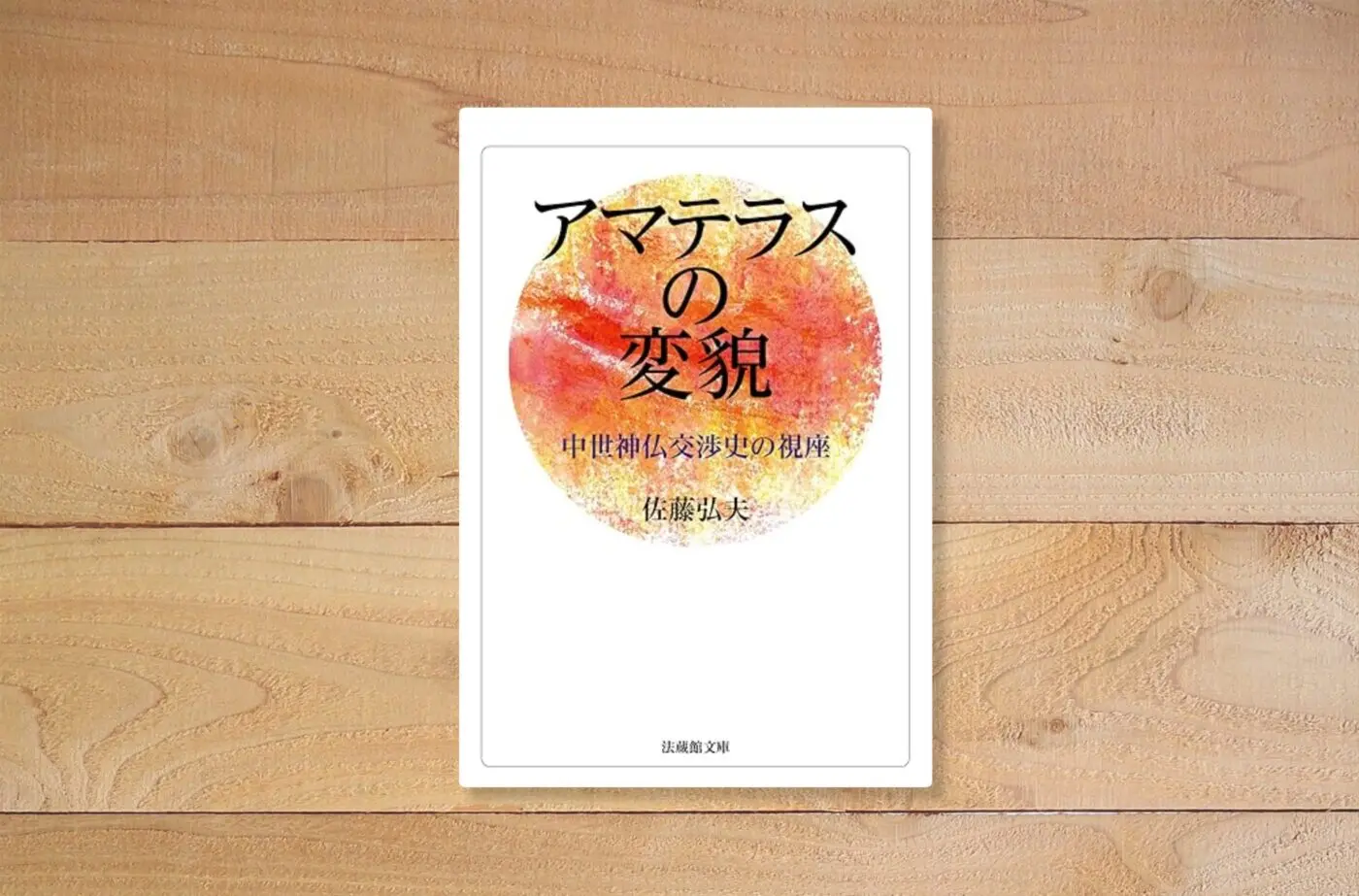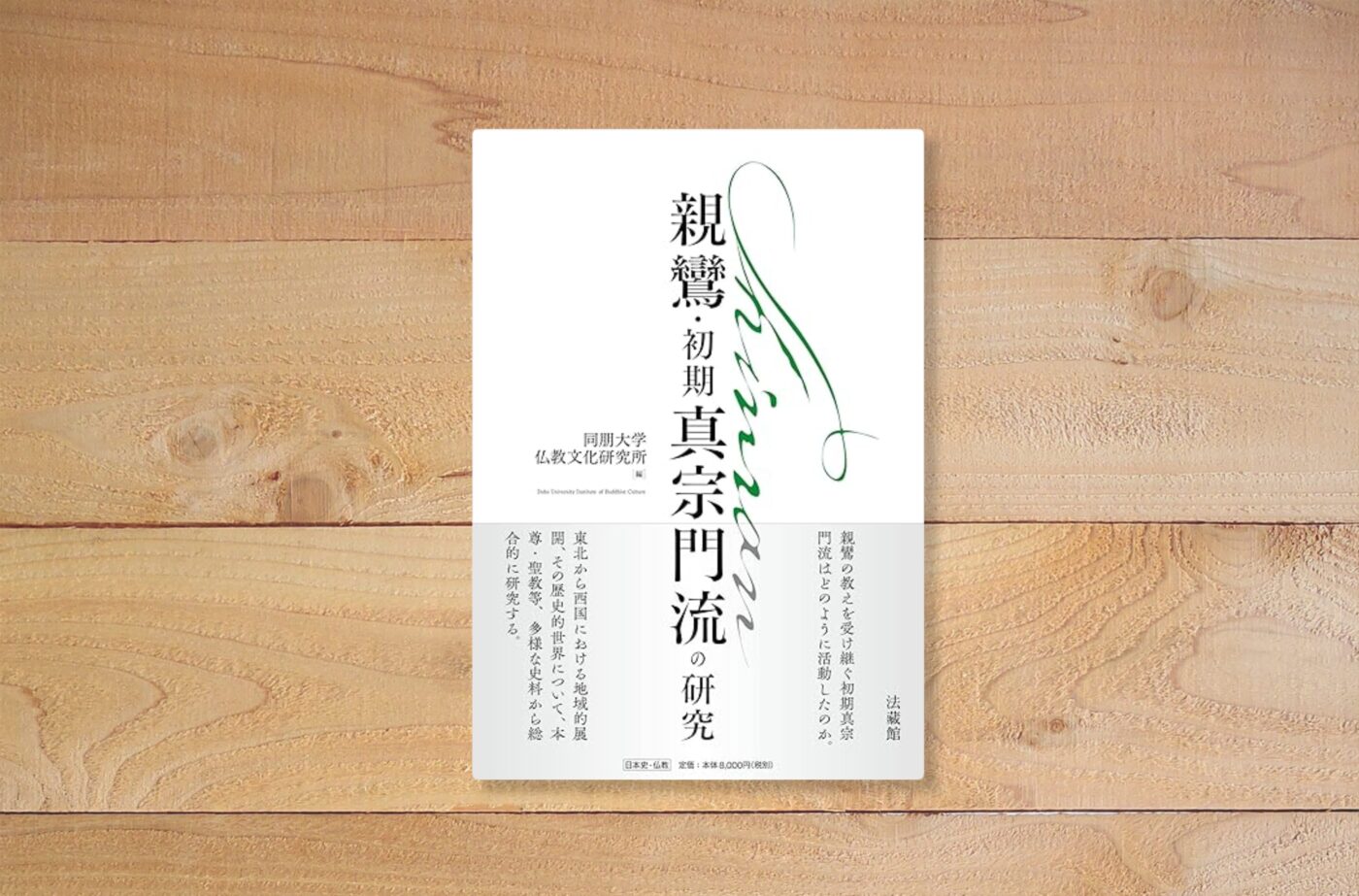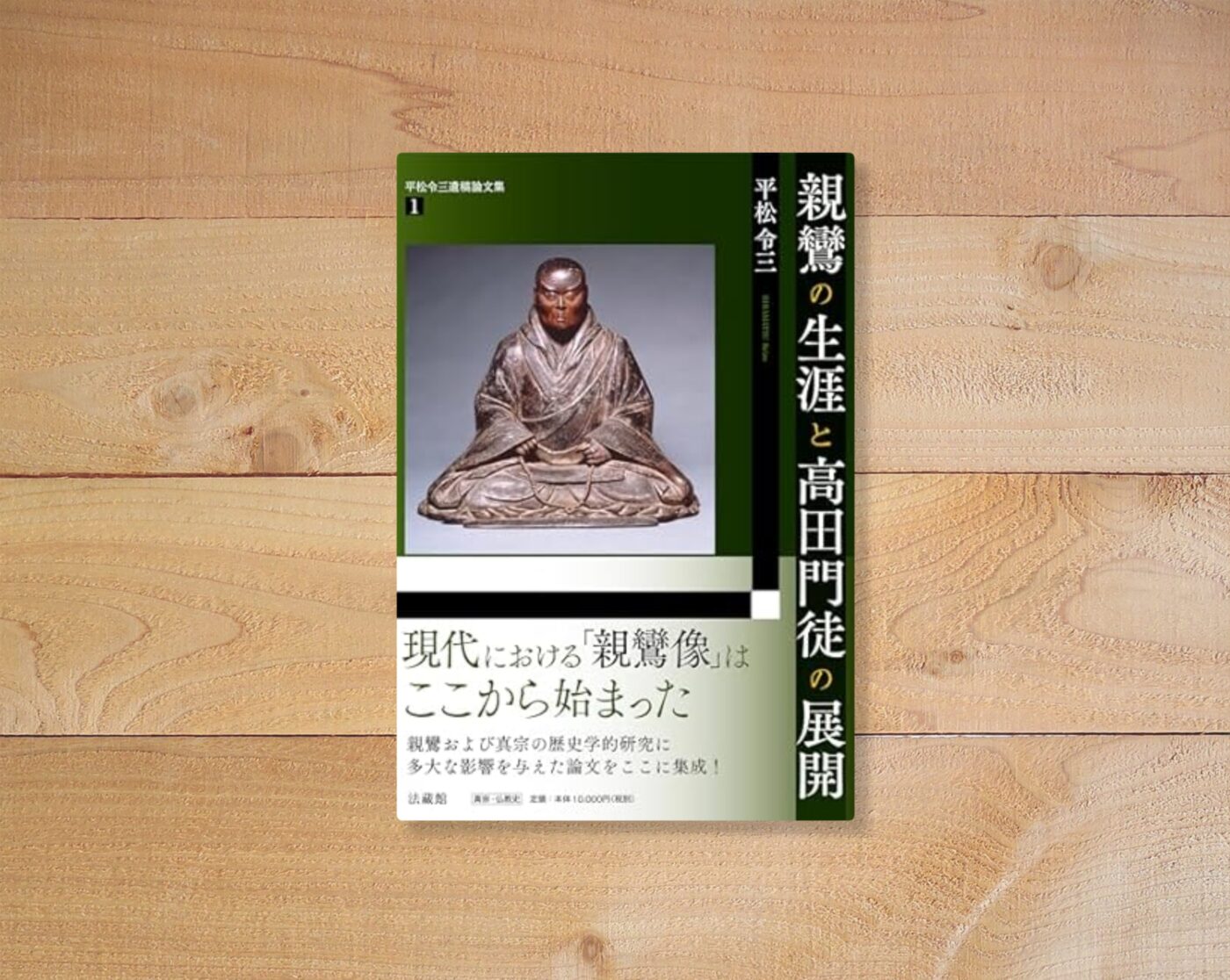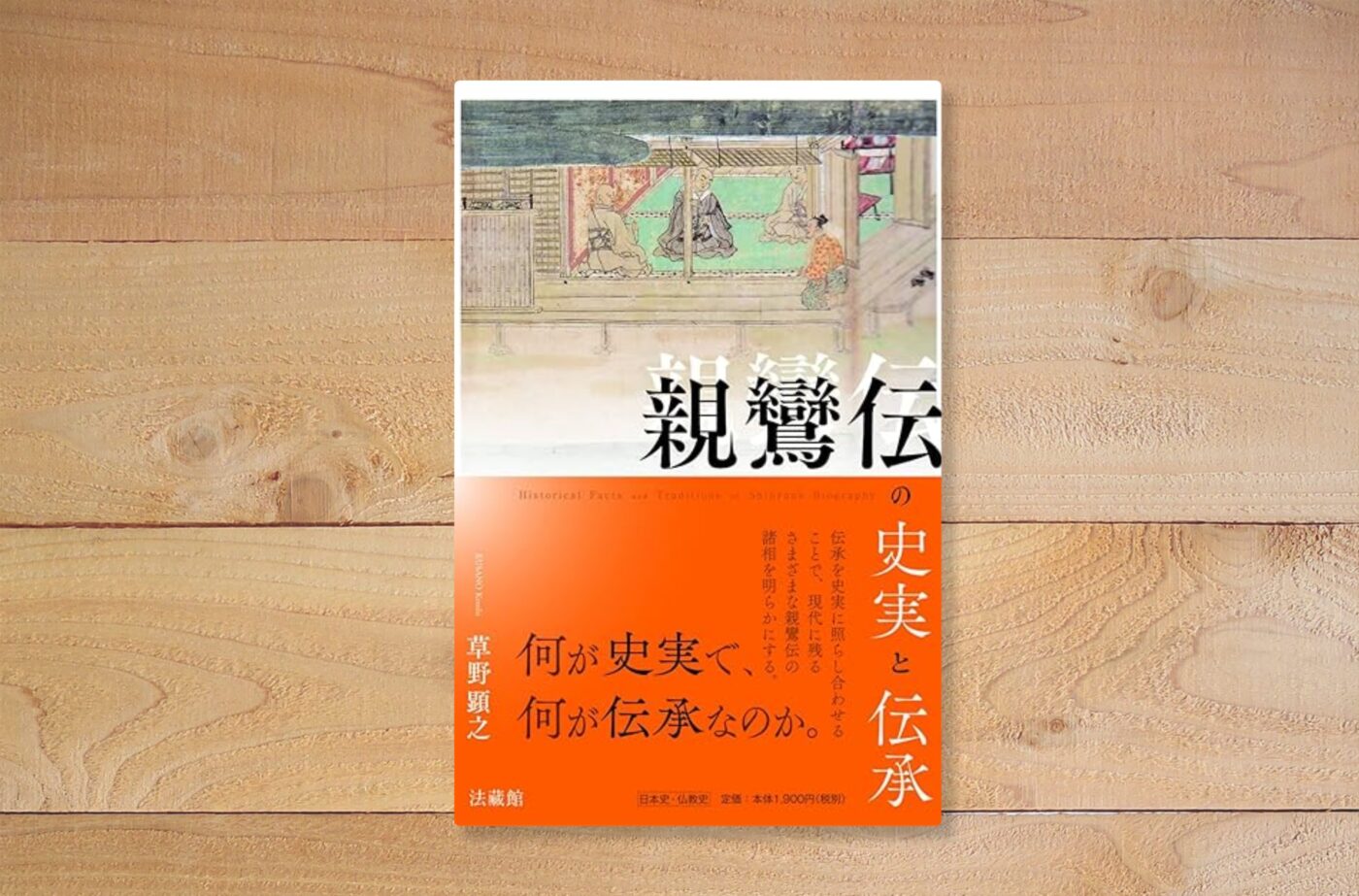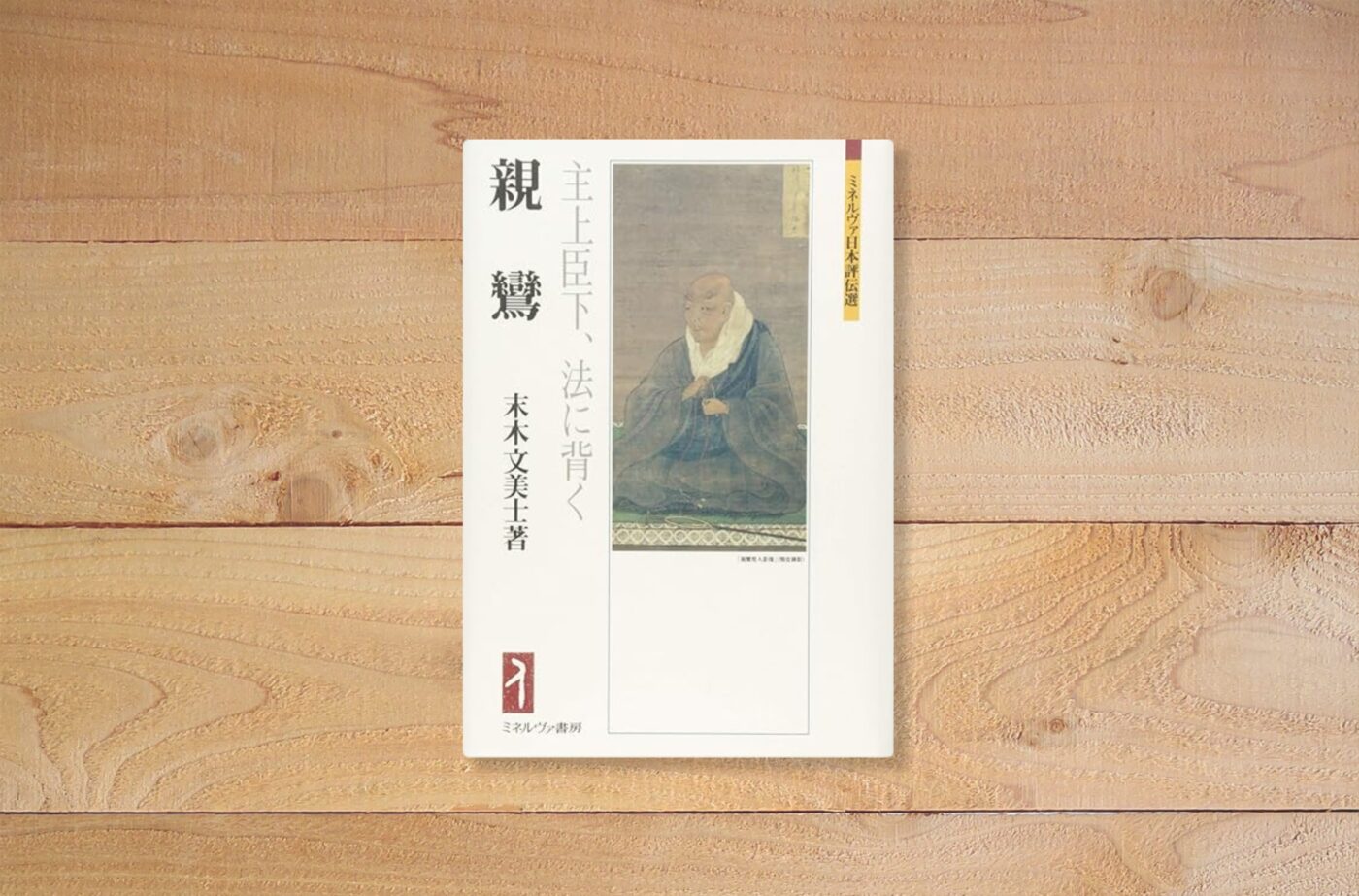根井浄『観音浄土に船出した人びと 熊野と補陀落渡海』概要と感想~熊野と海の関係について学べるおすすめ参考書
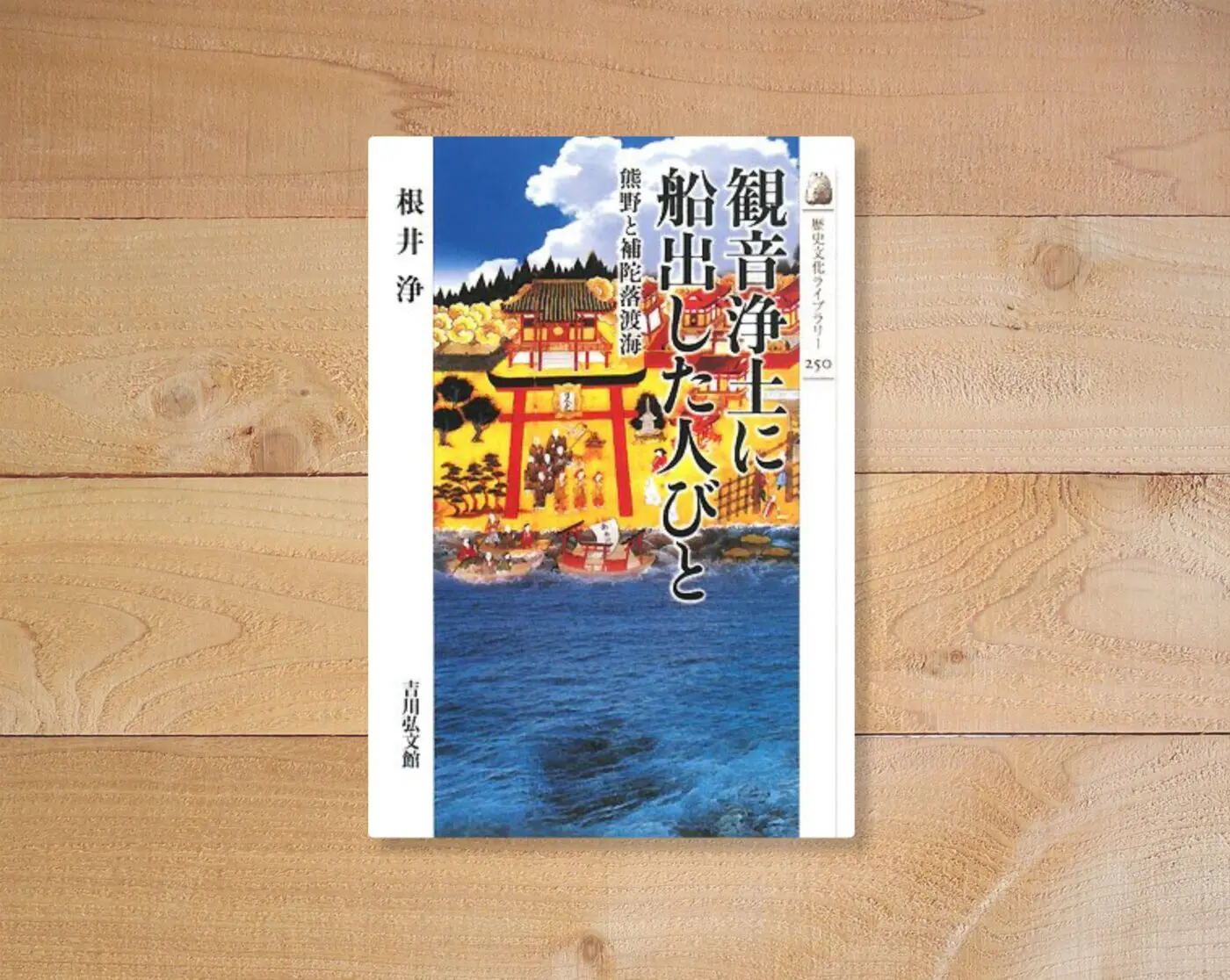
根井浄『観音浄土に船出した人びと 熊野と補陀落渡海』概要と感想~熊野と海の関係について学べるおすすめ参考書
今回ご紹介するのは2008年に吉川弘文館より発行された根井浄著『観音浄土に船出した人びと 熊野と補陀落渡海』です。
早速この本について見ていきましょう。
補陀落渡海とは何か。観音菩薩が住む南方海上の浄土=補陀落世界を目指し、現身を船形の棺に納めて大海原に船出した人びとがいた。九世紀半ばに始まり十六世紀に隆盛を見せた「南方往生」を探る。源平争乱期の平維盛、室町時代の万里小路冬房、熊野の補陀洛山寺の上人たち…。宣教師の記録や絵画史料、船の構造から、補陀落渡海の世界観を解明する。
吉川弘文館商品紹介ページより
前回の記事「五来重『熊野詣』概要と感想~死者の国、浄土信仰の聖地としての熊野を知るのにおすすめ参考書」では熊野詣についてのおすすめ参考書をご紹介しましたが、今回の記事ではそれに付随して熊野の観音信仰についてのおすすめ本をご紹介します。
上の本紹介にもありますように補陀落渡海は観音菩薩の住む南方海上を目指して海へ出ることを指します。私達現代人にはなかなか耳慣れない言葉ではありますが、この補陀落渡海は『平家物語』にも関係し、かつての日本人においてはよく知られていた慣習でもありました。
この補陀落渡海については本書冒頭で次のように説かれています。
フダラクとは、古代インドの文語(梵語)「Potalaka」(ポータラカ)の音写であり、補陀落・補陀洛・普陀洛とも漢訳される。フダラクは端的にいえば観音菩薩が住む浄土の世界である。現実の世界として、中国の長江(揚子江)河口に浮かぶ舟山諸島の普陀山であるとか、インドの南海岸にある海島とも想像された。日本では和歌山県南部の熊野那智山、高知県の室戸岬や足摺岬、九州の有明海など、上に霊峰をいただき水平に連なる滄海が補陀落山に擬せられ、補陀落渡海の出帆基地となった。
補陀落渡海とは、このような南方海上にあると想像された補陀落世界に往生を願い、または真の観音浄土を目指して船出する宗教的実践行である。観音に対する真剣な信仰表出であり、漂着・入水の形態をとっておこなわれた。文献史料によると、九世紀半ばすぎか、十八世紀初頭まで、断続的、あるいは集中的におこなわれた。
補陀落渡海の跡地は、北は高海上人が出帆した茨城県那珂湊の海岸から、南は舜夢上人の補陀落渡海の石碑を伝える鹿児島県の加世田にいたる領域に多くある。なかでも和歌山県の熊野那智の海岸は、補陀落渡海の日本最大の母港であった。その海岸線の奥にたたずむ補陀洛山寺は、補陀落渡海の歴史を語り続けている寺院である。
熊野といえば平安時代に隆盛を見た「熊野詣」が有名である。平安時代後期の公卿で中御門右大臣ともいわれた藤原宗忠は、天仁二年(一一〇九)に熊野三山(現在の熊野本宮大社・熊野速玉大社・熊野那智大社)に参詣したとき那智の海岸が「補陀落浜」と呼ばれていたことを自分の日記『中右記』に書いている。さらに『平家物語』は、平維盛一行が熊野三山参詣のあと、寿永三年(一一八四)三月、那智の海に浮かぶ山成島に身を沈めたと語る。有名な平維盛の入水往生讃である。人間の壮絶な死の瞬間を描写し、誰もが哀憐をおぼえる物語りである。維盛の入水往生も熊野那智の補陀落信仰を抜きにしては説明できないだろう。
補陀落渡海は水葬や捨身や入水往生など多面的な性格を持ち合わせていた。多くの人びとの耳目を奪ったこの行為は、十六世紀に隆盛を見せ、衆目の的となっていた。補陀落渡海は観音浄土を現世に求め、あえて生身のままで海を渡っていく点に本義があるだろう。現実的には死の形態をとりながらも、実は生に裏打ちされた実践行であった。
生きながら観音浄土へー観音菩薩の浄土・補陀落世界に魅せられて、多くの修行者や人びとが小舟を仕立て、太平洋の南方海上の彼方に消えていった。これが日本宗教史上における希有な現象として知られる補陀落渡海である。
本書は、補陀落渡海の本源・展開・変容・継承・本質について私見を述べたものである。補陀落渡海を決して猟奇的に見るのではなく、補陀落信仰の完結者として勇猛果敢に「南方往生」を企てた人間の大先輩たちをできるだけ多く紹介しようと思う。
吉川弘文館、根井浄『観音浄土に船出した人びと 熊野と補陀落渡海』P5-7

ここで述べられましたように、補陀落渡海は命を賭して行われる船出です。いや、確実に死を迎える船出という方が正確するかもしれません。上の解説にありますように、補陀落へ向かって船出するといっても、実際にこの海の先に観音菩薩が住む補陀落があるわけではないのです。ですが、その熱烈な信仰ゆえ生きたままそこに飛び込まんとする修行者が後を絶たなかったのです。つまり、事実上即身成仏と同じように自ら死を選び取る最後の修行なのでありました。

本書ではこうした補陀落渡海の歴史や行者の姿を詳しく見ていくことができます。熊野といえば山の中の古道が連想されがちですが、実は海にも信仰の歴史があったのです。観音信仰は日本人にもとても馴染み深いものでありますが、その極致とも言える補陀落渡海について知れる本書は非常に貴重です。
ぜひおすすめしたい一冊です。
以上、「根井浄『観音浄土に船出した人びと 熊野と補陀落渡海』概要と感想~熊野と海の関係について学べるおすすめ参考書」でした。
Amazon商品紹介ページはこちら
観音浄土に船出した人びと 熊野と補陀落渡海 (歴史文化ライブラリー 250)
次の記事はこちら
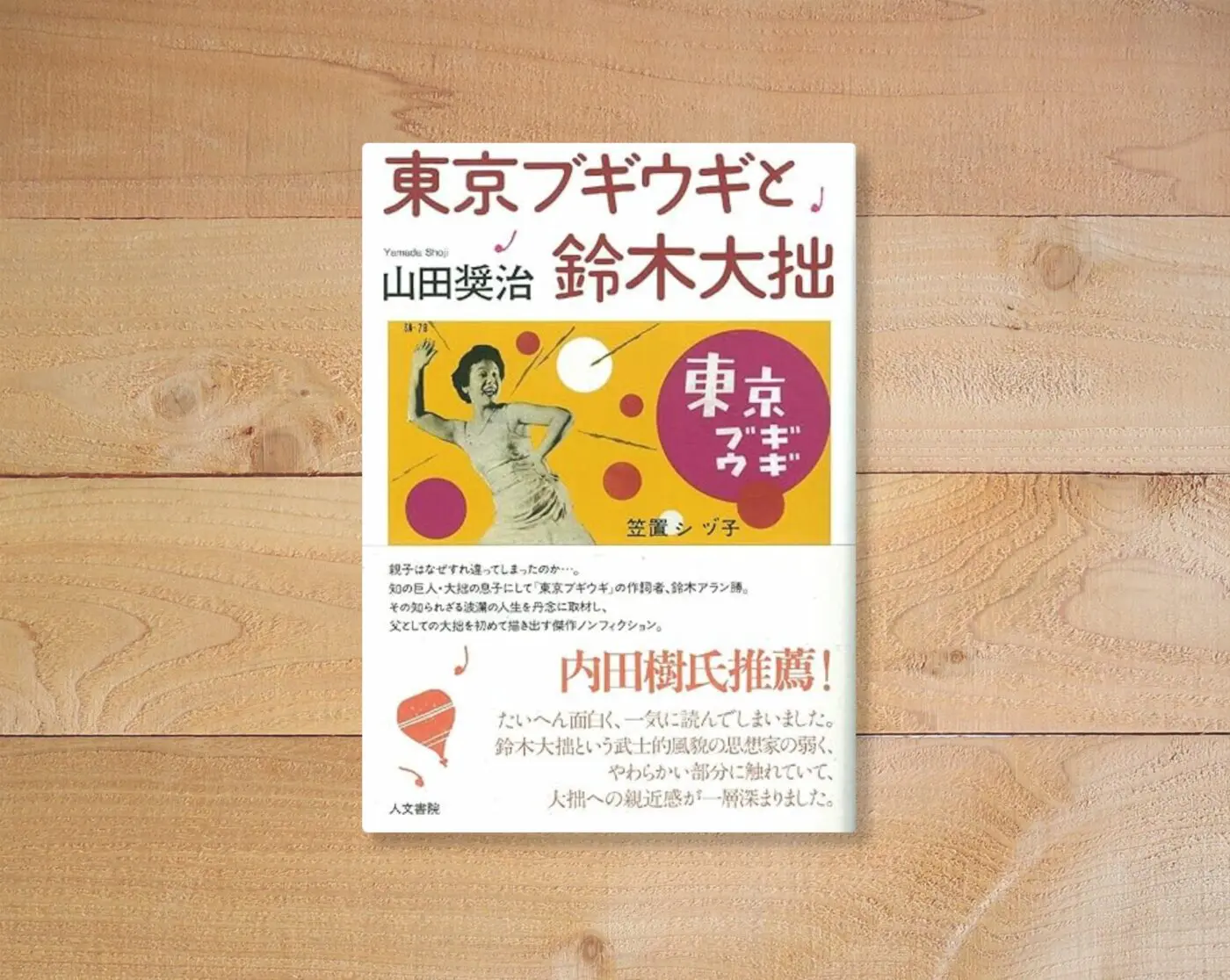
前の記事はこちら

関連記事