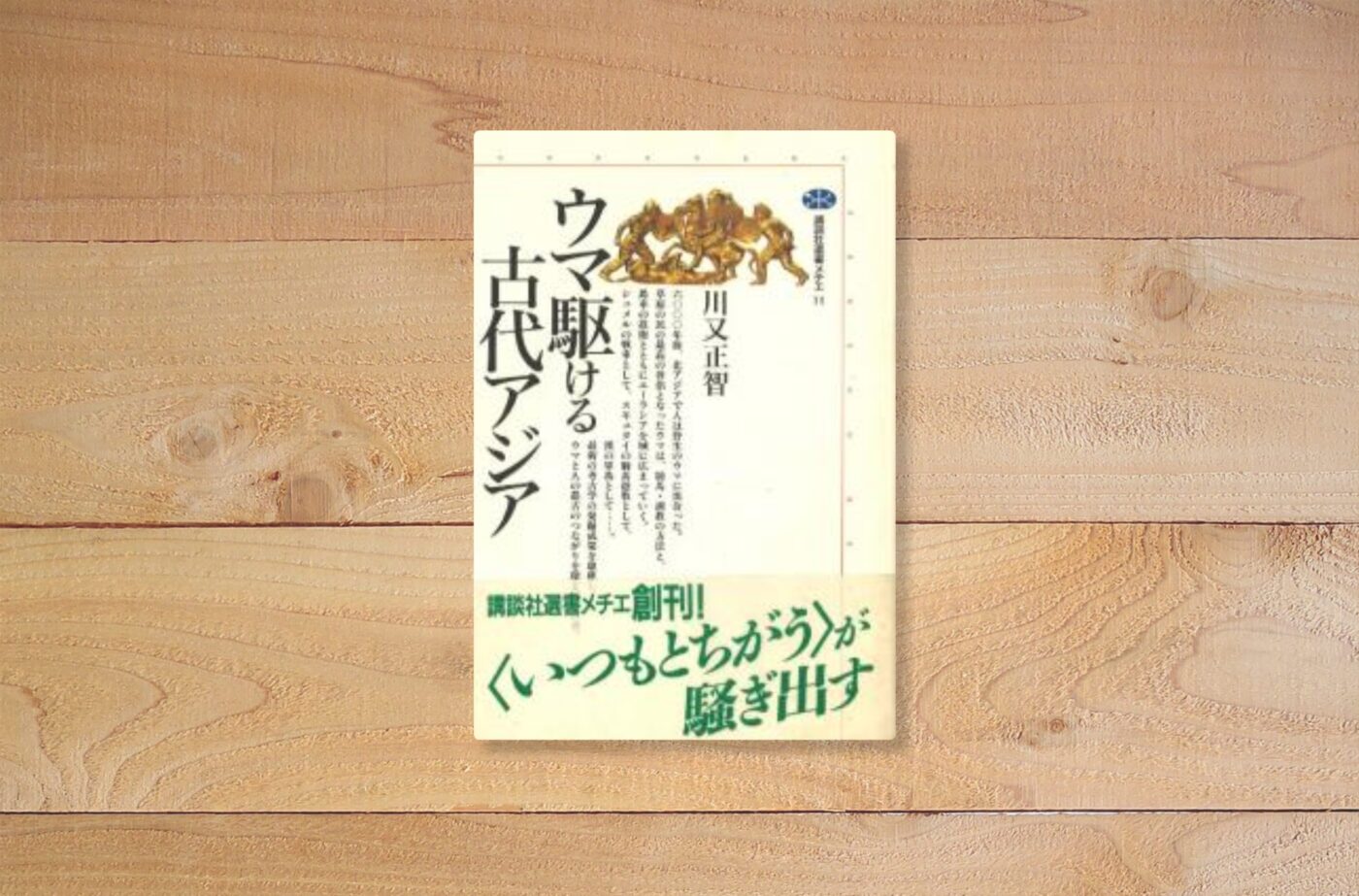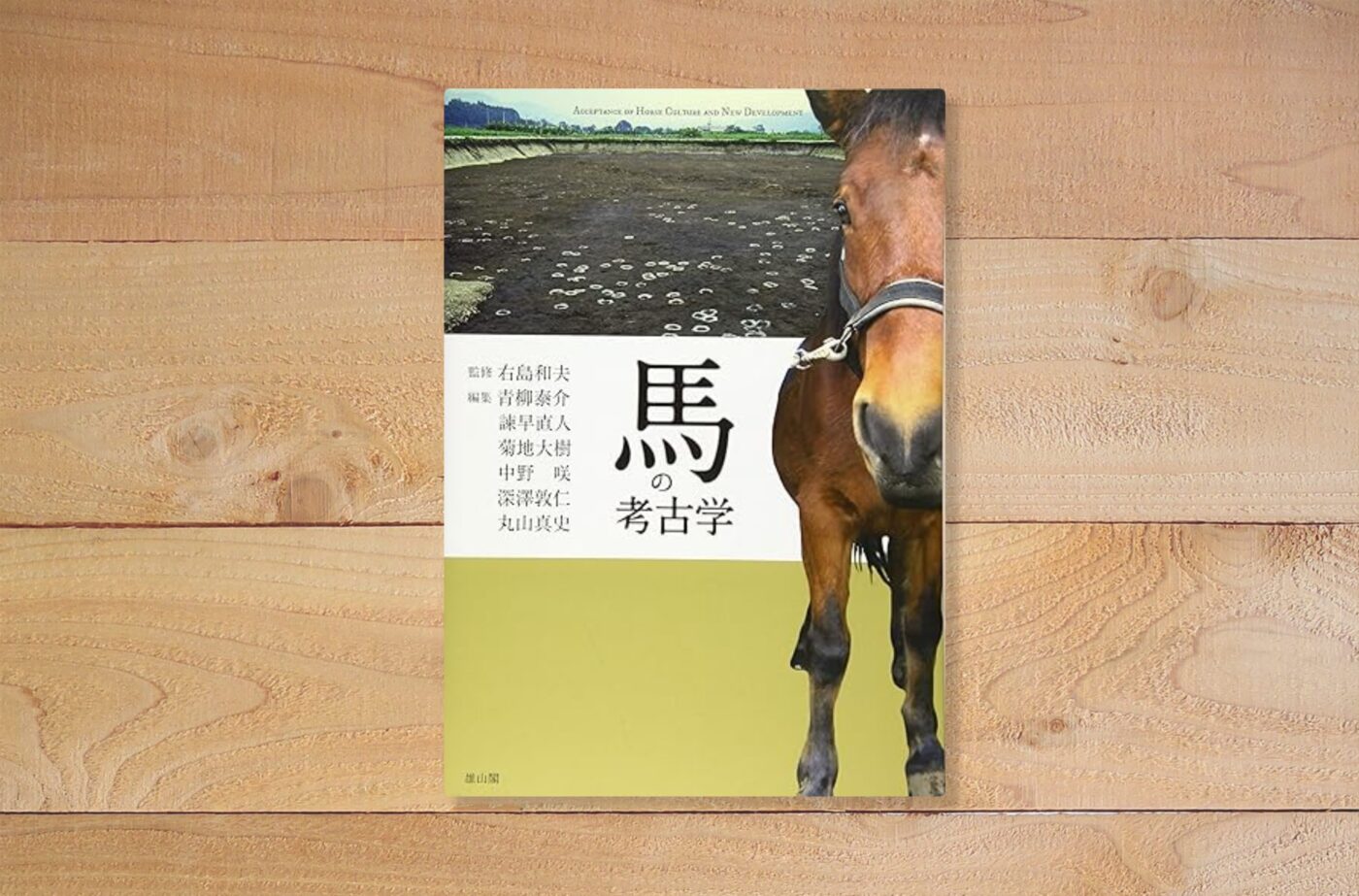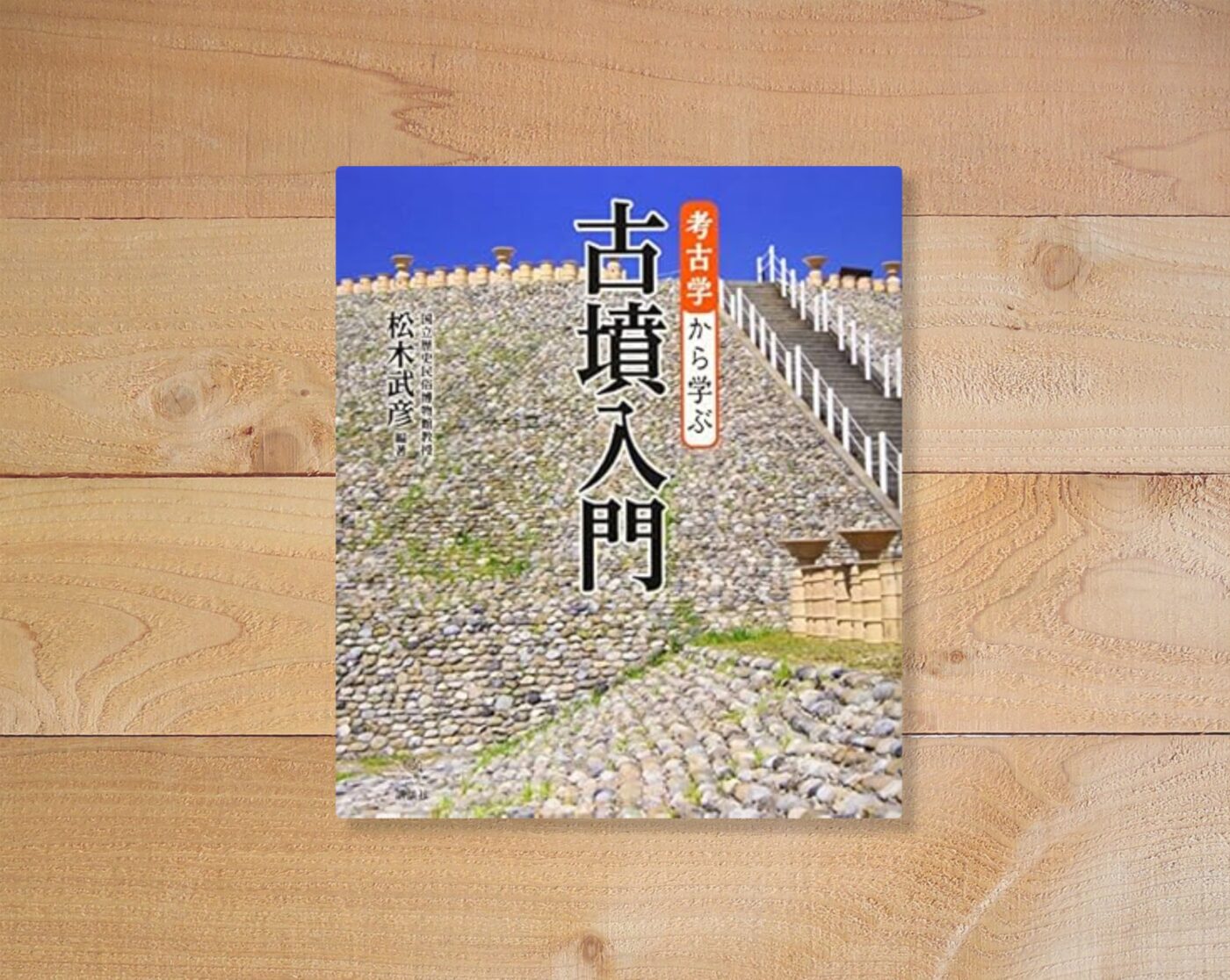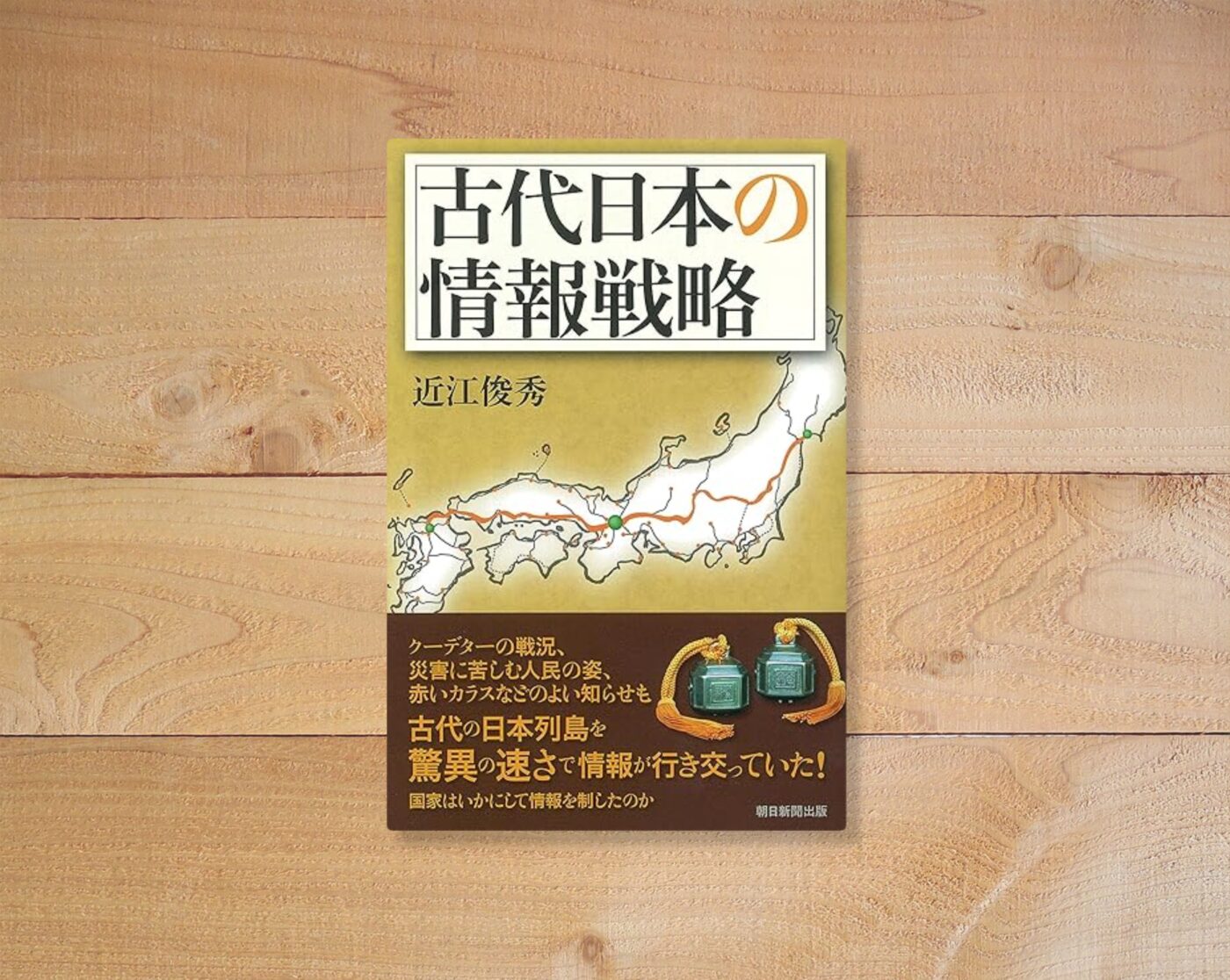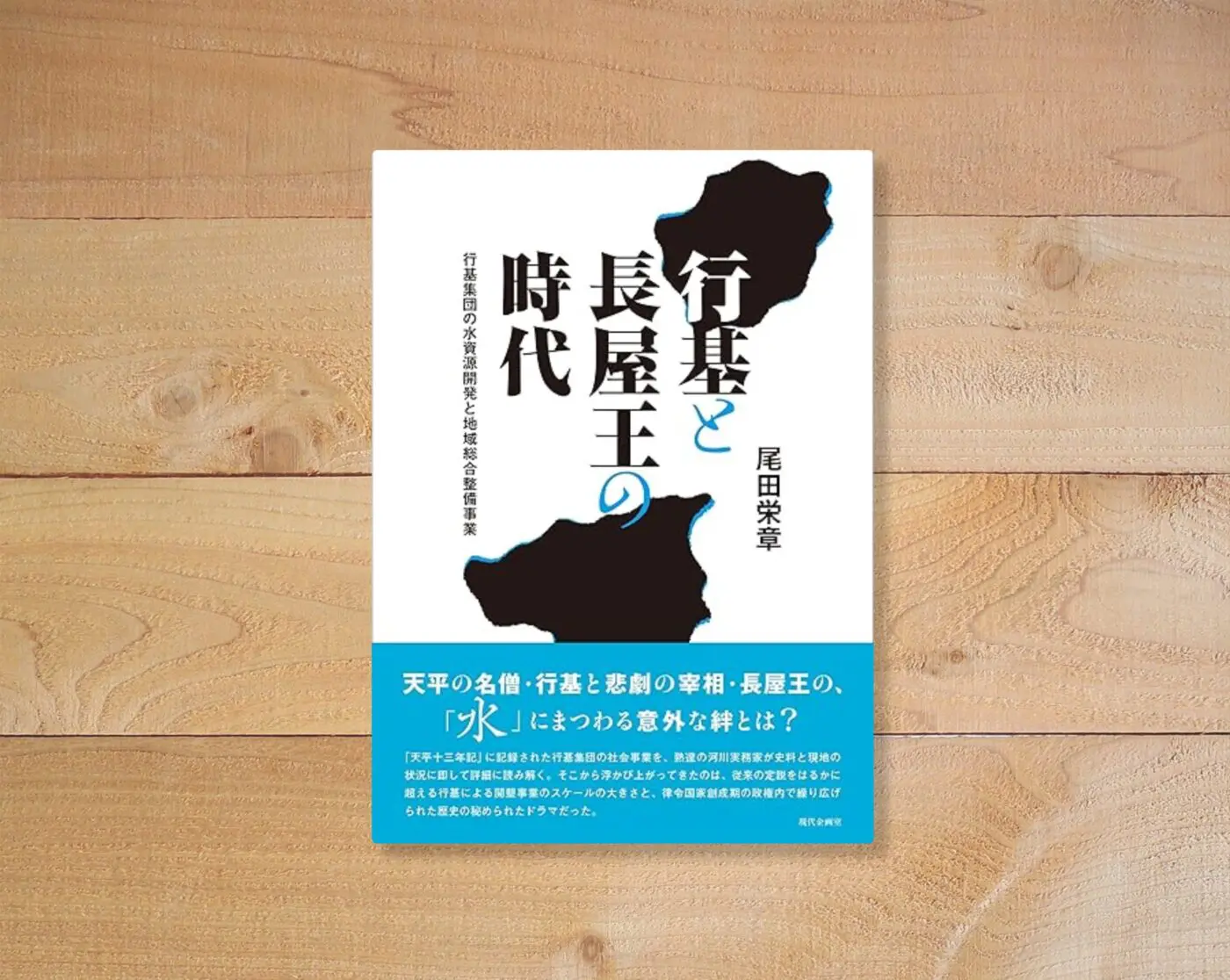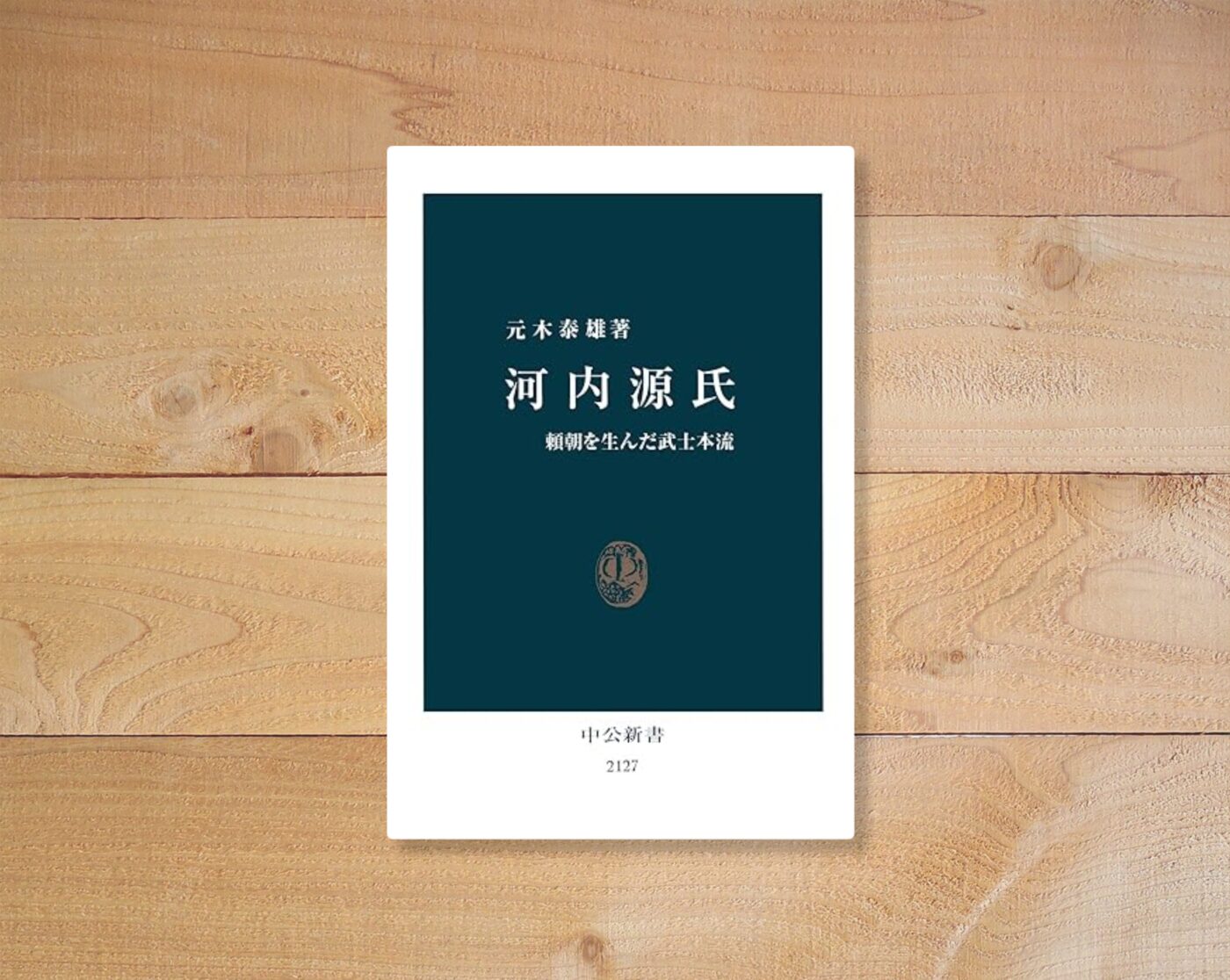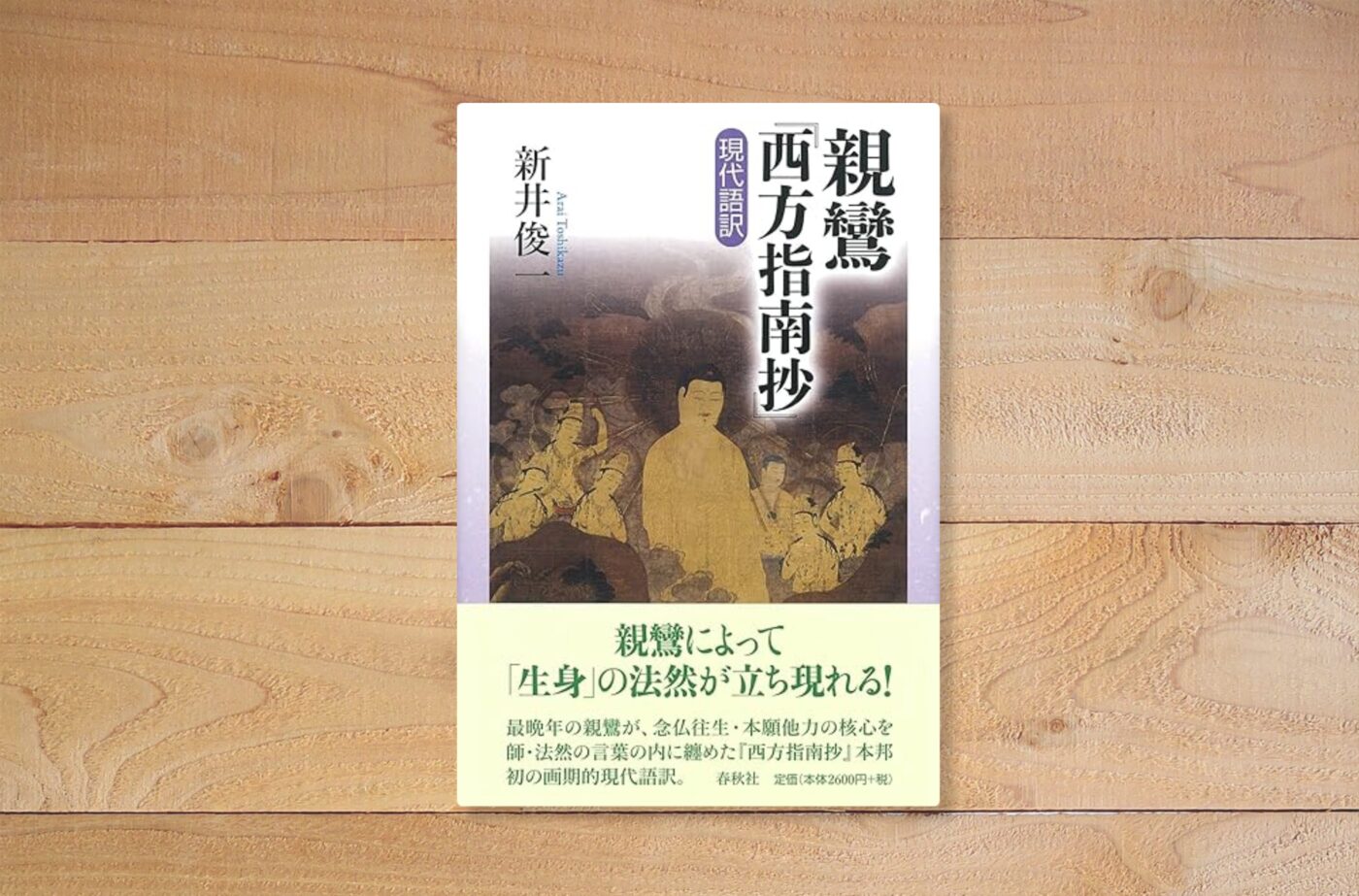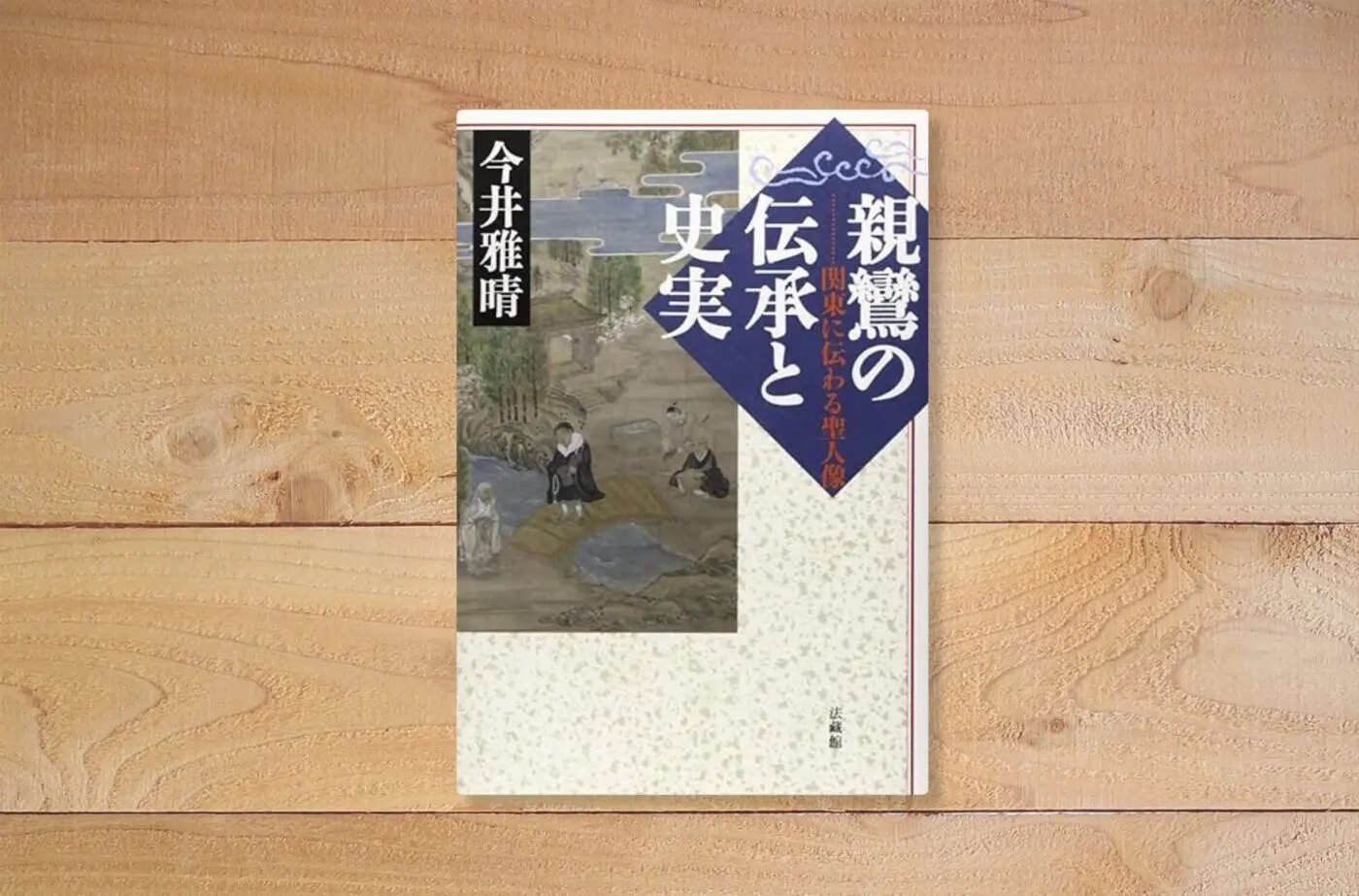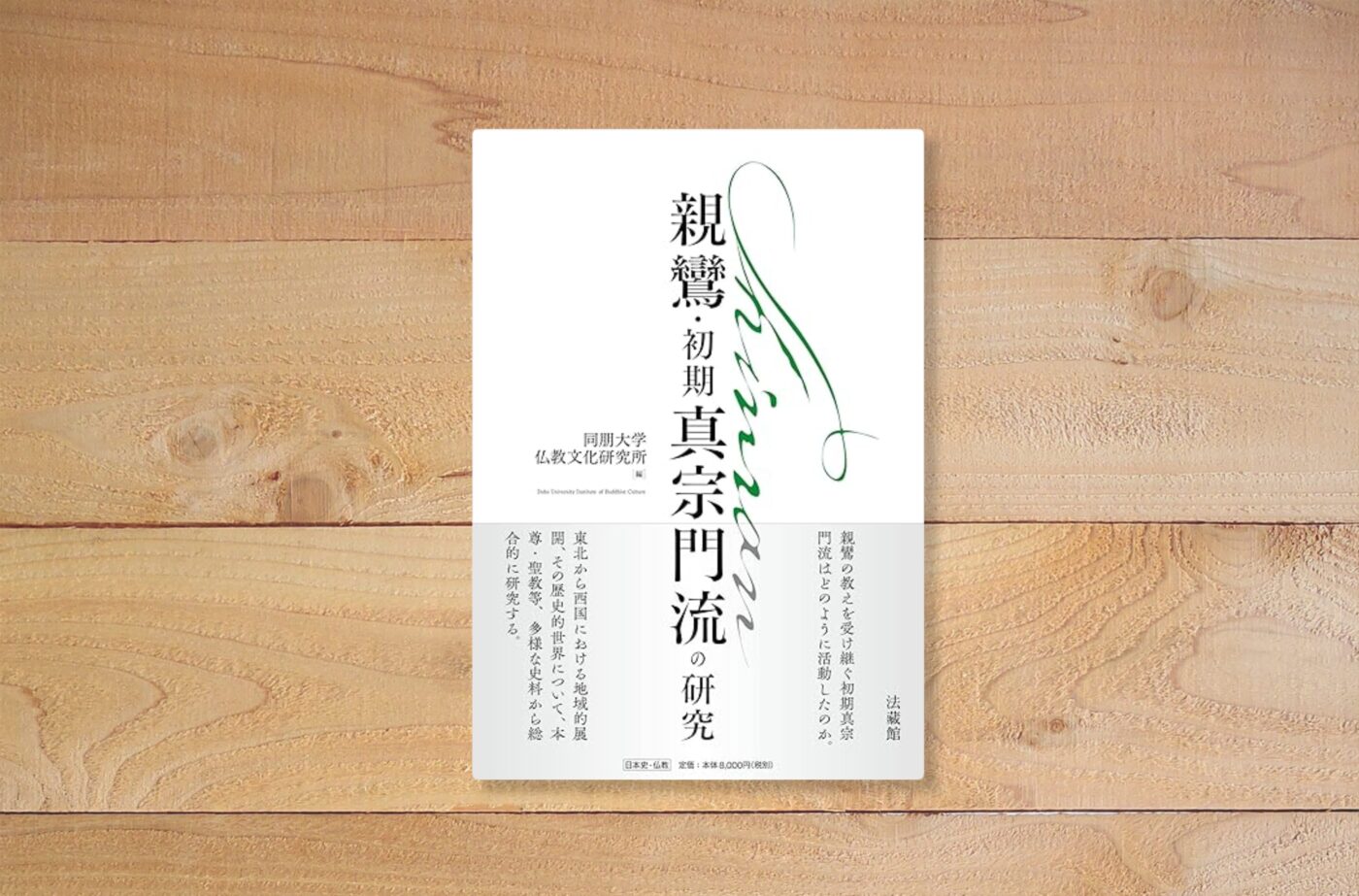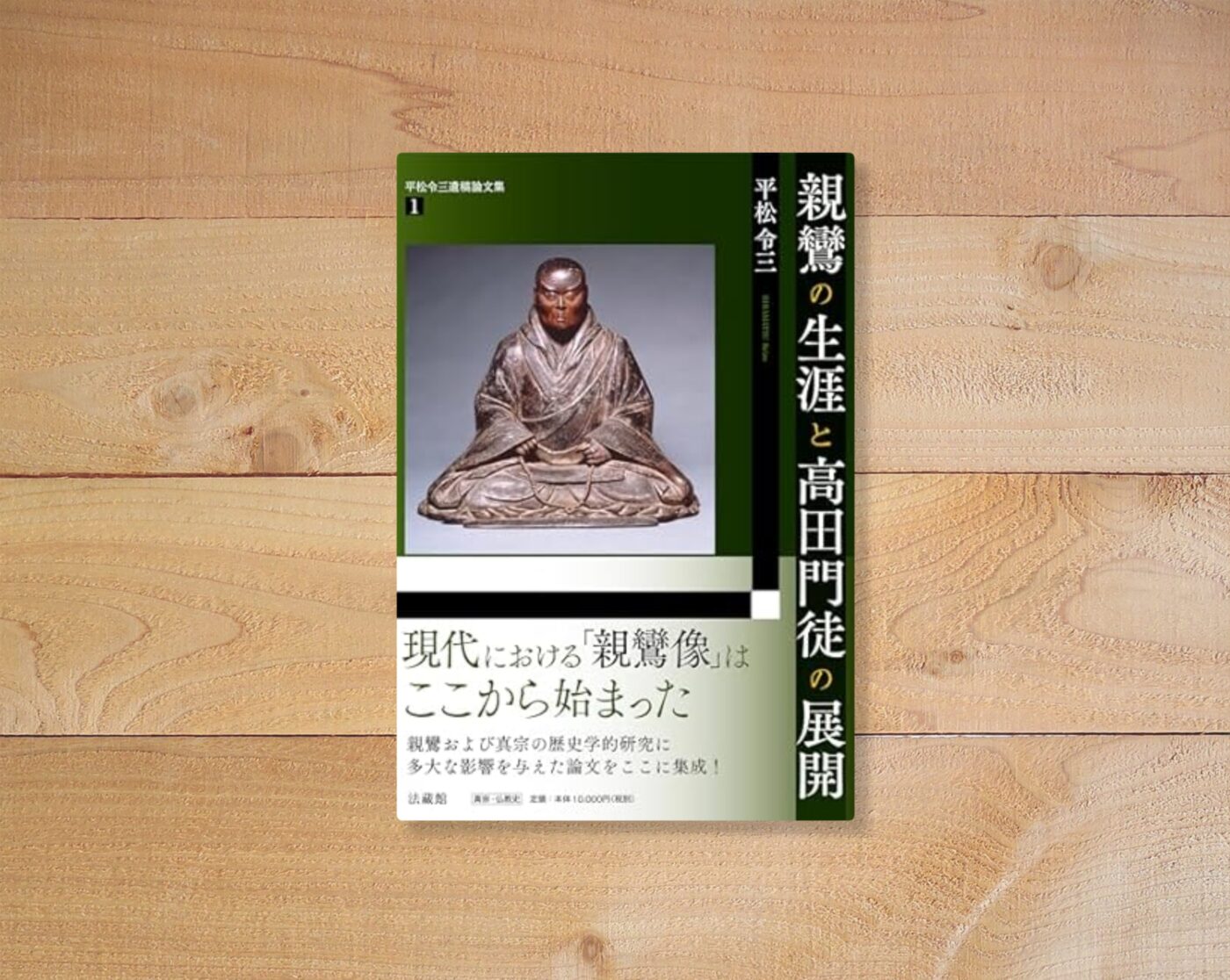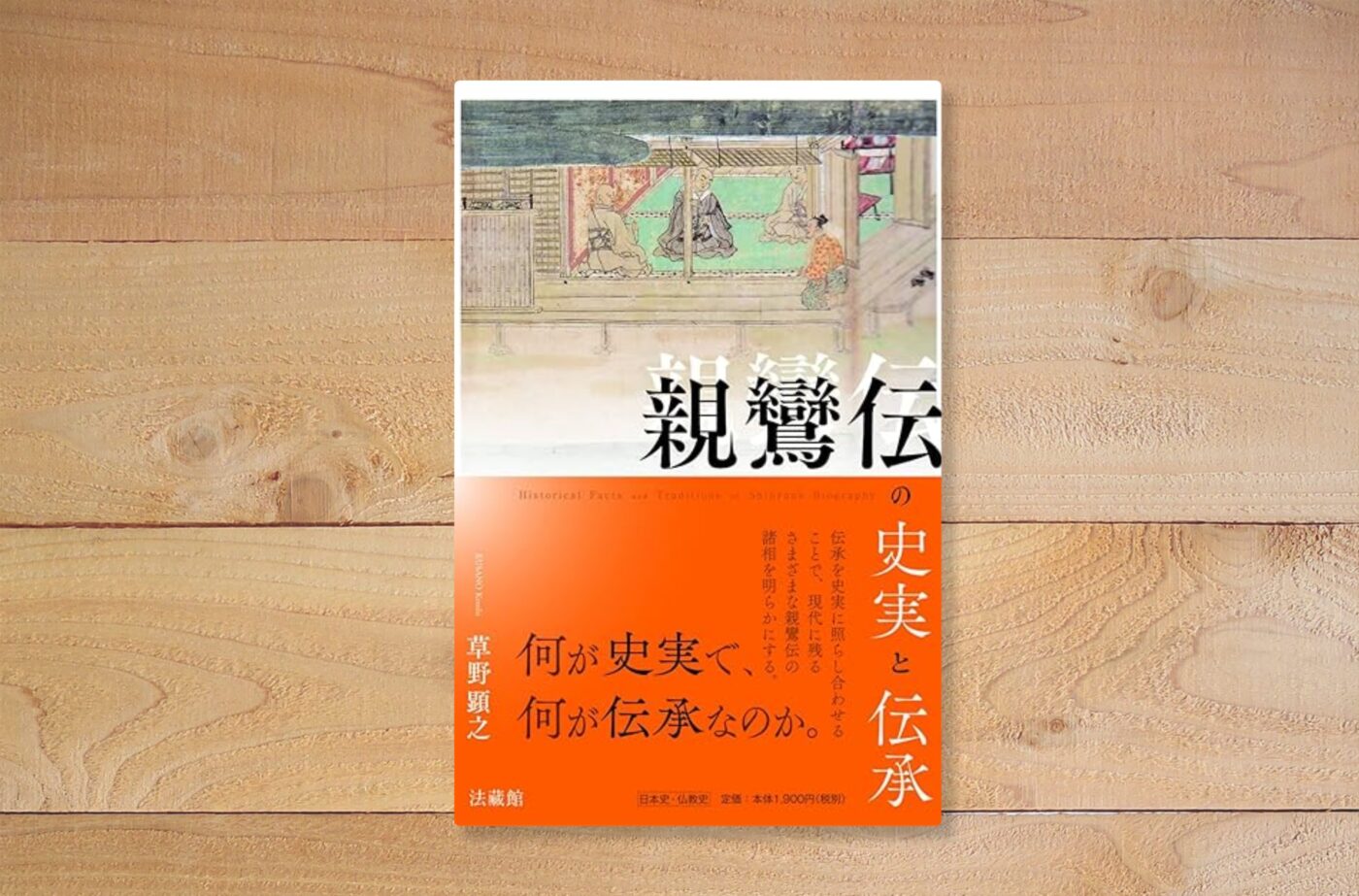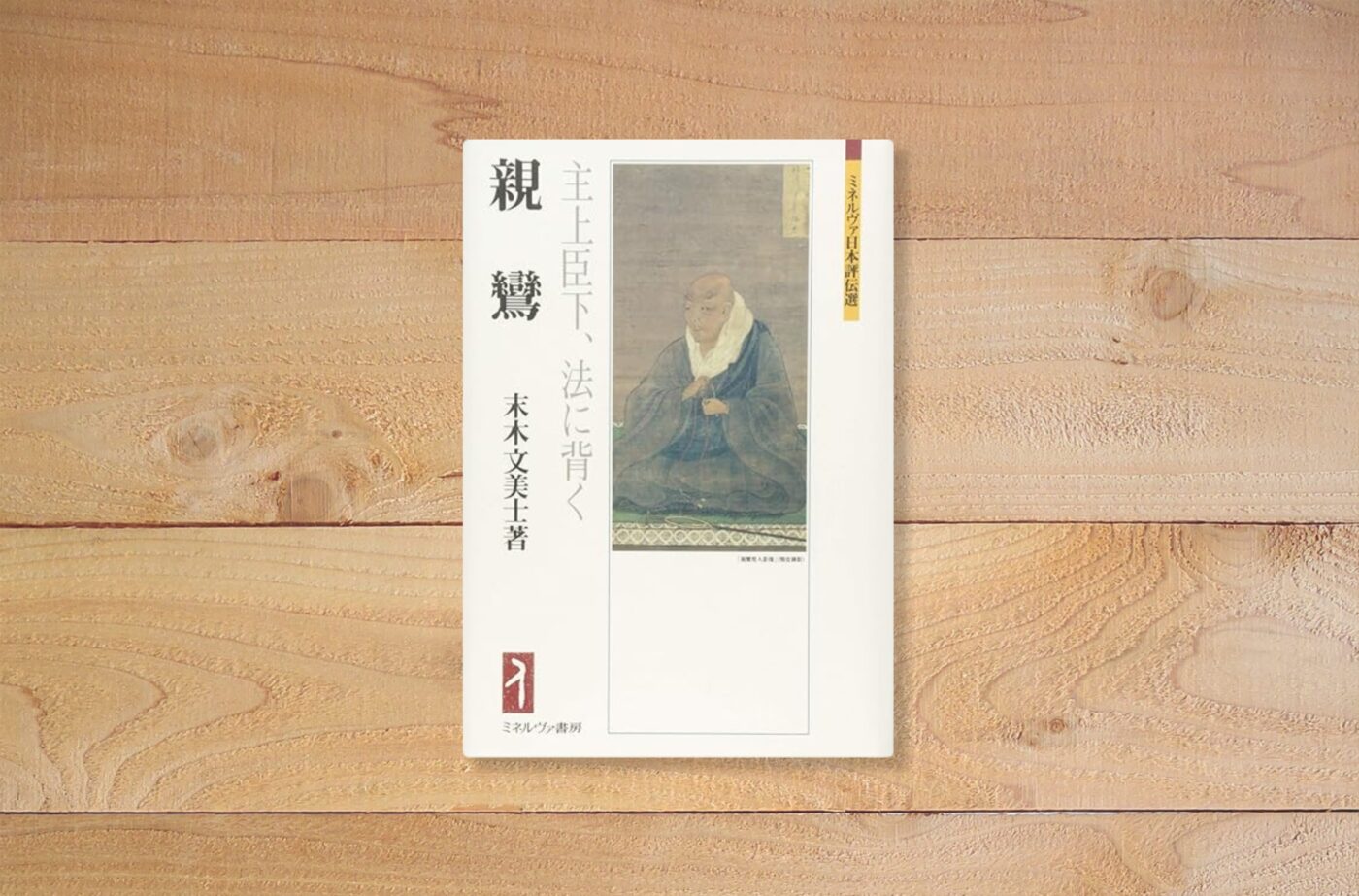蒲池明弘『「馬」が動かした日本史』あらすじと感想~日本は草原の国だった!?日本史の見え方が変わる刺激的な一冊!
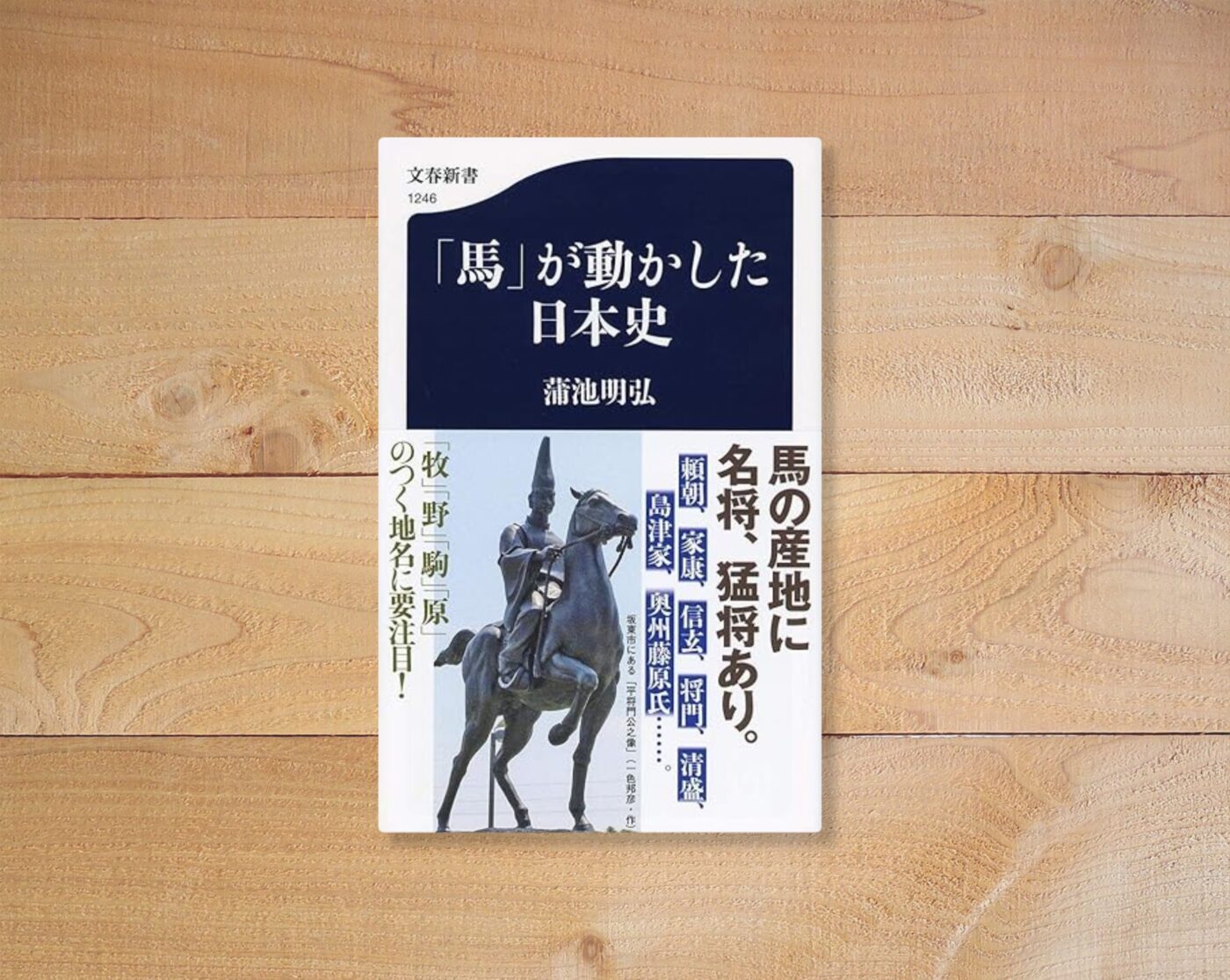
蒲池明弘『「馬」が動かした日本史』あらすじと感想~日本は草原の国だった!?日本史の見え方が変わる刺激的な一冊!
今回ご紹介するのは2020年に文藝春秋より発行された蒲池明弘著『「馬」が動かした日本史』です。
早速この本について見ていきましょう。
馬が日本の歴史を動かした!
もともと馬がいなかった日本列島に、馬が持ちこまれたのは五世紀ごろ。
古墳時代の中期である。それを期に、この国は大きく変貌を遂げた。
「馬」という補助線をひいて、日本の歴史を考えると、これまで謎とされてきた事象が説明できる。○なぜ世界最大の古墳は、ヤマト王権の中心地であった奈良ではなく、大阪・河内地方にあるのか。
○なぜ東日本最大の古墳は群馬県にあるのか。
○なぜ九州最大の古墳は宮崎県にあるのか。
○なぜ前方後円墳がもっとも多いのは千葉県なのか。
○なぜ武士政権は東日本に誕生したのか。こうした謎を解く鍵が「馬」なのである。
Amazon商品紹介ページより
山がちでありながら、じつは日本列島には馬の飼育に適した草原が広がっており、東アジア随一の巨大な馬の生産国だったのだ。
本書はとてつもなく刺激的な一冊です!これは驚きでした!
上の商品紹介にありますように、本書は「馬」という視点から日本史を見ていくのですが目から鱗の事実がどんどん出てきます。
まず、この記事のタイトルに書きましたが、日本が草原の国というのは全く考えたこともありませんでした。完全に山と森というイメージでしたが、実は草原の国でもあったのです。
著者も次のように述べています。
日本の歴史を考えるうえで、きわめて重要であるにもかかわらず、従来、軽視されていたことがある。それは、日本には「草原の国」としての一面があることだ。一説によると、縄文時代は列島の三割を草原的な環境が占めていたともいう。中国東北部からモンゴルに至る大草原をのぞけば、東アジア、東南アジア地域のなかで、日本は有数の草原のある国であり、それを背景とする馬産地が関東、東北、九州などに形成された。
文藝春秋、蒲池明弘『「馬」が動かした日本史』P21-22
そしてこの馬の産地がある場所に巨大な古墳が造られているという興味深い事実があります。上の本紹介にもありましたように、日本最大の古墳たる大仙古墳は政治の中心たる奈良ではなく河内国、今の堺に作られています。ここは当時馬の産地として多いに繁栄していた場所でした。
このことについて著者は次のように述べています。
なぜ河内に世界遺産の巨大古墳があるのか
以前、新聞社の経済部で勤務していたせいか、遺跡や文化財も、芸術的観点からではなく、経済の視点から見てしまうクセがある。戦国時代末期は日本史上、とくに景気の良かった時期だと推定できるが、バブル的な繁栄を織田信長、豊臣秀吉が築いた安土城、大坂城の記録によって知ることができる。世界遺産に登録されている姫路城をはじめ、全国各地に現存する国宝級の城郭の多くは、同じころに建てられたものだ。
金の茶室、金の茶碗。秀吉の黄金趣味が示しているとおり、この時代の景気の良さの原因は、日本列島の金、銀の採掘がピークにあったことだ。ことに銀は世界全体の産出量の三分の一に達していた時期がある。
一九八〇年代後半のバブル経済期には、不必要なほど大きな地方自治体の庁舎が各地につくられ、その後、「バブルの塔」と揶揄されることになる。思いもよらぬ経済的な恩恵がもたらされたとき、巨大な建造物をつくってしまうことは、古今東西、共通してみられる人間の行動パターンだ。古代的な蕩尽の結果ともいえる前方後円墳についても、ヤマト王権との関係をうんぬんする以前に、その地域に巨大古墳を造営するだけの経済力があったという事実を直視する必要を感じる。
巨大な前方後円墳のはしりといわれる箸墓古墳(二七八メートル、一部の研究者は卑弥呼の墓だと主張)は三世紀中ごろ、現在の奈良県桜井市に出現した。そのあと天皇陵の候補となるような巨大な前方後円墳は、桜井市、天理市など奈良盆地の南西部に造られ続けている。ところが五世紀になると、奈良盆地で大規模な古墳は造られなくなり、大阪府に巨大古墳の造営地が移動している。仁徳陵古墳、応神陵古墳をはじめとする世界遺産の巨大古墳は、前方後円墳発祥の地である奈良県ではなく、大阪府にある。
なぜ、巨大古墳の造営地は移動したのだろうか。いくつかの説があるが、五世紀ごろ、政治の中心が奈良から大阪の河内地方に移動していたからだという説が最もよく知られている。しかし、巨大古墳が造られた原因を「政治カ」ではなく、「経済カ」と見るならば、従来とは違った解釈が可能となる。本稿全体のテーマとして注目したいのは、関西における河内がそうであるように、東日本や九州でも代表的な馬産地に、そのエリアでは突出した規模の前方後円墳が存在していることだ。
文藝春秋、蒲池明弘『「馬」が動かした日本史』P47-49
特に「ヤマト王権との関係をうんぬんする以前に、その地域に巨大古墳を造営するだけの経済力があったという事実を直視する必要を感じる」というのは非常に鋭い指摘ですよね。『「政治力」ではなく「経済力」にも注目すべき』というのはあらゆるジャンルのことにも応用が利きそうです。仏教史を考える上でもこれは重要な視点だと思われます。
そして上の引用の後半にもありましたように、馬産地があるところに巨大な古墳が造られているというのも興味深いですよね。そしてこの引用箇所の直後に「日本で一番前方後円墳が多いのはどこでしょうか」という問いが私達に投げかけられるのですが、その答えもびっくりです。なんと、日本で一番前方後円墳が多いのは千葉県なのだそうです。その理由はもう皆さんもわかりますよね。そうです。ここにも広大な馬産地があったのでした。
本書ではこのように馬産地と日本史の意外な繋がりを見ていくことになります。これら巨大古墳の話の後には武士の成立や繁栄についても語られていきますのでこれはもう面白くてたまりませんでした。
本書は私達のものの見方をひっくり返す実に刺激的な作品です。これは楽しい読書でした。ぜひぜひおすすめしたい一冊となっています。ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。
以上、「蒲池明弘『「馬」が動かした日本史』あらすじと感想~日本は草原の国だった!?日本史の見え方が変わる刺激的な一冊!」でした。
Amazon商品紹介ページはこちら
次の記事はこちら
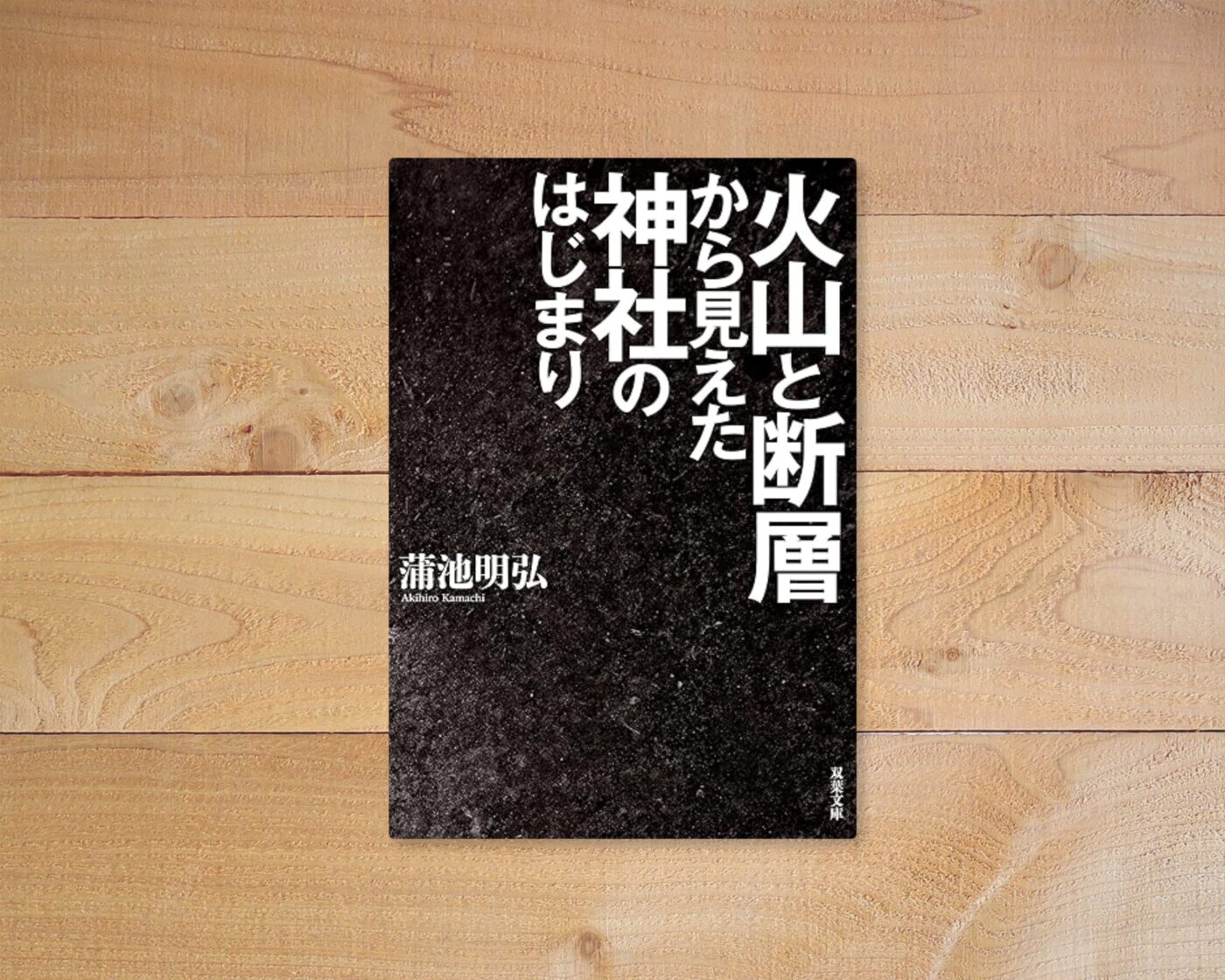
前の記事はこちら
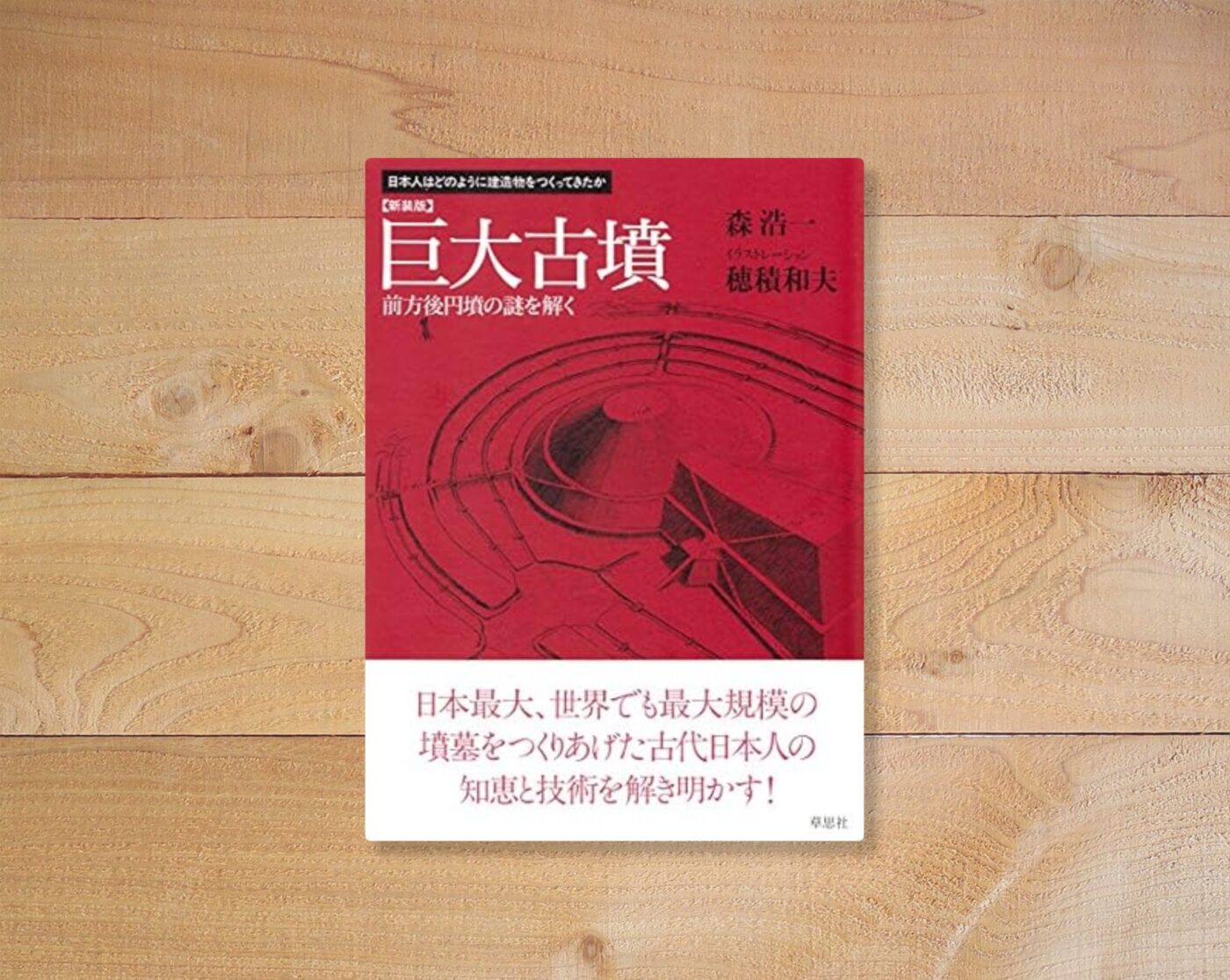
関連記事