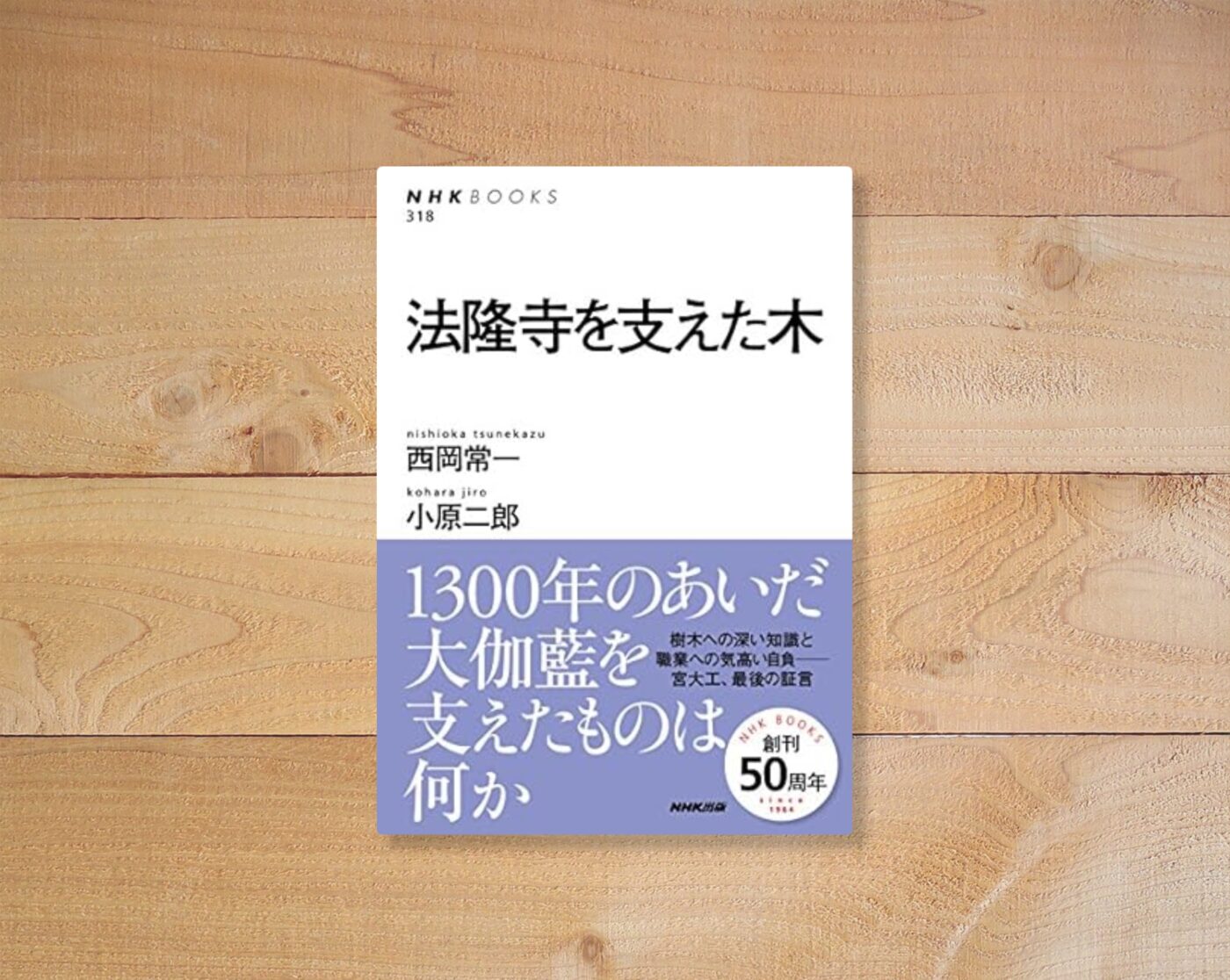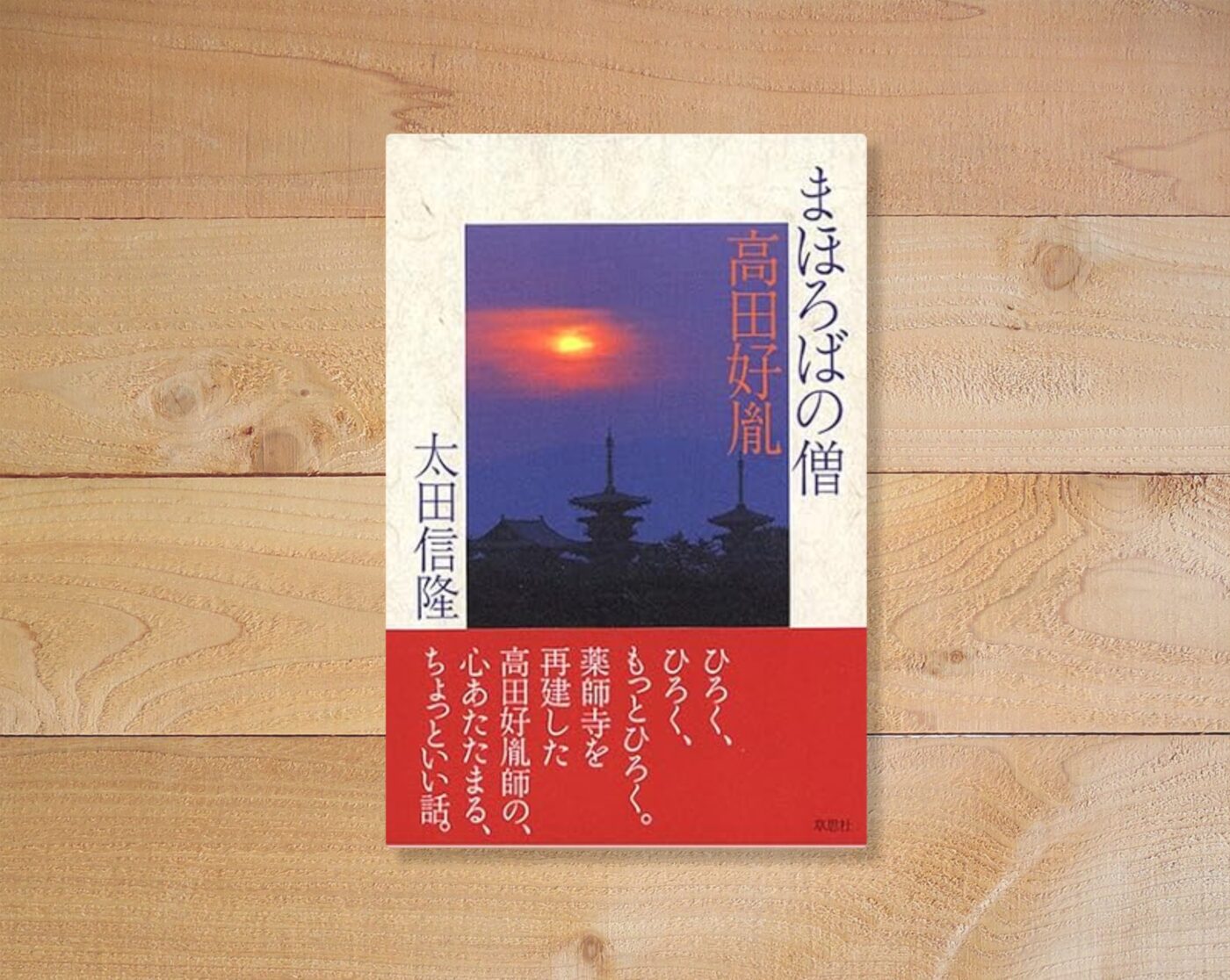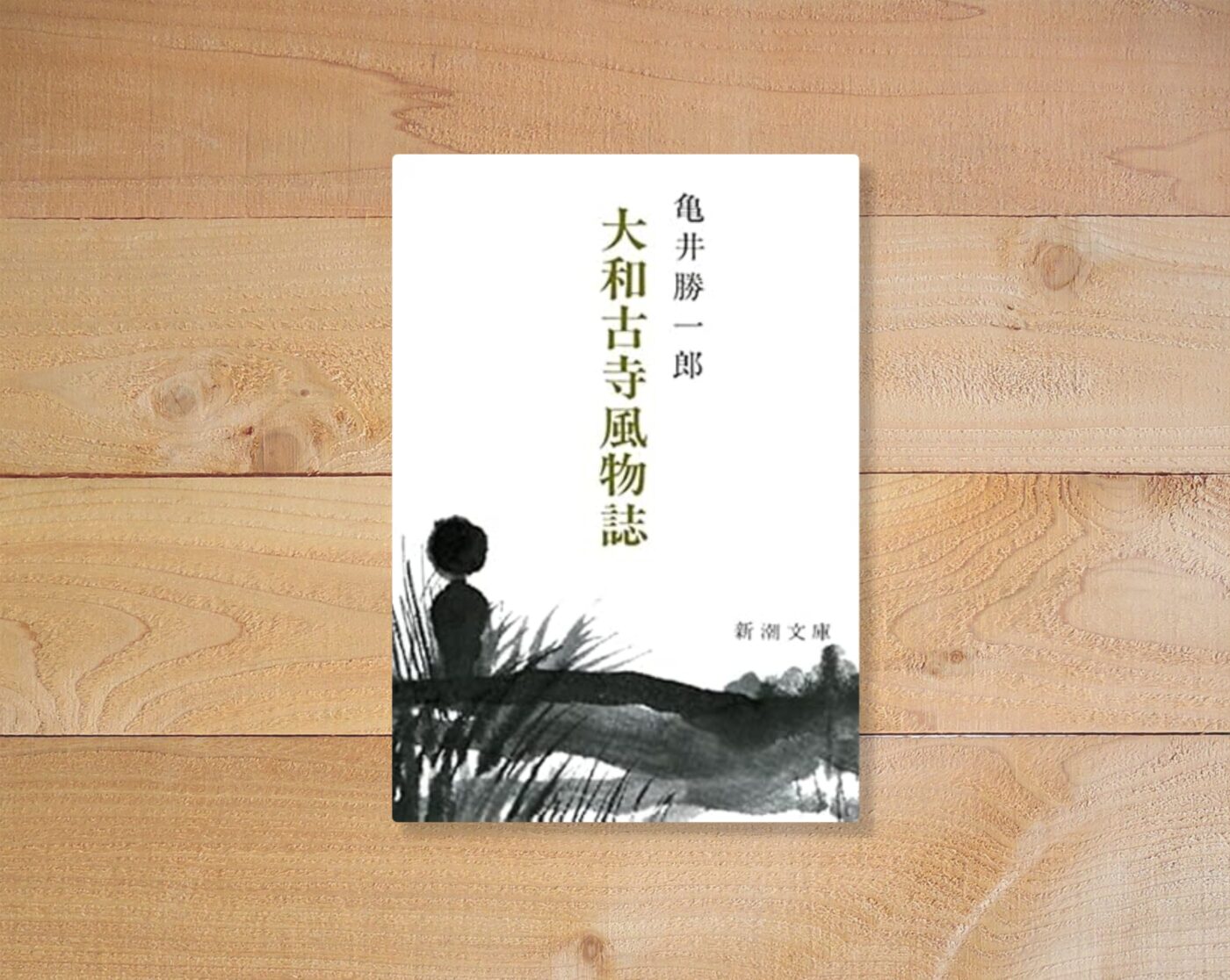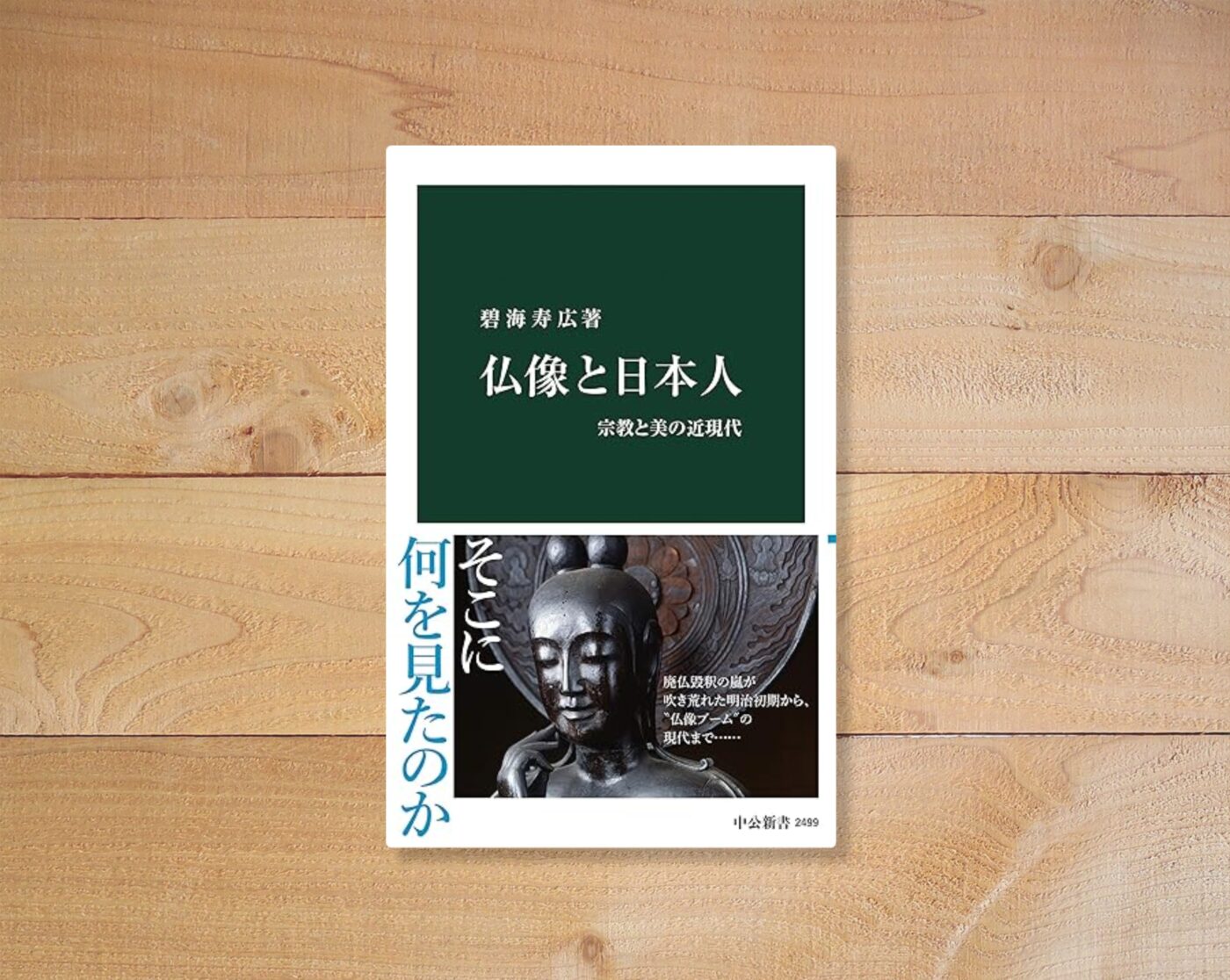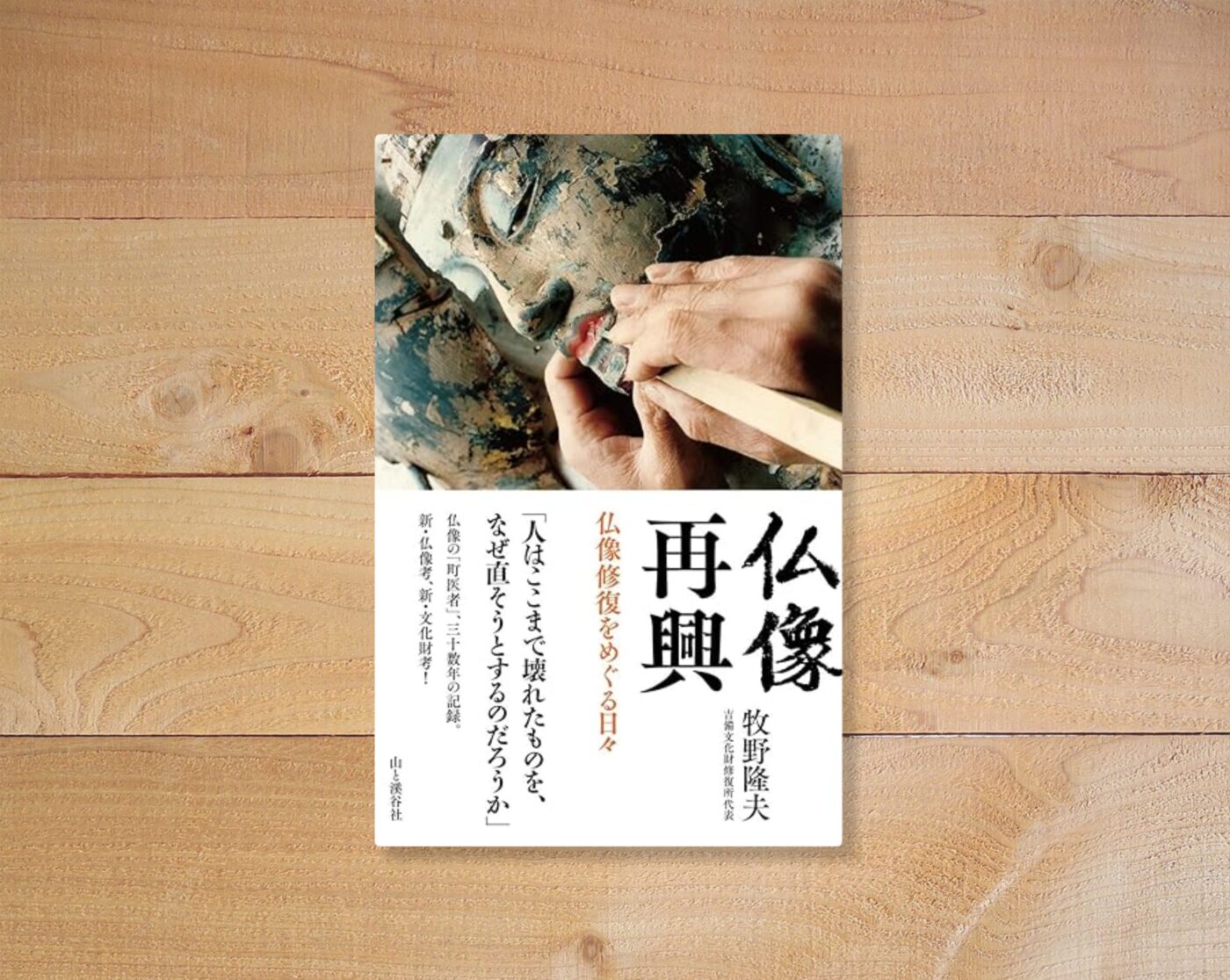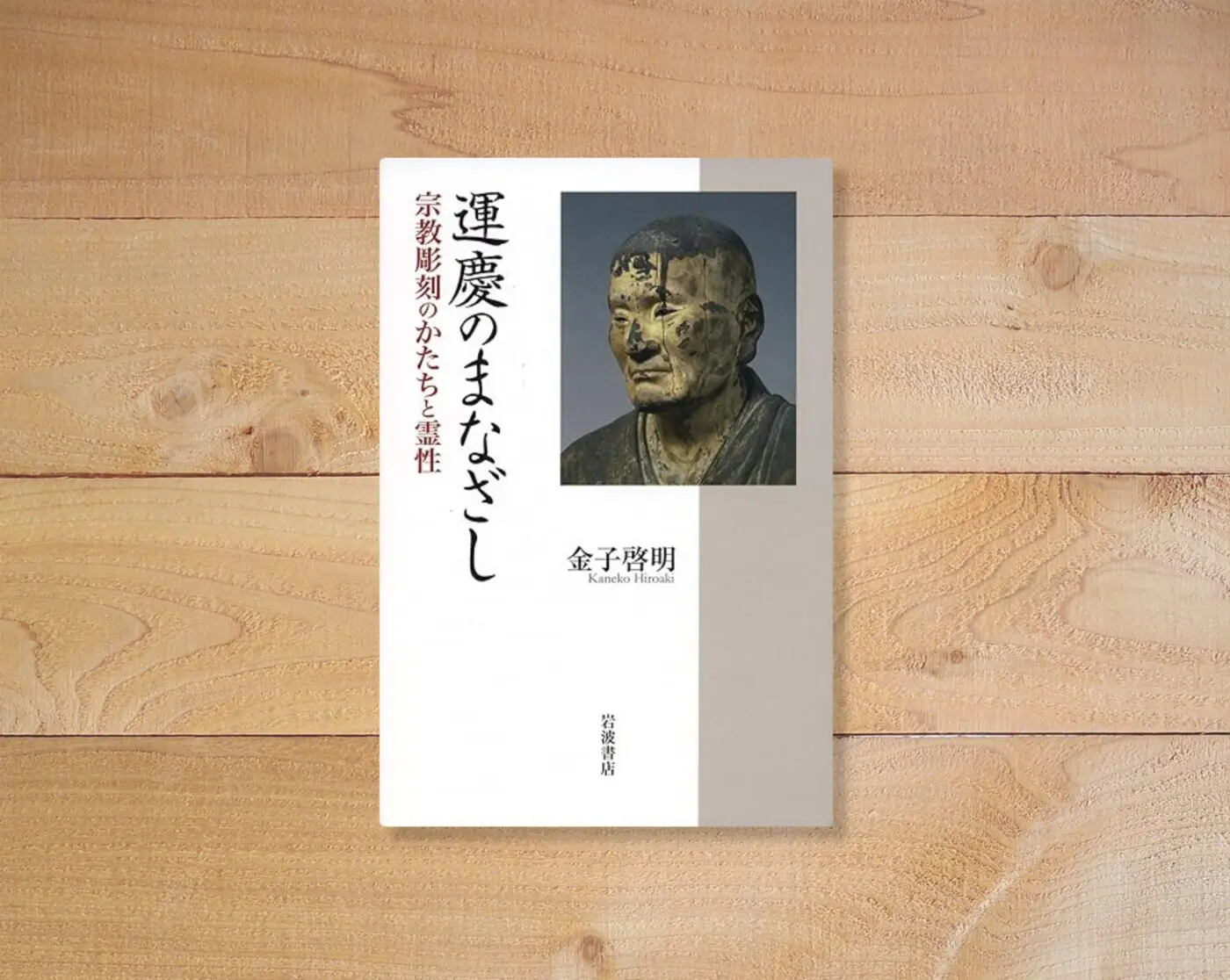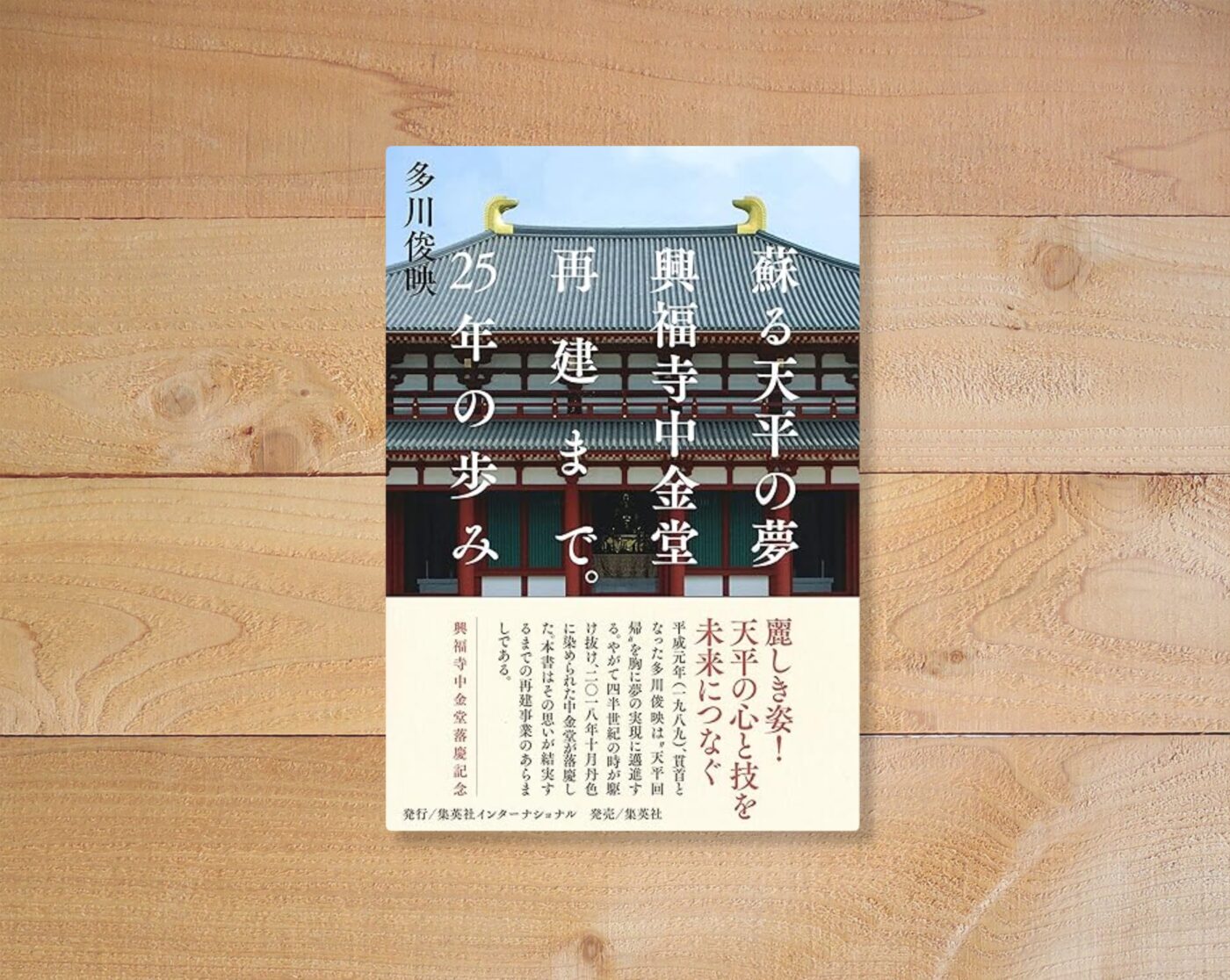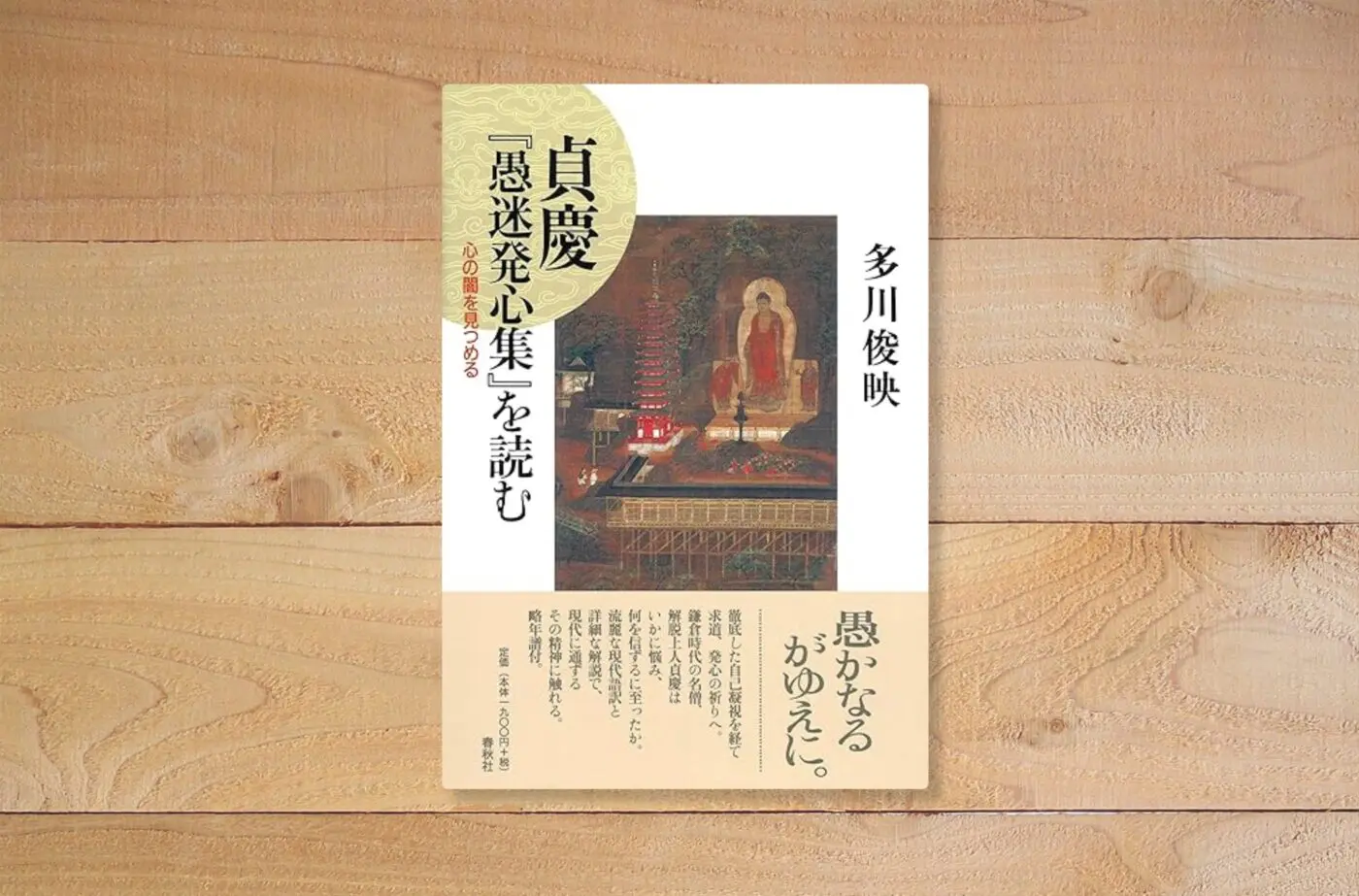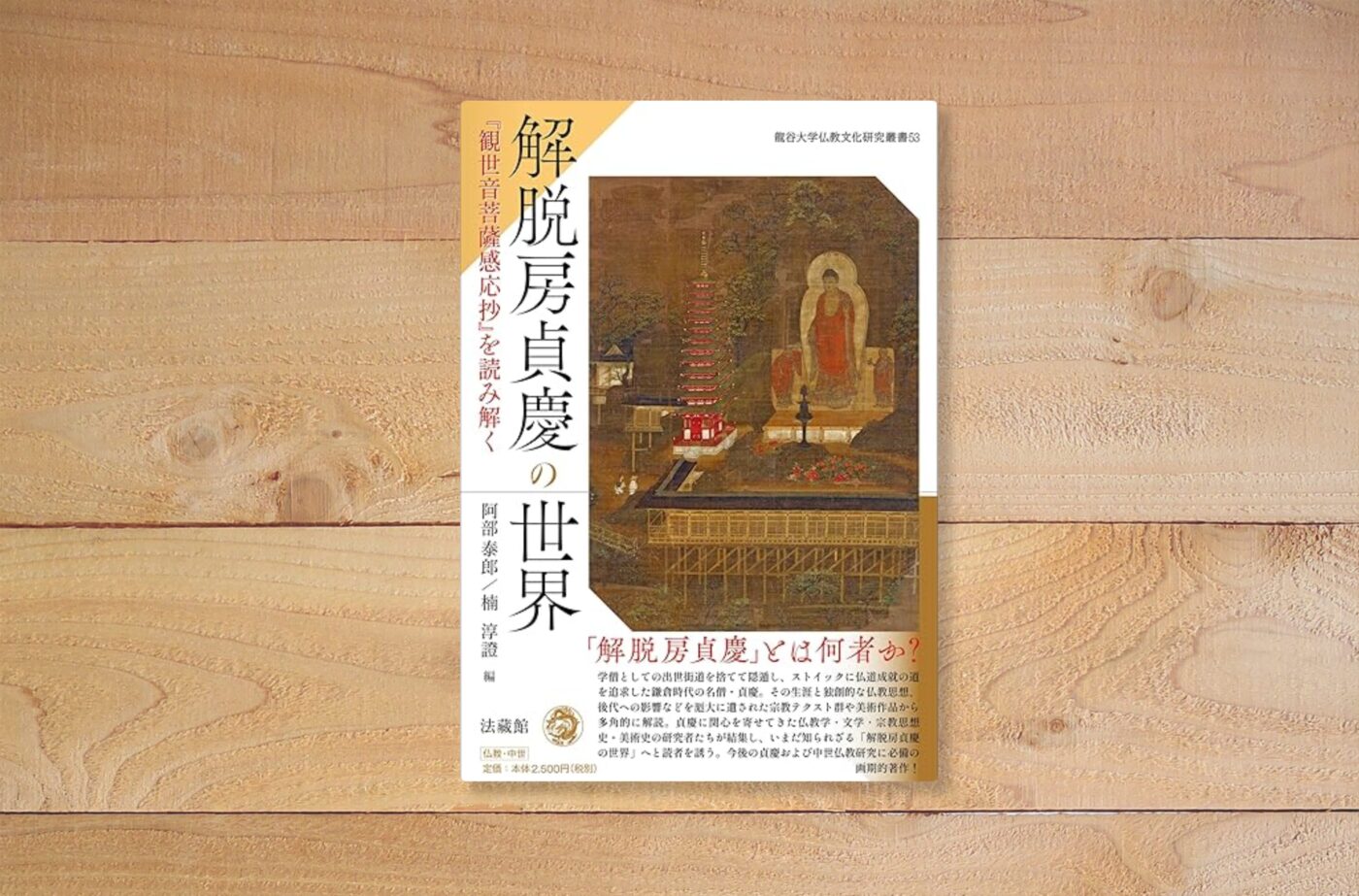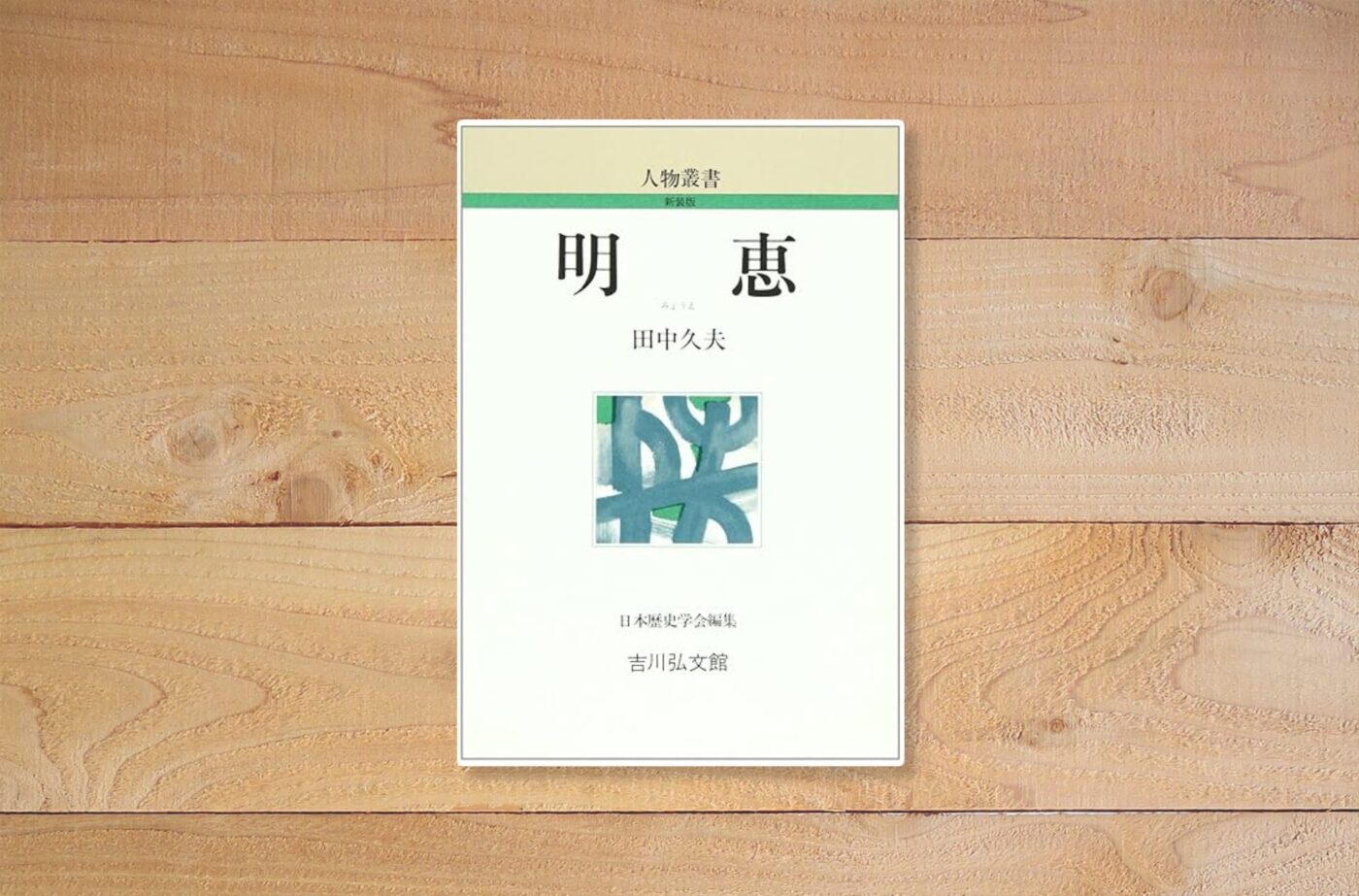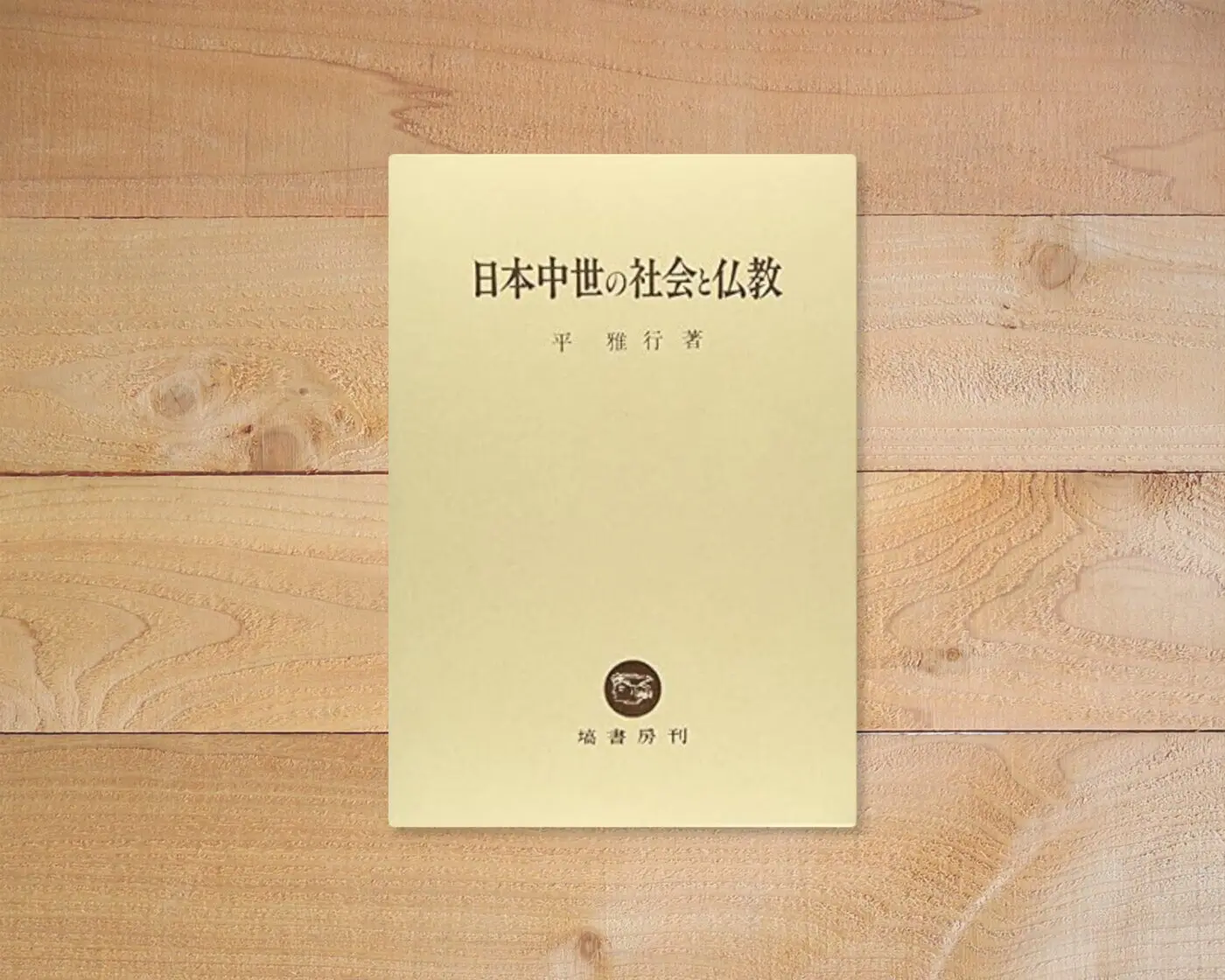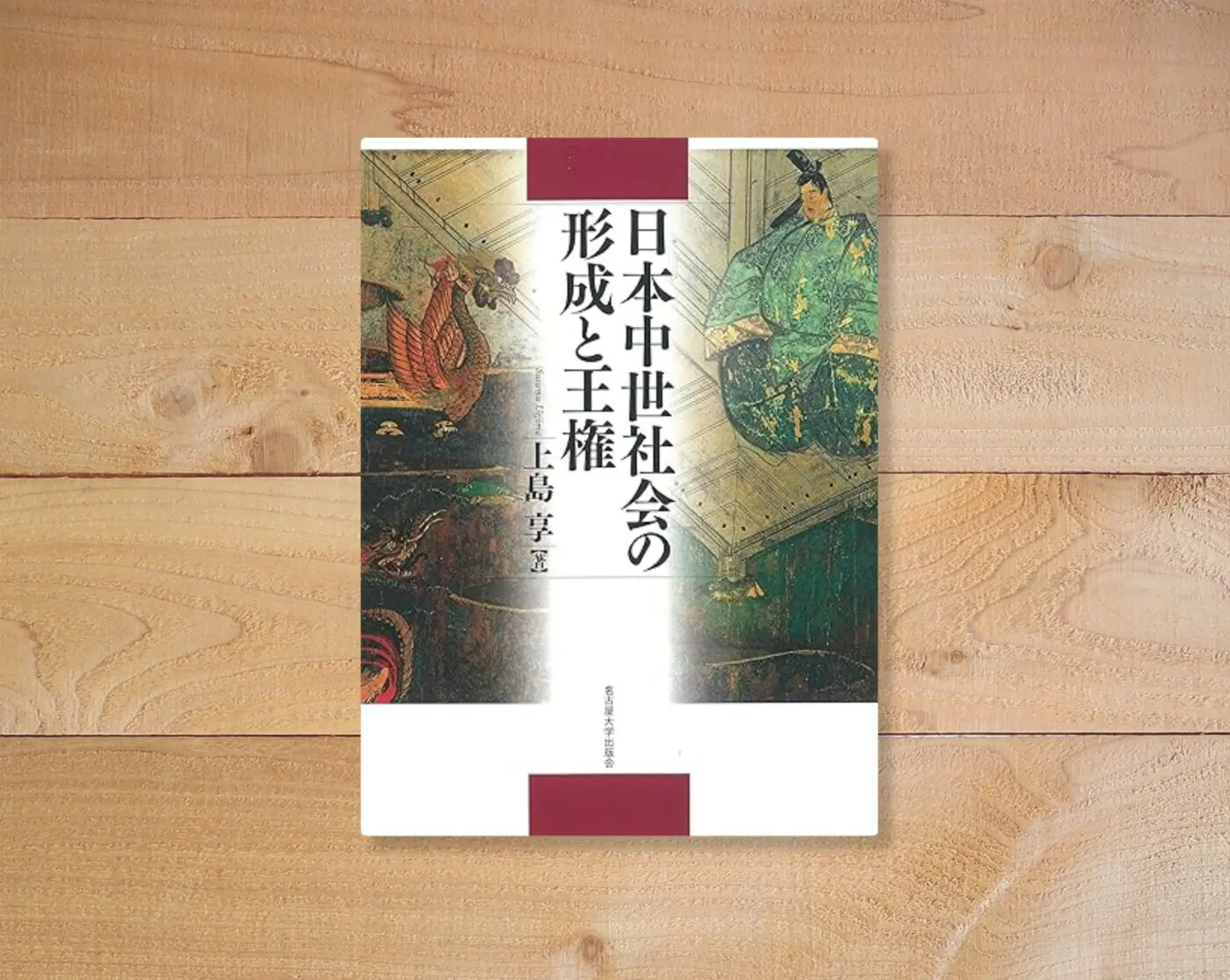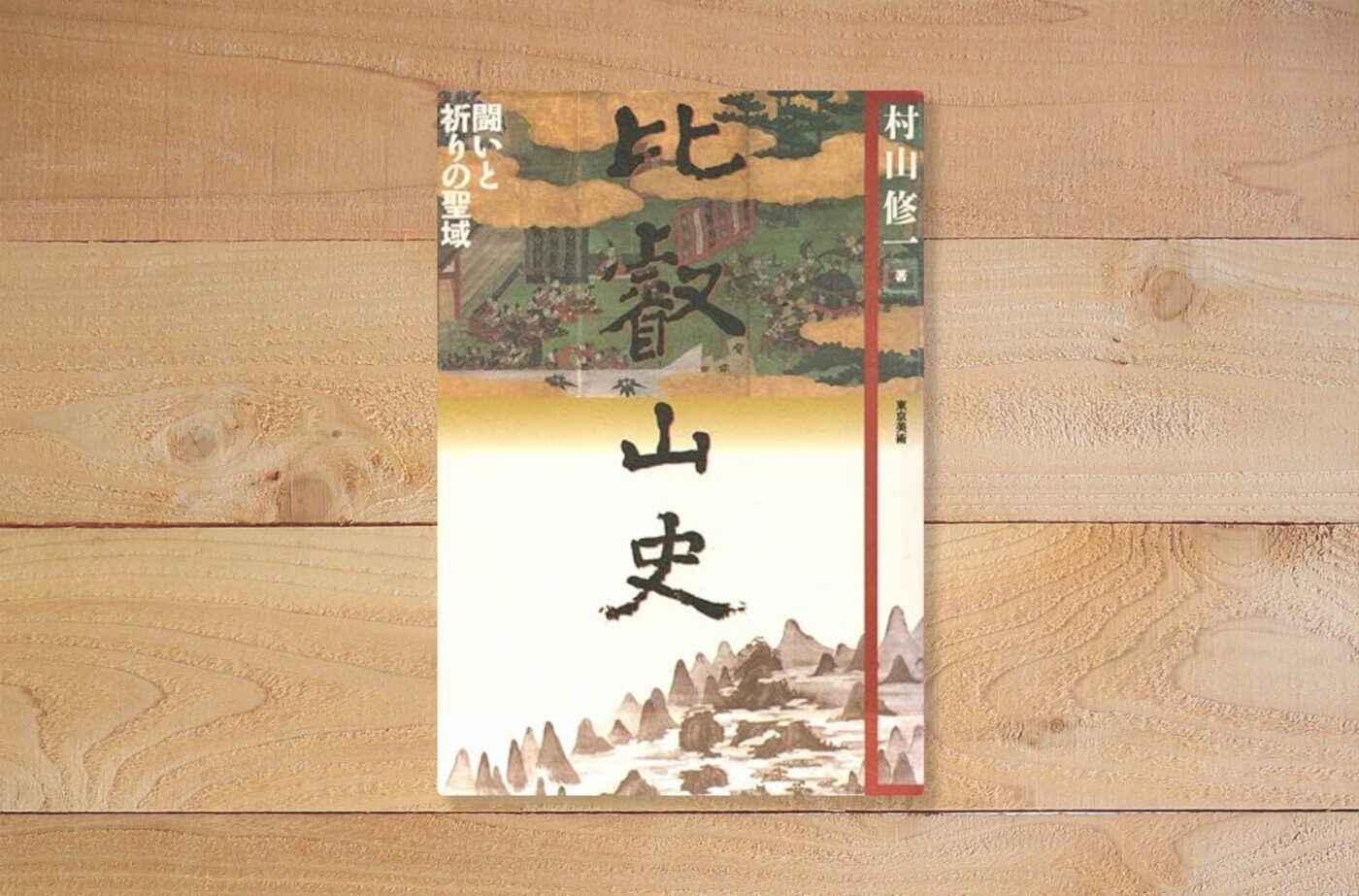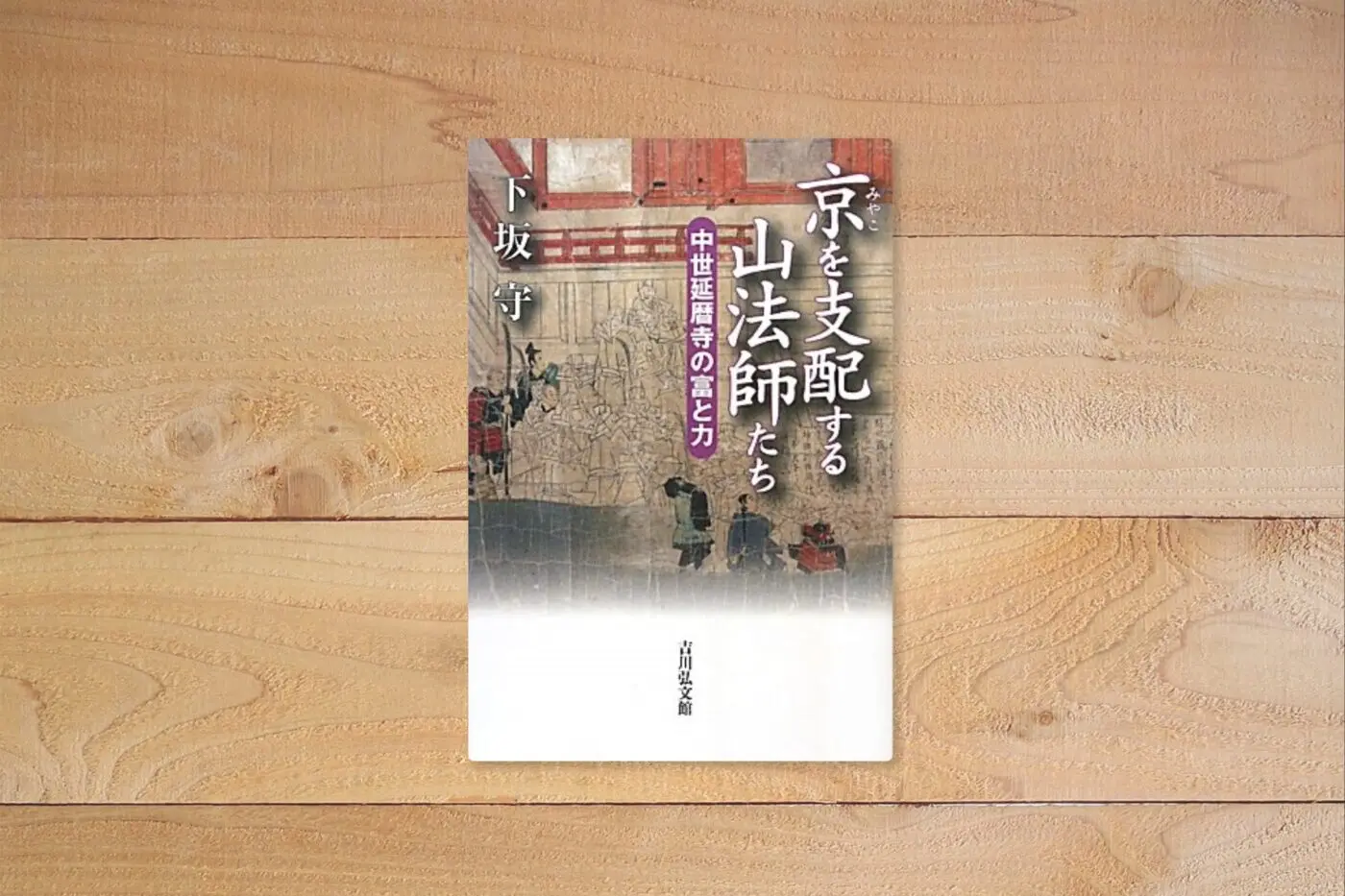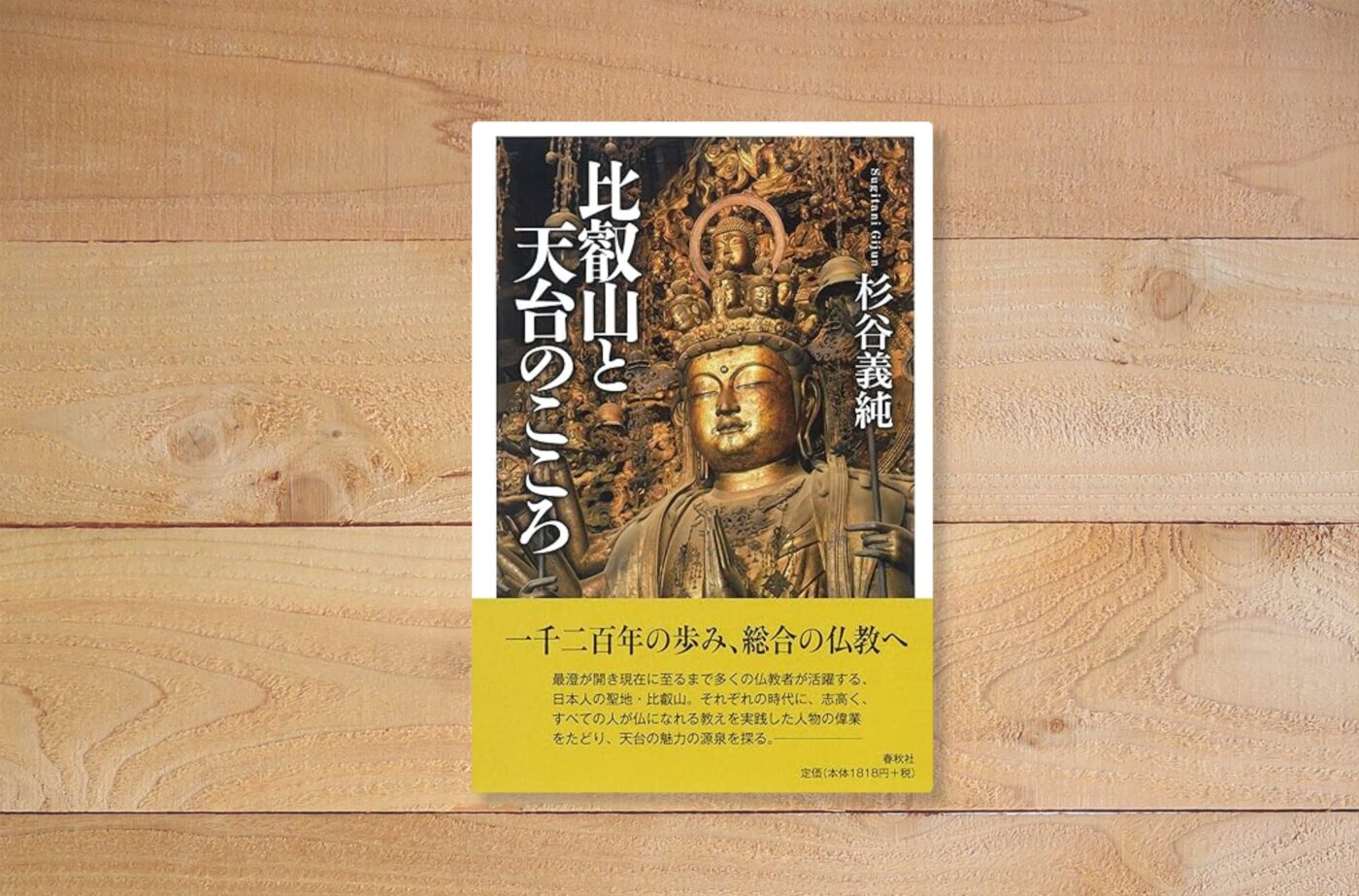西岡常一、小川三夫、塩野米松『木のいのち木のこころ〈天・地・人〉』あらすじと感想~古寺を守り続けた伝説的な宮大工の言葉を聞けるおすすめ本
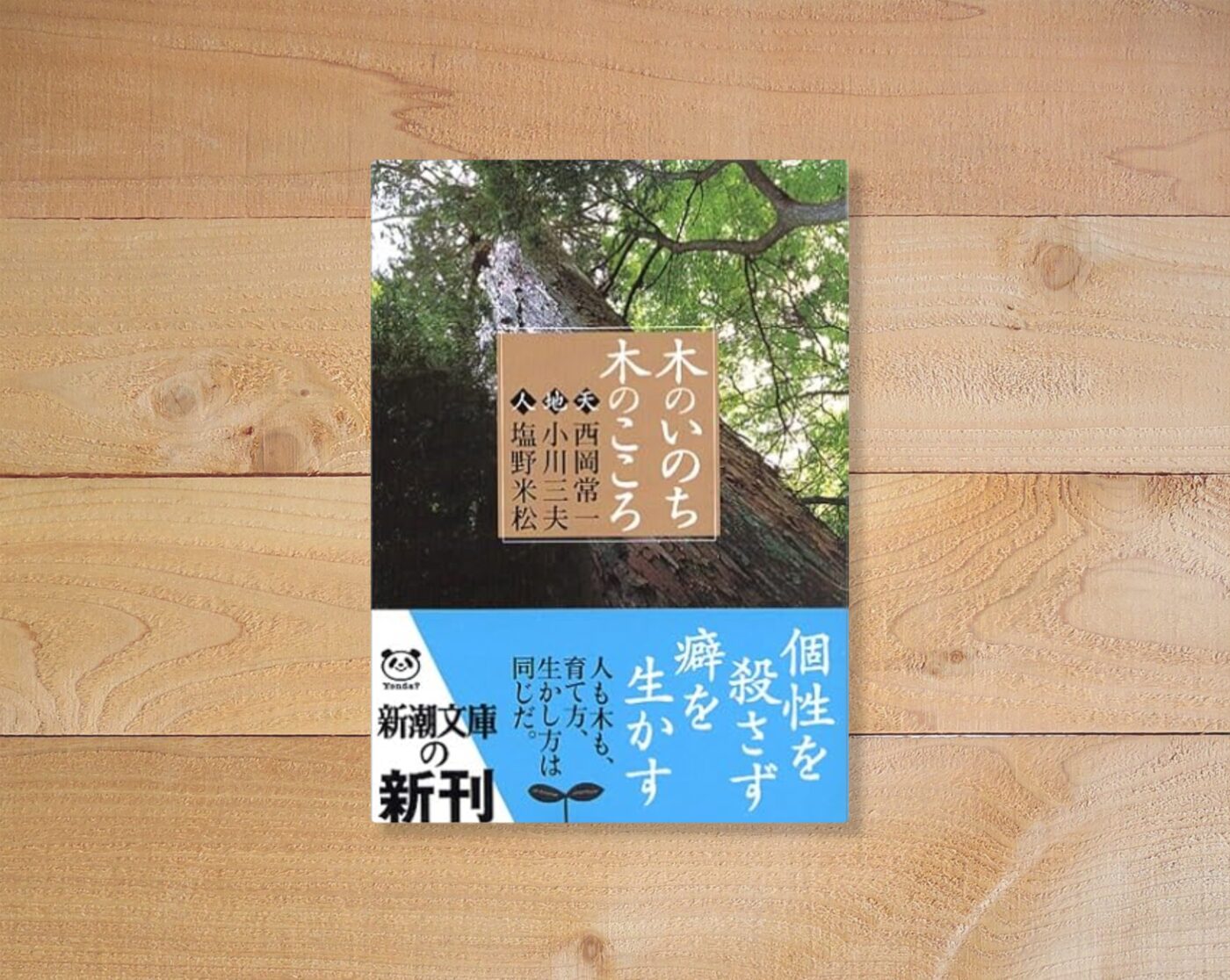
西岡常一、小川三夫、塩野米松『木のいのち木のこころ〈天・地・人〉』あらすじと感想~古寺を守り続けた伝説的な宮大工の言葉を聞けるおすすめ本
今回ご紹介するのは2005年に新潮社より発行された西岡常一、小川三夫、塩野米松著『木のいのち木のこころ〈天・地・人〉』です。
早速この本について見ていきましょう。
個性を殺さず癖を生かす。人も木も、育て方、生かし方は同じだ――。
Amazon商品ページより
最後の宮大工とその弟子たちが充実した毎日を語り尽す。
法隆寺を1300年守ってきたのは、職人の手から手へと引き継がれてきた技と知恵。それは決して言葉にできない手の記憶である。“最後の宮大工”西岡常一が木と人の育て方を語る〈天〉の巻。三度追い返されながらも遂に西岡の唯一の内弟子となり、夢を実現させた小川三夫が、宮大工の未来を語る〈地〉の巻。さらに小川が主宰する鵤工舎の若者19人へのインタビュー〈人〉の巻。聞き書きの名作。

本書の著者のひとり、西岡常一は法隆寺の宮大工で日本の数々の古寺を修復した伝説的な棟梁です。上のNHKアーカイブスでは3分ほどの短い動画で西岡棟梁について知ることができますのでぜひご覧ください。(リンクはこちら)
さて、私が本書を手に取ったのは以前当ブログで紹介した太田信隆著『まほろばの僧 高田好胤』がきっかけでした。この本では薬師寺再建に奔走する高田好胤師の伝記が語られますが、その薬師寺再建のキーパーソンとしてこの西岡棟梁がクローズアップされていたのです。
この西岡棟梁の仕事はまさに伝説的なものでした。法隆寺の宮大工を代々継いできた家に生まれた西岡棟梁は幼い頃から宮大工として育てられます。本書ではそんな職人としての生涯や、仕事論、教育についての珠玉の教えを聞くことができます。
その中でも特に印象に残ったのが次の箇所です。
明治からですな、大工が尊敬されなくなったのは。建築物と建築学者が別れ、仕事師と学者が別れてからですわ。西洋の学問が入ってきて、建築学というようなもんが幅をきかせて、木をいじる大工でない者が設計するようになってからですな。とにかく明治以来、建築学者というのが出てきた。そして設計事務所ができて、分業になりましたわな。設計は設計事務所、積算は積算というふうに。昔の棟梁は、石から材木から、いっさい自分の責任でやったんですな。今じゃ材木は材木屋、石は石屋というふうになってしまった。それもたんなる職業で、道具が使えるだけの道具使いになってしもうた。そうやおませんのや。
学者があって建造物があるのやなくて、建造物があって初めて学問がありますのや。飛鳥様式だとか、白鳳様式だとかといいますが、それは後からついてきたもんですわ。そうでっしゃろ、何でも計算や形に当てはめて考えるから物事が逆さまになりますのや。
コンクリートや鉄やったら実験して強さや耐用年数が計算できるかもしれませんが、木はそうはいきませんのや。現代建築にしてもそうでっせ。何でもかんでも計算通りにいくと思うとる。
木は生きているんです。計算通りにはいかんのですわ。一本一本、木の性質は違いますわ。そりゃ、そうですね。人間と同じです。育った場所も気候も、風当たりも日当たりも、性根もまったく違いますのや。それをみんな同じものだとして計算して、そのうえ目の前で設計図通りに仕上げればいいと思うてますやろ。けど、造られたものはその後、何十年も、何百年も、ものによっては千年を越えて建っていますし、残っていきますのやで。
私ら檜を使って塔を造るときは、少なくとも三百年後の姿を思い浮かべて造っていますのや。三百年後には設計図通りの姿になるやろうと思って、考えて隅木を入れてますのや。
こうしたことは学校や本では学べません。大工や職人の仕事というのは体で覚え、経験を通して学んだ学問なんですわ。それが無視されてますな。軽んじられてますわ。何でも計算できると思っているんですな。そして、そうした学問が重要視されてますな。本のなかや議論のうえでは、そらいいでっせ。しかし、私らは実際に堂や塔を造らなならんのです。大きな立派な建物を建ててますが、名を残すわけではないんです。造ったものだけが判断される。頼りにするのは先人の残してくれた知恵と積み重ねてきた経験ですな。それと勘です。長いこと木を扱い、金槌で釘を打ち込んできた経験が教えてくれる勘ですわ。
新潮社、西岡常一、小川三夫、塩野米松『木のいのち木のこころ〈天・地・人〉』P64-67
この後も西岡棟梁は学者について「体験や経験を信じないんですな。本に書かれていることや論文のほうを、目の前にあるものより大事にするんですな。学者たちと長ごうつきあいましたけど、感心せん世界やと思いましたな。」と述べています。
宮大工の世界では明治維新の後に建築学という学問が登場し、実践の場で積み重ねられていた経験や勘が軽んじられていた・・・私はこの歴史に既視感があります。これはまさに日本仏教の世界でも似たような現象が起こっていたのです。日本でも明治に入ってから仏教学というものが導入され、旧来の仏教は迷信的なもの、堕落したものとして排斥された歴史があります。このことについては以前当ブログでも紹介したフィリップ・C・アーモンドの『英国の仏教発見』で詳しく論じられていました。
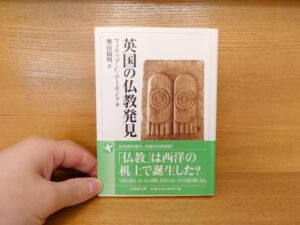
現場での経験が軽んじられ、計算できる実証的なもののみが重視される風潮。それはまさに文献を主体とした明治以後の仏教学にも当てはまります。
建築にせよ仏教学にせよ、計算できる学問としてそれらを全否定するわけではありませんが、過去の英知や現場で継承され続けてきた智慧まで無下に否定するのはやはり問題があると私も思います。
西岡棟梁も上の言葉の直後に「しかし、なかにはよく私らの話を聞いてくれる学者もおりましたし、自分の学説にしばられん人たちもおりました。そうした学者は本当の研究者やなと思いましたものな。」と述べています。学問そのものが間違っているわけではないのです。ただ、その姿勢が問題なのだということが本書でも感じられたのでありました。本書ではそうした学者との闘いが詳しく語られていますのでぜひ読んで頂きたいと思います。
そしてもうひとつ西岡棟梁の言葉で紹介したい箇所があります。それがこちらです。
世の中全体がせちがらくなってきました。人を育てるのも大量生産で、なにしろ早くですわ。それとそんなに丁寧にものを造ってもらわんでいい、適当な大量生産の安いものでいいというんですからな。そうすると、せっかく長い時間をかけて育てても活躍の場所がなくなってしまうんですな。職人の仕事のよさは一つ一つ違う材料のよさを引き出してものを造ることやけど、そんなもん、いらんというんですからな。
日本の文化はそうやって、自然の持つ素材のよさを生かして、自然のなかに置いて調和の取れるものを作っていくなかで生まれ、育ってきたんですけどな。
今は石油を材料にしてどんなに扱っても壊れん、隣りの人と同じもの、画一的なものを作れというんですからな。いつまでも壊れん、どないしてもいいというたら作法も心構えも何にもいらなくなりますわな。茶碗は人が丁寧に作ったもんでした。下手に扱えば壊れますな。二つと同じものがないんやから、気に入ったら大事にしますな。扱いも丁寧になります。他人のものやったら、なおさらそうでっせ。人様が大事にしているものを壊したらならん、と思いますやろ。物に対しても、人に対しても思いやりがそうしたなかから生まれるもんですわ。文化というのは建物や彫刻、書というものだけやおまへんのや。
均一の世界、壊れない世界、どないしてもいい世界からは文化は生まれませんし、育ちませんわな。職人もいりません。なにしろ判断の基準が値段だけですからな。これやったら学校も教育もそれでいいということになるんでしょうな。悲しいですな。
法隆寺や薬師寺に参拝に来ても、すぐに帰らんとよく見てくださいな。学校で習った、ここが千三百年たった日本で一番古い建物やとか、これが唯一残されている白鳳の建造物やといわれて、それだけで通りすぎるんやなしに、そこにどれだけの人が参加してこれを造ったのか、すべて人の手で造られたんやということを、ちょっとでも考えて見てくれるといいですな。
これらの建物の各部材には、どこにも規格にはまったものはありませんのや。千個もある斗にしても、並んだ柱にしても同じものは一本もありませんのや。よく見ましたら、それぞれが不揃いなのがわかりまっせ。どれもみんな職人が精魂を込めて造ったものです。それがあの自然のなかに美しく建ってまっしゃろ。不揃いながら調和が取れてますのや。すべてを規格品で、みんな同じものが並んでもこの美しさはできませんで。不揃いやからいいんです。
人間も同じです。自然には一つとして同じものがないんですから、それを調和させていくのがわれわれの知恵です。
徒弟制度といいましたら古いもんといわれていますが、古いからすべてが悪いというもんやないやないですか。すべて同じ人間にしようという教育よりは、よっぽど人間的な育て方でっせ。
私は長いこと法隆寺や薬師寺などの古代建築を見て不揃いの木を扱ってきましたが、自分が育てられて来た徒弟制がすべて悪いとは思いませんな。むしろこんな時代やから、個性を大事にして人を育てるという意味では、もっと見直されてもいいんと違いますか。
新潮社、西岡常一、小川三夫、塩野米松『木のいのち木のこころ〈天・地・人〉』P81-83
本書ではこの後も西岡棟梁の教育論が語られるのですが、私としては特に上の「法隆寺や薬師寺に参拝に来ても、すぐに帰らんとよく見てくださいな。学校で習った、ここが千三百年たった日本で一番古い建物やとか、これが唯一残されている白鳳の建造物やといわれて、それだけで通りすぎるんやなしに、そこにどれだけの人が参加してこれを造ったのか、すべて人の手で造られたんやということを、ちょっとでも考えて見てくれるといいですな。」という言葉が印象に残っています。
たしかに、法隆寺や薬師寺、東大寺は修学旅行などでも多くの人が訪れると思います。ですがその多くがただ通り過ぎるだけになってしまっているのも残念ながら事実なのではないでしょうか。しかし、西岡棟梁の言われるように、そこにどれだけ多くの人が関わり、どれほど高度な技術で作られたかに思いを馳せるならばその見え方は確実に変わってきますよね。私自身もこの本を読んで古寺に対する見方が変わりました。この本を読めば奈良、京都巡りにおいてもより深く個々の寺を味わえること間違いなしです。
そして本書の特徴としてはこの西岡棟梁の弟子である小川三夫氏と、さらにその弟子達の言葉も聞くことができます。西岡棟梁の技術や職人魂がどのように受け継がれているか、そして現代における徒弟制度のありようも見ていくことができます。昭和から平成にわたって伝統技術がどう継承されていったのか、そしてこれからどうなっていくのかということも本書では考えさせられます。これは普段なかなか考える機会すらないテーマですので、とても刺激的でした。
奈良の古寺を考える上でも本書はとてもおすすめです。ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。
以上、「西岡常一、小川三夫、塩野米松『木のいのち木のこころ〈天・地・人〉』あらすじと感想~古寺を守り続けた伝説的な宮大工の言葉を聞けるおすすめ本」でした。
Amazon商品ページはこちら
次の記事はこちら
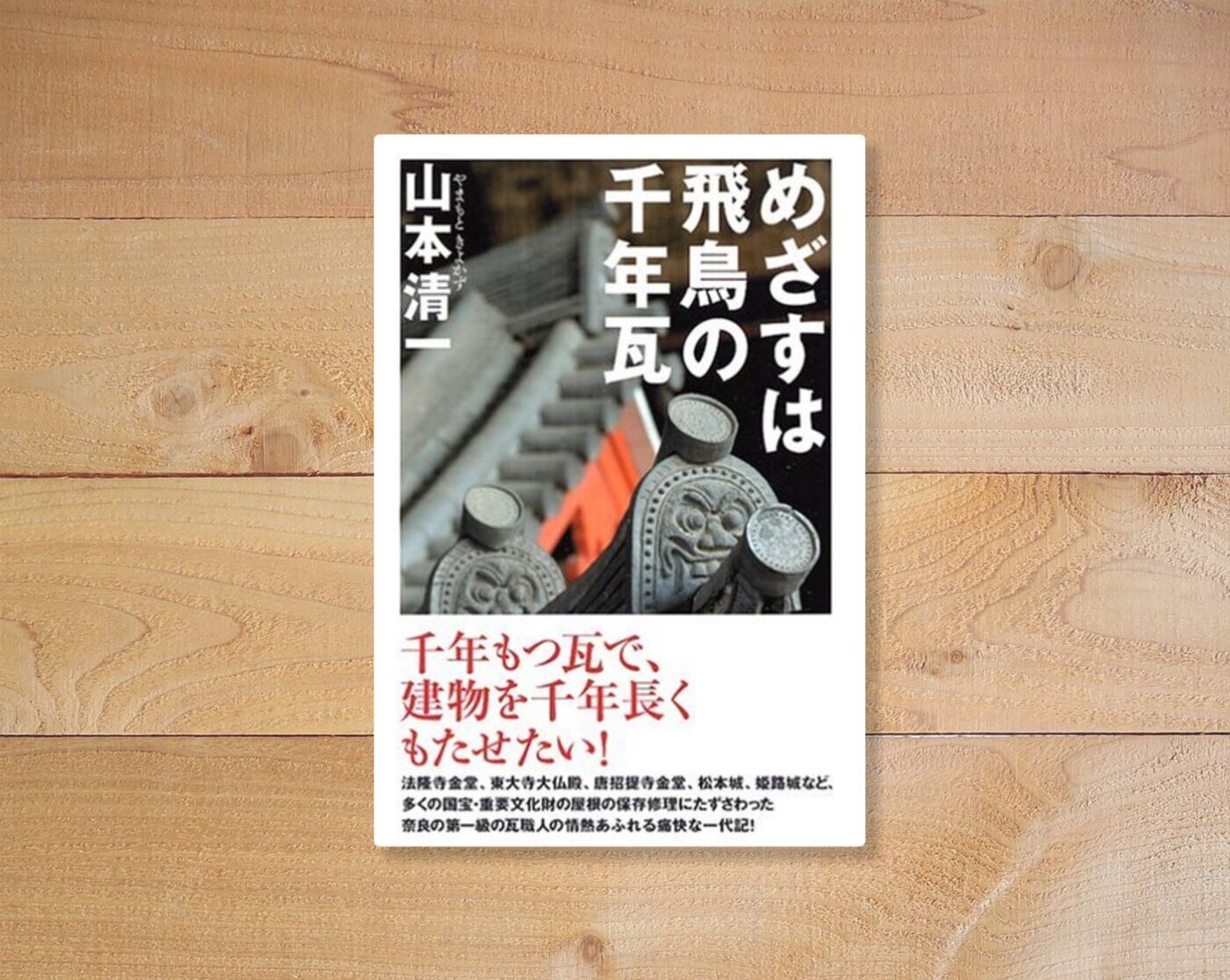
前の記事はこちら
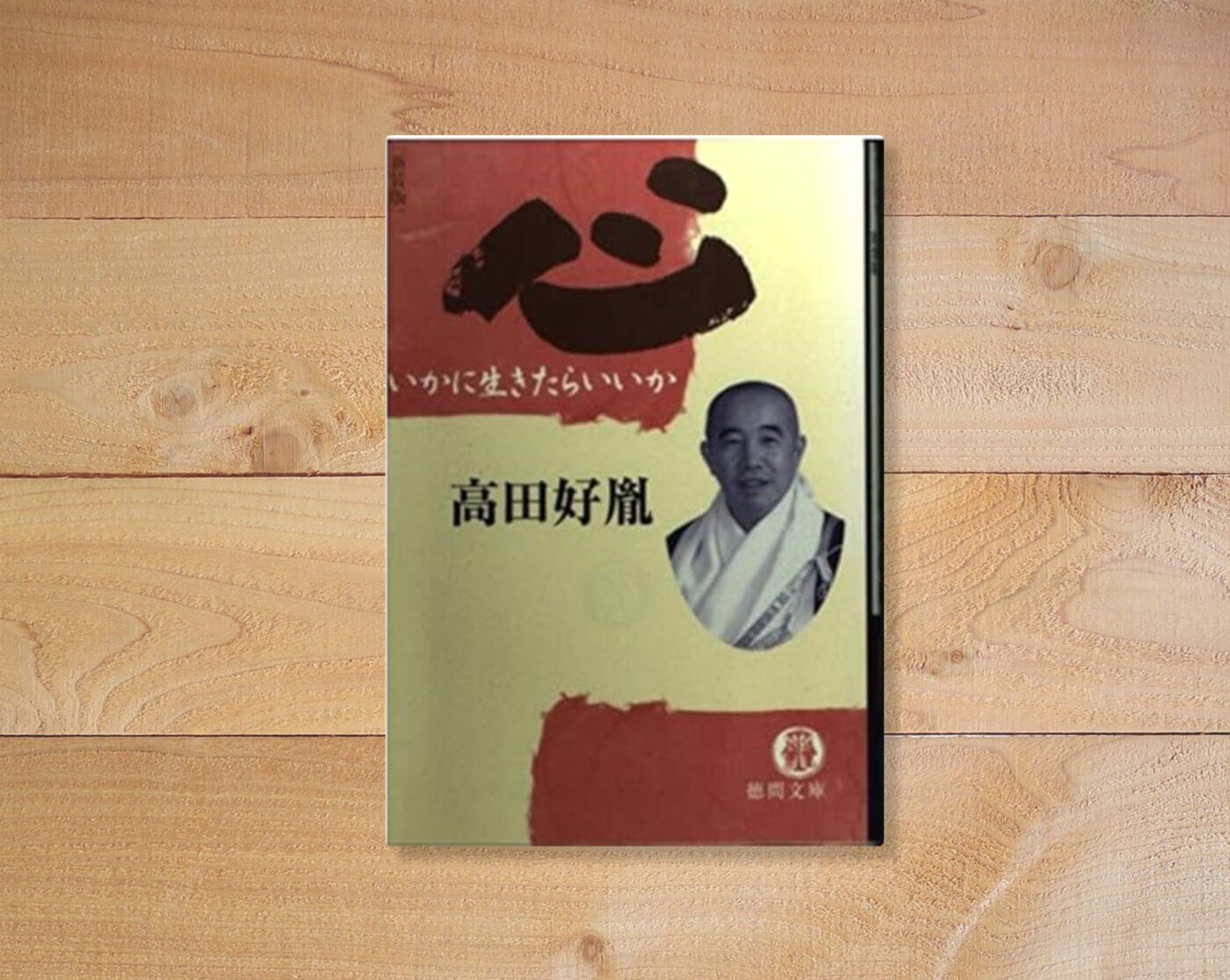
関連記事