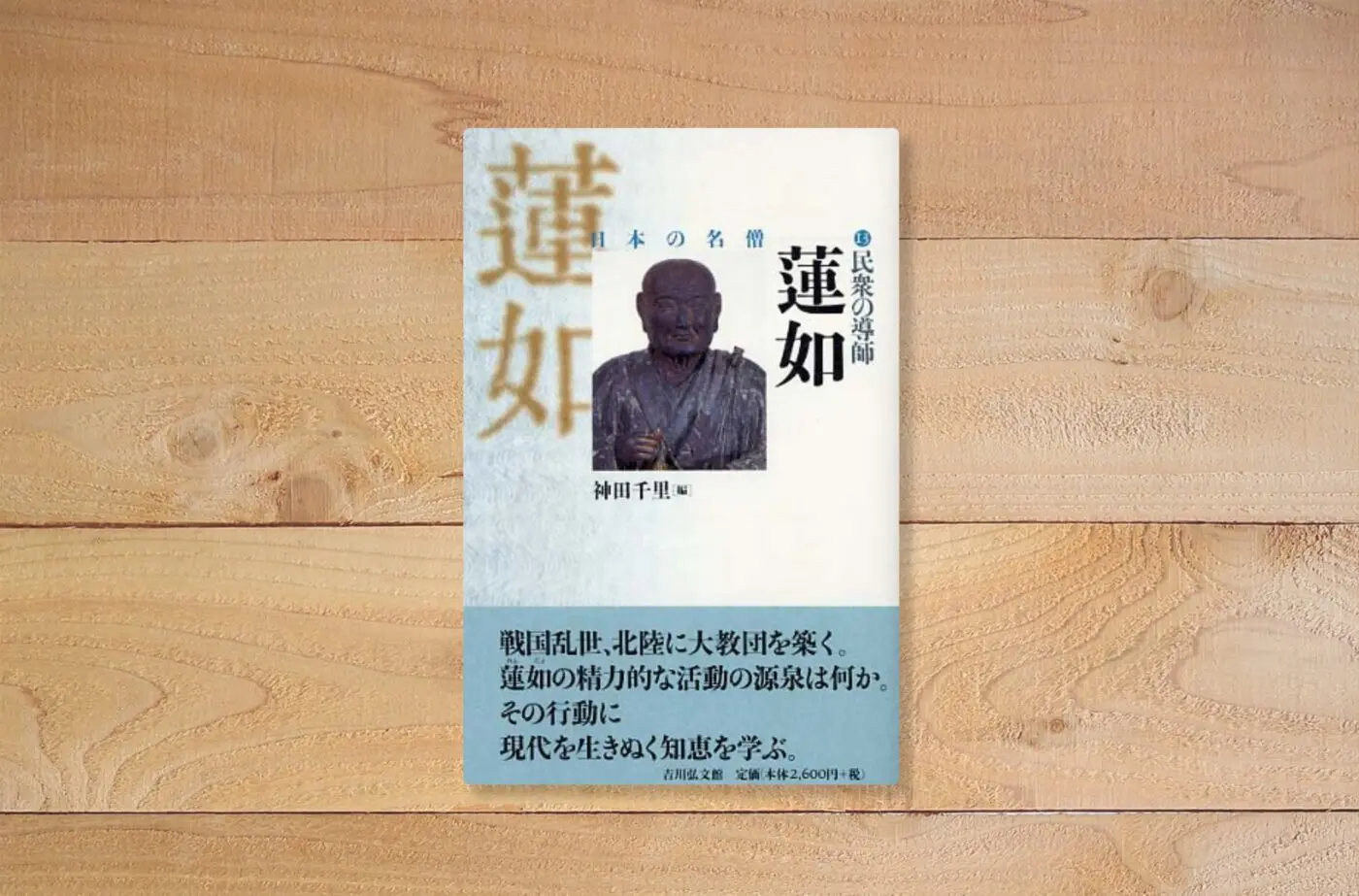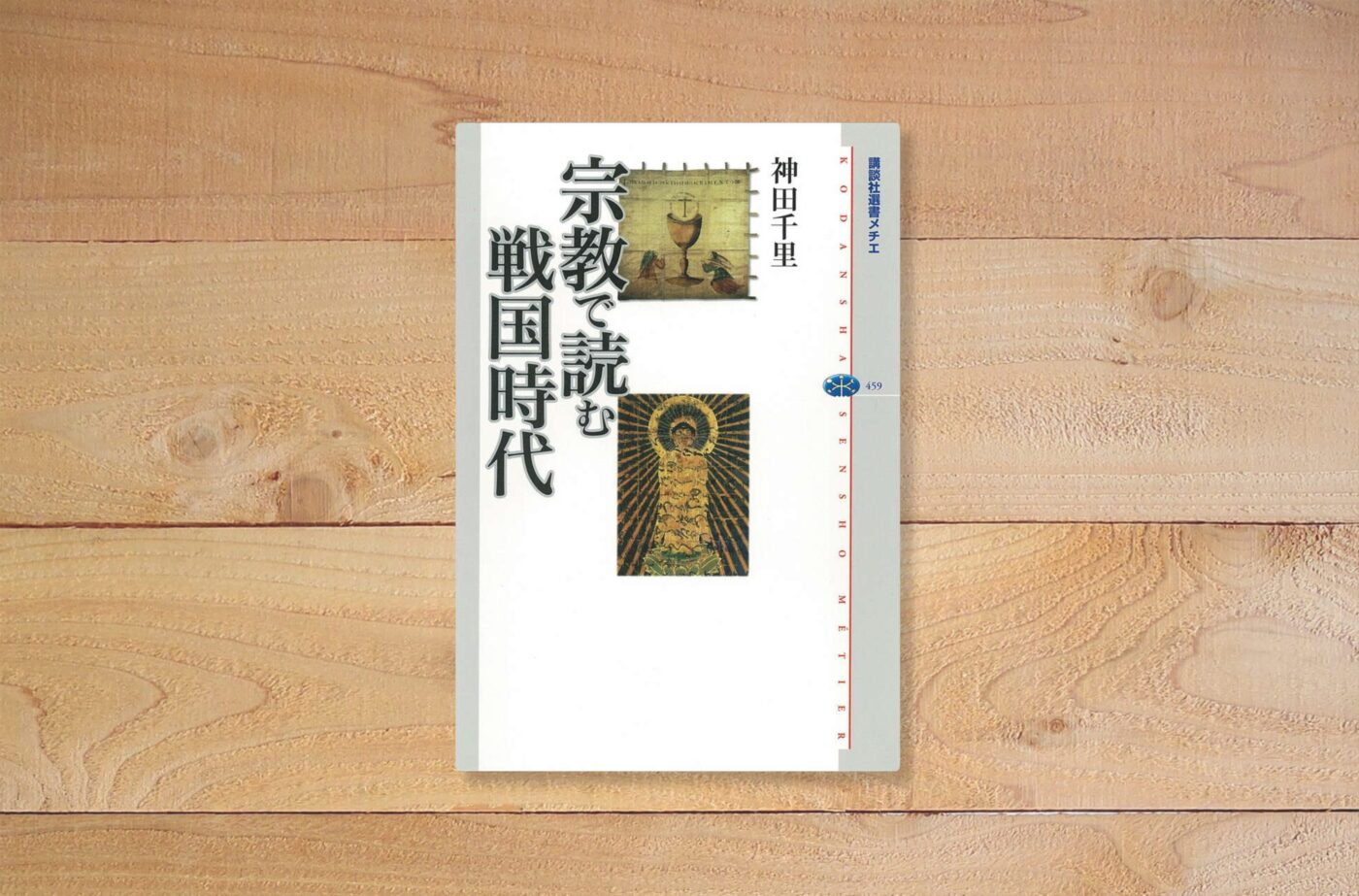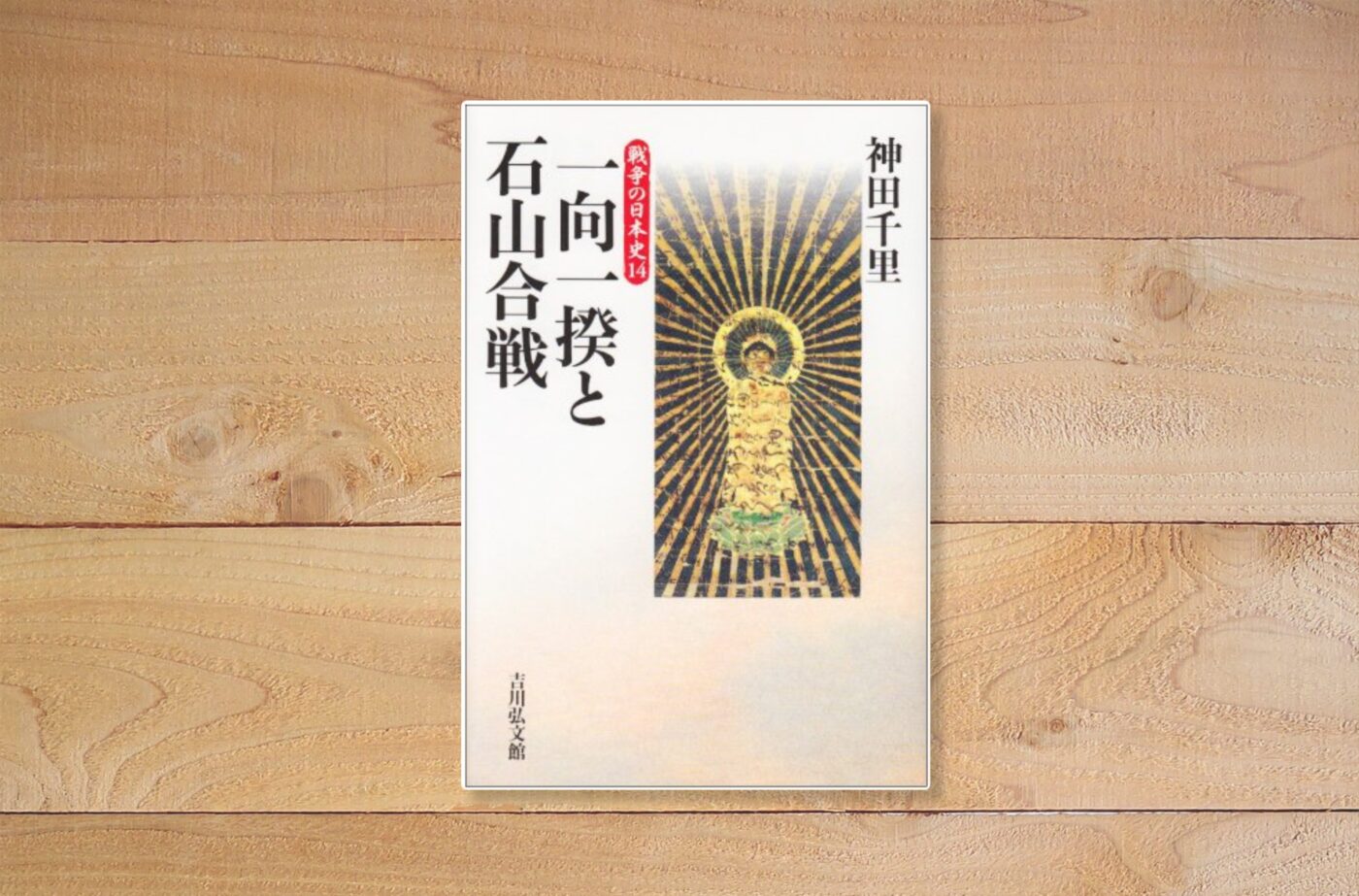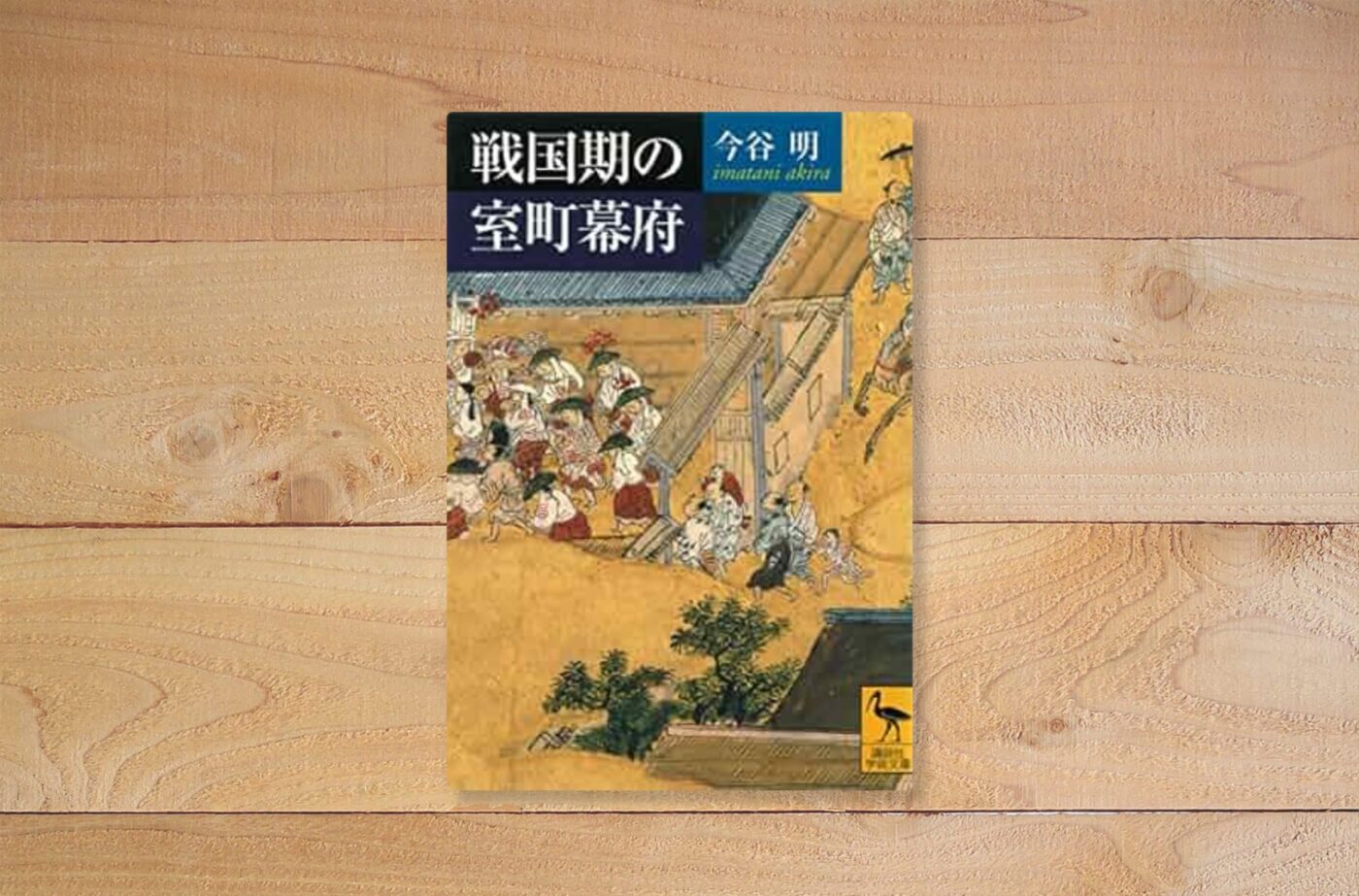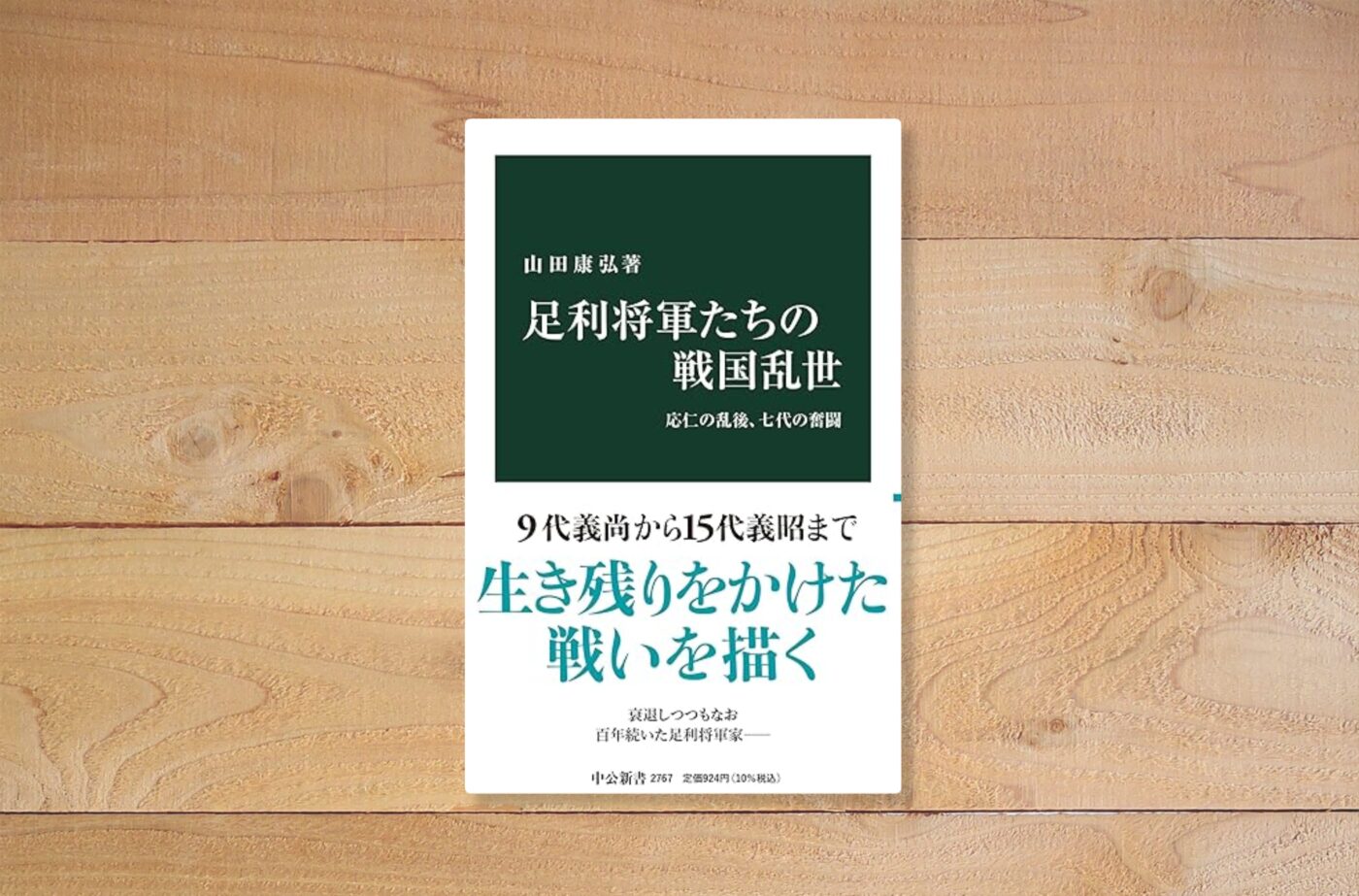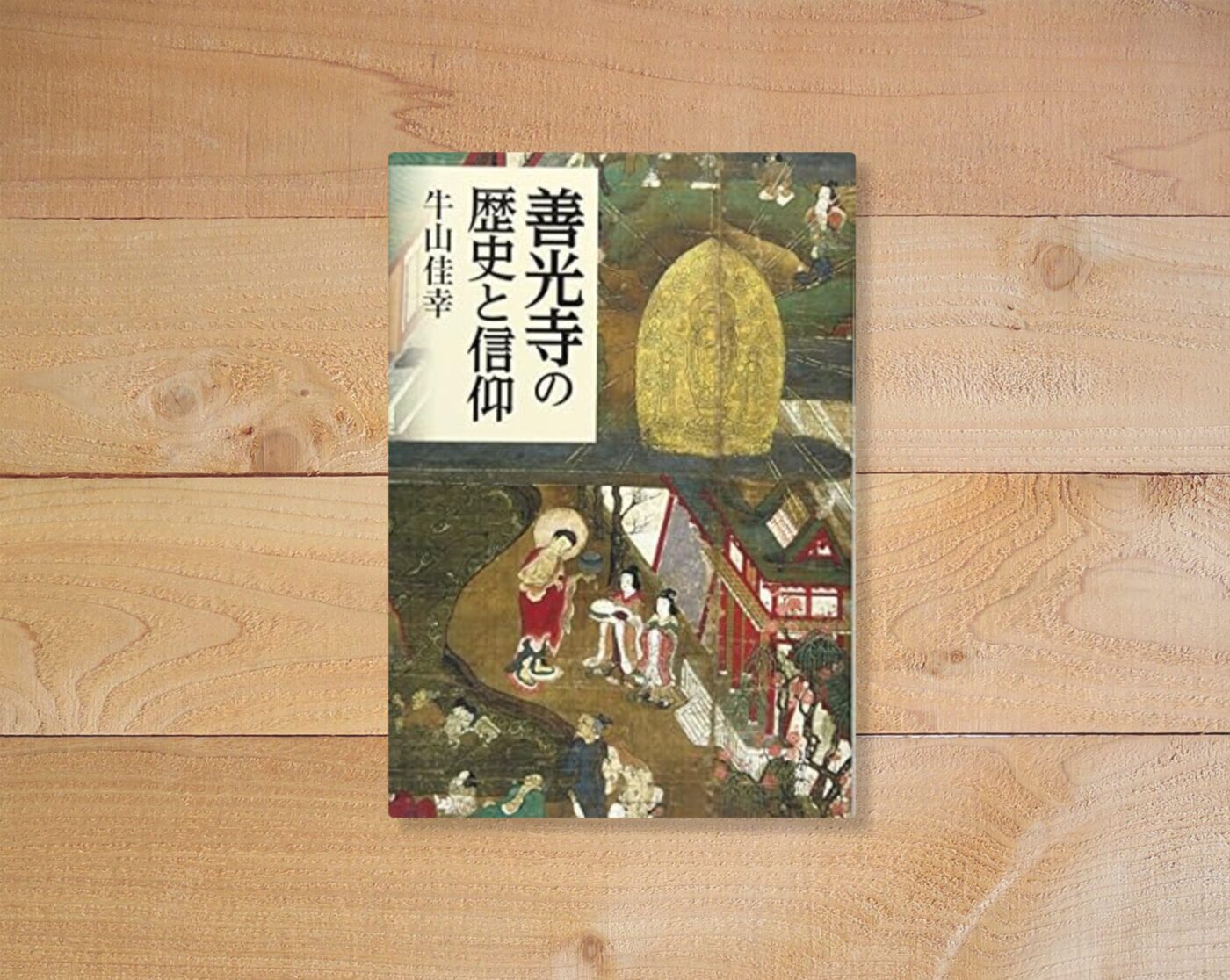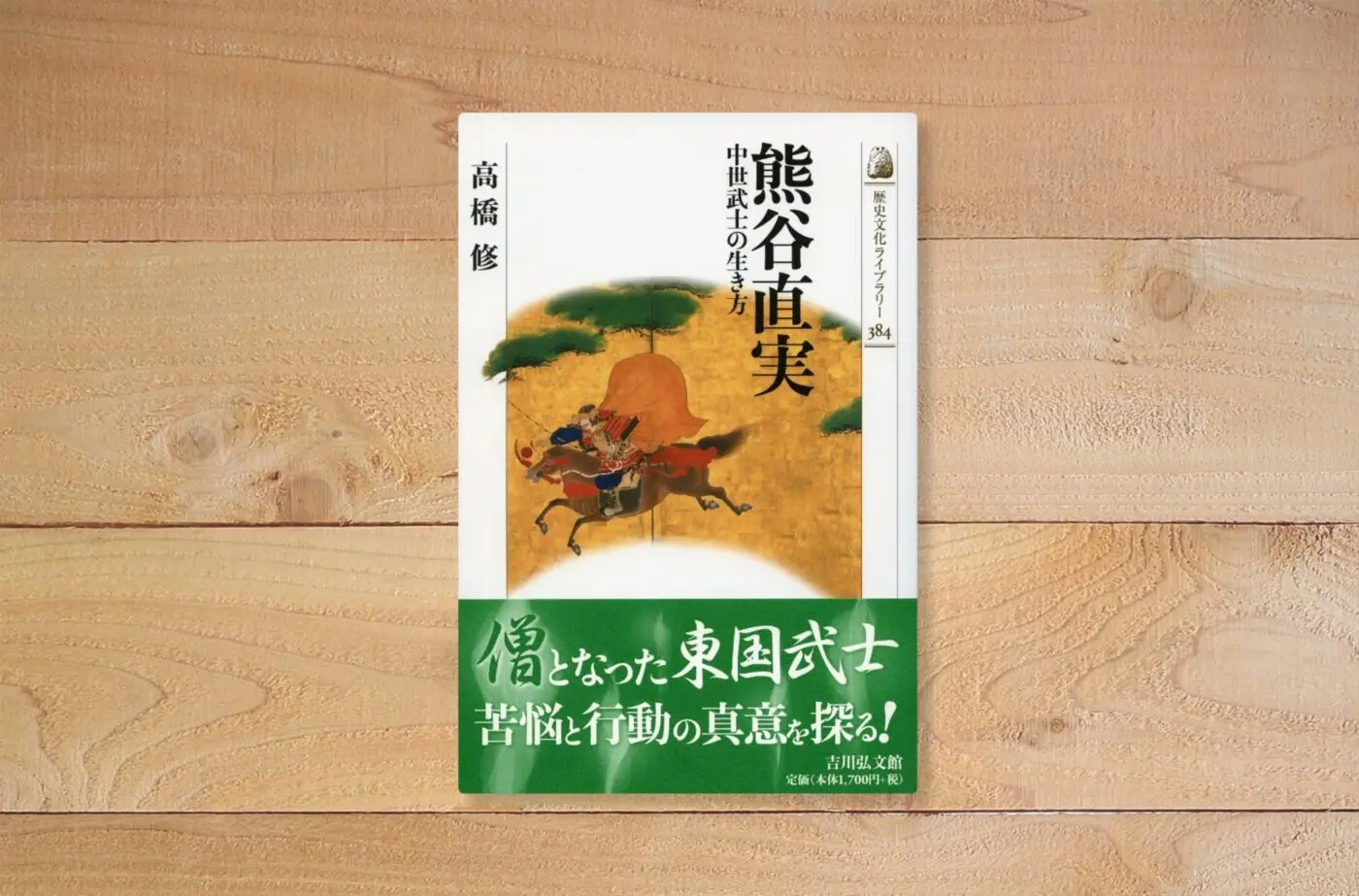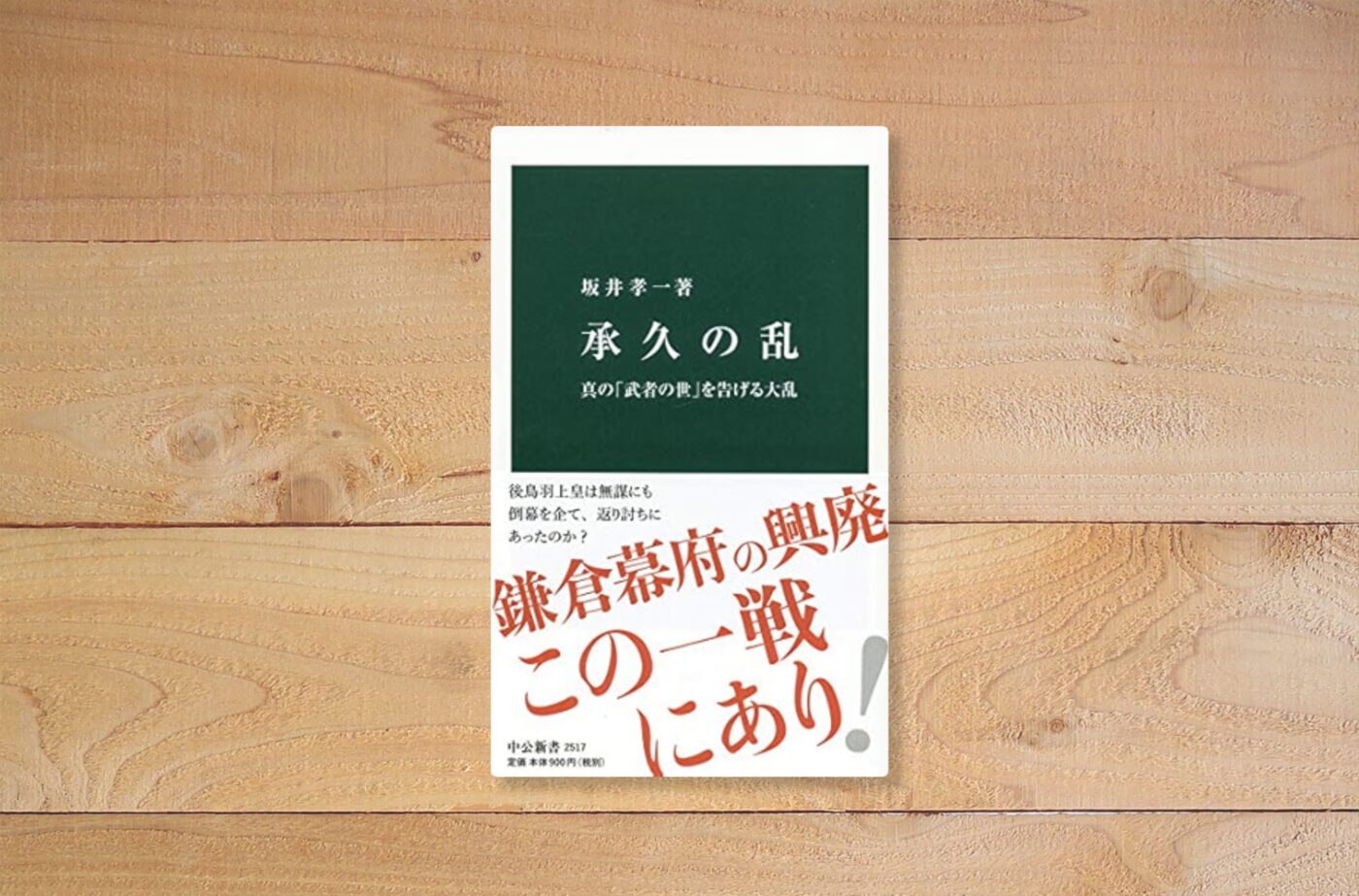井上鋭夫『本願寺』概要と感想~本願寺教団の歴史を学ぶのにおすすめの参考書
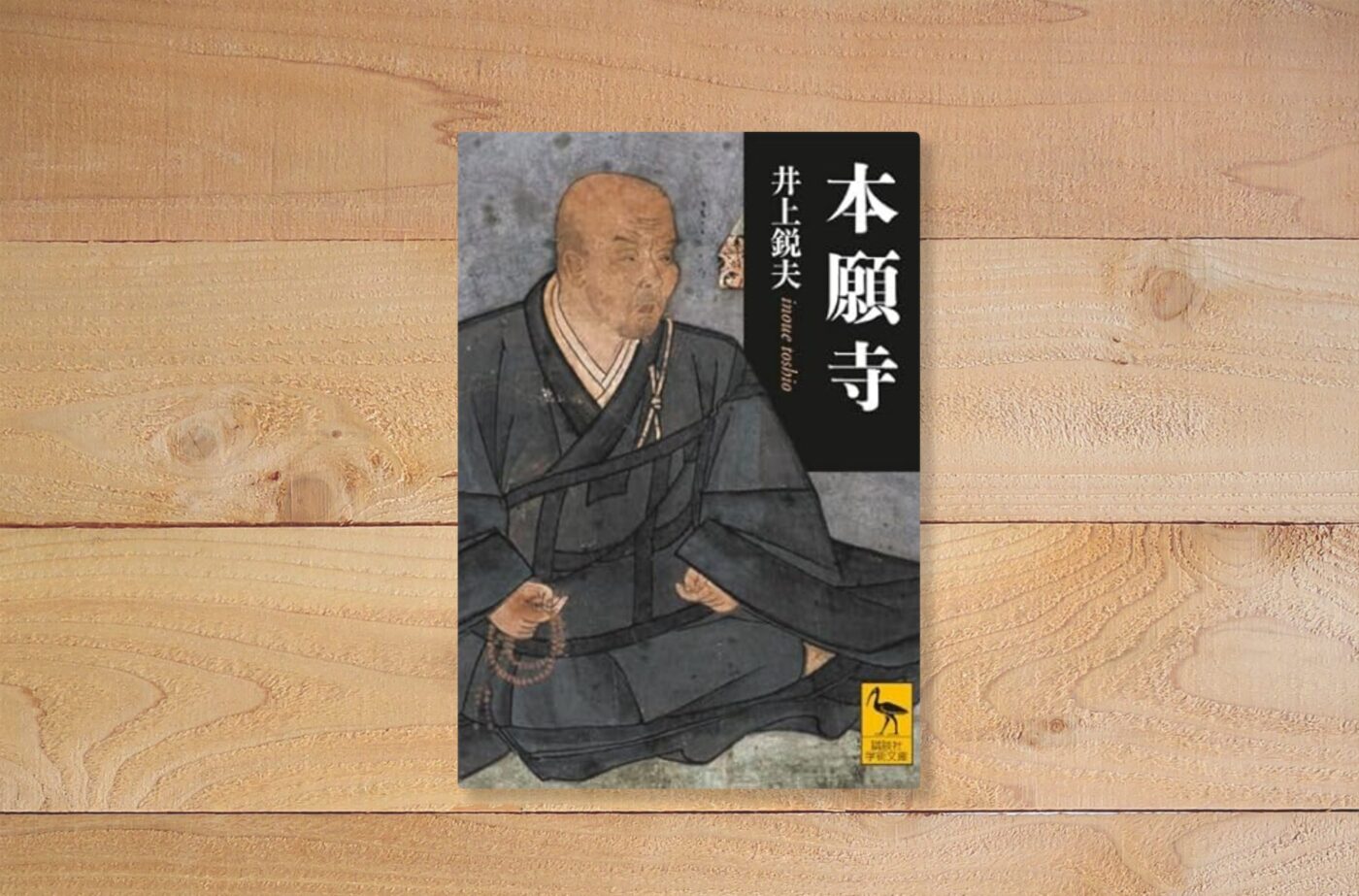
井上鋭夫『本願寺』概要と感想~本願寺教団の歴史を学ぶのにおすすめの参考書
今回ご紹介するのは2008年に講談社より発行された井上鋭夫著『本願寺』です。
早速この本について見ていきましょう。
日本史に大きな足跡を残す真宗本願寺の歴史 中世から時代を超え発展してきた教団。親鸞の跡目争い、大教団完成、信長との抗争、東西分裂等、社会・政治状況と絡まって展開してきた歴史を客観的に考察する。
Amazon商品紹介ページより

本書は浄土真宗の最大宗派たる本願寺の歴史を学ぶのにおすすめの参考書です。
著者は「はしがき」で本書について次のように述べています。
草深い東国の一隅で親鸞の開いた浄土真宗が、無数の人々を「安心」の境地に導き、日本仏教諸宗派のうちで最大の教団となったことは驚歎に値する。この真宗の中心は親鸞の墳墓で、本願寺はそこから、親鸞の外曾孫覚如によって、寺へと発展させられたものである。それもはじめはささやかな貧しい寺院であったが、封建社会の進展とともに急激に拡大し、真宗門徒のほとんどすべてを傘下に包容し、一大社会勢力として日本歴史の檜舞台に登場してきた。
私は本書において、この本願寺の数奇な波瀾に富んだ発展過程を客観的に考察し、その発展の背景をなす日本の社会・政治・経済・思想と関連させつつ叙述しようと試みた。その点これは本願寺の科学的由緒書のつもりであり、本願寺発展の謎に対する一つの解答でもある。しかし本願寺という複雑厖大な歴史的形成物は、日本社会の深部に浸透しているだけに、興味深いと同時に簡単に割り切れないものであることは断わっておかねばならない。
先ず第一章では真宗というものを私なりに把握し、親鸞の純粋な人間的な信仰と世俗との交接点に真宗教団が成立してくる様相を考えてみた。
第二章では大谷家の財産相続争いとこれに対する門弟の動向・態度から本願寺の成立が覚如によって強引に遂行される事情を説明している。
第三章は本願寺史上の暗黒・欠史時代とされる時期を扱い、大きく紙幅を割いて新しい史実で空白を埋め、飛躍的発展を前にした本願寺の漸進の姿を述べたものである。とくに本願寺と真宗諸派との関係に配慮している。
第四章は蓮如・実如・証如の本願寺の勃興期を扱い、農村を把握しつつ貴族化し、武家化・大名化することを述べた。
第五章は織田信長との対戦である石山合戦を通じて本願寺も門徒も近世的に変質し、豊臣・徳川政権に結びついて行く過程に注目した。とくに教義ではなく人間関係から、本願寺が東西に分かれ、政治によって宗門が支配されるが、教団の構造とその変質は幕藩体制と原理を共通にし、従って明治の変革を必然ならしめる点を詳説したつもりである。
講談社、井上鋭夫『本願寺』P3-4
以上が本書の大まかな流れになります。
まず最初に恐縮なのですが、上の引用の一番最初で「草深い東国の一隅で親鸞の開いた浄土真宗」と著者は述べていますが、最近の歴史学の研究では親鸞がいた東国は決して無知蒙昧な田舎ではなく、豊かで文化的にも進んだ地域だったことが明らかにされています。本書『本願寺』の原本は1962年の出版ですので当時の歴史学では東国はそうしたものとして受け止められていました。このことに関しては当ブログでも後に紹介する予定の今井雅晴氏の『親鸞聖人の一生』で詳しく説かれています。
さて、最初に注意書きのような形になってしまい申し訳ありませんでしたが、そうした1962年段階の著作という点を差し引いても本書が切れ味抜群の名著であることに変わりありません。
上の引用にありますように、本書では本願寺教団の歴史を背景となる「社会・政治・経済・思想」と共に見ていくことになります。
これは私も宗教を学ぶ際に大切にしている「宗教は宗教だけにあらず」という考え方と重なってきます。
本願寺教団の歴史はまさに信仰や教義のみで語られるものではありません。親鸞聖人没後、小さな廟堂であったお墓を寺院化し本願寺とした覚如。しかし当時は東国の門弟たちに頼らなければ生活すらままならないほどでした。そこから本願寺教団が一気に巨大化するのは室町中期を待たねばなりません。
私達は本願寺というと現在の巨大宗派を想像してしまいますが、実は親鸞聖人没後150年以上も小さな一寺院に過ぎなかったのです。その頃はむしろ親鸞聖人の弟子筋の教団である高田派や仏光寺派の方が圧倒的に大きな存在だったのです。
それがどうして室町・戦国期に逆転するのか、それが本書で明らかにされます。

従来の浄土真宗史観(本願寺派系)では中興の祖蓮如の才覚によって民衆の支持を得、それにより急拡大されたと語られがちですが実際には事はそう単純ではありません。蓮如の才覚、人柄の影響ももちろん巨大なものがありますが、当時特有の時代背景も見逃せません。本書ではその辺りの詳しい政治情勢も知ることができるので非常に刺激的です。
従来の本願寺教団側からの歴史に慣れた私達真宗僧侶にとってはかなり手厳しい意見も本書には出てきますが、歴史と向き合うことは大切です。その上で私達がどう信仰していくかが試されています。そうした意味でもこの本は非常に重要な一冊と言えるでしょう。
以上、「井上鋭夫『本願寺』概要と感想~本願寺教団の歴史を学ぶのにおすすめの参考書」でした。
Amazon商品紹介ページはこちら
次の記事はこちら
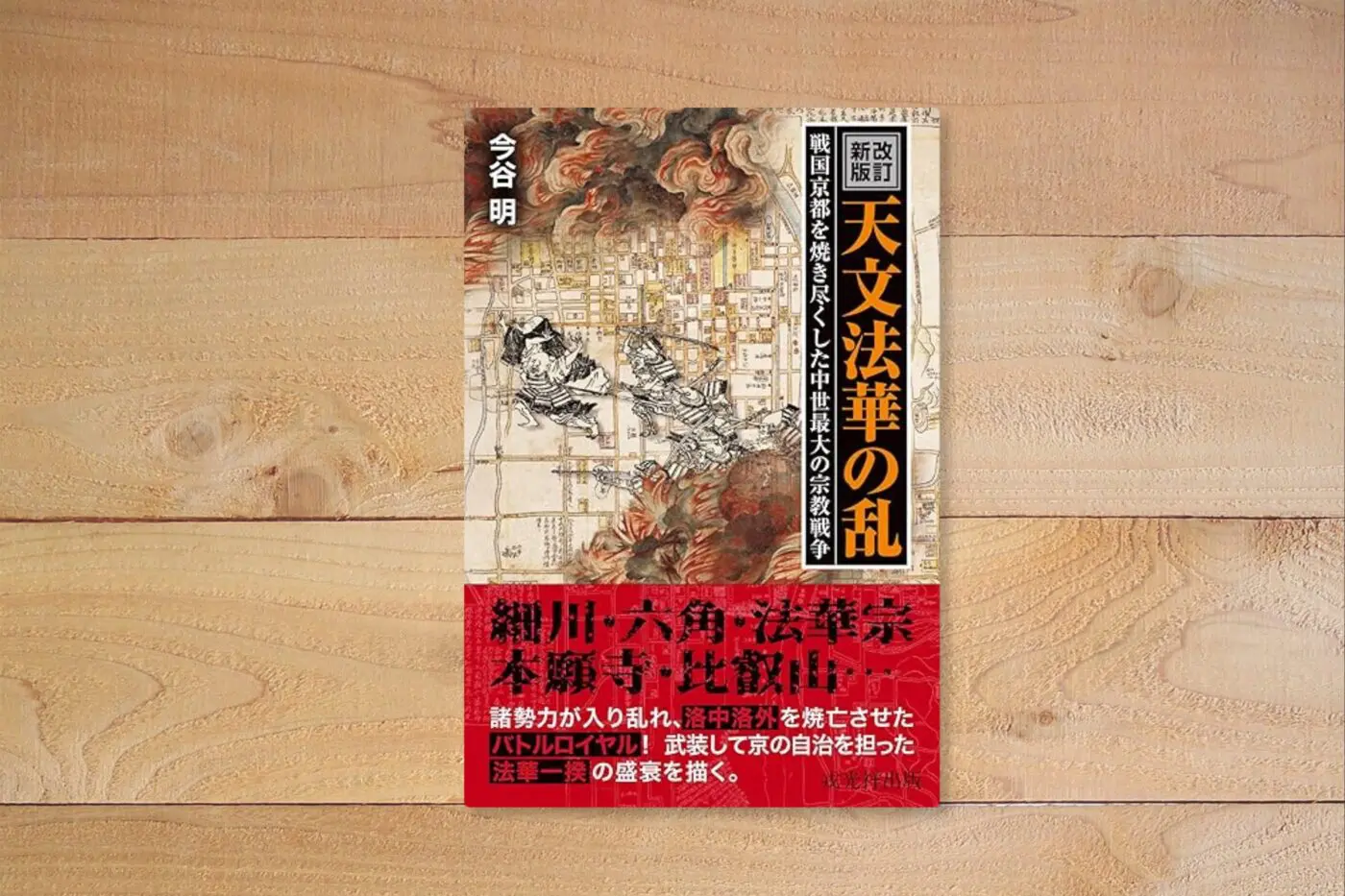
前の記事はこちら
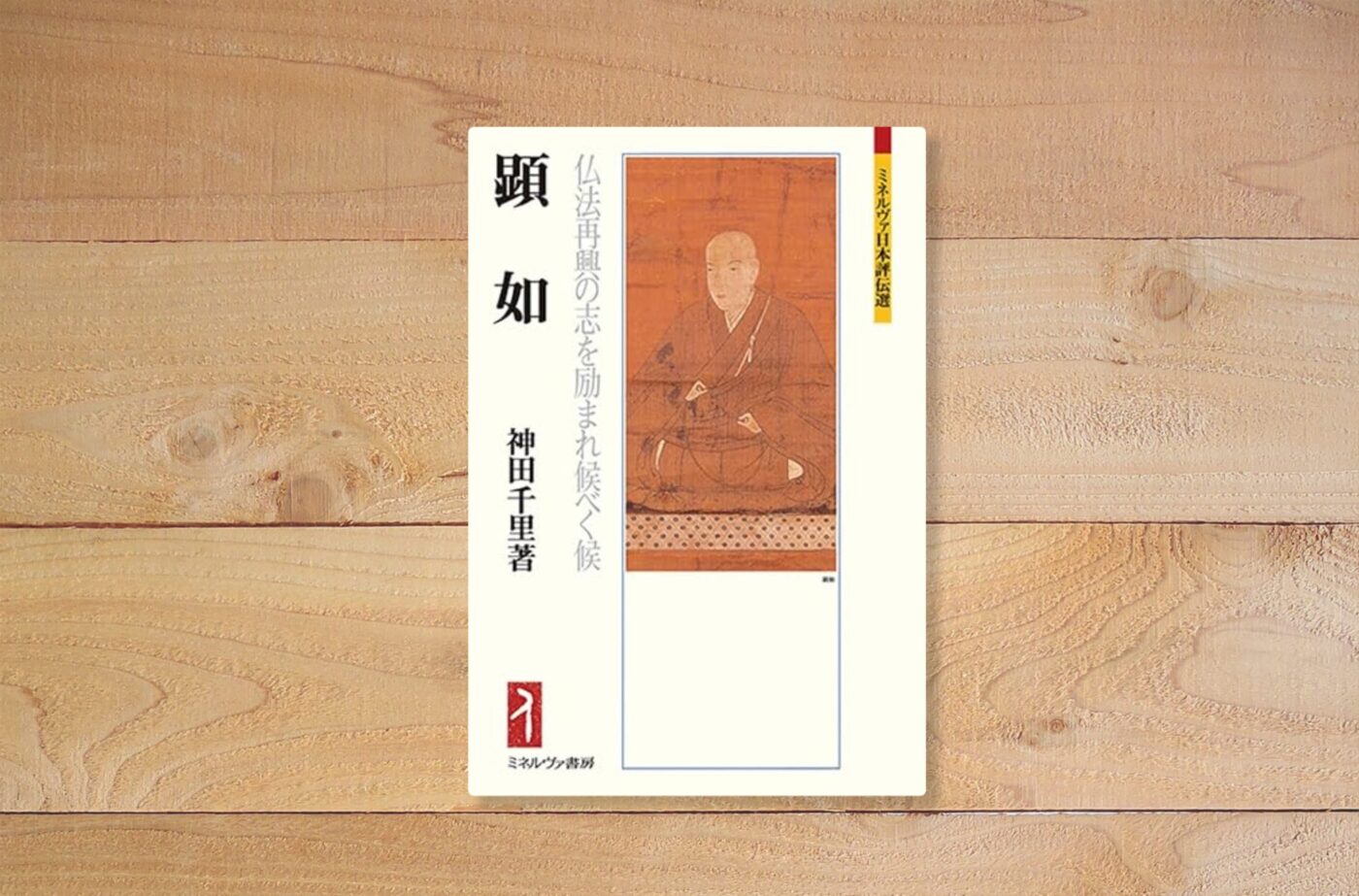
関連記事