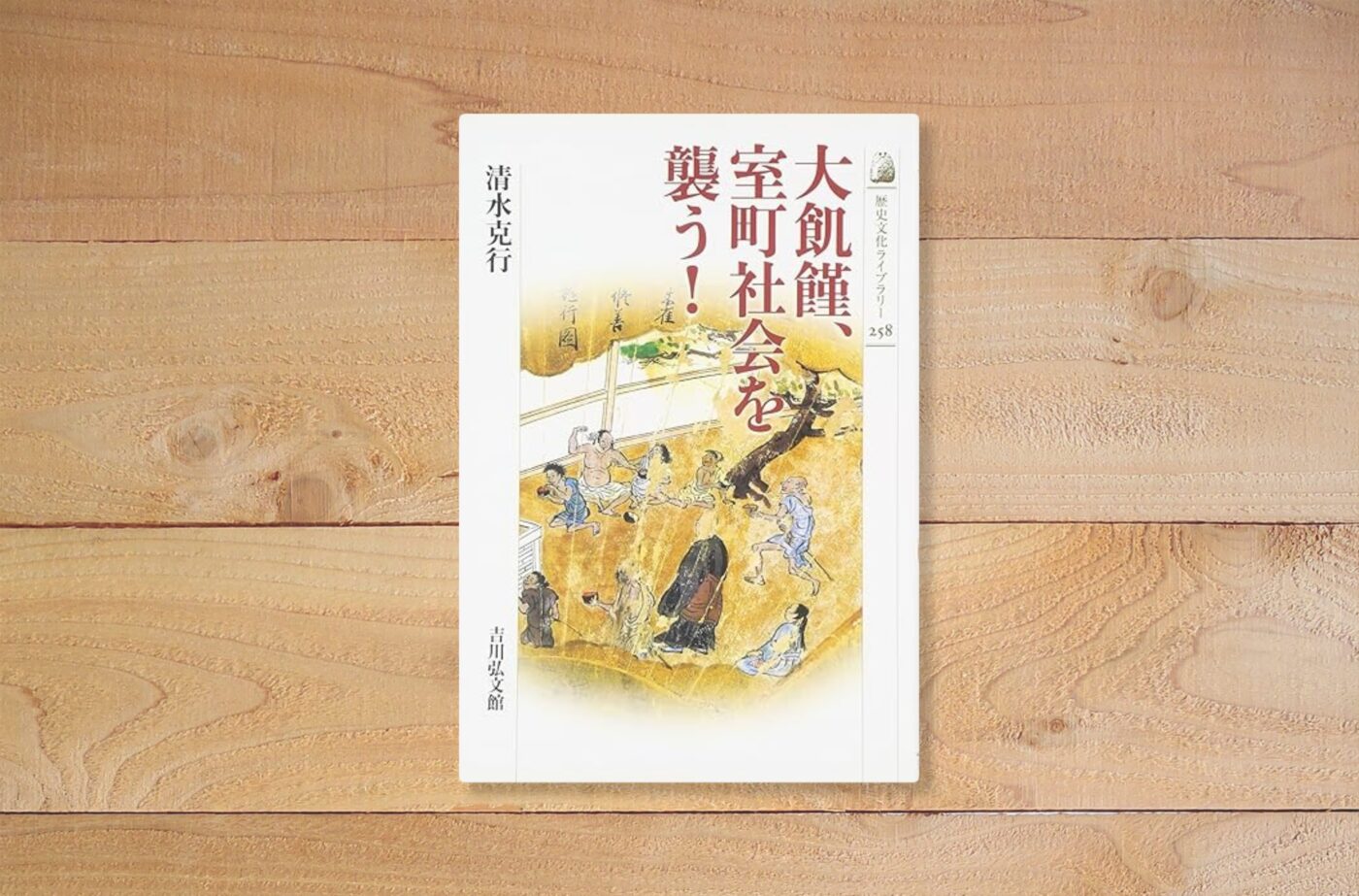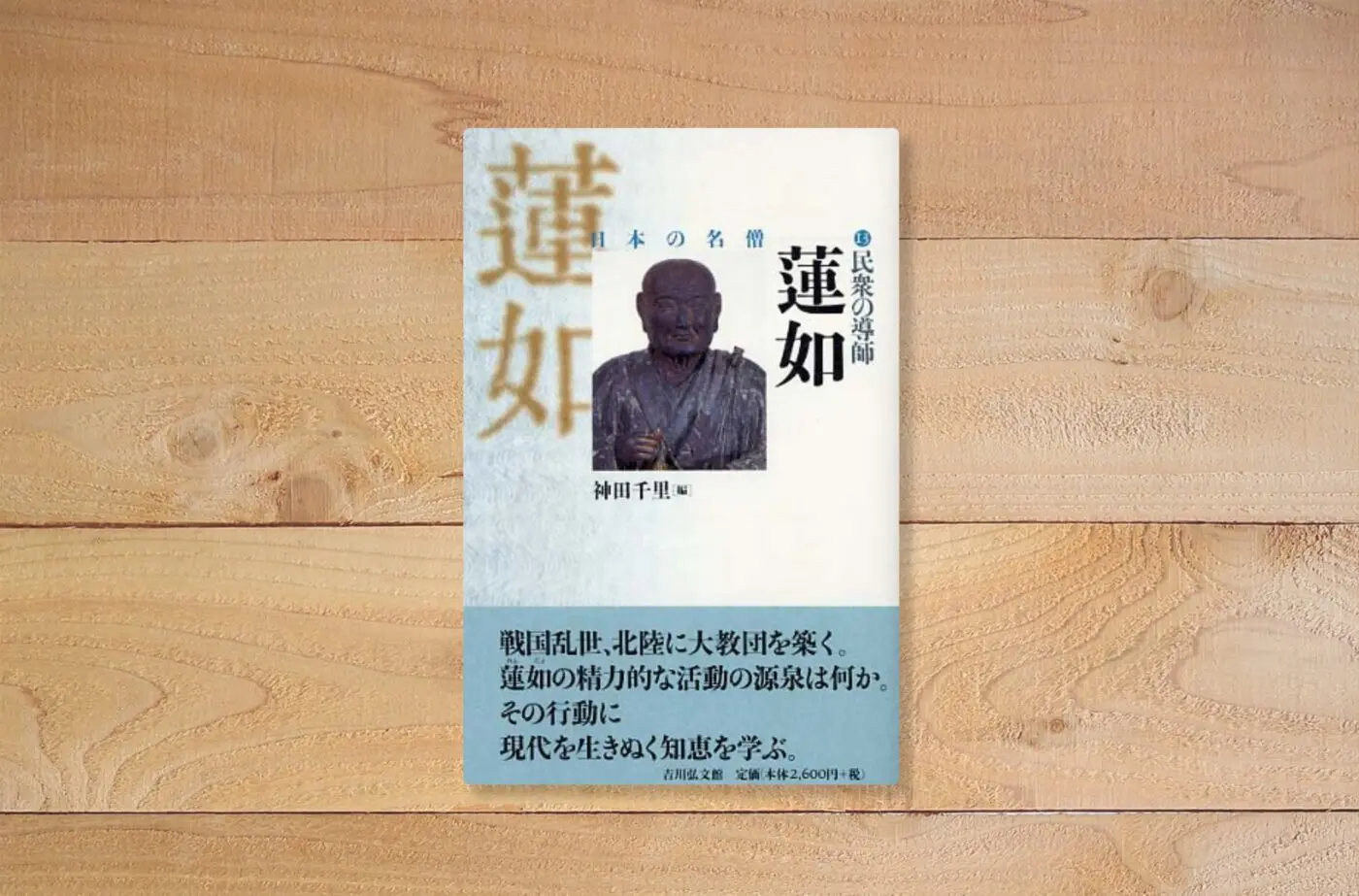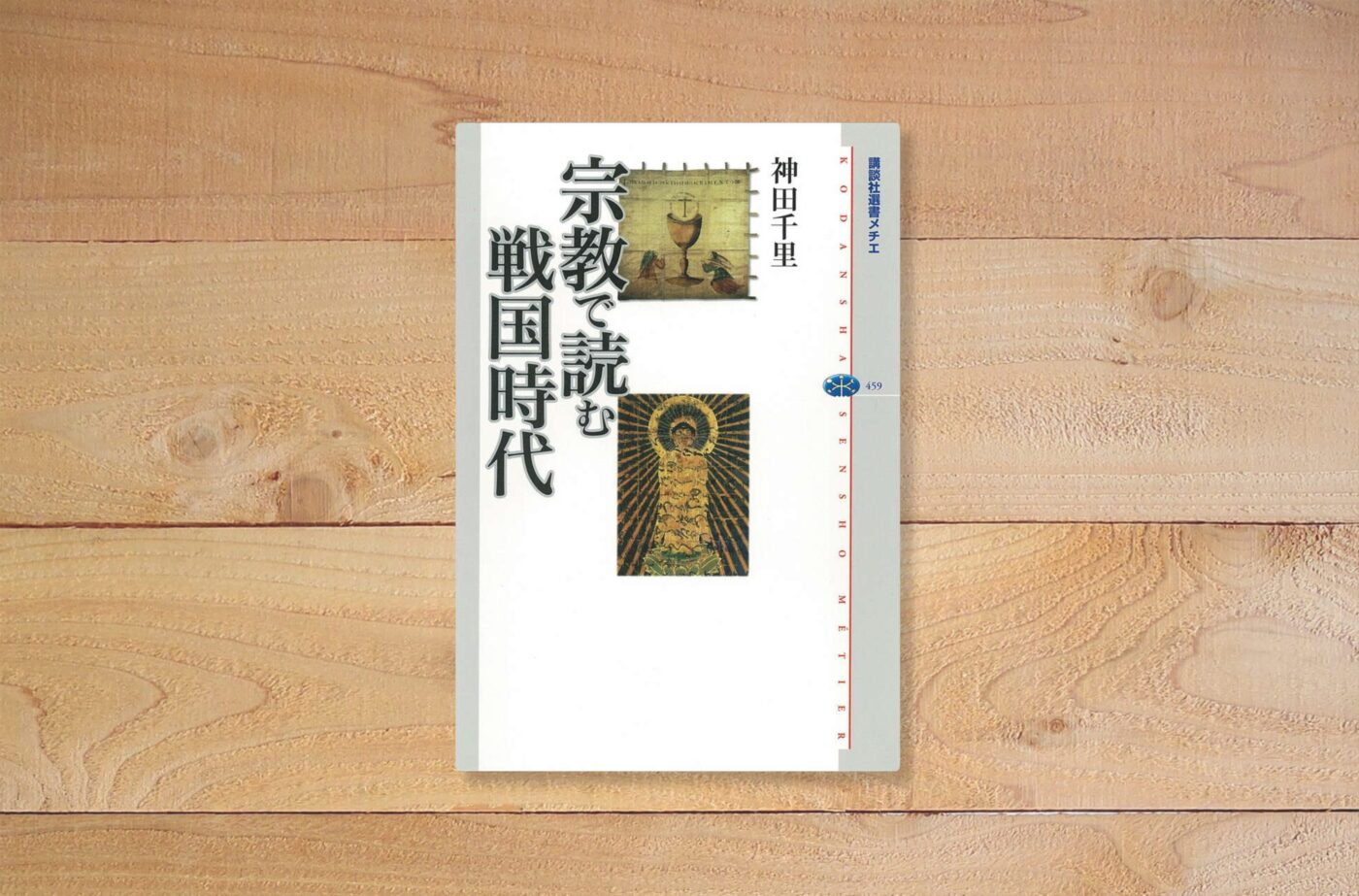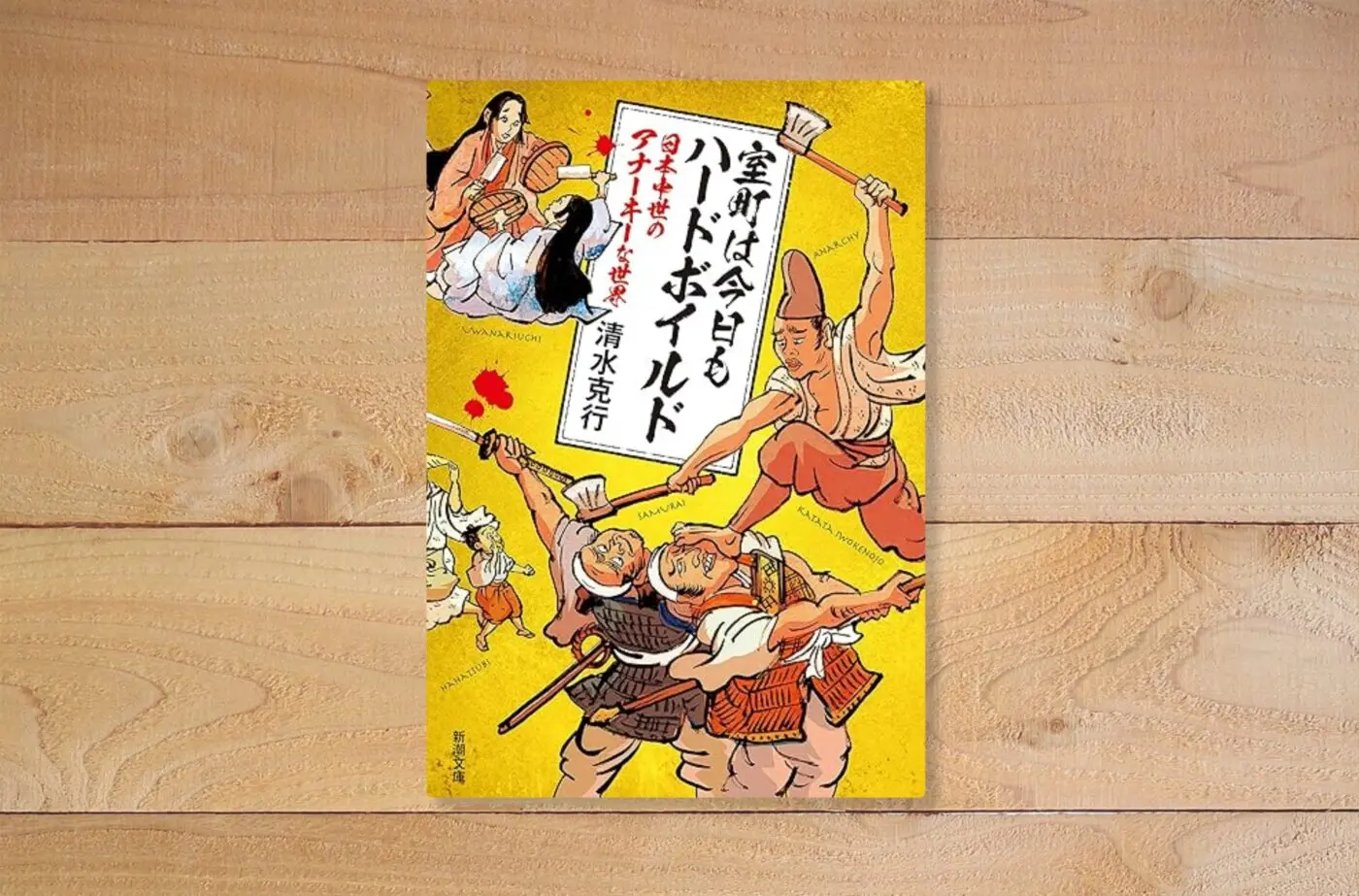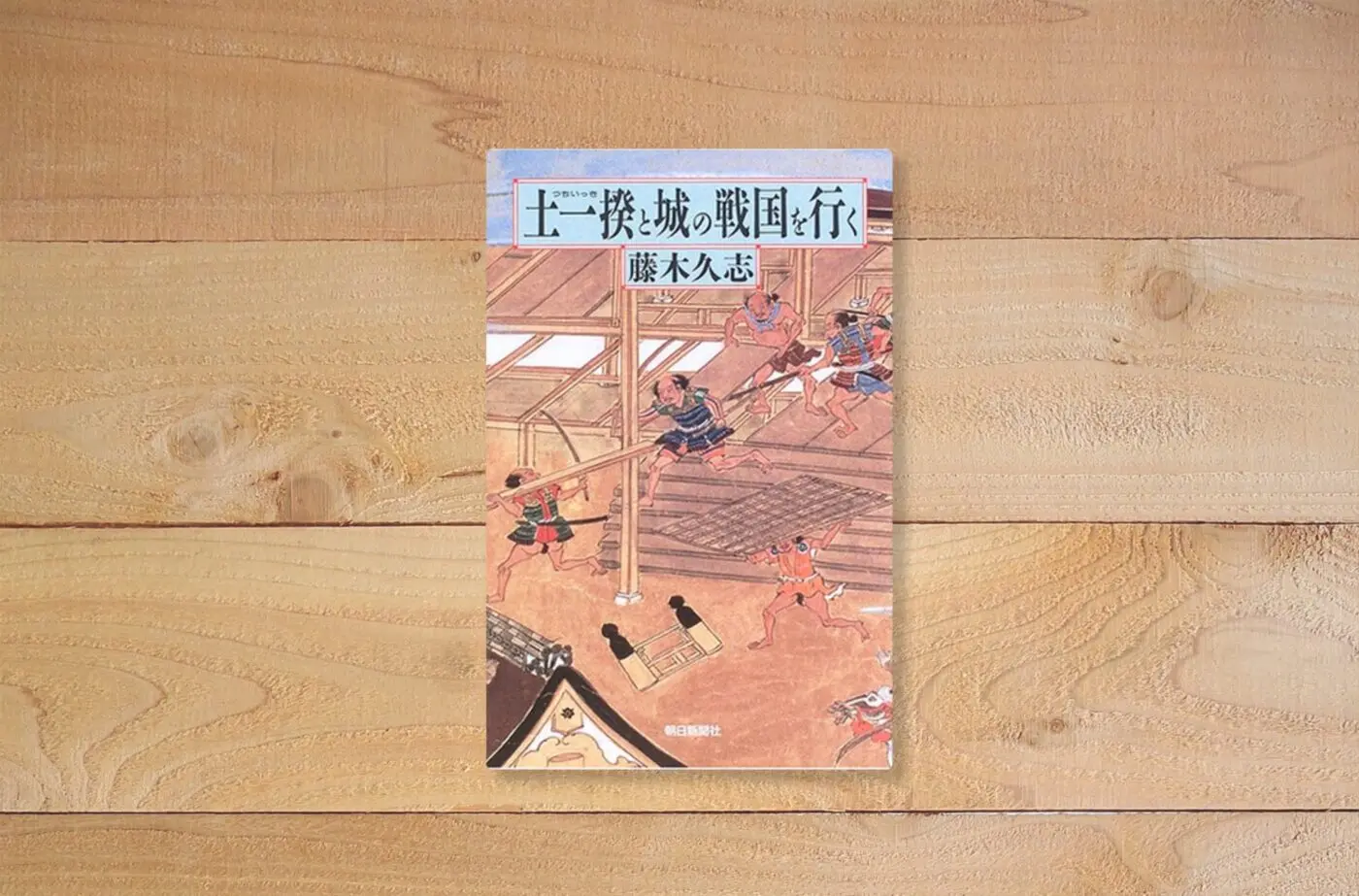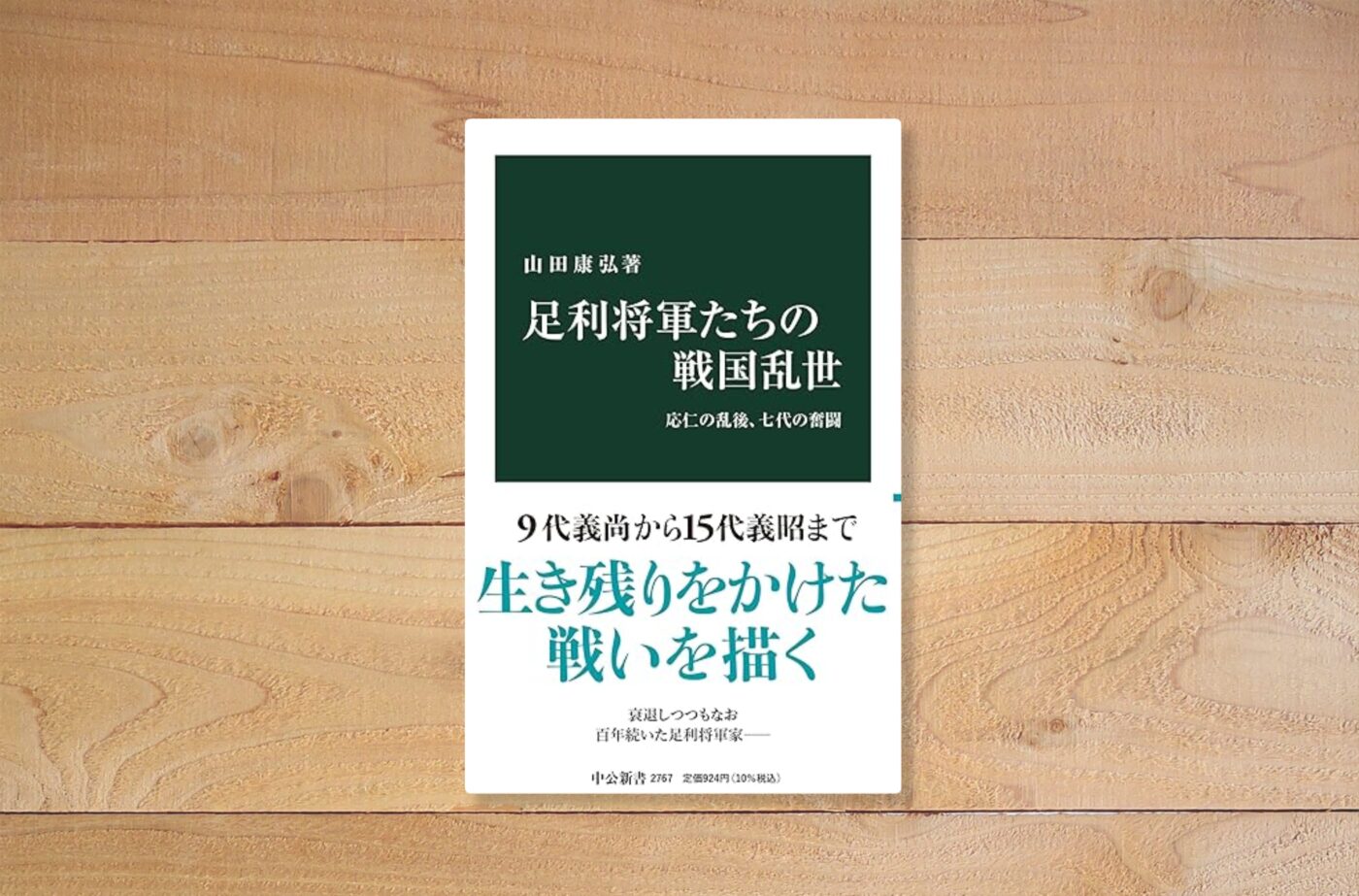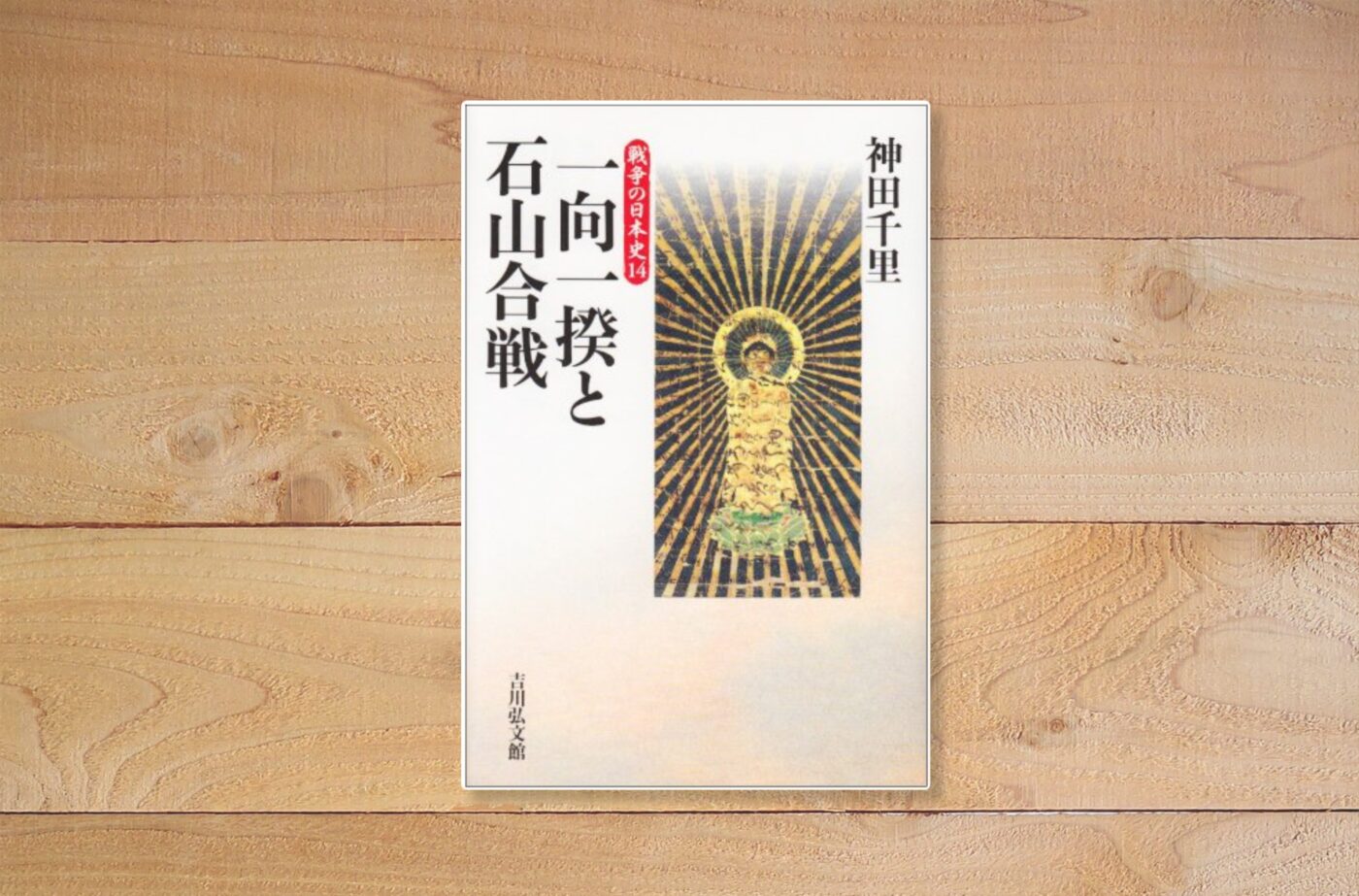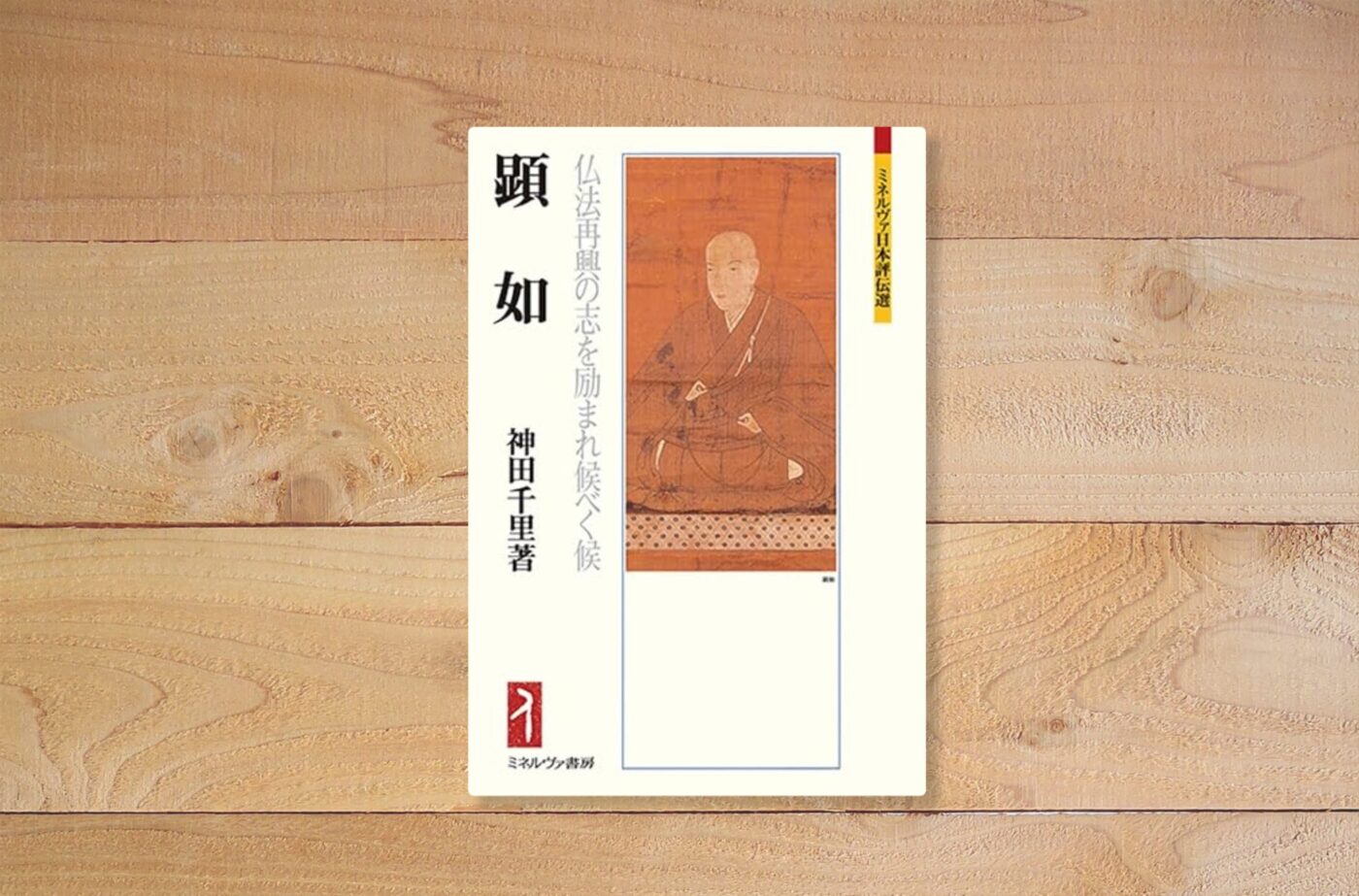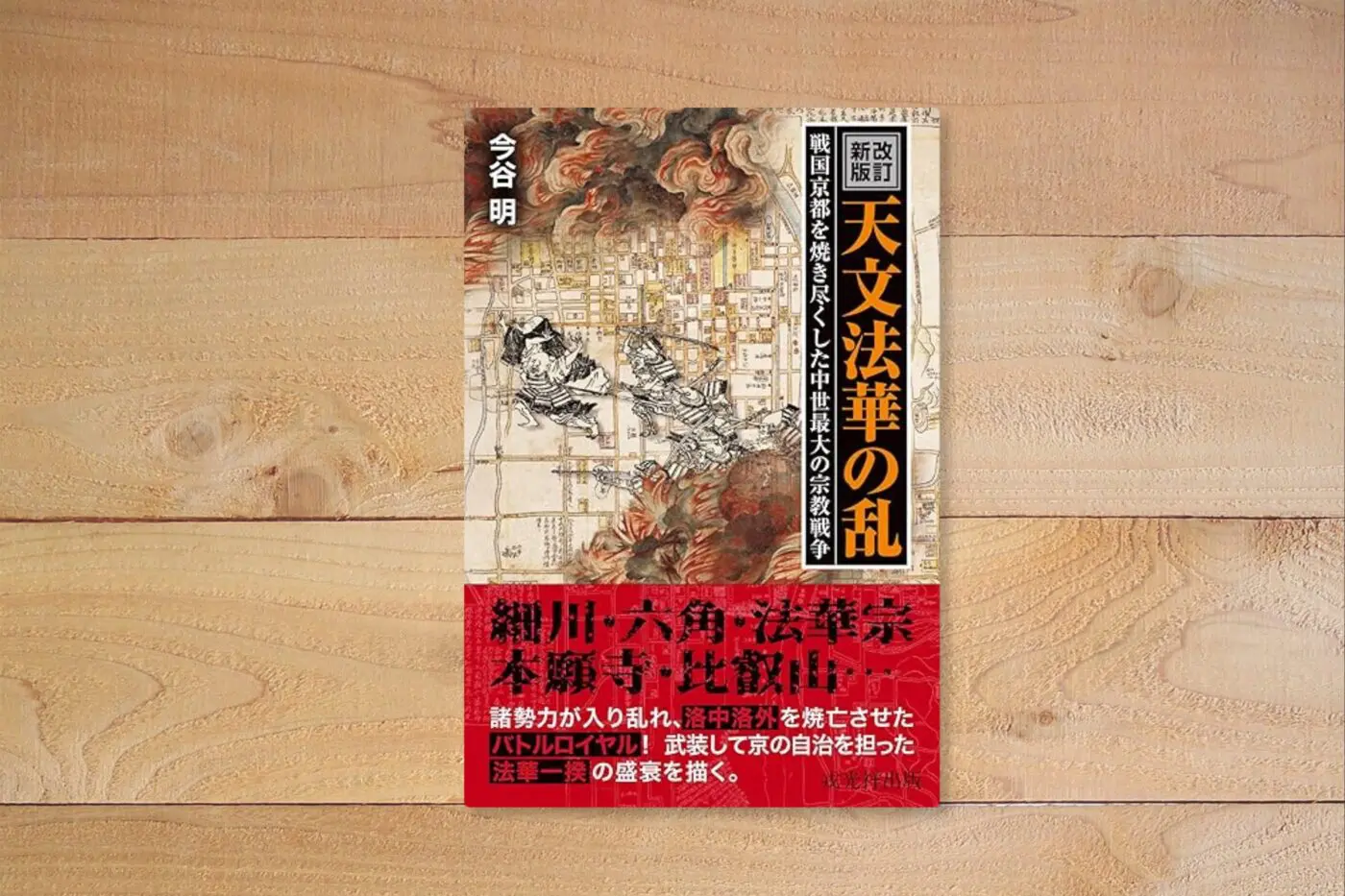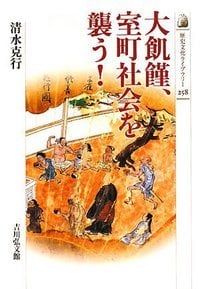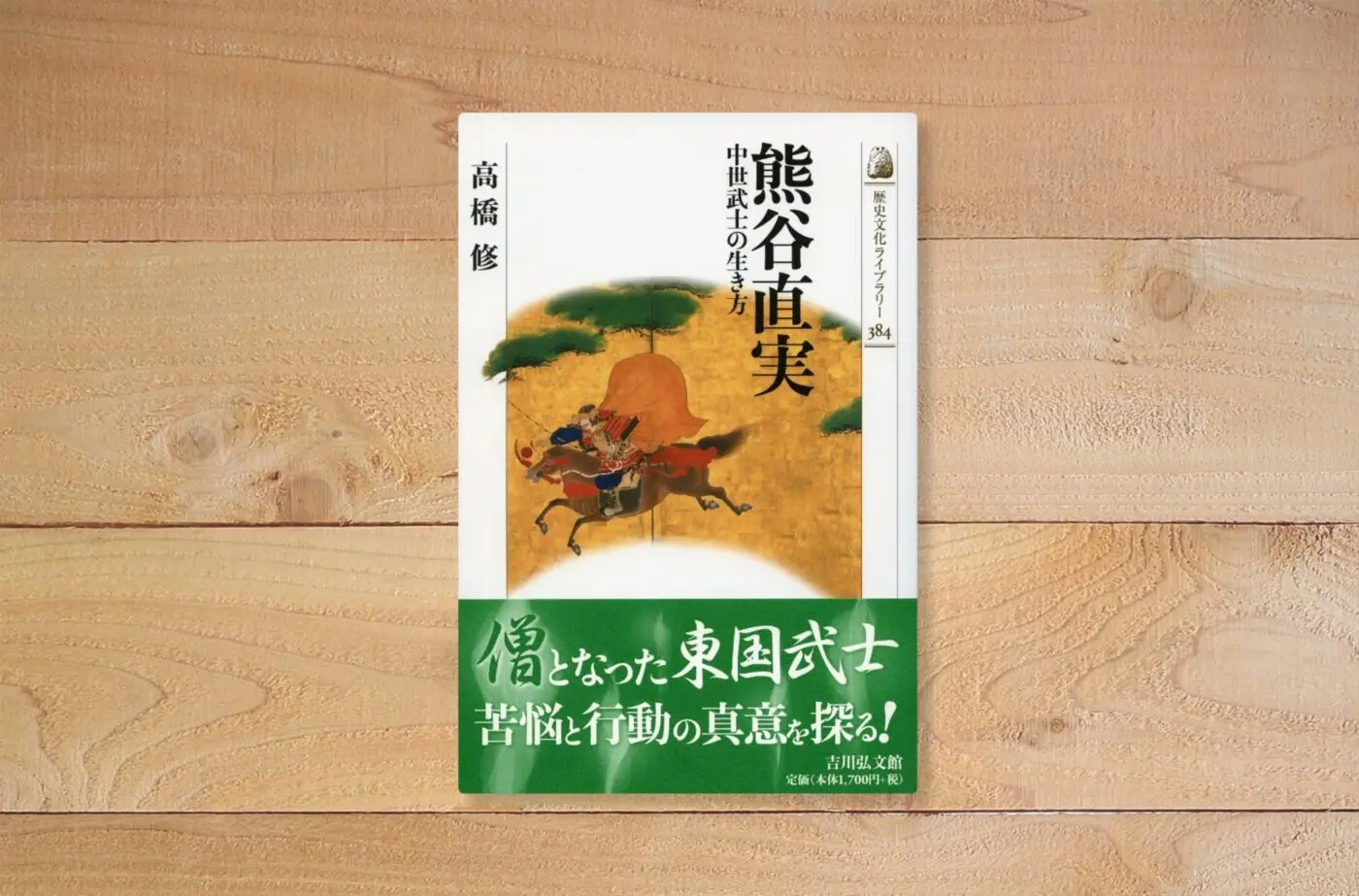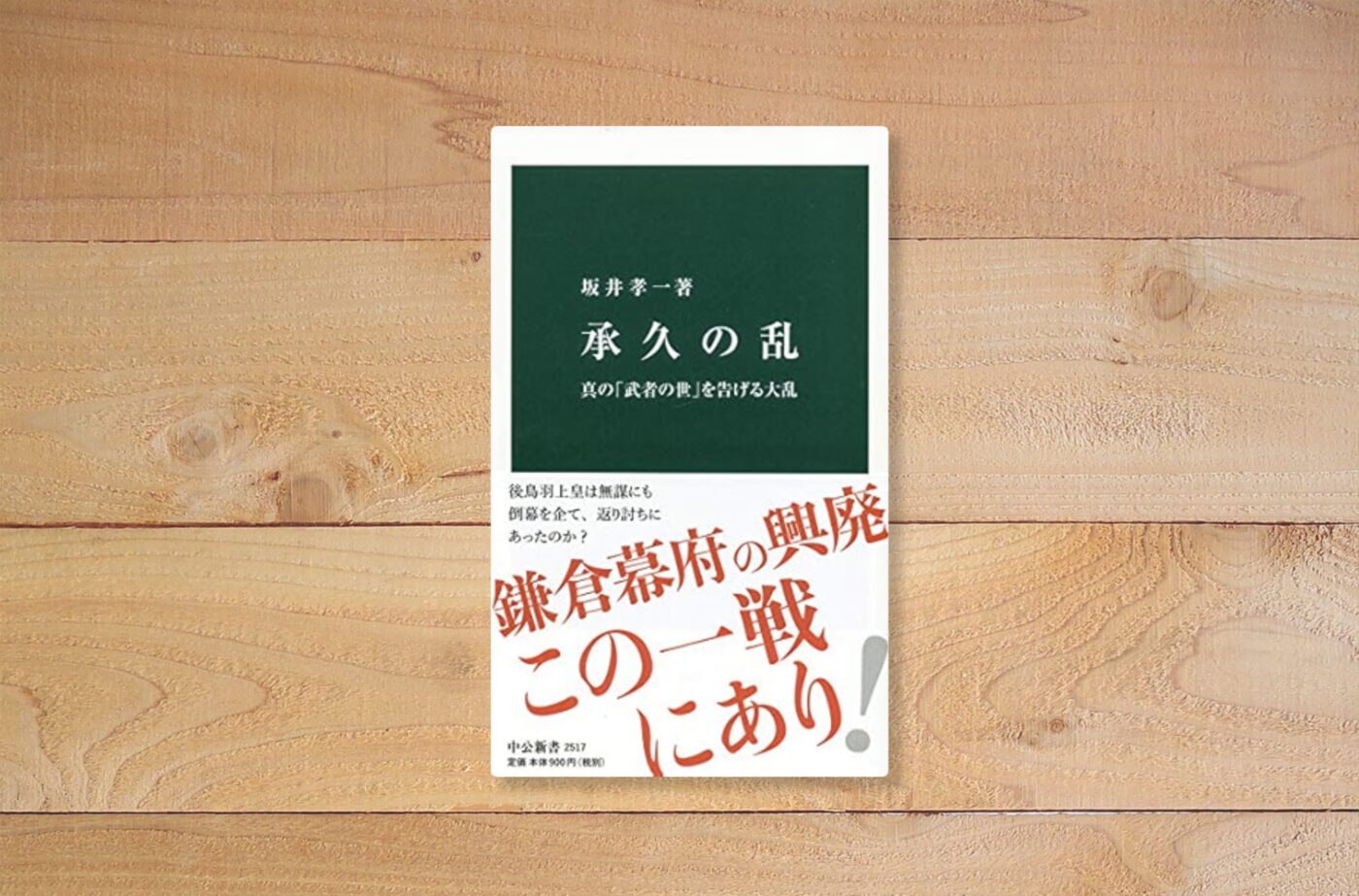目次
清水克行『大飢饉、室町社会を襲う!』概要と感想~室町時代の過酷な実態を知れる刺激的一冊!
今回ご紹介するのは2008年に吉川弘文館より発行された清水克行著『大飢饉、室町社会を襲う!』です。
早速この本について見ていきましょう。
慢性的な飢餓に直面し生と死の狭間で生きていた室町人。満腹感を得るため新米より古米を尊重し、出産では母親の生命も脅かされ、ようやく生まれた赤子も「間引き」や人身売買に…。そこに巨大飢饉が襲いかかったとき、人びとはどうしたのか。現代にも通じる飢餓と飽食の残酷な構造をえぐりだし、室町時代の実相を描き出す。中世社会の雑学も満載。
吉川弘文館商品紹介ページより
本書『大飢饉、室町社会を襲う!』が以前当ブログでも紹介した名著『室町は今日もハードボイルド』の著者清水克行氏の作品です。
本書では室町、戦国時代のアナーキーな時代をもたらした大きな要因のひとつである飢饉について語られていきます。
『室町は今日もハードボイルド』と同様、著者の語りはとてもわかりやすく読みやすいです。
本書について著者は次のように述べています。
まさに現代日本は〝飽食〟(食に飽きる!)のなかにある。しかし、すこし国際情勢に目を向ければ、地球上には相変わらず飢餓に苦しむ人々がそこかしこに存在するわけで、この日本の飽食の現状は世界的にみてもかなり希有で背徳的な状況であることに気づく。もちろん、こんなことは私があえて述べるまでもなく、心ある多くの読者にはすでに気づかれているところだろう。しかし、それでも私は本書でありのままの飢餓の現実、しかも五〇〇年も昔に起きた飢餓の現実を、あえて読者のまえに提示したいと思う。
では、なぜこの満ち足りた「飽食の時代」に、わざわざ陰惨な「飢餓の時代」を振り返らなければならないのか。以下、私が考える本書の特徴と、その狙いとするところを三点あげよう。
まず第一には、なにより五〇〇年以上前にこの国で起きた大飢饉のありのままを描くことで、この現代日本の飽食が歴史的に見ても特異な状況であることをあらためて訴えたいということである。それによって、私たちが〝常識〟としていることが、いかに〝飽食〟の時代に規定されたものであるかが、きっと分かってもらえるはずである。
また、本書では当時の社会の〝飢餓〟の対極にある当時の京都の〝飽食〟にも目を向けてゆく。この二つの正反対の世界は、現代の発展途上国の〝飢餓〟と先進国の〝飽食〟が密接な因果関係で結ばれているように、互いに連関するものだった。本書では第二に、現代にも通じる〝飢餓〟と〝飽食〟の残酷な構造も明らかにしてゆきたい。
そして、大飢饉の最中に一休や世阿弥が自己の思索を深めたように、当時の人々も危機に直面して手をこまねいていたわけではなく、生き抜くための真剣な営みに力を傾けていた。本書では第三に、飢饉の悲惨さもさることながら、そうした人々のバイタリティーにも目を向けてゆきたい。あるいは、そこから〝飽食〟を生きる私たちが失っている何かを見つけ出すことができるかもしれない。
また、平時よりも危機のときに物事の本質がよく現われるとは、よくいわれることだが、それは室町時代の飢饉についても当てはまる。本書では飢饉を通して、政治制度としての「室町幕府」や経済制度としての「荘園制」、中世人の心性の特質などについても、あわせて解説してゆきたい。
吉川弘文館、清水克行『大飢饉、室町社会を襲う!』P7-8
この時代の飢饉については以前当ブログで紹介した藤木久志著『土一揆と城の戦国を行く』ともテーマが重なりますが、本書ではまた違った視点から飢饉やその時代背景を学ぶことができます。
あの『室町は今日もハードボイルド』を書いた著者による語りは今作も刺激的です。ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。
以上、「清水克行『大飢饉、室町社会を襲う!』概要と感想~室町時代の過酷な実態を知れる刺激的一冊!」でした。
Amazon商品紹介ページはこちら
大飢饉、室町社会を襲う! (歴史文化ライブラリー)
次の記事はこちら
あわせて読みたい
神田千里編『民衆の導師 蓮如』概要と感想~本願寺中興の祖蓮如の生涯と時代背景を知れるおすすめ本
本書は浄土真宗中興の祖蓮如の生涯と時代背景を知れるおすすめ参考書です。
編著者の神田千里氏は当ブログでもこれまで『一向一揆と石山合戦』や『宗教で読む戦国時代』をご紹介しました。
神田氏は従来の通説的な歴史観ではなく、近年どんどん明らかになってきている当時の時代背景をベースに驚きの事実を紹介してくれます。
前の記事はこちら
あわせて読みたい
神田千里『宗教で読む戦国時代』概要と感想~戦国時代の人々が共有していた「天道」とは何か。私達の常...
戦国時代における宗教とはどのようなものだったのかを学ぶのにこの本は必読と言ってよいほど素晴らしい参考書でした。
しかもこの本でも私達の常識を覆す驚きの説が語られます。特に「天道」という当時の日本人が広く受け入れていた考え方についての考察はあまりに衝撃的でした。
関連記事
あわせて読みたい
清水克行『室町は今日もハードボイルド』概要と感想~私達の常識を覆す衝撃の1冊!面白すぎです!
この本は私達が驚くような内容が次々と語られる一冊です。
室町時代がいかにアナーキーで暴力的でハードボイルドだったか。エンタメ感の強いタイトルや表紙とは裏腹に著者は資料に基づいた学術的な内容を楽しく解説していきます。
著者の語るエピソードもくすっとしてしまうユーモアもたっぷりで非常に読みやすいです。
あわせて読みたい
清水克行、高野秀行『世界の辺境とハードボイルド室町時代』概要と感想~室町とソマリランド!強烈な対...
以前の記事で紹介した『室町は今日もハードボイルド』も最高にエキサイティングな作品でしたが、今作は対談ということでまた違った視点から室町や現代世界を見ることができる実に刺激的な一冊となっています。これはぜひ学生にも読んでほしいなと強く思います。私達の常識や先入観を破壊する名対談です。ぜひぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。
あわせて読みたい
藤木久志『土一揆と城の戦国を行く』概要と感想~室町時代のどぎつい現実を知れるおすすめ本!自力救済...
本書では室町、戦国時代にかけて頻発した土一揆や戦乱による村人の苦しい生活ぶりを知ることになります。
この本も私達の固定観念を覆す刺激的な一冊です。私達が想像するよりもはるかにバイオレンスな世界がそこには広がっていました。
あわせて読みたい
山田康弘『足利将軍たちの戦国乱世』概要と感想~戦国時代の室町幕府の意外な事実を知れる刺激的な名著!
応仁の乱後の室町幕府の将軍は傀儡だったというのが世間の一般的なイメージでありますがそれとは全く異なる事実を本書で見ていくことになります。戦国時代に比べて影の薄い室町時代ではありますが、こんなに面白い時代だったとは!これはものすごい名著です。ぜひおすすめしたいです。
あわせて読みたい
神田千里『一向一揆と石山合戦』概要と感想~一向一揆は作られたイメージだった!?本願寺教団急拡大の背...
戦国時代の一揆といえば浄土真宗門徒による一向一揆というイメージが私達にはありますが実はこれが後世に作られた説話だったとしたらどうでしょう。戦国当時としては「一向一揆」という言葉がほとんど使われず、真宗門徒による一揆という観念すら乏しかったのだそうです。では、なぜ「この時代に一向一揆が頻発し、歴史に大きな影響を与えた」と私達は教えられることになったのでしょうか。そうしたからくりが本書で明らかにされます。これには私も驚きました。
あわせて読みたい
神田千里『顕如』概要と感想~本願寺教団はなぜ戦国時代に信長と戦えるほど巨大化したのか。その歴史的...
顕如は石山合戦で織田信長軍と戦った本願寺の門主として有名な人物です。
この本では戦国時代になぜ本願寺は織田信長と10年近くも戦えたほど強力な存在だったのかを知ることができます。
本願寺教団側から語られる歴史とは違った視点で学べる本書は実に刺激的な一冊です。
あわせて読みたい
今谷明『天文法華の乱』概要と感想~1530年代京都で起きた宗教戦乱の実態に迫るおすすめ参考書
本書は私達の常識を覆す衝撃的な1冊です。
室町、戦国期はとにかく複雑です。なぜ京都で日蓮宗が急拡大し、1536年に京都を焼き尽くす大事件が起きるほどになってしまったかということには多種多様な背景が絡んできます。まさに宗教は宗教だけにあらず。本書ではそんな複雑怪奇な政治経済、時代背景を時系列に沿って読み解いていきます。