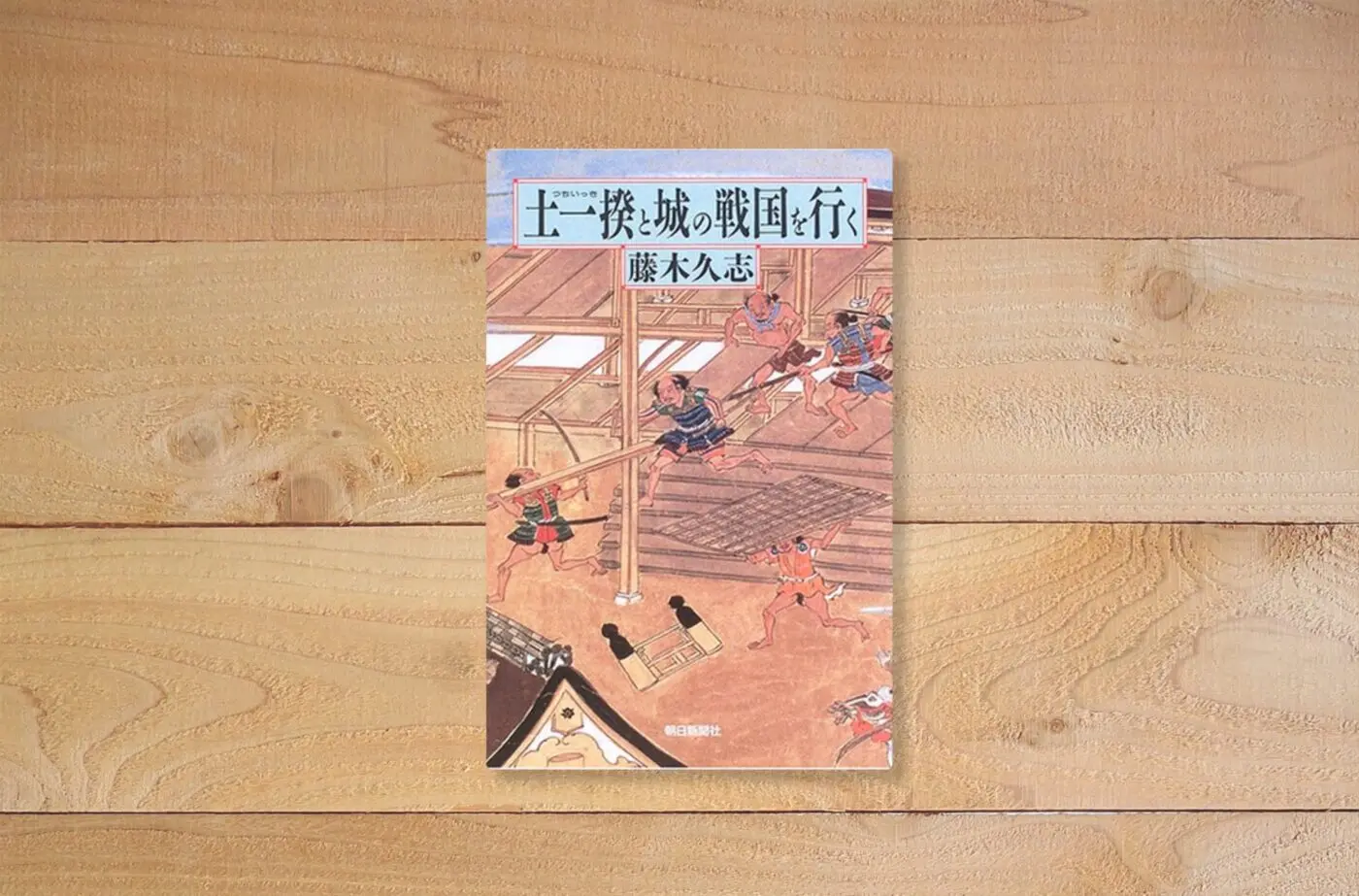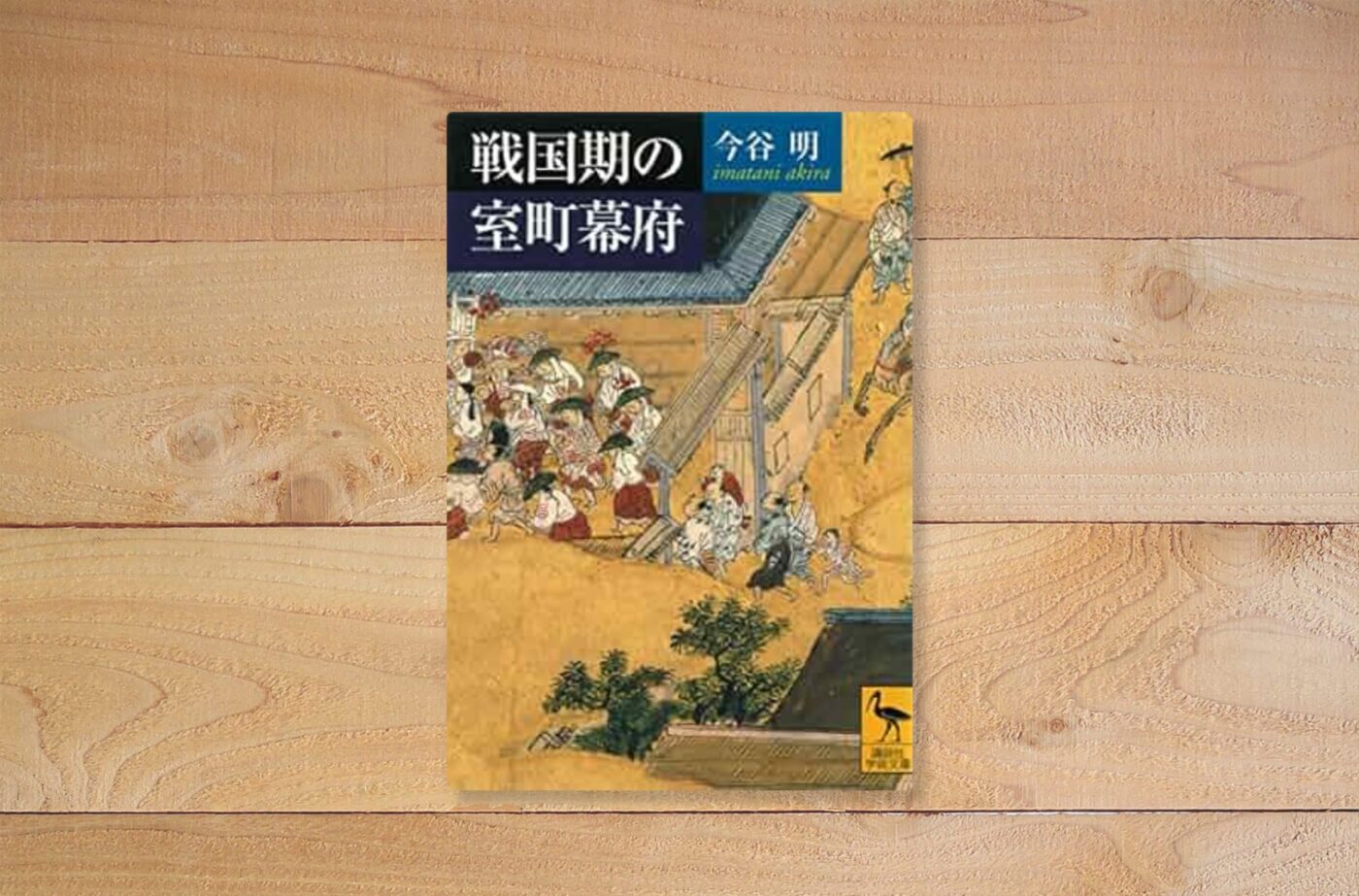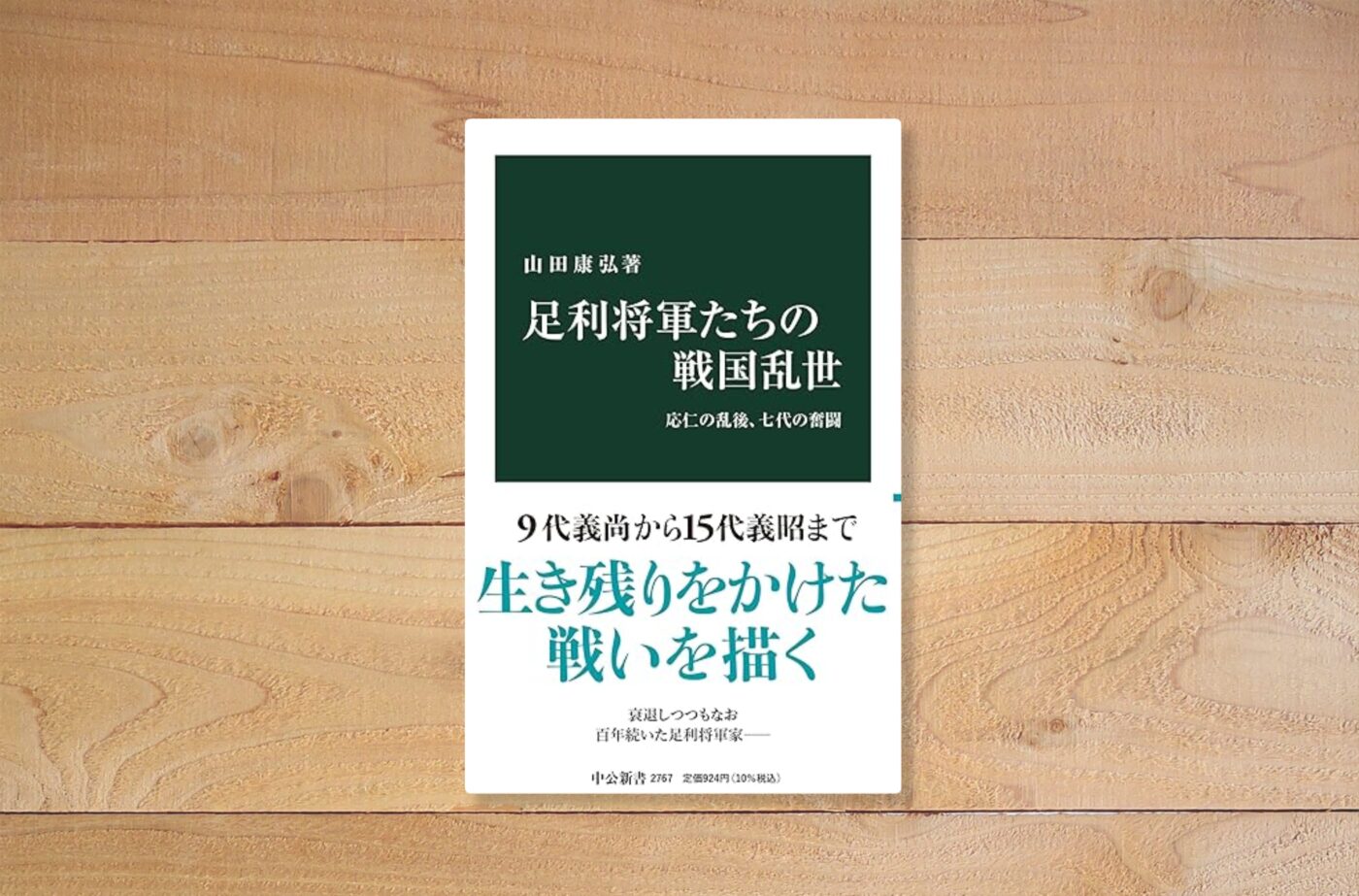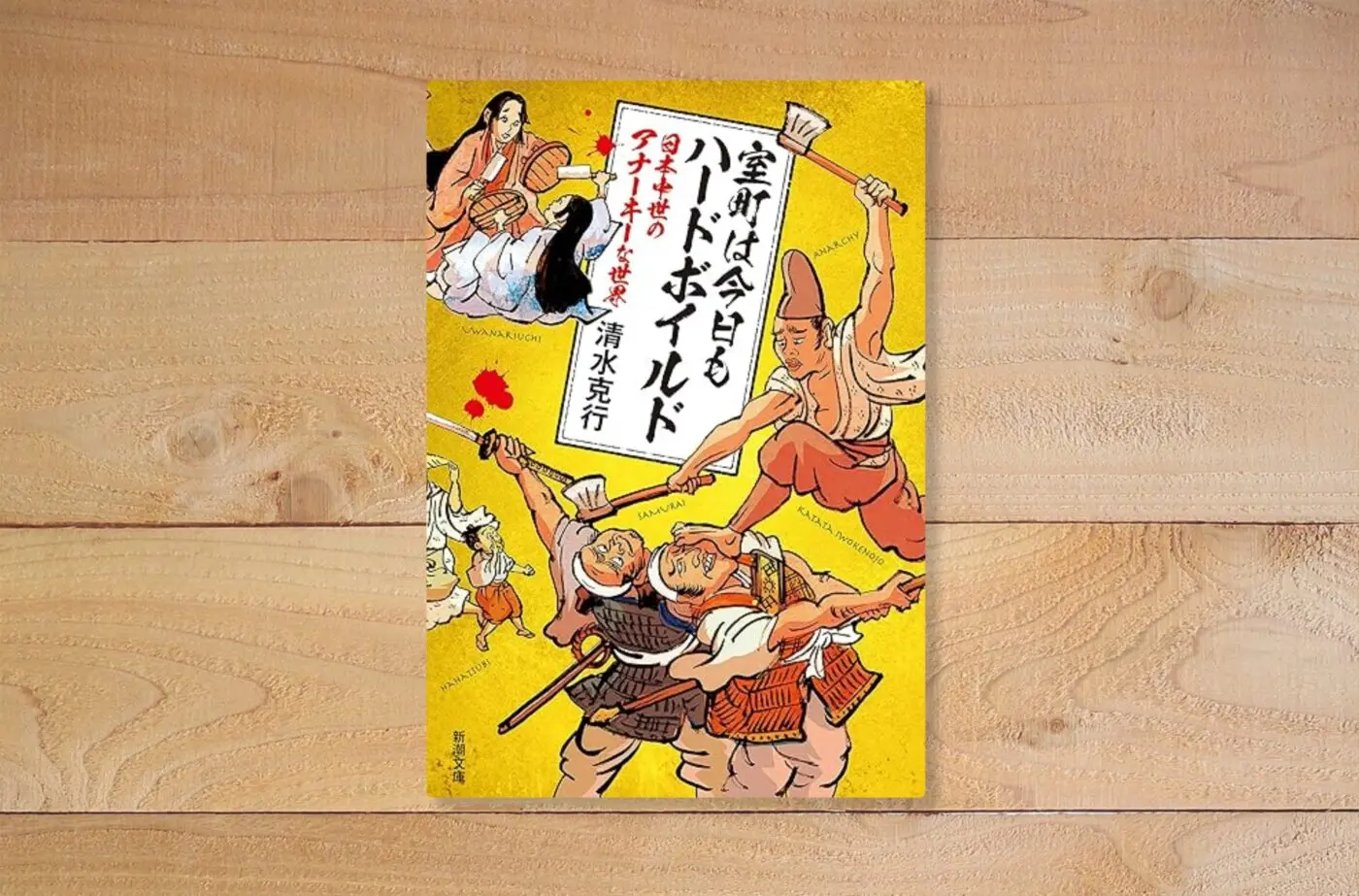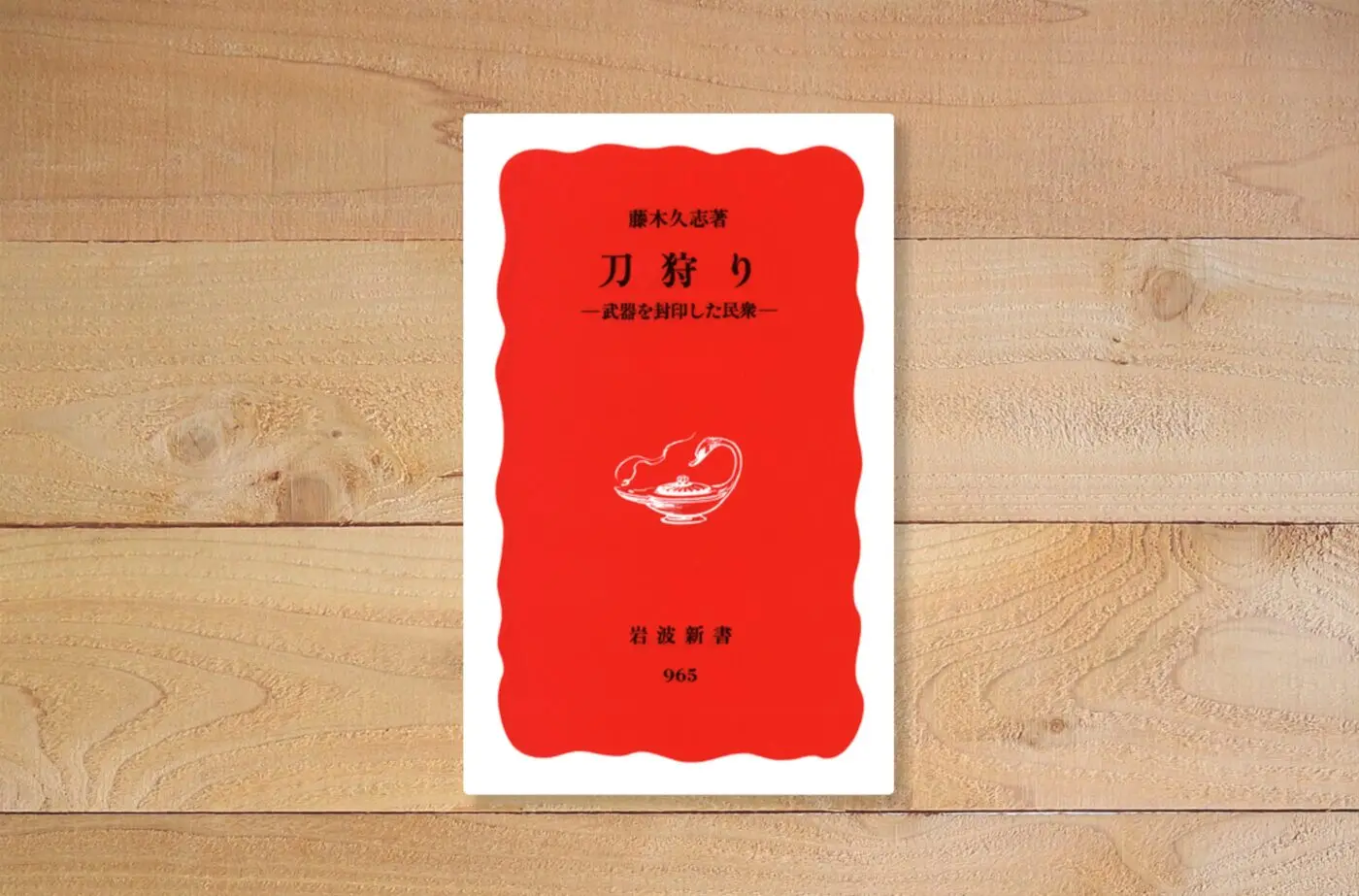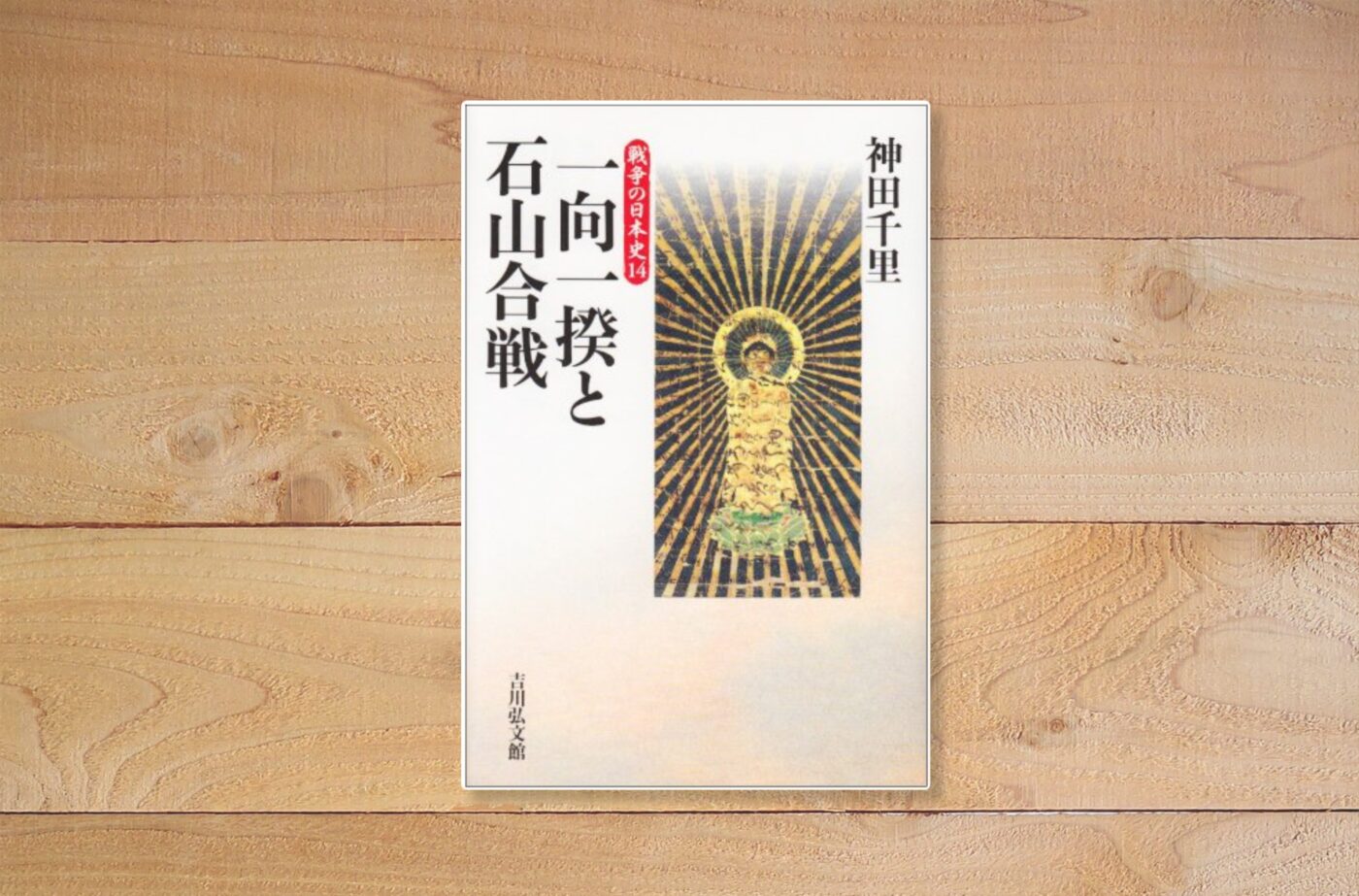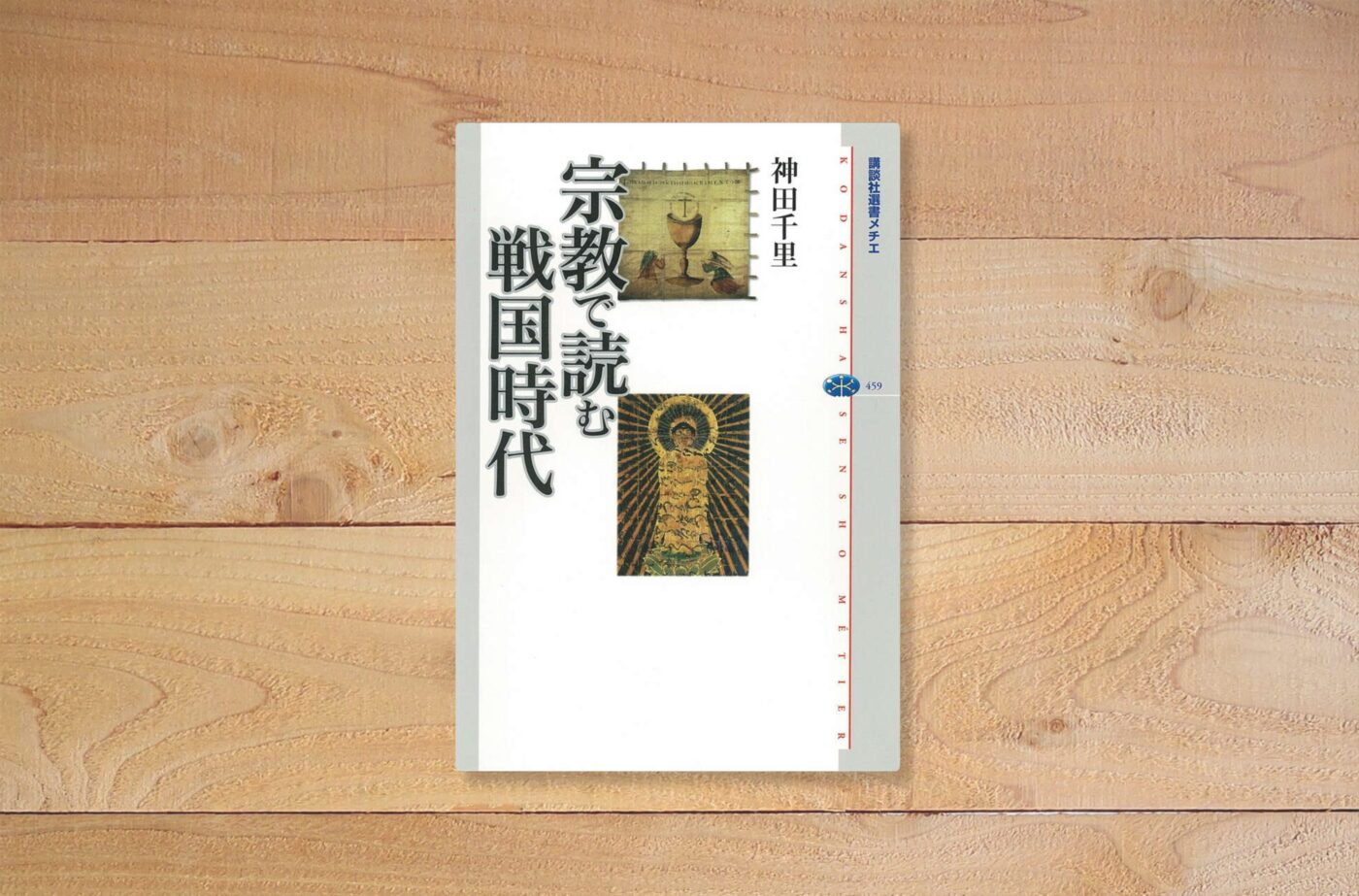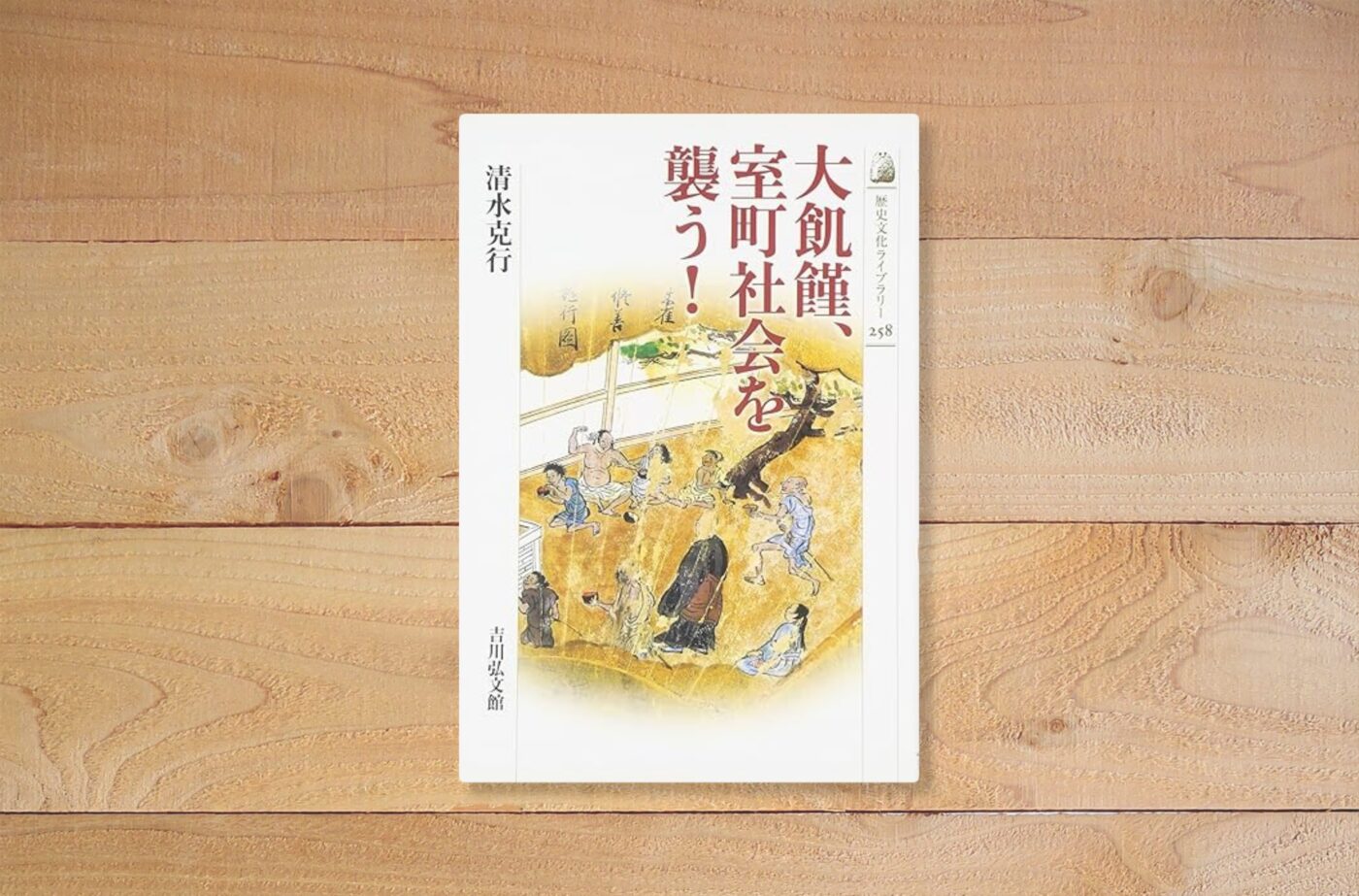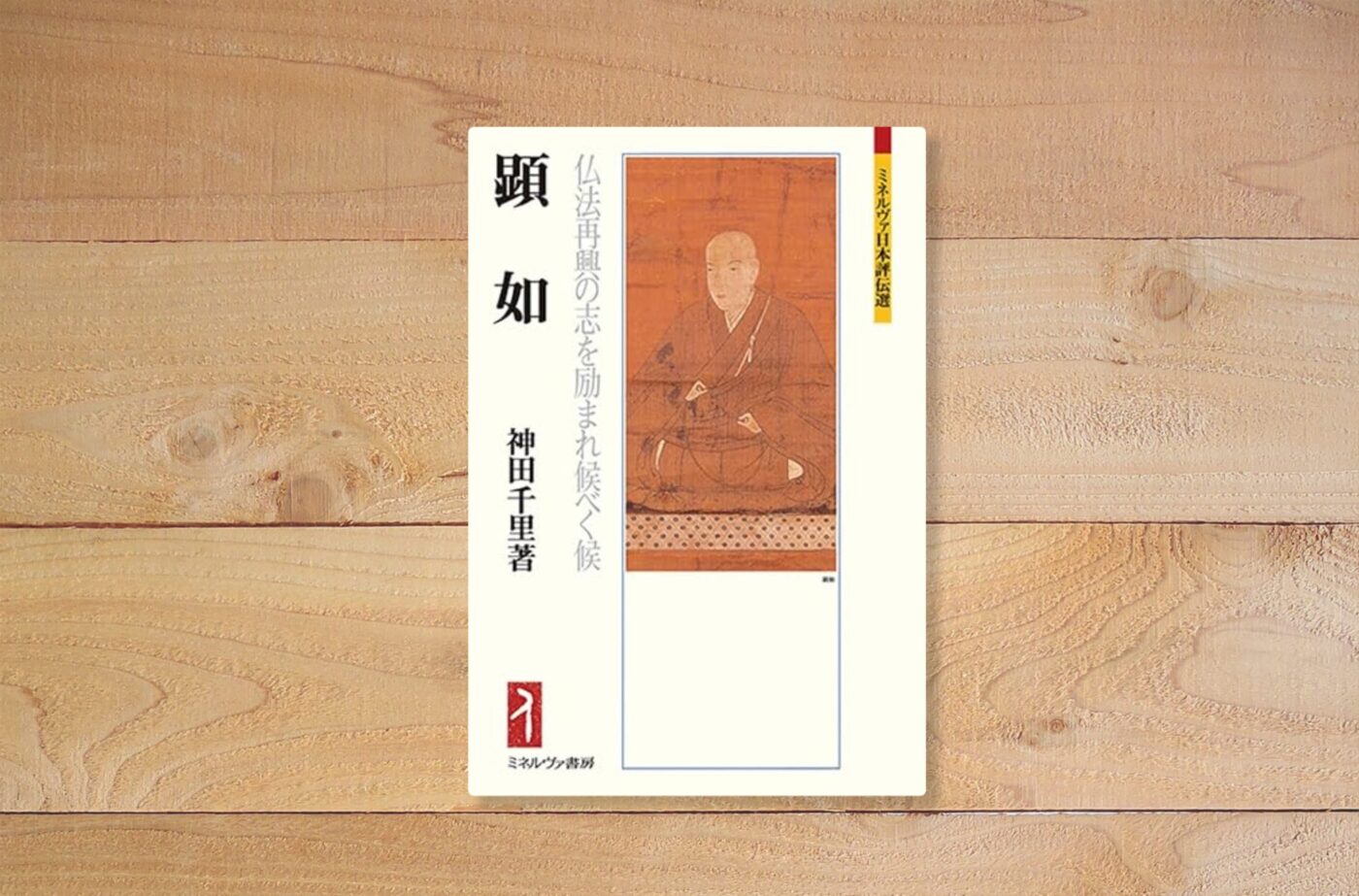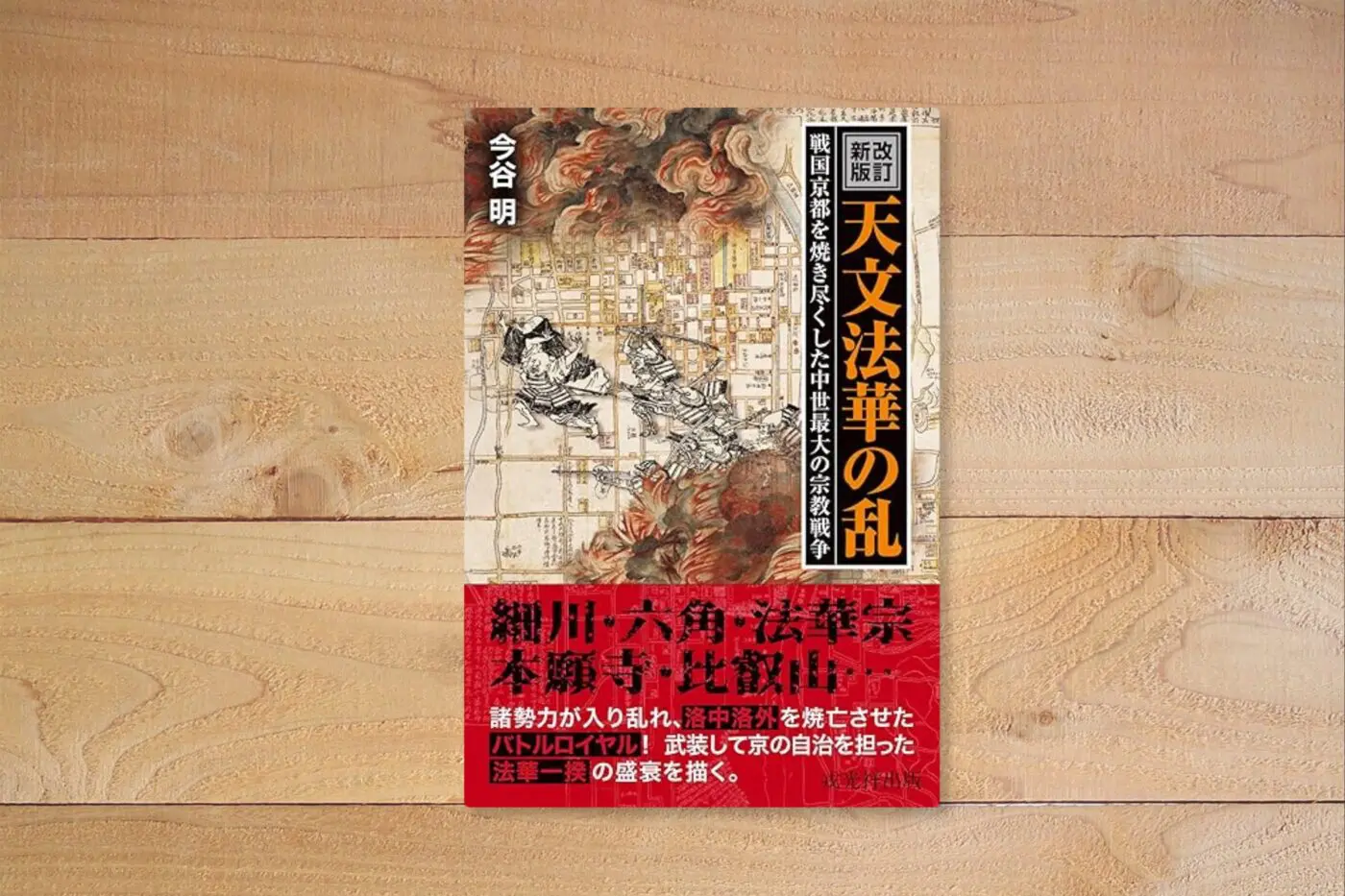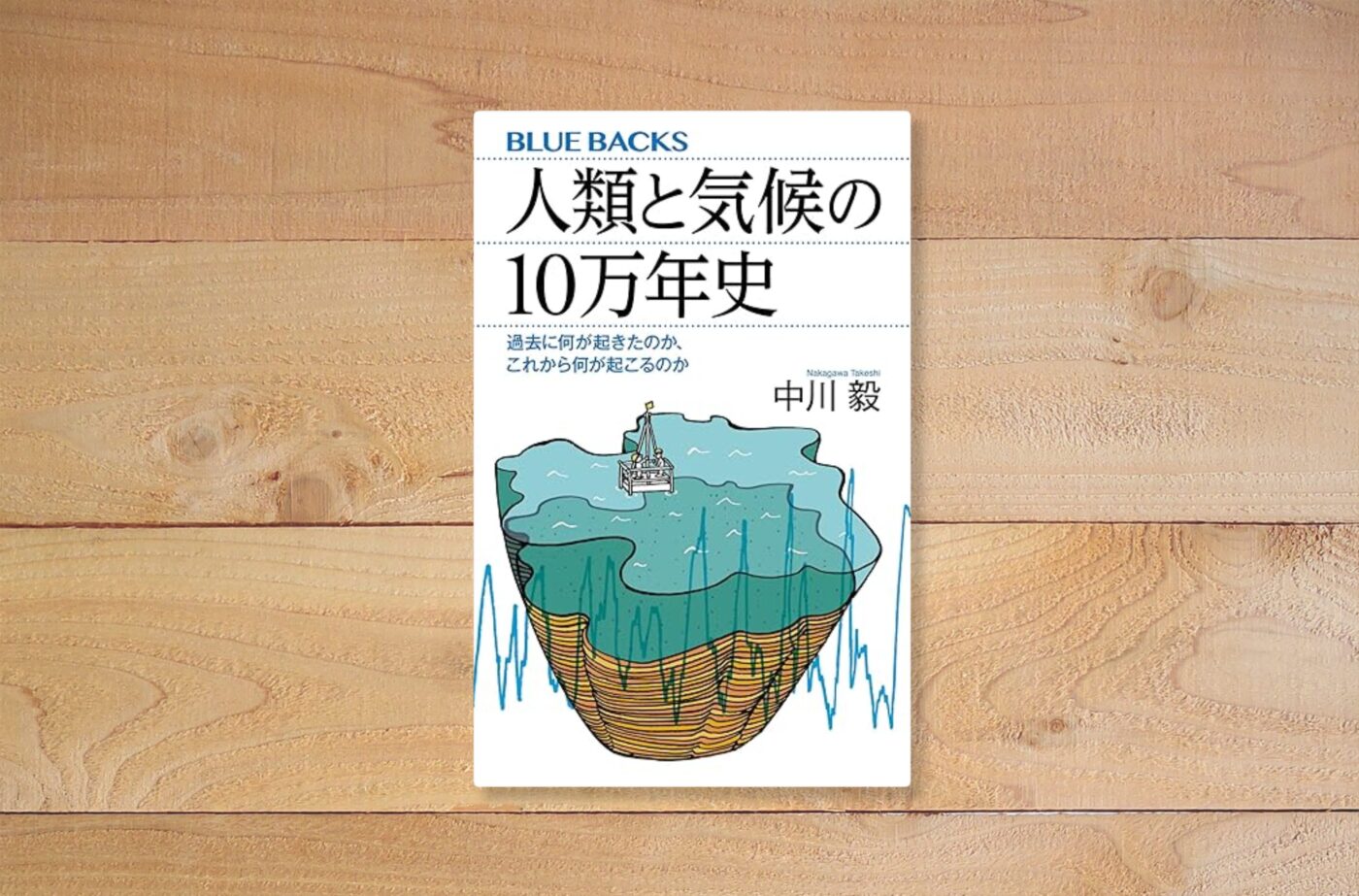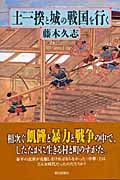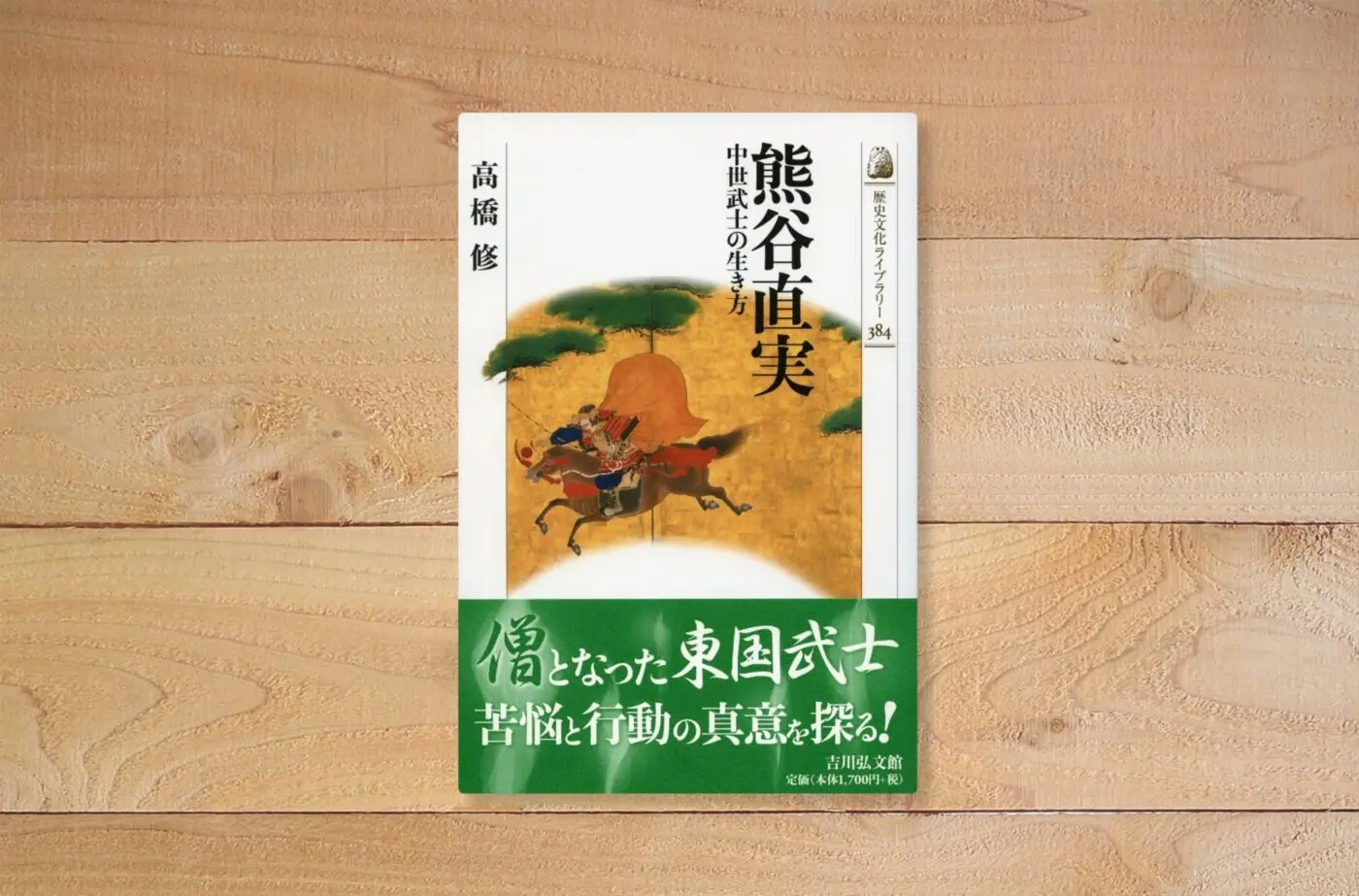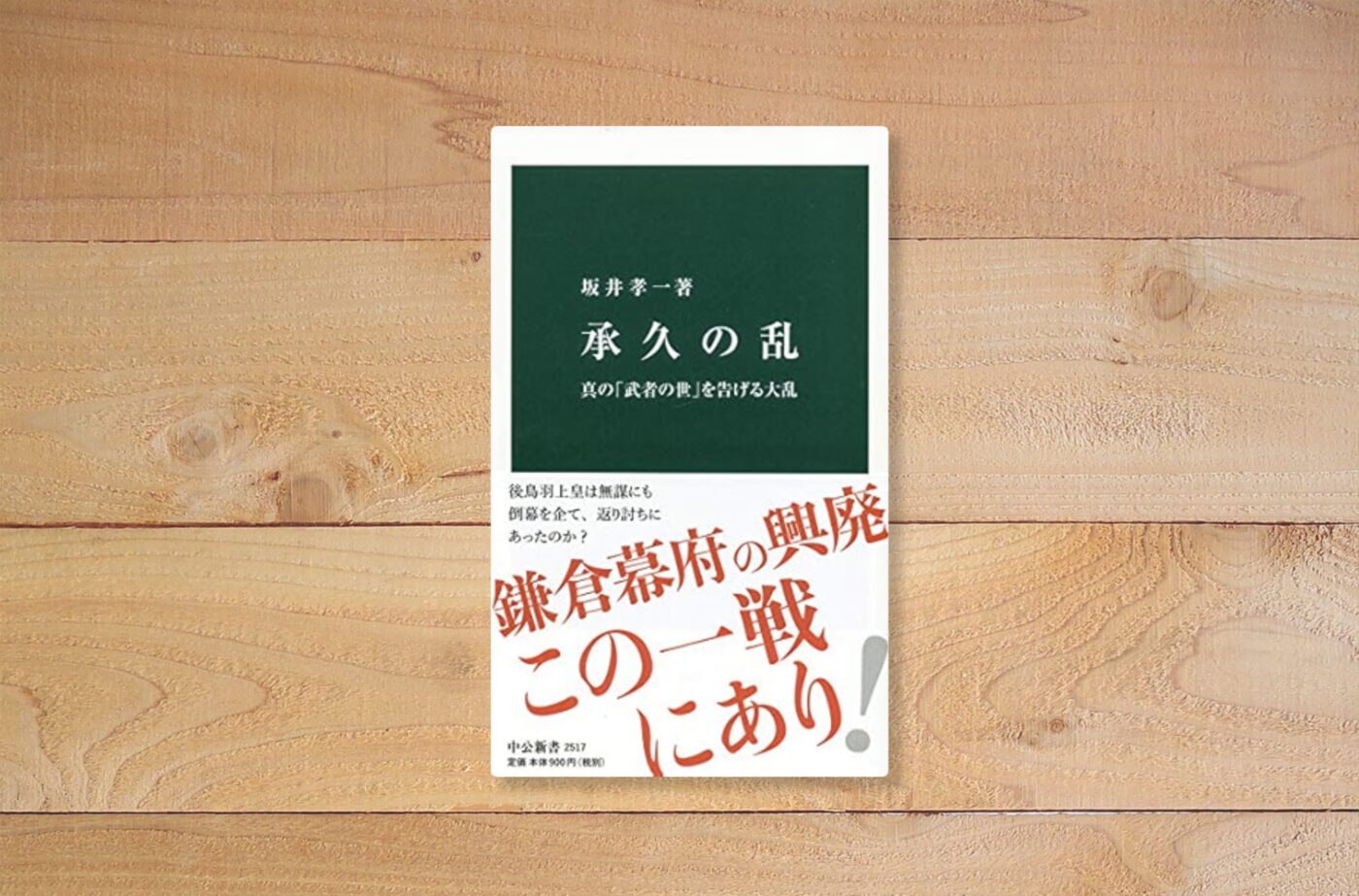目次
藤木久志『土一揆と城の戦国を行く』概要と感想~室町時代のどぎつい現実を知れるおすすめ本!自力救済社会の究極がここに
今回ご紹介するのは2006年に朝日新聞社より発行された藤木久志著『土一揆と城の戦国を行く』です。
早速この本について見ていきましょう。
世界各地で広がり続く内戦は多くの難民を生み出している。かつて日本にも同様な時代があった。飢饉で村を捨て、都市に流れ込む。流民たちが武器を持ち、生存をかけて戦う。日本の中世とはそういう時代だった。戦争から平和へ、武具を取り上げた近世の太平は、中世を克服することにほかならなかったのだ。『雑兵たちの戦場』で鮮やかに日本の中世像を書き換えた著者の「戦国を行く」シリーズ第3弾。
朝日新聞出版商品紹介ページより
本書では室町、戦国時代にかけて頻発した土一揆や戦乱による村人の苦しい生活ぶりを知ることになります。
著者によれば1300年頃から1850年頃は地球規模の「小氷河期」となっていて、特に応仁の乱を挟む100年は「夏が来なかった時代」と言われるほどの厳しい気候だったとされています。つまり、絶望的な飢饉が日常的に人々を襲う時代だったということになります。
そんなただでさえ生存困難な気候の中、さらに戦乱で田畑は荒らされ、恐るべき荒廃が街を襲っていました。そんな極限状態の中、村の人々はどのように生き抜いたのかということが本書で語られます。この本も私達の固定観念を覆す刺激的な一冊です。私達が想像するよりもはるかにバイオレンスな世界がそこには広がっていました。
暴力という前提がなければ全く生存不可能な世界です。ただ、そんな中でも本書を読めば寺院がある特殊な役割を果たしていたことにも私達は気づかされることになります。これもまた本願寺教団の形成を考える上で大きな示唆を与えてくれる内容でありました。
前回の「今谷明『戦国期の室町幕府』概要と感想~臨済宗五山派と幕府の関係性について知るのにおすすめ!実務官僚としての禅僧の存在とは」の記事でも室町戦国期の独特な時代背景があったからこそ本願寺教団が急拡大したということをお話ししましたが、本書ではそれをさらに具体的に見ていくことができます。
これは私も読んで衝撃でした。やはり「宗教は宗教だけにあらず」。私達の常識や先入観を覆すとてつもない世界がここにありました。これはものすごい名著です。
以前紹介した清水克行著『室町は今日もハードボイルド』もこうしたアナーキーでハードボイルドな室町時代について詳しく論じていますが、ぜひ合わせておすすめしたい作品となっています。ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。
以上、「藤木久志『土一揆と城の戦国を行く』概要と感想~室町時代のどぎつい現実を知れるおすすめ本!自力救済社会の究極がここに」でした。
Amazon商品紹介ページはこちら
土一揆と城の戦国を行く (朝日選書 808)
次の記事はこちら
あわせて読みたい
清水克行、高野秀行『世界の辺境とハードボイルド室町時代』概要と感想~室町とソマリランド!強烈な対...
以前の記事で紹介した『室町は今日もハードボイルド』も最高にエキサイティングな作品でしたが、今作は対談ということでまた違った視点から室町や現代世界を見ることができる実に刺激的な一冊となっています。これはぜひ学生にも読んでほしいなと強く思います。私達の常識や先入観を破壊する名対談です。ぜひぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。
前の記事はこちら
あわせて読みたい
今谷明『戦国期の室町幕府』概要と感想~臨済宗五山派と幕府の関係性について知るのにおすすめ!実務官...
本書はとてつもない名著です。私もこの本には参りました。「え!?」という事実が次から次に出てきます。完全に常識が覆されました。それほどこの本は衝撃的です。
関連記事
あわせて読みたい
山田康弘『足利将軍たちの戦国乱世』概要と感想~戦国時代の室町幕府の意外な事実を知れる刺激的な名著!
応仁の乱後の室町幕府の将軍は傀儡だったというのが世間の一般的なイメージでありますがそれとは全く異なる事実を本書で見ていくことになります。戦国時代に比べて影の薄い室町時代ではありますが、こんなに面白い時代だったとは!これはものすごい名著です。ぜひおすすめしたいです。
あわせて読みたい
清水克行『室町は今日もハードボイルド』概要と感想~私達の常識を覆す衝撃の1冊!面白すぎです!
この本は私達が驚くような内容が次々と語られる一冊です。
室町時代がいかにアナーキーで暴力的でハードボイルドだったか。エンタメ感の強いタイトルや表紙とは裏腹に著者は資料に基づいた学術的な内容を楽しく解説していきます。
著者の語るエピソードもくすっとしてしまうユーモアもたっぷりで非常に読みやすいです。
あわせて読みたい
藤木久志『刀狩 武器を封印した民衆』概要と感想~「武器を失って平和化した民衆」は幻だった?常識を...
豊臣秀吉による刀狩は教科書にも掲載されている歴史上の超有名な出来事ですよね。
しかしその刀狩に関する認識が間違っていたとしたら?
本書の著者藤木久志氏の著作は以前当ブログでも『土一揆と城の戦国を行く』という名著をご紹介しましたがこの本も私達の常識を覆す作品です。
あわせて読みたい
神田千里『一向一揆と石山合戦』概要と感想~一向一揆は作られたイメージだった!?本願寺教団急拡大の背...
戦国時代の一揆といえば浄土真宗門徒による一向一揆というイメージが私達にはありますが実はこれが後世に作られた説話だったとしたらどうでしょう。戦国当時としては「一向一揆」という言葉がほとんど使われず、真宗門徒による一揆という観念すら乏しかったのだそうです。では、なぜ「この時代に一向一揆が頻発し、歴史に大きな影響を与えた」と私達は教えられることになったのでしょうか。そうしたからくりが本書で明らかにされます。これには私も驚きました。
あわせて読みたい
神田千里『宗教で読む戦国時代』概要と感想~戦国時代の人々が共有していた「天道」とは何か。私達の常...
戦国時代における宗教とはどのようなものだったのかを学ぶのにこの本は必読と言ってよいほど素晴らしい参考書でした。
しかもこの本でも私達の常識を覆す驚きの説が語られます。特に「天道」という当時の日本人が広く受け入れていた考え方についての考察はあまりに衝撃的でした。
あわせて読みたい
清水克行『大飢饉、室町社会を襲う!』概要と感想~室町時代の過酷な実態を知れる刺激的一冊!
本書では室町、戦国時代のアナーキーな時代をもたらした大きな要因のひとつである飢饉について語られていきます。
『室町は今日もハードボイルド』と同様、著者の語りはとてもわかりやすく読みやすいです。
あわせて読みたい
神田千里『顕如』概要と感想~本願寺教団はなぜ戦国時代に信長と戦えるほど巨大化したのか。その歴史的...
顕如は石山合戦で織田信長軍と戦った本願寺の門主として有名な人物です。
この本では戦国時代になぜ本願寺は織田信長と10年近くも戦えたほど強力な存在だったのかを知ることができます。
本願寺教団側から語られる歴史とは違った視点で学べる本書は実に刺激的な一冊です。
あわせて読みたい
今谷明『天文法華の乱』概要と感想~1530年代京都で起きた宗教戦乱の実態に迫るおすすめ参考書
本書は私達の常識を覆す衝撃的な1冊です。
室町、戦国期はとにかく複雑です。なぜ京都で日蓮宗が急拡大し、1536年に京都を焼き尽くす大事件が起きるほどになってしまったかということには多種多様な背景が絡んできます。まさに宗教は宗教だけにあらず。本書ではそんな複雑怪奇な政治経済、時代背景を時系列に沿って読み解いていきます。
あわせて読みたい
中川毅『人類と気候の10万年史』概要と感想~気候変動と歴史的大事件との驚きのつながりを知れる刺激的...
皆さんは「水月湖」という湖をご存じでしょうか。
かく言う私もこの本を読むまでその存在を知らなかったのですがこれが世界的にも奇跡と言われるとてつもない湖だったのです。日本では未だにマイナーな湖ではありますが地球の歴史、特に気候変動の歴史を知るのにこの湖は世界で最も注目されている湖なのだそうです。
本書はそんな奇跡の湖を調査した古気候学者中川毅氏による超刺激的な気候の歴史を知ることができます。