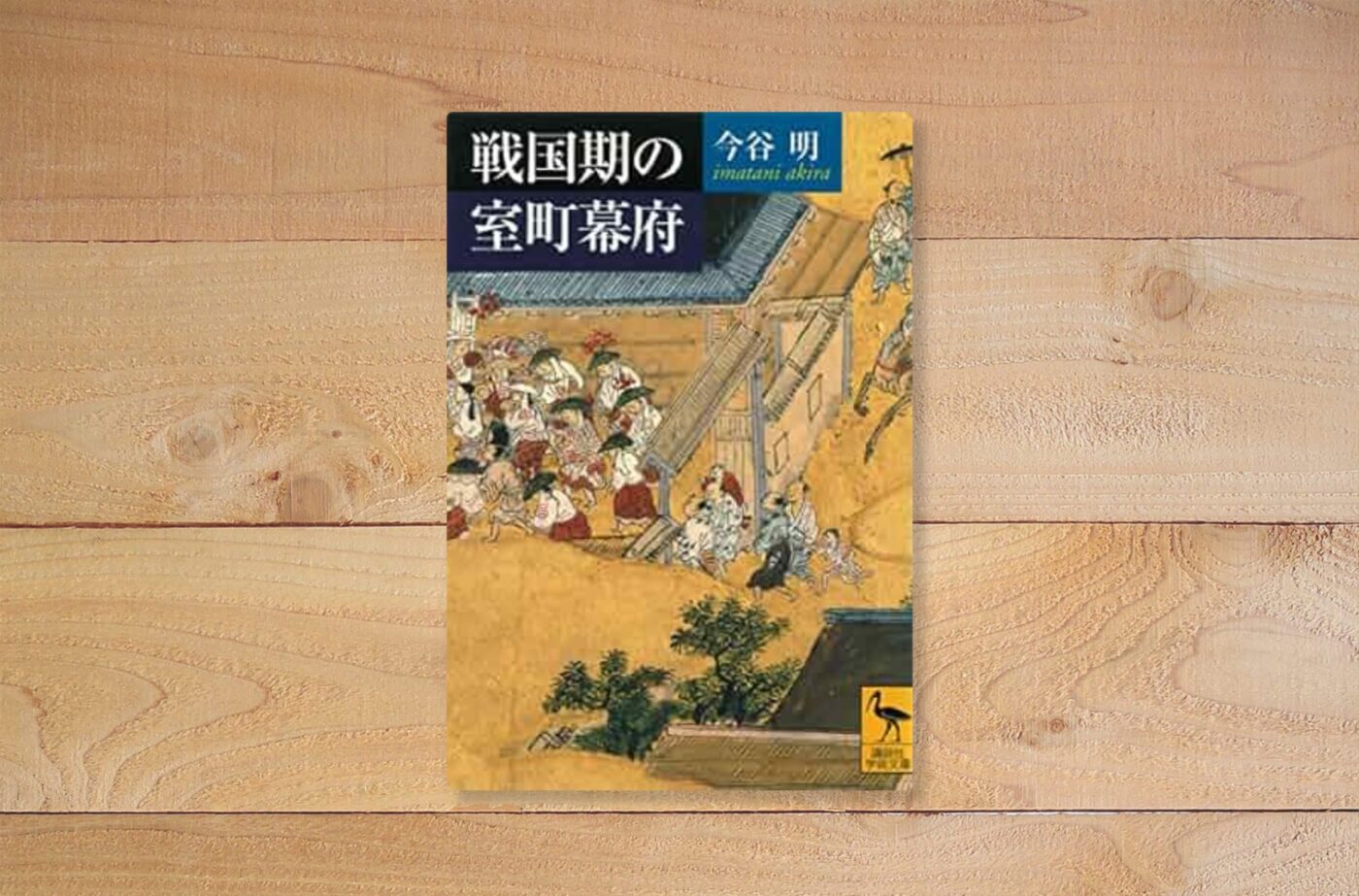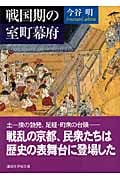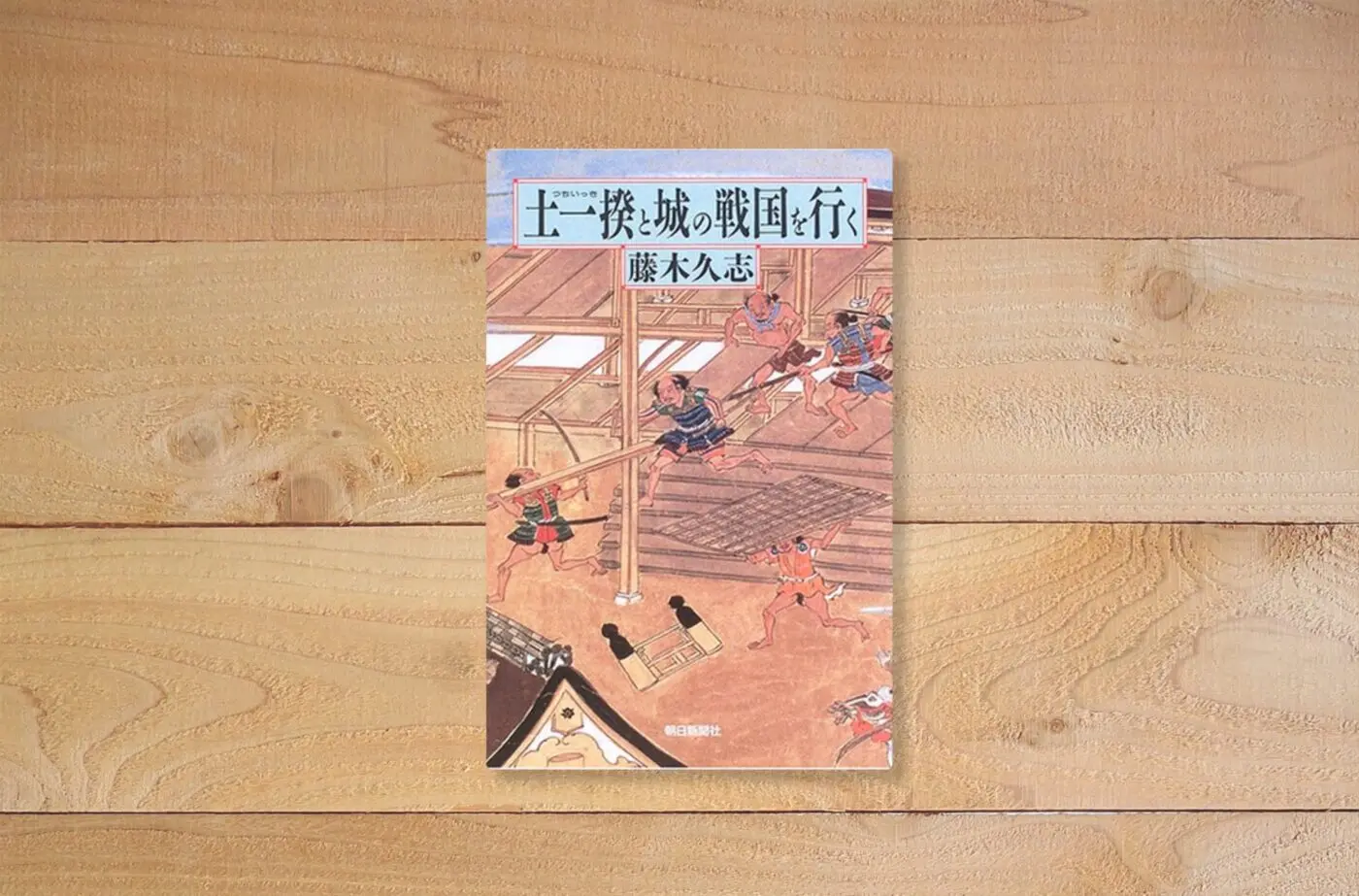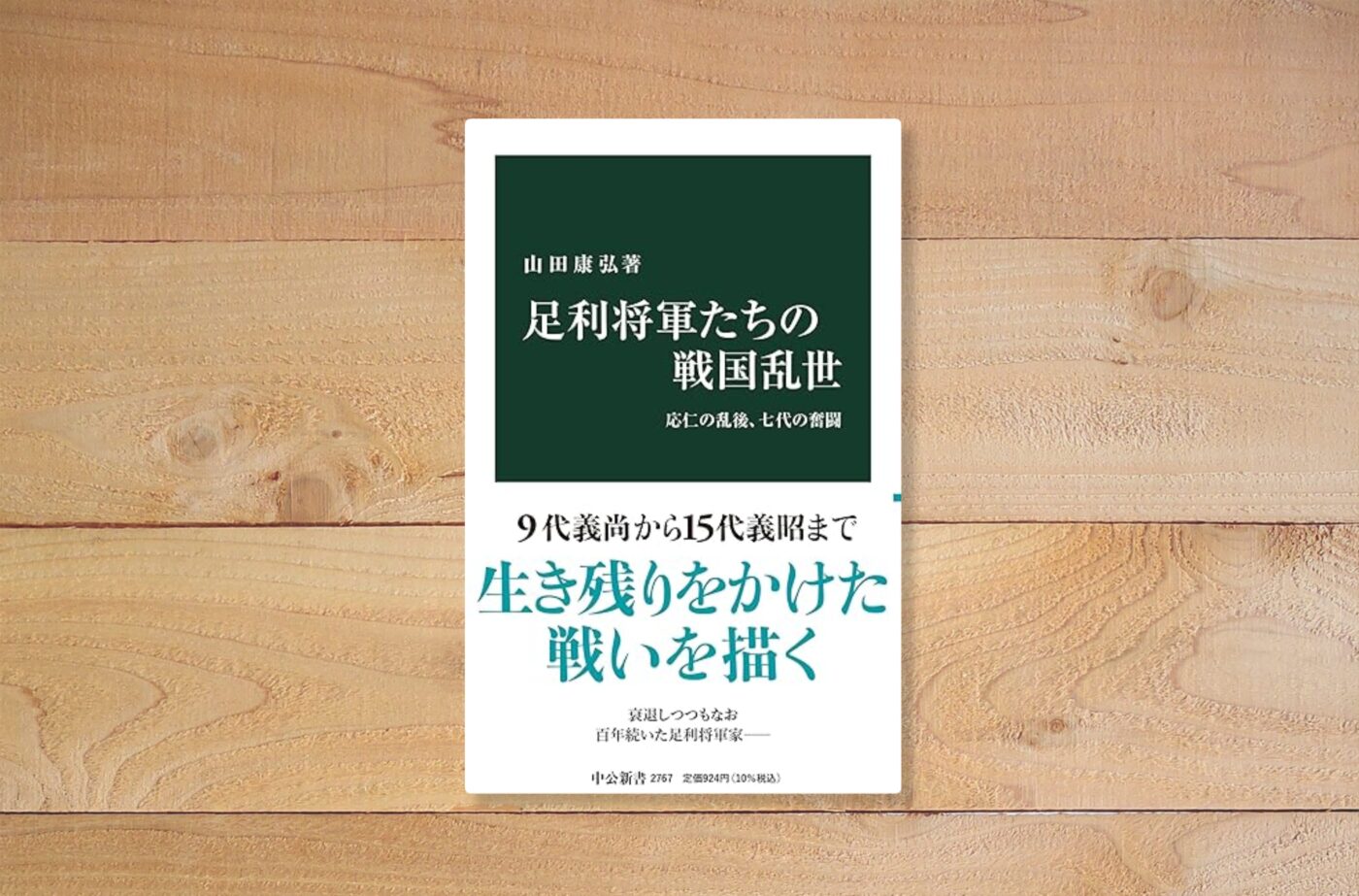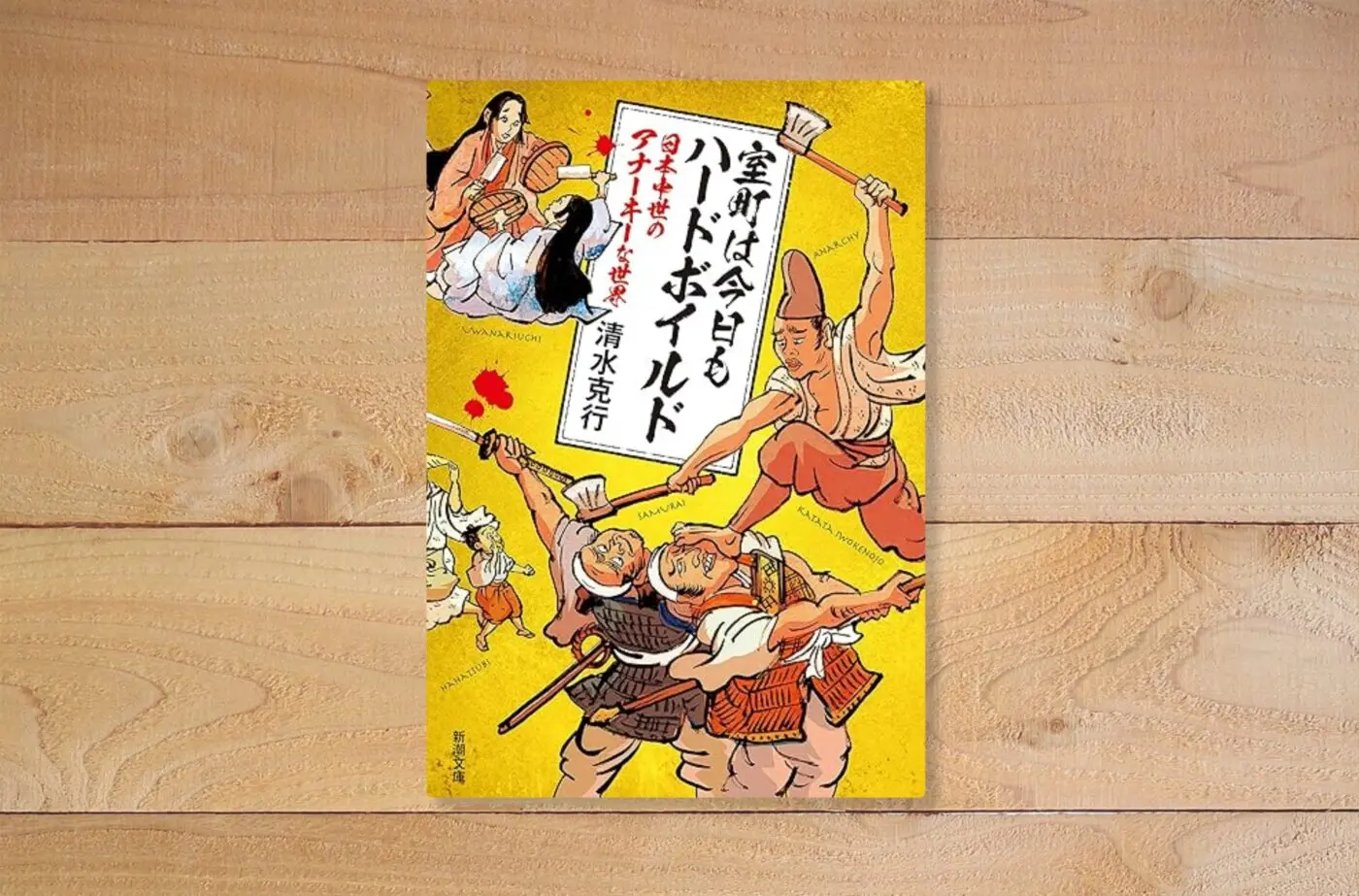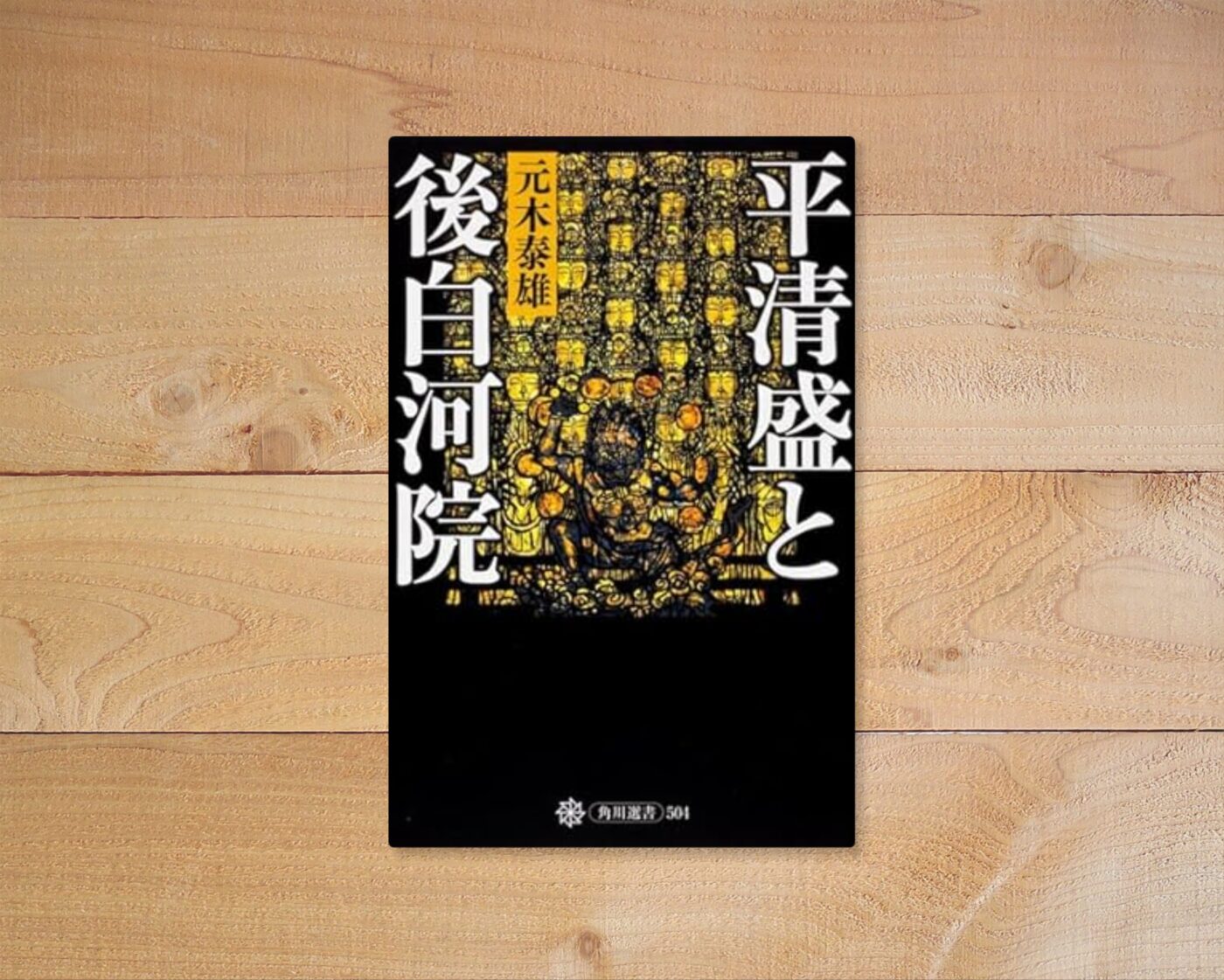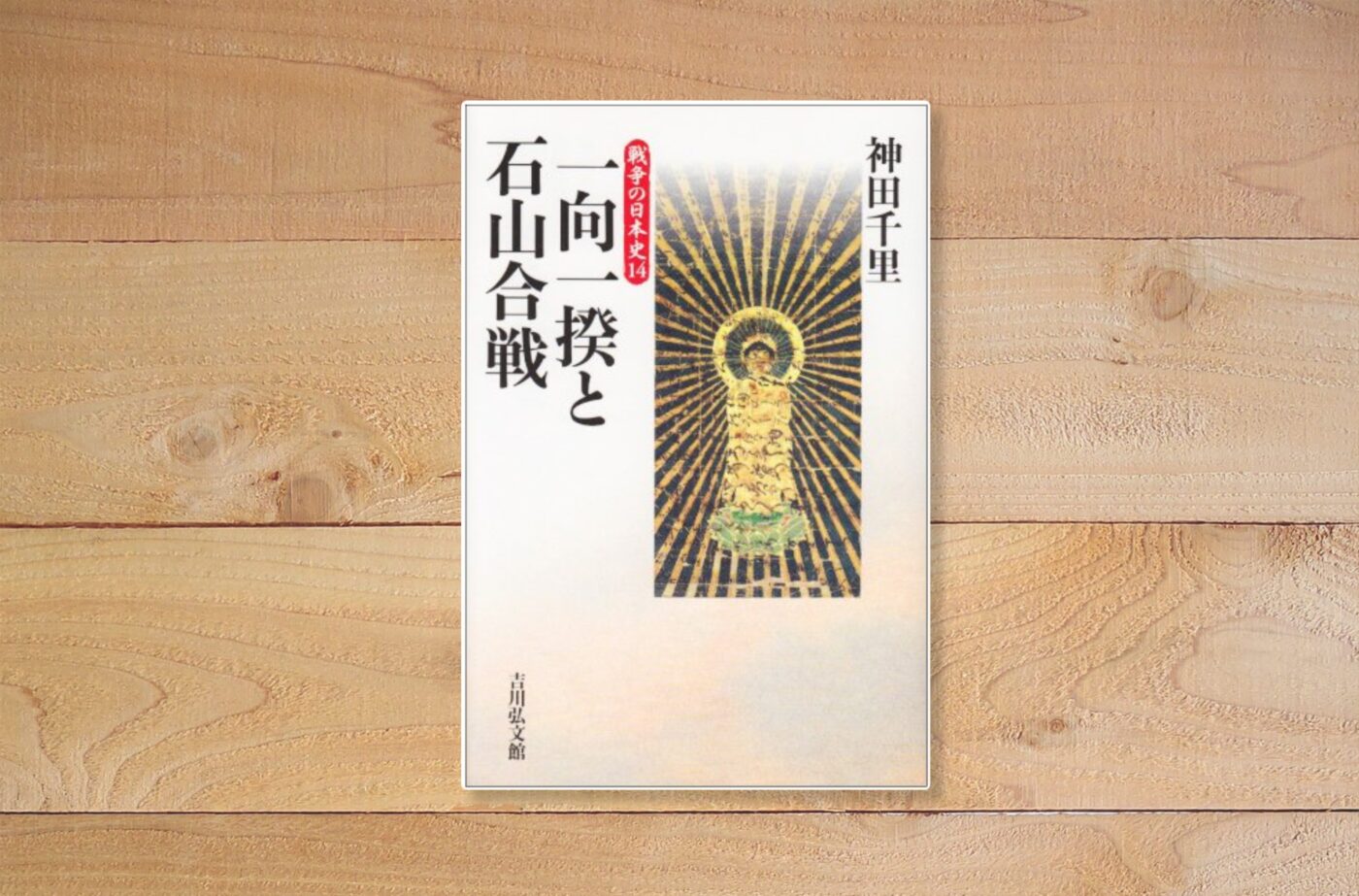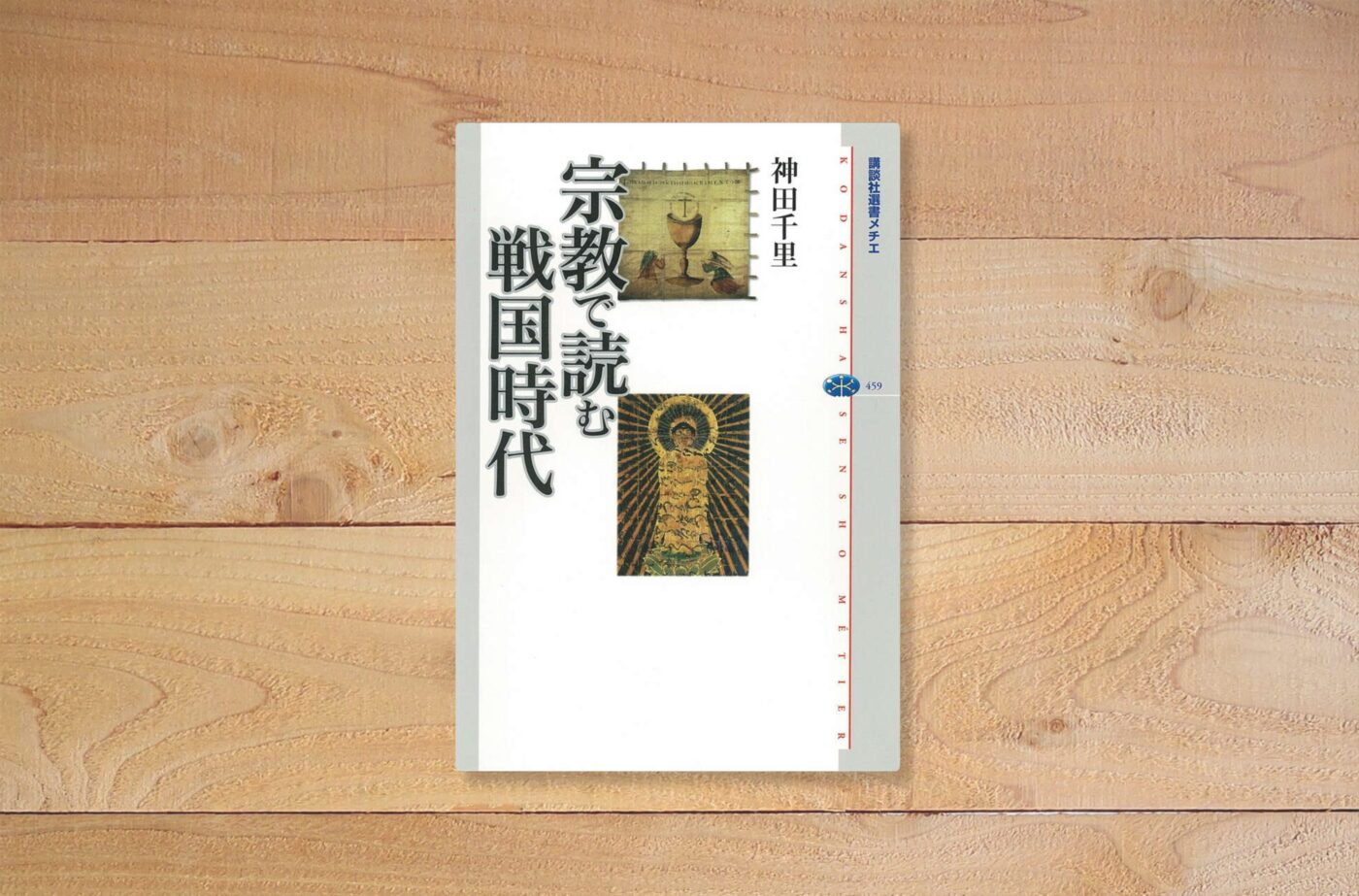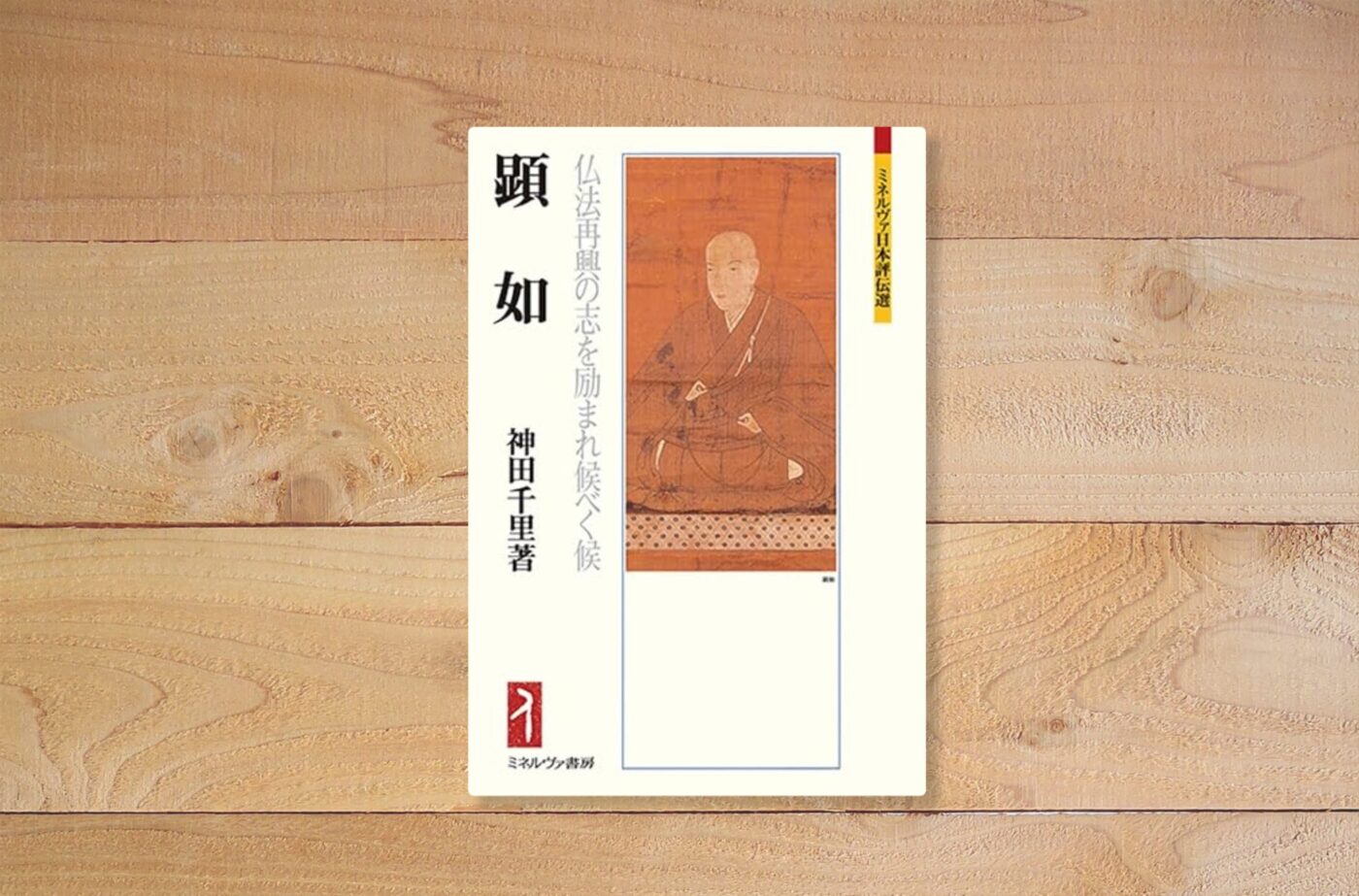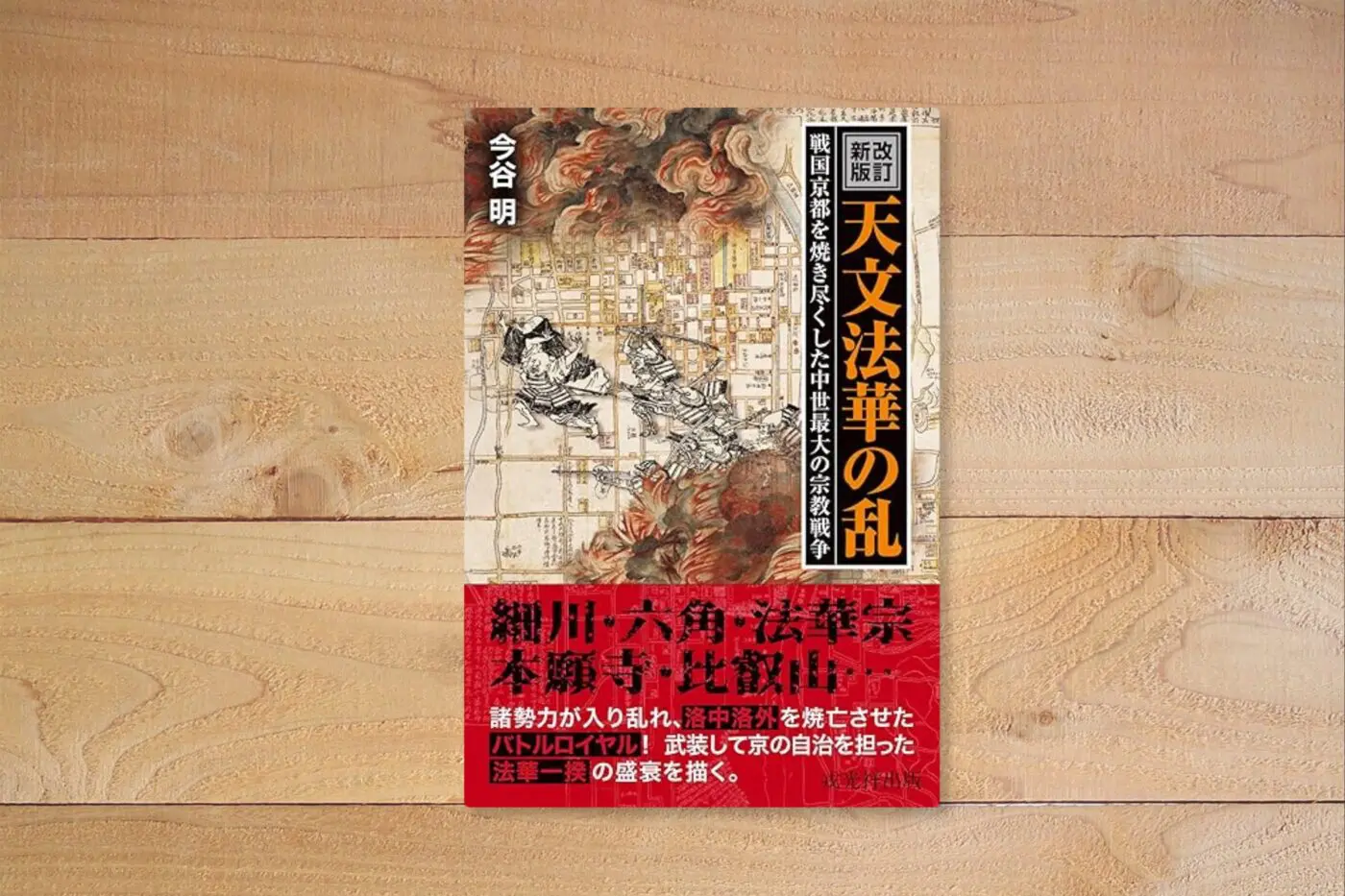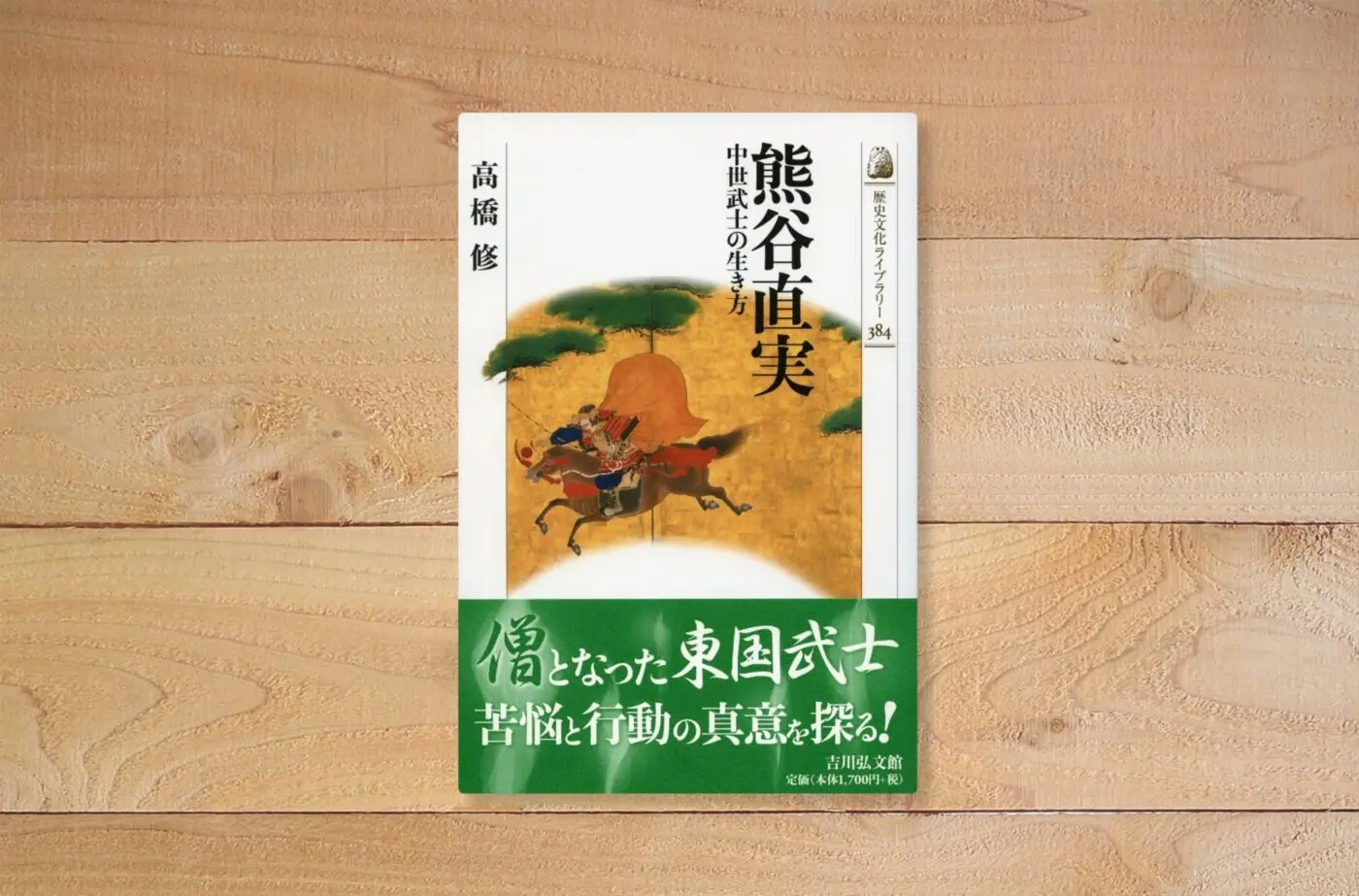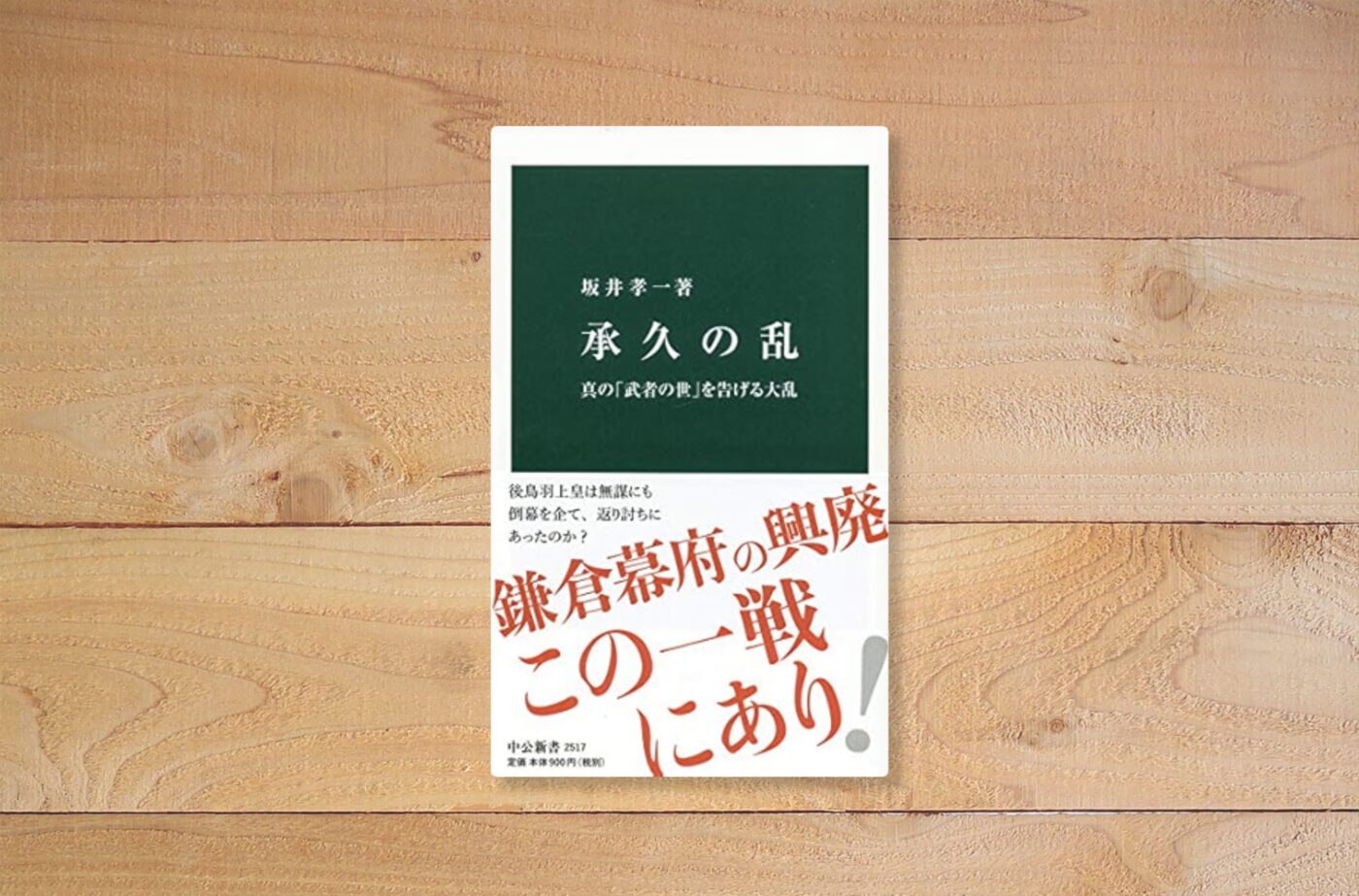目次
今谷明『戦国期の室町幕府』概要と感想~臨済宗五山派と幕府の関係性について知るのにおすすめ!実務官僚としての禅僧の存在とは
今回ご紹介するのは2006年に講談社より発行された今谷明著『戦国期の室町幕府』です。
早速この本について見ていきましょう。
土一揆の勃発、足軽・町衆の台頭――
戦乱の京都、民衆たちは歴史の表舞台に登場した
民衆が歴史の表舞台に登場し、日本文化の伝統が形成された戦国時代の京都。その実像とはどのようなものか。本書は山門と五山の争い、幕府財政、警察制度、徳政一揆等を素材に政治経済都市としての中世末期の京都を概観、応仁の乱後の自治都市成立までを精緻な論証に基づいて活写する。中世史研究に一石を投じ高い評価を得た幻の名著、待望の文庫化
Amazon商品紹介ページより
本書『戦国期の室町幕府』はとてつもない名著です。私もこの本には参りました。「え!?」という事実が次から次に出てきます。完全に常識が覆されました。
本書で最も刺激を受けたのが室町幕府と臨済宗(特に五山派)の関係性です。
室町幕府は五山たる臨済宗寺院を積極的に支援していました。そしてその支援をもとに臨済宗は一気に拡大するのでありますが、話はそれで終わりません。
なんと、当時の五山の僧侶は官僚としての役目を果たしており、幕府の経済や外交、事務を担う重要な任務を帯びていたのでありました。五山の僧侶たちは中国の先進的な文化や教養を身につけており、実務的な能力が抜群だったためその力を買われて新興勢力として急速に幕府と関係を深めていくことになります。
そして新興勢力が勃興するということは旧来の勢力が没落していくということです。
これまでの仏教界で支配的な勢力と言えば比叡山延暦寺や南都興福寺がその代表格です。これら南都北嶺の大寺院は軒並みこの室町期に大打撃を受けています。平安時代から続いてきた旧体制にとどめを刺したのが室町幕府と五山派の勃興なのでありました。
私も読んで驚きました。なんとその結末として1435年に比叡山延暦寺が完全に焼失していたのです。しかもこれが室町幕府への抗議を込めた焼身自殺だったのです。政治的に追い込まれた比叡山僧侶たちが自ら延暦寺に火をかけ、お堂だけでなく貴重な仏像や文献、あらゆるものを道連れにしたのでありました。
そうです。比叡山は織田信長が焼き討ちにする135年も前にすでに灰燼に帰していたのです。つまり信長の比叡山焼き討ちのハードルはこの時点で一気に下がっていたのです。これがもし創建以来の建物や宝物が残っていたのだとしたらさすがの信長も躊躇したかもしれません。しかしこの時点ですでに焼き討ちされていたとなると話は別です。もちろん、それでも比叡山を焼き討ちにするのはとてつもないことではありますが、私は本書を読みそれこそ仰天することになりました。
他にも本書では驚くことがどんどん出てきます。蓮如を筆頭とした本願寺教団が一気に勢力を増すのもこの時代のことです。本書では直接的には蓮如のことは語られませんが、このように従来の旧勢力が軒並み没落していく中で新興勢力が生まれてくるという混沌とした時代がこの室町戦国期なのでありました。
本願寺教団の急成長の背景を考える上でも本書はあまりに刺激的な一冊でした。ここではこれ以上どう語っていいか私も困惑しています。それほどこの本は衝撃的です。私達の常識を破壊する凄まじい一冊です。ぜひぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。
以上、「今谷明『戦国期の室町幕府』概要と感想~臨済宗五山派と幕府の関係性について知るのにおすすめ!実務官僚としての禅僧の存在とは」でした。
Amazon商品紹介ページはこちら
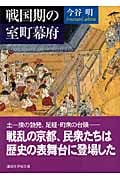
戦国期の室町幕府 (講談社学術文庫 1766)
次の記事はこちら
あわせて読みたい
藤木久志『土一揆と城の戦国を行く』概要と感想~室町時代のどぎつい現実を知れるおすすめ本!自力救済...
本書では室町、戦国時代にかけて頻発した土一揆や戦乱による村人の苦しい生活ぶりを知ることになります。
この本も私達の固定観念を覆す刺激的な一冊です。私達が想像するよりもはるかにバイオレンスな世界がそこには広がっていました。
前の記事はこちら
あわせて読みたい
山田康弘『足利将軍たちの戦国乱世』概要と感想~戦国時代の室町幕府の意外な事実を知れる刺激的な名著!
応仁の乱後の室町幕府の将軍は傀儡だったというのが世間の一般的なイメージでありますがそれとは全く異なる事実を本書で見ていくことになります。戦国時代に比べて影の薄い室町時代ではありますが、こんなに面白い時代だったとは!これはものすごい名著です。ぜひおすすめしたいです。
関連記事
あわせて読みたい
清水克行『室町は今日もハードボイルド』概要と感想~私達の常識を覆す衝撃の1冊!面白すぎです!
この本は私達が驚くような内容が次々と語られる一冊です。
室町時代がいかにアナーキーで暴力的でハードボイルドだったか。エンタメ感の強いタイトルや表紙とは裏腹に著者は資料に基づいた学術的な内容を楽しく解説していきます。
著者の語るエピソードもくすっとしてしまうユーモアもたっぷりで非常に読みやすいです。
あわせて読みたい
元木泰雄『平清盛と後白河院』あらすじと感想~清盛の権力奪取がそう単純ではなかったことを知れるおす...
予測不能のカオスを丁寧に追っていく本書は非常にスリリングで刺激的です。たしかにこの本は複雑で難しいです。ただ、何度も言いますがそれは著者の責任ではなく、そもそもそういう複雑な人間関係が絡む難しい時代なのです。それをじっくりと感じていける点にこの本の最大の意義があると思います。
あわせて読みたい
清水克行、高野秀行『世界の辺境とハードボイルド室町時代』概要と感想~室町とソマリランド!強烈な対...
以前の記事で紹介した『室町は今日もハードボイルド』も最高にエキサイティングな作品でしたが、今作は対談ということでまた違った視点から室町や現代世界を見ることができる実に刺激的な一冊となっています。これはぜひ学生にも読んでほしいなと強く思います。私達の常識や先入観を破壊する名対談です。ぜひぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。
あわせて読みたい
神田千里『一向一揆と石山合戦』概要と感想~一向一揆は作られたイメージだった!?本願寺教団急拡大の背...
戦国時代の一揆といえば浄土真宗門徒による一向一揆というイメージが私達にはありますが実はこれが後世に作られた説話だったとしたらどうでしょう。戦国当時としては「一向一揆」という言葉がほとんど使われず、真宗門徒による一揆という観念すら乏しかったのだそうです。では、なぜ「この時代に一向一揆が頻発し、歴史に大きな影響を与えた」と私達は教えられることになったのでしょうか。そうしたからくりが本書で明らかにされます。これには私も驚きました。
あわせて読みたい
神田千里『宗教で読む戦国時代』概要と感想~戦国時代の人々が共有していた「天道」とは何か。私達の常...
戦国時代における宗教とはどのようなものだったのかを学ぶのにこの本は必読と言ってよいほど素晴らしい参考書でした。
しかもこの本でも私達の常識を覆す驚きの説が語られます。特に「天道」という当時の日本人が広く受け入れていた考え方についての考察はあまりに衝撃的でした。
あわせて読みたい
神田千里『顕如』概要と感想~本願寺教団はなぜ戦国時代に信長と戦えるほど巨大化したのか。その歴史的...
顕如は石山合戦で織田信長軍と戦った本願寺の門主として有名な人物です。
この本では戦国時代になぜ本願寺は織田信長と10年近くも戦えたほど強力な存在だったのかを知ることができます。
本願寺教団側から語られる歴史とは違った視点で学べる本書は実に刺激的な一冊です。
あわせて読みたい
今谷明『天文法華の乱』概要と感想~1530年代京都で起きた宗教戦乱の実態に迫るおすすめ参考書
本書は私達の常識を覆す衝撃的な1冊です。
室町、戦国期はとにかく複雑です。なぜ京都で日蓮宗が急拡大し、1536年に京都を焼き尽くす大事件が起きるほどになってしまったかということには多種多様な背景が絡んできます。まさに宗教は宗教だけにあらず。本書ではそんな複雑怪奇な政治経済、時代背景を時系列に沿って読み解いていきます。