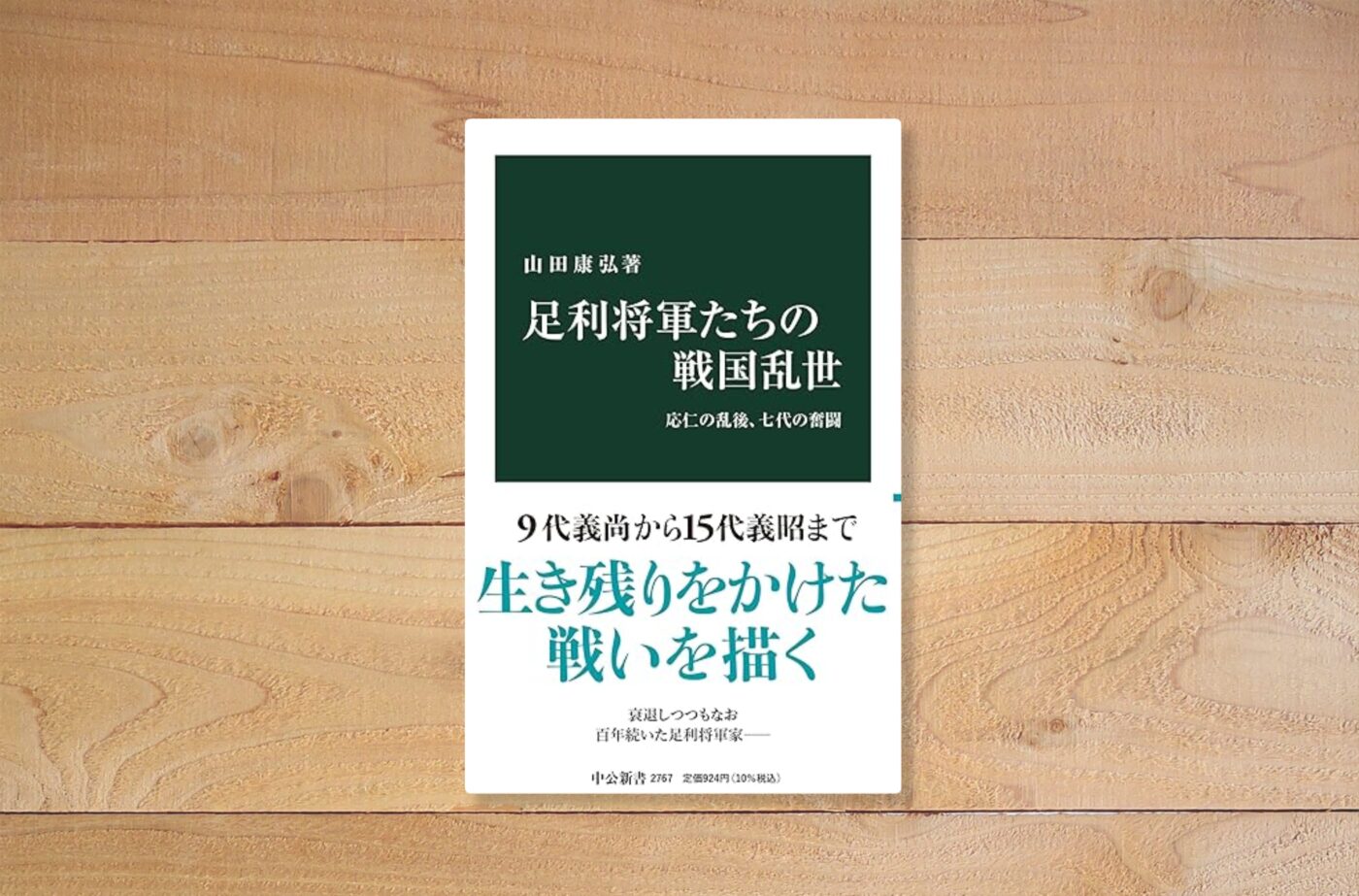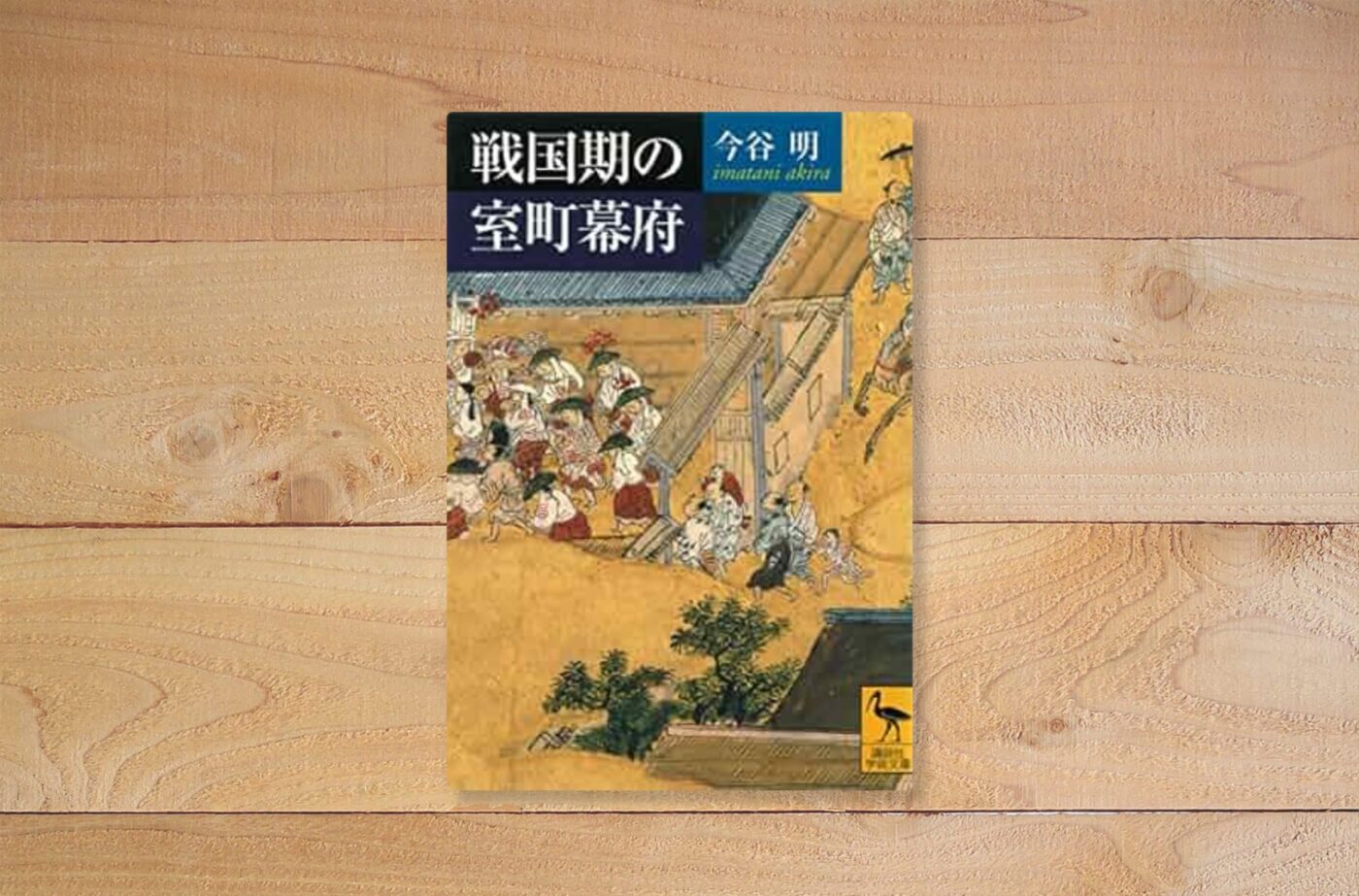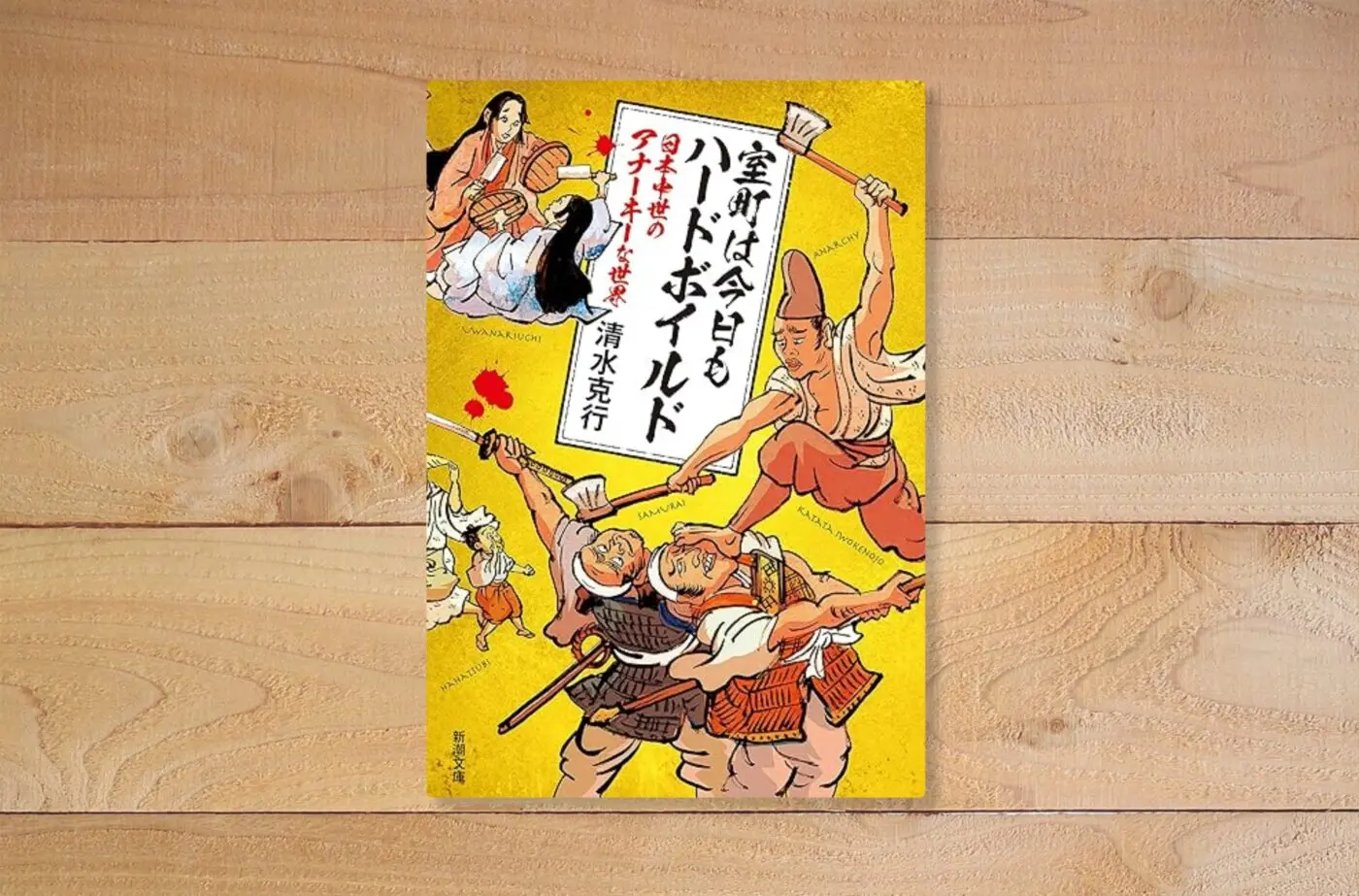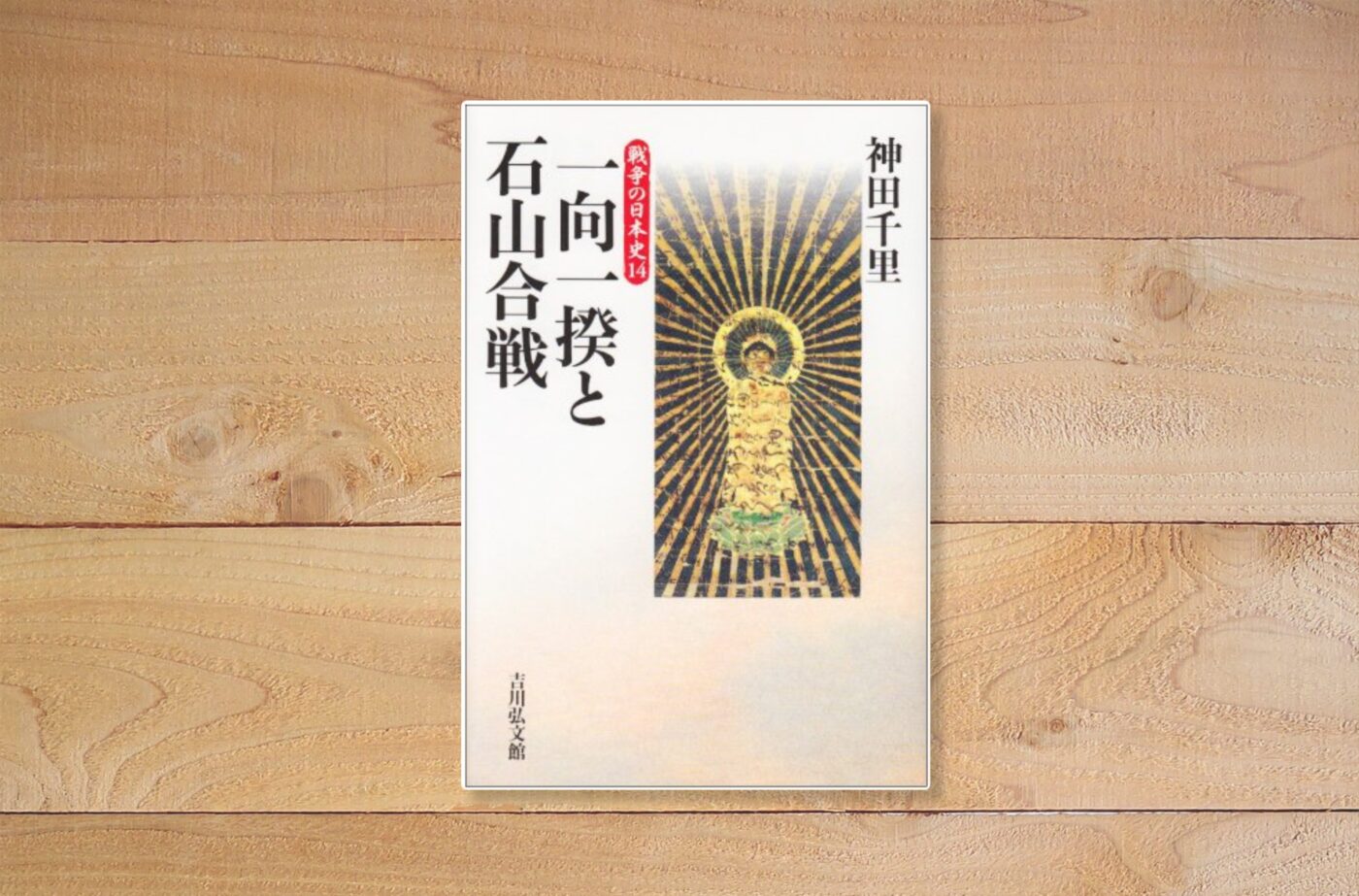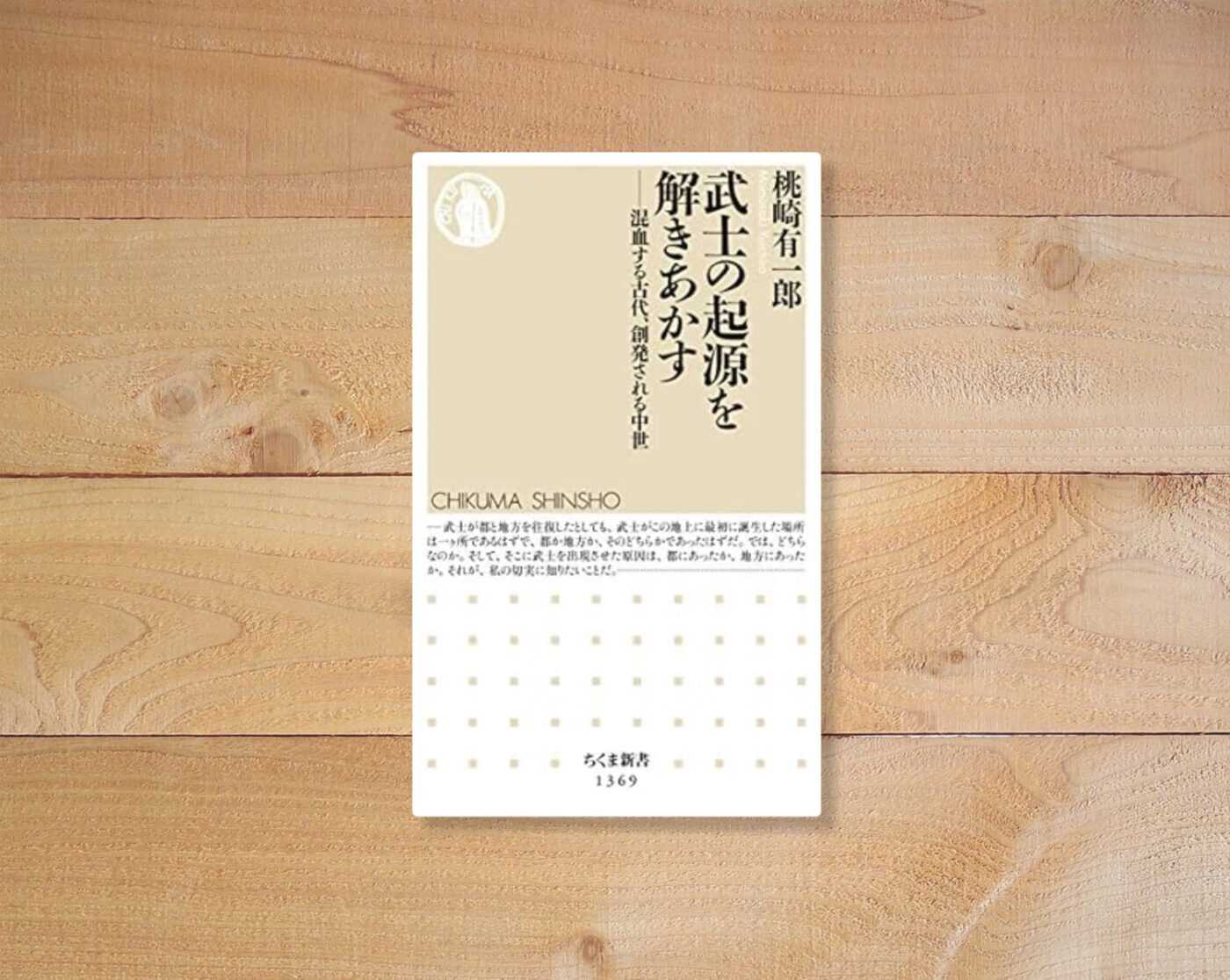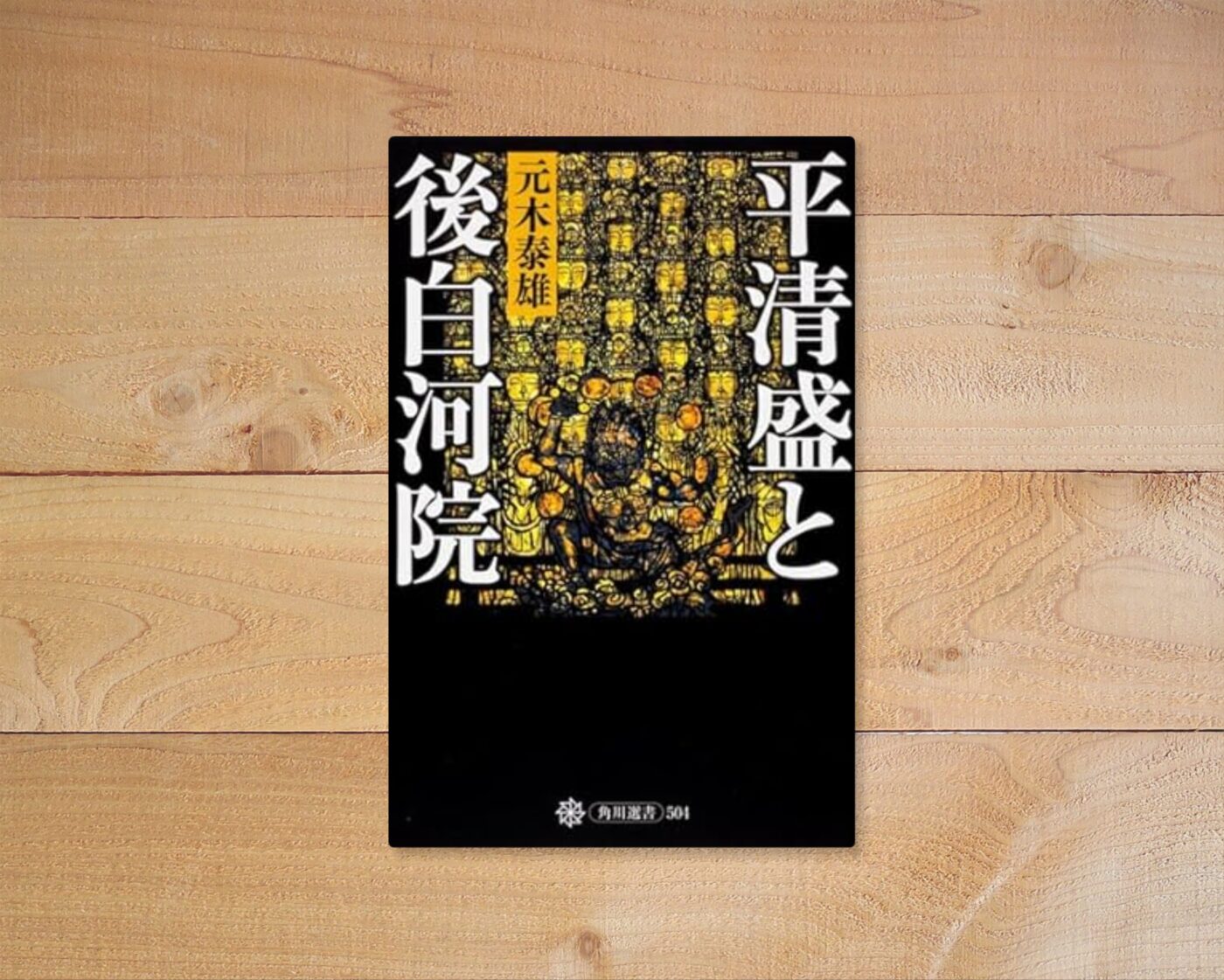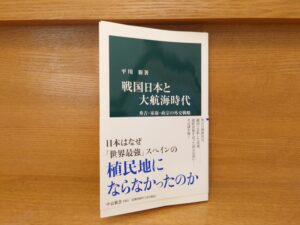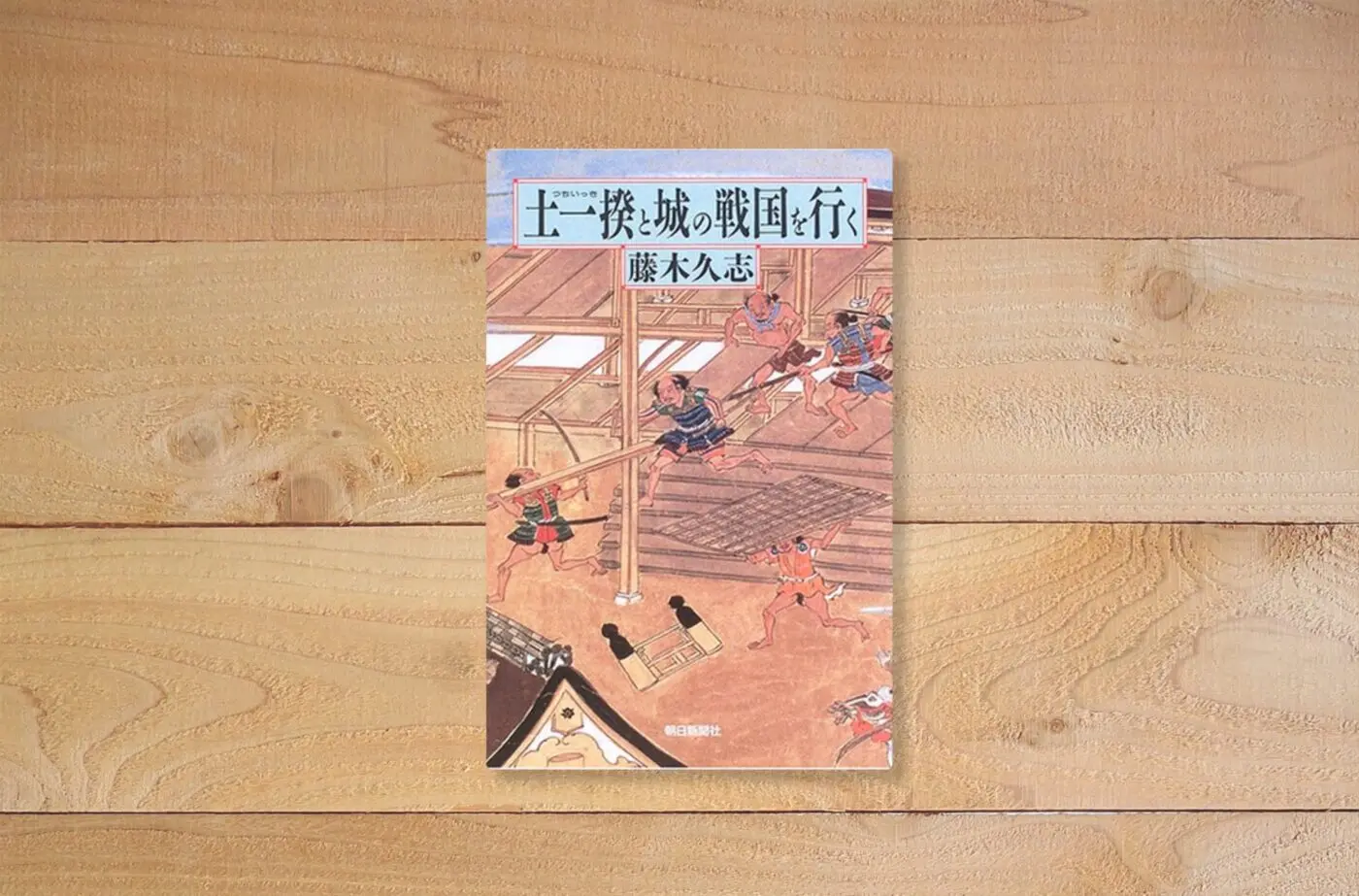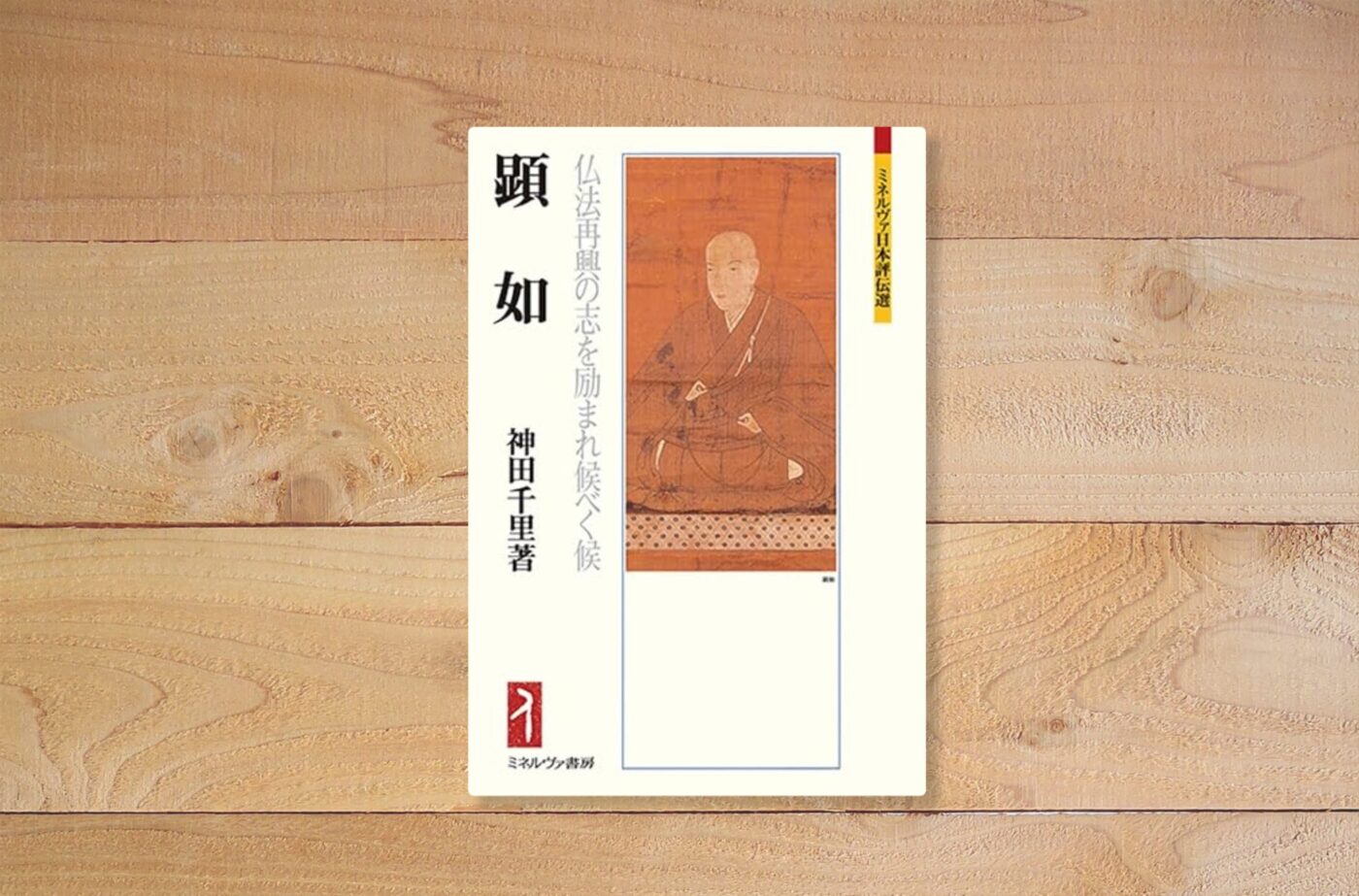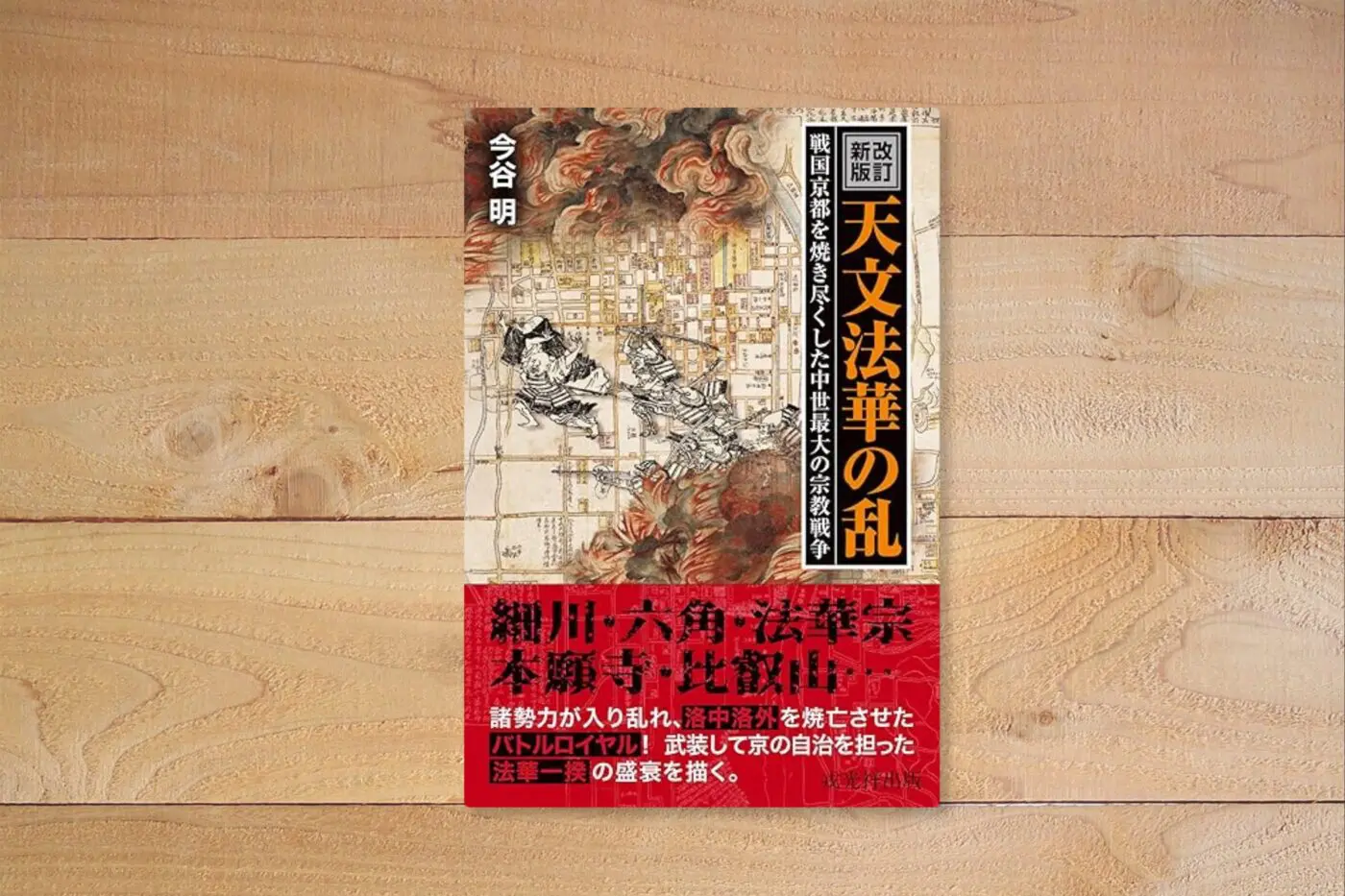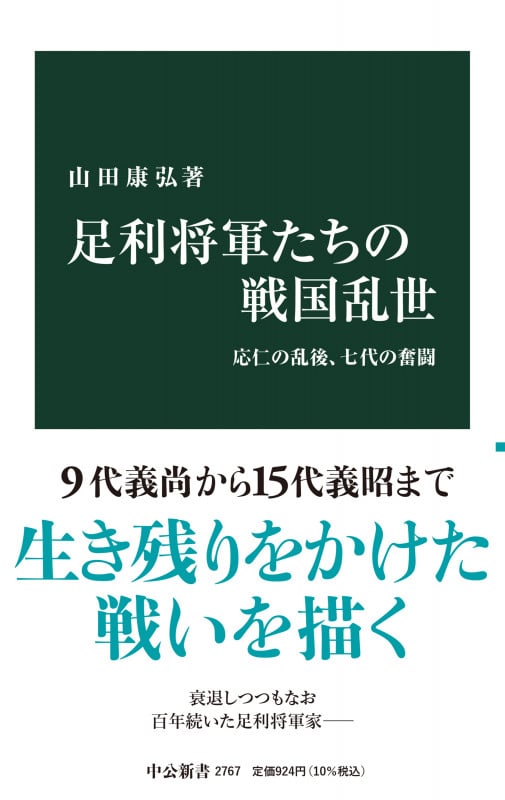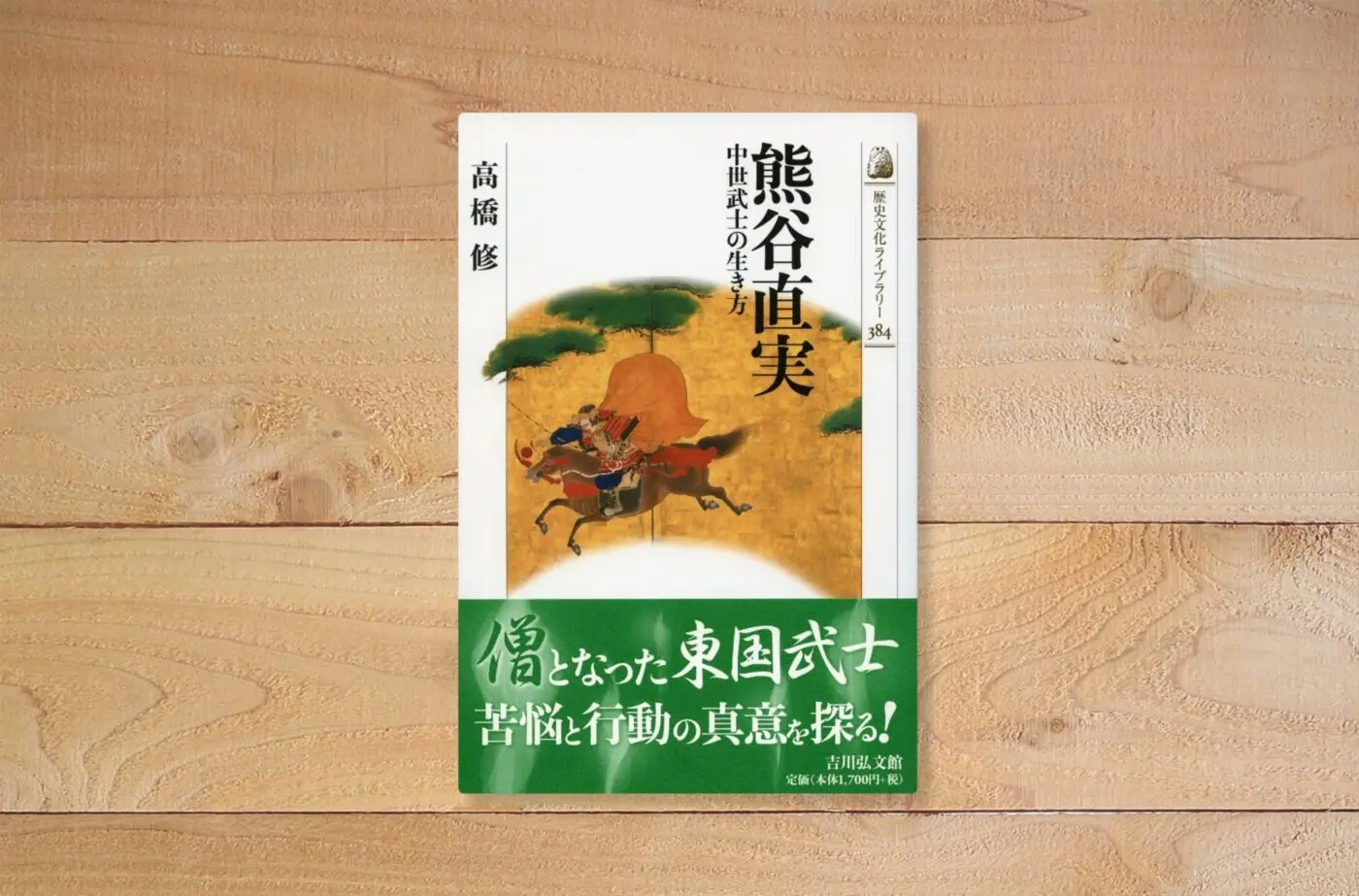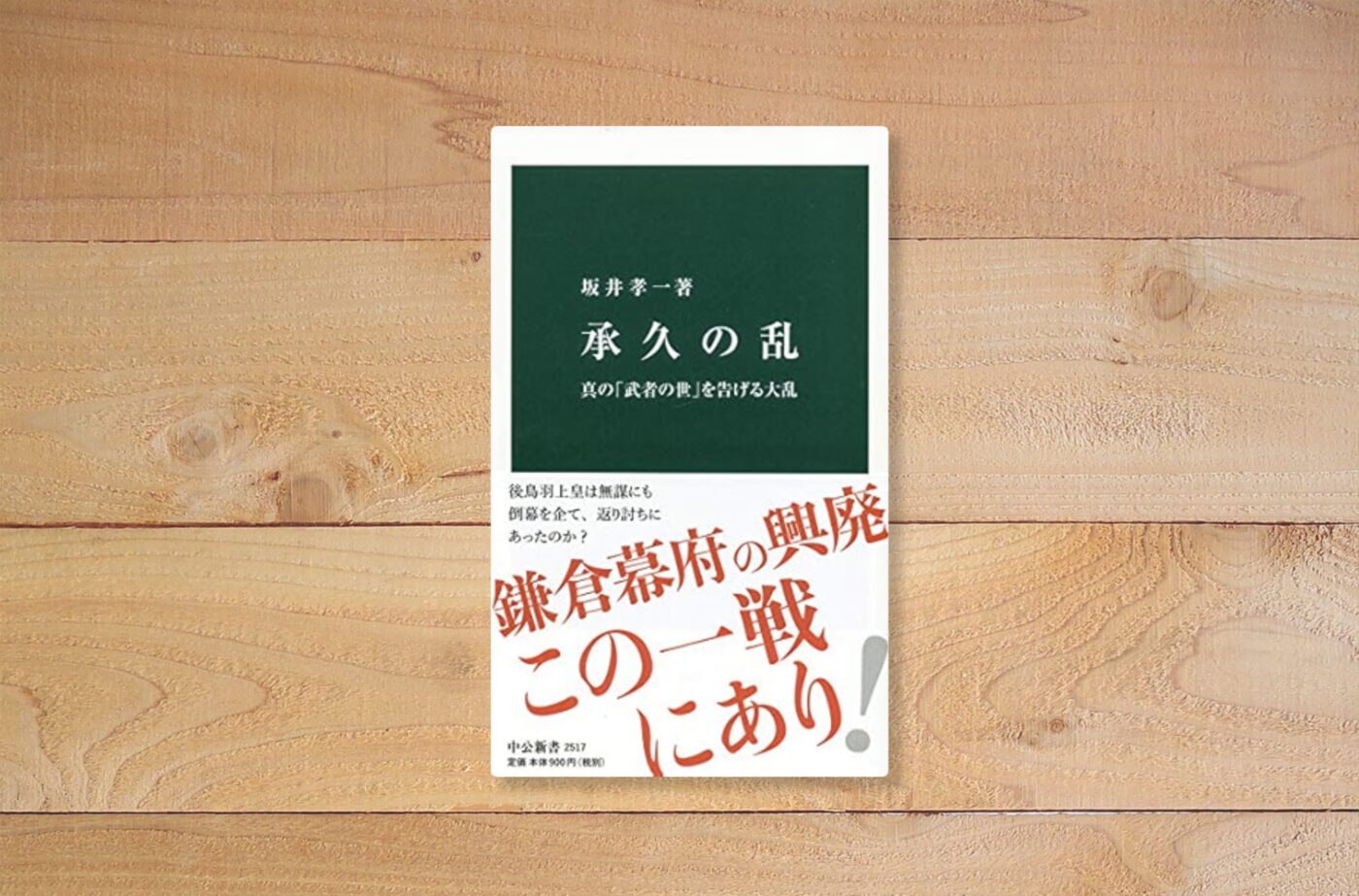目次
山田康弘『足利将軍たちの戦国乱世 応仁の乱後、七代の奮闘』概要と感想~戦国時代の室町幕府の意外な事実を知れる刺激的な名著!
今回ご紹介するのは2023年に中央公論新社より発行された山田康弘著『足利将軍たちの戦国乱世 応仁の乱後、七代の奮闘』です。
早速この本について見ていきましょう。
足利将軍家を支える重臣たちの争いに端を発した応仁の乱。その終結後、将軍家は弱体化し、群雄割拠の戦国時代に突入する。だが、幕府はすぐに滅亡したわけではない。九代義尚から十五代義昭まで、将軍は百年にわたり権威を保持し、影響力を行使したが、その理由は何か――。歴代将軍の生涯と事績を丹念にたどり、各地の戦国大名との関係を解明。「無力」「傀儡」というイメージを裏切る、将軍たちの生き残りをかけた戦いを描く。
中央公論新社商品紹介ページより
 最後の将軍足利義昭(1537-1597)Wikipediaより
最後の将軍足利義昭(1537-1597)Wikipediaより
本書は室町幕府の流れを知るのに最高の一冊です。主題は応仁の乱後の幕府と将軍の動きでありますが、本書前半でそこに至るまでのおおまかな流れも解説してくれますのでこれは非常に助かります。しかもとにかく読みやすくてわかりやすい!物語調で歴史を語ってくれるためすっと流れが入ってきます。
そして応仁の乱後の室町幕府の将軍は傀儡だったというのが世間の一般的なイメージでありますがそれとは全く異なる事実を本書で見ていくことになります。戦国時代に比べて影の薄い室町時代ではありますが、こんなに面白い時代だったとは!これはものすごい名著です。ぜひおすすめしたいです。
そして著者はこの時代を学ぶことの意義について次のように述べています。
私たちは現代に生きている。それゆえ、現代の世界についてよく知らない、というのは危険なことである。「自分がいまどのような場所にいるのか」がわからなければ、これからどちらに進むべきなのか、ということもわからないだろう。しかし現代は、私達にとってあまりにも身近な存在であるがゆえに、私たちには現代の姿がなかなか見えない。当たり前すぎて、ついつい見すごしてしまうのだ。あるいは「現代のことなど、すでによく知っている」と思いこみ、じっくり考えることを怠ってしまうこともある。
そこで戦国時代を知り、これと現代の世界とを比較してみるのである。すると、現代の特徴が浮き彫りになり、その結果、「すでによく知っている」と思いこんでいた現代の世界を、自分が意外に知っていなかったことがわかってくる。そして、日ごろは当たり前すぎて気づかない、現代の世界があらためて見えるようになってくるのだ。つまり、戦国時代の日本列島を知ることは、私たちに、現代の世界を再発見する気づきをあたえてくれる。だから、私たちにとって戦国時代を知ることには「意味がある」のである。
中央公論新社、山田康弘『足利将軍たちの戦国乱世 応仁の乱後、七代の奮闘』Pⅳーⅴ
ここで著者が述べるように、本書は戦国時代のあり方を通して私達の生きる現代も考えさせられることになります。
上でも述べましたが本書では私達の常識や先入観を覆す衝撃の事実が次々と明らかにされます。
また、私達浄土真宗僧侶にとっても室町幕府と本願寺教団の関係性は見逃せません。本願寺教団は蓮如という偉大な中興の祖の存在によって急拡大したと一般的には語られますが、彼一人の存在で織田信長と戦えるほどの巨大王国になることはありえません。実はこの急拡大にも幕府と当時の時代背景が密接に絡んでいたのです。読めば読むほど呆然としてしまうほどの背景がそこにあったのでした。
この本を読むと私達が今まで教わってきた歴史とは一体何だったのかということまで考えさせられます。まさに戦国時代を通して今が問われてくるわけです。
これはとてつもない名著と出会ってしまいました。ぜひぜひおすすめしたい作品です。ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。
以上、「山田康弘『足利将軍たちの戦国乱世』概要と感想~戦国時代の室町幕府の意外な事実を知れる刺激的な名著!」 でした。
Amazon商品紹介ページはこちら
足利将軍たちの戦国乱世 応仁の乱後、七代の奮闘 (中公新書 2767)
次の記事はこちら
あわせて読みたい
今谷明『戦国期の室町幕府』概要と感想~臨済宗五山派と幕府の関係性について知るのにおすすめ!実務官...
本書はとてつもない名著です。私もこの本には参りました。「え!?」という事実が次から次に出てきます。完全に常識が覆されました。それほどこの本は衝撃的です。
前の記事はこちら
あわせて読みたい
清水克行『室町は今日もハードボイルド』概要と感想~私達の常識を覆す衝撃の1冊!面白すぎです!
この本は私達が驚くような内容が次々と語られる一冊です。
室町時代がいかにアナーキーで暴力的でハードボイルドだったか。エンタメ感の強いタイトルや表紙とは裏腹に著者は資料に基づいた学術的な内容を楽しく解説していきます。
著者の語るエピソードもくすっとしてしまうユーモアもたっぷりで非常に読みやすいです。
関連記事
あわせて読みたい
神田千里『一向一揆と石山合戦』概要と感想~一向一揆は作られたイメージだった!?本願寺教団急拡大の背...
戦国時代の一揆といえば浄土真宗門徒による一向一揆というイメージが私達にはありますが実はこれが後世に作られた説話だったとしたらどうでしょう。戦国当時としては「一向一揆」という言葉がほとんど使われず、真宗門徒による一揆という観念すら乏しかったのだそうです。では、なぜ「この時代に一向一揆が頻発し、歴史に大きな影響を与えた」と私達は教えられることになったのでしょうか。そうしたからくりが本書で明らかにされます。これには私も驚きました。
あわせて読みたい
清水克行、高野秀行『世界の辺境とハードボイルド室町時代』概要と感想~室町とソマリランド!強烈な対...
以前の記事で紹介した『室町は今日もハードボイルド』も最高にエキサイティングな作品でしたが、今作は対談ということでまた違った視点から室町や現代世界を見ることができる実に刺激的な一冊となっています。これはぜひ学生にも読んでほしいなと強く思います。私達の常識や先入観を破壊する名対談です。ぜひぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。
あわせて読みたい
桃崎有一郎『武士の起源を解きあかす』概要と感想~脳内スパーク間違いなし!武士の始まりに迫る衝撃の...
本書は衝撃的です。脳内スパークのとてつもない作品です!
「サムライ好きの日本人が、誰も知らない武士の正体。
歴史学界が匙を投げた、
日本史、最大級のミステリーに気鋭の歴史学者が挑む!」
あわせて読みたい
元木泰雄『平清盛と後白河院』あらすじと感想~清盛の権力奪取がそう単純ではなかったことを知れるおす...
予測不能のカオスを丁寧に追っていく本書は非常にスリリングで刺激的です。たしかにこの本は複雑で難しいです。ただ、何度も言いますがそれは著者の責任ではなく、そもそもそういう複雑な人間関係が絡む難しい時代なのです。それをじっくりと感じていける点にこの本の最大の意義があると思います。
あわせて読みたい
平川新『戦国日本と大航海時代』あらすじと感想~なぜ日本はポルトガルや英蘭東インド会社の植民地にな...
西洋諸国が日本を狙わなかったわけがありません。アジア諸国も続々と彼らに支配されていく中でなぜか日本だけは彼らに屈することがありませんでした。
なぜこんなことが可能だったのでしょうか。それがこの本で語られます。
あわせて読みたい
藤木久志『土一揆と城の戦国を行く』概要と感想~室町時代のどぎつい現実を知れるおすすめ本!自力救済...
本書では室町、戦国時代にかけて頻発した土一揆や戦乱による村人の苦しい生活ぶりを知ることになります。
この本も私達の固定観念を覆す刺激的な一冊です。私達が想像するよりもはるかにバイオレンスな世界がそこには広がっていました。
あわせて読みたい
神田千里『顕如』概要と感想~本願寺教団はなぜ戦国時代に信長と戦えるほど巨大化したのか。その歴史的...
顕如は石山合戦で織田信長軍と戦った本願寺の門主として有名な人物です。
この本では戦国時代になぜ本願寺は織田信長と10年近くも戦えたほど強力な存在だったのかを知ることができます。
本願寺教団側から語られる歴史とは違った視点で学べる本書は実に刺激的な一冊です。
あわせて読みたい
今谷明『天文法華の乱』概要と感想~1530年代京都で起きた宗教戦乱の実態に迫るおすすめ参考書
本書は私達の常識を覆す衝撃的な1冊です。
室町、戦国期はとにかく複雑です。なぜ京都で日蓮宗が急拡大し、1536年に京都を焼き尽くす大事件が起きるほどになってしまったかということには多種多様な背景が絡んできます。まさに宗教は宗教だけにあらず。本書ではそんな複雑怪奇な政治経済、時代背景を時系列に沿って読み解いていきます。