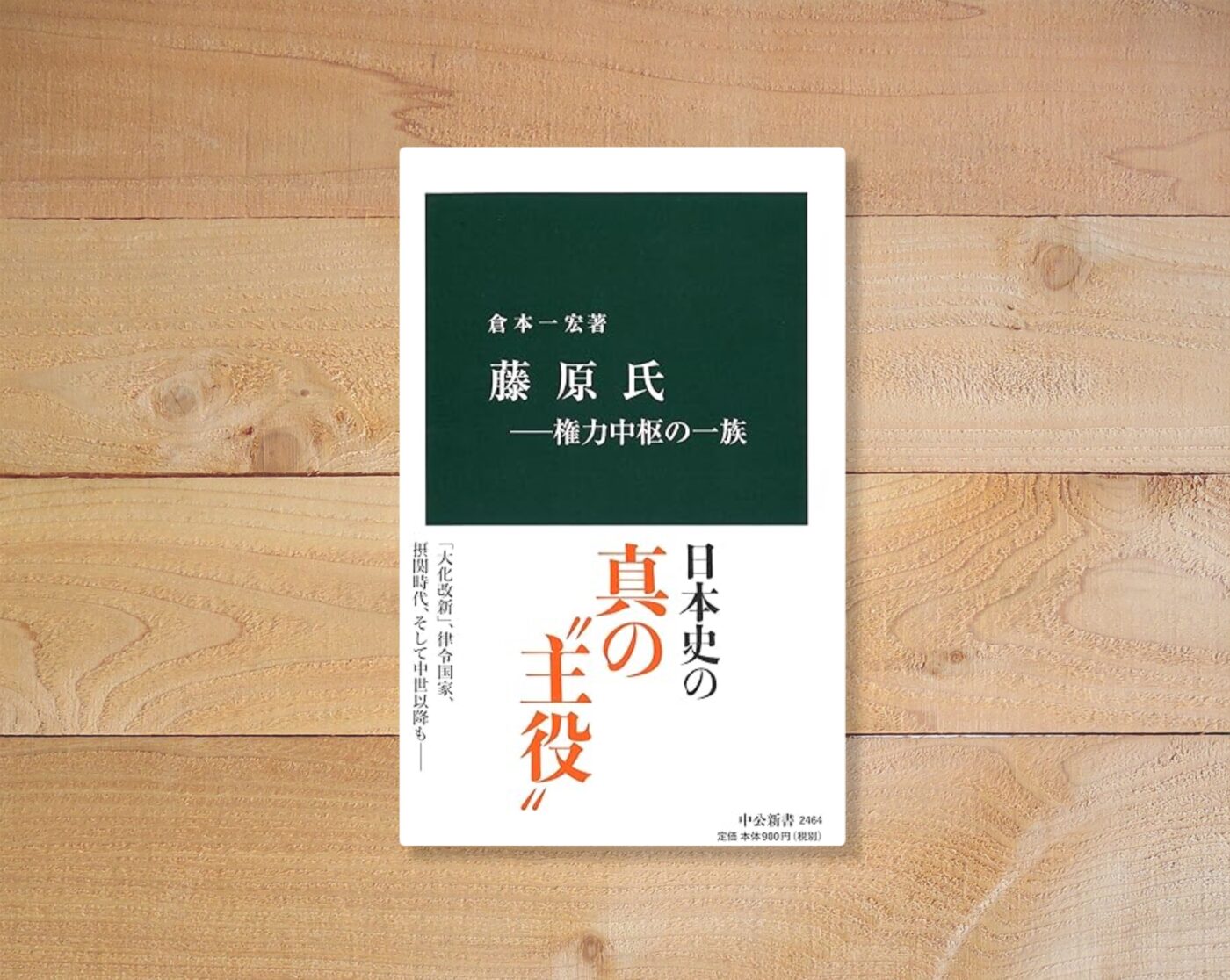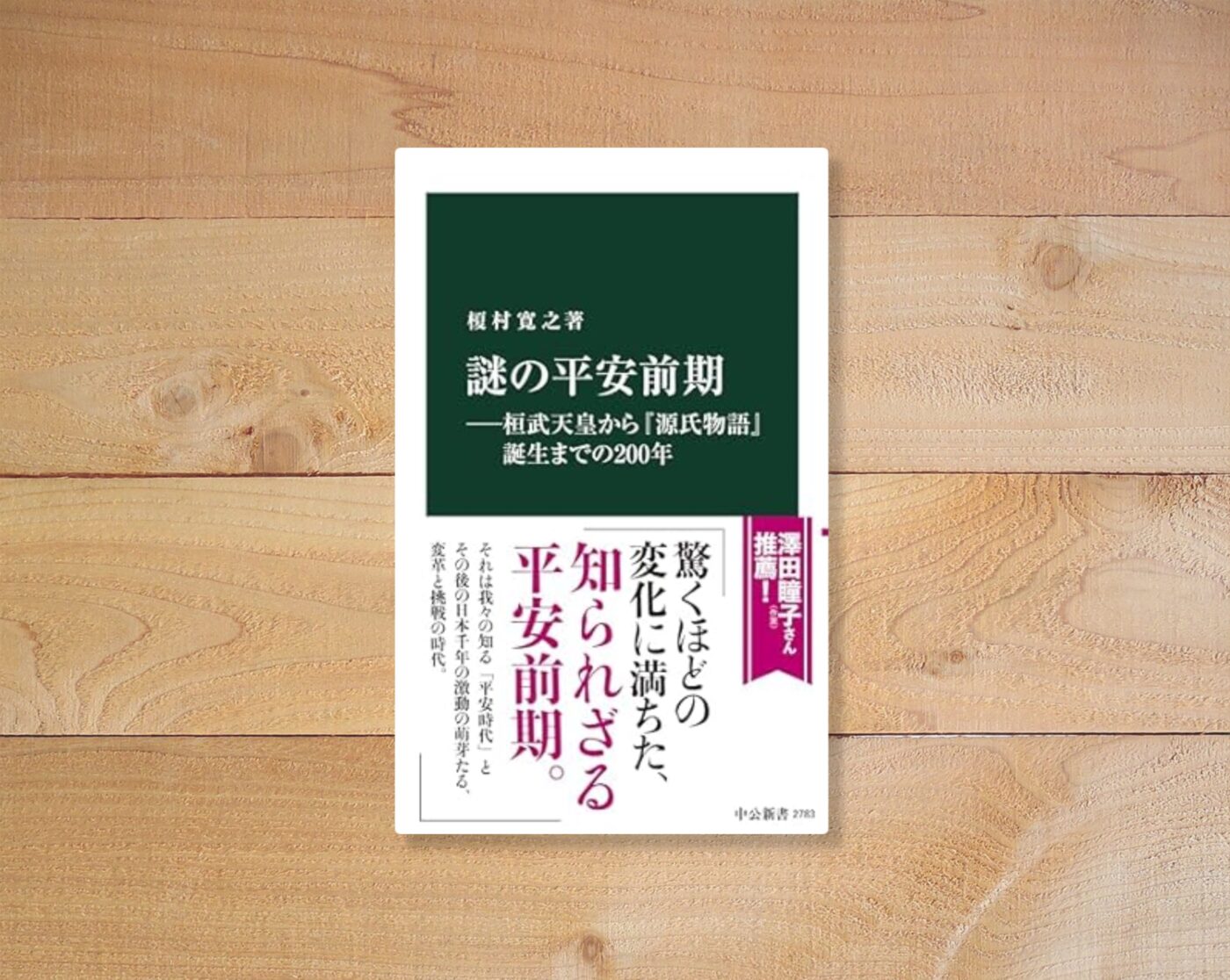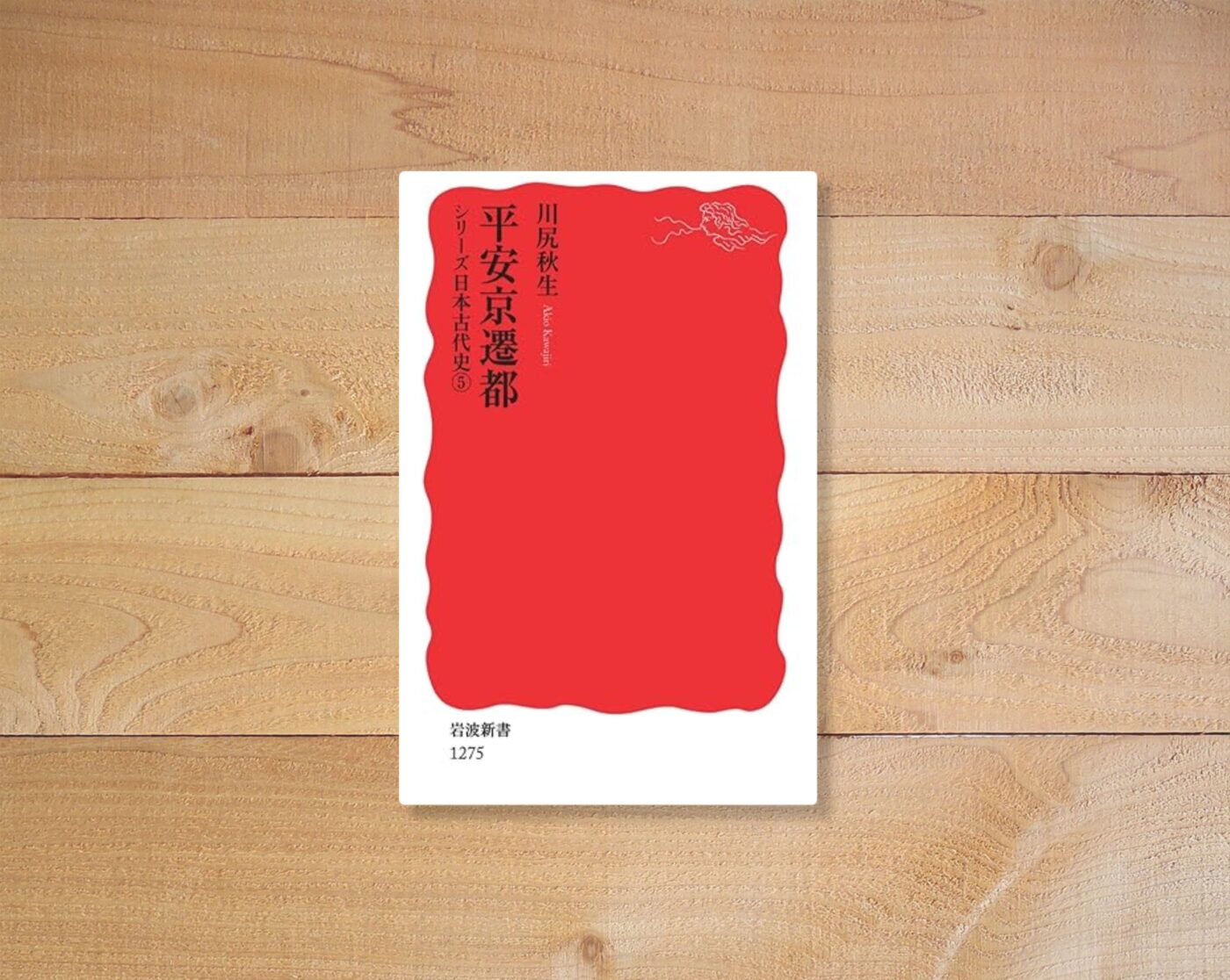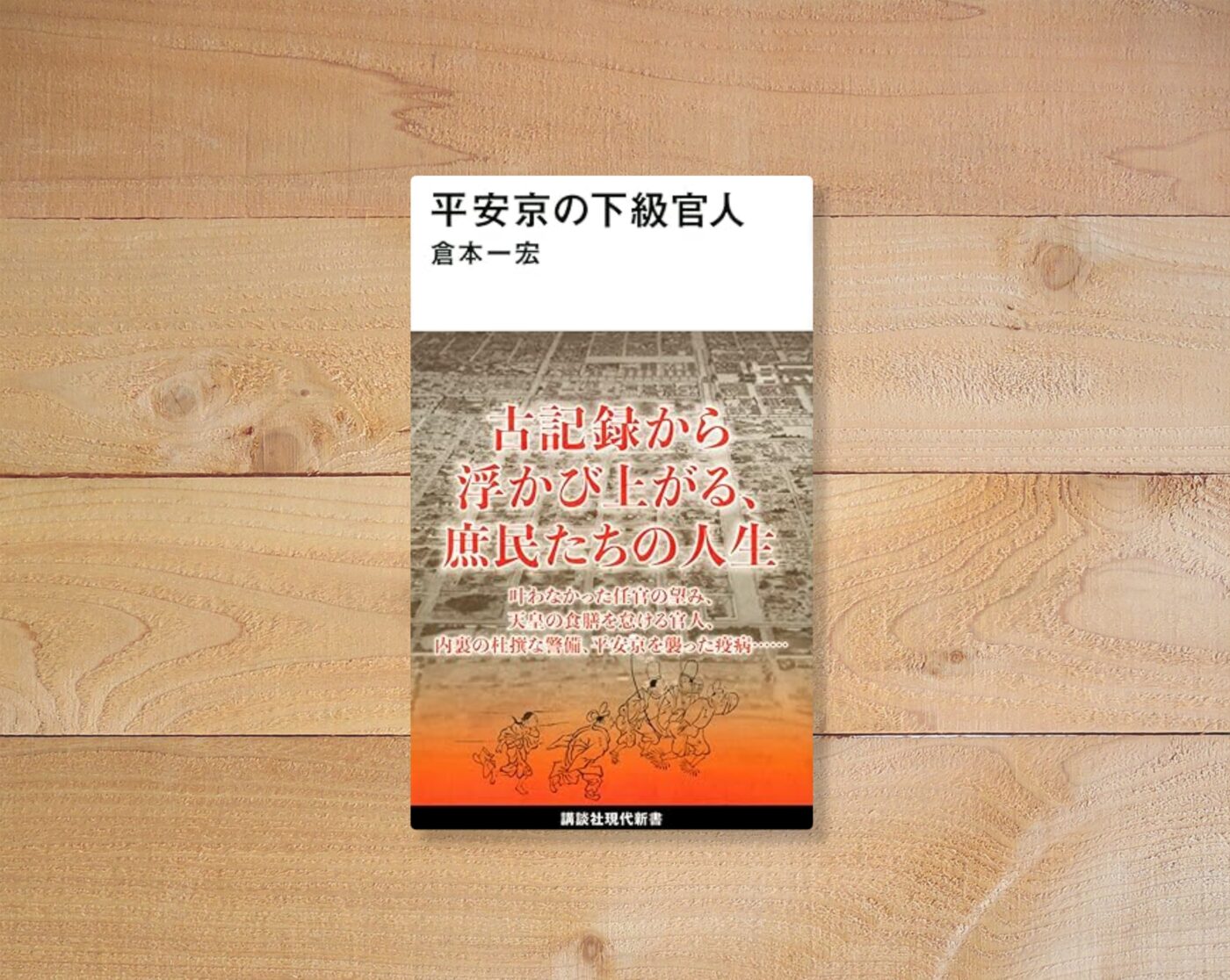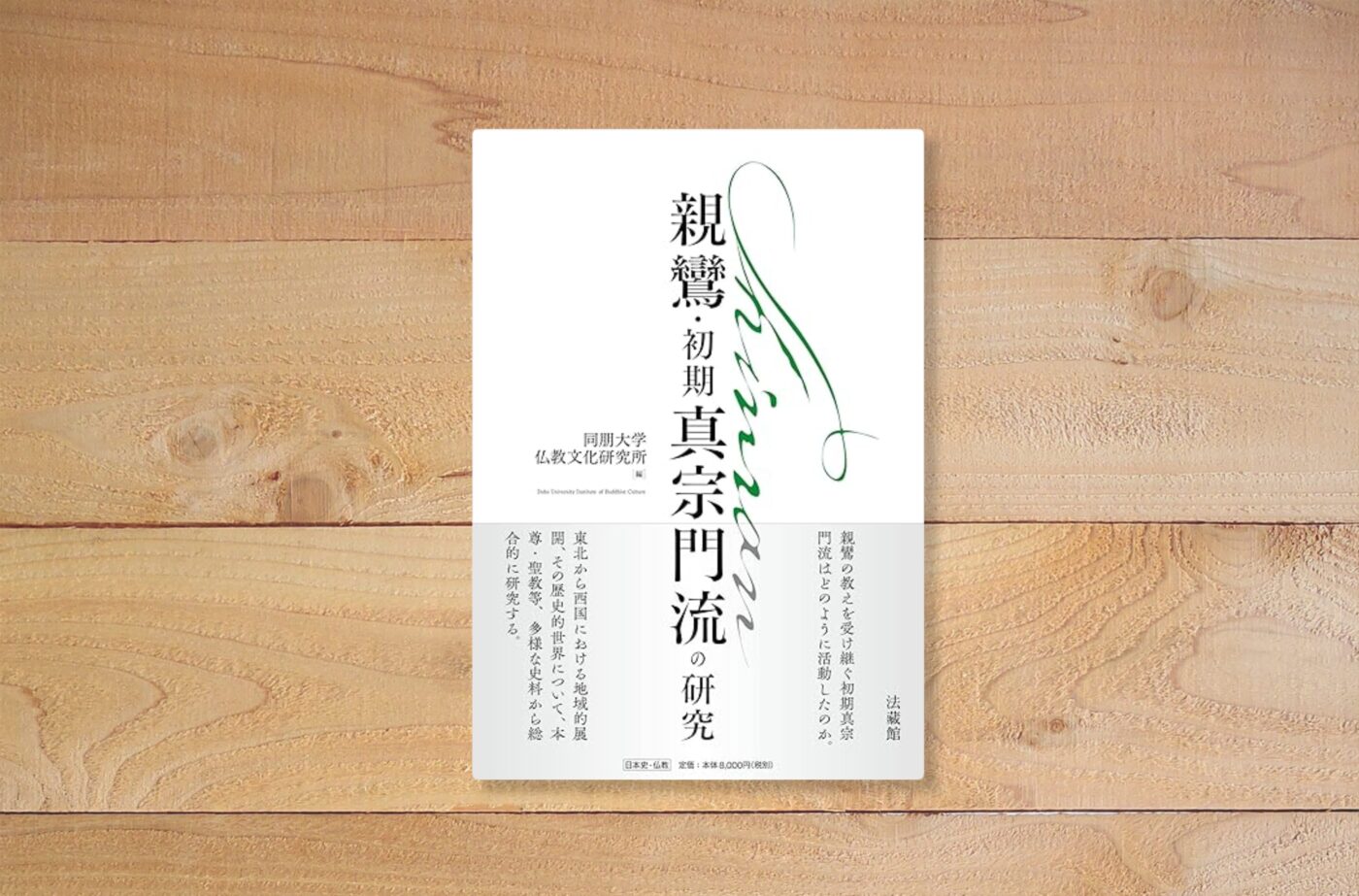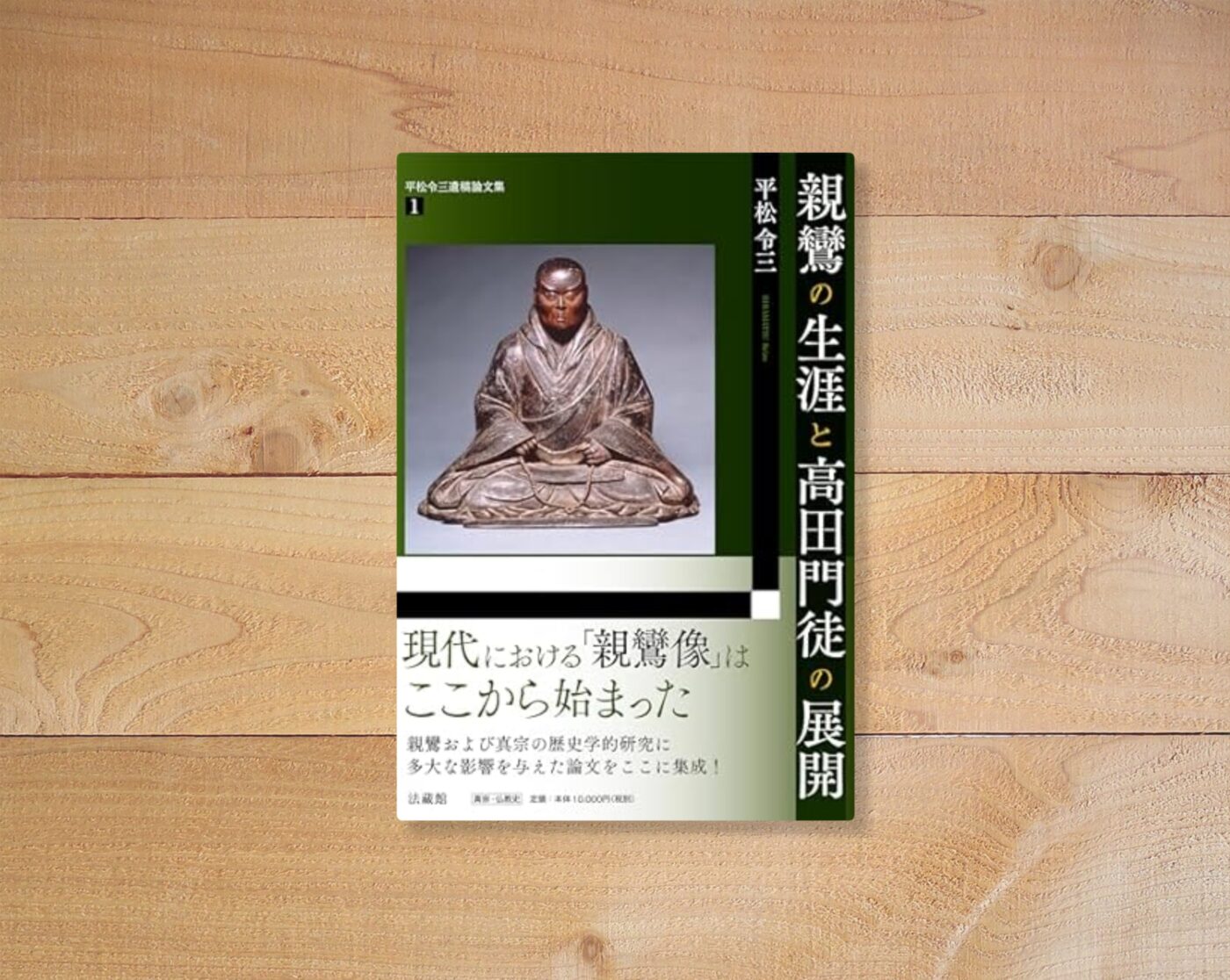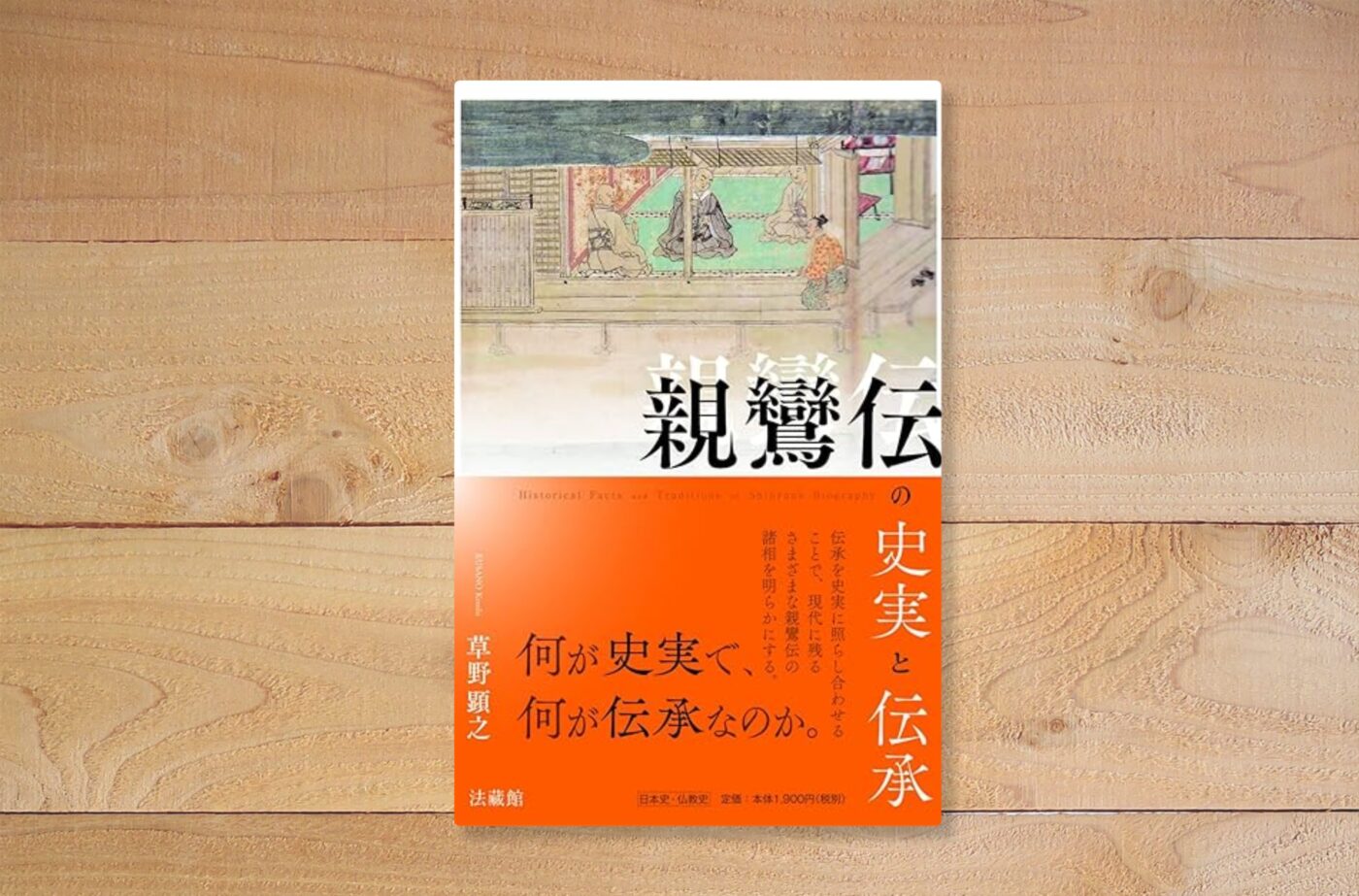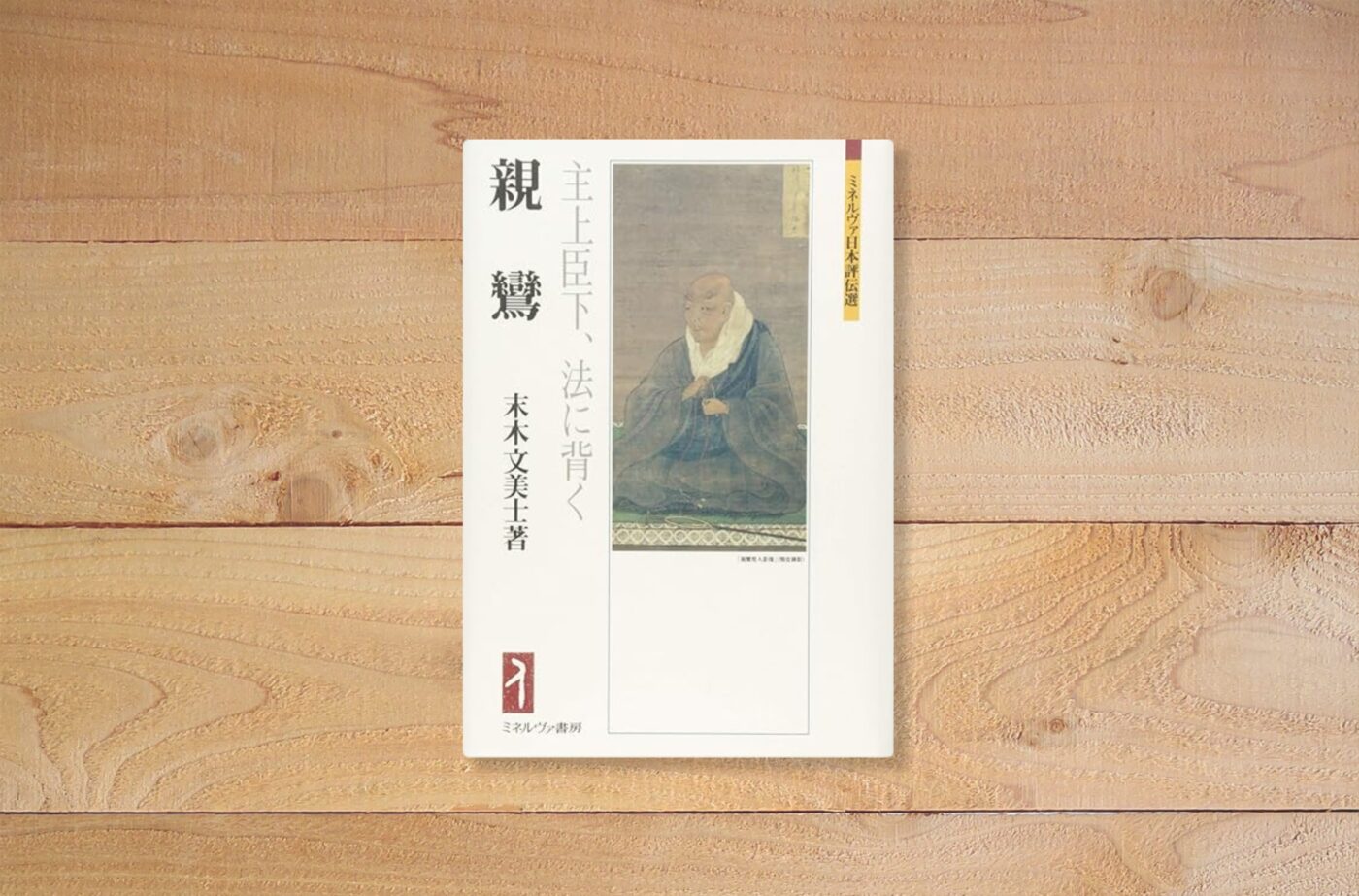倉本一宏『紫式部と藤原道長』概要と感想~『源氏物語』が無ければ藤原道長の繁栄もなかった?大河ドラマ「光る君へ」の副読本にもぜひ
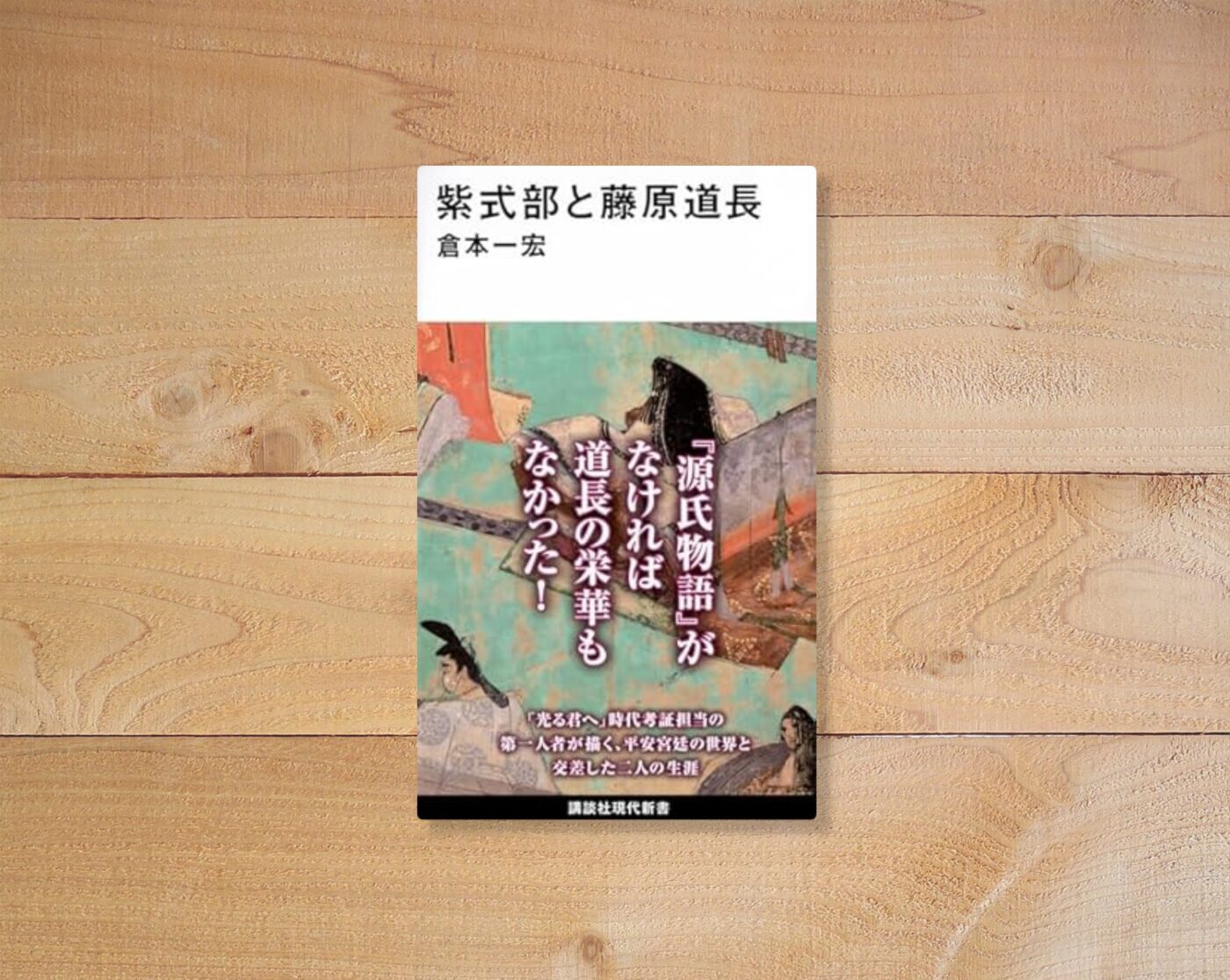
倉本一宏『紫式部と藤原道長』概要と感想~『源氏物語』が無ければ藤原道長の繁栄もなかった?大河ドラマ「光る君へ」の副読本にもぜひ
今回ご紹介するのは2023年に講談社より発行された倉本一宏著『紫式部と藤原道長』です。
早速この本について見ていきましょう。
『源氏物語』がなければ道長の栄華もなかった!
無官で貧しい学者の娘が、なぜ世界最高峰の文学作品を執筆できたのか?
後宮で、道長が紫式部に期待したこととは?
古記録で読み解く、平安時代のリアル24年大河ドラマ「光る君へ」時代考証担当の第一人者が描く、平安宮廷の世界と、交差した二人の生涯!
Amazon商品紹介ページより
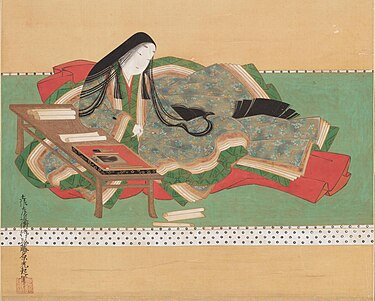
本書は『源氏物語』で有名な紫式部と藤原道長の驚きの関係性を知れる参考書です。
巻末のあとがきで著者は本書について次のように述べています。
これまで、紫式部と藤原道長の生涯を、確実な一次史料のみを読み解くことによってたどってきた。
もうおわかりいただけたことと思うが、紫式部は道長の援助と後援がなければ『源氏物語』も『紫式部日記』も書けなかったのであるし、道長は紫式部の『源氏物語』執筆がなければ一条天皇を中宮彰子の許に引き留められなかったのである。道長家の栄華も、紫式部と『源氏物語』の賜物であると言えよう。
その意味では、「道長なくして紫式部なし、紫式部なくして道長なし」ということになる。世界最高峰の文学作品と日本史上最高の権力者が、お互いの存在なくしてはあり得なかったということは、歴史上の奇蹟と称すべきことであると同時に、また歴史上の必然でもあったことになる。
『源氏物語』以降、この国、いや世界はこれほどの文学作品は生み出してはいないのだし、道長以降、日本ではこれほどの権力を持った政権担当者は現われなかった。
我々は、千年前のこの二人のリアルな生涯を、伝説や伝承ではなく、ほぼそのまま復元することのできる材料である古記録が残されていることの幸いを、あらためて感じざるを得ない(これは王朝交替がなく、主な貴族の家も存続したこと、内戦も比較的少なかったお陰である)。
せっかくであるから、読者の皆さんは、『源氏物語』を、何も原文でなくても、現代語訳でも漫画でもいいから(良質なものに限るが)、是非とも全文、読み通していただきたい。きっと新しい人生観が芽生えてくることであろう。
講談社、倉本一宏『紫式部と藤原道長』P319-320
「世界最高峰の文学作品と日本史上最高の権力者が、お互いの存在なくしてはあり得なかったということは、歴史上の奇蹟と称すべきことであると同時に、また歴史上の必然でもあったことになる。」
これはロマンがありますよね。このような奇跡と言ってもよい関係性が紫式部と藤原道長にはあったのでした。本書ではそんな二人の生涯とつながりがわかりやすく解説されます。「紫式部=源氏物語」という単なる単語の暗記であった受験時代から一気にその世界が広がります。紫式部をはじめ当時の女流作家たちがどのような生活をしていたのか、なぜ彼女たちが素晴らしい作品を残すことができたかも知ることができます。
また、摂関政治の象徴として有名な藤原道長の苦労も本書では知ることになります。道長といえば自分の娘を天皇に嫁がせて政治を思うままに操ったという悪いイメージを持たれがちですがやはり事はそんなに単純な話ではありませんでした。
上の引用で語られたように、『源氏物語』という世界最高峰の文学があったからこその栄華だったということに改めて歴史の面白さを感じさせられます。
2024年には大河ドラマ『光る君へ』が放送されました。その副読本としてもぜひおすすめしたいと思います。
著者も上の引用の後で述べていましたが、ドラマはドラマということで史実と違う部分があります。ドラマを事実と鵜呑みにするのではなく、その違いを知った上で楽しむことが大切であると述べています。私もそう思います。現実とドラマの違いを知った上で楽しむことも歴史ドラマの醍醐味であるのではないでしょうか。そこにドラマの作り手の個性や思いが見えてくるのではないかと思います。
そして上の引用の最後にありましたように、この本を読んでさらに『源氏物語』を読みたいという気持ちが強くなりました。私は今日本史の勉強をしている最中ですのでこれが一段落したら早速取り掛かりたいと思います。きっとかつて受験勉強のために読んだ時とは違う感覚になるのではないかと今から楽しみです。
これは刺激的な一冊でした。ぜひおすすめしたい参考書です。
以上、「倉本一宏『紫式部と藤原道長』概要と感想~『源氏物語』が無ければ藤原道長の繁栄もなかった?大河ドラマ「光る君へ」の副読本にもぜひ」でした。
Amazon商品紹介ページはこちら
次の記事はこちら
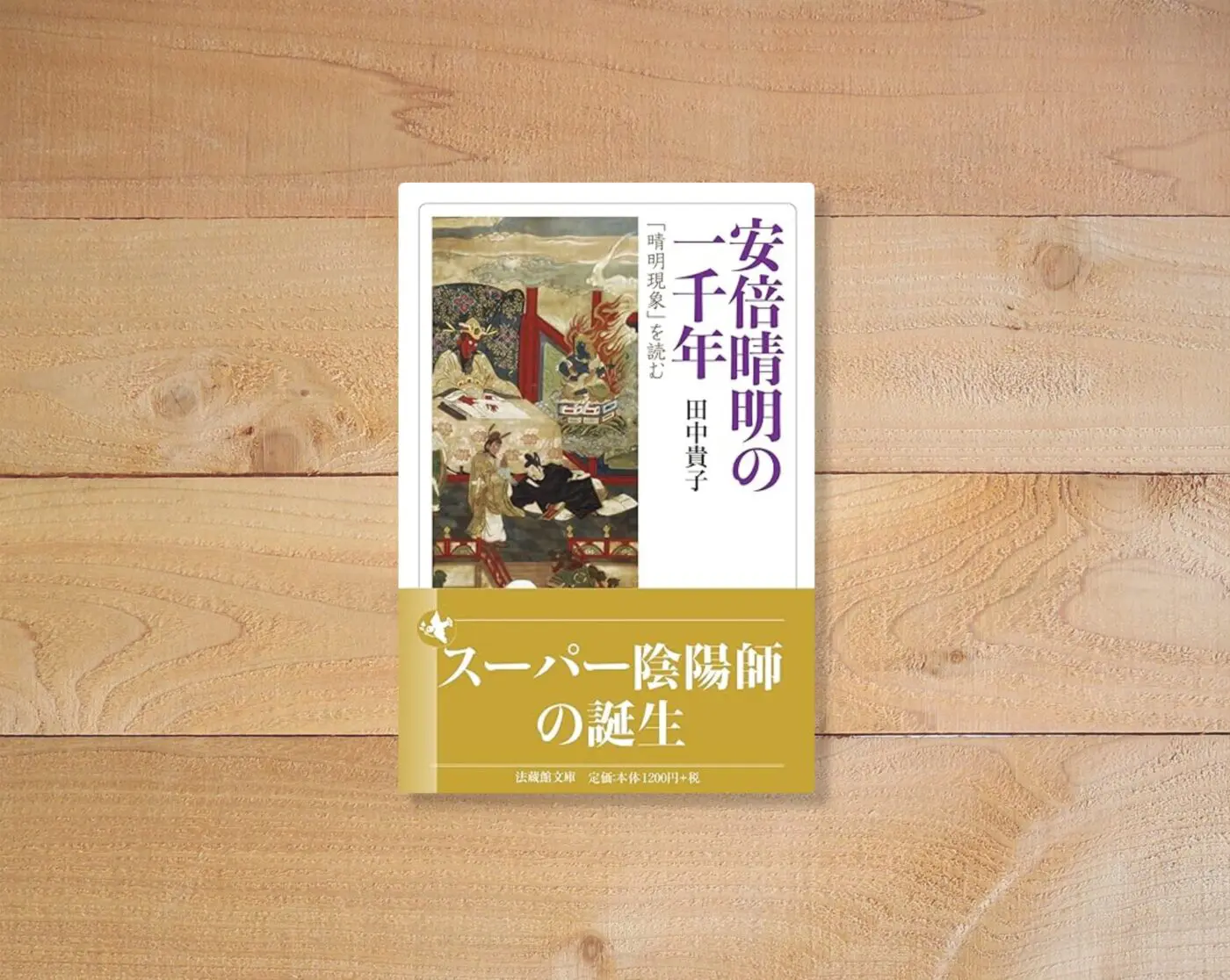
前の記事はこちら
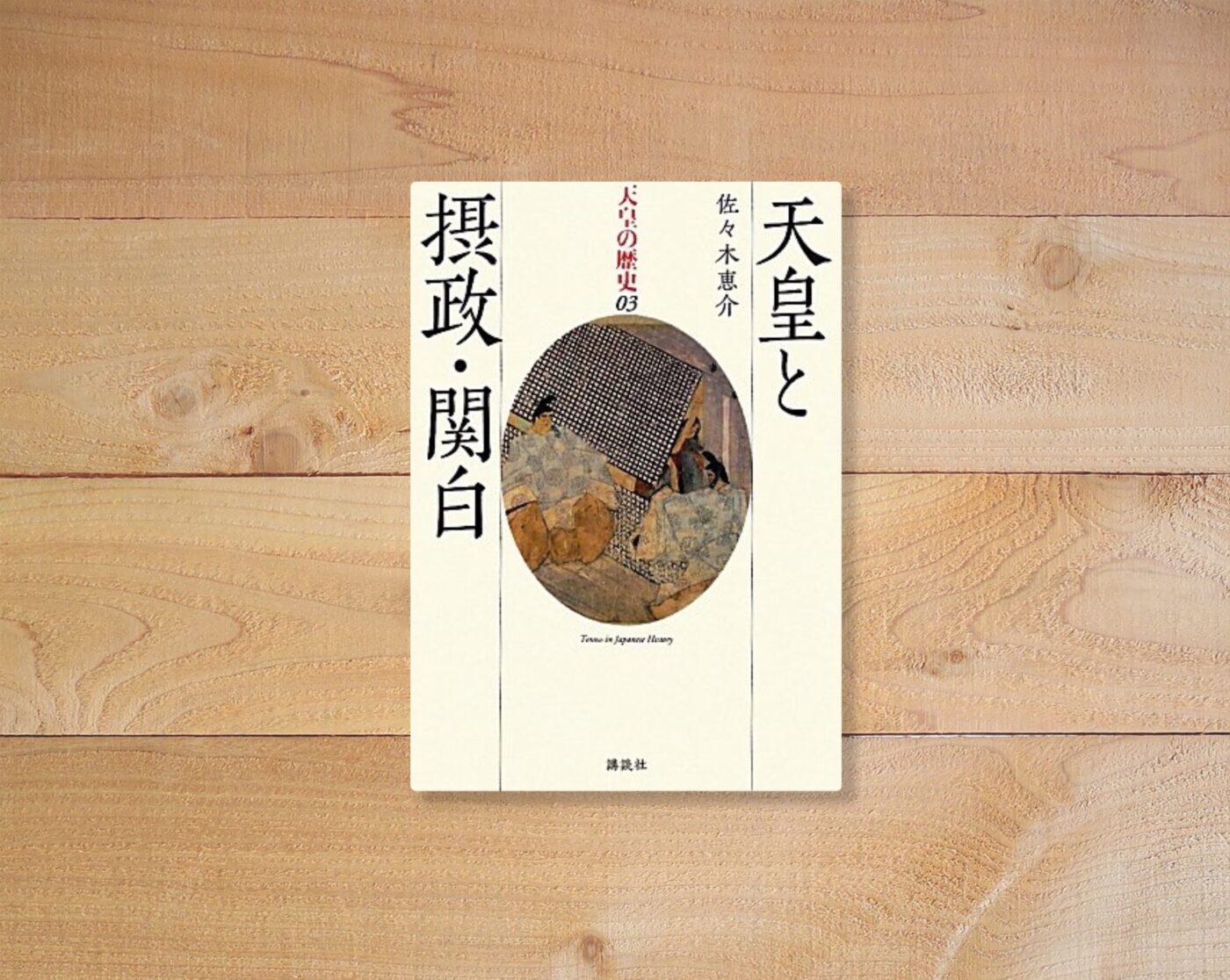
関連記事