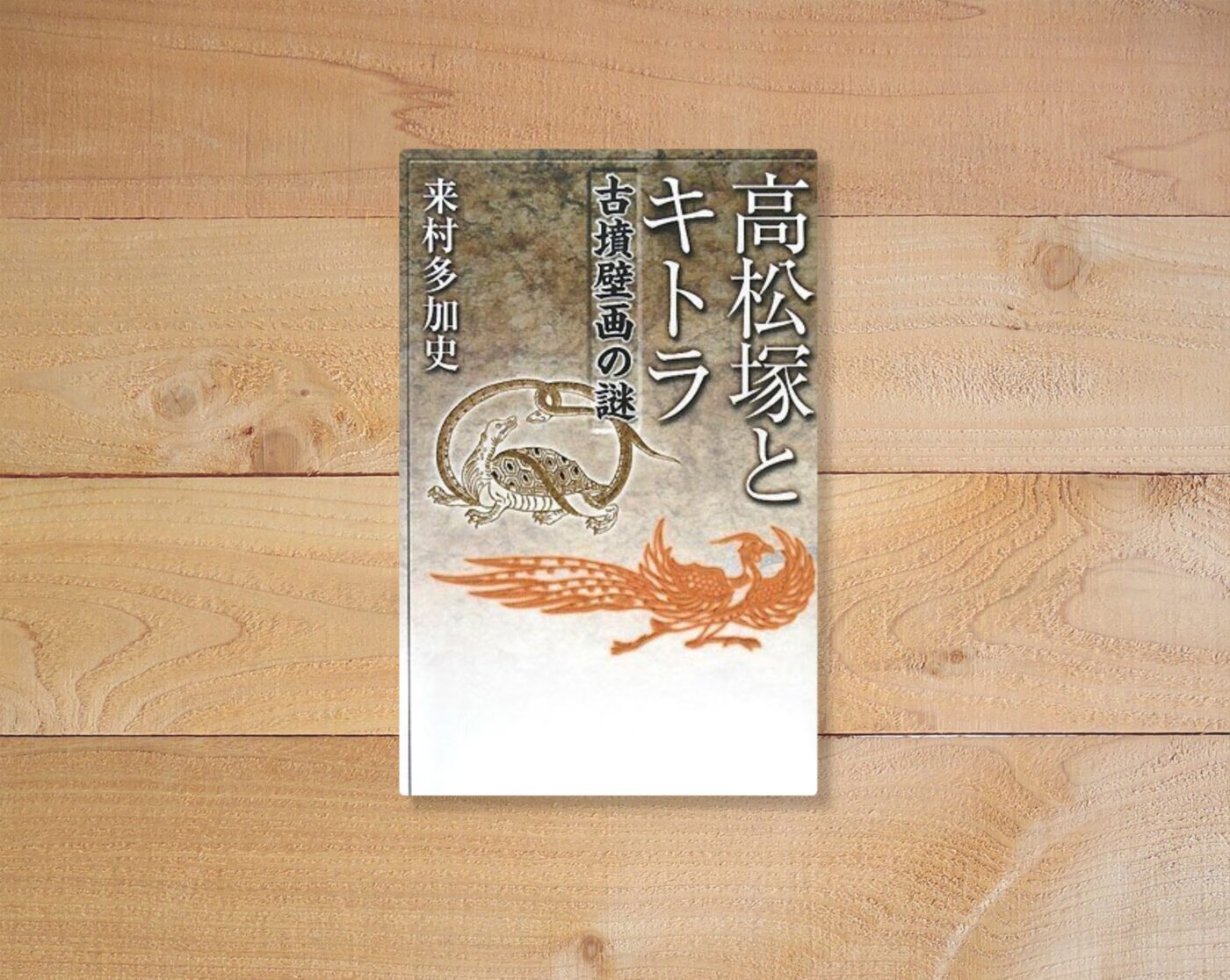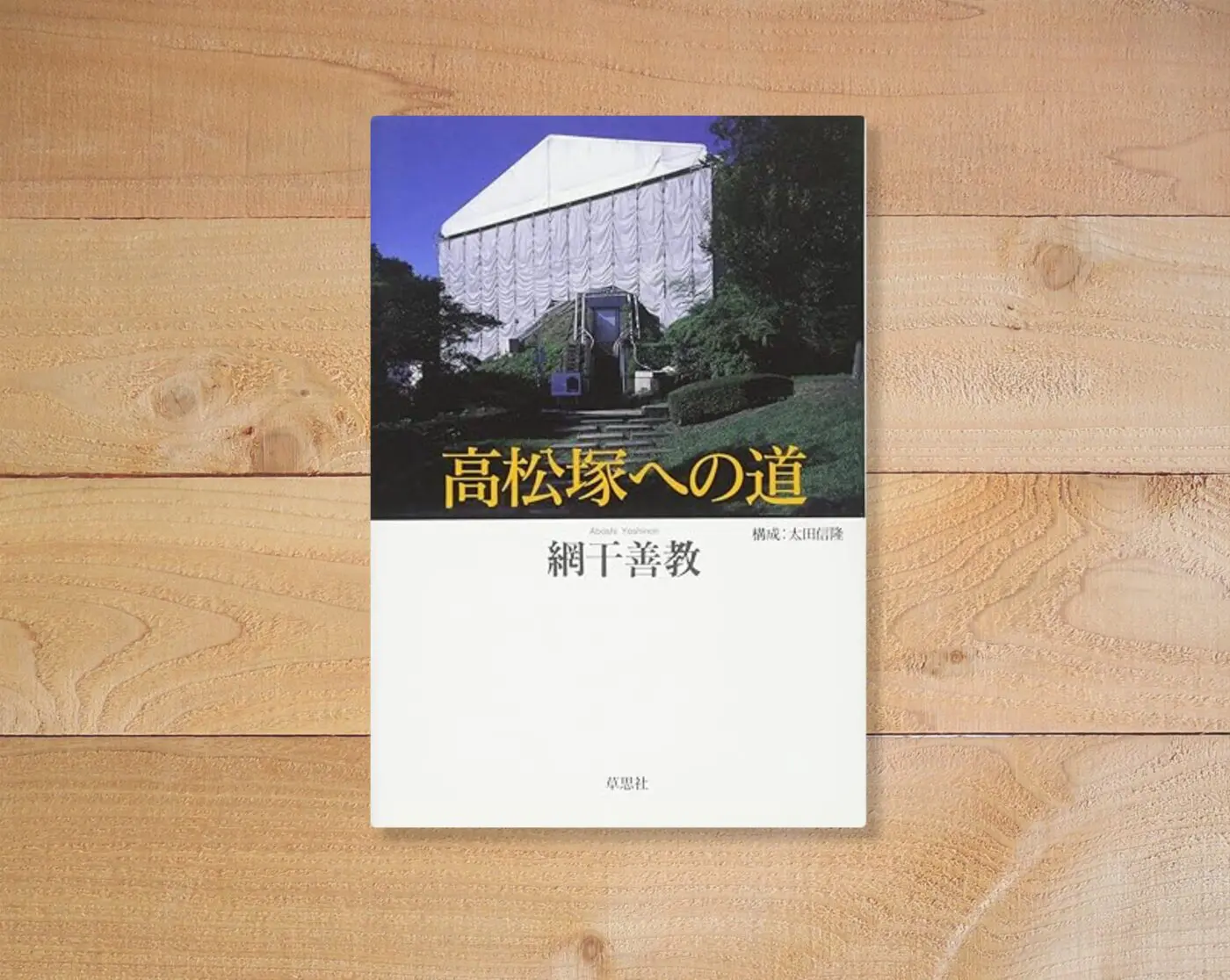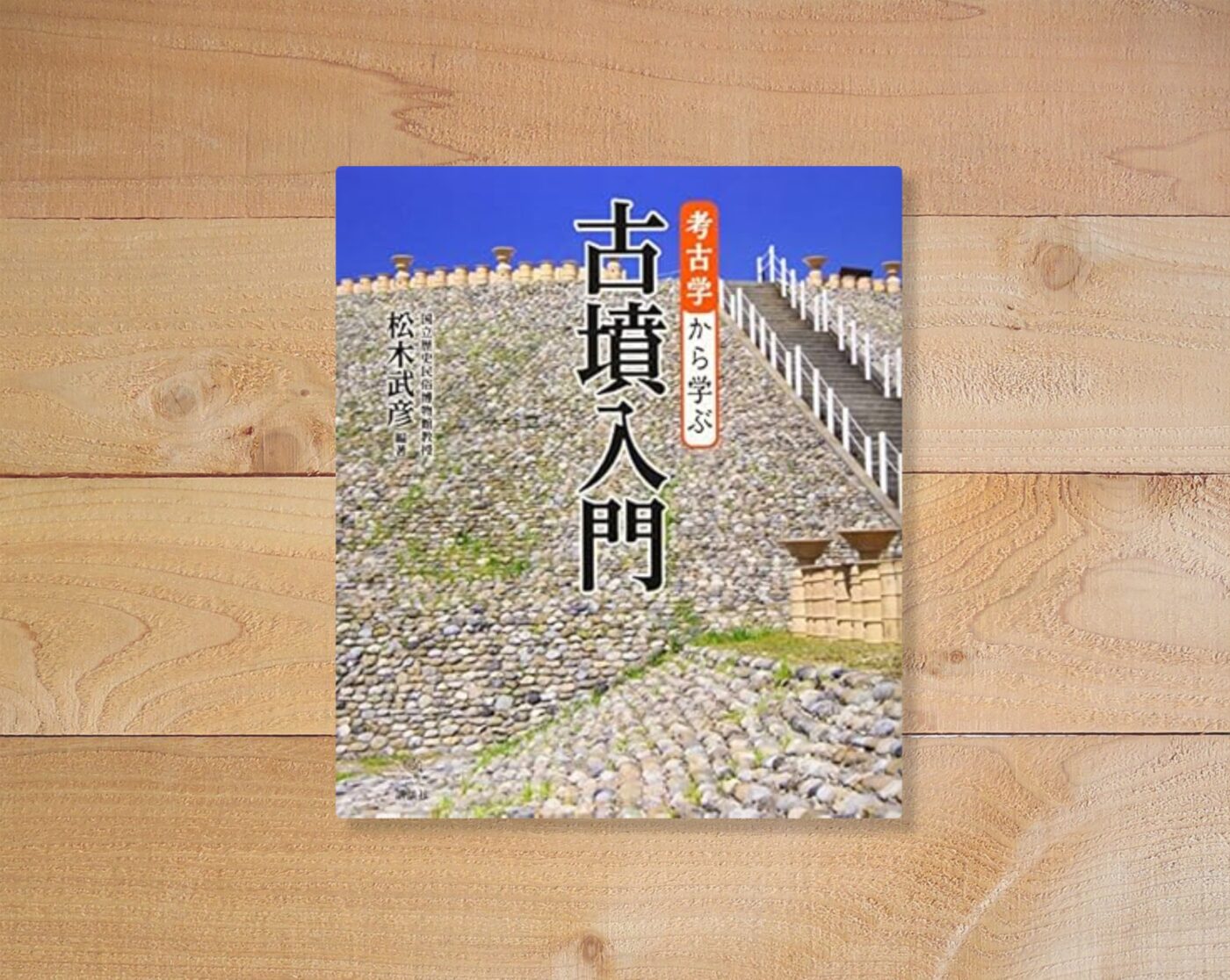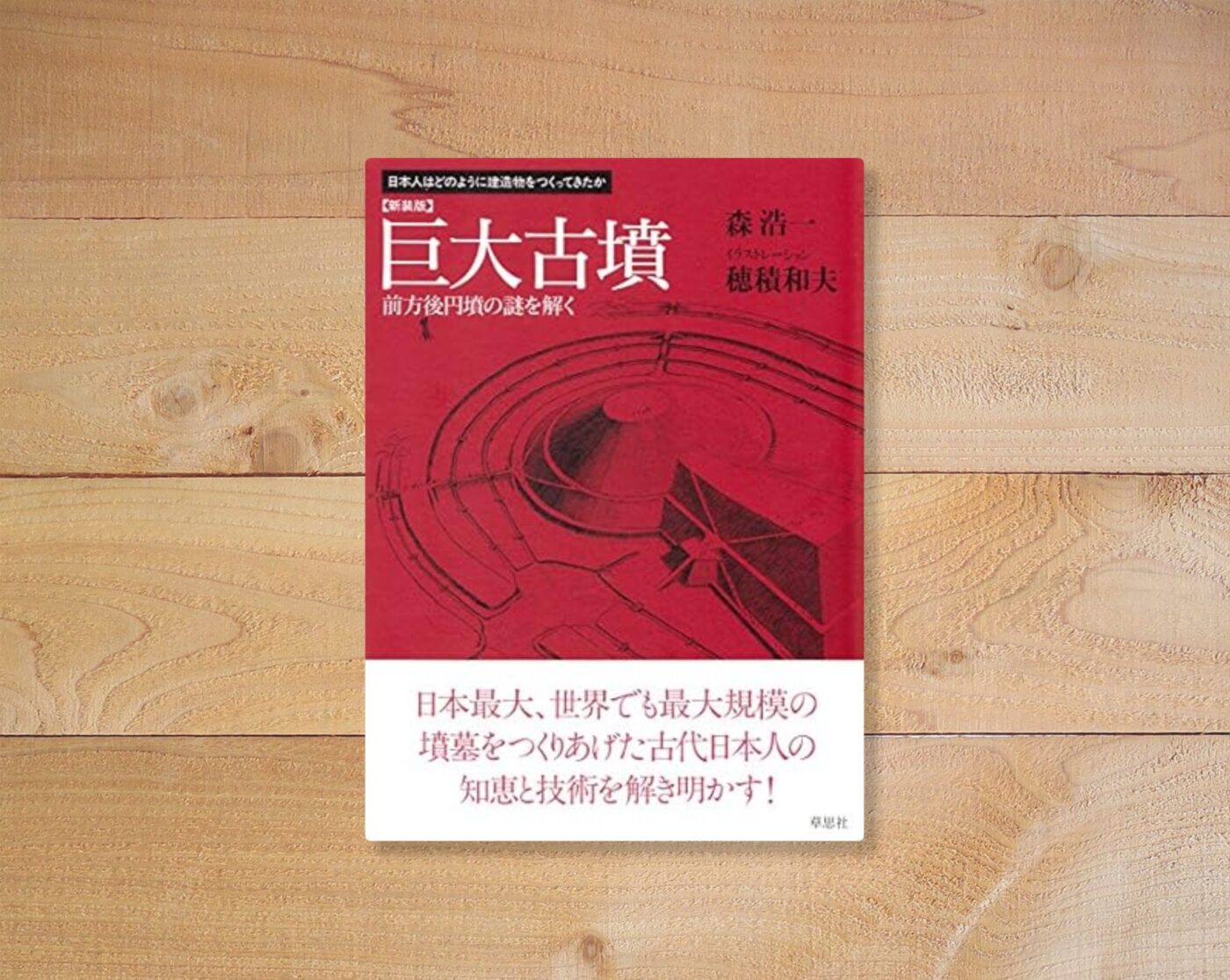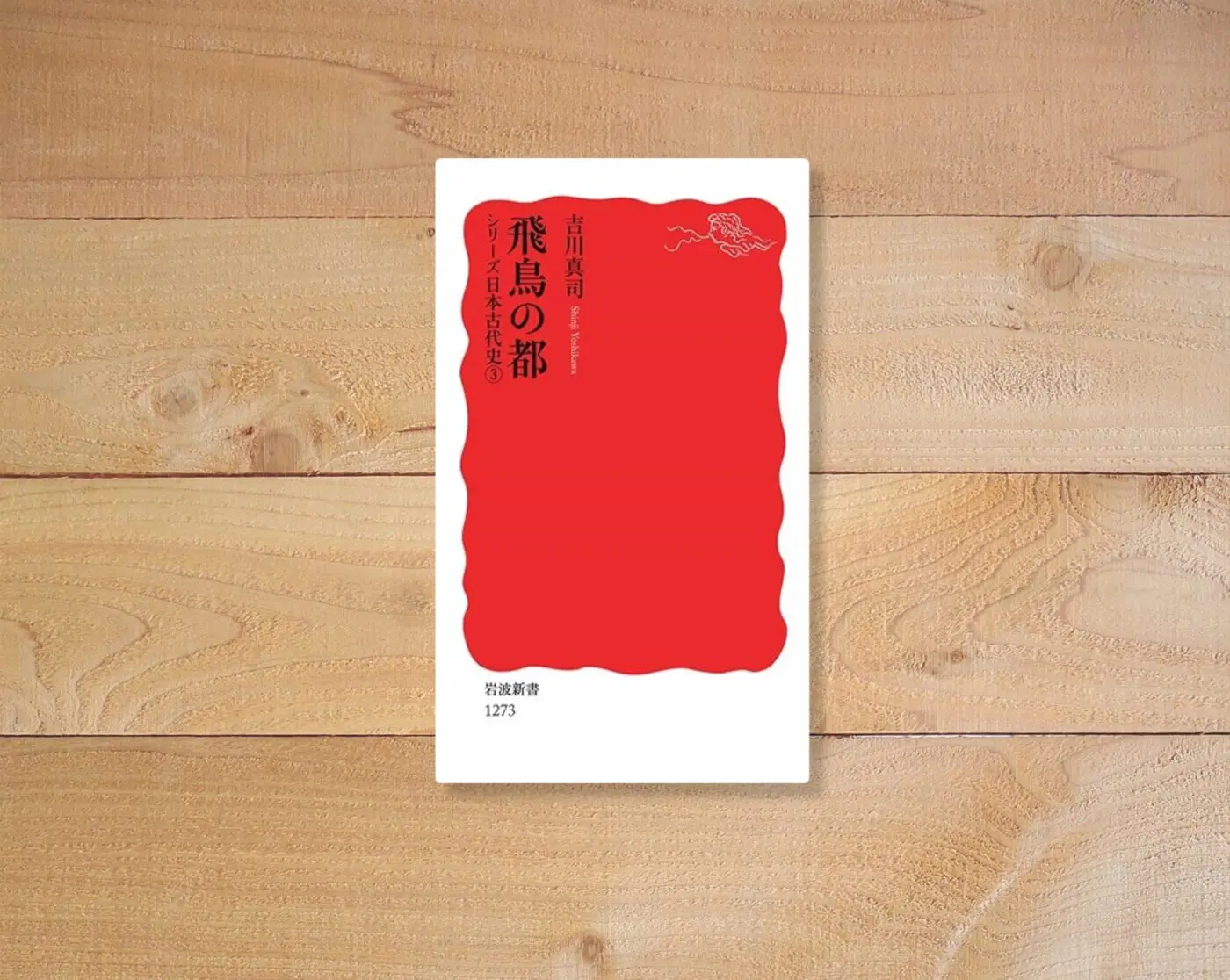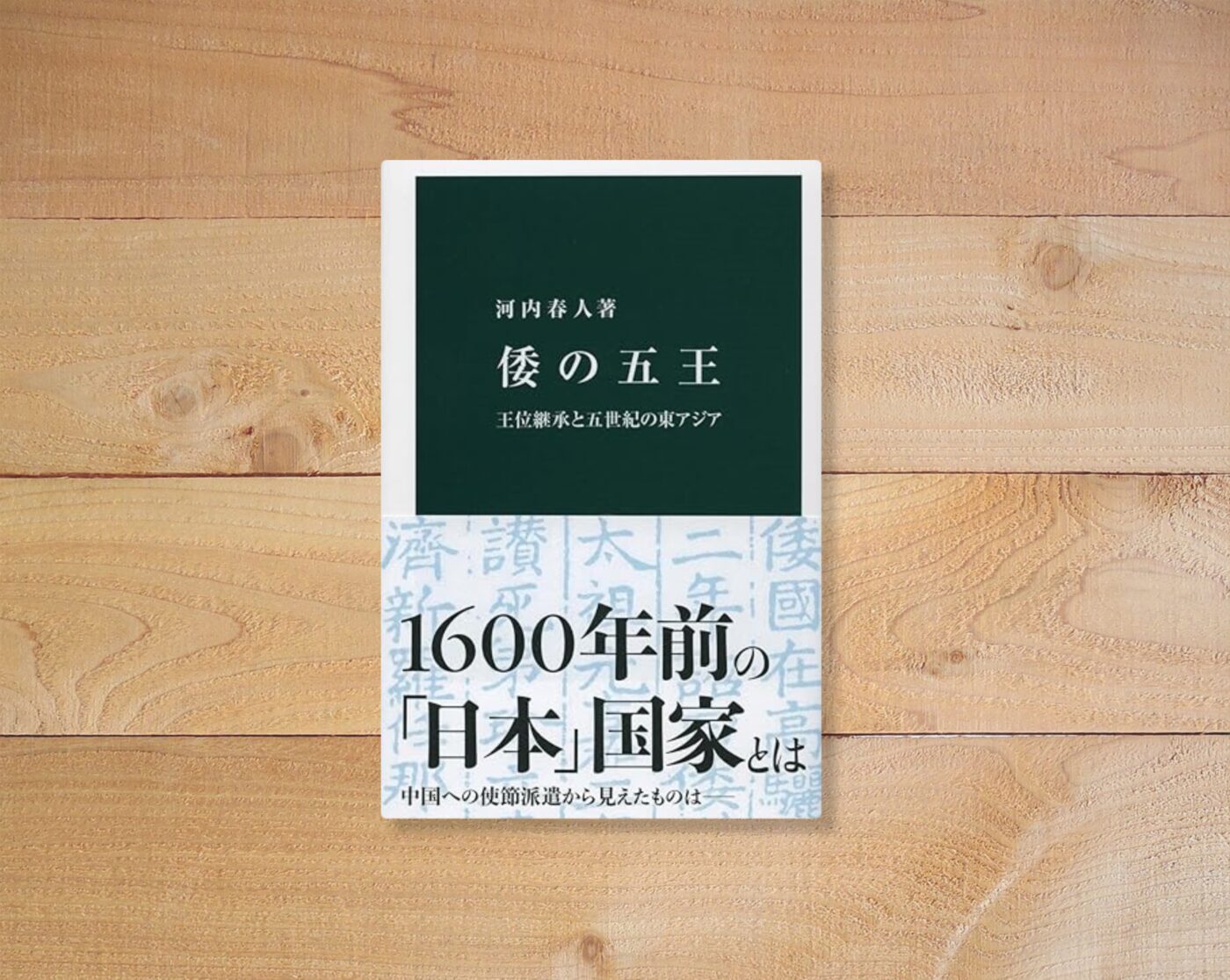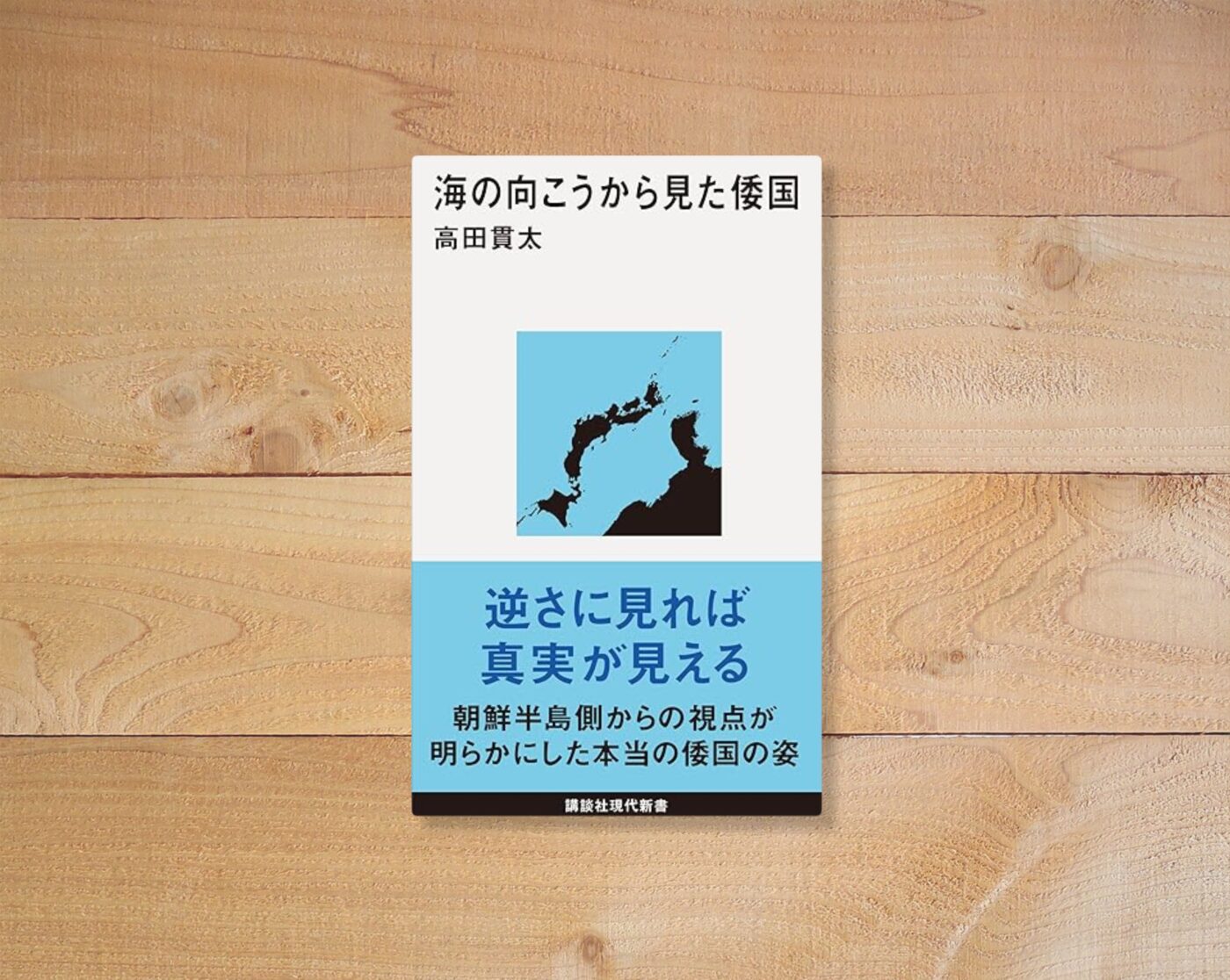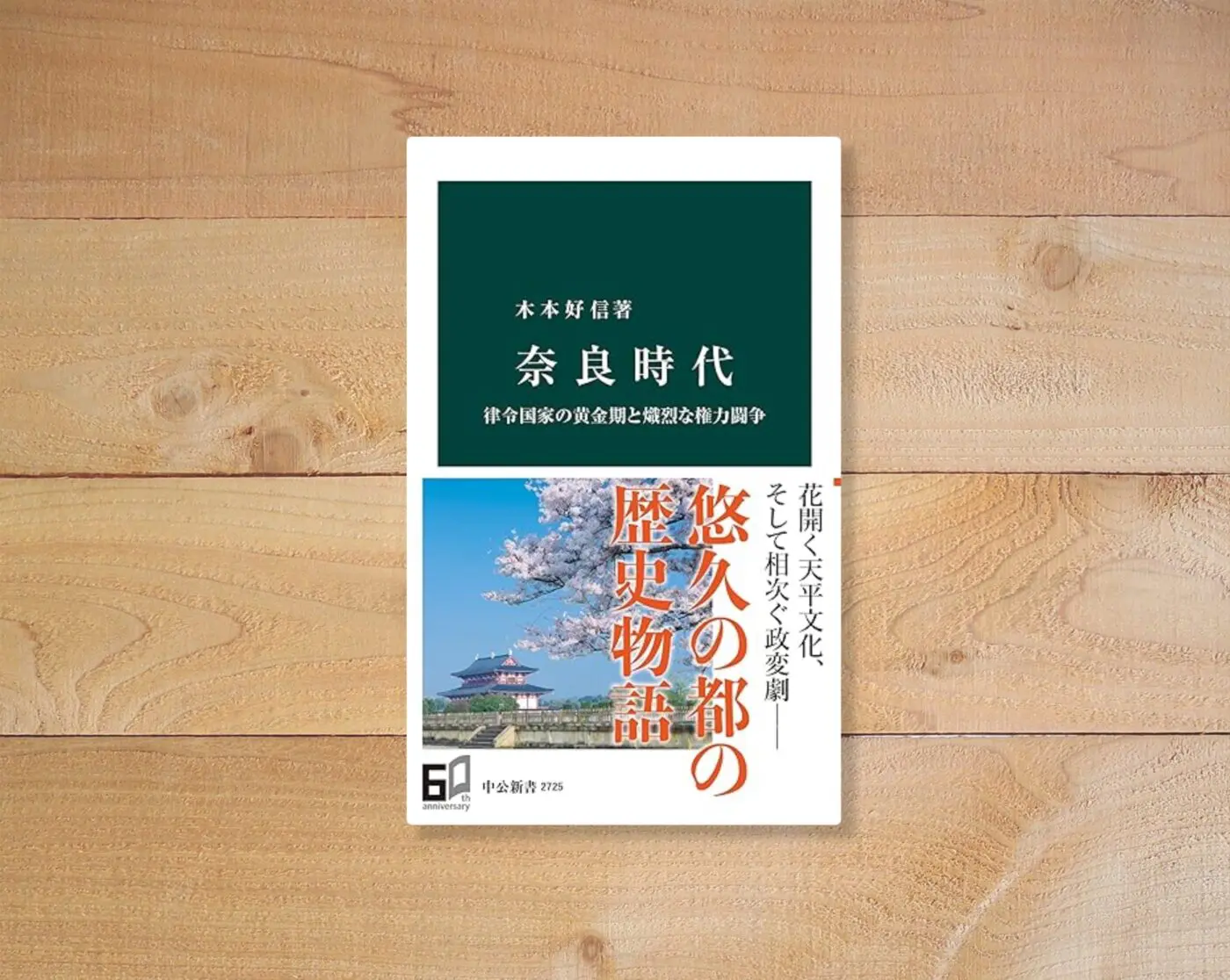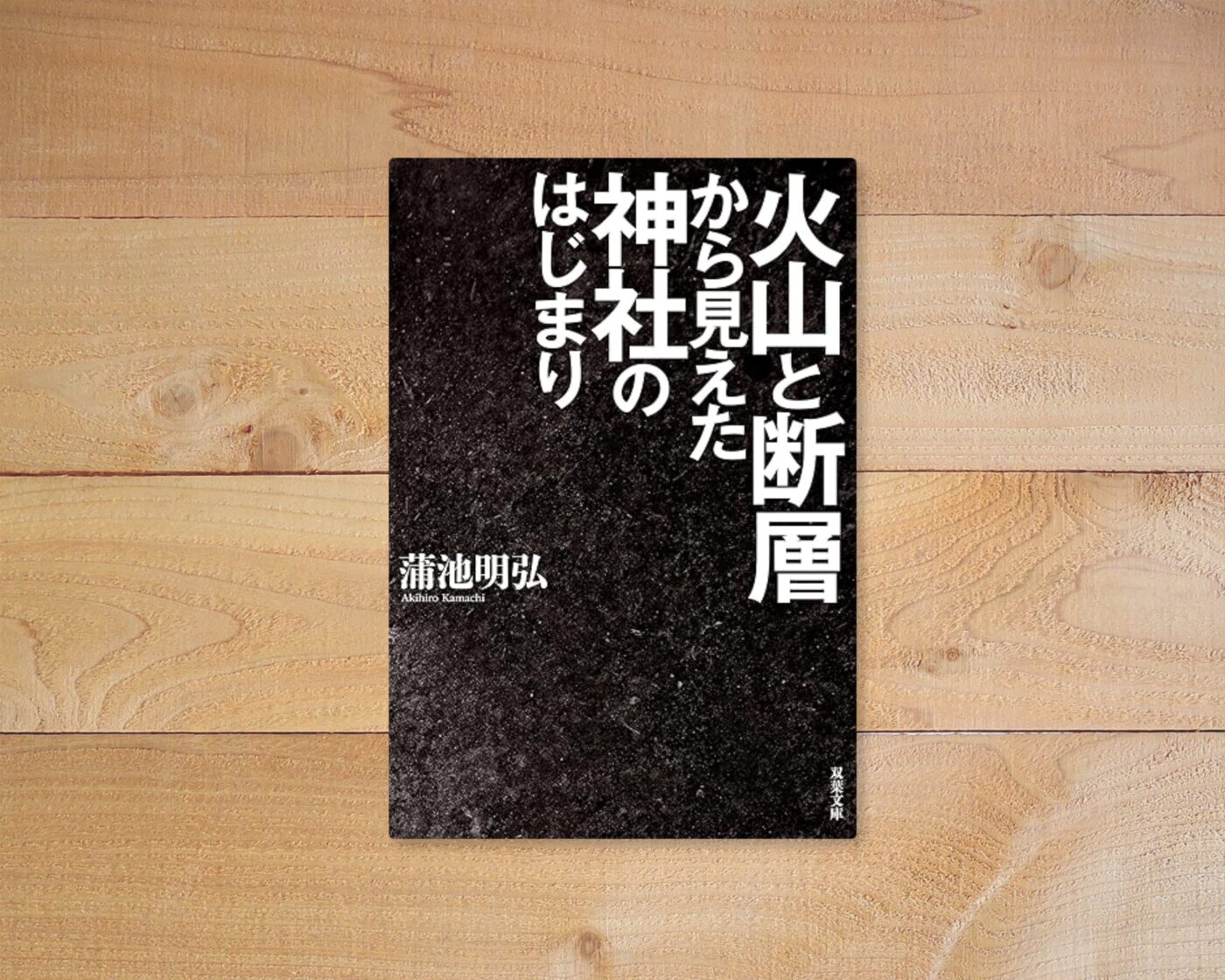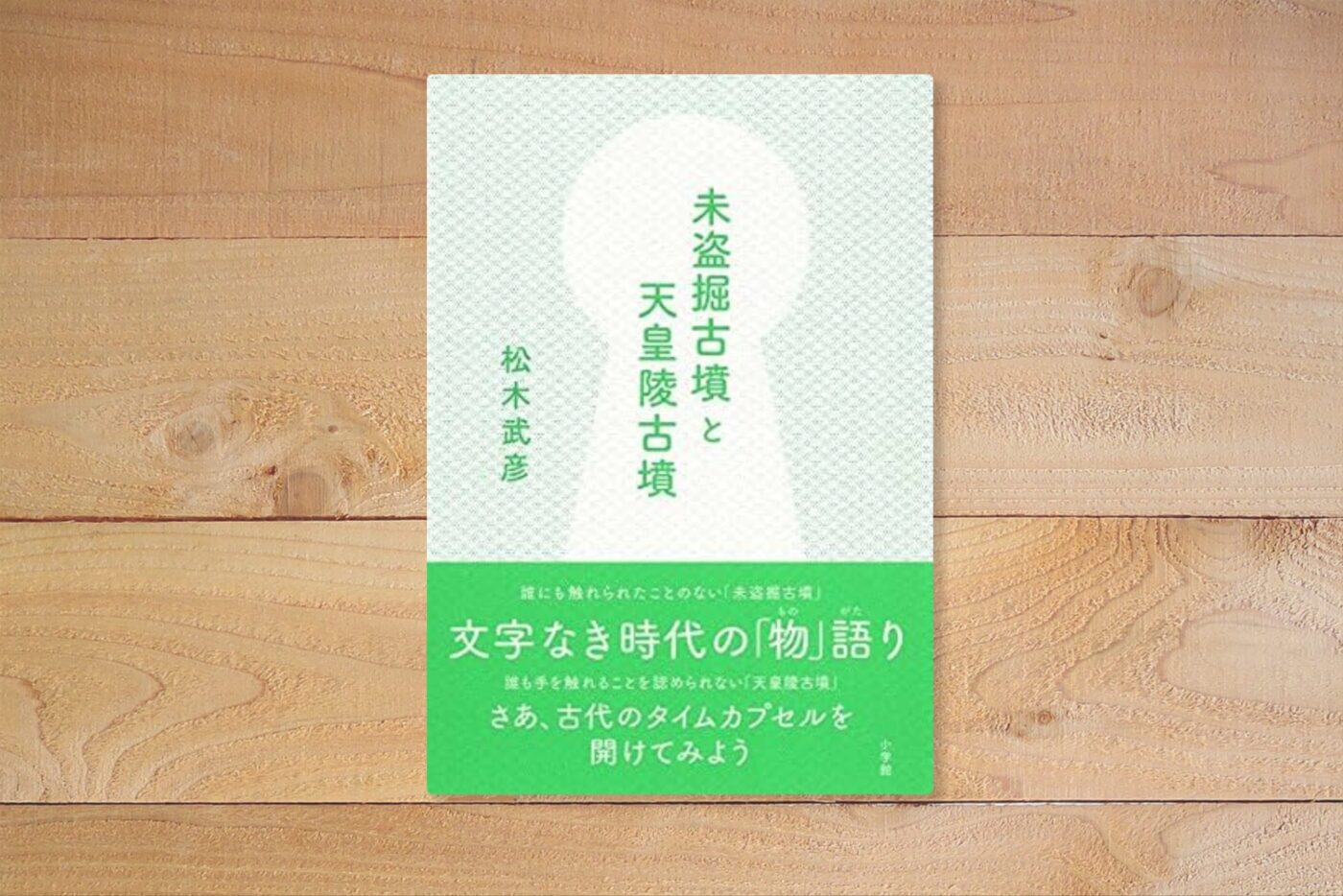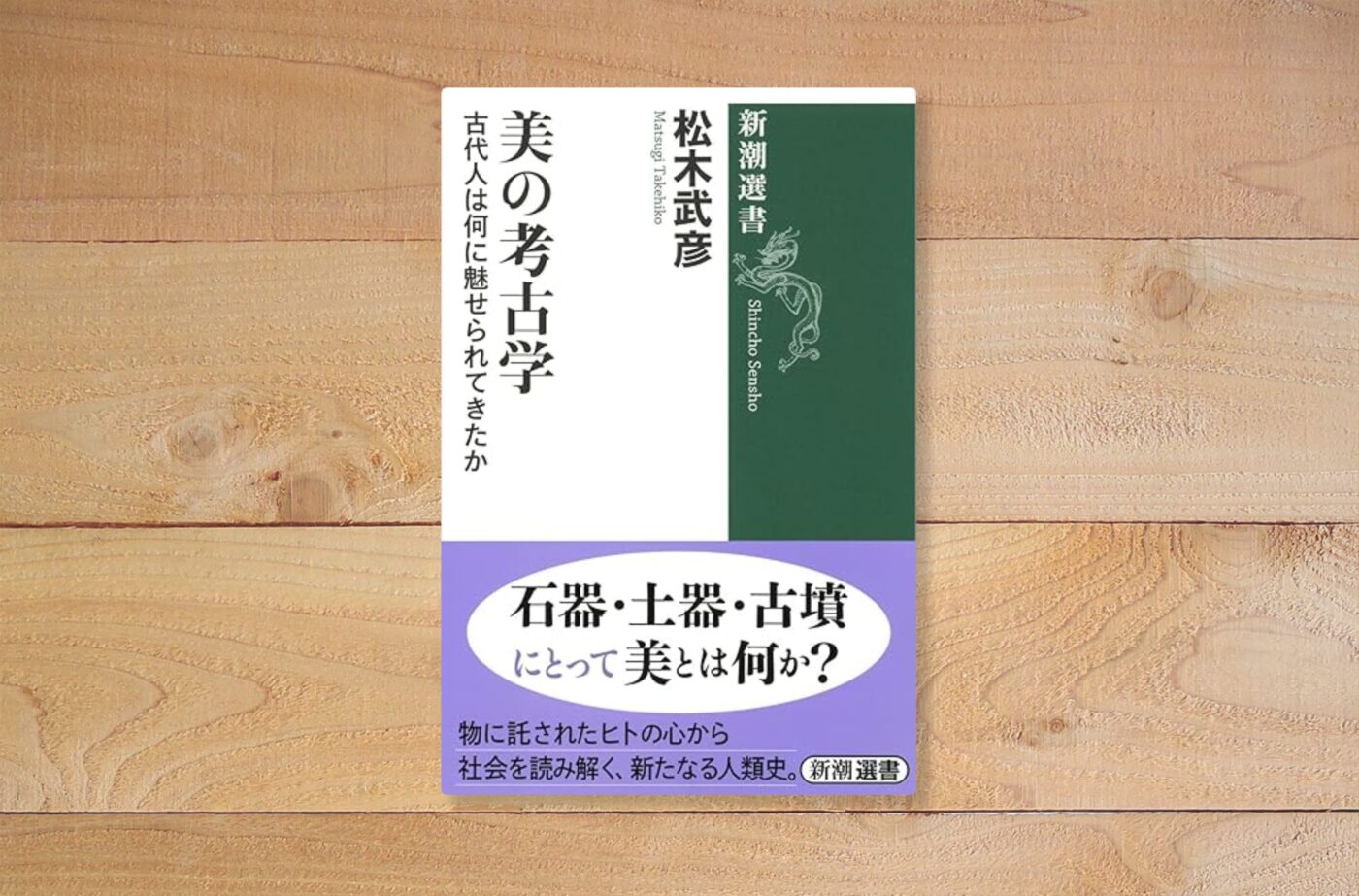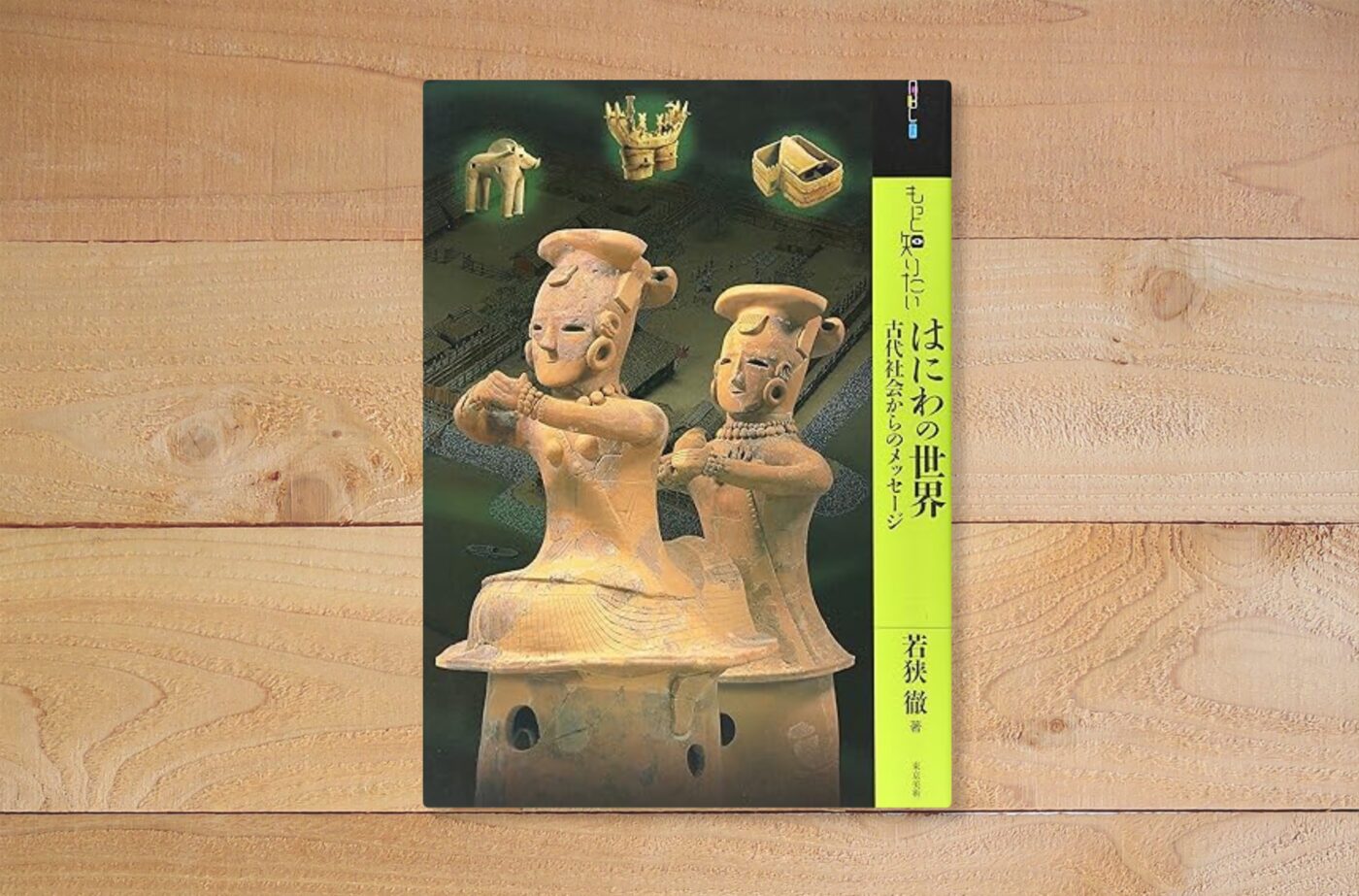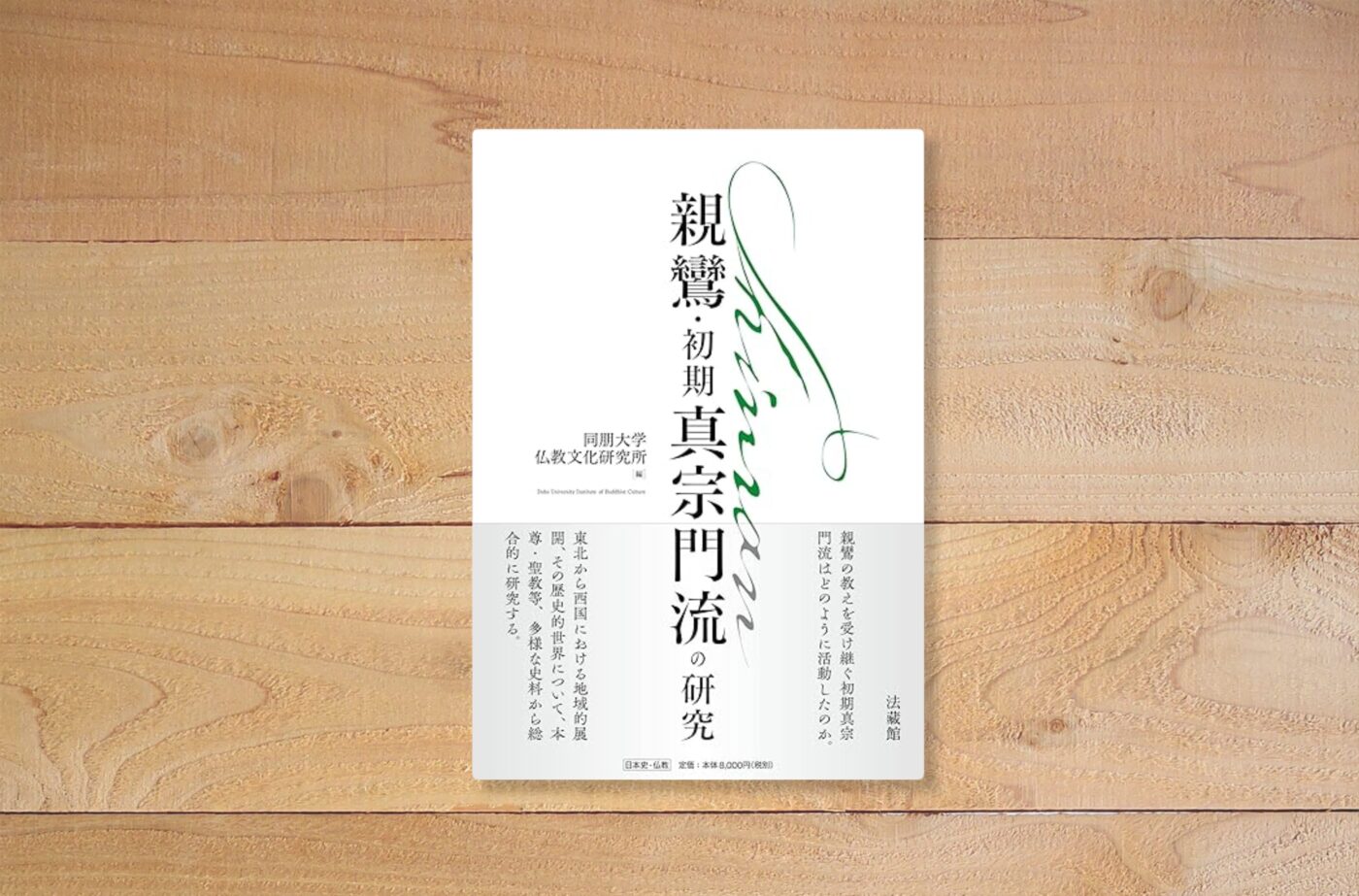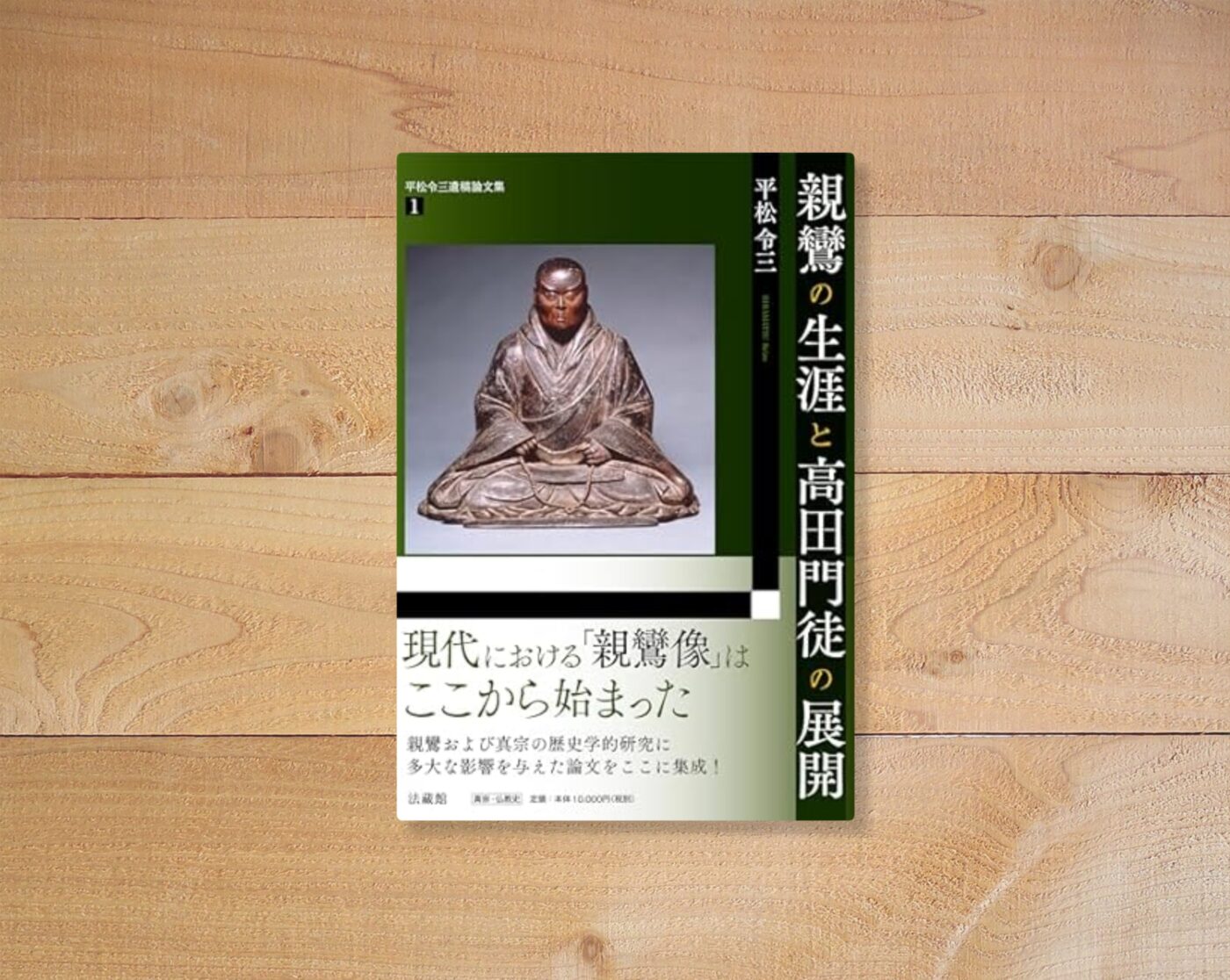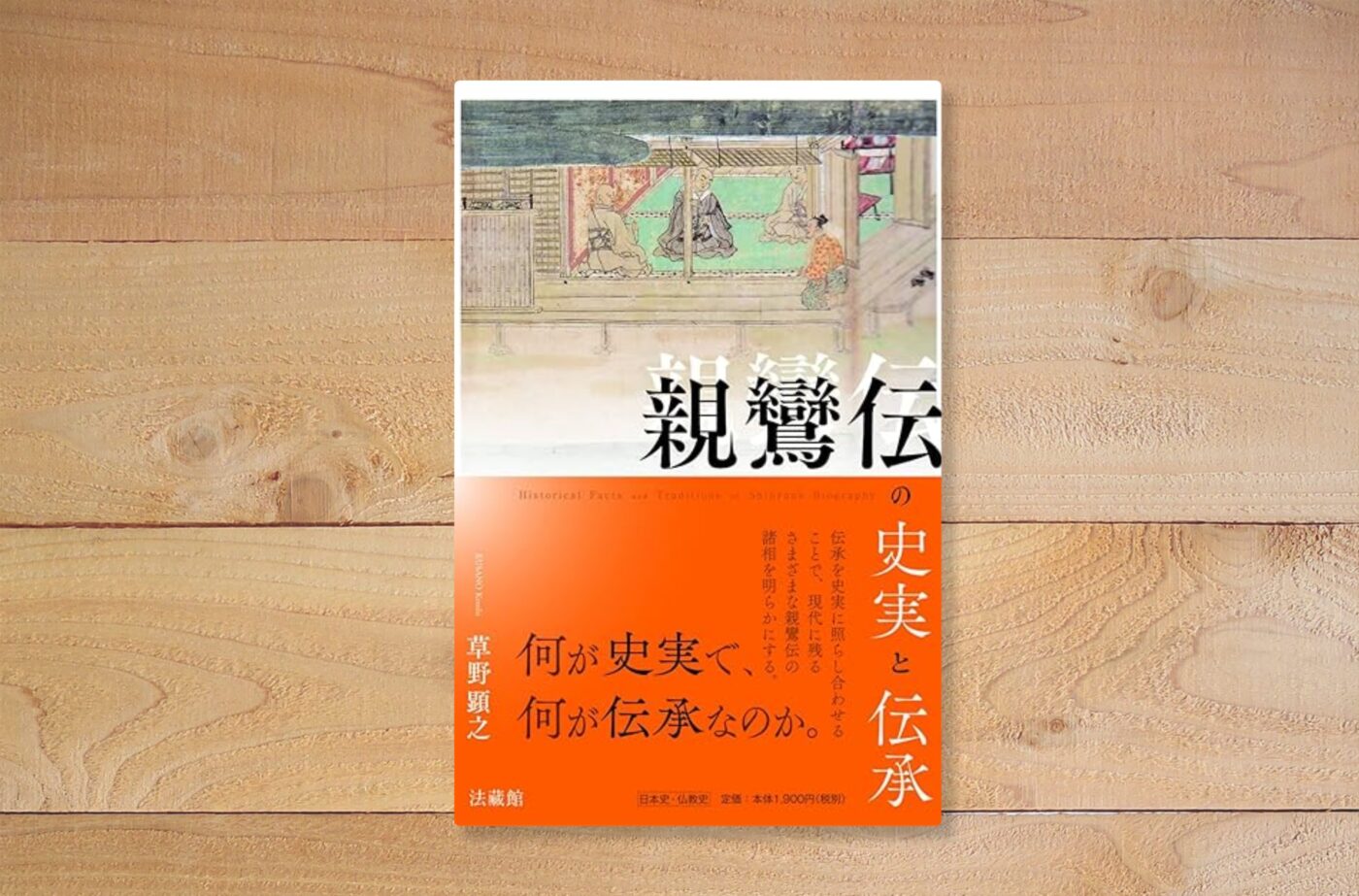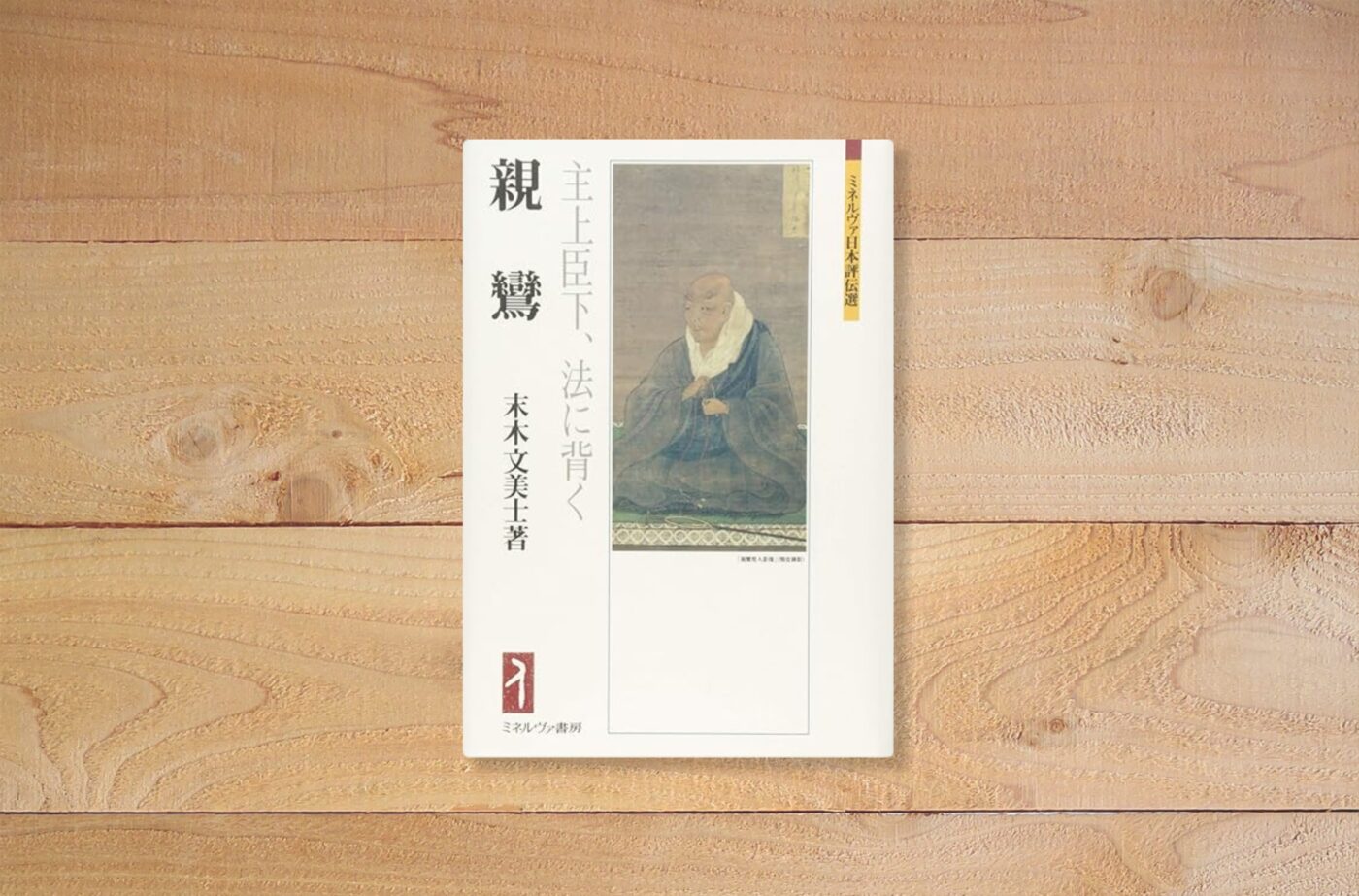目次
来村多加史『高松塚とキトラ 古墳壁画の謎』あらすじと感想~有名な四神壁画の驚くべき事実とは!
今回ご紹介するのは2008年に講談社より発行された来村多加史著『高松塚とキトラ 古墳壁画の謎』です。
早速この本について見ていきましょう。
壁画にかくされた知られざる古代の宇宙観 高松塚古墳とキトラ古墳。壁画の発見以来、被葬者は誰か、保存法をどうするか注目されてきたが、本書は壁画にこめられた意味を明らかにする。画期的な分析。
Amazon商品ページより
 高松塚古墳壁画 西壁女子群像 Wikipediaより
高松塚古墳壁画 西壁女子群像 Wikipediaより
 石室レプリカ(キトラ古墳壁画体験館 四神の館) Wikipediaより
石室レプリカ(キトラ古墳壁画体験館 四神の館) Wikipediaより
高松塚古墳、キトラ古墳は共に700年頃に作られた古墳です。所在地も共に明日香村近辺です。
私がこの古墳に関心を持ったのはほんの偶然でした。前回の記事「松木武彦『考古学から学ぶ古墳入門』概要と感想~古墳とは何かをわかりやすく学べるおすすめ入門書」でもお話ししましたように、私はこの度急遽飛鳥寺を訪問することになりました。そしてその周辺の地図を見ていると、なんと歴史の教科書に出ていた高松塚古墳がすぐ近くにあるではないですか!
ということでせっかくならば足を延ばしてみようと思いこの古墳について調べてみたのがそのきっかけです。そして手に取ったのが本書『高松塚とキトラ 古墳壁画の謎』という本でした。
この本を読んでまず驚いたのがそもそもこれらの古墳が造られたのが700年頃ということでした。700年といえば聖徳太子登場からほとんど100年も経った時代です。奈良の平城京遷都までもあとわずかです。そんな時代にまだこうした古墳が造られていたということに今更ながら驚いたのです。これは僧侶である私だからこその盲点かもしれません。仏教が伝来して時が経ち、数多くの寺院が建造されていたことに目が向かいがちでしたが、古墳はまだまだ作られていたのです。しかもその最高峰の芸術がまさにこの高松塚古墳とキトラ古墳に施されていたのでした。
古墳と言えば古代的なイメージがどうしても強くなってしまいますが、700年当時でもこうして古墳と日本人は共存していた・・・。これは私自身目が開かれるようでした。
また、本書では高松塚古墳とキトラ古墳の壁画の画家が同一人物であるということが論証されていきますが、この謎の画家がまたまた興味深い!なんと、この人物は唐に留学し現地の絵を学び、その技術を駆使してこれらの壁画を描いていたというのです。これも驚きでした。たしかに600年代には遣隋使、遣唐使が何度も派遣されています。その遣唐使に随行した画家がこの傑作絵画を生み出したのではないかという説を本書ではじっくり見ていくことになります。この画家への著者の熱意が伝わってくる熱い文章です。ものすごく引き込まれました。
さらに壁画本体に関する考察も実に刺激的です。壁の四方にはそれぞれ青龍、白虎、朱雀、玄武が描かれているのですが、この四神が石室に描かれたことの意味や、画家の工夫、制作エピソードなども詳しく語られます。当時の死生観も本書では語られますのでこれも非常に興味深かったです。
本書は高松塚古墳とキトラ古墳の歴史やその特徴を概観した上でさらに深いところまで連れて行ってくれる名著です。高松塚古墳とキトラ古墳はそもそも私の中で別個の存在だったのですが、ここまでリンクしている存在だったとは驚きでした。皆さんもこの本を読めばきっと驚くと思います。著者の熱い思いも感じられるおすすめ作品です。ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。
以上、「来村多加史『高松塚とキトラ 古墳壁画の謎』あらすじと感想~有名な四神壁画の驚くべき事実とは!」でした。
Amazon商品ページはこちら
高松塚とキトラ 古墳壁画の謎
次の記事はこちら
あわせて読みたい
網干善教『高松塚への道』あらすじと感想~世紀の大発見の裏側と考古学の面白さを知れる名著!これを読...
それにしても本書には驚きました。
とにかく面白いのです。
しかも網干先生その人についての事実が私にとっては刺激的なことばかりでした。この本を読んだ時間は至福と言っても過言ではありません。
前の記事はこちら
あわせて読みたい
松木武彦『考古学から学ぶ古墳入門』概要と感想~古墳とは何かをわかりやすく学べるおすすめ入門書
この本では古墳の歴史やその作り方、発掘のプロセスがわかりやすく解説されます。そしてさらには「古墳の見つけ方」という刺激的な章まであります。古墳に全く関心のなかった方でも自然に興味を持ってしまうような章立ては見事です。とても刺激的で一気に読み込んでしまいました。
関連記事
あわせて読みたい
森浩一、穂積和夫『新装版 巨大古墳』あらすじと感想~大仙古墳はどのように作られたのかをイラストで学...
私達も教科書などで必ず習う大仙古墳でありますが、その名前や写真に関しては知ってはいてもいざそれがどのように作られたかというと意外とピンと来ないですよね。私もそうでした。ですがこの本を読めばどれだけ高度な技術が用いられていたのかがよくわかります。そして単にこの巨大古墳の造り方だけでなく、その存在意義についても考えさせられることになります。
あわせて読みたい
吉川真司『飛鳥の都』概要と感想~7世紀日本の流れや国際関係も知れるおすすめ入門書
飛鳥時代といえば聖徳太子がクローズアップされがちですが、その存在の背後にはグローバルな時代背景が広がっていました。そして奈良時代に向けて倭国がどのように変貌していったかという過度期の内実を知れる本書は実に刺激的です。
あわせて読みたい
河内春人『倭の五王』概要と感想~5世紀頃の東アジア情勢と日本外交を学べるおすすめ本!古代日本は想像...
本書を読んでいると、古代日本を含めた昔の首脳部がいかに海外情勢を詳しく知っていたかに驚くことになります。現代のような通信手段もなかった時代にどうしてそんなに海外のことを知れたのかと驚くばかりでした。
古代日本は私たちが想像するよりはるかに国際的な世界を生きていたようです。
あわせて読みたい
高田貫太『海の向こうから見た倭国』あらすじと感想~古代日本と朝鮮、中国の相互関係を学べる刺激的な作品
古代日本では朝鮮から様々な技術が伝わっていたことはよく知られていますが、5世紀が「技術革新の世紀」とまで呼ばれていたのには驚きました。
そして本書を読めばこうした朝鮮との交流が5世紀どころか弥生時代の後半頃から断続的に続いていたことも知ることになります。
あわせて読みたい
奈良時代の仏教と歴史・時代背景を学ぶのにおすすめの参考書12選!
この記事では仏教が日本に本格的に根付いていくことになる奈良時代の仏教やその歴史・時代背景を学ぶのにおすすめの参考書を紹介していきます。
あわせて読みたい
蒲池明弘『火山と断層から見えた神社のはじまり』あらすじと感想~火山の近くに聖地が生まれる?宗教と...
私達が良く知る古墳や神社と火山のつながりには驚くしかありません。神社や古墳に対する見方が変わると言ってもよいでしょう。
古代史については様々な仮説が提唱されていますが、かつて日本はどのような状況だったのかと考えるのはとてもロマンがあります。
あわせて読みたい
松木武彦『未盗掘古墳と天皇陵古墳』あらすじと感想~古墳発掘の現場に生きる考古学者の仕事を知れる刺...
本書の著者松木武彦氏は私が古墳にはまるきっかけとなった『考古学から学ぶ古墳入門』の著者でもあります。
『未盗掘古墳と天皇陵古墳』というタイトルだけを見るとかなり難しそうな本のように思えますが、これがとにかく面白い!古墳発掘の現場に生きる著者だからこそ知れる現場の雰囲気や古墳にまつわる様々なエピソードを聞くことができます。
あわせて読みたい
松木武彦『美の考古学 古代人は何に魅せられてきたか』あらすじと感想~人を動かす力とは何か。考古学か...
古代人は美の力を使って社会の結びつきを作り、より大きく緊密な共同体を作ることに成功しました。実用的には一見「無用」に思える美こそ、深いところで人を繋げる究極の媒介となっていたのです。
いや~これはすごい本でした!松木武彦氏の著書はどれも刺激的ですが、本書も大変なことになっています。
あわせて読みたい
若狭徹『もっと知りたい はにわの世界』概要と感想~知れば知るほど奥深い埴輪の世界のおすすめ入門書!
本書『もっと知りたいシリーズ』はこれまでも当ブログでもたくさんの本を紹介してきました。やはり何と言ってもこのシリーズは図版が豊富!しかも解説も入門者向けに非常にわかりやすいものになっており、ガイドブックとして実に優秀です。