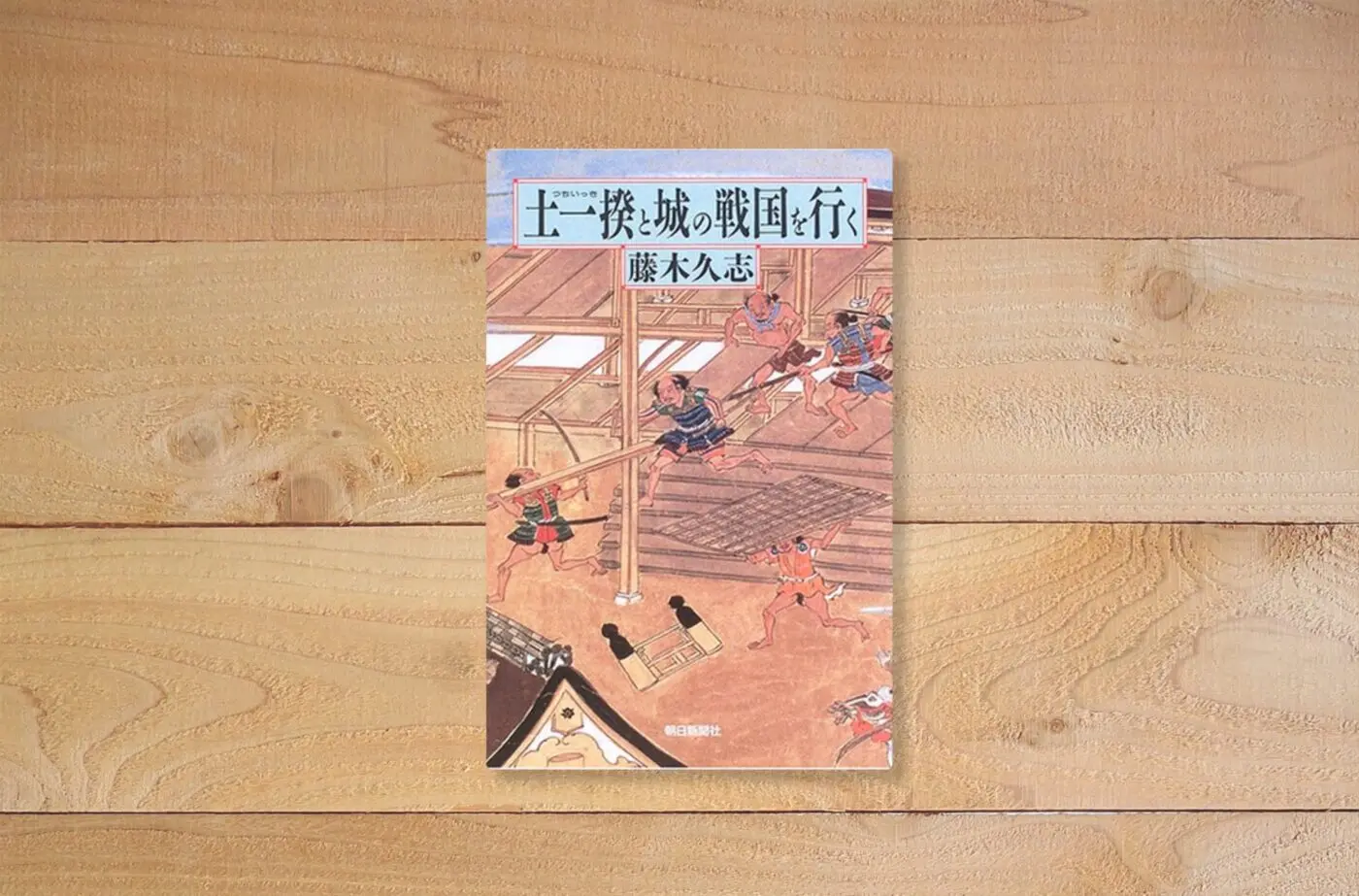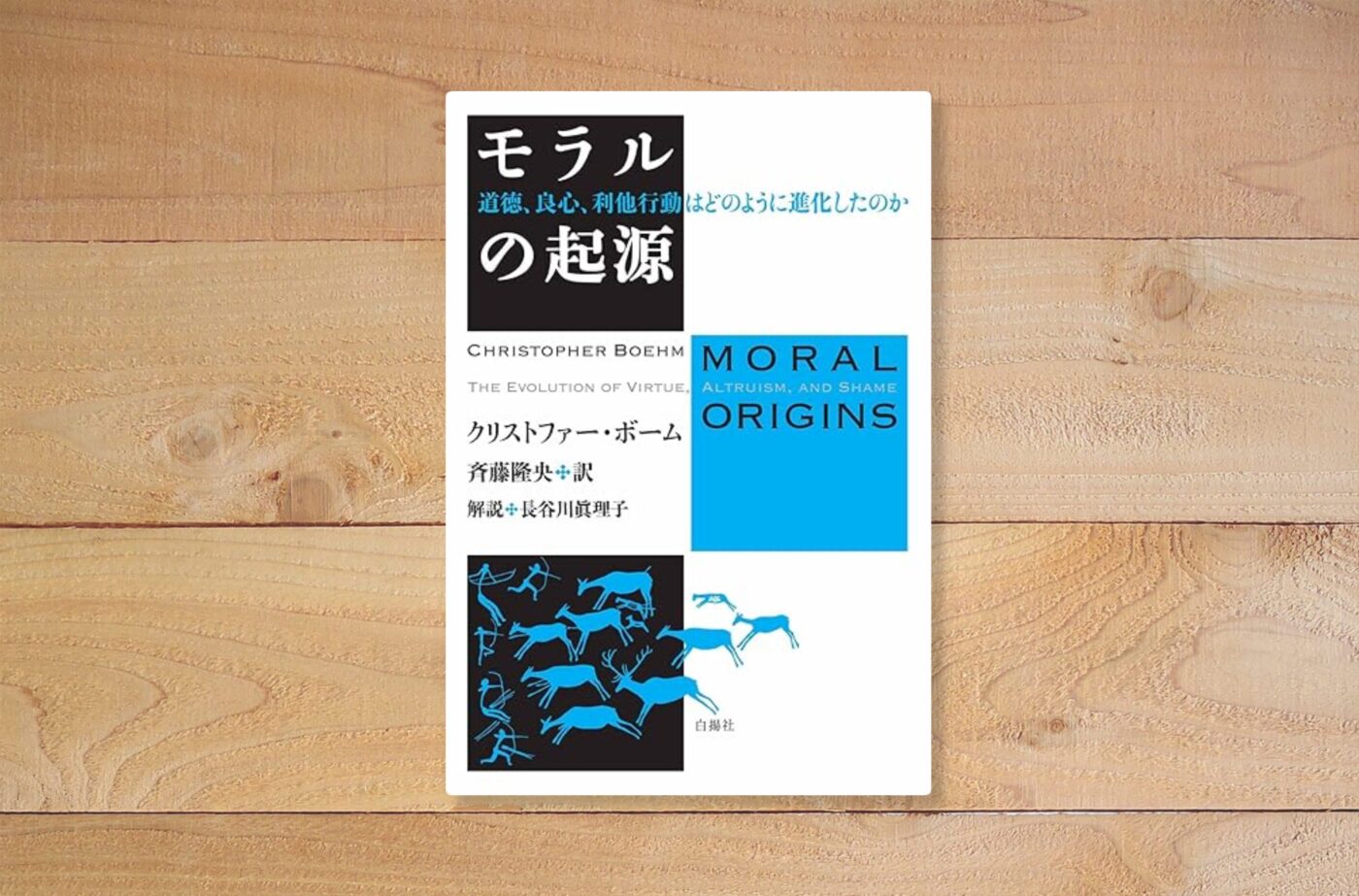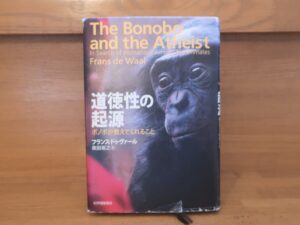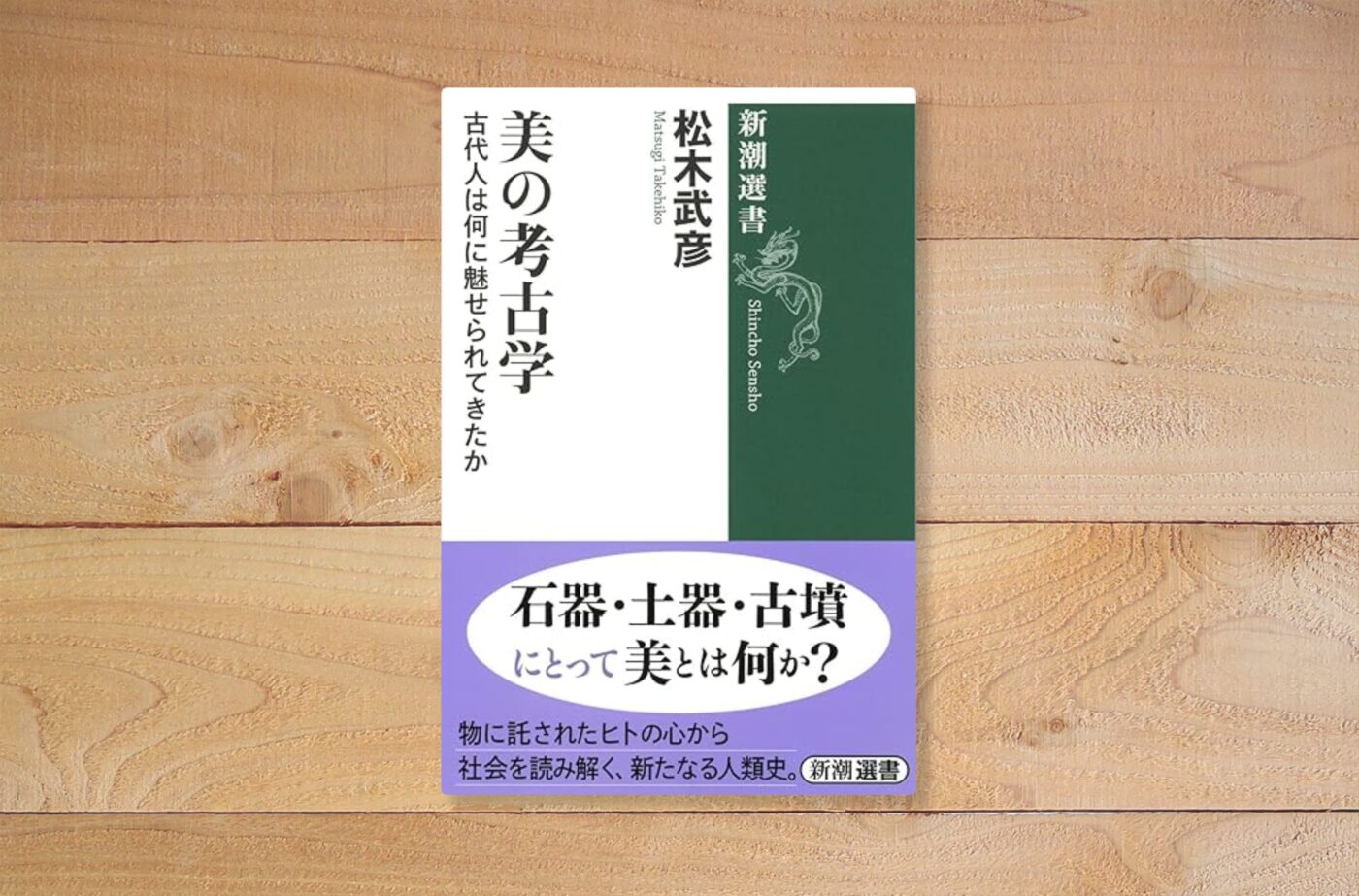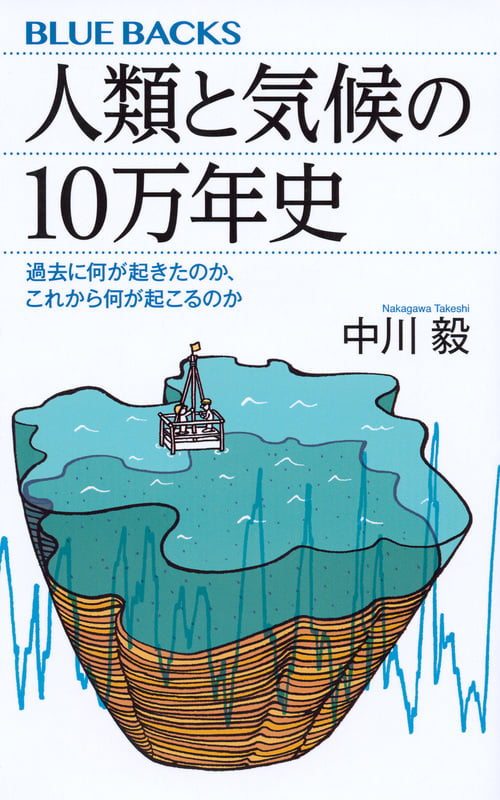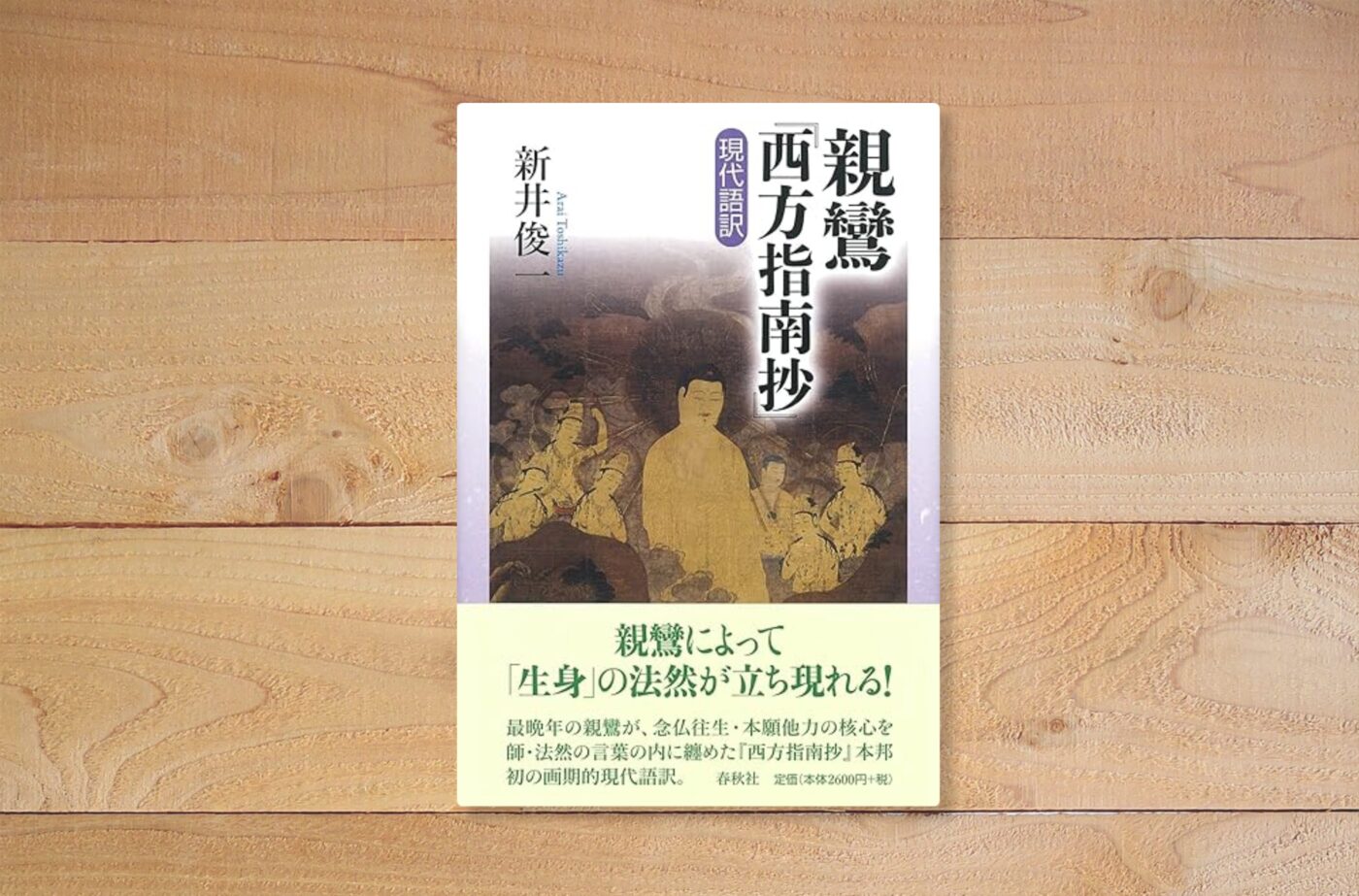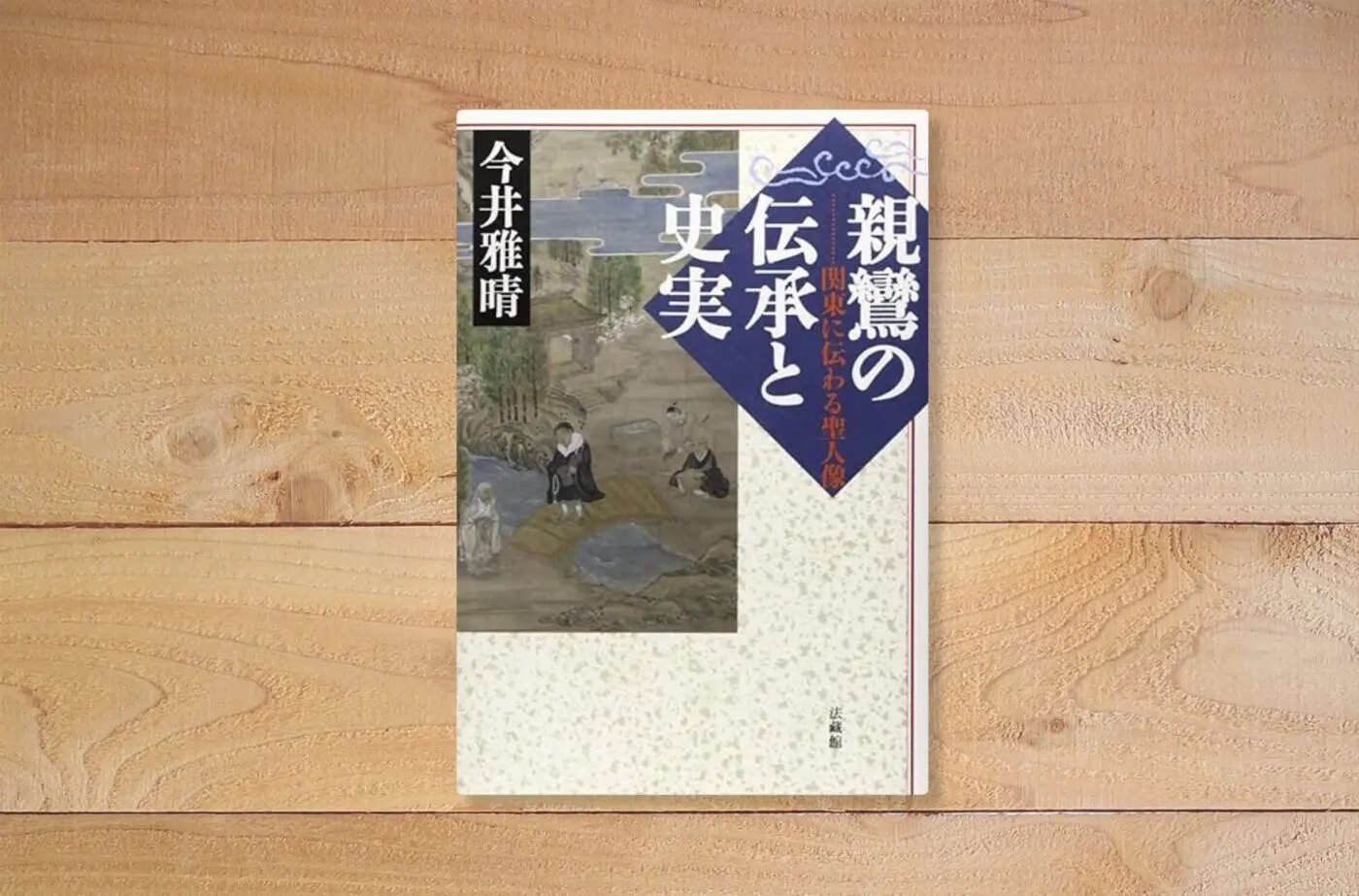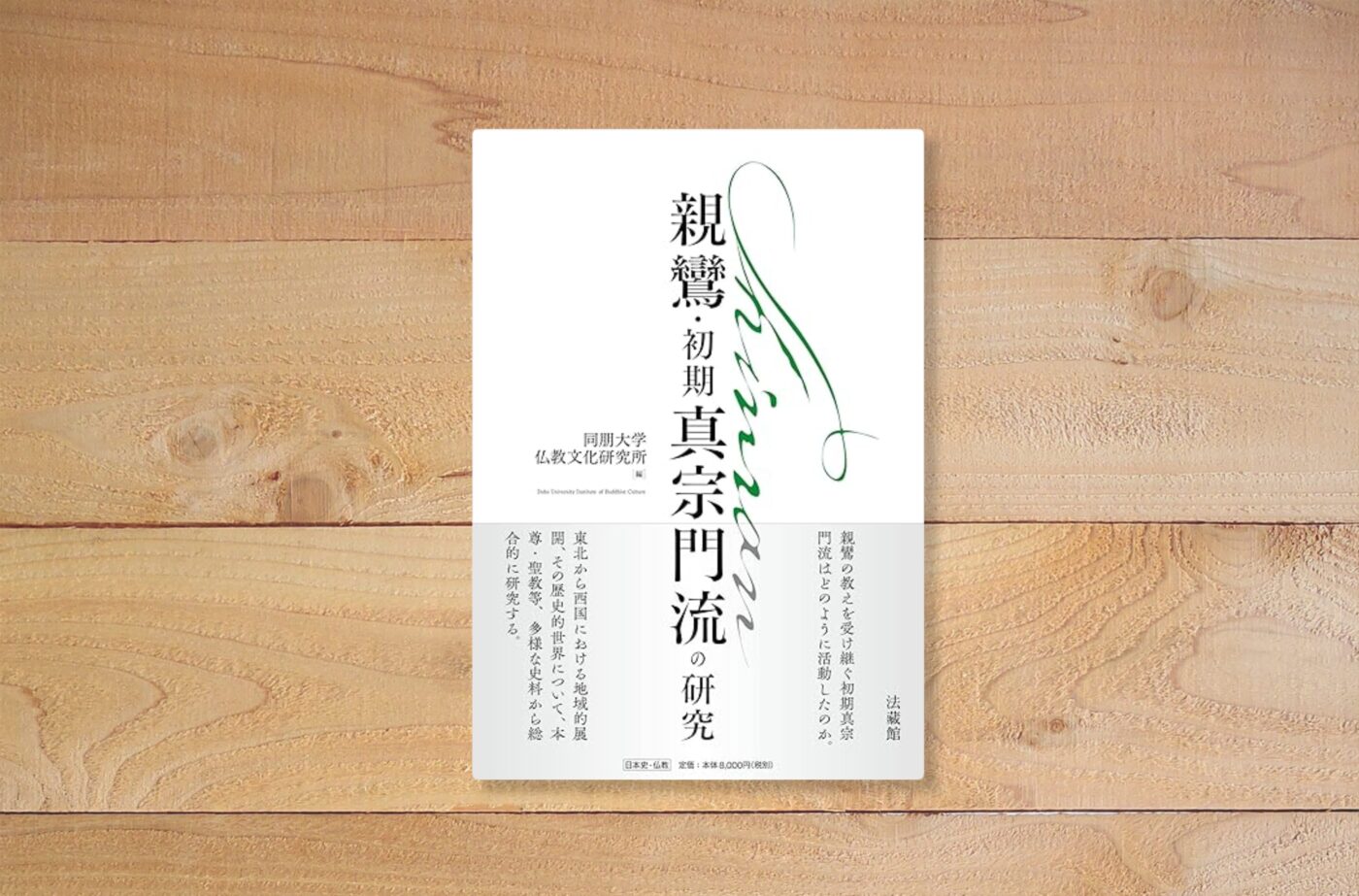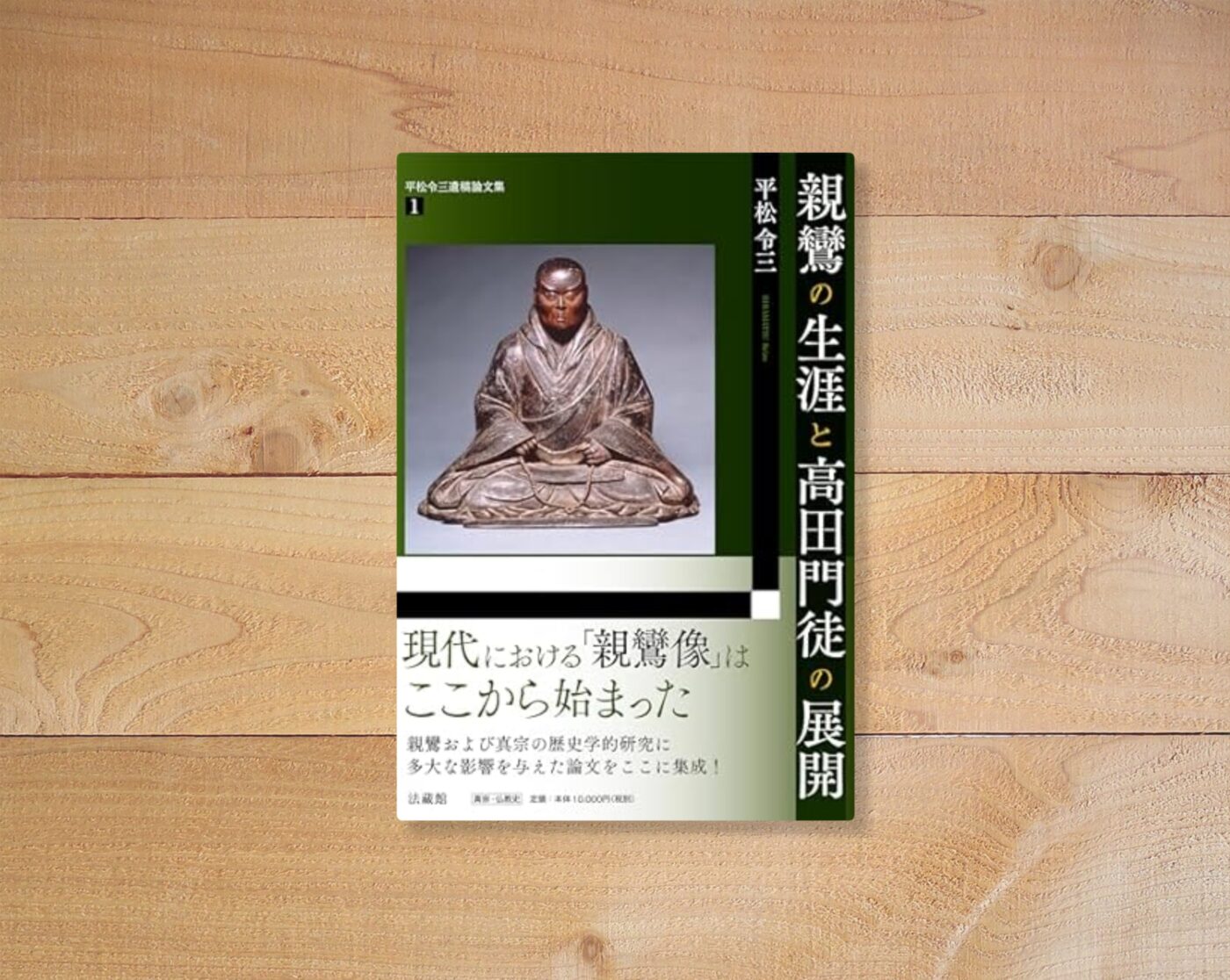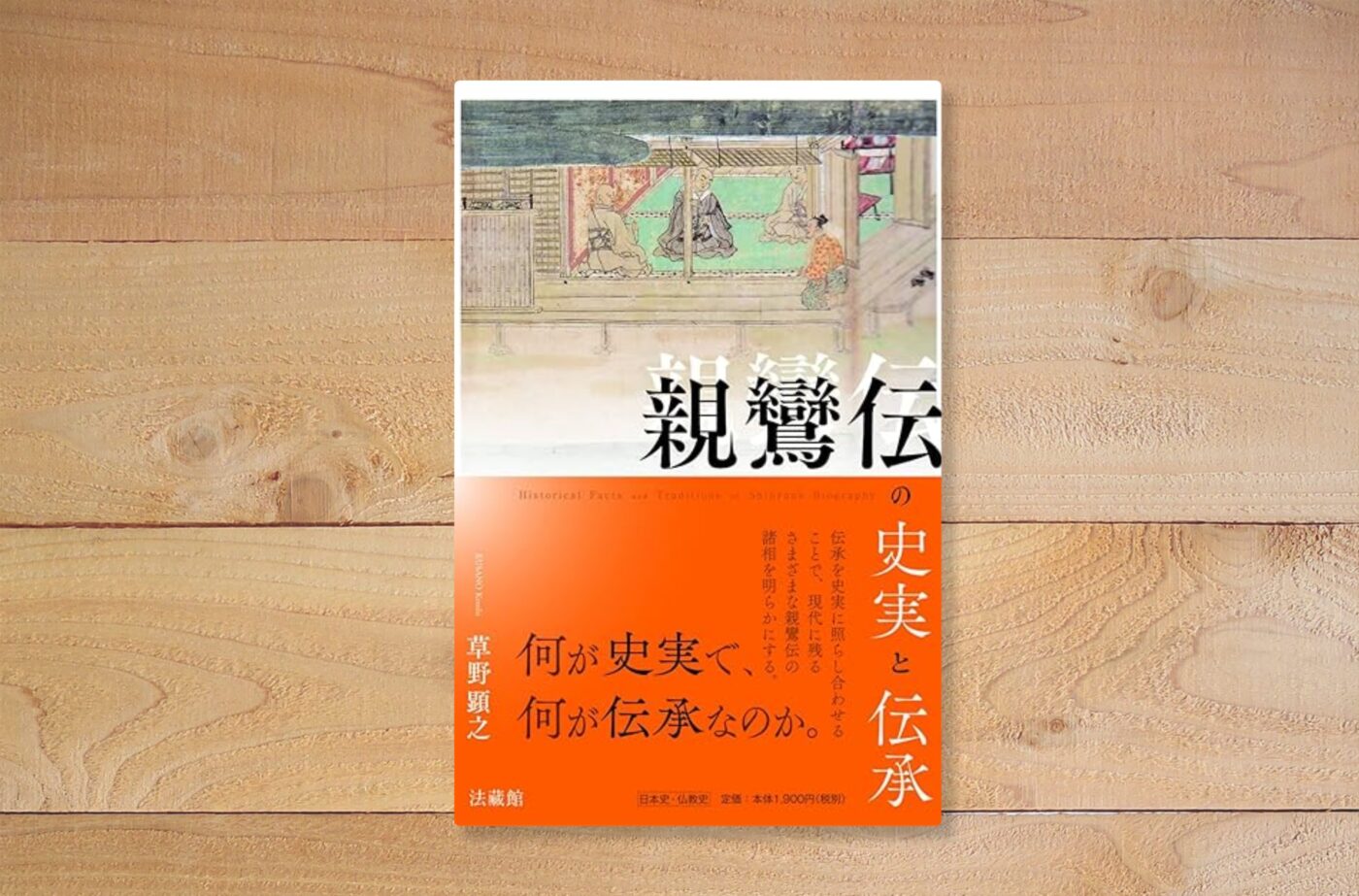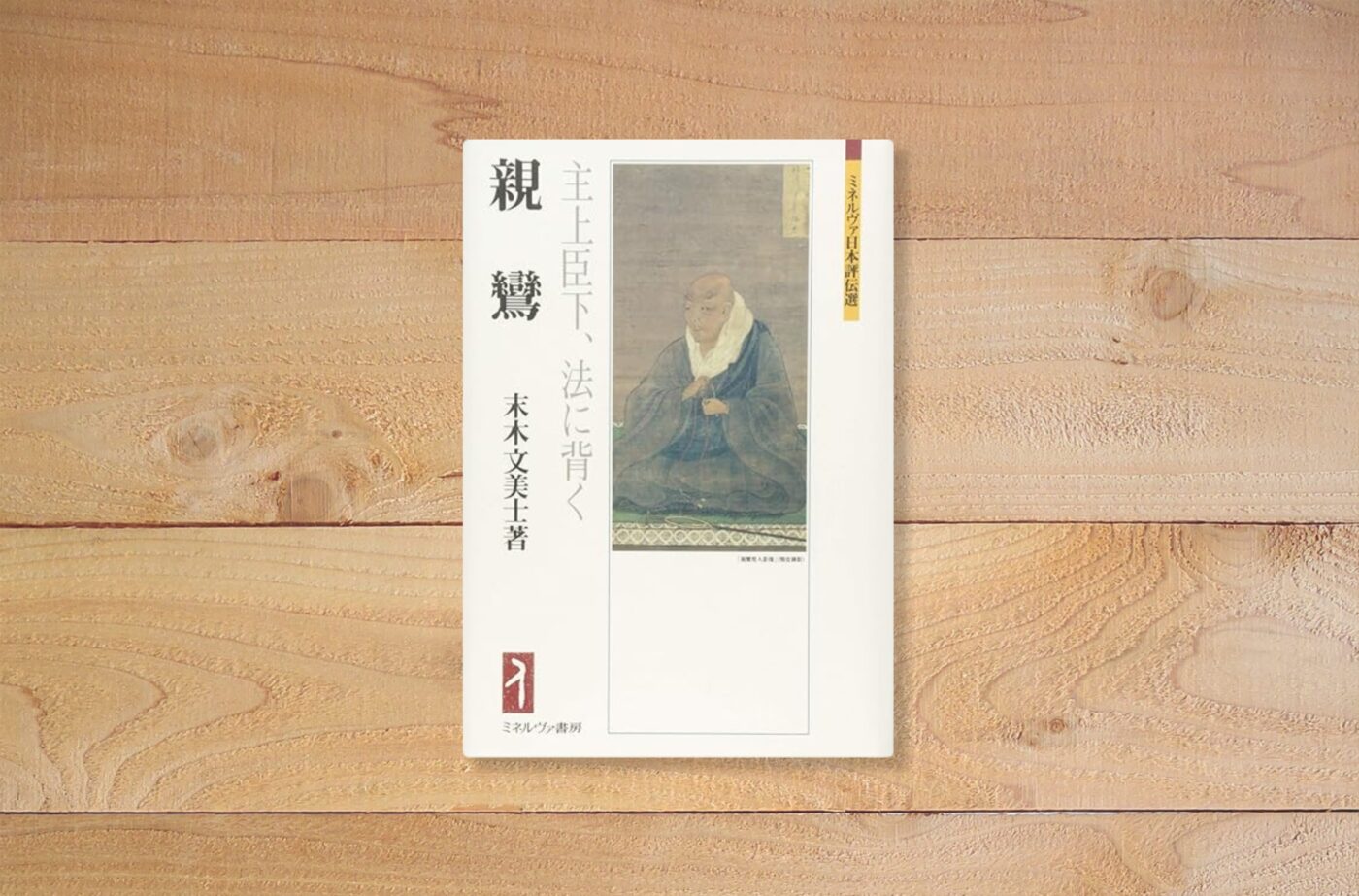中川毅『人類と気候の10万年史』概要と感想~気候変動と歴史的大事件との驚きのつながりを知れる刺激的な一冊!
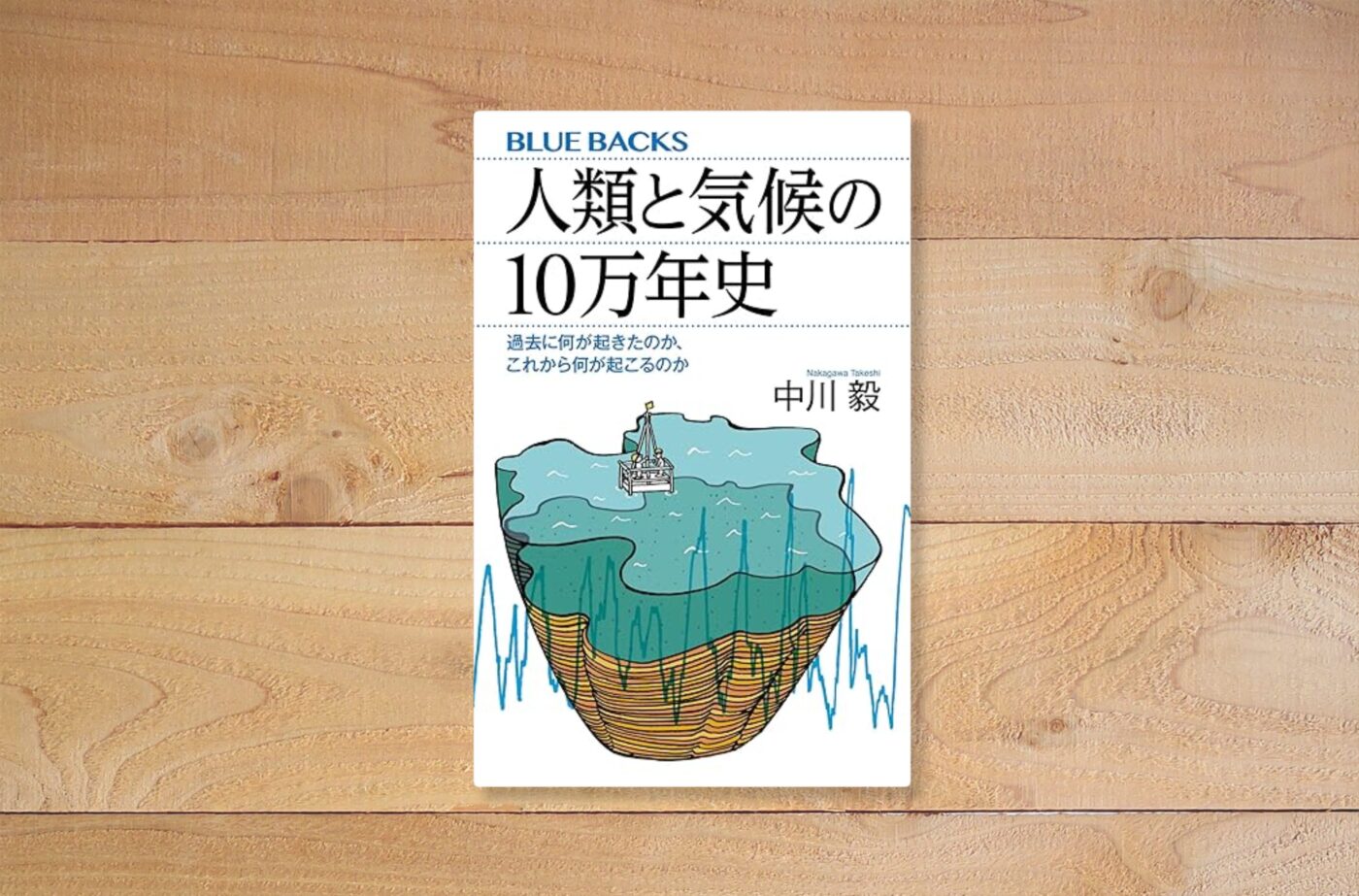
中川毅『人類と気候の10万年史』概要と感想~気候変動と歴史的大事件との驚きのつながりを知れる刺激的な一冊!
今回ご紹介するのは2017年に講談社より発行された中川毅著『人類と気候の10万年史』です。
早速この本について見ていきましょう。
福井県・水月湖に堆積する「年縞」。何万年も前の出来事を年輪のように1年刻みで記録した地層で、現在、年代測定の世界標準となっている。その年縞が明らかにしたのが、現代の温暖化を遥かにしのぐ「激変する気候」だった。人類は誕生から20万年、そのほとんどを現代とはまるで似ていない、気候激変の時代を生き延びてきたのだった。過去の詳細な記録から気候変動のメカニズムに迫り、人類史のスケールで現代を見つめ直します。
Amazon商品紹介ページより

皆さんは「水月湖」という湖をご存じでしょうか。
かく言う私もこの本を読むまでその存在を知らなかったのですがこれが世界的にも奇跡と言われるとてつもない湖だったのです。日本では未だにマイナーな湖ではありますが地球の歴史、特に気候変動の歴史を知るのにこの湖は世界で最も注目されている湖なのだそうです。
本書はそんな奇跡の湖を調査した古気候学者中川毅氏による超刺激的な気候の歴史を知ることができます。
私がこの本を手に取ったのは以前当ブログでも紹介した藤木久志著『土一揆と城の戦国を行く』に1300年頃から1850年頃まで地球規模にわたる小氷河期があったと書かれていたのがきっかけでした。そしてこの期間に作物の不作が続き社会情勢は危機を迎え戦国時代へと向かっていったと説かれていました。つまり歴史の大変動には気候の変化も見逃せないということをその本で知ったのでした。
というわけで気候変動についてもっと知りたいと思った私が出会ったのが本書『人類と気候の10万年史』なのでありました。
そして読んでびっくり。まず上でも紹介した水月湖の存在にも驚きましたが、この10万年の内に地球は何度も急激な気候変動を繰り返しているというのです。しかも特に驚いたのが、現代では人間の活動による温暖化がよく言われますが、地球のサイクルから言えば今はもう寒冷化が始まっていても全くおかしくないのだそうです。つまり、人間は今寒冷化を食い止めているとさえ言えるのだそう。これには私も驚きでした。
また、過去10万年にはわずか数年で気温が7度も上昇した時期があるそうです。これは東京がフィリピンのマニラの気候になってしまうほどの差だそうです。人間の活動とは別に、地球はこれほど急激に気温を上げてしまうメカニズムがあるとは私も驚きました。そしてそれは逆も然り。地球は何度も急激な寒冷化を経験しています。
本書でもこの急激な寒冷化による人類史への影響の例として次のものを挙げていました。
歴史的に見ると、ほとんどの古代文明は1年の不作であればなんとか対応できるだけの備蓄を持っていた。だが、不作が2年続いても耐えられる文明は少ない。3年以上連続する不作は、現代の日本ですら想定していない。だが現実問題として、歴史に残るような大飢饉の多くは、天候不順が数年にわたって容赦なく続くことによって発生しているのである。
1980年代にアフリカで発生した干ばつは、4年にわたって継続したことで300万人の命を奪った。日本においても、近世最大の飢饉である天明や天保の大飢饉は、いずれも冷夏が5年以上も続いたことで深刻化した。
異常気象の原因は厳密には特定されていないが、天明の大飢饉については、アイスランドのラキ火山や浅間山の噴火によって大量のちりやガスが放出され、日傘効果で寒冷化が起こったとする説が有力である。これは、ピナツボ火山の噴火が原因と推定される1993年の冷夏を強く連想させる。ちなみに、1783年にラキ火山が噴火した後は、ヨーロッパでも冷害が発生し、食糧供給の不足と物価の高騰を引き起こした。これによって生じた社会不安は、1789年からはじまったフランス革命の遠因であるとも言われている。
講談社、中川毅『人類と気候の10万年史』P177-178
急激な寒冷化は火山の噴火でももたらされることはよく知られていますが、これがフランス革命にもつながったというのは刺激的ですよね。以前当ブログでもG・ルフェーヴル著『1789年―フランス革命序論』を紹介しましたが、まさにこの本でも記録的な不作が革命につながったことが書かれていました。まさかここでつながるとはと読んでいて驚きました。
他にも本書を読んでいると驚くことがどんどん出てきます。著者たち研究者たちの凄まじい研究姿勢にも頭が上がりません。
気候に関する私達の先入観を覆す素晴らしい一冊でした。ぜひぜひおすすめしたい名著です。ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。
以上、「中川毅『人類と気候の10万年史』概要と感想~気候変動と歴史的大事件との驚きのつながりを知れる刺激的な一冊!」でした。
Amazon商品紹介ページはこちら
人類と気候の10万年史 過去に何が起きたのか、これから何が起こるのか (ブルーバックス)
前の記事はこちら
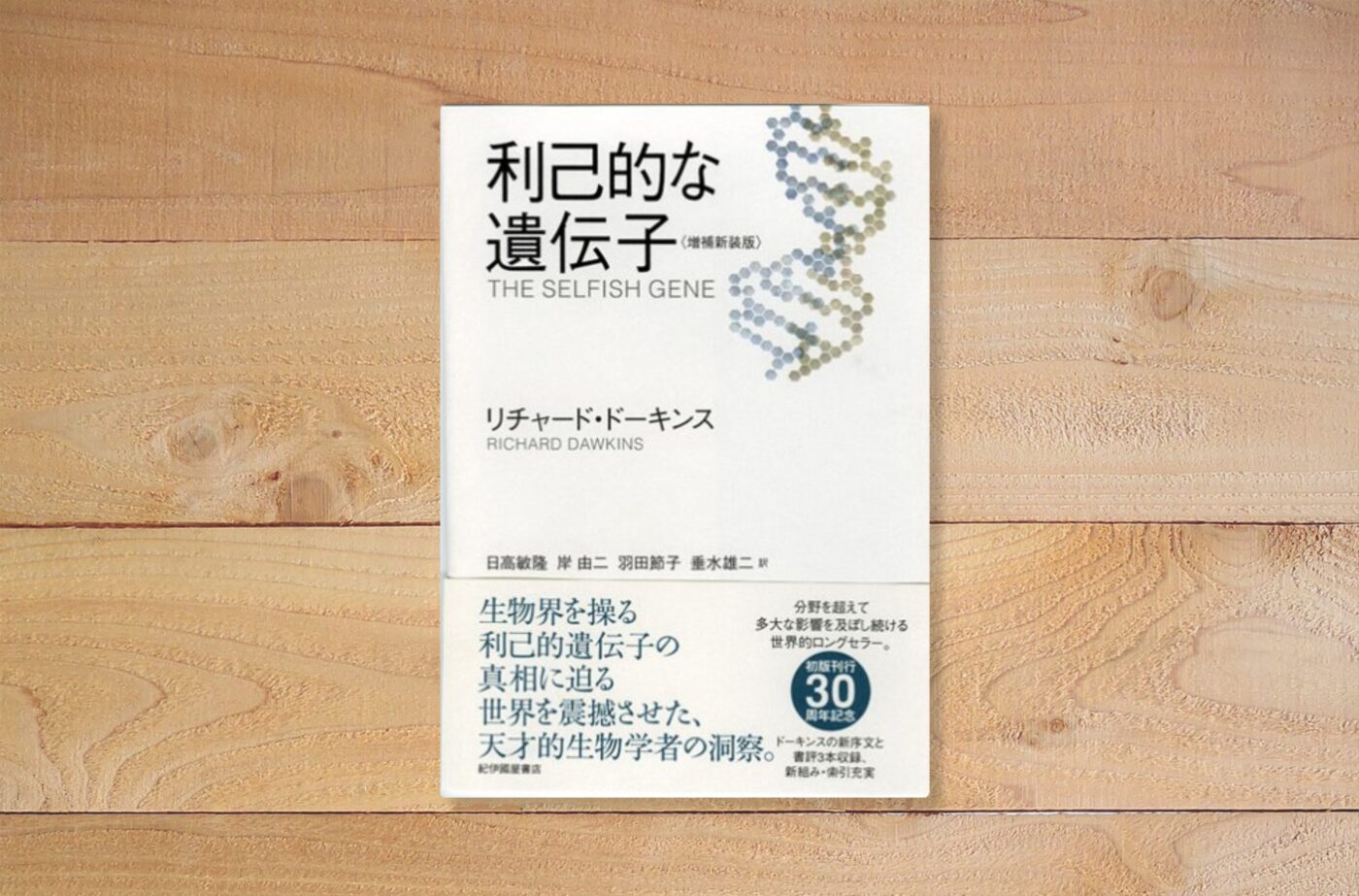
関連記事